
(最新見直し2015.10.26日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「村上幸三郎」を確認しておく。
2007.11.30日 れんだいこ拝 |
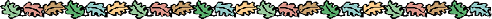
| 【村上幸三郎(むらかみ こうさぶろう】 |
天保12年、生まれ。
明治33年、出直し(享年61歳)。 |
| 天保12年、生まれ。 |
| 明治13年、坐骨神経痛を助けられて入信。 |
| 明治14年、真誠組結成。 |
| 明治24年、光道講第五号と改称。 |
| 明治25年、泉東教会設立。泉東初代会長。高安部属。 |
| 明治33年、出直し(享年61歳)。 |
| 72「救かる身やもの」、97「煙草畑」。
|
| 【村上幸三郎逸話】 |
72「救かる身やもの」。
| 明治13年4月頃から、和泉国の村上幸三郎は、男盛りのさ中というのに、坐骨神経痛のために手足の自由を失い、激しい痛みにおそわれ、食事も進まない状態となった。医者にもかかり様々治療の限りを尽したが、その効果なく、本人はもとより家族の者も、奈落の底へ落とされた思いで、明け暮れしていた。何んとかしてと思う一念から、竜田の近くの神南村にお灸の名医が居ると聞いて、行ったところ、不在のためガッカリしたが、この時、平素、奉公人や出入りの商人から聞いていた庄屋敷の生神様を思い出し、ここまで来たのだからとて、庄屋敷村めざして帰って来た。そして、教祖に親しくお目にかからせて頂いた。教祖は、「救かるで、救かるで。救かる身やもの」と、お声をおかけ下され、いろいろ珍しいお話をお聞かせ下された。そして、かえり際には、紙の上に載せた饅頭3つと、お水を下された。幸三郎は、身も心も洗われたような、清々しい気持になって帰途についた。家に着くと、遠距離を人力車に乗って来たのに、少しも疲れを感ぜず、むしろ快適な心地であった。そして、教祖から頂いたお水を、なむてんりわうのみこと なむてんりわうのみことと、唱えながら、痛む腰につけていると、3日目には痛みは夢の如くとれた。そして半年。おぢば帰りのたびに身上は回復へ向かい、次第に達者にして頂き、明けて明治14年の正月には、本復祝いを行った。幸三郎42才の春であった。感謝の気持は、自然と足をおぢばへ向かわしめた。おぢばへ帰った幸三郎は、教祖に早速御恩返しの方法をお伺いした。教祖は、「金や物でないで。救けてもらい嬉しいと思うなら、その喜びで、救けてほしいと願う人を救けに行く事が、一番の御恩返しやから、しっかりおたすけするように」と、仰せられた。幸三郎は、そのお言葉通り、たすけ一条の道への邁進を堅く誓ったのであった。 |
|
97「煙草畑」。
| ある時、教祖は、和泉国の村上幸三郎に、「幻を見せてやろう」と、仰せになり、お召しになっている赤衣の袖の内側が、見えるようになされた。幸三郎が、仰せ通り、袖の内側をのぞくと、そこには、我が家の煙草畑に、煙草の葉が、緑の色も濃く生き生きと茂っている姿が見えた。それで幸三郎は、お屋敷から自分の村へもどると、早速煙草畑へ行ってみた。すると、煙草の葉は、教祖の袖の内側で見たのと全く同じように、生き生きと茂っていた。それを見て、幸三郎は、安堵の思いと感謝の喜びに、思わずもひれ伏した。というのは、おたすけに専念する余り、田畑の仕事は、作男にまかせきりだった。まかされた作男は、精一杯煙草作りに励み、その、よく茂った様子を一度見てほしい、と言っていたが、おたすけに精進する余り、一度も見に行く暇とてはなかった。が、気にかからない筈はなく、いつも心の片隅に、煙草畑が気がかりになっていた。そういう中からおぢばへ帰らせて頂いた時のことだったのである。幸三郎は、親神様の自由自在の御働きと、子供をおいたわり下さる親心に、今更のように深く感激した。 |
|
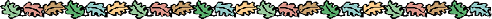



 (私論.私見)
(私論.私見)
村上幸三郎 むらかみこうざぶろう
専東分教会(大阪府堺市)の初代会長。
天保12年(1841)9月19日、父村上源次、母乃婦の長男として生まれる。
経済的に豊かな環境で育った村上幸三郎は、明治8年(1875)に北野清平の長女コトと結婚。
家督を継いで暮らしていたが、明治13年4月頃から坐骨神経痛を患い、手足の不自由や痛みに苦しむようになった。
さまざまな治療を試したが効果はなく、以前から噂を聞いていた「庄屋敷の生き神様」を頼って教祖(おやさま)を訪れた。
その際、教祖から
「救かるで、救かるで。救かる身やもの。」
というお言葉をかけられ、鮮やかなご守護をいただいた。
明治14年の正月には本復祝いを行い、お礼のためにおぢばへ帰った。
このとき教祖は、幸三郎に
「金や物でないで。救(たす)けてもらい嬉しいと思うなら、その喜びで、救けてほしいと願う人を救けに行く事が、一番の御恩返しやから、しっかりおたすけするように。」
と仰せられた。
この入信の経緯については、『稿本天理教教祖伝逸話篇』に詳しく記されている(72話「救かる身やもの」)。
この後、熱心なおたすけと布教活動を続けた幸三郎は、頻繁におぢばへ帰り、教祖から親しく教えを仕込まれた。
当時の記録や拝戴した赤衣(あかき)も現存している。
明治14年には、幸三郎を講元として真誠組を組織し、困難の中にも信仰を広め、明治23年の高安分教会設置の際に部属の講社となる。
明治25年、髙安分教会部属の泉東支教会が設置されると初代会長になり、明治33年4月2日に61歳で出直すまで、布教活動に専心する生涯をまっとうした。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』には、前記の入信の逸話のほかに、教祖が
「幻を見せてやろう。」
と仰せになり、赤衣の袖の内側から幸三郎に煙草畑の様子を見せたという話が取められている(97話「煙草畑」)。
[参考文献]
- 村上嗣昭監修『天理教泉東分教会史』(天理教泉東分教会、1992年)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)