
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.12.11日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「一派独立運動始まる」を確認しておく。「別章【明治32年お指図】」。
2007.11.30日 れんだいこ拝 |
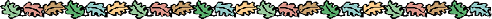
1.8日、安堵事情の収集のため、喜多、桝井両氏が大分県へ巡教のため出張。
1.17日、山名の平出団次郎、高室清助、**布教の御許しを受ける。
2.4日、御供えの金平糖の中にモルヒネが入っているとの風説があり、当時お供えは部内教会より本部にお供えし、それを下げて各教会で包んで渡していたのを、本部より直属教会に渡して取り扱うようになる。
5.21日、神道本局管長・稲葉正善氏が、真柱に天理教一派独立を勧める。
5.30日、神道本局管長・稲葉正善氏より中山真次郎教長に独立請願の件示唆あり。これより本部員、直属教会長の大会議行われる。
| 【一派独立運動始まる】 |
5.30日、一派独立運動始まる。真柱の伺いに対するお指図。
| まあ一つ、教会と云うて、順序、世上世界の理に許しおいていたるところ、どうでもこうでも世上の理に結んであるからと云うて、世上の理ばかり用いてはならんで。(中略)事情は、世界の理に結んでも、なお々元々もんかた無きところより、始め掛けた一つの理を以って、万事くくり方、治め方、結び方と云う、この理一つが道の理であるほどに。(中略)びっくりするようなことある。よう聞き分け。日々と云う、諭し方は、元々始め掛けた理より外に理は無いで。(中略)地場始めたと云う理は、容易や無いで。世上世界の理と一つになってはならん。(中略)尋ねた事情、成るならんはさておき、一ヵ年二ヵ年では、鮮やかな事情見られようまい。さあさあ始め掛け、ぼつぼつ始め掛け。 |
|
| 以後、10年にわたり一派独立運動始まる。 |
|
6.6日、独立請願の件につき、本部員、分教会長召集の上、衆議一決し神意を伺う。「一派独立運動の神意伺い」に対するお指図。
| 「掛かりたところが、一寸にはいかん。一寸にはいかんが、どうでもこうでも早くから、いらってはならん。あちらにも心がある。こちらにも心がある。心がよるから万事成り立つとみにゃなろうまい。(中略)なんぼ大きいものでも、すくんでいては分からん。畝序へ出る、分かると云うようなものや。やりかけたら、どこまでも、やらにゃならんが一つの理であろう。(中略)皆揃うて一つ心、教祖存命の心をもって尋ね出た。一日の日の心の理に万事許しおこう々」。 |
| 「まあ一寸にはいかん。そこで、こんな事ならと思う日もあろう。その日あっても、何でもかでも、順序一つの心をもって通らにゃならん。通り損のうてはならんで。元々西も東も北南も、何にも分からん中から、でけた道やで。いばらとも、崖道とも、細道とも云う。容易ならんこの道であるほどに、今の道は今一時になった道やあろうまい。この心しっかり治めて、事情かかるが道の花と云う」。 |
|
|
6.14日、松村吉太郎、清水与之助を天理教別派独立交渉委員に任命する。この時のお指図。
| 「この道と云う、元々難しいて々ならん道から成り立つのや。その中を道に一つの心寄せて順序運び来た。真実働きは目に見えやせんで。順序から分かる道もある。心に任せおく。どんな日もあるで。これではなあと云う日もあるで。どんなことも云うておかにゃ分からんで」。 |
|
| 6.15日、松村吉太郎、清水与之助の両名が、一派独立につき、神道本局管長・稲葉氏と交渉の為、上京する。 |
|
神道本局は、「一派独立の分離金」として天理教の教会数と教師数から算出して36万円を要求してきた。立交渉委員に与えられていた権限は1万円であった。清水がおぢばに帰り、神意を伺う。6.25日、「一派独立の分離金」のお指図。
| 「一時にいかん、一寸いかん。(中略) 頼んでする道じゃない。どこへどうするのやない。(中略) さき一本だち、しんの心は一本立ち、皆々一つ心を持ってくれにゃならん。一時のところ、いやとは云えようまい。それで一寸にはいこうまい。(中略) 成る成らん年限と云う道と云う理を持ってくれ」。 |
| 「ならんと云えばならん。なると云えばなる。めをかけていけばきりがない。必ず/\急くこといらん」。 |
| 「これ一つ心にこれだけ、ならんもの無理にならん。運ぶところ運んで、ならにゃ、じっとするが良い」。 |
|
|
| 7.12日、天理教会長代理/松村吉太郎、立会人天理教教師総代/清水与之助が、神道本局管長代理幹事/野田菅麿、立会人/平岡好国の間で、本教独立請願の交渉取りまとめ双方契約書を作成する。
|
| 初代管長が、清水与之助、平野楢造、松村吉太郎、永尾楢治郎、篠森乗人の5氏を随行させ上京する。神道本局管長稲葉正善の承認を取付け、神道本局の添書を得る。 |
|
| 8.9日、 内務省(内務大臣・西郷従道)に対し第1回独立請願書を提出した。「現今各府県下に分教会18、支教会200、出張所720、布教所548、教師1万8150名、信徒数200万人。一派独立の基礎堅固なれば、本請願に対する認可を与えられたし」と記している。請願書に連署したる者は、神道天理教会長中山新治郎、教師総代飯降伊蔵、清水与之助、平野楢造、松村吉太郎、永尾楢治郎。加えて信徒総代諸氏の面々。但し、そのまま却下された。
|
9.4日、四年制の天理教教校設立請願書を奈良県庁へ提出。9.26日、天理教教校設立の件、奈良県知事より認可あり。
11.2日、お指図(午前4時頃の刻限お指図)。
| 「さあさぁ一寸一つ話、さあさぁどういう事知らす。どんな事を聞かすやら分からん。さあ、あっちでも手が鳴る、こっちでも手が鳴る。鳴ってから、あら何でやいなあと言うてはなろまい。さあ刻限知らす事は違わんで。あちらで声がする、こちらで声がする。何でやろう。行く先々前々より知らしたる事見えてない。道を知らする事、度重なると分かる。一時筆取りたらあら/\の事も悟るやろう。初めも知らす。身の直る事まで。これさあ刻限/\。刻限の話、理によりて深く見にゃならん。聞かにゃならん。いかな事も、詰みて/\詰み切ってある。外から見たら、むさくろしいてならん。さあ掃き掃除拭き掃除、掃除に掛かれば箒も要る。どんな道具も要る。拭き掃除にも道具が要る。要らん道具は要らん。どんな働きもする。怖いと思わにゃならん。嬉しいと思わにゃならん。勇まにゃならん。実々どんな道が付くとも計られん。何でも諭さにゃならん。うっとしいてならん。明らかなる面々心から、どうもならん。いかな事も聞き分け。重なりたら、間違いの理が重なれば、どんな事こんな事もある。一人残してある。皆の者も、皆手を打たねばならん/\という理を、一寸諭しおこう」。 |
| 「さあさあ道理上々これから道理上、暫く道理上を通らんならん。(中略) 長い間道理上の道を通れと云わん。何年々々のきりを切りておこう)。 |
| 「一人残してある。皆なの者も皆な手を打たねばならん/\という理を一寸諭しおこう)。 |
11.3日、「昨夜のおさしづに付き、本部員一同打ち揃いの上願い」。
| 「さあさぁ段々尋ねるところ、刻限順序の理を尋ねる。刻限というものは、何時でも話するものやない。刻限は詰まり/\てどうもならんから、それぞれ決まりた理を知らす。何の事でも違うという事は一つもない。なれど、これまでというものは、刻限の理を聞きながら、どうもならん。何を聞いて居たのやら分からんようなもの。どうでも刻限は間違わん。刻限は積もり積もらにゃ話出けん。時々諭したところが分からん。そこで、何ぼ言うたて分からん。刻限は積もり/\ての刻限である。善き事は何ぼ遅れてもよいがなれど、成らん敵わん声もなく、堪えるに堪えられん事察してみよ。誰の事とは言わん。紋型なきところからの道理を見れば嘘はあろまい。間違いはあろまい。言い難い事も言い、難しい事も解きほどきて一つ扱う。世上から眺めて聞くにも聞かれん、見るに見られん、心にあれど口には出せぬが理。よっく聞き分け。又集まりて刻限道理から一つ道あれば、疑う事できようまい。よう聞き分け。(中略) 一つ諭しの中、道理がある。元という中に一つ聞いて成程は理である。どういう事ぞいな。あんな事かと、これで道として理に当たるか、理に当たらんか。日々働いて居る/\。よう聞き分け。人の事とは思うなよ。我が事になってから、どうもならん。これ聞き分け。何ぼどういう事を言うたて、言うのが悪いなあ、言うてはいかんなあ。包んで居ては真実真の事とは言わん。我が身捨てても構わん。身を捨ててもという精神持って働くなら神が働く、という理を、精神一つの理に授けよう」。 |
| 「さあさぁもう一言/\押しておこう。さあさぁもうこれ、どうでもこうでも、掃除という。刻限出した限りには仕遂げにゃならん。掃除仕遂げる。隅から隅まで掃除に掛かる。掃除に掛かりたら、あちらこちら声が聞く/\。どんな事を聞いても、心を授けた限り、一名一人の心という。おめも恐れもない。控え心は受け取る事出けん、と諭しおこう)。 |
|
12.29日、お指図。
| 「指図こうやけど、どうもなあ、と言うようでは天の理に背く。教祖一つの理にも背く」。 |
|
| 【橋本清口演「天理教の内幕」発刊】 |
この年、橋本清が、昨年に続いて天理教会本部に金5百円を請求するも、拒否される。橋本は、「右金額を貸与すれば良し、貸与せざれば冊子を発刊して本教に大害を与える」と恐喝した、と伝えられている。その後、橋本清口演「天理教の内幕」が発刊された。「序」に於いて次のように述べている。
| 教会本部にありてその衝に当り、親しくその弊源を実験し、根本的改良を企画せんとて意見を提出せし結果、衝突して断然職を辞し、(中略)年一年その害毒の猖獗(しょうけつ)を極めるを観て(はなはダ)憤慨に堪えず、ここにその弊害の由って来るところを口演して云々。 |
同著は、当時の天理教を代表して仏教側と論争して来た人物の手になるものであるだけに天理教教理の裏からの俯瞰的把握を開陳しており、興味深い。 |
| (道人の教勢、動勢) |
| 6.14日、西浦彌平が出直し(亨年56歳)。弘化1年(1844)10月4日、大和国山辺郡園原村(現・奈良県天理市園原町)生まれ。明治7年、長男・楢蔵のジフテリアをご守護頂き入信。上田嘉治郎(嘉助)、ナライト等を導く。本席よりかんろだいのさづけ。(稿本天理教教祖伝逸話篇39「もっと結構」) |
| この年、水屋敷事件で免職された飯田岩治郎が神道大成教の教師の資格を取得する。 |
天理教事典/教会史編P154が次のように記している。
神殿ふしんと支教会昇格
明治31年秋頃には、部内出張所はほとんど神殿建築を完了していたが、嶽東は設立当初のままで、手挟で粗末であったので、部内相談の結果、神殿建築費としてたちまちかなりの額が集まった。初代会長は、嶽東がこのように結構に栄えたのは、ひとえに「おぢば」のお陰であるから、この費用をおぢばに供えたいと信念を述べて、真実を込めてお供えした。翌32年4
月23日、大岡村字中石田2488番地に移転の許しを頂いた。敷地は2、726坪(8、963㎡)で、年内に整地した。越えて33年1月12日、建築の許しを得て着工し、翌34年2月、堂々たる神殿と客殿、会長室、事務所、その他合計8棟、建坪150坪余(497㎡)が竣工した。
|
|
| (当時の国内社会事情) |
| 11.15日、阪神地方にペスト流行。 |
| 不平等条約の条約改正が実現し、欧米列強の意向を顧慮する必要が薄れた。 |
| 東京大阪間長距離電話開通。 |
| (田中正造履歴) |
| 1899(明治32)年、59歳の時、議員歳費値上げ案反対演説をし、歳費を辞退。足尾鉱毒被害状況を基に鉱業停止の質問をする。 |
| (宗教界の動き) |
| 7.27日、神道仏教以外の宗教の宣布・堂宇建立・移転廃止についての届出規則制定。宗教法案貴族院否決。 |
| 歴史教科書に天照大神、三種の神器、天孫降臨を加える。 |
| 新渡戸稲造『Bushido The spirit of Japan』。 |
| 【王仁三郎が、大本教の直の末娘すみの婿となる】 |
| この年、王仁三郎が、大本教の直の末娘すみの婿となった。独自の霊学に古事記研究を加味した教義を作り、皇道大本と名づけた。やがて世界統一を成し遂げて綾部を首都とし、出口家が祭祀長として神勅を受けるのだと説き、知識階級、軍人、官僚らにも多くの信者を獲得していくことになる。
|
|
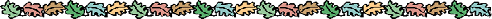



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)