| 1892年 |
明治25年 |
教祖墓地を善福寺から豊田山へ改葬 |

更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.12.17日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「1892(明治25)年、教祖墓地を善福寺から豊田山へ改葬」を確認しておく。「別章【明治25年お指図】」。「神一條(神一条) 資料2 」。
2007.11.30日 れんだいこ拝 |
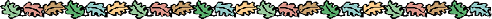
| 【お指図】 |
1.14日、お指図。
| 「日々にあたゑ、これ諭すから皆んな揃うて、互い互いの理は、重々聞かさず々の理は、とんと受け取れん。慎みが理や、慎みが道や。慎みが世界第一の理、慎みが往還や程に。これ一つ諭しおこう」。 |
| 「見える/\、見えるから諭す。よく聞き分け。これまで順々道すがら、いかなる事もあったやろ。難儀不自由の道を通れと言うやない。日柄も限ってあるで。惜しいことやと思わんよう。心散乱という。世上の理を思わんよう。見え掛けると、どんなこと見えるとも分からん。これまで成らん中、どうでもこうでも治めて来た。一寸楽々の道を付けた。どういうところに、どえらい土手がある、石浜がある、難海がある。三つの理を思わにゃならん」。 |
|
| 【お指図】 |
2.18日夜のお指図。御在世当時、教祖は「赤衣(あかき)」と呼ばれる赤い着物をお召しになり、それを仕立て直されて「お守り」として信者たちに渡していたが、その在庫に底がついたことから、どう対処したらよいのかということを伺った時のお指図。
| 「(前略)休息所日々綺麗にして、日々の給仕、これどうでも存命中の心で行かにゃならん。(中略)存命中同然の道を運ぶなら、世界映す又々映す」。 |
押して、給仕は日々三度ずつ致しますもので御座りますやと伺う。
| 「宵の間は灯りの一つのところは二つも点け、心ある者話しもして暮らして貰いたい。一日の日が了えばそれ切り、風呂場のところもすっきり洗い、綺麗にして焚いて居る心、皆なそれぞれ一つの心に頼みおこう」。 |
| 「治まる道は神一条の道である。神一条ならば存命一つの理、これ第一である」。 |
| 「指図の理はたった一つの理を諭してある。なれど分かりゃせん。理の指図には違わんという理を取らにゃならん。身上に事情と言えど事情による」。 |
|
| 【お指図】 |
4.23日、お指図。「平等寺小東小玉、前川菊太郎へ縁談に付き、平等寺小東よりしてよろしきや、又は大阪小東政太郎よりしてよろしき哉、又は教興寺松村よりしてよろしき哉伺い」。
| 「さあさぁこうと思うだけ運んで/\、分からんなれど一つ治まる、理を治まったら治まる。あちらこちらどうと分かろまい、なれど治まる理だけ運んで治まらねば又一つ理治めてくれるがよい」。 |
|
| 【浅草支教会史】 |
天理教伝道史Ⅶ、P40「高野友治」(道友社、1968)が次のように記している。
| 1968.4.25日、浅草講社が御本部のお許しをいただいて浅草支教会となった。このとき、浅草南講社は浅草支教会の管轄となった。南講社から道の伝わった埼玉県八条村立野堀の信者たちは浅草支教会の管轄となり、浅草支教会と同じ日、立野堀出張所のお許しをいただいた。これを機会に、浅草支教会は山川町に移転することにして、普請を開始した。立野堀出張所では居宅を改造して神殿とし、同年6月27日には開莚式を執行し、浅草支教会は教堂の新築を待って、9月17日・18日の両日にわたって行なった。このころでは、埼玉県の立野堀、四丁野、大沢、粕壁、春安、青柳、蓮田、野田、牛重などの信仰もはじまっており、すばらしい勢いであった。だが、教会運営の経済力となると、さすがに旧吉原講社が握っていたようである。山川町の教堂建築は2,000円かかったといわれる。その金は、埼玉県下の信者たちからも多数の信者が浄財を運んでくれた。だが、建築費の大半は旧浅草講社の数人のものによってまかなわれていた。だが、土地は借地であった。これは少し後になるが、この土地を中米楼の女将赤倉すま姉が3,700円で買収して教会へ寄付した。農村の金と吉原の金とは、そのように違う。万事そんな調子だったという。お祭になると賽銭があがる。献金などという考えのなかったときで、処置に困って遊びにくれてやったという話がある。お祭あとの直会で、村松万蔵氏が隅田川の向うの別荘へ役員たちを招待して、ゆっくりやったこともあるという。とにかく、一夜千両といわれたあぶく金で生きていた人々であるから、気がむけば農家の一年分の収入ぐらい一人で出す人が相当いたらしい。
これが加藤新兵衛のいう東京風の運営方式かも知れない。自由で、拘束されることなく、心のままを行なって楽しむ。そして人に負担をかけない。部下の献金を問題にしない。だから、みんなから喜ばれたに違いない。関東人はかかる処置を喜ぶ。日本橋、京橋、深川、芝、麻布、本所などの諸教会の場合も、江戸っ子の集りだけに自由の愛好者たちであり、かかる処置を望んでいたことであろう。 |
|
| 【お指図】 |
5.14日午後7時40分、お指図。「本席歯のお障りに付き御伺い」。
| 「治まる道は神一条の道である。神一条ならば存命一つの理、これ第一である」。 |
| 「指図の理はたった一つの理を諭してある。なれど分かりゃせん。理の指図には違わんという理を取らにゃならん。身上に事情と言えど事情による」。 |
| 「さあさぁ身上一条尋ねる。いかなるところ尋ねる事情、さあさぁ時々の事情/\、事情時々の事情に、身に障ると言うて、早く尋ねば諭さにゃならん。刻限というは、身上一条、尋ねる事情、いかなるところ、どうにもならん。月が重なる、日が重なる。どういうものであろ。日が重なる月が重なる。身上に事情あれば尋ねるも一つ聞くも一つ。治まる理も治まらん理もあろ。不思議/\の理が分かろまい。難しい理であろ。余儀なくの事情、月々段々これより諭し掛ける。一時刻限重々の理に諭さんならん。刻限と尋ね事情とはころっと変わるで。刻限の事情というは、これまで一つ不思議/\を皆な知らしたる。身の内の障りは、人々それぞれ心の理に諭したる。刻限の理は、世上も分かろまい。内々も分かろまい。刻限いかなる事情、鮮やか心の理が分からんから、よう諭して置く。刻限という理、身の内の理、同じ理のように思う。刻限というは、世界もあれば内々事情もある。分かる分からん、刻限事情、身上障り出越す。事情指図する。どれだけの案じ諭せば怖き危なきところでも許しおくというは案じなき事情、理を通してある。(中略) 席と言えば、何でもないように思う。聞けば/\世上何である。不思議やなあ。日々聞き分け。ほんになあ、理が集まるという道から考えば一つの理も分かる。無理な事せいとも言うやない。よう聞き分け。心に掛かりて日々という。指図万事よう聞き分け。尋ね事情に一つの理の間違いはなけれども、面々心の理より、聞きよう取りようで違う。心が違う。こうであろか、あゝであろかと、面々心に拵え(こしらえ)案じる。これ聞き分け。何時(なんどき)刻限事情にて諭し掛ける。万事忘れなよ/\。何時刻限で知らすやら分からん。いつであろか。分からん/\の理のようなものや。一寸聞く。聞けば当分一時のところに治まる。なれど日が経ち、月が経てば忘れる。面々勝手、面々の理、事情で皆忘れる。不足言うやない。成らん事をせいと言うやない。これまでの道、面々皆な通りたやろ。どうであろうどうであろうと暮らして通りた道である。よう聞き分け心に治めてくれ」。 |
|
| 【お指図】 |
6.4日、お指図。
| 「幾重の指図もあろう。引き合わせてみよ」。 |
| 「多くの中に澄んでく早く汲みに来んかいなと、水を澄まして待って居る。(中略) わしが匂い掛けた、これは俺が弘めたのや、と言う。これも一つの理なれど、待って居るから一つの理も伝わる」。 |
|
| 【お指図】 |
6.24日、お指図。「教祖御墓所石玉垣造る事の願い」。
| 「仕切った事情は未だ/\。一時のところどうでも受け取る事できん。どういうもので受け取る事できんなら、地所はようよぅの理に集まりて治まり、一日ともいう。幾日(いっか)/\事情、仕切った事情は大変という。きっしょうという定めてくれ。一つ治まりてあるところ、事情さあさぁどうがよかろ、こうがよかろ、色々理を寄せるところ受け取る。いつまで事情こうしてという理を以て始めてくれ。これでという出来は未だ/\先の事、年々長い間の楽しみ、結んで了うたら、それ仕舞の理である」。 |
|
| 【お指図】 |
6.30日、お指図。「教祖豊田山墓所五日取り掛かりの願い」。
| 「前々諭したる。多く地を均し、道を拵え、幾日という切った日限があろ。日は余程長いようなものなれど、ついつぃ経つ。段々の理をあちらも寄せ、こちらも寄せ、どうがよかろ、こうがよかろ、尽くすところは受け取るなれど、一時多く広く地を均らし、それぞれ一寸一通り道を付け、真ん中に一寸理を拵え、此処かいなあと言えば、又、何ぞいなあという事情に治め。運ぶ尽くす理は受け取る。たヾ受け取ると言えば、どうしても受け取るであろう、というような心持ってはならん。世界の理がなくばならん。仕切ってすれば、思わくの道が段々延びる。 早い/\。忠義粗末とは必ず思うな。これまで指図の理に定めてくれ。(中略) 忠義の道は未だ/\先の事。(中略) 千里一跨げの理は未だ/\であるから、人間の理はすっきり要らん。(中略) しょうまいと思たて、出来掛けたら出けるで」。 |
|
| 【お指図】 |
7.1日、お指図。「教祖墓所造営に関係あるお指図」。
| 「何にもないところから始め掛けたるところ、人間心さらさらない。何が偉いと言うたとて、ほんの音だけ聞くだけやろ。何も拵えは要らん。どんな事もひながたという。どれだけの事したとて、理に中(あた)らねばこうのうとは言わん。不思議々々々出て来る処、世上の理さえ聞き分けるなら、何も間違う事はない。合い言(こと)問い言(こと)の理はあろまい。何程呼び返やすとて、大きな声で呼び返やす。一時一つの理があれば、どういうものであろ。どれだけこうせにゃ人が笑うと思う。何が笑うぞ。笑うは楽しみと出してある。どんな事も尋ね掛けて運べ。決議だけでは思い/\の理があろ。刻限という理は外せんで。刻限は何でもない事は呼ばんで。これ、よっく聞き取ってくれ幾重の指図もあろう。引き合わせてみよ」。 |
|
| 【豊田山墓地に改葬】 |
| 教祖の遺骸は、中山家祖先累代の菩提寺たる勾田村の善福寺境内に葬られていたが、天理教開祖を仏教寺院内に葬りおいては仏教と縁が切れぬ、これは教祖の意思ではないと云う豊田村改葬の議が起った。1.26日、ご神慮を伺い、お許しを得る。2月、豊田村買い入れ。 |
| 7.5日、豊田山墓地工事ひのきしん始まる。平野楢造、松村吉太郎二氏が工事掛かりを任命され、日夜工事を督励し、70日間で完成させた。12.13日、教祖墓地を善福寺から豊田山へ改葬。
|
| 【お指図】 |
8.21日、お指図。
| 「どんな道もつれてとほりたいから、にがい事もきかし、云ひにくい事も云ふてきかし、いくへ理もさとすのやで」。 |
|
| 【お指図】 |
9.30日、お指図。
| 「どういう筆を取る、こういう筆を取る。筆に記してくれにゃならん。言葉で諭してもならん。十分知らしたら、一つ一つ治めてくれにゃならん。筆に記したとてどうもならん。皆勝手の理を拵える。何を思うても、この道神一条の道は、どんな事も立てゝ見せる。これからどんな事も神は大目に見て居る。神というもの、そんな小さい心でない。(中略)知らんとも言えようまい。今日の日見て居る。神一条の道で神一条の言葉で出来たもの。早うから仕込んである。どんな事もこんな事も分からん事情又替わる。代の替わるようなもの。代替わり、根がどうも難しいてならん」。
|
| 「何ぼ諭した神のさしづ、皆んなあちらへ映るこちらへ映る。勝手の悪いさしづは埋もって、こんな事では一分の日難しいなる。迫って来る。この迫って来るはどういう順序の理諭さりょうか。多くの中、楽しみ々いう理が何から出来たものであろう。容易ならん道、欲を離れて出てくる。何と思うて居る。日々改めて居る。種という理を以て話し掛け。種は元である。口上手弁が達者やと言うても何もならん。日々取り扱い本部員本部員というは神が付けたものか。これ一つ改めてくれ。そういう理は人間の心で付けた道、世界は人間の道。このやしき人間の心で通る事出来ん。神の理それだけ難しい。何處へ行っても無理という理はない。神が理を治め掛けたる。世上どういう理以て、何でも彼でも治めて掛かる。この順序聞き分けてくれにゃならん。何處で真似をしたとてならん。何處で店を張ったとてどうもならん。元が無いから。このやしき元なるぢばと言うたる。その元へ入り、神一条の理を持ってくれ」。 |
| 「長い短い問い返やせと々言うに、もう宜しいと言うから、神が退いてしもうた。それから会議々々と言うたて、人間さしづを拵え、取次見苦しい。ごもくだらけ。一寸々々日々積もれば山となる。この、山となったらどうするか、この順序聞き分け出来ねば、人間心通るだけ通りてみればよい」。 |
| 「あの人面々頼り持ったなら、重々の理を楽しみ、理を積もり恐ろしや。たゞ一つの臺である。前々本部員々と言うて居る。これも段々ある。本部員々何人ある。本部員というものは、神から言うたのか。人間が言うたのであろ。人衆始め掛けと寄せてある。これから一つ考えてみよ。表並び々高い低いも長い短いも分かるである々。我が事した事は、皆人の事と思うたらあきゃせん。(中略)何ぼ本部員第一の空に居た者である。下からならん々。この理皆それぞれ散乱して心を計ってみよ。上に留まっても、足持って蹴ってしもたら、ころころと行ってしもうた。可哀そうなものや。それじゃから、本部員じゃという」。 |
|
| 【お指図】 |
10.7日、お指図。「本席身上願」。
| 「刻限からできて来た。皆合紋印(あいもんじるし)打って来た。皆一二三四の印、一つ違うたら組んで行からせん。西は西、東は東、北は北、南は南。違うたら西は東、北は南、後手(ごて)になりて組まらせん。皆見通して付けて来た。刻限で知らしたる話の伝えから考えてみよ。無理な事無理にせいとは、たヾ一つも諭してない。出けん事無理にせいとは言わん。日々身上迫れば、皆運んで居る。運べなんだ事なら、一も取らず、二も取らず。刻限話他所に聞き、人間心を面々出して運んで居る。日々取扱いも放って置き、一寸掛かりて来れば一寸開きて/\草深でよいと言うであろ。刻限諭し聞かぬようになりたら、何も聞かぬようになる。 あちらも半端や、こちらも半端や。天然自然の理も幾度聞かしたるやら知れやせんで。大層大儀な道やあろまい。一時の道やない。一寸に出ける道やない」。 |
|
| 【お指図】 |
11.9日、お指図。
| 「身の内苦しんで居る処を見て尋ねるは、辛度の上に辛度を掛けるようなもの」。 |
| 「刻限なしてしまい、刻限見逃し聞き逃し、子供のする事が、親は今まで見ていた聞いていた。なれど、人間心の理が栄える。それでは見て居られん」。 |
|
| 【お指図】 |
11.9日午前4時、お指図(刻限お指図)。
| 「刻限という事情納(なお)しておいて、人間心で、何もならん事に目をほし、あゝ目がくたぶれた。何もならん。刻限事情一寸も違わん。刻限納(なお)して了い、刻限見遁(みのが)し聞き遁し、子供のする事が、をやは今まで見て居た聞いて居た。なれど人間心の理が栄える。それでは見て居られん。刻限を台として始めた道、一名ともいう二名ともいう、又それぞれともいう。刻限をよう思やんせよ。それを納(なお)しておいて何も尋ねる事要らん。日々出入り苦しんだ理で、何処へ行こうが、結構な道が一寸付けてある。一つの理を互い互い聞き分けるなら自由という。これ聞き分けにゃならん。前々刻限どういう事であった。これ事情聞き分け。十分の道九分までの道に連れて上りた。もう一だんえらい難し道が通り掛けて居る。面々こうせにゃならん、どうせにゃならん、皆談じ合うた処が何にもならん。刻限の理を外すなら尽くすまでや。ワァ・・・・、さあさぁどれだけえらい剛気、豪傑、力が強いと言うたて、入るや否や、一寸は連れて通る。面々心で押してみよ、突いてみよ、たかってみよ、触ってみよ。どれだけの者でも、身の内かりものという真が分からねばどうもならん」。
|
|
| 【お指図】 |
11.19日、お指図。「前川菊太郎結婚の盃の際お話し」。
| 「この度は待ちかねた/\、長らく/\、一寸筆/\、さあさぁ、やれやれ、待ちかねて/\もう待って/\これまでぢゆう/\、やま/\古き事これまで聞いていれど、あと/\みて一つ日このところ、よもや/\の道は分からん。どうなるも因縁もって引き寄せる、年が何年たとうが日がおくれようが、話し通り伝えた通り見せにやならん、結ばにやならん。皆な結び一つ/\心を寄せてあらためば、一つは理を積む理を集める。ゆく/\長く楽しみ、楽しむよう/\一つはじまり、二つはじまり、又一つあとしばらく長い間じや、道をみせて急ぐ心、これからせく心、今までやう/\やれ/\ウ‥‥。」。
|
|
| 【お指図】 |
12.5日、のお指図。
| 「さあさあもうこれ一日の日を、段々追い詰めてある。日柄もまずない。又一つ天災という事情も聞き分けにゃならん。掃除は、万事の処に心を治めてくれ。掃除掃除天災一つの理は計られん」。
|
|
12.13日(陰暦10.25日)、教祖墓地を善福寺から豊田山へ改葬(参拝者10数万人)。式典で奏楽を演奏する。この時初めて天理教教徒だけの奏楽となった。
12.20日、天理教一派独立に付き、お指図を伺い、真柱らが東京へ。
この年、全国府県の半数以上に天理教会ができた。160教会、信者117万人に及んだ。
この年、京都の綾部に天保7年に生まれた出口直(ナオ)が神がかりとなって物質万能の世を直すとお筆先を沢山作って、艮(うしとら)の金神を祀るようになる。やがて、うしとらの金神による〈世の立替え立直し〉を訴えていくことになる。
| (お道の教勢、動勢) |
| 積善講(講元/飯田岩次郎)が講元宅に平安支教会を設置し、やがて教会新築もなる。東京に浅草教会。埼玉県で、25年4月、立野堀、同年9月、秩父の二教会がもっとも早く設置された。立野堀とは南埼玉郡八条村大字立野堀(現草加市)のことで、この地の高橋庄五郎が家族の病気について深い悩みをもっていたのを、東京浅草の布教師に救われたことに教会は始まっている(現在立野堀大教会は草加市稲荷町にある)。この高橋ほか一名から信仰へ導かれた人びとの中に、大沢町の高野柳蔵とその母ふじがあり、この両人と大沢町の金物商深野太郎右衛門とが力をあわせて布教に努め、浅草支教会に属する大沢布教所の設立を25年4月に達成した。
|
| (当時の国内社会事情) |
| 1892(明治25).2.2日、亀の瀬トンネル開通。大阪湊町・奈良間の鉄道全通(現関西線)。 |
| (宗教界の動き) |
| 奈良吉野神宮 後醍醐帝 創建←吉水神社 |
| 府県社神官資格制定。天皇御真影奉蔵学校儀式方。 |
| 帝大教授・久米邦武の学術論文「神道は祭天の古俗」を巡って激しい論争(久米邦武筆禍事件)。久米邦武は帝国大学教授職非職となり、『史学雑誌』『史海』の論文が掲載された該当号は内務大臣品川弥二郎により発禁処分。 |
| この年、大本教開教。 |
| 日本福音ルーテル教会設立。 |
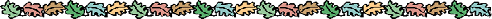



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)