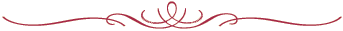
| れんだいこの中山みき論 |
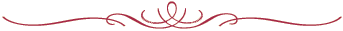
更新日/2024(平成31→5.1栄和改元/栄和6)年3.4日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「れんだいこの中山みき論」をしておく。 2007.2.25日 れんだいこ拝 |
| (「中山ミキ教祖伝」 はじめに) | |
| れんだいこは、江戸幕末期に呱呱の声をあげた天理教教祖中山みきを、日本の生んだ最大の傑物宗教家にして、「西のイエス、東のみき」と並び称されるに値する御方であると受けとめている。この彼女の実像を知れば、同時代に西欧から起こったマルクス主義と並行して、ほぼ同じ共生観点よりする社会変革の担い手であったことが知れるであろう。残念ながらみき教義がこの社会思想的観点から考察されることは皆無であるように思われる。それは、マルクス主義の西欧に於ける宗教批判を単に横滑りさせただけの、経文読みの経文知らず的知の貧困の為せる技であろう。彼らは科学教信者でしかないというのに。もとへ、そういう意味において、本レポートは貴重な役割を持つものと自負している。 もう一つ、こちらの方が通常の見方であるが、天理教を宗教として観た場合にも白眉であることが案外と知られていない。世界中の宗教に精通している俊英小滝透/氏は、著書「いのち永遠に−教祖中山みき」の後書き中で次のように述べている。
れんだいこは、この言い回しにマルクス主義、あるいはアナーキズムとの絡みの考察を加えれば、他に付け足すことはない。(と、こう書いていたが、今は付け足す必要を感じている。今日では出雲王朝論を獲得しており、この観点からの縄文社会主義論を生み出している。こうなると、マルクス主義、アナーキズム、イエス教との絡みで捉えるよりも、縄文社会主義の幕末的再生と云う観点から照射してみたいと思っている。この方面からの摺り合わせの必要を感じている。2018.7.6日現在) 有難いことに、知ってか知らずでか、お道の初期信者は、みきの伝記資料を細かに塊集している。それは、原始キリスト教教団がイエスの行状を大切に口伝保存してきた様子に匹敵している。但し、みき資料もイエス資料同様に玉石混交させられているので実像が分かりにくい。これを仕分けする能力が問われていると心得ている。 以下、れんだいこは、みきの生涯をできるだけ時系列で追うことにする。但し特に重要な史実についてはそこで項目を立てて一区切りになるよう経過を叙述した。内容に立ち入る必要のある場合にはさらに項目を立てて分析した。そういう意味では時系列には必ずしもなっていない。全体として出版前の予備資料としてレポート形式で書き上げているので、前後の文章は接合されていない。必要な個所についてはその都度私見.私論を書き添えた。 なお、非常に長文化している為最重要事項についてはゴシック大文字で記した。最初はこの部分のみを読み進めたほうが判りやすいし疲れない、次に普通文字を読み進めるのが適切かと老爺婆心ながら御提言させていただきます。 2006.11.18日再編集 れんだいこ拝 |
| 【れんだいこが、中山みきに注目する理由】 | |||||
| 以上、天理教教祖中山みきを、同時代の西欧に起こったマルクス主義と比較して論ずること、及び天理教教祖中山みきを、イエスキリストと同じ座標で捉え「男イエス、女みき」と二つ一つで評すること。みきがそのように評されることは未だないが、魅力的なテーマである。 れんだいこが、中山みきに注目するのは、その御教えが思想戦線での現代の混迷を解くカギを握っているのではなかろうかと思うからである。現代は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、その他諸宗教との卍巴(まんじともえ)の争いが続いているが、このまま行くと世界絶滅宗教戦争にまで達しそうである。互いが引くに引けないところまで進みつつあるように思われる。れんだいこの見るところ、ユダヤ教パリサイ派の得手勝手且つ狂信的な「選民−ゴイム思想」に基づくネオシオニズムが諸悪の根源ではないかと見立ている。 この闘いに中山みきの御教えを対置したところで何の歯止めもかかりそうにないが、れんだいこは、ユダヤ教のどこがおかしいのかを宗教原理的なところで明らかにするのに、中山みきの御教えが役に立つと思っている。そういう意味で、中立的に割り込むのではなく、ユダヤ教に濃厚な「選民−ゴイム思想」原理をたしなめ、改心させ、そのことによってユダヤ教とキリスト教の確執、ユダヤ教&キリスト教連合とイスラム教の確執をも和らげようと思う。そうすることでしか卍巴戦の陥穽から抜け出せそうにないと思っている。 中山みきの御教えは、その核心を為す元始まり譚「元の理」が、ユダヤ教−キリスト教−イスラム教世界が信を置く聖書式天地創造譚に対置された、史上初めての質量ともに秀でた天地創造譚であるところに価値がある。ユダヤ教−キリスト教−イスラム教の蒙を拓く為の唯一無比の創世記である。これを知らしめることこそが、時代閉塞打開のキーなのではあるまいか。人類がこれを学ぶことこそが平和共存生活の始まりなのではなかろうか。れんだいこは、元始まり譚「元の理」をそのように高く評価している。 小滝氏に一連の中山みき研究がある。「いのち永遠に」の観点をほぼ踏襲できるので以下紹介する。(れんだいこ観点によりアレンジしている)
小滝氏は、「これから語る天理教もそうした新宗教群の一つである」として解説に踏み込み、同時期のそれらよりも抜きんでいる特質を次のように指摘している。
|
|||||
| 小滝透/氏は、中山みきの何たるかを見事に語っている。それによれば、幕末新興宗教の一つとして生まれた天理教が、他のどの宗派よりも幕末期の時代的閉塞を打ち破り、今後の日本社会に隆盛しようとしつつあった私有財産制を鋭く批判し、縄文社会主義とも申すべき共産共同制社会を髣髴とさせる共生理想を掲げて幕末から明治維新期を躍動し、幕末新興宗教の最大セクトへと成長していったことを炯眼している。ユダヤ、キリスト、イスラムの西欧宗教に精通した小滝氏は、「ある意味で、民衆的な回天運動であり、驚くべき普遍性と世界性を秘めたものになっていた」とまで評している。 これほどに高く評価される「中山みきの思想と生き様(ひながた)」が埋もれているのは惜しいことである。れんだいこは、若かりし頃、ひょんな機縁から中山みきを知った。驚きの連続であった。本部教団のテキストを通じてしか知られないみきではあるが、それを通してでさえ本部教団テキストからはみでる中山みきを知ることができる。以来、それなりにみき研究を続けてきた。 なぜ今「中山みき」なのか。この問いと答え方が肝心だ。れんだいこは次のように思っている。一つは、今や既成の価値観の虚飾が誰の目にもはっきりしつつあり、賢明なる者はそうした価値観を生み出す思想そのものから一歩も二歩も遠ざかりつつある。つまり、思想喪失の時代に突入している。はたして、その長きを数えることが誉れであろうか。これに対して、既成の思想の解体を優先的に標榜する者が生まれるのも自然の勢いというものだろう。それに対してれんだいこはこう思う。確かに解体を通してしか再生はあり得ないとしても、再生プランを持とうとしない解体作業はやはり変調ではなかろうか。 このように考えたとき、中山みきの教理が輝いてくる。近代にあって資本主義的な道が敷かれ詰めようとしていた時、彼女はそれと対極的な道を提示していた。その教義の真髄が長らく無視されてきているが、耳を傾けて損はなかろう。思えば、資本主義的な道は果して、歴史法則的な必然の道なのだろうか。それもやはり政策的に選択された「作られた歴史」なのではなかろうか。 もっとはっきり云えば、近世以来の資本主義化は、「シオンの議定書派」即ち今日的なネオシオニストが、陰謀的申し合わせの下に世界諸国に押し付け誘導した結果としての体制なのではなかろうか。植民地主義も帝国主義も世界大戦も国際連盟、国際連合も、米ソ冷戦も世界各地の紛争も、ネオシオニスト的軍需政商が意図的に引き起こしてきた歴史なのではなかろうか。原発も著作権も(その後の世界同時多発的コロナ騒動も)然りである。マルクス主義の歴史理論は、そのような人為的資本主義を歴史法則的に認識させようとしている点で、同じ穴のムジナではないかとの疑念を生む。れんだいこはそう思うようになった。 もし、「作られた歴史」なら別の歴史を創ることが可能なのではなかろうか。その際、みき教理の指針は貴重な手引きになるのではなかろうか。みき教理の本質は、「互いが相食む関係から共生の関係」への転換を迫るところにある。その論を非政治的に構築しているので見落とされがちであるが、れんだいこが判ずれば立派な政治思想である。みきの政治思想を検証することはことのほか意義が大きいように思われる。 もう一つ。みきは、人がその寿命を費やす過程で「勇む」心を非常に重視した。その反対は「いずむ」であったが、それは心の持ち方の間違いから生まれているとして「埃」(ほこり)に例え、それを祓う「つとめ」を教えた。「埃(ほこり)論」の価値も高い。それまでの因縁、罪業、原罪、宿命的な諦観論によってではなく、日本古神道的な祓いたまえ清めたまえ教理を媒介させて、掃除して祓うことのできる「埃(ほこり)のようなもの」へと認識を転換させた。目指すところは「人々互いに陽気づとめによる陽気暮らし世界の湧出」であった。この指針の下に、道人の滋養強壮となる「つとめ」が考案された。「つとめ」の哲理も深い。 これを思えば、近代から現代に至る心の持ちようの何と「陰」な精神が跋扈していることだろう。権利ー義務観念も、その正の面は良しとしても、「いずむ」に繋がる負の面をも知るべきではなかろうか。 残念なことは、この「お道」の教義を信奉する者達の間にもいつの間にか「いずむイズム」がはびこっているように思われることである。「お道」にとって気難しさはその教えの対極であろうに。例えば、各教会では月に一度の祭典がありその後に「なおらい」と云われる食事会がある。こうした時には、まさに世にも珍しい「陽気暮らし」を現出させるべきではなかろうか。その心を忘れた「なおらい」は単にスケジュールでしかなく、それは廃れる前兆であろう。しかして、「なおらい」はその教会の質のバロメーターかも知れぬ。 2003.8.7日、2006.7.2日再編集 れんだいこ拝 |
| 【れんだいこ中山みき天理教教祖伝の視座について】 |
|
天理教徒の大きな財産の一つに「教祖(おやさま)中山みき」(以下、「みき」と云い換える)の生涯の道すがらがある。天理教理では、この道すがらを「ひながた」(雛型)と云い、天理教徒の信仰上の指針「めどう」(目標)として重要な役割を果たしている。この「教祖ひながた」をどの時点より認めるのかにつき見解の相違がある。これについては、「「ひながた」考」に記す。 |
| 【「中山ミキ教祖伝」叙述の観点について】 | |
| ところで、「みき」であれ一般に或る人を考察する場合に、どの様な角度から浮き彫りにしていけば正鵠を期しえるであろうか。この為の絶対的な手法は在りや否や。というわけで、私の方法論をここで概括しておこうと思う。私は、或る人に影響を及ぼすであろう諸要因のうちより、その人の活動範囲の親しきところより次第にという手法で、つまり次の角度より照射して論述して行こうと思う。 まず第一の要因として、その人を取り巻いた地理的自然的「衣食住」的環境の諸要因に注目することである。その人の生まれ育った土地の温度、湿度、地質、風景、「衣食住」などの及ぼした影響に対する考察という意味であり、具体的に云いかえればその人の生息した地域の自然的な環境の及ぼした影響を探ることと云えようか。即ち温暖な地域であったのか寒冷な地域であったのか、河川海洋に隣接した地域であったのか内陸的もしくは山岳地域であったのか、どんな「衣食住」をしていたのか等々を調べることである。この要因は、確実に或る人に或る影響を刻印しているであろう。 次に、その人の生活した社会的な環境の諸要因に注目することである。その人の生まれ育った地域の生産的.就業的.家族的な環境の影響に対する考察という意味であり、具体的に云いかえれば、その人の生息した地域の社会的なものの及ぼした影響を探ることと云えようか。即ち農業地域で育ったのか、山間部であったのか海岸部であったのか、周囲の環境がどのような産業を基調にしていたのか、そうした中で当人が農林魚業、商工業あるいはその他の職業のいずれで生計を得ていたのか等々を調べることである。更にその人に纏わる家族的紺帯の制約の影響を尋ねることも重要である。こうした要因も又、確実に或る人に或る影響を刻印しているであろう。 次の要因として、その人を制約した歴史的社会的な環境の諸要因についても考察が必要であろう。即ち、その人の生活した時代の生産力(社会の豊かさ)と生産的な諸関係(身分)の問題であり、身分的な階層、階級分化の中で占めた立場により蒙った影響による考察である。言い替えれば、その人が生活して交わった地域がどんな歴史を辿ってきており、どんな変遷段階にあって、どういう趨勢乃至変革の流れの中にいたのか、どういう政治経済文化に浴していたのかという面での考察である。こうした要因も確実に或る人に或る影響を刻印しているであろう。 最後に、当人の身体的精神的資質に伴う特徴による能力も指摘されねばならないであろう。この能力は、当人が生活した時代の空気と向かおうとする新時代への息吹を吸収する感性的な能力を遺伝的な資質をまで含めて考察されねばならないであろう。こうした視点に立って或る人をレリ−フすることにより、正確な考察に近づけるのではなかろうかと思う。 尤も、それぞれの視点は単独に成立しうるものではなく、それぞれが相互に作用しあっておるのが実際であるうから、記述上は非常に困難なことでもある。しかしながら、整理上は上述の観点により導かれざるを得ぬことと思われ、私の「中山ミキ伝」執筆において、このことをどこまで能くなし得るかは心許ないけれども、ともあれこうした要因を念頭に置きながらいざ執筆の航海に船出しようと思う。 最後に、本書執筆の視点について述べておこうと思う。「中山ミキ伝」を、「みき」の精神の内在的な発展という角度から追跡していくことを既に述べたが、実際のところあらゆる方面にわたって「みき」の詳細な研究を為すということは不可能であろう。そこで、次の三ベクトルに照準をあてて、本書を執筆していくという角度を定めておきたい。一つは、「みき」の宗教的な世界観及びその認識について。一つは、宗教的な表象の背後に潜んだ「みき」の社会観及びその変革論乃至は人間認識観及びその変革論について。一つは、家族制度における戸長権、夫婦、男女に関する論について。 事実この三つの要素を廻っての教え、諭しこそ、「みき」生涯にわたって示された数々のうちにも白眉であったものと思われる。本書はこうした角度よりの執筆を心掛けたたわけであるけれども、どこまで能く為し得たであろうか、読者諸兄のご判断を仰ぐ次第であります。 |
|
| (補足) 神崎繁・東京都立大学哲学科助教授の2001.2.20日毎日新聞「未来の発見者たち−プルタルコス」は次のように述べている。
|
|
| (補足) 「世界宗教研究センター」所長を勤めたことのあるW.C.スミス教授は次のように述べている。
|
| 【「中山ミキの原像」について】 |
| 「中山ミキの原像」が定まらない。みきを直接知るには、「お筆先、み神楽歌、諭し、口伝」を通してしか知るよりない。このうち、「お筆先、み神楽歌」についてはみき直伝であるのでそれから知れば良い。問題は「諭し、口伝」の方である。こちらは、聞き手の気質、性向、能力により歪められたみき論がはびこる可能性がある。しかしながら、「お筆先、み神楽歌」の教科書的言語に比して、「諭し、口伝」の方にこそみきの肉声が宿されている面があり、それやこれやでややこしい。 以上のことを踏まえて「中山ミキの原像」に迫る必要がある。れんだいこが思うに、市井に漏れ伝わるみき像には正確な面と逆の面の両方がある。それ故に、我々は、正確なみき像を引き出し、不正確なみき像を忌避する能力を身につける必要がある。それは如何にして可能であろうか。このことは何もみき論ばかりではない。評論一般に通用することである。結論は、受け手の能力が問われており、そこに評論の醍醐味があることを弁え、信に足りるものを取捨選択しながら学び取っていく以外にないということになる。しかしてそれも又能力であろう。蛇足ながら、能力とは知識を云うのではない。感性力、その媒介にある霊能までも含めた総合能力のことを云っている。 ここまで説くと当然のことながられんだいこの能力が問われることになる。れんだいこは逃げず、れんだいこのみき論を呈示しようと思う。採りあえず概略スケッチしおきたいが、その前にれんだいこの忌避するみき論を概述しておきたい。逆から見る方法も有効であるから。 その一は、本部教理に基づくみき像である。教団は現在、「稿本天理教教祖伝」を発行している。「稿本天理教教祖伝」はそれまでの幾多の教祖伝に比べればそれなりによくできた教祖伝ではある。最近気づいたことは、村松梢風氏の「大和の神楽歌」(共立出版、1943(昭和18).6.25日初版)を下敷きに更に考証を加えた作品のように思われる。興味のある方は確認されてみるが良かろう。問題は、稿本とあるように、教団が策定した時点では仮の教祖伝としていたことが分かるように決して完成されたものではない。れんだいこの判ずるところ、「中山ミキの原像」にも正確な教理にも未だ迫れていない。 その二は、預言者然として捉えられるみき像である。重複するが、「稿本天理教教祖伝」もその他諸氏の教祖伝も、みきを如何にも宗教家としての範疇に押し込んで教説にしてしまっており社会思想的なアプローチができていない。みきの予言能力は事実であるが、その方面のみからみきを捉える必要はなかろう。もっと大胆に真実そうであったであろう社会思想的能力に光を当てるべきではなかろうか。かく弁えるべきであろう。 その三は、みきの教えと全く違う観点からのみき像である。これは主にみきの不肖の弟子達が己の甲羅に合わせて理解したみき像であり、自身の悟りとしてみき像を云々する限りでは構わないのだが、これがみきが云い為したこととしてあらぬことを吹聴するとこれは具合が悪い。みきの新思想としての偉大さを引き出さず、従来の仏教的、神道的あるいはキリスト教的ユダヤ教的理解に基づくみき論の愚を戒めねばならないであろう。これを確認する。 |
| 【近代創始宗教の中での天理教の地位考】 |
| 「近代創始宗教の中での天理教の地位」を確認しておく。ネット検索で、松井圭介氏の「カリスマの継承からみた天理教系教団の分派形成」に出くわした。いろいろ示唆されるところ多であるが、重要なところで観点を共有できないところがあるので俎上に乗せておく。松井氏曰く、如来、黒住、金光、天理等の近代(幕末)創始宗教は、「封建社会末期に生きる抑圧された民衆の切実な願いに応えようとする新しい宗教運動であったが」云々としている。この観点は松井氏のみならず近代(幕末)創始宗教論の通説であるが、れんだいこは若干異を唱えたい。れんだいこは、その「封建社会末期」論、それに呼応する「抑圧された民衆」論の観点が共有できない。近代(幕末)創始宗教のスケールはもっと大きく、その底流にあったものは黒船来航前夜の日本史上由々しき事態を見据えての、日本国體の覚醒を図ろうとする暗中模索だったのではなかろうか。それをいわば最も深化させたレベルで教理を説いたのが天理教で、その深みの分だけ信徒を増したのではなかろうか。「中でも天理教は、第二次世界大戦後まで最大の教勢をもつ新宗教教団として、近代以降の新宗教教団に大きな影響を与えてきた」と記述されている通りである。思えば、それらのエネルギーを引き出した当時の社会は、「抑圧された民衆」どころか「自由闊達な能力を持つ民衆」を生み出していたと受け止めるべきではなかろうか。ここのところに我慢ならない観点の差があるので明瞭にしておく。 次に、天理教に対する弾圧が突出していたことに対して、「みきの宗教活動が後に厳しい弾圧を受けるようになるのも、この宗教的開明性が当時の社会の価値観を乱すものとなったことに起因している」としている件(くだり)が共有できない。みきの宗教活動の弾圧要因として「宗教的開明性」を挙げ、「当時の社会の価値観を乱すものとなった」としているが、本当にそうだろうか。私は、ほぼ真逆で捉えている。即ち、黒船来航以降の西欧勢力の日本史に対する容喙、それに続く幕末維新、明治維新を経て次第に黒船勢力が日本国體権力を掌握し始め、これに呼応して近代(幕末)創始宗教の日本国體覚醒運動が掣肘され始め、中でも最も手強いと見做されたのが天理教であり、弾圧に次ぐ弾圧を余儀なくされたと捉えるべきではないのか。ここを曖昧にすると全てが模糊になるのではなかろうか。 次に、「みきによる新しい世界の創造が、最も鮮明に現れているのがこの神観と人間観である。唯一絶対なる神のもとでの人間の平等は、天理教の世界観、救済観の根本であるといってもよいであろう」と述べている。「唯一絶対なる神」なる表現は問題で、ユダヤ-キリスト教的ゼウス観化させていることになる。みきの教理は日本古来の出雲神道(古神道)と親和しており、ユダヤ-キリスト教的神観で説くのは邪道であろう。 次に、「村上(1980)も指摘するように、幕末維新期に生れてきた民衆宗教に共通する特徴の一つに新しい人間観の確立がある。人間は如来の子であるとして平等を唱えた一尊如来きの。天照を万物の根源とし、人間はその分身であり神人不二であるとし、人間の平等と尊厳を宗教的に基礎づけた黒住宗忠。神の氏子としてあらゆる人間の平等を説いた金光大神。彼らと中山みきの間には共通のモティーフが存在している」と記している。ここの件は参考になるので取り入れたい。続いて次のように述べている。「それは当時の歴史的状況が民衆に対してもたらした、社会的な抑圧からの解放である。それは人間が人間らしく生きるための主張である」。如何なものだろうか。既に指摘したが、「社会的な抑圧からの解放」を云われるほど抑圧されていなかったのではなかろうか、「人間が人間らしく生きるための主張」も然りで、今日の方がよほど貧困で世論操作されている社会になっているのではなかろうか。 |
| 【れんだいこの「中山みき最後の天啓の巻」批判】 | |||||||||||||||
「天理教教祖資料集」の「中山みき最後の天啓の巻」には次のような話が掲載されている。いろんな箇所で、みきが云う訳がないことを記しているが特にひどいのを参考事例として挙げる。
れんだいこは、上記一、二、三の観点はいずれも真実のみき像からかけ離れていると考えており、故に排斥したい。しかしこれだけでは消極的過ぎるので、れんだいこのみき像を打ち出したい。れんだいこ理解によれば、みきとは本サイトで考究したような像になる。 2005.4.19日、2007.10.6日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)