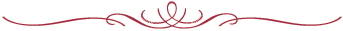
| 【第一部】 |
|
はじめに(その1) |
世界三大宗教との関係づけ |
|
はじめに(その2) |
当時の西欧思潮との関係付け |
|
はじめに(その3) |
みきの家系 |
|
はじめに(その4) |
生まれた地域の風土 |
|
誕生から嫁ぐまで(その1) |
みきの誕生の様子 |
|
誕生から嫁ぐまで(その2) |
みきの幼少の頃の様子 |
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(1) 】
|
発心 |
|
誕生から嫁ぐまで(その3) |
娘時代のみきのご性状 |
|
誕生から嫁ぐまで(その4) |
みき寺小屋に通う |
|
誕生から嫁ぐまで(その5) |
嫁入り問答 |
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(2) 】 |
みきの尼僧願望 |
|
【みきの「自律」足跡行程(1)】 |
嫁入前の三条件 |
|
誕生から嫁ぐまで(その6) |
みき中山家へ嫁ぐ |
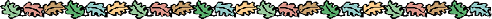
| 【第二部】 |
|
主婦時代のみき(その1) |
新婚時代の様子 |
|
【みきの「自律」足跡行程(2)】 |
寸暇を惜しんでの仏間のひと時 |
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(3)】 |
浄土宗信仰 |
|
主婦時代のみき(その2) |
へら渡し |
|
主婦時代のみき(その3) |
五重相伝の授戒 |
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(4)】 |
浄土宗信仰との決別 |
|
主婦時代のみき(その四) |
「おかの寵愛事変」 |
|
主婦時代のみき(その五) |
長男誕生、出産の慶び |
|
この頃の世相 |
|
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(五)】 |
衆生救済の萌芽
|
|
主婦時代のみき(その六) |
「ほうそう事件」 |
|
【みきの「自律」足跡行程(三)】 |
主婦の座に磐石の地位を得る |
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(六)】 |
みき神通力を味得する |
|
主婦時代のみき(その七) |
みきの主婦の鑑時代 |
|
この頃の世の荒びとご政情(一) |
天保の大飢饉と世相 |
|
この頃の世の荒びとご政情(二) |
おかげ参り |
|
この頃の世の荒びとご政情(三) |
大塩平八郎の乱 |
|
この頃の世の荒びとご政情(四) |
国学の動き |
|
この頃の世の荒びとご政情(五) |
洋学の動き |
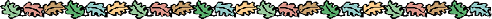
| 【第三部】 |
|
この頃の新潮流(一) |
隆盛する民間信仰 |
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(七)】 |
諸仏諸神信仰詣で |
|
この頃の新潮流(二) |
幕末宗教界の動き【教派神道の発祥】 |
|
この頃の新潮流(三) |
西欧社会運動の動き【マルクス主義の発祥】 |
|
この頃の新潮流(四) |
アメリカ新大陸の動き【モルモン教の発祥】 |
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(八)】 |
真言密教への接近と山伏修験道の修行と転輪王信仰】 |
|
みきの神がかり前の様子 |
長男秀司の身上と加持祈祷 |
|
【みきの宗教的精神史足跡行程(九)】 |
「転輪王」信仰に辿り着く |
|
【みきの「自律」足跡行程(四)】 |
矛盾の飽和点
|
|
みきの神がかり(一) |
降神現象と天啓問答の始まり |
|
みきの神がかり(二) |
天啓問答 |
|
みきの神がかり(三) |
みき、「神の社」に貰われる |
|
「みきの『神の社』貰い受け」考 |
|
|
天啓、神がかり考 |
|
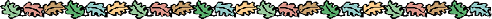
| 【第四部】 |
|
みきの教義形成の歩み(一) |
内蔵篭り |
|
【みきの「自律」足跡行程(五)】 |
内蔵篭り |
|
みきの教義形成の歩み(二) |
「貧に落ちきれ」 |
|
神言(一) |
貧に落ちきれ考 |
|
【みきの「自律」足跡行程(六)】 |
神格憑依 |
|
みきの教義形成の歩み(三) |
善兵衛の苦悶と世評と狐つき騒動 |
|
みきの教義形成の歩み(四) |
「屋形毀ち」 |
|
神言(二) |
「屋形毀ち」考 |
|
みきの教義形成の歩み(四) |
みきの「身上」と中山家の親族会議 |
|
【みきの「自律」足跡行程(七)】 |
みきの「身上」考 |
|
みきの教義形成の歩み(五) |
みきの苦悩と宮池事件 |
|
【みきの「自律」足跡行程(八)】 |
宮池事件考 |
|
みきの教義形成の歩み(六) |
堪能の日々その一段階 |
|
【みきの「自律」足跡行程(九)】 |
堪能考 |
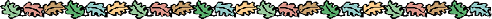
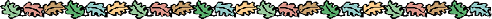
| 【第八部】 |
|
開教(一) |
お針子、寺子屋を開く |
|
【みきの「自律」足跡行程(十)】 |
お針子考 |
|
神言(三) |
夫善兵衛の出直しと母屋取りこぼち |
|
【みきの「自律」足跡行程(十一)】 |
母屋の取壊し考 |
|
開教(二) |
更に堪能練りあいの日々 |
|
お諭し(一) |
不足を云うな、にちにちを楽しめ |
|
開教(三) |
こかんの大坂布教 |
|
幕末世相(一) |
米艦隊司令長官ぺルリ来航 |
|
幕末世相(二) |
幕末志士活動と世直しの動き |
|
開教(四) |
「をびや許し」のはじめ/世界助けの道開け |
|
お諭し(二) |
神の自由自在「をびや許し」考 |
|
お諭し(三) |
男女隔てなし、反習俗、女性解放 |
|
開教(五) |
みきの「珍しいお助け」始まる |
|
開教(六) |
貧のどん底 |
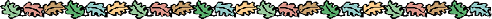
| 【第九部】 |
|
お道の発展(一) |
道の黎明-初期信者参集 |
|
信仰作法の変遷(一) |
最初期の信仰形態考 |
|
信仰作法の変遷(二) |
みきの出張り |
|
信仰作法の変遷(三) |
授け |
|
お道の発展(二) |
飯降伊蔵の引き寄せ |
|
お道の発展(三) |
建て家談議と普請の始まり |
|
お道の大節(一) |
第一次大和神社事件と伊蔵の誠真実 |
|
みきのお助け百景(一) |
ハンセン病患者の「お助け」 |
|
お道の発展(四) |
つとめ場所の完成 |
|
教理考(一) |
つとめ場所考 |
|
この頃の迫害の様子(一) |
宗派問答発生する |
|
お道の大節(二) |
助造事件 |
|
お道の発展(五) |
信仰の拡がり |
|
この頃の迫害の様子(二) |
妨害者次々参上する |
|
お道の発展(六) |
真之亮の誕生と教勢拡大 |
|
この頃の迫害の様子(三) |
古市代官所へのお出まし |
|
『応法の理』の動き(一) |
吉田神祇管領の配下になる |
|
お道の発展(七) |
つとめの歌と手振りの教え |
|
教理考(二) |
「おつとめ」考 |
|
お道の発展(八) |
「十二下りのお歌」の御作成 |
|
教理考(三) |
「お歌」考 |
|
お道の発展(九) |
お手振りのご指導 |
|
教理考(四) |
神楽づとめ、手踊り考 |
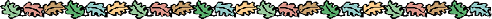
| 【第十部】 |
|
幕末の動き |
|
|
明治維新 |
|
|
お道の発展(十) |
「お筆先」の御執筆 |
|
教理考(五) |
「お筆先」考 |
|
お道の大節(三) |
官制「神随らの道」とお道の真っ向対立 |
|
教理考(六) |
お道教義の特質としてのみきの「神随らの道」 |
|
秀司の動き(一) |
この頃の中山家と秀司の嫁取り |
|
お道の発展(十一) |
教勢の発展と講の結成 |
|
この頃の迫害の様子(四) |
迫害の予言 |
|
お道の発展(十二) |
教祖、断食後「別火別鍋」宣言 |
|
教理考(七) |
「別火別鍋」考 |
|
お道の発展(十三) |
飯降、甘露台の模型を作る |
|
教理考(八) |
甘露台考 |
|
明治新政府の宗教統制の動き(一) |
「廃仏毀釈運動」 |
|
明治新政府の宗教統制の動き(二) |
「教派神道13派」統制の動き |
|
明治新政府の宗教統制の動き(三) |
天皇制イデオロギー運動 |
|
明治新政府の宗教統制の動き(四) |
靖国神社運動 |
|
お道の発展(十四) |
みきの論戦 |
|
お道の発展(十五) |
みきのお筆先執筆加速 |
|
お道の発展(十六) |
神楽面のお出まし |
|
お道の発展(十七) |
「高山」布教、教祖、迫害を予見す |
|
お道の大節(四) |
第二次大和神社事件 |
|
教理考(九) |
「高山」布教考 |
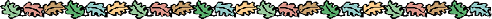
| 【第十一部】 |
|
お道の大節(五) |
「山村御殿」問答 |
|
お道の発展(十八) |
教祖、「月日」と改める |
|
この頃の迫害の様子(五) |
「中教院事件の節」 |
|
お道の発展(十九) |
教祖赤衣を召す |
|
教理考(十) |
教祖「月日」赤衣考
|
|
お道の発展(二十) |
「おさづけの理」 をお渡す |
|
教理考(十一) |
おさづけ考 |
|
お道の発展(二一) |
教勢発展と弾圧の予感 |
|
お道の発展(二二) |
中南の門の建築始まる |
|
お道の発展(二三) |
ぢば定め |
|
教理考(十二) |
ぢば定め考 |
|
お道の発展(二四) |
【「おつとめ」の整備、完結 |
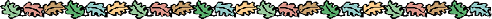
| 【第十二部】 |
|
教祖のご苦労(一) |
教祖最初のご苦労 |
|
教理考(十三) |
ご苦労考 |
|
お道の挫折と発展(一) |
こかんの出直し |
|
お道の挫折と発展(二) |
この頃の教勢と中山家 |
|
お道の挫折と発展(三) |
講の結成続々 |
|
教理考(十三) |
講考 |
|
『応法の理』の動き(二) |
蒸風呂、宿屋の営業 |
|
お道の挫折と発展(四) |
鳴物の教え |
|
当時の社会事情 |
|
|
お道の挫折と発展(五) |
教祖、「月日」から「をや(親)」へと称す |
|
『応法の理』の動き(三) |
「転輪王講社」の設置 |
|
教理考(十二) |
『応法の理』の動きに対する教祖の態度 |
|
お道の挫折と発展(六) |
真之亮養子入りと伊蔵の伏せこみ要請 |
|
お道の挫折と発展(七) |
「こふき」をつくれ |
|
教理考(十三) |
「こふき」考 |
|
お道の挫折と発展(八) |
秀司の出直し |
|
教理考(十四) |
出直し考 |
|
お道の挫折と発展(九) |
伊蔵の伏せこみ |
|
教理考(十五) |
伏せこみ考 |
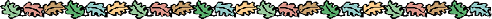
| 【第十三】 |
|
お道の挫折と発展(十) |
かんろだいの没収と迫害 |
|
お道の挫折と発展(十一) |
「お筆先」最後のご執筆 |
|
教祖のご苦労(二) |
奈良監獄署への二度目の御苦労 |
|
お道の挫折と発展(十二) |
ご休息所の普請始まる |
|
お道の挫折と発展(十三) |
毎日つとめ |
|
教理考(十六) |
毎日つとめ考 |
|
お道の挫折と発展(十四) |
我孫子事件 |
|
お道の挫折と発展(十五) |
燃え上がる信仰と弾圧 |
|
教祖のご苦労(三) |
教祖又もや「ご苦労」 |
|
お道の挫折と発展(十六) |
御休息所の建てかけ |
|
お道の挫折と発展(十七) |
教勢のますますの発展 |
|
お道の挫折と発展(十八) |
伊蔵が名代勤める |
|
教理考(十七) |
伊蔵の名代考 |
|
お道の挫折と発展(十八) |
雨乞いづとめと拘引 |
|
教理考(十八) |
雨乞いづとめ考 |
|
お道の挫折と発展(十九) |
度重なる「ご苦労」 |
|
『応法の理』の動き(四) |
教会設置運動その一 |
|
『応法の理』の動き(五) |
教会設置運動その二 |
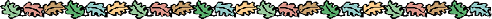
| 【第十四】 |
|
教祖のご苦労(四) |
最後の御苦労 |
|
お道の挫折と発展(二十) |
この時の取調べの苛酷な様子 |
|
お道の挫折と発展(二一) |
高弟仲田儀三郎の取調べの苛酷な様子 |
|
お道の挫折と発展(二二) |
ご帰還とその後のご様子 |
|
お道の挫折と発展(二三) |
真之亮の苦悩 |
|
お道の挫折と発展(二四) |
「御請書事件」神道管長他との問答 |
|
お道の挫折と発展(二五) |
厳寒のせき込み |
|
おさしづ問答その一 |
|
|
おさしづ問答その二 |
|
|
おさしづ問答その三 |
|
|
「扉をひらいて」教祖御身隠し |
|
|
教理考(十九) |
「教祖御身隠し」考 |
|
教理考(二十) |
存命の理 |
|
教祖没後その一 |
伊蔵の刻限話、本席に定まる |
|
『応法の理』の動き(六) |
神道天理教会設置の動き |
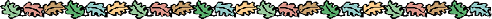
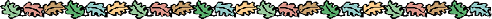



 (私論.私見)
(私論.私見)
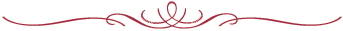
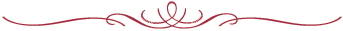
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)