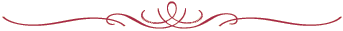
| 般若心経れんだいこ訳 |
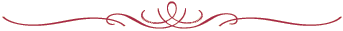
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.6.11日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 般若心経はインド仏教のサンスクリット語の漢語音訳である。両語の原義を踏まえて能く為されているようが、サンスクリット語の音をそのまま当て字している場合も有ったりで意味が今ひとつ分かりにくい。そこで、れんだいこが現代日本語訳を試みようと思う。いつしかやりたかったのだができずに今日まで至っている。いよいよ着手する。 れんだいこ訳の特徴として、般若心経を9文節に仕切った。意味に忠実に従った結果こうなった。今後はこれを基本とすべきではなかろうか。比較の為に、原文、その他を併載しておくことにする。まだまだ不十分であるが、釈迦の御教えの中心的思想の概要が分かるような気がする。 2008.5.29日 れんだいこ拝 |
| 【漢訳原文】 |
|
仏説摩訶般若波羅蜜多心経 |
| 【漢訳原文読み】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【訓み下し和訳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【中村元(はじめ)日本語訳】 | |
|
「日本語訳(小本 インド哲学の国際的な権威東大名誉教授中村元(はじめ)、岩波文庫1960年)」の該当箇所より転載する。
|
| 【れんだいこ意和訳】 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| Re:れんだいこのカンテラ時評405 | れんだいこ | 2008/06/01 |
| 【般若心経れんだいこ訳】 著作権考に分け入る事で、これが思想問題であることに気づきました。このことに気づかないまま小正義を振り回して、世の中を息苦しくしていく輩にどう対応すべきか。その一法として般若心経を考察する事にしました。直接的には関係有りませんが、大いに参考になる面があるように思います。 れんだいこが、般若心経に耳を傾けてみようと思う気になったのは、現代が余りにも思想が細っているとみなすからです。隆盛しているのはユダヤ教内タルムード派とも云うべき現代国際金融資本帝国主義即ちロスチャイルド派のネオ・シオニズムの奏でるご都合主義的な世界観、社会観、処世観に基く拝金、蓄財イデオロギーばかりで、人類は彼らが跳梁するようになって以来、精神の背丈が随分低くなった気がしています。 そうではない、もっと別の芳醇な思想があった筈だ、般若心経もその一つではないかと考え、初めてじっくりと解析しようと思い立ちました。但し、般若心経の訳たるや非常に様々で、いろんな風に説かれております。それらのうち、れんだいこが満足できるものはありません。そういう訳で、れんだいこ訳を市井提供いたします。ぜひ参考にして下さい。検索していましたら、この世界にも著作権が徘徊しております。れんだいこは無茶と思うけども、これが只今の世の倣いのようです。この先どこまで首絞めが続くのか。頼むから正義面だけはせんで欲しい。 原文はこうです。 仏説摩訶般若波羅蜜多心経 観自在菩薩行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄 舎利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識亦復如是 舎利子 是諸法空相 不生不滅 不垢不浄 不増不減 是故空中 無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法 無眼界 乃至無意識界 無無明 亦無無明尽 乃至無老死 亦無老死尽 無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故 菩提薩埵 依般若波羅蜜多故 心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃 三世諸仏 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多 是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪 能除一切苦 真実不虚 故説般若波羅蜜多呪 即説呪曰 羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶 般若心経 【訓み下し和訳】 仏説摩訶(まか)般若波羅蜜多心経 観自在菩薩が、般若波羅蜜多を熱心に行じし時、五蘊(ごうん)は皆、空(かいくう)と照見して、一切 の苦厄を度したまえり。 舎利子。色は空に異ならず、空は色に異ならず、色は即ち空であり、空は即ち色である。感覚、思うこ と、行う事、識ることも叉かくの如しと云われた。 舎利子。諸法は空相にして、生ぜず滅せず、垢(あか)つかず、浄からず、増えず減らず、この故に空の 中には色無く、受無く、想無く、行無く識無い。眼無く、耳無く、鼻無く、舌無く、身無く、意も無い。 色も声も香も味も触も法も無い。 眼界も無く、ないしは意識界も無い。無明も無く、叉無明が尽きることも無い。ないしは老も死も無く、 叉老と死の尽きることも無い。苦も集も滅も道も無い。智も無く叉智を得ることも無い。得ること無い故に である。 菩提薩埵(ぼだいさつた)は、般若波羅蜜多に依る故に、心に悩み心配無し。悩み心配無き故に、恐怖も無い。一切の転倒妄想を遠離し、涅槃(ねはん)を極める。三世諸仏(さんせぃしよぶつ)は、般若波羅蜜多 に依る 故に、得阿耨多羅三藐三菩提(とくあのくたらさんみやくさんぼだい)を得る。 故に知るべし。般若波羅蜜多は、これ大神呪(だいじんしゅ)なり。大明呪(だいみやうしゅ)なり。無上呪(むじょうしゅ)なり。無等等呪(むとうどうしゅ)なり。能く一切の苦を除き、真実にして虚ならず。 故に説般若波羅蜜多の呪を説く。 即ち、呪を説いて曰く、羯諦(ぎやてい)羯諦波羅(はら)羯諦、波羅僧(はらそう)羯諦 菩提薩婆訶(ぼじそわか) 般若心経 【れんだいこ意和訳】 この世の真実を知る根源的な叡智としての摩訶(まか)般若波羅蜜多の神髄を表わす仏説経文を奉る。 この世の真理真実を悟り賜われた観自在菩薩であられる釈迦(釈尊)は次のように説かれました。釈迦が修行時代かって深い悟りの瞑想に入り、熱心な行により、奥深い真実の智恵である般若波羅蜜多を会得せんとしていました。或る時、この世の全ての物の性質や形あるものの姿である五蘊(ごうん)の存在、その相関を自問自答の末に、五蘊の本性は皆、空であると見定められ、悟りを開かれました。以来、一切の苦厄から抜け出すことができたのです。 釈尊の高弟の一人で、バラモン教経由の智慧第一と云われていました舎利子(シャーリプトラ)が、かって釈迦に、「最深最高の智慧とはどのようなものでしょうか。それ得ようとすれば、どのように学び修行すべきでしょうか」と尋ねられました。 釈迦は次のように説かれました。この世に於いては、あらゆる物質、事象即ち色なるものは実体が在るようで有りません。究極、空として捉えるべきです。その空から色が生まれるからして空は色とも云えます。色は即ち空であり、空は即ち色であると認識すべきです。かく捉えないから拘りが生まれ、諸苦、諸病、諸厄の原因になっているのでは有りませんか。 感覚、想念、思想、意思、思考、行動、実践、知識等々も然りで、本性上空と了解すべきです。これが世の実相なのでは有りませんか。この理を知れば執着が生まれません。執着在るところに災禍が生まれております。更に云えば、世の中に絶対的にこうである、こうでなければならないとするのも執着で、これから解脱せねばなりません。この世の理法に反するからです。にも拘らず理法に反する規則や命令が出され、人々がこれを受け入れております。これらは世の実相に反しています。ここに全ての過ちが起因しているのでは有りませんか。 舎利子は更に問い、釈迦は次のように答えました。世の諸法は究極空相であり、これを大きな循環で観れば本質的に生ぜず滅せずでは無いでしょうか。この世に絶対的な汚れや穢(けが)れは有りません。絶対的な聖や浄も有りません。万事、増えもせず減りもせず大河の流れの如く悠久です。これが天地自然の理法です。 能く考えてみましょう。この世に存在するもの一切が本質上空では有りませんか。それ故に、思索抽象的に捉えられるもの、例えば色(物質、事象)、受(感覚、意識)、想(思想、概念)、行(行動、実践)、識(知識、分別)等々も叉生成変化の流転中に在り、絶対的真理だとして定言的にこうだと云えるものは何一つ有りません。にも拘らず、人々はこれに捉われております。ここに間違いが認められます。 感覚的具体的に捉えられる六識も然りです。例えば眼(視覚)、耳(聴覚)、鼻(嗅覚)、舌(味覚)、身体(痛覚)、意識(知覚)も叉相対的なもので、絶対的なものは何一つ有りません。更に云えば、六境を形成する色も、声も、香も、味も、触も、法も然りです。これらの基準は全て比較的なものであり諸行無常なものです。にも拘らず、人々は絶対的な基準を押し付け押し通そうとしております。これらは皆、誤りです。 眼界で捉えられるもの全てが相対的なものでしか有りません。当然にそれを反映する意識界もそのようなものでしか有りません。かく悟れば、不明や迷いも相対的なものでしか無いと気づくべきです。且つ叉、不明や迷いが解消されることも有りません。老も死も相対的なものでしか有りません。叉、老と死の意味が解明されることも有りません。 無苦集滅道の四諦と云われる苦しみ、集(執着の積み重ね)、滅(煩悩)、道(人倫の理想郷)も相対的なものでしか有りません。絶対的な智というようなものは無く叉そのような智を得ることも有りません。得ようにも得られないことを弁えるべきです。かく分別すべきではないでしょうか。 菩提薩埵(ぼだいさった)は、この真実の般若波羅蜜多の神髄に依る故に、心に障りや妨げ、拘りが有りません。それ故に恐怖も有りません。一切の顛倒した妄想の類いから遠離していますので、迷いから脱した境地である涅槃(ねはん)を極め住しています。過去、現在、未来にまします諸仏であります三世諸仏(さんせぃしよぶつ)は、真理である般若波羅蜜多に依る故に、この上なく正しく目ざめており、本物の悟り仏であると云えます。 それ故に知るべしです。般若波羅蜜多は、究極のマントラ(箴言、神言)です。悟りのマントラです。これ以上の悟りは無く、無比なるマントラです。能く一切の苦を除き、真実にして虚ならずのマントラです。 釈迦はかく教え、般若波羅蜜多の呪(秘法)を説き伝えました。即ち曰く、生きとし生ける者よ、極めんとする者よ、修行する者よ。 この者たちに幸いあれ、この尊い御教えである般若心経を日々唱えて導きとせよ。 般若心経考 (ttp://www.marino.ne.jp/~rendaico/meibunhonyaku/hannyashingyo/hannyashingyo.htm) 2008.5.31日、2008.6.1日再編集 れんだいこ拝 |
||
| 【解説】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 般若心経の概略は「般若心経関連考」で確認する。以下、仏教の基本的教義を般若心経の説く流れに従って解説する。これを知り踏まえればなお能く分かるという構図になっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 般若心経は、観自在菩薩即ち釈迦が、仏陀の十大弟子の一人「舎利子」(シャーリプトラ)に説法するという設定になっている。釈迦は説法する際、聴衆の中から誰か一人を選んで語りかけるのを常とした。ここでは、「舎利子」に語りかけていることになる。 「舎利子」はバラモン族の出とされており、バラモン教の聖典である「ヴェーダ」を学び、伝統的な思想、宗教、学芸すべてに通じていた。仏陀の弟子アッサジを通じて仏教に帰依し、「釈迦弟子中の智慧第一の長老」と云われる人物である。智恵第一と称せられた二大弟子のもう一人は目連(もくれん)で、「神通第一」と称せられた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「摩訶般若波羅蜜多心経」の「摩訶」は、梵語の「マハー」で「偉大なるもの」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「般若」は梵語の「プラジャニー」で「深い知恵」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「波羅蜜多」は梵語の「パーラミター」の音写語で「到彼岸、悟りの境地に到る」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「心」は梵語の「フリダヤ」で心臓を意味しており「真髄」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「経」は梵語の「スートラ」で「永遠に変わることのない常住不変の義ないし法」を意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢訳には題名に「経」が付されているが、サンスクリットテキストの題名には「経」に相当する「スートラ」の字句はない。中国に伝わった際に「経」が最後に附けられたと考えられている。元来「経」は縦糸を意味し、それが転じて「教えの基本線」と云う意味になり、釈迦や賢人の教えを「経」と称するようになったとされる。「心経」をサンスクリット語で「マントラ」とも云う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仏教の経典類は「三蔵」と呼ばれる「経」、「律」、「論」に分類される。釈迦の説法を記録したのが「経」であり、自分を律する内面的な道徳規範としての戒律を定めたのが「律」であり、釈迦の教えを解釈し体系化したものが「論」である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仏教では、瞑想を「止(サマタ)」、瞑想に拠って得られる観察分析果実を「瞑観」叉は単に「観(ヴィパッサナー)」と呼ぶ。「六波羅蜜多」の5番目の「禅波羅蜜多」が「止」に、6番目の「般若波羅蜜多」が「観」に相当するとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
般若波羅蜜多は菩薩の修行徳目である六波羅蜜(布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧)の一つの智慧波羅蜜を指すとも、六波羅蜜全てを含むものとしての般若波羅蜜であるとも解されている。六波羅蜜は次の通り。
これらの修行徳目の実践を通して「智慧」に導かれるとされている。「智慧」の裏付けがないと実践はその場限りのものとなり、良い習慣、更には良い人格に結びつくことがないとされる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持戒波羅蜜の五戒は次の通り。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観自在菩薩は、その名の通り「観自在」の菩薩を意味する。「菩薩」は「菩提薩埵(ぼだいさった)」の略で、「ボーディサットヴァ」の音写語。精進により悟りを得た者を云い、後に観自在菩薩、観世音菩薩、地蔵菩薩など様々な菩薩達が考え出され信仰されることとなった。 観自在菩薩は「観音菩薩」のことであり、元々「妙法蓮華経観世音菩薩普門品」(観音経)に登場する菩薩で、人間の苦しみを観、聞き分け、あらゆる姿に変身して救いにきてくれる菩薩とされている。この菩薩を、鳩摩羅什は「観世音」、玄奘は「観自在」と訳した。サンスクリット語での言語は「アヴァローキテーシュヴァラ」であり、これは「アヴァローキタ」(観)と「イーシュヴァラ」(自在)に分解できるため、玄奘は「観自在」と訳したと考えられる。また、更に古い時代には言語が「アヴァローキタスヴァラ」だったと推定され、これは「アヴァローキタ」(観)と「スヴァラ」(世の中のすべての音)に分解できるため、鳩摩羅什は「観世音」と訳したと考えられている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釈迦時代のそれまでの修行法は、禁欲、苦行、無念無想の瞑想を行って欲望や執着を制御することで解脱できるとして、様々な難行苦行が試みられていた。釈迦は、難行苦行を排し、むしろ瞑想(観=ヴィパッサナー瞑想)により得られる正しき智慧を生むことを重視した。これによって欲望や執着から解放される解脱の道を切り開いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釈迦説法の中核は「空」思想にある。その説法の中でも最も重要なのが「五蘊」の「空」である。玄奘訳では「五蘊は空である」と訳されているが、サンスクリット原典では「五蘊があり、それが空である」と書かれている。つまり、五蘊説をまず認め、次にそれを実体と見ることを否定している。この方が正確な受け取りではなかろうかと思われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄奘訳に「色不異空 空不異色/色即是空 空即是色」という有名な一節があるが、サンスクリット原典などにはこの前に「色性是空 空性是色」と訳される部分がある。この方が正確な受け取りではなかろうかと思われる。してみれば、本来は三段階の説明であったことになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「諸法」の「法」は、サンスクリット語で「ダルマ」、パーリ語では「ダンマ」であり、多くの意味を持つ。一般的には教法、秩序、定め、法則、規範、真理、物、道徳、正義、習慣、習性、性質、真実、最高の実在などの意味を表す。ここでは、仏教独特の用法で「あらゆる存在や現象、事象」の意味で用いられ、「森羅万象」とも言い換えることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「相」は、一般的には「すがた」や「かたち」、「ありよう」の意味で用いられるが、ここでは「特徴」や「特質」との意味である(サンスクリット原本からの翻訳では「特性」)。「空相」は、「森羅万象には空という特性があり」との意味となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 般若心経が次々と数え上げながら否定しているのは、「五蘊」、「十二処」、「十二縁起」、「四諦」などで、これが釈迦仏教の中心的な教説となる。これを「法(ダルマ)」と呼ぶ。釈迦は、瞑想-瞑観によって「法」を見極め、真実の智慧を得て煩悩をなくすことで悟りが得られるとした。その際、「空」のを洞察する智慧によってこそ悟りに至ると説いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「五蘊」は、色、受、想、行、識の5つの蘊から成る。蘊(うん)は「集まり」を意味する。これを図示すれば、次のように整理することが出来る。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「度」は、岸から岸へ渡すことを意味し、解き放たれることを意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「度一切苦厄」の文句はサンスクリットの原本にはないため、漢訳した玄奘が加えたものと考えられているとの解説が為されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仏教には「四大(しだい)」の考え方があり、地、水、火、風の4つの要素が合わさり世界や身体が形成されていると了解する。この四大に「空」を加えたものを「五大」と呼び、五大が万物の構成要素と考えられている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「無明」は、原始仏教の根本の教えである「十二縁起」(「十二因縁」ともいう)の最初の項目である。「十二縁起」は次の通り。1・ 無明(むみょう、無知)、2・ 行(ぎょう、潜在的形成力)、3・識(しき、認識作用)、4・名色(みょうしき、精神と肉体、名称と形態)、5・六入(ろくにゅう、六つの感覚器官=眼、耳、鼻、舌、身、意)、6・触(そく、心が対象と接触すること)、7・ 受( じゅ、感受作用)、8・愛(あい、愛欲、妄執)、9・取( しゅ、執着)、10・有(う、生存)、11・生(しょう、生きること)、12・老死(ろうし、老いゆくこと、死ぬこと)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このうち眼、耳、鼻、舌、身、意を「六根」という。根は、根茎や根本といった意味。「六根」にに基いて生まれるものを「六境」とする。「六根」器官によって「六境」を認識するという関係に在る。「六境」は、色、声、香、味、触、法を認識する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼根は、眼で、「色」を見る。耳根は、耳で、「声」を聞く。鼻根は、鼻で、「香」を嗅ぐ。舌根は、舌で、「味」を味わう。身根は、身で、「触」に触れる。意根は、意識で、「法」を考え廻らす。六根と六鏡はこういう関係に有り、これを総合して「六識」と云う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「六根」と「六境」を合わせて「十二処」、これに「六識」を加えて「十八界」となる。「界」とは、「人間存在の構成要素」といった意味である。「十八界」とは次の通り。眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、意界、色界、声界、香界、味界、触界、法界、眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意識界。「眼界」が「十八界」の初めとなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「六根」、「六境」、「六識」の関係を図示すれば、次のように整理することが出来る。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二縁起は、人の精神的発展過程について分析したもので、釈迦が悟ったのがこの「縁起の理法」とされる。これらを順に並べ、無明に縁りて行あり(無明があるから行があり)、行に縁りて識ありと続け、生に縁りて老死あると説く観方を「順観」、その縁起を「流転(るてん)の縁起」と云う。逆に、無明から初めてその根本原因を克服滅失させ老死に辿り着くまで十二縁起を反証的に見ることを「逆観」と呼び、その縁起を「還滅(げんめつ)の縁起」と云う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「苦集滅道」は、原始仏教の根本の教えである「四諦(したい)」を指す。「四聖諦」とも云われる。「四諦」は「十二縁起」とともに、原始仏教の根本の教えである。「諦」は梵語(サンスクリット)の「サティア」で、真理、真実を意味する。四諦は次の通り。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「四苦八苦」とは、人間が生きていくうえで背負う苦しみを云う。「四苦」は、生老病死を云う。「八苦」とは、生老病死の四苦に「愛別離苦」、「怨憎会苦」、「求不得苦」、「五陰盛苦」の四苦を加えた八苦を云う。 これを図示すると次のように整理できる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「八正道」(八聖道ともいう)は仏教での修行の基本となる、次の八つの実践徳目である。正見(偏らない見立て)、正思惟(認識)、正語(言葉、誓い)、正業(生活行為)、正命(生き方)、正精進(偏らない努力)、正念(思念)、正定(実践)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「十界論」(十法界論)の教えもある。十界とは、生命、処世の在りようステージ(境涯)に於ける態様を云うもので、下から順に1・地獄界、2・餓鬼界、3・畜生界、4・修羅界、5・人界、6・天界、7・声聞界、8・縁覚界、9・菩薩界、10・佛界から成る。法華経は、それまでの教説が十界をそれぞれ別のステージとして捉えていたのを、それぞれの生命の中に宿るステージとして捉えている。これを「十界互具」と云う。 これを図示すると次のように整理できる。
どこまでが釈迦の教えか不明であるが、仏教通説では、1・地獄、2・餓鬼、3・畜生の世界を苦悩の境涯として「三悪道」(「三悪道」)と云う。これに4・修羅を加えて「四悪趣(しあくしゅ)」と云う。これらに5・人、6・天界を加えて「六道輪廻」と云う。六道の境涯までは環境に左右されている。三悪道に対し、修羅界、人間界、天上界の三種を「三善道」とも云う。 人間界の上位に位置する天界は、具舎論によれば、下から六欲天、色界、無色界に別れる。仏道修行によって得られる声聞、縁覚、菩薩、仏を「四聖(ししょう)」と云う。大乗仏教では、このうち声聞、縁覚を二乗とも云い、小乗で得られる境涯としている。 日蓮大聖人は次のように宣べている。「天下萬民諸乗一仏乗と成りて妙法一人繁昌せん時、萬民一同に南無妙法蓮華経と唱え奉らば、吹く風枝をならさず、雨土くれをくだかず、代は羲農の世となりて、今生には 不祥の災難を払い、長生の術を得、人法共に不老不死の理顕れん時を各々御覧ぜよ、 現世安穏の證文疑い有る可からざる者なり」(如説修行抄)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「無智亦無得」の「智」とは、仏教の教えを学習して知識として理解することであり、「得」とは身をもって教えを実践し体得することである。学び実践し、実践してまた学ぶ不断の努力精進が修行であり、悟りの境地とされる。「無智亦無得」とは、「智も無く叉智を得ることも無い。得ること無い故にである」と訳されるが、「智無ければ得ず」とも読める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「菩提薩[土垂]」は、パーリ語の「ボーディサッタ」、梵語(サンスクリット)の「ボーディサットゥヴァ」の音を写した語で、「観自在菩薩」の「菩薩」は、この「菩提薩[土垂]」を略したものといわれている。意味は、悟りを求めて修行する人、仏になろうと志す人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「罣礙」は、仏教の言葉で、「こだわり」、「さまたげ」、「わだかまり」といった意味である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「三世」は、過去、現在、未来の三世を云う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「仏(佛)」は、悟った者、真理に目覚めた人。「諸佛」とは、釈迦仏(ゴータマ・ブッダ)のほか、阿弥陀仏、弥勒仏、薬師仏など諸々の三世の時間を越えて常住する諸仏を云う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「阿耨多羅三藐三菩提」は、梵語(サンスクリット)の「アヌッタラーサミヤックサムボーディ」の音を写した語で、「この上ない正しいさとり」を意味する。漢訳では、「無上正等覚」と記す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
仏教では、次の4つの「顛到」があると説く。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「夢想」は、これらの誤った考えを夢のように想い描くことを意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「遠離」は遠ざけることを意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「究竟」は到達することを意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「涅槃」は、俗語「ニッバーン」の音写語で、サンスクリット語では「ニルバーナ」、パーリ語では「ニッバーナ」という。「迷いの火を吹き消した状態」を意味し、悟りの境地、迷いの無い境地、心の安らぎの状態と理解できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 般若心経は、末尾で、「真言(呪文・マントラ)」を称えて紹介している。「咒」は「呪」とも書き、原語は梵語(サンスクリット)の「マントラ」で、インドのヴェーダでは、神々への賛歌、祭詞、歌詠といった意味に用いられている。「箴言」、「真言」、「神言」と訳す。サンスクリット語では「マントラ」と呼ばれる。 般若心経の「真言」は正規のサンスクリット語ではなく、その意味がはっきり分らない。「智慧よ悟りをもたらし給え」という内容と考えられており、修行の目標そのものを意味していることになる。 インド仏教の最終形態である密教では、特に仏や菩薩の力を示す秘密の言葉として重要視している。同じような意味を持つものに「陀羅尼」があり、サンスクリット語の「ダーラニー:心にとどめて忘れないこと」の音写語。マントラとダーラニーは真実そのものであり、意味を訳さずそのまま口で唱えれば真実と合一できると考えられた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「大神咒」は、「偉大にして神聖なる真言」といった意味。「是(これ)」が指すものは、般若波羅蜜多(「到彼岸の知恵」)である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大明咒の「明」はサンスクリット語の「ヴィドヤー」のこと。「明るいこと」、「ものごとがよく見えること」、「知」、神通力を意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「無上咒」は、「この上ない真言」といった意味。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「無等等咒」は、「等しいもののない最上の真言」といった意味。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弘法大師は、「大神呪」は声聞のマントラ、「大明呪」は縁覚のマントラ、「無上呪」は菩薩のとなえるマントラ、「無等等呪」は密教の真言に当たると説いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「虚」は、中身のない、実がないとの意味で、「不虚」は絵空事や戯れ言ではなく、現実に影響を与える実質的な力があるとの意味。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「羯諦」の意味は「行ける者よ」叉は「生きとし生ける者よ」である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「波羅」の意味は「彼岸まで極めんとする」を意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「僧」の意味は「修行する」を意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「菩提薩婆訶」の意味は「悟りよ、幸あれ」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)