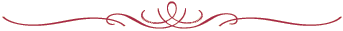西暦2~3世紀、インドの龍樹が般若経典の注釈書である「大智度論」を著したとされ、般若心経もこの頃に成立したものと推定する説がある。しかしながら、龍樹直筆本は存在せず、現存する最古のサンスクリット(梵字)本は法隆寺所蔵の8世紀後半(伝承では609年請来)の写本とされる貝葉本であり、漢訳経典より時代を下る。現在チベットやネパール等に伝わる写本も、それ以降の時代のものであり原形については不明である。
般若心経の中国訳の完成時期も定かでは無い。「摩訶般若波羅蜜神咒一巻」及び「般若波羅蜜神咒一巻 異本」は、後世の文献では前者は3世紀頃の中央アジア出身の支謙、後者は鳩摩羅什の訳とされているが、「綜理衆経目録」には訳者不明(失訳)とされており、この二人に帰することは信憑性にとぼしい。
前者は現存せず、後者は大蔵経収録の羅什訳「『摩訶般若波羅蜜大明咒經」とされるが、羅什の訳経開始が402年であるため、釈道安の没年385年には未訳出である。またそのテキストの主要部は宋・元・明大蔵経版の鳩摩羅什訳「摩訶般若波羅蜜経」のテキストと一致するが、宋版大蔵経の刊行は12世紀後半であるため、このテキストが羅什訳であるということも疑われている。
649年、インドより帰還した玄奘(西遊記の三蔵法師のモデル)の般若心経訳が流布されている。玄奘は西暦628年に唐の都の長安を出発してインドに入り、中インドのナーランダー寺院で戒賢(かいけん)らについて学んだとされる。また、インド各地を訪ねて膨大な梵字仏教経典を集め、645年に帰国した。そして没するまでの18年ほどの間に般若心経の漢語訳に勤めたとされる。
しかし、文献学的にはテキストの主要部分が高麗大蔵経版(13世紀前半)の鳩摩羅什訳「摩訶般若波羅蜜経」からの抽出文そのものであり、玄奘が翻訳した「大般若波羅蜜多経」の該当部分とは異なるため、これも羅什訳と同様に真正に玄奘訳であるかどうか疑われている。
玄奘が訳した般若心経は「小本」と呼ばれる版であるが、これよりやや長い完全版の「大本」という版もある。 「小本」には観自在菩薩の説法だけが抜き出されているが、「大本」には経典の物語の基本設定に当たる部分が書かれている。