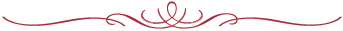
| 在任中の流れ1、1972年、1973年の動き |
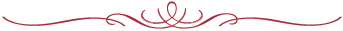
更新日/2022(平成31.5.1日より栄和元/栄和4).2.5日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
|
アメリカをオーバーへット゛して日中友好条約を締結し、冷戦下でソ連との外交距離を縮め、米国メジャーを通さずに独自で中東から石油買い付けルートを作り上げ、アメリカに内密でカナダから核燃料を購入する準備にも向かいつつあった。アメリカからの報復が始まる。ネオ・シオニスト・エージェントキッシンジャーがこれを采配する。以下、この流れを検証する。「戦後政治史検証」の「1972年通期」、「1973年通期」と重複する。ここでは角栄に特化した流れを主に確認し、全般的な流れは「戦後政治史検証」に記すことにする。 |
| (1972年、田中政権発足後の動き) | 【「72年当時」】 |
| 【第一次田中内閣発足】 |
| 7.7日、第一次田中内閣発足。官房長官・二階堂進、幹事長・橋本登美三郎、副幹事長竹下。事実上の竹下幹事長であったと云われている。福田に入閣を求めたが、福田は拒否し、福田派からの入閣も断っている。これほどの確執が生じたということである。(福田が入閣するのは、5ヵ月後の第二次田中内閣で行政管理庁長官としてであった) |
| 【初閣議での首相談話】 | ||
|
7.7日夕、田中首相は初閣議を開き、その後の首相談話で次のように述べている。
大平外相も、記者会見を開き、「日中国交正常化に決意をもって当たる」と述べた。その後、田中首相と大平外相は、赤坂の料亭「千代新」に外務省の橋本ひろし中国課長を呼び、大平が次のように申し渡している。
田中首相は、「橋本君頼む」と云い、以降の作業に付き、大平外相に全て直接報告するよう厳命された。当時の外務省には新台湾派官僚も多く、交渉の進展が漏れないように種々打ち合わせもした。 |
| 【周恩来中国総理のエールと二階堂官房長官のコメント】 | |
|
7.9日、田中内閣誕生を見て、周恩来中国総理が、人民大会堂でのイエメン人民民主主義共和国代表団歓迎夕食会の演説で、「日本においては長い間、中国を敵視していた佐藤政権がついに任期前に退陣せざるをえなくなった。田中内閣が7日に成立した後、外交面において日中国交正常化の実現を促進すると発表したことは、これは歓迎するに値することである」とエールを送り、「田中内閣成立は日中国交正常化の早期実現を目指すもので、歓迎する」と演説した。
|
7.10日、田中首相、大平外相、二階堂官房長官、外務省当局が協議し、二階堂官房長官が「政府の日中国交正常化に寄せる熱意が、中国側に十分理解されたことは、結構なことである。政府としては、今や、日中政府間接触の機が熟しつつあると考える、今後は、政府の責任において、日中国交正常化のため具体策を、着実に進める考えである」との談話を発表。
この日、社会党の成田知己委員長が、「日中問題で、田中内閣が復交三原則を認めるならば田中内閣を支持する」と記者団に語る。7.12日、民社党も「原則を明らかにして取り組めば協力する」、7.13日、公明党も「田中首相が日中打開への決断さえ持てば、強力は惜しまない」とそれぞれ歓迎の辞を述べている。
7.10日、孫平化が率いる上海バレエ団が東京に到着し、各地で公演する。孫平化は田中角栄首相の訪日の段取りをつけるための来日。
7.11日、アメリカの民主党大会で、マクバガンが大統領候補に指名される。
7.13日、田中首相が労働代表と会談する。
7.13日、自民党が、役員会で、それまでの「中国問題調査会」を「日中国交正常化協議会」に拡大改組することを取り決めた。会長・小坂善太郎、副会長・江崎真澄、木村俊夫、小川平二、古井喜実、宇都宮徳馬、田川誠一、川崎秀二、秋田大助、北沢直吉、山田久就、塚田十一郎、大野市郎の12名、事務局長・鯨岡兵輔。当時の衆参両院議員431名のうち249名が参加した。
7.16日、訪中していたむ社会党元委員長の佐々木更三が周恩来と会談した席上、周総理が、「日本之外務大臣が北京へ来て、私と話し合う可能性があると思う」と語った。
7.16日、外国人力士として初めて高見山が優勝。
7.18日、田中首相が竹入公明委員長、春日民社両党委員長と個別に会談と会談。
7.19日午前、インガソル米国駐日大使が、大平外相、田中首相と会談。「中国問題に対する新政権の考えを打診」した。田中首相が、首相就任後初の記者会見を開き、日中問題に関して次のように述べた。「日中国交正常化は機が熟してきたの一言に尽きる」と意欲を示す。
| 概要「日中両国が正常な状態になることは、国民のすべてが望んでいると思う。その機運も熟してきた。台湾も、歴史の上では、日本と密接な関係にあり、国交も有る。その意味で、台湾問題も重要な問題だが、二中国交正常化という大きな問題が解決するとき、合わせて解決されるべきだ。常識的にそうご理解いただきたい。中国側は『北京の空港は、日本の為にいつでも開かれている』と云われるが、私も『東京の空港も、いつでも開かれている』と申している。いつ、誰が、という問題ではなく、自ずから開ける問題だと思う。復興三原則に関しては、中国側が、中国の立場で申し述べられたことは、そのまま理解すると云うことだ」。 |
7.19日、パリでベトナム秘密会談が本格化する。 8.11日、アメリカの地上軍のベトナム撤退が終了する。8.15日、アメリカのキッシンジャー大統領補佐官が、パリで北ベトナム側と秘密会談を行う。
7.20日、台湾の沈外相が声明を発表した。「田中内閣は、共産中国と国交樹立の交渉を行おうとするならば、それが世界における日本の評判と、国府、日本との間の友好、協力関係に、どういう影響を与えるか、真剣に考慮すべきである」、「日本側が、日中国交回復を目差している今日の動向は、国際的な真偽と、条約尊重の義務に反するものである」。
7.21日、田中首相、成田社会党委員長と会談。
7.22日、北京を訪問して周恩来と会って来た佐々木更三社会党元委員長が首相官邸を訪ね、田中首相と会談し、「周総理は田中首相と大平外相の訪中を歓迎する」との伝言を伝える。「訪中するなら早いほうがいい」とのコメントを述べている。
7.22日、大平外相が孫平化中日友好協会副秘書長と会談する。中国は、田中首相を招請する。
7.24日、田中首相が、自由民主党日中国交正常化協議会の初会合に出席して決意を表明、党内での合意を強調し、基本姿勢10項目を示した。その中で次のように位置づけている。
| 「日中国交正常化は、吉田内閣の平和条約締結、鳩山内閣の日ソ国交正常化、岸内閣の安保改定、池田内閣のOECD加盟、佐藤内閣の日韓平和条約締結及び沖縄返還にも匹敵する大事業であり、この認識に立ちつつ、党、政府としても、慎重且つ勇断をもって当り、有終の美を飾りたい。8.31日と9.1日に、ハワイで行われるニクソン米大統領との会談では、アメリカの対中姿勢や考え方について十分ただしたい」。 |
首相に続いて、大平外相、小坂会長が発言し、後押しした。
7.25日、忍者外交といわれたキッシンジャー米大統領補佐官の対中国政策が成功して、ニクソン大統領が訪中。米・中関係は急速に前進した。
| 【竹入-周恩来会談】 |
|
7.25日、竹入公明党委員長が二度目の訪中で北京入り。7.27日、周恩来首相と延べ10時間に及ぶ会談。この時の打ち合わせが「竹入メモ」となる。その内容は、1・中華人民共和国と日本国との間の戦争状態の終結させる、2・日本政府が、中華人民共和国を中国を代表する正式政府と認める、3・中華人民共和国は、日本国に対する戦争賠償請求権を放棄する、4・双方がアジア太平洋地域での覇権を求めず、覇権の企図に反対する、5・中国側は、日米安保条約に触れない。「安保と日中問題」を切り離す、6・台湾は中国の領土であり、日本側は中国の内政問題として認めるなどを骨子とする8項目メモであった。 8.3日、竹入委員長が帰国。 |
7.28日、中国当局者が、林彪副首席が毛首席暗殺計画に失敗して前年9月にモンゴルで死去したことを認める。田中首相と孫平化の会談が行われる。孫平化が正式に田中首相の招待を伝える。
7月下旬、日米通商箱根会談が開かれた。この席で、日本側は、航空機や濃縮ウラン、農産物などの緊急輸入を呈示していた。この政府間の交渉を受けて、ロッキードをはじめ、グラマン、ボーイングといったアメリカの民間航空機製造会社が、こぞって日本に売り込みをかけてきた。
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その1】 |
| (新井雄(国立政治大学歴史学科博士課程)の「自由民主党親台湾派の活動─日台断交時期を中心に(1972-1975)─」その他を参照する。) 8.3日、田中政権が日中国交正常化に臨む基本見解を発表。大平外相が、自民協・常任幹事会の場で、日中正常化の目的、姿勢、三原則に対する考え方など6 項目からなる政府の基本方針を初めて説明し、了承を得た。但し、賀屋興宣、町村金五、菊池義郎ら台湾擁護派が「日華条約消滅」に疑義を唱え、「日中国交正常化は、慎重のうえにも慎重でなくてはならない。国際信義上、非礼であり、中国への土下座外交だ」と外相を突上げ激しく反論している。同幹事会では「党内不一致の印象を避ける」というという名目で、政府見解も含め公表しないことを申し合わせた。自民党内の「親台湾派」とは、岸信介、賀屋興宣、青木一男などの戦前派と、石井光次郎、大野伴睦、船田中、千葉三郎など保守系の党人派、福田赳夫、椎名悦三郎、田中龍夫などの岸側近たち、「吉田学校」出身の官僚派である佐藤栄作などであった。自民党内の「タカ派」を形成する。 |
8.4日、帰国した竹入公明党委員長が、田中首相と大平外相を訪ね、周首相との会談について説明、中国側の考え方をまとめた「竹入メモ」を手渡す(中日新聞の本田晃一氏より「竹入メモ」を聞かされたともある)。この頃、右翼の街宣車が「国賊・田中角栄」を連呼しながら、あるいはビラを街中に貼られていった。
| 【日共・野坂議長の日中国交回復慎重論】 |
|
8.7日、共産党が、日中問題についての見解を明らかにした。野坂中央委員会議長談話の形式で、「日中国交回復は、日台条約の破棄を含む日中復交三原則を、前提として進めるべきだ。日中間にある根本問題を解決しないで、性急に、日中国交回復を進めるやり方では納得できない」。 |
| 【「日本列島改造問題懇談会」が初会合】 |
| 8.7日、首相の私的諮問機関として「日本列島改造問題懇談会」が初会合。「日本列島改造論に経済成長第一、公害をまきちらすなどの批判が出ているが、経済成長がなければ道路も住宅も託児所も老人ホームもできないことは過去のデータが示しており、議論の余地がない」とした。当初75名とされた懇談会の委員は途中で90名に増員された。9月には総理府政府広報室が、「日本列島改造論」について「知っているか」、「主要点の賛否」「期待」などについて面接聴取している。またグリーンピア構想は、日本列島改造論に促されて具体化し、8月に厚生省年金局と大蔵省理財局がグリーンピアの設置に合意した。 |
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その2】 |
| 8.8日、自民協・常任幹事会で、親台湾派は、田中首相、大平外相らが明らかにした「台湾との国交関係消滅」という見解を批判し、「基本問題についても党の合意を得たうえで、交際にのぞむべきだ」と迫った。 |
8.9日、自民党の「中国問題調査会」から発展・改組した「日中国交正常化協議会」(会長・小坂善太郎)の総会で、田中首相の訪中と国交正常化推進を決議した。
8.12日、中国の姫鵬飛外相が、「周首相が、田中首相の中国訪問を歓迎し、招待する」と声明。
| 【駐米大使の牛場信彦の水差しと二階堂官房長官の批判】 | |
|
8.14日、駐米大使の牛場信彦が、ワシントンで記者会見し、「中国が国交正常化の前提としている日中国交回復三原則は認められない」とコメントした。これに対し、二階堂官房長官が次のように批判している。
法眼次官は、「一国の大使の発言として軽率である」と注意処分に付した。 |
8.15日、外務省が、賀屋興宣らの質問書に対して、回答書をまとめ発表した。
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その3】 |
| 8.15日、党本部で、大平外相と自民協・常任幹事会の交渉が続いた。衆参両院議員の46名の常任幹事と、大平外相、法眼晋作外務事務次官、吉田健三アジア局長、橋本恕中国課長ら外務省代表が出席した。大平外相は、「自分はまだ“断交”とか“断絶”ということばを使ったことがない」と断りながらも「“一つの中国”と日本は一つの関係しか持てない。中華人民共和国が唯一の合法政府いう認識に立ってこちらと国交を結べば、残念だが中華民国との関係は持てなくなる」と述べ、台湾政府との断交の方向を明らかにした。これに対し、賀屋興宣、中川一郎、源田実、藤尾正行、中山正暉らが次々と反論した。「筋論ではなく、国府(台湾政府)との関係をできるだけ温存する方向をさぐるのが外交だ」、「断交ということばを使わなくても、外相の言っているのは同じことだ。そんなことをいつ決めたのか」などと反論した。大平外相は、「台湾との関係をそのままにして中華人民共和国政府との関係を正常化した国はどこにもない」と説明したが、親台湾派の議員たちは一歩も引かず、「外相が公の立場で“日台条約”という表現をしたのはおかしい」、「日華条約を破棄することは、憲法98 条の国際条約遵守義務の違反だ」などと追求した。外相が途中で退席した後も親台湾派の発言は延々と2 時間以上も続き、「台湾問題に関する外相発言を取り消す決議をすべきだ」という強硬な意見も出された。このため最後に江崎真澄副会長が「小坂会長が大平外相に台湾問題を慎重に扱うよう申し入れる」という妥協案で、この日の会議を収拾した。 |
8.15日、帝国ホテルで、田中首相と孫平化中国バレー団団長、肖向前・弁事処首席代表が会見。日本の総理大臣が中国政府の要人とあうのは、これが戦後初めてとなった。首相訪中の意思が正式に伝達された。会談後の田中首相と大平外相の間に次のような会話が交わされたと伝えられている。大平「中国側の真意は、ほぼ分かった。あとは、やるだけだ。ここはお互い腹を括ってやろうじゃないか」。田中「わかった。どうせ、人は一生一度しか生きられないんだ。それじゃ、行くか」、田中は付け加えた。「具体的な交渉は、君に任せる。党内のことは、俺が責任を持ってやる」。
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その4】 |
| 8.16日、自民協の小坂会長、江崎真澄、北沢直吉両副会長、鯨岡兵輔事務局長らは、外務省で大平外相に会い、「中国問題について発言する場合は、自民協にはからないで、断定的なことはいわないようにしてほしい」と申し入れた。これは、15日の同協議会の幹事会で、賀屋興宣から「政府、外務省は自民党内のコンセンサスがまとまる前に、台湾切り捨ての既成事実を作ろうとしている」と、とくに大平外相の国会発言について、強い不満が出されたため、協議会として外相に伝えることになったものであった。「日中国交正常化問題に関する賀屋興宣、北沢直吉両氏への答弁書」の内容について「承服できない」と激しく批判した。 |
8.17日、正常化協議会幹事会で、台湾擁護派の反発が最高潮に高まり、「台湾を切り捨てないという『田中原則』を打ち出せ」と迫り紛糾した。
| 【田中・キッシンジャー会談】 | |||||
|
8.19日、キッシンジャーが来日し、軽井沢の万平ホテルでキッシンジャー-田中首相会談。目的は、ハワイ会談に向けて、日米貿易不均衡問題の処理を目指して経済分野での大枠を決めるためだった、とされている。文芸春秋2001.8月号「角栄の犯罪25年目の真実」によれば、次のような会談記録を披瀝している。
更に、オフレコを条件に次のような内容のコメントをしているとある。(「角栄の犯罪25年目の真実」の筆者は、「恐るべきこと」と記しているが、為にする書き方でしかない)
このコメントをもって、「角栄の犯罪25年目の真実」の筆者は、次のように重大視している。
|
|||||
| れんだいこ見解はこうだ。角栄が防衛問題(この場合には軍備費)にかくも詳細に首を突っ込んでいる例は初耳であり、このコメント内容が角栄のものであるかどうか精査を要するように思われる。中曽根的コメントならピタリと当てはまるだけに差し替えられている懼れなしとしない。次に、これを角栄の間違いない発言だとして、日米貿易摩擦の解消策として述べられている点で、それは有効な選択肢であったわけだから、これでもって角栄のいかがわしさを証拠付けるものではなかろう。それにしても、キッシンジャー相手の会談で、「外に漏らされては困る話をしますと」とは、少々胡散臭い。 もう一つ付け加えれば、このストーリー通りとして、こうなるとキッシンジャーのお膳立てで田中首相が日米貿易摩擦の解消策として航空機購入を指示していったということになり、そうなるともはやこれは「日米国際政治の丁丁発止の遣り取り」であり、これが犯罪とさせられることは理不尽ということになるだろう。どちらにしても、角栄を誹謗する材料にはならないということだ。お分かりかね。 2006.9.13日 れんだいこ拝 |
8.21日、椎名悦三郎が自民等副総裁を受諾。8.22日、自民党副総裁に椎名悦三郎氏が就任している。8.23日、自民党副総裁椎名悦三郎、台湾への政府特使を受諾。8.30日、首相田中角栄と会談。
8.22日、自民党総務会で、日中国交正常化の促進と田中首相の訪中を党議決定した。党内台湾派の根強い抵抗があったが押し切っている。自民党副総裁に椎名悦三郎氏が就任している。
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その5】 |
| 8.24日、自民党の常任幹事会で、日中国交正常化に伴う台湾問題について協議した。その結果、①中国の復交三原則は理解できる、②しかし、日本と台湾との関係については、日華条約があるので、さらに時間をかける、③台湾の関係をそのままにする交渉ができるのかどうかは中国側との折衝中で、中国側に伝える、以上の三項目でまとまり、党内コンセンサスをつくる上で最大の焦点だった台湾問題は、ほぼ決着がついた。 この幹事会では、玉置和郎、賀屋興宣、藤尾正行ら親台湾派が台湾切捨て反対論を繰り返した後、中川一郎が、「日本も日華条約を締結した歴史がある。台湾問題にはもう少し時間をかけるべきだ。その交渉ができるかどうか中国側に強く要望して欲しい」という動議を提出した。この動議では親台湾派が決議するように要求したが、採決せず「合意」という形でまとめ、首相、外相に伝えるにとどめた。 |
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その6】 |
| 8.29日、自民協が常任幹事会を開き、さきに正副会長会議で決定した「自民党国交正常化五原則」案について協議した。同会議において、親台湾派が問題としたのは、前文に書かれている「わが国と台湾との深い関係に鑑み、この関係に十二分の配慮を要するという有力な意見があった」というくだりであった。この日の常任幹事会は、大平外相の出席を求めて開かれたが、開会冒頭、親台湾派の藤尾正行が「正副会長会議で決定した日中国交正常化案を常任幹事会の了承をえないで、公表したのは手続き的に間違っている」と小坂会長、江崎副会長、鯨岡事務局長に強く釈明を求めた。これに対し江崎副会長は、「この案は、タタキ台として会員全員に配布したもので手続きを的に間違っていないと思う。これに基づいて党議を進めて欲しい」と事態収拾をはかったが、中川一郎、渡辺美智雄、大野市郎ら親台湾派が次々に立ち、「内容的にも手続き的にも認められない」と強く突き上げた。江崎副会長は「この案に基づいて党議を 進め、修正して欲しい」と突っぱねたが、親台湾派は了承せず会議は紛糾した。このため小坂会長らが正副会長会議を開いて協議した結果、先の日中国交正常化五原則案を撤回、30日の正副会長会議で字句などを再検討することになった。 |
8.29日、三木武夫が副総理に就任。
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その7】 |
| 8.31日、自民協が常任幹事会を開き、日中国交正常化に伴う台湾の扱いなどについて協議したが、親台湾派が小坂会長、江崎副会長、鯨岡事務局長ら執行部に不信任動議を出すなど激しく執行部側を突き上げて、ヤジ、怒号の大荒れのうちに、結局なんらの結論を得ないまま散会した。その後、小坂会長ら執行部は善後策を協議した結果、9 月1 日の正副会長会議で5 原則案をさらに修正のうえ、総会を開いて収拾することにした。 |
| 【日米首脳会談(田中.ニクソン会談)】 |
| 8.31日、ハワイのクイリマホテルで日米首脳会談(田中.ニクソン会談)が開かれた(外遊交渉1)。安全保障、経済摩擦等様々な懸案が話し合われているが、真意は日中交渉の米側への報告と了承を得ることにあったものと思われる。 アメリカ側は、ニクソン、キッシンジャー、日本側は田中、牛場信彦駐米大使。その後、ロジャーズ国務長官、大平外相が加わっている。この席で、中国問題、特に日中交渉、国際収支問題、日米貿易不均衡問題等が包括的に話し合われている。こうして。田中は、米国への根回しを終えた。 日米貿易不均衡問題を見ておくと、70年までは、日本の対米貿易黒字は数億ドル単位だったものが、71年には25億ドル、72年には30億ドルを軽く突破する見込みとなっていた。 9.1日、日米安保条約の維持・日中国交正常化・日米貿易不均衡是正の共同声明が発表された。文芸春秋2001.8月号の「角栄の犯罪25年目の真実」によると、概要「ニクソン政権としては、何とか日本の輸入を増やしてもらい、貿易収支の改善を図ろうと懸命な時期だったわけである。この会談で、アメリカのドル防衛と、日米貿易摩擦改善の為に、日本が、アメリカから7億1千万ドル(約2千億円)の緊急輸入を行うことが決定した。その目玉が日本の民間航空会社による3億2千万ドルの航空機輸入だったのだ。田中は、日米関係強化のためにも民間航空機調達といった手土産を、ハワイ会談までに用意しなければならない立場にあった。こうした日米間の貿易摩擦問題の中で、日米を跨ぐ形でロッキード事件が起きたことを強調しておきたいと思う」とある。 この時、竹下副幹事長、金丸国会対策委員長、亀岡経理局長等20数人が同行している。その中の大物議員の一人が「ニクソンがロッキード、ロッキードと言うので困ったよ」とオフレコで語っている、と伝えられている。 |
| 【キッシンジャー大統領補佐官の田中首相批判】 | |
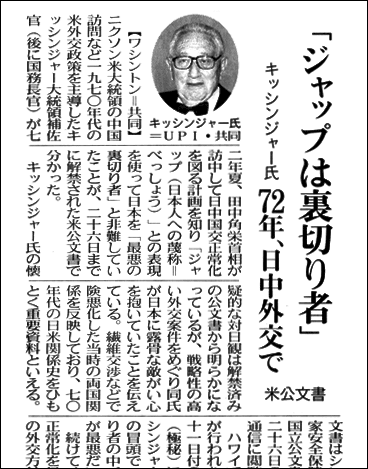 ( 2006年5月27日付け東京新聞 )
|
8.31日、橋本中国課長らの外務省事務担当者一行が隠密的に田中訪中の先遣隊として北京に向かい、訪中時の行事日程、催し、趣向の詰めを行った。
| 【日米首脳会談(田中.ニクソン会談)】 |
|
8.31日、ハワイのクイリマホテルで日米首脳会談(田中.ニクソン会談)。アメリカ側は、ニクソン、キッシンジャー、日本側は田中、牛場信彦駐米大使。その後、ロジャーズ国務長官、大平外相が加わっている。この席で、中国問題、特に日中交渉、国際収支問題、日米貿易不均衡問題等が包括的に話し合われている。このときロッキードの密約があったといわれている。 この時、竹下副幹事長、金丸国会対策委員長、亀岡経理局長等20数人が同行している。その中の大物議員の一人が「ニクソンがロッキード、ロッキードと言うので困ったよ」とオフレコで語っている、と伝えられている。 |
8.31日、ダイエーが売り上げで三越抜き小売業第1位となる。
8月、中国銀行と東京銀行が、元・円の決済制度新設に関する合意書に調印。
8月、周恩来総理が日中文化交流協会代表団一行と会見。
9.5日、アラブ・ゲリラ,ミュンヘン五輪村襲撃。ミュンヘン五輪でパレスチナゲリラ「黒い9月」がイスラエル選手団11名を殺害する。
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その8】 |
| 9.5日、総裁直属の日中国交正常化協議会が、「日中国交正常化基本方針」を決定した。1・日中正常化は、国連憲章、バンドン十原則に基くべし。2・相互に異なる体制を尊重し、内政に介入せず、友好国との関係を尊重する。3・相互に武力及び武力による脅迫を行使しない。4・相互に平等な経済的文化的交流の増進に務め、差別的取り扱いをしない。5・相互にアジアの平和と繁栄の為に協力する。 9.5日、自民協常任幹事会は、親台湾派や日中復交促進派から出された提案、さらに賀屋興宣から出されていた基本方針案に加えて、小坂会長が今までの案を練り直した4 番目の案が報告された。その報告に対し、中川一郎、浜田幸一らが「この際、役員の不信任動議を白紙に戻し、小坂会長の練り直した案をタタキ台に、4 案を勘案して字句修正し、まとめるべきだ」という動議を出し、基本方針の策定に入った。この日の小坂会長は、先に提案した5 原則のほか、交渉にあたっての要望事項として「わが国と中華民国との深い関係に鑑み、この関係の継続について十分配慮の上、交渉されたい」と説明したが、これに対し、親台湾派は「日中正常化は、わが国と中華民国との外交関係を堅持して交渉にあたるべきだ」と主張し、特に賀屋興宣は「日中国交正常化交渉にあたっては中華民国との国交を継続し、日華平和条約は有効にして将来もこれを破棄しないようにすべきだ」と、最後まで強い台湾擁護論を述べた。 |
9.7日、スラエル軍がレバノンへ侵入する。9.8日、「黒い9月」によるミュンヘンオリンピック村の選手村事件の報復として、イスラエル軍がシリア、レバノンのパレスチナ・ゲリラ基地を空襲する。
| 【大平正芳外相の自民協・常任幹事会説得経緯その9】 |
| 9.8日、自由民主党は、日中国交正常化協議会に引き続き総務会を開き、日中国交正常化の基本方針を党議決定、反対を続けていた台湾派を説得。 自民協・総会で、先に常任幹事会で決めた「日中正常化にのぞむ基本方針案」をわずかに字句修正して決定した。同総会では、賀屋興宣ら親台湾派から「原案の中にある“台湾との従来の関係が継続されるよう配慮のうえ交渉されたい”というくだりの“従来の関係”の中には外交関係も含むことをハッキリすべきだ」という強い主張が出され、小坂善太郎会長は「従来の関係とは、日華平和条約を結んで以来、わが国と台湾との間に保たれてきたよい関係のことだ」と間接的な表現で外交関係が含まれることを認めた。また、大野市郎は「政府は忠実に党議決定に従って交渉すべきであり、外交は政府の専権という態度では困る」と発言した。ついで源田実も「政 府は、台湾との従来の関係を十分配慮して交渉したが、結果的に日本の主張が取りいれられなかったといいのがれをする恐れがある。政府は、台湾に関する日本の主張が、取りいれられなかった場合はどうするのかをはっきりさせるべきだ」と主張した。最後に、中川は原案の「(台湾との従来の関係を配慮のうえ)交渉されたい」を「交渉すべきである」と修正すべきであると要求し、これを認めたうえ、基本方針を決定した22。以上のように、親台湾派は、田中首相、大平外相など政府側の対中積極政策に反対し、最後まで台湾との外交関係維持の主張を展開した。 「基本方針案」とは以下の5 項目。①日中正常化は、国連憲章、バンドン十原則にもとづいて、行なわれるべきである。②相互に異なる体制を尊重し、干渉せず、友好国との関係を尊重する。③相互に武力および武力による脅迫は行使しない。④相互に平等な経済的、文化的交流の増進につとめ、差別的取り扱いをしない。⑤相互にアジアの平和と繁栄のため、協力する。 |
9.9日、シリアがイスラエルを爆撃する。9.16日、イスラエルがレバノンに侵攻する。レバノンは全土に非常事態宣言を発する。
9.12日、田中派(七日会)正式発足。
9.14日、小坂代表団が訪中。9.18、19両日、周恩来首相と会談。
| 【椎名副総裁の対台湾事前根回し】 |
| 9.17日、自民党副総裁の椎名悦三郎氏が、「戦後に受けた中華民国への恩義は忘れず、政治的にも従来の関係を継続したいが、諸般の事情により若干疎遠になるので我慢して欲しい」旨の田中親書を持って日本政府特使として台湾を訪問した。台湾では日中正常化に反対する市民の激しいデモに遭い、生卵を投げられたり車を棒で叩かれたりした。 9.18日、沈外相、厳副総統、何中日文化経済協会長と相次いで会談し、日中国交正常化についての日本側の事情を説明。椎名は田中親書を携えていたが、蒋介石は風邪と称して会わなかった。9.19日、将経国・行政院長らと会談。民間関係維持で平身低頭。蒋経国総理との会談で、それぞれの国の事情を理解し合う線で両国の面子が立つ状態で話し合いができた。「椎名氏と蒋経国氏の二人の人格の触れ合いの中で解決できた面が大きかった」とある。 |
9.18日、田中内閣の支持率62%で吉田内閣を上回り戦後最高を記録。
9.21日、二階堂官房長官が、田中首相の訪中について「9.25日訪中し、30日帰国」と公式発表。
| 【田中派「7日会」が発足】 |
|
9.21日(12日?)、田中派の7日会が正式発足(衆院41名、参院42名)。 |
| 【この局面での田中首相、大平外相の態度】 | ||||||||
|
この頃の角栄の日中問題に対する態度が次のように伝えられている。
この頃の大平の日中問題に対する態度が次のように伝えられている。
|
| 【訪中直前の角栄の様子】 | ||||
|
訪中直前の角栄の様子について次のように伝えられている。観念や面子にこだわることはない、実利を取ればいい、というのが田中のスタンス。秘書の佐藤昭子の「私の田中角栄日記」は次のように記している。
エリザベス女王との会談に真紀子を連れて行ったが、このときは同行を許していない。次のように述べている。
9.23日、彼岸の中日、田中は、吉田茂、池田隼人、鳩山一郎各氏の墓参りし、佐藤に挨拶、病床の石橋にも見舞いをかねて報告に行っている。 |
| 【訪中直前の右翼の抗議活動の様子】 | |
「田中角栄入門」の「10.日中国交回復の舞台裏この頃」に次のように記されている。
|
| 【キッシンジャー大統領補佐官の怒り】 |
| 2006.5.26日、ニクソン米大統領の中国訪問など1970年代の米外交政策を主導したキッシンジャー大統領補佐官(後に国務長官)が72年夏、田中角栄首相が訪中して日中国交正常化を図る計画を知り「ジャップ(日本人への蔑称(べっしょう))」との表現を使って日本を「最悪の裏切り者」と非難していたことが解禁された米公文書で分かった。キッシンジャー氏の懐疑的な対日観は解禁済みの公文書から既に明らかになっているが、戦略性の高い外交案件をめぐり、同氏が日本に露骨な敵がい心を抱いていたことを明確に伝えている。日米繊維交渉などで険悪化した当時の両国関係を反映しており、70年代の日米関係史をひもとく重要資料といえる。 |
北京入りの前日、次のような政治部記者の証言がある。
|
9.23日、フィリピンで戒厳令。フィリピン、マルコス大統領が独立後初の戒厳令を出す。野党のベニグノ・アキノ自由党幹事長を政府転覆罪の容疑で逮捕する。
| 【田中首相、大平外相が日中国交正常化交渉に中国に出向く】 |
| 日中国交交渉の経過は「日中友好条約、国交回復交渉」に記す。 |
| 9.25日、田中首相と大平外相一行が北京に向かった(外遊交渉2)。周恩来が出迎える。数次の会談が積み重ねられ、二階堂官房長官は、「驚くべき率直な意見の交換が交わされた」とスポークスコメントした。以降、秘術を尽くしての外交が積み重ねられていくことになった。しかし、歓迎晩餐会の席上での田中首相の挨拶に「詫び」がないことで波瀾が起る(「多大のご迷惑をおかけした」という部分が不十分という内容)。 9.26日、第2回日中首脳会談が紛糾する。前日の田中首相の挨拶の内容が謝罪となっていない、というもの。 9.27日、万里の長城参観のあと日中の第3回の首脳会談が行われ、「戦争状態の終結」を「不正常な状態の終結」とすることで合意する。夜、田中首相は毛沢東主席と会談する。毛発言「喧嘩はすみましたか、喧嘩しなくては駄目ですよ」。「不正常な状態(戦争状態)の終了、中国が唯一の合法的政府であることを認める」など共同声明に盛り込む。 9.28日、第四回目の会談。 9.29日、田中角栄首相と周恩来首相が日・中戦争状態終結、人民大会堂で日中共同声明が調印され、日中の国交が回復する。日中国交正常化共同声明に調印。「日中国交回復」が成り、日中共同声明を発表した。日中国交回復に反発した若手タカ派が「青嵐会」を結成した。台湾との国交を破棄することとなる。 |
9.27日、民青同盟が3年半ぶりに大会を開く。第12回全国大会。
| 【台湾が国交断交を発表】 |
| 9.29日、日中共同声明が発表されたことを受けて台湾の国民政府が国交断交を発表し、日本と台湾の国交が断絶した。これにより1954年から「日華平和条約」という政府間による法的基盤に基づいて構成されてきた日台間の政治、経済その他の関係は継続不可能となった。これによって、中華民国政府は台湾にあった日本企業の在外資産を凍結した。総額120億ドルにのぼった。各企業への補償は、日本政府によって為された。この時凍結された日本企業の資産は、中華民国政府の「秘密資金」となり、中曽根がこれに目を付けることになる。 |
| 【帰国後の報告の様子】 | ||||
| 日中国交正常化共同声明調印後のどの時点か定かでないが、田中首相は、中国から羽田孜に電話を入れ、帰国したら直ちに党本部に行く、自民党議員を集めておけと指示している。 9.30日午後1時前、羽田着の日航特別機で帰国。田中首相は、羽田空港に帰国した際のステートメントで次のように述べている。
帰国後の雰囲気は「党が大変」だった。皇居で帰国報告の記帳の後、自民党執行部に報告(自民党本部で椎名副総裁、橋本幹事長ら党執行部と懇談)。午後2時20分から官邸で臨時閣議を開き、国交正常化交渉の経過と成果を報告。午後3時過ぎ、首相官邸でテレビ中継の合同記者会見に臨んだ。午後4時過ぎ、党本部の9階講堂で開かれた自民党両院議員総会に出席し訪中結果を報告。この時、次のように述べている。
演壇に立った田中は次のように述べている。
共同声明について党の最終的了承を求め、台湾派の野次と怒号のなかで自民党は田中報告を了承した。 |
| 【日中共同声明後の台湾との折衝経緯】 |
| 日本外務省は、台湾外交部に対し、経済貿易を中心とした領事関係の維持は国際法の原則として一般的に認められていることに基づいて、断交後も台湾と経済など実務関係が続けられることを希望する日本政府の意思を伝えた。それに対して、台湾側は同日夜、「対日断交声明」を発表し、「中国を代表する唯一の合法政府」という台湾の法的地位は日本との断交によって傷つけられることはないと主張し、断交は日本政府の「日華平和条約の一方的な廃棄」、 「背信行為」であると厳しく批判する他方で、台湾政府はこれからも「全ての日本の反共民衆と友誼を永続する」と日台実務関係を継続する意思を表明した。但し、10.9日、覚書貿易弁事処が外交特権を得て、大使館扱いとなった。10.26日、日台双方の大使館は、それぞれ国旗掲揚を停止し、11.28日に彭孟緝駐日大使、同日30日に宇山厚駐台大使がそれぞれ帰国した。 |
10.3日、米ソが戦略兵器制限条約(SALT I)の批准書を交換する。
10.4日、成田社会党委員長と会談。
10.5日、竹入公明党委員長、春日民社党委員長と会談。
10.8日、キッシンジャー大統領補佐官とレ・ドク・ト北ベトナム顧問がパリで秘密会談を行う。北が9項目の和平案を提示する。
10.9日、閣議で、第4次防衛力整備計画(4次防)が正式決定される。早期警戒機の国産自主開発の動きに対して、国産化の方針を撤回、輸入化に道を開いた。これは、「国産化推進の中曽根構想が消え、日本政府がグラマン社製を購入する可能性が出てきたことを意味する」。
10.11日、チリで、アジェンデ大統領の経済政策に反対してストが多発し、非常事態宣言が出される。
10.13日、日銀発表の9月卸売り物価指数が前月比0.9%急騰と発表。
10.17日、韓国の朴正煕(パク・ジョンヒ)大統領が、全国に非常戒厳令を宣布すると同時に国会を解散し、全大学の休校措置を実施する。
10.19日、ルバング島で、元日本兵の小野田寛郎の生存が確認される。同時に発見された小塚金七一等兵は銃撃戦で死亡する。
10.19日、パリで、欧州共同体(EC)の首脳会議が開かれる。
10.22日、ニクソン大統領が対北ベトナム和平案に同意する。10.23日、ニクソン大統領が北爆の一時停止を指示する。10.26日、北ベトナムが9項目の停戦協定の概要を公表する。
10.22日、三菱重工長崎造船所に世界最大のドック完成。
10.24日、ソ連を訪問している大平外相がコスイギン首相と会談する。
10.25日、国連総会、「中国招請・国府追放」決議案可決。
| 【初の所信表明演説】 | |
|
10.27日、第70回臨時国会召集。10.28日、初の所信表明演説。「日本列島改造論」を内政の柱とするとして次のように述べている。
7月に首相就任してから10月に国会で所信表明演説をするまで113日経過している。これは日本国憲法下で初就任した首相の中では最も遅い記録である。 |
10.28日、中国から贈られたジャイアントパンダのカンカンとランラン2頭が羽田に到着。上野動物園へ。
10.30日、全日空がトライスター導入を決定。
| 【物価、地価が騰勢】 | |
|
この頃物価が騰勢。列島改造論が不動産市場を活気づけ、ブームとなっていた。
|
10月、周恩来総理、姫鵬飛外交部長が来訪の藤山愛一郎議員と会見。中日友好集会、北京で開催。中国側300人、日本側420人が参加。
11.7日、アメリカ大統領選挙で、ニクソンが再選される。
| 【早大で「川口リンチ殺害事件」が発生】 |
|
11.9日、早大で革マル派による「川口リンチ殺害事件」が発生した。東京.本郷の東大構内付属病院前にパジャマ姿の川口氏が放置されていた。死体には全身アザだらけの殴打の跡があり、骨折した腕から白い骨がのぞいていた。早大文学部2年生川口大三郎(20才)、中核派シンパとみなした革マル派によるリンチ事件であることが判明した。 早大の馬場素明委員長は11.11日の記者会見で、「今回の事件は革マル派の組織が引き起こしたもので行き過ぎであった。しかし、リンチそのものは特殊な政治力学の中では今後も有り得る」と居直った。革マル派は、事件に対し、「追及過程での意図せぬ事態、ショック症状による死亡---党派闘争の原則から実質的にはみ出す行為に走ったといわざるを得ない---一部の未熟な部分によって起こった事態---率直な自己批判を行う」と表明した。 11.23日付け朝日新聞に革マル派の最高幹部・土門肇氏の次のようなコメントが掲載されている。「我々の党派闘争は他党派の解体を目的とする闘いであって権力との闘いとは異なる。他党派の誤りを暴露するイデオロギーの闘いが基軸であるが、中核派は今日我々の殲滅を戦略目標に掲げている。こうした我々に対する暴力的敵対に対し我々の自己武装は不可避である。イデオロギー闘争を補助するために暴力行使は存在する。相手に自分の行為の犯罪性を自覚させ、反省させるための補助的方法である」(鈴木卓郎「共産党支配30年」)。 |
11.13日、田中首相が衆議院解散。「日中解散」と云われる。
11.13日、岡田嘉子が亡命先のソ連から34年ぶりに帰国する。
11.8日、衆議院本会議で、「日中共同声明に関する決議案」を全会一致で可決。
11.12日、角栄がジャック.二クラウス選手とプレーし、「帝王」からの手ほどきを受けて満悦している。
| 【第33回総選挙公示】 |
|
11.13日、衆院解散(日中解散)。11.20日、公示。 |
11.19日、列島改造ブームで地下急騰と報じられる。
11.20日、総選挙に臨んで、NHKの「わが党はかく戦う」の座談会番組で、公明党の竹入委員長が、共産党の宮本委員長に、「敵の出方論」の真意を質した際に、宮本は、「我が党の文献をよく読んでください。さようなことは一言も触れておりません」と言い放っている。おかしなことである。竹入委員長の二の矢が無かったことによりそれ以上突っ込まれなかったが、党文献から「敵の出方論」を探し出すことはさほど困難なことではない。宮本の二枚舌の例証である。
11.21日、東京高裁が、メーデー事件控訴審で騒乱罪は成立しないとの判断を下す。
11.21日、アメリカとソ連が第2次戦略兵器制限交渉(SALT II)を開始する。
11.21日、韓国の朴正煕大統領の憲法改正案が国民投票で可決され、大統領指導体制が強化される。
11.28日、リチャードソンが、レアード米国防長官の後任に就任する。
11.29日、日航機が、モスクワ空港離陸直後に墜落し、61人が死亡する。
12.1日、日本政府は、日中国交正常化により日台間の外交関係が断絶しても、実務的関係を維持する方針をとり、窓口となる「交流協会」を発足させた。日本側に「財団法人交流協会」、台湾側に「亜東関係協会」が成立した。本部を東京に置き、会長に堀越禎三(経団連副会長)、理事長に板垣修(元駐台大使)が就任、スタッフはほとんど元外務省、通産省のメンバーで構成された。
12.7日、ソウル高裁が、在日韓国人留学生の徐勝のスパイ事件控訴審で無期懲役の判決を下す。
| 【第33回総選挙】 | ||
|
12.10日、第33回衆議員総選挙(田中首相、橋本登美三郎幹事長)。(自民271名、社会118名、共産38名、公明29名、民社19名、諸派2名、無所属14名当選)。
12.11日、田中首相は、選挙結果に対し次のように述べた。
|
12.12日、第二次田中内閣スタート。第71特別国会が召集される。衆院議長・中村梅吉。
12.14日、田中-福田会談。
12.15日、平垣美代司氏が「現代の労働運動と日本共産党」を公刊。大阪を主とした労働運動の方針と指導を廻っての日本共産党のやり方を批判し、自己批判を求めた。これに対し、日共は、「労働運動を毒す悪書」、「デマ・中傷の反共本」、「意図は共産党躍進の妨害」ビラを大量個別配布し、名誉毀損・侮辱罪で告訴した。
12.18日、ベトナム戦争、ニクソンが最も激しい北爆「クリスマス爆撃」を12日間行う。
12.20日、9中総で、社会党を「中間政党」と批判。
| 【第二次田中内閣が組閣される】 |
| 12.22日、第二次田中内閣発足。三木、大平、中曽根、福田氏らが入閣となった。二階堂官房長官(留任)、橋本幹事長、鈴木総務会長、倉石忠雄(福田派)政調会長。三木副総理・環境庁長官、大平外相、中曽根通産相が留任。福田が行政管理庁長官、愛知揆一蔵相、江崎真澄自治相。(オイルショック→高度経済成破綻・田中→参議院に小選挙区制導入を示唆) |
| 第71回特別国会始まる。 |
12.23日、韓国で、朴大統領を新憲法による大統領に選出する。
12.25日、小選挙区制示唆。
12.26日、トルーマン(Truman,Harry Shippe)没。88歳(誕生:1884/05/08)。アメリカの33代大統領。
12.27日、北朝鮮最高人民会議が社会主義憲法を採択する。12.28日、北朝鮮最高人民会議が、金日成を国家主席に選出する。
12.28日、厚生省人口動態調査まとめる。205万人出生、第2ベビーブームが本格化。
12.28日、パレスチナ・ゲリラがバンコクのイスラエル大使館を襲撃し、イスラエル大使らを人質にして岡本公三らゲリラ36人の釈放を要求する。
12月、6中総。党組織活動改善の一連の「手引き」を決めた。「6中総決定」と呼ばれる。不破書記局長は、「高度に発達した資本主義国でありながら、対米従属下にある日本の革命闘争で、日本共産党がレーニン型の党建設理論をプロレタリア.ヒューマニズムと英雄主義の立場から創造的に具体化した画期的なもの」であったと自画自賛。「金ある者は金を、力ある者は力を」式の改変。
社労党・町田勝氏の「日本社会主義運動史」は次のように伝えている。
|
48年度予算は一般会計14兆2840億円。「列島改造予算」と云われるように大盤振る舞いの積極的財政政策が取られた。新幹線、道路など公共投資を前年度比34%増、14兆2800億円を計上した。
| 流行歌。女の道(ピンからトリオ)。瀬戸の花嫁(小柳ルミ子)。旅の宿(吉田拓郎)。 |
| 流行語。「お客様は神様です」。「日の丸飛行隊」。「ナウ」。「恥ずかしながら」 |
| 映画。「男はつらいよ 柴又旅情」(山田洋次監督)。関東緋桜一家(マキノ雅弘監督)。ゴッドファーザー(米国)。 |
| 出版。「恍惚の人」(有吉佐和子)。日本列島改造論(田中角栄)。ユダヤの商法(藤田田) |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)