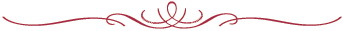
| 反立花論客(渡部昇一、石島泰、井上正冶)考 |
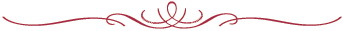
更新日/2020(平成31→5.1栄和元/栄和2).9.13日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、反立花の論客三銃士(渡部昇一、石島泰、井上正冶)の言説を確認しておく。 2011.05.13日再編集 れんだいこ拝 |
| Re::れんだいこのカンテラ時評927 | れんだいこ | 2011/05/13 | ||
| 【「反立花論客三銃士」考】 久しぶりにロッキード事件を振り返る。今までに言及し得なかった面を確認しておく。政治が面白くなくなると、時間がもったいないので角栄に立ちかえる癖があるようである。 1984(昭和59)年と云えば、前年の東京地裁第一審有罪実刑判決を受けロッキード事件公判闘争の最終局面である。この時期、ロッキード事件の正義性を廻って、訴追派の雄たる政治評論家の立花隆に立ち向かう論客が登場した。上智大学教授(専攻は英語文法史)の渡部昇一、弁護士の石島泰、九州大学名誉教授の井上正冶である。これを仮に「反立花論客三銃士」と命名したい。 中でも、渡部氏が公開論争、論戦を繰り返している。ふと、これを振り返りたくなった。一体、どのような内容のやり取りだったのだろうか。当時の熱っぽい雰囲気から逃れて、今静かに振り返るのも一興ではなかろうか。と思い、ネット検索してみたが異常に出てこない。マシなものとしては、れんだいこのサイトが紹介されているぐらいのものである。他は「立花是、渡部非」を巧妙に云い繕うロクデナシものばかりである。この連中によって次のように評されている。
この評が適切なものであるのかどうかを検証したい。れんだいこの観点ははっきりしており、逆の立場で次のように評したい。
この両論のどちらに軍配が挙げられるべきか。いずれにせよ「立花―渡部論争」に対する学的考察が為されているように思えないので、じっくり腰を据えて確認しようと思う。但し、今のところ資料と時間が揃わぬ為、アウトライン的なスケッチにとどめ仕込みの段階としておく。 1984.1月号諸君に渡部昇一「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」が登場した。この時期、文芸春秋、朝日ジャーナルが立花を寵児として持ち上げ、論客第一人者として一種独壇場になっていた。これに「もの申す」の声を挙げた格好となった。 それにしても、諸君の異色な立場が分かり興味深い。諸君は3月号でも渡部昇一「角栄裁判・元最高裁長官への公開質問七ヶ条」を掲載した。同7月号で、立花隆「立花隆の大反論」、渡部昇一「英語教師の見た『小佐野裁判』」、同8月号で、匿名法律家座談会「立花流『検察の論理』を排す」、伊佐千尋・沢登佳人「『角栄裁判』は宗教裁判以前の暗黒裁判だ!」、同9月号で、立花隆「再び『角栄裁判批判』に反論する」、「『角栄裁判』論争をどう思いますか?」と題するアンケート特集が掲載されている。 渡部氏は後に「万犬虚に吠える―角栄裁判と教科書問題の誤謬を糺す」(PHP研究所、1994.4.1日初版)を刊行している。ロッキード事件の下りの論文の見出しは次の通りである。「角栄裁判は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」、「角栄裁判・元最高裁長官への公開質問七カ条」、「英語教師の見た小佐野裁判」、「角栄裁判に異議あり!」、「立花隆氏にあえて借問す」、「田中角栄の死に救われた最高裁」。たかが、これだけの情報を集めるのにも骨が折れる仕掛けになっている。そういう意味で「反角栄政治網」が用意周到に敷かれていることが分かる。この現象は一事万事で、何も言論界だけのことではなかろう。 れんだいこは、この時期の渡部昇一氏の言論意欲を高く評したい。歴史の審判は、俗論の立花軍配から渡部軍配へと差し替える日が近いと思う。ちなみに、この時期の角栄擁護、ロッキード事件そのものへの疑惑スタンスをとった論者を確認しておく。順不同であるが、戸川猪佐武、早坂茂三、小室直樹、太田龍、馬弓良彦、新野哲也、渡部昇一、石島泰、井上正冶、秦野章、古井喜實、蜷川真夫、小林吉弥、砂辺功、鵜野義嗣、岩崎定夢、松下三佐男、俵孝太郎、中野士郎、内海賢二、渡辺正次郎、山本七平、林修三、会田雄次、谷沢永一、浅利慶太、小堀桂一郎、勝田吉太郎、屋山太郎の面々である。三浦康之、青木直人、木村喜助、相沢正、小山健一等々が続く。最近では角栄の番記者を務めていた増山榮太郎氏も好意的に回顧しつつある。 やや中立的に久保紘之、北門政士、水木楊、大下英治、宮崎学等々。田原総一朗はロッキード事件疑惑で名を売り、その後大きく右旋回したことで知られている。 角栄擁護派の列氏を正確に見れば曖昧な者も居ようが、概ねこれらの論者が有能だったことになる。ここに挙がらない者は端から言論レースに出る素養がないことを物語っている。その俗物どもが、その後の言論界を牛耳り今日に至っているので、政界同様の貧相さを免れ難いのは当然である。 ロ裁判擁護派は立花隆、猪木正道、杉森久英らである。中間派は村上兵衛(批判派寄り)、松村暎(批判派寄りだが、立花隆ではなく専門家の裁判擁護論掲載を望むという立場)、岡田英弘(田中角栄には批判的だが裁判には関心がないとのこと)。 2011.5.13日 れんだいこ拝 |
||||
| れんだいこのカンテラ時評№961 投稿日:2011年 7月29日 |
| 【月刊誌「諸君!」誌上での渡部昇一氏のロッキード裁判批判功績考】 1984.1月号「諸君!」に渡部昇一「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」が登場した。この論文が、「始めに結論ありき」の意思統一の下で角栄有罪に向けて事を押し進める当時のロッキード裁判批判の先鞭をつけた。その論旨を確認しておく。 ところで、この時の渡部氏の立論に対するネット上での評判がすこぶる悪い。「渡部昇一の『暗黒裁判』論を読む」、「シリーズ・『田中角栄の真実』批判 」などが典型で「渡部非、立花是」からものしている。れんだいこには、その論旨の薄っぺらさに耐えられない。 渡部論文を掲載した「諸君!」でも、誰が執筆したのかは分からないが「ウィキペディア諸君」に従う限り、その沿革史においてロッキード事件論争の際に「諸君!」が果たした役割について、恐らく意図的故意に欠落させている。一事万事で、現代世界を牛耳る裏政府たる国際金融資本帝国主義批判に繫がるような言論が著しく掣肘され言論統制されているのが通り相場なのだが、ここでも垣間見られる。そこで、れんだいこが是正し、「渡部是、立花非」の観点から一文をものしておく。 その前に、これを掲載した「諸君!」について確認しておく。「諸君!」は㈱文藝春秋が発刊していた月刊オピニオン雑誌であり、1969.5月に7月号として創刊されている。当時の文藝春秋社長の池島信平氏が、「文藝春秋は売れすぎて言いたいことが言える雑誌ではなくなった。だから小数部でも言いたいことを言う雑誌を作ろう」との思いから創刊したと述べている。初代編集長は田中健五。当初の執筆陣は福田恆存、三島由紀夫、小林秀雄、竹山道雄、山本七平、江藤淳、林健太郎、田中美知太郎、高坂正尭、村松剛らであった。 その後の論客として、順不同であるが、白洲次郎、清水幾太郎、山本夏彦、石原慎太郎、古森義久、佐伯啓思、中嶋嶺雄、西部邁、野田宣雄、秦郁彦、平川祐弘、渡部昇一ら。他に中曽根康弘、池部良、山本卓眞、渡邉恒雄、勝田吉太郎、岡崎久彦、佐々淳行、曾野綾子、深田祐介、屋山太郎、金美齢、佐瀬昌盛、山崎正和、平沼赳夫、渡辺利夫、立花隆、黒田勝弘、長谷川三千子、山内昌之、鹿島茂、関川夏央、阿川尚之、東谷暁、井上章一、荒木和博、石破茂、坪内祐三、福岡伸一、佐藤優、福田和也、櫻田淳らが名を列ねている。以来40年を経て、2009.6月号を最後に休刊した。 「諸君!」は、渡部論文を1月号に続いて3月号でも掲載した。1月号は「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」、3月号は「角栄裁判・元最高裁長官への公開質問七ヶ条」。同7月号で、立花「立花隆の大反論」、渡部「英語教師の見た『小佐野裁判』」が併載されている。同8月号で、匿名法律家座談会「立花流『検察の論理』を排す」、伊佐千尋・沢登佳人「『角栄裁判』は宗教裁判以前の暗黒裁判だ!」、同9月号で、立花「再び『角栄裁判批判』に反論する」、「『角栄裁判』論争をどう思いますか?」と題するアンケート特集が掲載されている。 これを見れば、当時の論壇が朝日ジャーナルを始めとして反角栄一色に染まり、角栄訴追の大合唱に明け暮れる中、「諸君!」がただ一誌、異色の「始めに結論ありき的ロッキード事件」批判の姿勢を示していたことになる。この稀有の姿勢が当時の編集部の政治能力に基づいていたものなのか単に注目を浴び売れ行きを伸ばす為のものであったのかは分からない。いずれにせよ当時の角栄包囲網に加担しなかった栄誉に与っている。このことはもっと注目されても良い史実と思う。然るに、「諸君!」のこの栄誉の痕跡が消されている。そこで、れんだいこが一筆啓上しておく。これが本稿の意義である。 この時の渡部昇一氏の諸論は、「万犬虚に吠える―角栄裁判と教科書問題の誤謬を糺す」(PHP研究所、1994.4.1日初版)として発行されている。ここでは教科書問題はさて置き、角栄裁判を採り上げる。渡部氏は、「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」以前にも「諸君!」にロッキード事件絡みの寄稿をしているようである。その一は、1975.2月号に「腐敗の効用」、その二は1976.5月号に「公的信義と私的信義」、その三は1976.10月号に「小佐野賢治考」。計三本をものしている。 それから6、7年鳴りを潜めていたが、1983.10.12日のロッキード第一審判決に合わせての10.15日付け毎日新聞朝刊に掲載された「ロッキード事件当時の最高裁長官にして最高裁免責証書を発行した張本人の元最高裁長官・藤林益三のインタビューコメント」、10.21日付けの朝日新聞朝刊に掲載された「元最高裁長官・岡原昌男のインタビューコメント」にコチンと来て、やおら「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」を書き上げ、1984.1月号「諸君!」に掲載されたと云う経緯のようである。 ところで、この時の元最高裁長官・藤林益三、岡原昌男とは何者か。これを記しておく。両名は、本来ならコメントを自粛すべき事件関係者である。なぜなら、藤林は、1976(昭和51).2.4日、ロッキード事件が勃発し、喧騒が始まり、最高検察庁が「角栄逮捕を意思統一」し、東京地検の堀田力主任検事らが米国の裁判所に事件調査に出航した直後の5.25日、最高裁判所判事から第7代最高裁長官に就任し、東京地検の「不起訴宣明書」を出すようにとの催促を受けて、藤林長官以下15名の最高裁判事全員一致による「不起訴宣明書」を提出している利害関係者であるからである。 藤林氏は根っからの無教会派クリスチャンでもあった。無教会派とは、キリスト教会の各系統の中でユダヤ教教義を重視する宗派である。何か怪しいものが臭うではないか。岡原昌男とは、1977.8.26日、弁護士出身の藤林益三長官の後を受けて、第8代最高裁判所長官に就任している人物である。両者とも、「始めに結論ありき的ロッキード事件」渦中で角栄訴追側に与して訴訟指揮した人物である。 普通、こういう利害関係者は、ロッキード第一審判決に関してノーコメントするのがマナーであろう。これを良識と云う。渡部昇一氏は、その良識のなさに呆(あき)れ、事件そのものには関心があったものの公判には門外漢として留意していなかったところ、やおら検察の論告の解析に入った。これにより、検察正義を擁護し抜く新種の御用評論家・立花隆の論調と鋭く対立し、両者間で論争し合う経緯を見せて行くことになる。 その発端が「諸君!」1月号の渡部寄稿「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」である。今これを読むのに、「渡部VS立花」どちらに軍配を挙げるべきだろうか。立花ヨイショの「渡部昇一の『暗黒裁判』論を読む」、「シリーズ・『田中角栄の真実』批判 」的評論に抗して、れんだいこが渡部ヨイショを試みることにする。 2011.7.29日 れんだいこ拝 jinsei/ |
| れんだいこのカンテラ時評№962 投稿日:2011年 7月31日 | ||||||||
| 【渡部昇一著「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」考】 1983(昭和58)年、 10.12日、東京地裁のロッキード事件丸紅ルート第一審有罪実刑判決が下された。主文と要旨のみ下され、要旨文中にはところどころ「略」とされていた。且つ正文は添付されていなかった。元首相を裁く判決文にしては随分失礼な暴挙と思われるが特段に問題にされていない。 そういう判決文によって田中元首相は、検察側の主張通りに受託収賄罪などで懲役4年、追徴金5億円、榎本秘書も有罪とされた。贈賄側は丸紅社長の檜山広が懲役2年6ヶ月、伊藤宏専務が懲役2年、大久保利春専務が懲役2年、執行猶予4年。田中は直ちに保釈の手続きをとった。 れんだいこが、ロッキード事件、ロッキード事件裁判、その判決文に注目する理由は、これがその後の国策捜査の嚆矢であると思うからである。この時の「司法の型」が延々とその後も繰り返され、主として戦後日本の在地土着系政治家叩き、潰しに悪用されて行くことになった。これが現在の小沢キード事件まで続いている。「法の番人による上からの法破り」であるが、これが公然白昼罷り通ってきた。この「検察不正」が、先の厚生労働省元局長・村木不当逮捕事件公判で満天下に明らかになり、検察内部が遂に自浄に乗り出し、現在まで揺れに揺れているのは衆知の通りである。 もとへ。かの時、毎日新聞10.15日付け朝刊が、白根邦男・社会部長による藤林益三・元最高裁長官インタヴュー記事が掲載された。その中で、藤林氏は次のように語っている。
朝日新聞10.21日付け朝刊が、岡原昌男・元最高裁長官のインタヴュー記事が掲載された。その中で、岡原氏は次のように語っている。 見出しは「一審の重みを知れ、居座りは司法軽視・逆転無罪有り得ない」。
既に述べたように、両氏ともロッキード事件、ロッキード裁判渦中の最高裁長官を務めた人物である。幾ら在任中の事件として責任があったにせよ、こう云う場合には「渦中の一人」として発言を差し控えるのが嗜みであろうに露骨に角栄訴追加担コメントしている。これはどういうことだろうか。 よりによって元首相を裁く特殊な事案であると云う首相職の権威に対して配慮する姿勢が微塵もなく、逆に被告人の控訴を司法軽視と看做して「首相経験者として絶対に許されることではない」と恫喝している。察するに、この元最高裁長官二氏が日本国の最高権威である№1の天皇、№2の首相よりも、より権威のある筋からの差し金に従い、それ故に、こうも威猛々しくコメントしているのではなかろうか。これを逆に云えば、後ろ盾なしには恐れ多い裁判だったのではなかろうかと云うことになる。この推理を否定するなら他にどういう理由が考えられようか。 秦野法相は、月刊誌「文芸春秋」12月号に寄稿し、角栄の人権擁護の観点から国連の人権宣言の趣旨を援用して、「第一審判決の際の藤林、岡原コメント」を批判した。これに対し、藤林、岡原両氏は、秦野発言に対し「法律のシロウトの云うこと」と反論している。しかし、これも失礼な話である。秦野法相は元警視総監である。その警視総監を「法律のシロウト」呼ばわりする神経が解せない。警視庁が愚弄されておりメンツに関わる初言であるが、警視庁が抗議したのかどうかは分からない。いずれにせよ軽率な暴言には違いない。 当然、「第一審判決の際の藤林、岡原コメント」は、コメントした藤林、岡原両元最高裁長官だけの問題ではない。それを大々的に取り上げ、「角栄よ観念せよ」的論調を煽った毎日新聞、朝日新聞の記事姿勢も徹底的に批判されねばならない。しかし、当時のマスコミから内部批判が出た形跡がない。否それどころか「角栄よ観念せよ」的論調を競って記事にして、「権威のある筋」からの覚えめでたさを買おうとしていた:ゲスな生態ばかりが透けて見えてくる。 ちなみに、当の角栄は判決に激怒した様子を伝えている。
この日の夕刻、田中の秘書である早坂茂三が「田中所感」を読み上げた。
渡部氏は、この時点で、炯眼にも次のように述べている。
渡部氏は続いて、藤林、岡原両名に対し、法の番人の元最高トップたるものが一審の重みを語るが故に間接的に三審制の意義を否定しているところにも問題ありと批判している。これ又炯眼であろう。次のように述べている。
故に、「角栄よ徹底的に争え」として次のように述べている。
ロッキード裁判の検察司法の乱暴さは目に余る。この点については追々確認して行くことにする。渡部氏が中でも批判し抜いたのが、免責特権付きの外国人証言に対して反対尋問する機会が与えられぬまま証拠採用され、有罪とされたことに対してであった。次のように述べて結んでいる。
こうした渡部氏の論調に小室直樹氏の識見が作用していたようである。「同氏は田中裁判に関連した本も二、三冊書いておられるし、いろいろのところで発言もしておられるから」、「小室氏が田中裁判について書かれた本を以前に読んだ時は、ただ『面白い指摘だな』と思っただけであったが、司法界に、あるいは日本全体にみなぎる『予断』という点に気付いた今では、『やはりそうだったのか』と改めて慄然とするのである」と述べており、注目していたことが分かる。 2011.7.31日 れんだいこ拝 jinsei/ |
| れんだいこのカンテラ時評№963 投稿日:2011年 8月 1日 | |
| 【渡部昇一著「角栄裁判・元最高裁長官への公開質問七ヶ条」考】 「諸君!」は、渡部昇一論文を、1984.1月号の「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」に続いて3月号でも「角栄裁判・元最高裁長官への公開質問七ヶ条」を掲載している。これを確認しておく。 冒頭で、軍人勅諭の一節「世論に惑わす政治に拘らずただただ一途に己が本分の忠節を守り」云々を挙げ、日本の司法もこの伝統を守るべきところ、戦前の軍部がこの戒律を犯したと同様にロッキード事件に於いて暴走し始めていることを危惧している。 「第一審判決の際の藤林、岡原コメント」がその典型であるとして、ロッキード事件の渦中の最高裁長官が引退後に於いて判決文にコメントすることが異常かどうかを「公開質問の1」としている。岡原発言は藤林発言に比して更に露骨に恫喝的であり、これが裁判に予断を与える恐れがあるのではないかと云う点を「公開質問の2」としている。 次に、日本の刑事訴訟法、検察法にない米国式の嘱託尋問制を採用し、しかもその嘱託尋問に米国では当然視されている証人に対する反対尋問の権利を奪った上での一方的な云い勝ち云い得証言を採用していることにつき、岡原元最高裁長官の見解を仰ぐとして、これを「公開質問の3」としている。 そういう曰くつきの嘱託尋問により証拠採用するに当り、事前に検察総長の「免責宣明書」(1976.7.21日)に続いて最高裁決議(1976.7.24日)まで提出していることにつき、これが適正なものなのかどうか岡原元最高裁長官に問うとして、これを「公開質問の4」としている。 続いて、「第一審判決の際の藤林、岡原コメント」が一審判決を絶対視させ結果的に三審制を軽視している発言内容につき、元最高裁長官の識見を問うとして「公開質問の5」としている。加えて「第一審判決の際の藤林、岡原コメント」が、角栄訴追のエールと化して政治的意味合いの強い発言となっていることにつき、識見を問うとして「公開質問の6」としている。 次に、立花隆の「被告人田中角栄の闘争―ロッキード事件傍聴記」(朝日新聞社、1983年刊)の嘱託尋問を廻る記述で、概要「(嘱託尋問には適法手続きでやや問題があるが、田中被告側にも問題があり)反対尋問のテストつきの嘱託尋問を新たにやり直そうではないかという主張を本気ですることができない。それをすれば、自分たちに不利な証言が法的に完全に固まってしまうからである」と記述していることに対して、そのウソを暴いている。 渡部氏は、田中被告側が1982.2.10日付けで反対尋問請求を正式に東京地裁に提出していたこと、それが同年5.27日付で請求却下されているとして、立花式の「田中被告側が反対尋問により藪蛇になることを恐れてビビった」なる論が悪質なデマであると批判している。渡部氏はかの東京裁判でさえ反対尋問を認めていたことを伝え、ロッキード事件の捜査手法の異常性を批判している。 この下りは、デマを平然と書く立花、その立花を「知の巨人」とあがめるマスコミの知性の空恐ろしさが透けて見えてくる話である。これを踏まえて、「元最高裁長官たちにお尋ねしたい。今回の裁判で反対尋問を必要なしとして却下したひとは正当であったとお考えかどうか」として、これを「公開質問の7」としている。 最後に、違法性承知のなりふり構わぬ田中角栄訴追派の魂胆の正義性を問い、「目的は手段を神聖化する」ことができるのどうかを問うている。渡部氏は例として戦前軍部の反乱将校が引き起こした5.15事件、2.26事件を例にして是非を問おうとしている。渡部氏のスタンスは、反乱将校の決起を法治主義遵守の立場から非と論じ、ロッキード事件に於ける司法当局の手法を同様なものとして批判している。その上で、次のように述べている。
これが渡部氏の終始一貫した論調である。政治的中立を重んじ、事の是非以前の問題として手続き民主主義の重要性を説いていると窺うことができる。このように説く渡部氏の論理論調のどこに非が認められようか。如何にも学者的に理路整然としていると看做すべきではなかろうか。 ここで、渡部氏が立花論法のデマゴギー性を鋭く衝いたことから、この後、「渡部VS立花論争」が始まる。これからそのサマをも見て行くが、既述したようにネット検索では「立花是、渡部非」見解のものが圧倒的に多い。れんだいこは、どう読めばそういう結論になるのかが不思議でさえある。渡部氏のどこが間違いなのか、れんだいこにはさっぱり分からない。恐らく立花派と渡部派には頭脳の配線コードで交わらない何か先天的なものがあるのかも知れない。しかし待てよ、世の中には「どっちもどっち」で済ませられる場合、済ませられない場合がある。本事案は済ませられない事案であり曖昧にする訳にはいかない。 ここでは、立花の「被告人田中角栄の闘争―ロッキード事件傍聴記」記述にある「嘱託尋問の再チェックを田中被告人側が恐れたなる論」の正否を吟味し白黒つけねばならない。これがウソであるとすると、立花は平気で詐術する異常言論士であると云うことになる。前述したが、そういう御仁が「知の巨人」なる誉れを得、自他ともに自負し通用してきたが、そろそろ地に落とさねばなるまい。「知の虚人」であることを知らせたいと思う。 れんだいこ的には、立花が角栄評価を終始デタラメにしたまま今日を迎えていることもあり、この際、立花が角栄研究をしたように、れんだいこが立花研究をしたいと考えている。立花が角栄研究を否応なくしたように、れんだいこも否応なくするハメにあっている。なぜなら、ロッキード事件以来の日本ジャーナルの変調の嚆矢が立花より始まると看做しているので、どうしてもこの関門を越さねばならないからである。 2011.8.1日 れんだいこ拝 jinsei/ |
| れんだいこのカンテラ時評№964 投稿日:2011年 8月 2日 | |
| 【渡部昇一著「英語教師の見た『小佐野裁判』」考】 「諸君!」は、渡部論文を、1984.1月号の「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」、3月号の「角栄裁判・元最高裁長官への公開質問七ヶ条」に続き、7月号で「英語教師の見た『小佐野裁判』」を掲載している。これを確認しておく。この時、立花の「立花隆の大反論」が併載されているが、その内容が分からない。強権的な著作権論がなければ、どこかでサイトアップされているのを見つけられると思うが出てこない。残念なことである。 冒頭、K女子から小佐野賢治氏の裁判闘争に知恵を貸してほしいと頼まれた経緯を明らかにしている。小佐野氏は20万ドル受領容疑その他で裁判に付されていたが、否認していた。クラッタ―証人が「1973年の11月3日、12時より前か後かははっきりしないが、とにかくmidday前後に小佐野氏と会い20万ドルを授受した」と証言していた。但し、小佐野氏は、この時間帯はホノルル経由でロスアンゼルス国際空港に向かうユナイテッド航空114便に乗っており機中の人であった。到着時刻が4時18分。 第一審判決(判谷恭一裁判長)は「午後4時半頃もmiddayのうち」と解釈して有罪を宣告した。控訴趣意書で「middayは午後4時半までは及ばない」と主張。高裁で、この点が争われていた。1983.10.14日、渡部氏は鑑定証言者として高裁に出向き、概要「middayは真昼、daytimeは昼間と識別できるが混同は許されない」と証言した。 この証言から半年余り、1984.4.27日、控訴審判決(海老原裁判長)が下り、この点について一審と同じく有罪とされた。但し、一審がmiddayを午後4時半まで拡張したのに対し、控訴審では「右供述は単なる記憶違いと見る余地がある」としていた。こうなると、裁判は付け足しでしかなく「有罪は裁判の前から決まっていた」と云うことになる。渡部氏は次のように述べている。
本論文は概略以上の短文である。 ことのついでに小佐野賢治論を書きつけておく。俄か拵えなので十分なものになり得ないが、足らずは追々書き加えて行くことにする。 「田中角栄と小佐野賢治の刎頚の友考」 (kakuei/sisosiseico/jinmyakuco/ osanokenjico.html) 角栄と小佐野の出会いに就いて、角栄は次のように証言している。 「昭和22~23年頃、正木亮先生の紹介で小佐野氏を知った。特に小佐野氏と親しくなったのは、私が昭和25年に長岡鉄道の社長に就任、同社のバス部門の拡充に際して国際興行から大量に車両の提供を受けたことからです」(ロ事件検察官調書から)。 二人は小佐野が大正6年、角栄が7年と云う1歳違いの同年代にして、頭脳優秀ながら出自は貧乏家庭、共に苦労しながら若くして頭角を現していた点で共通していた。その後の進路は角栄が政治、小佐野は実業に向かい「畑」は違ったが肝胆相照らす仲になり生涯の刎頸の交わりとなる。両者の逸材ぶりを見抜いた正木弁護士も偉いと云うことになる。 両者は戦後日本の在地土着型の登竜者であり、現代世界を牛耳る国際金融資本が手なづけられなかった日本国産の戦後のモンスターであった。れんだいこ史観に照らせばホリエモンなどもこの部類に入る。ここを理解しないと俗流の金権批判に踊らされてしまう。 角栄と小佐野は陰に陽に提携し助け合ったことは容易に推定できる。恐らく、角栄は小佐野を政商的に利用し、小佐野は角栄の政治能力を行政的に活用したものと思われる。れんだいこの知る圧巻は、角栄がヒモつきになる財界からの政治献金を極力遠慮し、ここ一番では小佐野から用立てていたと思える節がある。当然自力調達した上での話である。今日びの政治家は法によりがんじがらめにされているので、こういう芸当はできないが、当時に於いては金力は権力の必須条件であった。 関心すべきは、両者は案外と身ぎれいに関係しあっていることである。時に虎の門事件のように(深い事情は分からないが)露骨な稼ぎを生んでいるが、それ以上のものは確認できない。互いの能力を認め合い識見を競っていたと思える節がある。世上の角栄論、小佐野論と大きく違うだろうが、れんだいこの見方の方が正鵠を射ていると思う。角栄式金権論については次のサイトに記している。 「れんだいこの角栄金権考課評」 (kakuei/sisosiseico/kinkenmondaico/ rendaiconokinkenron.htm) 角栄と小佐野を利権まみれ的に見る評論が後を絶たない。しかし、それらは下種の勘ぐりと呼ばれるものであり、実態は時代の能力者が必然的に邂逅した出会いだったと思いたい。戦後日本には、こういう角栄と小佐野、ミニ角栄とミニ小佐野が全国各地に輩出したのであり、今その後裔たちが苦しめられている現実こそ嘆きたい。 2011.8.2日 れんだいこ拝 |
| れんだいこのカンテラ時評№965 投稿日:2011年 8月 3日 | |||||
| 【渡部昇一著「『角栄裁判』に異議あり」考】 渡部氏は、1984.10月号の文芸春秋に「『角栄裁判』に異議あり」を寄稿している。かなり長文で、1983.10.12日のロッキード第一審判決以来のわだかまりを本格的に解析している。「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」以来、渡部氏の法律的知識が格段に進んだのであろう、「証拠能力(許容性)」と「証拠の証明力(信用性)」の違いに触れた後、ロッキード事件における免責証言の証拠採用につき次のように批判している。
ロッキード事件に於ける「利害関係外国人による外国地での免責特権付き且つ反対尋問なし証言」は、日本国憲法37条2項の「刑事被告は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己の為に強制的手続きにより証人を求める権利を有する」規定を真っ向から蹂躪している。故に、以下、分かり易くする為に仮に「失格違法証言」と命名する。 「失格違法証言」は、本来であれば証拠採用し得ないのにロッキード事件では意図的故意に採用された。これをどう評するのかが問われた。渡部氏は、東京裁判でさえ反対尋問が認められていたことを例に挙げ、「失格違法証言」採用をオカシイと云い、立花は問題ないとした。立花は、田中側が反対尋問を要求しなかったのであり、その理由として藪蛇になるのを恐れ尻込みしたなるデマを振りまいていた。渡部氏が、それがウソであることを指摘したのは前稿で述べた通りである。 渡部氏は、検察論告の5億円授受ストーリーにも疑問を投げかけている。5億円の札束を段ボールに詰めた人も見た人も一人として証言者がいないことに対して、「罪体がない」ことになるのではないかと述べている。「第一審判決の際の藤林、岡原コメント」は共に口裏合わせたかのように「7年にもわたり審理を充分に尽くしており」と述べているが、肝腎の「罪体の決め手」を欠いたまま経過した裁判でしかなかったとして「罪体なしの攻防だから、まずは壮大な時間の空費みたいな印象を受ける」と述べている。 最高裁が、日本国法に定めのない刑事免責宣明書を米国地裁に退出したことのオカシサにも言及している。刑法学者の井上正治氏の「日本の裁判史上に於いて、最も恥ずべき裁判例の一つになる」との指摘を支持し次のように述べている。
続いて、検察式の首相権限論に疑問を投げたり、陪審員制に言及した後、1984.4.13日号の朝日ジャーナルの匿名論文「“知的ピエロ”渡部昇一の歪んだ角栄擁護論」に反論している(その内容を確認したいがネット上に出てこないので分からない)。渡部氏は、「拙論の内容的批判には立ち入らず、愚にもつかぬ個人攻撃ばかりである」ことを批判している。渡部氏は既に1972年の教科書問題で、朝日新聞と論争していた。14カ条の公開質問状を提起したが、朝日新聞から責任ある反論はなかった云々。加えて、こたびの朝日ジャーナルの「匿名による人身攻撃」に対して何故に署名論文で応じられないのかと批判している。 渡部氏がこのように縷々ロッキード事件の不正を批判していたが、法曹界―マスコミ界主流からは「素人発言」として無視されていた。ところが、自由法曹団の重鎮にしてメーデー事件、松川事件、砂川事件等で勝訴し、吉田石松岩窟王事件で再審への道を開く等「日本一の刑事弁護士」の名声を得ていた石島泰・氏が「諸君!」1984.5月号に登場し、「角栄裁判は“司法の自殺だ”」と断じ、渡部見解を援護射撃する局面になった。付言しておけば、石島泰・氏は戦後共産党の徳球―伊藤律系党中央時代のキレ者であり、共産党内政変による宮顕―不破党中央時代になるや煙たがられ不遇であった。共産党内政変がこういうところにも現われてくる見本である。 石島泰・氏は、1973.2月、検察の論告求刑直後の弁護士研修講座で「刑事弁護の思想と技術」と題する講演の中で次のように弁じている。
プロ中のプロである石島泰・氏がかく述べたことで、それまでの「素人のくせに何を云うか」なる批判が成り立たなくなった。続いて、「諸君!」1984.6月号に元九州大学法学部教授、法学部長の井上正治氏論文「『角栄裁判』は主権の放棄だ!」が掲載された。井上氏は更に歯切れよく意訳概要「ロッキード裁判は主権の放棄、司法(裁判所)と行政(検察官)の談合による植民地特有の迎合裁判」であると断じていた。 この流れに対し、立花が「“角栄裁判”批判を批判する!立花隆の大反論」で登場した。立花反論は、「田中角栄の収賄は絶対的事実」と予断認定した上で、この犯罪を暴く為には「基本的人権と公共の福祉は等距離にあるべきである」として検察正義を賛美するスタンスから、石島泰・氏の諸論に悪罵を投げかけていた。その理論は、「東京地検特捜部の廊下を自由に歩ける唯一のフリーのジャーナリスト」と呼ばれる「誉れ」を地で行く検察擁護論のオンパレードで構成していた。渡部論文は、この立花見解の杜撰さを個々に分析しているが、ここでは採り上げない。 これに対して、匿名法律家3名による「諸君!」1984.8月号に「立花流“検察の論理”を排す」が掲載された。「匿名法律家3名」が誰であるかは分からないが、こう云う場合には堂々と実名で登場すれば良いのにと惜しみたい。続いて「諸君!」1984.9月号に小室直樹氏の寄稿が掲載された(論文名は分からない)。小室氏は、立花式論理論法を次のように断じている。
こうしてみれば、かの時ロッキード事件騒動に於ける角栄批判の大合唱のさ中で「諸君!」が唯一棹さしていたことが分かる。当時の編集長が誰か分からないが功績だろう。尤もその後させんでもされたのではないかと気にかかる。 この時の渡部派の立論、立花派の立論を比較対照して論じてみればより分かるだろうが、これが為されているように思えない。れんだいこも時間がないのでできない。推定するのに、渡部派の法が筋が通っており、立花派の方は悪しき弁論技術を磨いただけの修辞言論にまみれているのではなかろうか。 この頃より、検察正義を後押ししするジャーナルが堂々と登場したことになる点が見逃せない。以降、この連中が闊歩し始める。その後の言論界では渡部氏の方がナンセンス化され、立花の方が「知の巨人」の名声を得て君臨するようになる。ネット言論は、この類で溢れている。しかし、これはジャパンハンドラ―ズの言論操作によってそうなったものであり、日本の言論界がこれを防げなかったことを意味している。言論界がそのように操作され汚染されていることを確認すべきだろう。れんだいこはかく理解している。 渡部論文は付録として次のような情報を伝えている。石島泰・氏に対して、共産党常任幹部会委員・法対部長の小林栄三が、1984.6.7日付け赤旗に「『諸君!』石島発言の虚と実」と題して、石島発言が党の方針に反しているとして批判している。更に弁護士にして共産党代議士の正森成二が文化評論7月号で、ロッキード事件の一審判決を支持し、石島氏を批判している。井上氏は中核派系の破防法弁護団主任を辞任させられている。 中核派は今からでも遅くない、この時の対応を自己批判すべきであろう。日共は「悔い改めない」、「左」を偽装してジャパンハンドラ―ズに飼われているに過ぎない連中だから云うだけ無駄である。日本左派運動が、かくも変調に冒されていることを確認すべきであろう。れんだいこには、角栄擁護で登場した人士こそ本来の左派だと断じたい。 2011.8.3日 れんだいこ拝 |
| れんだいこのカンテラ時評№966 投稿日:2011年 8月 4日 | |||
| 【「立花隆氏にあえて借問す」、「『田中角栄の死』に救われた最高裁」考】 「諸君!」は、渡部論文を、1984.1月号の「『角栄裁判』は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」、3月号の「角栄裁判・元最高裁長官への公開質問七ヶ条」、7月号で「英語教師の見た『小佐野裁判』」に続き、1985.2月号で「立花隆氏にあえて借問す」と題して掲載している。これを確認しておく。 ロッキード事件の変調が小室直樹、秦野章、俵孝太郎、渡部昇一、伊佐千尋、石島泰、井上正治氏らにより手厳しく批判され始めると、立花が文芸春秋、朝日ジャーナルを根城にして反論に出ていた。文芸春秋の1983.12月号で「田中擁護のあらゆる俗論を排す」、以下朝日ジャーナル1984.10.12日号の「発言ねじまげるイカサマ論法」、「渡部昇一の『知的扇動の方法』」、同10.19日号の「渡部昇一の『慄然』引用術」、同10.26日号の「渡部昇一の『探偵ごっこ』」、同11.2日号の「渡部昇一の『知的不正直のすすめ』」、同11.9日号の「渡部昇一と『妄想カルテット』」、何号か明示していないが「幕間のピエロたち―立花隆・ロッキード裁判批判を斬る」がそれである。この時の編集長が誰か分からないが、「諸君!」編集長と張りあっていたことになる。 渡部氏は、次のように判じている。
立花の渡部批判論文の見出しはいずれも煽情的嘲笑的である。その言を鵜呑みにすれば、渡部氏の方が詐欺師に見えよう。しかし、両者の言論内容を精査すれば、一貫して誠実なのは渡部氏の方であり、立花の如きは検察正義プロパガンダの請負人でしかなく、中身で反論できないものだから修辞レトリックで貶しているに過ぎないことが判明する。しかし世の中は妙なもので、この修辞レトリックにヤラレてその気になる手合いが多い。何度も言うが、ネット言論上の「立花是、渡部非」立論者はこの類である。 渡部氏は、この論文で、立花が朝日ジャーナルから、角栄裁判批判を斬る為に「いくらでも書きたいだけ書いて良いと潤沢なスペースを提供して貰った」ことを明らかにしている。これは朝日ジャーナルの1984.10.12日号の立花自身の弁のようである。立花とこの時の朝日ジャーナルの編集長とはよほど深い絆で結ばれていることが分かる話である。この編集長が誰であるかは追々分かるだろう。この編集長の頭脳には、朝日ジャーナル誌上で立花論文と反立花論文を併載して読者の判断を仰ぐと云う気持ちはさらさらなかったことが分かり興味深い。普通はこういう関係をグルと云う。 渡部氏は、この論文で、立花に次のように問うている。その1、角栄逮捕の際の容疑が外為法違反であったが、こういう別件逮捕を是認されるのか。その2、検察の首相権限論によると、首相が私企業の商行為に無報酬介入する権利を認めていることになるが、これを是認されるのか。その3、検察の外国経由尋問調書の証拠採用を是認されるのか。その4、最高裁の免責宣明書提出を是認されるのか。その5、免責特権付き共犯者証言の証拠採用を是認されるのか。その6、反対尋問なしの共犯者証言の証拠採用を是認されるのか。 次のように結んでいる。
渡部氏の渦中のロッキード裁判批判は一応これで終わっている。他にもあるのかもしれないが、「萬犬虚に吠える」に収録されているのは以上である。補足として「諸君!」1994.2月号に「『田中角栄の死』に救われた最高裁」を著わしている。これについて確認する。 1993.12.16日、角栄が逝去した。角栄の死は、かの有能過ぎる角栄頭脳が1977.2月にロッキード裁判に初出廷以来17年も法廷に縛られたまま、国策捜査-国策裁判により封ぜられたことを意味する。渡部氏は、解析してきた4論文で言及を閉ざしたままであったが、角栄の死に際して8年ぶりに「『田中角栄の死』に救われた最高裁」で追悼したことになる。本稿で再度、嘱託尋問の不正に触れている。渡部氏は、角栄容疑の前段階の問題として、文明国にあるまじき変調な裁判手法の不正義を告発し抜いた。「素人は黙っておれ」に対し、「素人でもこれだけは云わせて貰う」として獅子奮迅の活躍をした。渡部氏はその後発言を封じた。立花はのべつくまなくしゃべり続けた。ここに両者の鮮やかな対比が確認できる。 渡部氏は、最後に角栄批判に終始纏わりついた金権政治批判について次のように述べている。
渡部氏の角栄を見る眼の眼差しは温かい。この観点に真っ向から対立しているのが立花―日共理論である。この両論、果たしてどちらに軍配を挙げるべきだろうか。 2011.8.4日 れんだいこ拝 |
| れんだいこのカンテラ時評№967 投稿日:2011年 8月 5日 |
| 【渡部昇一理論考】 以上、ロッキード事件絡みの渡部5論文を見てきた。これをどう評するべきか。ネット上で「立花が鎧袖一触、論破した」なる評が流布されているが、如何に為にする立花ヨイショ論であることか。そういう手合いに限って法律論を小難しく解説しているが、中身が空疎なことを隠すこけおどしに過ぎない。今後は本稿も検索に登場するだろうから良い按配に中和したつもりである。それにしても、本件に拘わらず知らぬ者を誑かすニセ評が罷り通っているので、見つけ次第に成敗せねばならない。 れんだいこの渡部昇一論を披歴しておく。思うに、渡部氏は実に面白い人物である。学者的良心に於いて一言居士であり学究的に深い。そこから生まれる政治的な知的感性が良い。「朝日新聞VS渡部の教科書問題」、「ロッキード事件に於ける言及」はその白眉の論考である。興味深いところは次のところにある。当人は体制側の保守言論の士として自ら位置付けているが、れんだいこの見るところ、その重心は定まっていない。つまり、本人の保守的言論士の思いとは別に案外そうではなく本来の左派精神に繫がる面を持っているように思われる。正確には、1970年代までの戦後日本の歩みを肯定する体制擁護論者とみなすべきではなかろうか。実はここに渡部氏の鋭い知的感性があると見立てたい。 仮に、日本の戦後体制をプレ社会主義的なものだとみなせば、どういうことになるのか。渡部氏本人は自ら保守系の論者として自己認識しているのではあるが、実はプレ社会主義体制の護持派でもあるということになりはすまいか。れんだいこが評すればそういうことになる。これを逆に云えば、多くの左派もんが角栄批判に興じてきたが、その角栄が戦後プレ社会主義体制の最も有能な牽引者であったと仮定すれば、その角栄を最も悪しざまに批判し続けた自称左派もんこそ最も反社会主義な言論士であり、戦後プレ社会主義体制の壊し屋と云うことになる。 れんだいこ史観によれば、ロッキード事件というのは実に奇妙且つ味わいのある事件であった。それは、表見保守にして真実は左派であった田中角栄政治をどう評するかが問われていた。角栄は首相の座にまで上り詰め、辞任後も隠然とした権勢を示していた。これに対し、角栄を捕捉し、日本を捕捉する為に現代世界を牛耳る国際金融資本が用意周到にワナを仕掛け断固たる鉄槌を下したのがロッキード事件であった。 しかし、幾ら国際金融資本の絶対指令とはいえ、当時の日本政界は角栄―大平派が牛耳っていた為に日頃の子飼い派だけでは勝ち目が薄かった。故に、表見左派にして真実は国際金融資本の御用聞きであった日本左派運動をも総動員して、つまり右から左まで駆り立て角栄訴追の大包囲網を敷き、これにマスコミの言論大砲を加えることによって事件化することができた。当然、角栄派も応戦する。ロッキード事件は、両者が攻防した戦後史上最大の政治事件となった。 そういう意味で、ロッキード事件は、このドラマの登場人物の表見ではなしの真実の右派左派を見分けるリトマス試験紙足り得ている。角栄擁護に回った者こそ戦後日本のプレ社会主義を守る者たちであり、そういう意味で当人の意識は別として本能的に左派であり、角栄批判に回った者こそ、当人の意識は別として本能的に右派である。否正しくは右派と云うより国際金融資本帝国主義の走狗と云うべきだろう。凡俗の歴史観からは導き出せないが、れんだいこ史観からはこういう見立てが必然になる。 この時、黙っておれないとして登場した渡部氏の果たした役割は本能的に左派のものであった。氏がロッキード事件に於いて果たした役割は戦後日本民主主義のプレ社会主義的なものが壊されて行くことに対する義憤であった。氏がそのことを自覚していないところが滑稽なだけの話しである。氏のロッキード事件批判、角栄に対する温かい眼差しはそういうものであったと確認しておきたい。 渡部氏はその後も正義の論を述べ続けて行くことになる。どのような政論を述べているのかにつき風評的なもの以上は知らないが、一言しておけば、国体論に於いて透徹した歴史観は持っていないように思える。教科書問題、ロッキード事件に於ける国体護れ論は正しかったが、その他の面においては皇国史観を突き抜ける国体論を持ち合わせていないことにより凡庸な保守系言論士になっているようにも見受けられる。これについては氏の他の論考を読んでいないので、これぐらいの感想に留めておく。 これと対極的に、平素左派圏界隈に出没し、ロッキード事件の牽引者として登場してきた立花とは何者か。背後に胡散臭いものを感じ取るのはれんだいこだけだろうか。史実は、その立花が奏でる検察正義論ジャーナルが持て囃され、表見左派が彼を支持し、以来日本のジャーナリズムをすっかり変質せしめてしまった。それまでの冤罪告発ではなく、180度転換して検察正義を後押し、したり顔して煽る構図ほど愚劣なものはあるまい。このニセモノ左派たちの政治遊びが政治にせよ評論にせよ今日まで続いていると見立てたい。そろそろお仕舞いにせねばなるまい。 最後に。この過程で確か「渡部VS立花のshall論争」があった筈である。これを確認しようとしたが、ネット検索からは全く出てこない。実際にあったのに出てこないのは何か裏があることが多いので余計に気にかかる。どなたか該当サイトを紹介くだされば、ついでに考察しておきたい。当時の印象として、「shall」の解釈を廻って、立花が渡部氏の本業である英語学に於いて堂々と論争していた記憶がある。れんだいこは、立花の裏に彼を教唆し知恵を授ける者の影を感じていた。それは「立花論文の一事万事の型」を示していた。こういうところを確認したいと思っている。どなたかご教示お願いしたいと思う。これにて「渡部昇一理論考」をひとまず完とする。立花については以下のサイトで考察している。本稿の格納庫も示しておく。 「立花隆論」 (ronpyo/mascomiron/ tachibanatakashiron/tathibanatakashiron.htm) 「反立花論客(渡部昇一、石島泰、井上正冶)考」 (kakuei/rokkidozikenco/ kakueihihanhatoshijihaco/hantathibanaco.html) 2011.8.5日 れんだいこ拝 jinsei/ |
| 補足として、上山 春平(うえやま しゅんぺい、1921年1月16日 -、日本の哲学者。京都大学名誉教授)の立花絶賛論があるようである。「竹中平蔵 vs. 金子勝」に次のようにある。「思想信条がこれまた異なるあの上山春平氏が、立花隆に絶賛の書簡を送ったことを思い出した。曰く、批判を今日的意味で実践している貴兄(立花氏)を尊敬します云々・・・」。これを確認したい。事と次第によっては、上山春平を成敗することになる。 |
| 【渡部対立花のロッキード裁判誌上論争考】 | ||
| 元首相・田中角栄の逮捕、実刑判決にまで至る大疑獄事件となったロッキード事件をめぐって立花隆氏と渡部昇一氏が長期間、繰り広げた朝日ジャーナル(筑紫哲也編集長)での激論。朝日ジャーナル誌上で立花と渡部が各5回ずつ計10回の論戦を行った。ちなみに筑紫と立花の親交が厚く、筑紫がTBSのニュース23のキャスターになってからも、他の問題でも立花をゲストに迎えた番組を度々つくってきた経緯がある。この時、渡部は角栄を擁護して「ロッキード裁判は東京裁判以上の暗黒裁判」とする論陣を張った。これに対し立花は検察正義を代弁した。「この論争は渡部昇一の負けであった」と通説化されているが、それはそういう風に誘導されているのに過ぎない。そういう意味で、この時の論争の公開が待たれている。 諸君誌上で1984年新年号から始まったロッキード裁判批判キャンペーンの中で、冒頭陳述の意味や、「証拠能力」と「証拠の証明力」の区別を知らず、裁判記録さえ読むことなく自らの妄想を元に批判したと立花隆に批判された。なお、渡部は立花との公開論争の後、この件に関して沈黙を続けていたが、渡部が1985年9月から「致知」において毎月連載している「歴史の教訓」において、2012年2月号の第181回で突然、立花の批判に「花隆氏よ 議論の土俵に出てこい」を発表、再反論し、要望があればいつでも立花との議論に応じる構えを見せている。なお、これに対する立花からの反応は現在のところない。 |
||
朝日ジャーナル(1985年8月30日号)に掲載された、立花隆とのロッキード裁判誌上論争の一コマ。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)