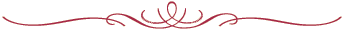「れんだいこのカンテラ時評677、角栄の『政治は力なり。力は数なり』論考」を書き換える。と云うのも、今日2011.1.10日午前8時からの朝日テレビ「スーパーモーニング」で、「右肩上がり昭和の象徴田中角栄元総理なら今」が放映され、気になったことを書きつけてみたいからである。
電波が公正な視点から角栄を採り上げるのは断然良い。これまで余りにも偏って批判し過ぎてきたので罪滅ぼしの意味もあろう。そういう意味で、タイトル名の「右肩上がり昭和の象徴田中角栄元総理なら今」と云う問いかけは良い。
その昔なら「諸悪の元凶、金権帝王角栄」式の罵詈雑言で編集されていたであろう。しかしながら、その後の日本が没落し痩せこけた今、角栄ありせばこうはならなかったであろう式の問いかけは十分意味があると思う。ロッキード事件後の日本は、重箱の隅のような正義を掲げるうちに虎の子の本体を傷めてしまった。今ならまだ間に合う。重箱正義のウソを衝き、堂々たる大人の政治論で巻き返さねばならない。以下、れんだいこのカンテラ時評677を書き換える。今も十分通用すると思う。
角栄の「政治は力なり。力は数なり」論が今も歪められて流布している。最近もどこの週刊誌か忘れたが、「政治は数、数は力、力はカネ」なる角栄式政治論批判を目にした。ポストか現代か新潮か文春のどれかの記事だったと思う。今日も「スーパーモーニング」で、このウソが大きくテロップで映し出されていた。
その意味するところは、「政治は力だ、力は数だ、数は金だ」という角栄以来の異常な権力と数と金に対する執念云々と云う口ぶりになる。記者、編集者のお粗末さが分かる。当人はそのように理解しているのだろうが、角栄のその種の発言は寡聞である。れんだいこは、角栄が、後段の「数は金なり」と言ったという話が信じられない。悪質な歪曲造語であろう。批判派の話法がこういう悪質論法によっていることを知る必要がある。
角栄は「政治は力なり。力は数なり」とは言ったと思う。しかし、「政治は力なり。力は数なり」に「力はカネなり」を付け加えると意味が大きく違うことになる。こういう歪曲批判は為にするもので人格識見が疑われよう。角栄批判者は、角栄が言ってもいない言を捏造し「諸悪の元凶角栄論」を幻像化させ批判のボルテージを挙げた。れんだいこが、ここで反論しておく。
角栄政治は専らこうした立花隆−日共流の針小棒大ないしは歪曲批判攻めで、その政治活動の稀有なまでの功績までもがタライごと流され全否定された。裏金に勤しむ検察、その検察が小沢の裏金を突く国策捜査の不正義は不起訴に終わった。しかし検察審査会なるものが登場し、小沢どん潰しに余念がない。その始発がロッキード事件である故に今こそ、事件に嵌められた角栄を歴史的に救済せねばなるまい。のみならず、角栄以降の政治の貧困を思う時、角栄政治を再検証し、好評価すべきところは復権させねばなるまい。角栄政治の見直しこそ、日本政治のカンテラとなるのではなかろうか。
そう云えば、「スーパーモーニング」は角栄著作の日本列島改造論を採り上げていた。その内容の説明たるやお粗末なものであったが採り上げぬよりは断然良い。れんだいこに云わせれば、日本列島改造論は日本政治のバイブルである。これに基づけば世の中が活性化し、人民大衆が政治の恩恵を受け、逆は逆になる。
ロッキード事件後の日本は、そういう角栄政治を葬り、代わりに中曽根政治を敷いた。お陰で日本の国富は国際金融資本に吸い上げられてしまった。当然の如く日本は衰微した。興味深いことは、日本は角栄政治を捨てたが、韓国、中国が代わりに角栄式列島改造論を学び、即ち公共事業型開発を重視し目覚ましい発展を遂げている。本家が捨てたものを隣家が拾うと云う形になっている。
公共事業敵視派の為に付言しておけば、角栄が手掛けた公共事業は殆どすべてお国に役立つものばかりであった。角栄はそれほど大義名分、目的性を重視していた。ミニ角栄になるとこの見識が弱くなり、ニセ角栄となると利権のみに執着し、反角栄派の公共事業となると不必要事業ばかりに精出すことになる。同じ公共事業でも、内実がこれほど違うと云うことが確認されなければならない。だから政治家は何より目利きでなければならない。ましてやシオニスタンではどうにもならない。こう立論するべきところ、日共は率先して公共事業不要論を唱え、これに小泉派が合体し、遂に年次式全国総合開発が終了され今日に至っている。日共は社会保障事業を名分、シオニスタンは軍事防衛を名分にし、共々で社会資本整備開発型公共事業を解体してしまって今日に至っている。これではレースにならない。
もとへ。角栄の「政治は力なり。力は数なり」は、これは一種の思想哲学である。いわゆる民主主義政治が多数決に基づく制度であることをことを見据えた言辞であり、何ら批判されるには及ばない。もしこれを批判するとするなら、君主政治、貴族政治、官僚政治の側に立たない限りできまい。戦後民主主義のシステムは、三権分立制の上で立法権の裁量を高め、立法権を普通選挙で選出される代議員制に委ね、国会を最高の権力機関とした。これによれば、国会は審議、立法の場であり、異論、異端、分派、野党がそれぞれ堂々と認められつつも最終的には、多数決民主主義の下に政権与党が政府を構成し、責任政治を担うことになる。
してみれば、角栄の「政治は力なり。力は数なり」は、戦後民主主義の何たるかを根底で捉えた見事な表現であろう。この当たり前の見地に対し、戦後民主主義を擁護するかの如くの言辞を弄しながら、角栄の「政治は力なり。力は数なり」を批判する芸当はヌエものでしかない。
もっとも、そのままでは批判できないから、こういう手合いは、批判の前に小細工を弄する。言を捻じ曲げ批判し易いように改竄してから叩く。これが、角栄が云ってもない「力はカネ」なる造語の秘密である。こういう連中が殊のほか著作権に煩い習性がある。れんだいこが告げておく。チョサクチョサク云う性根を直せ。論の技こそ磨け。変則技ばかり覚えずに正々堂々と論には論で挑め。
角栄の金権問題で、一言しておく。角栄式金権が案外と清廉潔白なものであったことが知られているだろうか。案外知られていない逸話を伝えておく。角栄は大臣になっても、各省に割り当てられていた交際費(大臣機密費)にビタ一文手をつけなかった。交際費(大臣機密費)とは、省庁ごとに予算金額は違うものの数千万円から億単位くらいまで予算化されており、各省庁の大臣、長官の自由裁量に任されている。官僚が新任大臣の評価の尺度の一つにこの大臣機密費のお手並み拝見があると云われているもので、歴代の大臣、長官の中には公私混同して顰蹙を買った者も少なくない。角栄は、「君達に任せるから、必要があったらこの中でやってくれ」と見向きもしていない(小林吉弥「田中角栄経済学」参照)。
こういう面での角栄の実像を知りたければ、以下のサイトを読むべし。
角栄論
(kakuei/)
田中角栄の思想と政治姿勢、資金源、人脈考
(kakuei/sisosiseico/sisosiseico.htm)
田中角栄と金権政治問題
(kakuei/sisosiseico/kinkenmondaico.htm)