520人が死亡した、日航ジャンボ機墜落事故の機長の娘は、実は今、日本航空の客室乗務員として働いている。事故から、12日で30年。彼女を支えていたのは、ボイスレコーダーに残されていた、父親の音声だった。
【空の安全願う…灯籠流し】
墜落現場がある群馬県上野村で11日夜、遺族たちは、それぞれの思いを灯籠に込めた。事故で娘を亡くした女性「30年娘を失った悲しみは変わりません、本当」。事故で娘2人を亡くした女性「立ち直れたなんてことは一切言えません。いつまでも引きずっていると思います」。あれから30年がたとうとしている。
【日航機墜落事故とは】
1985年8月12日、午後6時56分、上野村の御巣鷹の尾根にジャンボ機、日本航空123便が墜落した。死者520人。単独の航空機事故では世界最悪の事故だった。事故の原因は、客室の気圧を保つためのお椀型の壁「圧力隔壁」だった。ここに穴が空き、吹き出した空気が垂直尾翼などを破壊、制御不能になったのだ。
123便のボイスレコーダー。そこには、コックピットで格闘する機長たちの声が残されていた。機長(墜落32分前)「まずい、何か爆発したぞ」。機長(墜落6分前)「あたま(機首)下げろ、がんばれ、がんばれ」。副操縦士「コントロールがいっぱいです」。声の主は、高濱雅己機長(当時49歳)。高濱機長には、当時高校3年生の長女・洋子さんがいた-。
【長女・洋子さん、客室乗務員に】
事故から30年を前にした先月、私たちは、洋子さんを取材した。選んだ仕事は日本航空の客室乗務員。父と同じ“空の仕事”だった。洋子さんには、初めてのフライトから持ち続けているものがある。高濱洋子さん(48)「JALの飛行機を守ってくれている、そういう思いから持っております」。所々がすり切れた写真。それは、父がコックピットで写る唯一の写真だった。
【苦悩の日々】
自分自身も遺族である一方、“墜落したジャンボ機の機長の娘”という立場。事故当時、洋子さんにとって苦悩の日々が続いた。高濱洋子さん「『519人を殺しておいて、のうのうと生きているな』とか、たくさん電話がかかってきましたので。その度に母は、見知らぬ嫌がらせの電話にもきちんと応対し、『申し訳ございません』『申し訳ございません』、ただそれだけ何回も繰り返しておりました」。“父を探したい”、だが、昼間の遺体安置所には、多くの遺族がいた。そのため、ひと気がなくなる夜を待ってから父を探し歩いたという。しかし、事故から15年後、変化が訪れた。あのボイスレコーダーの音声が公になったのだ。
【ボイスレコーダー、公開】
激しく揺れる機体と最後まで闘った父の記録。機長(墜落27分前)「気合入れろ。ストール(失速)するぞ」。機長(墜落6分前)「がんばれ」。副操縦士「はい」。機長「あたま(機首)下げろ、がんばれ、がんばれ」。副操縦士「コントロールがいっぱいです」。機長(墜落前30秒)「パワー、パワー、フラップ!」。機関士「上げてます!」。機長「あげろ!」。
高濱洋子さん「父は本当に最後まであきらめず、最後の一瞬まであきらめず、頑張ったんですが、本当に無念であっただろう。最後まで父は頑張ったんだなと、誇りに思わなければいけない、そう思いました」。
【遺族に響いた父の声】
ボイスレコーダーに残された父の声。ほかの遺族たちの心にも響いたという。高濱洋子さん「『本当に最後まで頑張ってくれたんだね』『ありがとう』という言葉を、ご遺族から頂いた時には、本当に胸からこみ上げるものがあって…。涙が出る思いでした」「父はボイスレコーダーによって、残された私たち家族を、ボイスレコーダーの音声という形で、私たち家族を守ってくれたと感じました」。取材中、洋子さんが機長の娘だと知る1人の乗客が話しかけてきた。洋子さんの目から涙があふれた。「これからもJALに乗るから、頑張って」。そう声をかけられたという。涙が止まらなかった。事故から12日で30年。洋子さんにとって8月12日とは-。高濱洋子さん「父が残してくれたボイスレコーダーを聞き、新たに、また安全を守っていかなければという、再認識する、そういう一日かなと思います」。以上
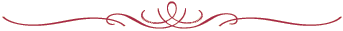
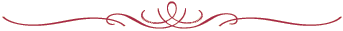
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)