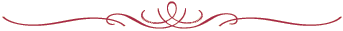
| イエズス会宣教師の日本布教史その2 |
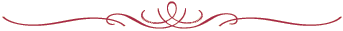
更新日/2018(平成30).4.28日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 2006.11.2日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【鉄砲伝来、宣教師ザビエル来日に纏わる改宗ユダヤ人マラノの介在について】 | ||||
| 1538年、ロヨラの聖イグナチオらが パりでイエズス会を結成し、イエズス会宣教士の世界布教が始まったことは「イエズス会考」で考察した。日本布教の始発は、1549年のイエズス会宣教師ザビエル、トレス、フェルナンデスの鹿児島到着に始まる。これにつき、本サイトで検証する。 イエズス会にネオシオニズムの陰を見て取るならば、即ちイエズス会活動をプレ・ネオシオニズムの動きとしてみれば、伝えられているものより本当の歴史はもっと根深い。1549年のザビエルの来日より6年前の1543年の鉄砲伝来から説き起こさねば真相が見えてこない。「ポルトガル人乗船のシナ・ ンヤンク船が種子島に漂着し、鉄旭伝来」こそが、ネオシオニズムの最初の出来事として記録されるべきではなかろうか。 鉄砲伝来がなぜネオシオニズムと関係するのか、その史実を確認する。鉄砲伝来の様子については、1607(慶長12)年に記録された南浦文之(なんぽぶんし・玄昌ともいう)の「鉄炮記」やフェルナン・メンデス・ピントの「東洋遍歴記」が歴史資料として残されている。記述に若干の違いがあるが、それらを読み取ると次のようになる。 1543年(天文12).8.25日、もしくはその前年もしくはその1年後、いずれにせよ、1543年(天文12)年辺りに種子島へポルトガルの一行がやってきた。暴風雨にあって漂着してきた、もしくは避難してきたとのことであるが、意図的に鉄砲売りつけの商売にやってきた可能性も考えられよう。 この問題につき、2018.4.23日号「週間大衆」の98P、歴史研究家/跡部蛮「日本史ミステリー 鉄砲伝来1543年説は本当か 種子島以外の伝来ルートが浮上」が次のように記している。
いずれにせよ、領主の種子島時堯(ときたか、15歳)は、ポルトガル人フランシスコ・ゼイモトが持っていた火縄銃の鉄砲に注目し、その威力を知り金2000両を投じて2挺を譲り受けた。その後、鉄砲は僅か2年ほどで国産化され、驚くべき速さで当時の戦国大名に伝えられていった。鉄砲は、戦争における主力兵器として活用され、軍事革命を切り開いていくことになったことは周知の通りである。 ここまでは調べれば誰でも分かる。ここから先が問題である。「日本・ユダヤ封印の古代史」、「ユダヤ5000年の智恵」の著者として知られる元日本ユダヤ教団のラビとして知られるマーヴィン・トケイヤー氏は、2006.1.31日初版「ユダヤ製国家日本」(徳間書店)の中で次のように述べている。トケイヤー氏は、日本とユダヤの親密な歴史的繋がりを説く為に記しているのだが、内容は重大である。ピントの活躍に注目し次のように記している。
かく、鉄砲伝来に纏わる改宗ユダヤ人マラノにして貿易商ピントの介在に言及している。 マーヴィン・トケイヤー氏の「ユダヤ製国家日本」の次のくだりも注目に値する。
マーヴィン・トケイヤー氏は、日ユ親和論の証拠例として、ピントの活躍を縷々語っているのだが、企図してかどうかは不明であるが重要な情報を開示している。その1、16世紀以降、改宗ユダヤ人マラノがポルトガル人、スペイン人、イギリス人、オランダ人と混じって貿易商として活躍し始めたこと。その2、イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルの来日を手とり足とり手引きしたのが改宗ユダヤ人マラノのピントであったこと。マーヴィン・トケイヤー氏の言に従うと、以上のようになる。まずこのことを確認しておきたい。 2006.2.4日 れんだいこ拝 |
| 【鉄砲の波状伝来の可能性について】 | ||
2006.11.2日付毎日新聞文化蘭で、伊藤和史氏が、「鉄砲伝来に新説 『種子島から全国に伝播』の定説を否定」の見出しで、次のように指摘している。
|
| 【藤田達生教授の鉄砲伝来論】 | ||||||||||||||||||||||
2022.6.7日、藤田 達生「なぜ150年続いた戦国時代は終わったのか…尾張の小さな戦国大名・織田信長が「天下人」になれた本当の理由」を転載しておく。
|
| 【イエズス会宣教師の日本布教史】 | |
| 当初インドに布教にやって来た聖フランシスコ・ザビエルはその地の布教状況に絶望し、その目は新天地に向けられるようになった。その頃、マラッカで薩摩の武士アンジロー(又はヤジロー)達と出会うこととなる。日本の状況を彼らに聞いたザビエルは日本布教を決意する。
アンジロー達3人の日本人が洗礼を受け最初の日本人キリスト教徒となる。アンジローはポルトガル語を習得していたため、教理書などの日本語への翻訳にあたった。インド布教に使われていた小カテキスモや、マタイ福音書なども邦訳されたようである。アンジローは元々真言宗だったらしく、訳に際して仏教用語を多く使っている。Deusを大日、Paradisoを極楽、Animaを魂、と言ったように。ザビエルは、日本で指導的立場に立てるように、とアンジロー達に徹底的にキリスト教の教えをたたき込む。イグナチウス・ロヨラ著「霊操」に基づく「心霊修行」まで受けさせている。
1549(天文18).8.15日、聖母被昇天の祝日にして鉄砲伝来の6年後のこの日、イエズス会の宣教師聖フランシスコ・ザビエルが、日本人ヤジロウの案内で二人のイエズス会士(コスメ・デ・ドーレス司祭とジョアオ・フェルナンデス修道士)と共に薩摩(鹿児島)へ上陸した。ヤジロウとは、マーヴィン・トケイヤー氏がピントの活躍紹介のくだりでアンジロウとして述べている人物のことだと思われる。こうなると、ザビエルに引き合わせたのも、薩摩(鹿児島)上陸を手引きしたのもピントと云うことになり、ザビエル来日の背後にはピント勢力の意向があった、ということになろう。 ここにイエズス会の宣教が始まる。ザビエルの足取りに就いては、「来日宣教師列伝」で考察した。ここでは、案外知られていない「イエズス会の宣教と国内の主要事件関わり」について憶測も含めて言及してみたい。 宇野正美氏は、「戦後50年、日本の死角」(光文社、1995.1.30日初版)の10章「新たなる歴史と民族の発見」で、次のように述べている。
この指摘は鋭いように思われる。 イエズス会宣教師の日本布教史の概略の流れは「関連年表」、「来日宣教師列伝」、「キリシタン大名の実態考」で個別に行うとして、ここでは政治的事件のみを抽出する。 9.29日、ザビエルは、薩摩藩主(鹿児島)の島津貴久(しまづ たかひさ)に謁見し、宣教のための許可を求めた。ポルトガルとの貿易を望んでいた貴久は、その願いに快く許可を与えた。同時に、小さな家をも貸し与えた。ザビエルは、日本語を上手に話すことができれば、多くの人たちがキリスト教徒になるだろうと考え、宣教師たちに日本語を学ぶようにすすめている。 ザビエルたちの布教に感銘を受け洗礼を受ける人たちがあらわれた。そのひとりに「ベルナルド」という洗礼名を受けた青年がいた。彼は、ザビエルの忠実な同伴者となった。「ベルナルド」平戸、山口、都へと旅をともにし、1551年、ザビエルと共にインドへ赴き、さらにヨーロッパに渡り、 1553年イエズス会に入会し、日本人の最初のイエズス会司祭となっている。その後、ポルトガルで勉強を続けていたが、1557年、道なかばで病気のために亡くなっている。ザビエルが鹿児島に滞在した1年の間に約100人が洗礼を受け、信徒となつている。 ザビエルは、日本の諸宗教を知るために、寺々を訪問し、僧侶たちと話している。そのなかのひとつ、曹洞宗 福昌寺(そうとうしゅう ふくしょうじ)をたびたび訪ね、東堂(とうどう・前住職)の忍室(にんじつ)と親しく話し合つている。しかし、しだいに仏僧たちの反感が強くなり、キリスト教の禁令を、領主貴久に要求した。貴久は、貿易のことを考え、躊躇(ちゅうちょ)していたが、1550年7月、フランシスコ・ペレイラ・デ・ミランダを船長とするポルトガル船が、鹿児島ではなく平戸に停泊したことを契機に、キリスト教の禁止に踏み切った。活動できなくなったザビエルは、祈りのうちに、ヤジロウの助けで、教理の本を日本語に翻訳したりしていた。はじめから日本の都である京都を目指していたザビエルは、この機会にそれを実行することにした。 1550.8月8、ザビエル一行は平戸へ向かった。領主松浦隆信(まつうら たかのぶ)に謁見し、宣教の許可を得た。彼らは、隆信の家臣の木村という武士の家に滞在した。 ザビエルとフェルナンデスは、鹿児島でつくった簡単な教理の本を使って宣教を開始した。木村家は家族全員が洗礼に導かれた。この木村の孫にあたる木村セバスティアンは、最初の邦人司祭として長崎で叙階され、1622年9月10日、長崎の西坂で火あぶりによって殉教している。彼の従弟レオナルドもイエズス会に入り、1619年11月18日、長崎で殉教。甥の木村アントニオは、1619年11月26日、長崎で斬首され殉教している。この3人は日本205福者殉教者にあげられている。ザビエルたちは2カ月の間平戸に滞在し、100人くらいの人びとに洗礼を授け、彼らをトルレ神父スに任せて、都へ向かうため当時西の京と目されていた山口に向けて旅立った。 当時、山口は、日本で一番栄えている町のひとつで、大友文化といわれる京風の文化が花開いていた。ザビエルが訪れたときの領主は、最も有力な守護大名のひとりの大内義隆(おおうち よしたか)で、彼は学問や芸術の保護を奨励し、各方面のすぐれた学者や僧侶を招いていた。ここでも、ザビエルはフェルナンデスを伴い、宣教を行った。しかし、山口で受洗した人はわずかだった。 1550年12月、ザビエルは、フェルナンデスとベルナルドを伴い都に向かった。山口から岩国までは徒歩で、岩国から堺までは船の旅となった。この旅は、冬の厳しい寒さと、食物の不足、それにあわせて一部の人たちの不親切のために大変苦しいものとなった。堺では、後に教会の柱となる商人 日比屋(ひびや)を訪れ、歓迎された。 1551年1月、ザビエルたちは平戸、博多、周防(山口)を経て京都へ上り、小西の家に都の宿を得た。小西家の長男 立佐(隆佐)は、それから8年後の1560年、洗礼を受けた。彼は、キリシタン大名として名高い 小西行長(こにし ゆきなが)の父である。そのころ京都は、11年にわたる応仁(おうにん)の乱ですっかり荒廃していた。後奈良天皇は力がなく、幕府の権威は地に堕ち、将軍 足利義輝(あしかが よしてる)は、近江に逃れていた。ザビエルは、内裏から日本全国で宣教する許可をもらい、都に聖母マリアを保護者とする教会を建てたいと望んでいた。しかし、「日本国王」としての天皇との謁見も、宣教も許されず、比叡山に入ることもできなかった。ザビエルは滞在わずか11日で失意のうちに都を去り平戸にもどつた。 1551年4月、ザビエルはフェルナンデスやベルナルド、もう1人の日本人キリシタンを伴い、ふたたび山口に入り宣教を試みた。先回のような貧しい姿ではなく、盛装してインドの副王使節として領主に謁見した。その際、ザビエルは、天皇に献呈するはずだったインドの副王と、ゴア司教の信任状と贈り物を大内義隆に差し出した。義隆が返礼にと用意した贈り物を辞退し、ただ福音の宣教を行うことの許しを願った。義隆は喜んで許可を与え、無人の寺を住居として提供した。宣教をはじめたザビエルは、ひとりの目の不自由な琵琶法師に洗礼を授けた。彼は、ロレンソと呼ばれ、イエズス会の最初の日本人入会者となり、説教師として多くの人に福音を伝えた。山口では、ザビエルが滞在した4カ月の間に約500人が洗礼を受けている。このころザビエルは、神を表すために用いてきた真言宗の「大日」を、ラテン語の「デウス」に改めている。これは、多くの各宗派の仏僧たちとの論争により得た成果だった。
|
|
| ザビエルと共に来日し、シャヴィエルが去ってからはコスメ・デ・トルレス神父が後を継ぎ布教長となつた。彼はシャヴィエルの精神を受け継ぎ、日本布教に際して日本に順応する適応主義の姿勢で臨んだ。すなわち、日本人と同じものを食べ、同じものを着、同じ所で眠る。また日本を知るため彼らは相当研究していたようだ。日本文学(平家物語など)がキリシタンによって写本されていたりしている。神儒仏の三教、特に仏教の研究にも熱心であり、仏僧との討論などもよく行われていた。「日本布教の際には、ローマの教会法の適用を待ってくれ」という内容の書簡がローマ宛に送つている。 | |
| そしてヴァリニャーノ神父に受け継がれていった。 | |
| 1552年、ガーゴ神父が府内に到着。 1556年、イ ンド副管区長・ヌーネス・バレトが日本視察のためガスパ ル・ヴィレラ神父を伴い府内に到着。 1559年、ヴィレラが、京都で宣教を開始している。総勢何名か不明であるが、かなりのイエズス会宣教師が来日していたと思われる。 1560年、将軍足利義輝、ヴィレラに 布教許可状を交付している。この間、豊後の大友義鎮(後の宗麟)が宣教師との交流に熱心となり、続いて、 1563年、肥前の領主・大村純忠、大和沢城主・高山厨書、1564年、その息子高山右近がイエズス会の洗礼を受けたキリシタンとなっている。 1563(永禄6)年、日本最初のキリシタン大名となった大村純忠の領内教化政策に対し、内紛が発生していることである。寺社勢力がこれを後押ししており、早くも寺社対イエズス会の抗争が始まっている。 1565年、13代足利将軍・義輝が暗殺されている。松永久秀と三好三人衆のクーデターによって居城であった二条御所が襲撃され、衆寡敵せず、最後は三好勢によって殺害された。この将軍暗殺事件との絡みは不明であるが、この年、勅命 「大うすはらい」によりヴィレラ、フロイス神父らが京都から追放されている。 1560年代に入ると、ポルトガルやスペインとの貿易による利益に着目する大名や、キリスト教の教えを封建体勢の強化につなげようとする大名も現れ、保護を受けたり、また大名自ら受洗する者も出てきた。こうなると、信者が増えるのは速い。大名が受洗すれば、おのずと臣下の者達や領民の改宗が進むこととなる。これまで10~100の単位でしか増えなかった信者が、あっさり1000や10000の単位で増えるのである。各地に教会、病院、神学校も建てられ、キリシタンは急速に増えていった。宣教師達は布教に際して、自然科学の講義から始める事があった。世の中の理を説き、そこからでうすの存在を証明するのである。自然科学が発達していなかった日本では、この方法は有効であった。また神学校などでは、仏僧との対決に備えて討論の練習が必須であった。 信者が増えるにつれて、洗礼や教会の儀礼を行う神父や修道士が不足した。そこで、日本人の平信徒に、洗礼を授けたり、ミサを行ったりする権限が与えていった。この体制が、潜伏時代になっても信仰を維持させる事につながった。 1570(元亀元)年、この頃、イエズス会上長カブラルと オルガンティーノが来日している。前上長トレス死去。カブラル神父が日本布教の上長となる。彼はシャヴィエル以来の日本適応政策を弱め、貿易による有力大名との結びつきで布教を拡大しようとする。織田信長のおぼえが良かった彼はそれに成功したが、信徒や宣教師達からの評判は良くなかった。それでも布教体制は整っていった。 1579年、巡察使ヴァリニャーノの来日によって、日本での布教体制は確立する。彼は日本適応政策を再び推進し、布教体制を整えていった。日本を独立した布教管区とすること、ローマとの通信体制の整備、布教費用の確保など次々と押し進めた。以下、長崎開港、堺港開港、本能寺の変、千利休切腹。 1582年、ヴァリニャーノは天正遣欧少年使節を引き連れ、ローマに向かった。折しもこの年、本能寺の変が起こり、キリシタン教界の保護者・織田信長が非業の死を遂げる。しかし、しばらくはキリシタン教界は、布教拡大政策と適応主義がはまり、順調に信者を増やしつつあった。 |
|
| 1587年、突如豊臣秀吉より、伴天連追放令が出されることとなる。その頃にはキリシタンは二十万人を超えるとも言われている。 |
| 【イエズス会宣教師の利権ないしは植民地化エージェント活動考】 | |||||
| TORA 氏は、「阿修羅空耳の丘42」の2006.1.27日付投稿「日本の歴史教科書はキリシタンが日本の娘を50万人も海外に奴隷として売った事は教えないのはなぜか?」で、当時の宣教師達の利権ないしは植民地化エージェントの動きを次のように伝えている。出典は、「日本宣教論序説(16) 2005年4月 日本のためのとりなし」のようである。これを参照する。 「ザビエルがゴアのアントニオ・ゴメス神父に宛てた手紙」が残されており、次のように書かれている。
これを踏まえて、次のように述べている。
イエズス会のドン・ロゴリゴとフランシスコ会の宣教師フライ・ルイス・ソテロらが、スペイン国王に送った上書は次のように記している。
この書翰(しょかん)により判明することは、キリシタン・バテレンたちの正体が対日諜報員であり、対日工作員であったということである。対日侵略は、初期の武力占拠を断念し、諸藩を貿易の利潤で誘い、キリシタンの布教を公許させる持久戦方策に転換していくことになる。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)