
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).2.18日
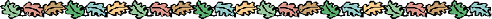
これより以前は、「日本囲碁史考、古代から奈良朝の囲碁」。
| 【平安文学に於ける囲碁記述】 |
| 794年、桓武天皇の京都・平安京遷都により平安時代が始まり、1192年、源頼朝による鎌倉幕府の創設まで続く。平安前期に「日本後紀」、「続日本後紀」、「文徳実録」などに囲碁の記事が多く見られる。平安後期にもなると紫式部の源氏物語、清少納言の随筆・枕草子が囲碁の専門用語を使いこなしており、碁を知っていなければ書けぬ情景描写をしている。紀貫之らが纏めた古今和歌集、今昔物語などにも文学中囲碁の描写が隋所に登場する。これらの文学書から、当時の宮廷を中心にした貴族社会では囲碁が非常に好まれていたことがわかる。恐らく、上級社会にあって暇つぶしのうちの最も高等な遊技として愛好されたものと思われる。 |
| 【補足、紫式部の「源氏物語」の囲碁場面】 |
| 平安時代に紫式部が世界に誇る長編恋愛小説「源氏物語」を著している。世に出たのは1008(寛弘5)年、完成したのは1022(治安元)年と云われる。小説の中に囲碁術語や囲碁用語がふんだんに登場している。囲碁の対局風景の描写から、紫式部が囲碁の手段に通暁しており、また、その造詣の深さと的確な表現からしても、今日でいう有段者、それ以上の実力を有していたと思われる。源氏物語54四帖の中に囲碁の話が随所に記され、囲碁を打つヒロインが何人も登場している。かの貴族社会に於いて囲碁が女性の間にも盛んになって流行していた様子が活写されている。 |
|
|
| 【源氏物語の囲碁描写】 |
源氏物語の囲碁描写で最も有名なくだりは、物語の前半での「空蝉」(うつせみ)の帖での「空蝉(うつせみ)と軒端の萩の対局シーン」の描写である。別の帖でも「打ちさして(打ち掛けて)」、
「手直し(手直り)」、「先指させ(先番で打たせる)」など、かなりの対局経験がないと使えない囲碁用語が出てくる。これらのきわめて具体的な描写から察して紫式部が相当の棋力を持っていたことが窺われる。
「空蝉」(うつせみ)の帖での描写は次の通り。夏の蒸し暑い夜、人妻である空蝉の邸に光源氏が忍んで行く。年増の空蝉(うつせみ)と継娘(義理の娘)の軒端の荻(のきばのおぎ)と云う若い女が、屏風をたたみ、几帳を押しのけて、灯火を近かじかと引き寄せ、盤に向かい合って囲碁に興じている。白い薄物の重ねに、ふた藍の小*を無造作にひっかけた軒端の萩の、肉づきのいい胸をはだけた姿が艶やかな情緒を醸し出している。その対局姿を、17歳の光源氏がみとれている。のぞき見していた光源氏の気配を察した彼女が薄衣を脱ぎ捨て逃げてしまう。あとに残された衣を蟬の抜け殻に例えたのが「空蟬」という帖名の由来となっている。
| 原文「なぞかう暑きにこの格子はおろされぬるととへば、ひるより西の御かたのわたらせ給ひて、碁うたせたまふといふ(中略)碁打ちはてて、けちさすわたり、心疾(と)げに見えて、きわぎわしう騒(そう)どけば、奥の人はいと静かに和(のど)めて、『待ち給へや。
そこは、ぢ(持)にこそあらめ。このわたりの劫(こふ)をこそ』 (など)と言へど、『いで、この度(たび)は負けにけり。隅のところどころ、いでいで(数へん)』と、お指(よび)を屈(かが)めて、『十(とを)、二十
(はた)、三十(みそ)、四十(よそ)』など数える様、伊豫の湯桁(ゆげた)も、たどたどしかるまじう見ゆ」。 |
| 現代訳 「碁があらかた終わり、ヨセの段階に入ったとき、軒端荻(のぎばのおぎ)は心せく様子で、たいそうざわついていたが、奥にいた空蟬はもの静かな調子でやんわりと、『待ってください。そこはセキ(持)ではありませんか。こちらのコウ(劫)のところを打つべきですよ』と言うと、
(軒端は)『そうですね、この度は負けました。隅のあちらこちらの地を数えましょう』と指を折り、『とう、はた、みそ、よそ』などと数える様子は、(数の多いことで有名な)伊予の国(道後温泉)の湯槽を数えるようにたどたどしく見える」
。 |
「十、二十、三十、四十」と地を勘定するくだりが注目される。前段に「隅のところどころをいでいで(数えん)」とあるので、「隅の地を10目ずつ区切って数えやすく作っている」ことが分かる。これを推理すれば、この当時より現代に至る日本式数え方が確立されていたことが分かる。即ち、古代の中国や百済の碁法を採用していないことになる。 |
| 「葵」巻では、源氏と若紫が碁を打っている。「絵合」巻では、源氏が「碁の上手下手というのは天分で決まるものだ」と語っている。 |
「竹河」の帖では、「桜をかけものにして、三番打って勝ち越した方に、この花をあげましょう」と云う一節があり、玉鬘(たまかつら)の姫君姉妹が庭の桜の木を賭けて碁を打っている。蔵人少将が姉妹の対局を垣間見ている。
| 「碁うち給へとさしむかひ給へる。かんざし御ぐしのかかのたるさまども、いと見どころあり。侍従のきみけんぞし給うとて、しじうのおぼへこよなくなりにけり。御ごのけんぞ許されにけるやとて、大人大人しき様してついい給へば、おまへなる人々とかういなをる」。 |
|
「古典と囲碁その10<玉鬘の二人の姫たちの対局ーその4>」。「竹河の巻」では、既に出てきた空蝉と軒端の荻の場合と同様に、二人の姫君が実際に碁を打つ場面が出てくる。即ち、ある春の日の夕暮れ時、玉鬘と今は亡き髭黒の大将との間にできた二人の姫君が打つ碁を、姫君の男兄弟たちが取り巻いてとりとめのない話をする情景と、その後の勝敗、その碁にまつわる男兄弟の回想などが、かなり長きにわたって記述されている。兄弟姉妹うちそろって囲碁という一つの文化を楽しみ、共通の話題とすることができるということは、当時の貴族文化において囲碁が如何に広く愛されていたかがうかがえよう。
| 原文「(少将)あさましきまで恨み嘆けば、この前申しも、あまりたはぶれにくく、いとほしと思ひて、いらへもをさをさせず。かの御碁の見証せし夕暮れのことも言い出でて、『さばかりの夢をだにまた見てしがな。あはれ、何を頼みにて生きたらむ。かう聞こゆることも、残り少なうおぼゆれば、つらきもあはれ、といふことこそまことなりけれ』と、いとまめだちて言ふ。あわれとて、言いやるべきかたなきことなり、かのなぐさめたまはむ御さま、つゆばかりうれしと思ふべきけしきもなければ、げにかの夕暮れの顕証なりけむに、いとどかうあやにくなる心は添いたるならむと、ことわりに思ひて、
(中将)『聞こしめさせたらば、いとどいかにけしからぬ御心なりけりと、うとみきこえたまわむ。心苦しと思ひきこえつる心もうせぬ。いとうしろめ たき御心なりけり』と向ひ火つくれば、(少将)『いでや、さはれや。今は限りの身なれば、もの恐ろしくもあらずなりにたり。さても負けたまひしこそ、いといとほしかりしか。おいらかに召し入れてやは。目くはせたてまつらましかば、こよなからましものを』など言ひて、いでやなぞ数ならぬ身にかなはぬは人に負けじの心なりけり。中将、うち笑ひて、『わりなしや。強きによらむ勝ち負けを心ひとつにいかがまかする』といらふるさへぞつらかりける。
(少将)『あはれとて手をゆるせかし。生き死にを君にまかするわが身とならば』。泣きみ笑ひみかたらひ明かす」。 |
| 現代訳「見苦しいまでに恨み嘆くので、この取次役も、たいして冗談にもできず、お気の毒と思って、返事もなかなかしない。あの碁に立ち会った夕暮のことも言い出して、『あれくらいの夢でも再び見たいものだなあ。ああ、何を頼みにして生きていよう。このように申し上げることも、寿命少なく思われますので、つれない仕打ちも懐かしい、ということは、本当ですね』と、実に真顔になって言う。『お気の毒だと言っても慰めようもないことである。あのお慰め下さるというお話は、少しも嬉しいと思うような様子もないので、なるほど、あの夕暮のはっきりと見えたことに、ますますこのように無闇な思いが募ったのだろう』と、無理もないことに思って、『お耳にあそばしたら、ますますなんとけしからぬお心の人なのだと、お恨み申されましょう。お気の毒だとお思い申していました気持ちもなくなってしまいました。とても油断のできないお方だったのですね』と、反対に文句を言うと、『ええい、どうともなれ。もうおしまいの身だから、何も恐くはなくなってしまった。それにしてもお負けになったことが、実にお気の毒であった。あっさりと招き入れてくれたら。目配せ申したら、絶対に勝ったろうものを』などと言って、『いったい何ということか、物の数でもない身なのにかなえることができないのは負けじ魂だとは』。中将は、吹き出して、『無理なこと、強い方が勝つ勝負事をあなたのお心一つでどうなりましょう』と答えるのさえ、辛いことであった。『かわいそうだと思って、姫君をわたしに許してください。この先の生死はあなた次第のわが身と思われるならば』。泣いたり笑ったりしながら、一晩中語らい明かす」
。 |
|
| 「橋姫」巻では、妻に先立たれた宇治の八の宮が、遺された姉妹と碁を打ったりして育てたとある。 |
| 「椎本」巻では、宇治の邸を訪問した匂宮を八の宮が歓待する遊びのなかに碁も登場する。 |
「宿木」の帖では、今上帝が娘の女二宮と碁を打ち、その後、片懸賞で帝と薫の君による男性同士の対局場面が次のように描写されている。薫が碁に勝ち、帝は懸物の菊の花にことよせて、薫に皇女との結婚を勧める。
| 「今上帝が、亡女御の喪中に姫と碁を打っているところへ薫の君が参内する。帝は『喪中なので管弦の遊びという気にはならないし、退屈をもてあましていた。こんな折の暇つぶしにはこれに限るね』とおっしゃって碁盤を取り寄せ相手をさせる。『今日は勝負にはいい賞品があるのだけれど、それは簡単にはわたせない。さて何がいいのだろう』と姫の縁談をそれとなく打診する。かくて、皇女二宮の婿にと望んでいた中納言である薫の君と三番勝負を打つが、薫の君が二番勝ち越せば姫君を嫁に差し出すという設定で、帝がわざと勝負に負ける。三番勝負で二敗した帝は、『いまいましいな。まあ、今日は賞品としてこの庭の枝一つだけ折ることを許そう』といわれ、薫の君は返事を申しあげないまま庭に下り、風情のある菊の一枝を折って戻った」(結局、この二人は結ばれることになる)。 |
|
| 「東屋」巻では、二条院で右大臣(夕霧)の子息たちが碁を打つ。 |
| 「手習」(てならい)の巻では、宇治十条のヒロインの浮舟がふさぎこんでいるのを少将の尼が慰めようと碁を勧める。浮船は「碁はとても下手なんですよ」と言うものの、打って見ると強く、少将の尼が驚嘆している。尼は先後を変えて打つ。碁が慰めや癒しに利用される例である。その後、ついに出家を果たした浮舟は尼君らと碁を打って気晴らしをしている。自らの業の深さに苦しむ浮舟が、老尼に誘われ碁を打つうちに、自らを取り戻していく過程が心情豊かに描かれている。 |
| 「」巻では、。
|
以下、「幕末本因坊伝【26】日本棋院囲碁殿堂資料館(7)源氏物語の囲碁描写」を参照する。
| 源氏物語五十四帖のうち最後の十帖(これを宇治十帖(うじじゅうじょう)という)をめくると、浮舟の君に係わる箇所で、囲碁に興ずる女性の立居振る舞い、からだのこなしから言葉のやりとりの描写で二人のヒロインを作り上げている。物語の前半に登場する空蝉(うつせみ)の君と宇治十帖の君。二人とも身分低く薄幸な身の上である。空蝉が後家となって嫁ぎ先の義理の娘と碁を打つところを光源氏が物陰から覗き見していた。若い娘の浮舟は顔立ちも華やかであるが、夏のことで胸元をはたけ盤面に熱中していた。対局が終わると甲高い声を張り上げて「地」を数えた。それに比べ、空蝉は容姿こそ老けているものの碁石を盤上に置くと、その指先をそっと袖口に戻す。その上品な振る舞いが光源氏の心をとらえた。勝負事はつい熱中して本性を現すものである。その情景を作者の紫式部が空蝉の内面の美、落ちぶれた身の悲しさ、盛りを過ぎ老いてゆく女心を囲碁の対局によって表現している。心にくいとしかいいようがない。紫式部は、光源氏を通して、女盛りを過ぎたとはいえ空蝉の内面の美や女の心うちを語りつくしているように思える。一方、空蝉とは対照的に若く美しい容姿を持つ浮舟は公卿たちを魅了するものの、田舎育ちで和歌の理解もなく琴も弾けぬ。つまり教養の低い女で若さと美形で公達たちを魅了したものの恋は成就しない。自己主張が強く、気性の激しさもあって入水自殺未遂の末、尼寺に匿われる。浮舟はここで身分も告げず、名前も明かそうとしなかったが、そんな彼女が尼僧に誘われて唯一興じたのが囲碁だった。大変な腕前だった。ここが作者の狙いであったのではなかろうか。平安時代の身分低く薄幸なヒロインが、披露した特技がまさかと思われる囲碁である。これを知って驚いたのは作中に出てくる尼僧だけでない。読者たちもまた、ここで囲碁の名手、浮舟という女性へのイメージを立て直すことになる。そして、作者の紫式部は囲碁を打つ女にどのようなイメージを持っていたのだろうかと思いをめぐらす。見事な筆遣いと云うよりほかない。 |
|
| 【補足、清少納言「枕草紙」の囲碁場面】 |
清少納言「枕草紙」の囲碁描写は次の通りである。清少納言の著した枕草紙を読むと、清少納言は若い貴族と対等に碁が打てたことが良く分かる。枕草紙には4種類の本文系統があり、そのうち堺本が碁の記述が多い。「つれづれをなぐさむるもの。物語、碁、双六(すごろく)」、「遊びわざは小弓、掩韻(えんいん)、碁。さまあしけれど鞠(まり)もをかし」と書いている。(小弓は二十間ほど離れた的に弓を射る遊びを云う。掩韻(えんいん)は古詩の韻字を隠したのを当てる遊びを云う)。
本枕草紙には、経験が豊かで場数を踏んでいる人にしか書けない記述が多くある。これを確認する。
(20段)「」の段。
| 「そのかたおぼめかしからぬ人、二三人ばかり召し出でて、碁石して數を置かせ給はんとて、聞えさせ給ひけんほど、いかにめでたくをかしかりけん」。 |
(堺本113段)「あへなきもの」の段。
| 「がっかりするものとして、碁を打つに、死んだ石をうまそうなふりをして置いていくうちに、まちがって人のは生き、自分のは死んで皆取り上げられた気持」。 |
(133段)「」の段。
| 「そのかたおぼめかしからぬ人、二三人ばかり召し出でて、碁石して數を置かせ給はんとて、聞えさせ給ひけんほど、いかにめでたくをかしかりけん」。 |
(139段)「」の段。
| 「つれづれなぐさむるもの。物語、碁、雙六(すごろく)」。 |
(154段、堺本250段)「碁をやむごとなき人のうつとて」の段。
| 「碁をやんごとなき人の打つとて、紐うち解き、ないがしろなるけしきに拾ひおくに、劣りたる人の、ゐずまひもかしこまりたる氣色に、碁盤よりは少し遠くて、およびつつ、袖の下つまかた手にて、引きやりつつうちたるもをかし」。 |
高貴な地位の人のうち寛いだ様子に対して、身分の下の相手が居住まいも畏まった様子で碁を打っている様子がよく描かれている。
(178段)「"三月晦日"(やよいつごもり)」の段。
| 「『碁盤侍りや、まろもうたんと思ふはいかが、手はゆるし給はんや。頭中將とひとし碁なり。なおぼしわきそ』といふに、『さのみあらば定めなくや』と答へしを」。 |
| 清少納言が、仲の良い藤原道長の従兄弟の藤原斎信(宰相中将)と碁の述語を交えて男女関係のことを語っているところへ、源中将(源宣方・のぶかた)が聞きつけて碁の述語について聞くことで会話に加わろうとする場面。清少納言と源中将のやりとりがおもしろい。源中将が"碁盤はありますか。私も貴方と打ってみたい。手ゆるしてください。宰相の中将さんと私は互先ですよ〟という。言外に"親しい仲になりたい。私は宰相の中将さんに劣らぬ男前ですよ。と、におわせているの。これに対する清少納言の返答がすばらしい。"さのみあらば定めなくや〟(私はそう誰とでもお手合わせするような、定めのないおんなではありません)。これをあとから聞いた宰相の中将は"よくぞ言ってくれました〟と大喜びしたとか。藤原斉信も源宣方も当時を代表するインテリであるが清少納言は一歩も引かない。"手ゆるしてください〟とお願いされるくらいだから、碁も強かったのだろう。 |
枕草子第百八十七段。
| 「心にくきもの。夜いたう更けて、人のみな寝ぬる後に、外のかたにて殿上人など物いふに、奥に碁石、笥に入るる音のあまた聞こえたる、いと心にくし」。 |
(堺本189段)「得意顔なるもの」の段。
| 「碁をうつに、さばかりと知らで、ふくつけきは、又こと所にかがぐりありくに、ことかたより、目もなくして、多くひろひ取りたるも嬉しからじや」。 |
| 「碁を打つときに、相手が完全にそんなことはないだろうと思って殺しておいた石をよく考えて生かし、相手のたくさんある石を殺して取り上げた人の様子もたいそう得意そうである。相手は、意表をつかれた思いで見守って、さあ良し悪しはどうであろうか、といって石を崩してしまったのはただの負けよりは、くやしいであろうと見えた」。 |
(201段、堺本134段)「心にくきもの(奥ゆかしいもの。深みがあるもの)」の段。
| 「夜いたくふけて、御前にもおほとのごもり、(人々みな寝ぬるのち)外のかたに殿上人などのものなどいふ。奥に、碁石の笥に入(いる)る音あまたび聞こゆる、いと心にくし」。 |
| (夜いたう更けて、中宮もおやすみになり、女房達も皆寝て後、外の方で、殿上人などがなにか話をしている。その奥で碁石の箱に入れる音が何度も聞こえるのも大層奥ゆかしい)。 |
「したり顔なるものの段」(この段は版本によって大きく異なる)の段。
| 「碁をうつに、さばかりと知らでふくつけきは、又こと(異)所にかかぐりありくにことかたより目もなくして、多くひろひとりたるもうれしからじや。ほこりかにうちわらひ、ただの勝ちよりはほこりかなり」 |
| (碁を打つとき、相手が不備のあるのを気づかず、欲張って別のところを打っている間に、思いもよらぬ方面から行動を起こして眼形を奪い、ついに本体の大石を仕留めてしまう。こんな勝ちかたはうれしい。誇らしげに高笑いして、地を囲ってただ勝つより、ずうっと誇らしい)(「清少納言の枕草子に見る囲碁用語」参照)。 |
清少納言と紫式部は、出仕した年代が違うので宮中で顔をあわせたことはないようであるが、どちらが碁が強かったかは興味ある話題である。(「アマの知らない囲碁の常識(3)」参照) |
| 【「着袴(ちゃっこ)の儀」と「深曾木(ふかそぎ)の儀」】 |
| 起源は分からないが少なくとも平安朝の頃よりは、宮廷において、皇子が5歳に達した時にその健やかな成長を祈る儀式として「着袴(ちゃっこ)の儀」、「深曾木(ふかそぎ)の儀」に碁盤が使われている。「着袴(ちゃっこ)の儀」は「碁盤の上に乗る」。「深曾木(ふかそぎ)の儀」は「碁盤の上から飛び降りる」。この儀式の意味は、「碁盤を宇宙にみたてて皇子が大地に降り立つ」という祝祭事であり、皇室の代々の儀式として今に伝わっている。これは民間の七五三に当たる行事である。「着袴(ちゃっこ)の儀」では、皇子は落滝津(おちたぎつ)と呼ばれる服と白袴(はかま)を着用し、東宮大夫(とうぐうだいぶ)が袴の紐(ひも)を締め、「碁盤の上に乗る」儀式を行う。初めて袴をきちんと着用することによって、その健やかな成長を祝う儀式と考えられる。続いて、「深曾木(ふかそぎ)の儀」では、皇子は童形服姿(亀甲や菊の柄の衣装を重ね着)に改め、右手に扇、左手に小松二本と山橘(たちばな)の小枝を持ち、足つきの碁盤(高さ約27cm)の上に吉方の南に向かって乗り、御用掛が髪を櫛で揃え、毛の先の三か所を少し切り取る。そして、青色の小石二個を足の指にはさみ、碁盤の上から飛び降りる儀式を行う。この儀式は現在でも続けられており、昭和天皇(当時明仁親王殿下)は昭和13年に、平成天皇(当時浩宮親王殿下)は昭和39年に、秋篠宮悠仁親王殿下は平成23年に経験されている。いずれの場合も事前に日本棋院から碁盤が宮内庁に献上され、それが使用された。 |
|
| 空海(24歳)の戯曲形式の処女作「三教指帰」(797年)が、「儒者が放蕩児の非行を『博エキの様は竹林の七賢人・玩籍をすら超える』と批判する」記述がある。玩籍には「母親の訃報に接して、打ち掛けの掛碁を止めなかった(「晋書」)の逸話がある。 |
| 【碁師/伴宿禰小勝雄(とものすくねおかつお)考】 |
| 伴小勝雄(とものこかつお) |
| 詳細は不詳。平安時代の伝説の人。遣唐使の一員として唐に渡り、天覧試合を行ったが、唐の国手に鎮神頭の妙手を打たれて敗れた、という話の主人公。この話は、日本国王子と唐の国手・顧師言の対局として伝わっている書物もある。鎮神頭の名がついた手順は、中国の古棋書「亡憂清楽集」に記録されているが、これが小勝雄の対局と同じ手であるかは定かではない。 |
804(延暦23)年、碁師の伴宿禰小勝雄(とものすくねおかつお)が遣唐使に加わっている。同行した青年の紀夏井は少勝雄の弟子で、後に師匠を超える碁打ちになる。夏井は菅原道真とも親交があった。道真も碁の漢詩などを作っている。日本三代実録(
901年成立史書)が次のように記している。
| 「碁師・伴宿禰少勝雄」(804年)。 貞観八年九月廿二日、甲子、…夏井兼ねて雑芸を能くし、尤も囲碁を善くす。伴宿禰少勝雄は碁を善くするを以て、延暦の聘唐の日に使員に備へり。碁師を以てなり。嘗て父善岑は美濃守にして、少勝雄は介たり。夏井、時に年十余歳にして囲碁を少勝雄に習ひ、一二年の間に殆ど少勝雄を超す」。 |
本文は後の866(貞観8)年の応天門の変の記録で、事件に連座して土佐に配流された紀夏井の略伝の条(部分)。その中で夏井の少年時代の碁の師匠・伴宿禰少勝雄のことに言及し、伴宿禰少勝雄は碁を善くしたので、碁師として延暦聘唐の使員になったと記す。延暦聘唐之日とは、804(
延暦23)年の遣唐使派遣をいい、大使は藤原葛野麿で、空海や最澄、道真の祖父菅原清公などが入唐した遣唐使団であった。その使員として碁師伴少勝雄がいたとする。延喜式(
年成立)に遣唐使の給禄規定があり、そこには上は大使、副使から末は水手にいたる役名と職種を記載している。芸能の職名には画師・音声生・射手・写字生などを記しているが碁師の語はみえない。この日本三代実録にいう備於使員。以碁師也は、派遣団の正式な使員の外に加えられたものだったのだろうか。なお、伴宿禰少勝雄は生没年を含め事跡は不明だが、史書日本後記続日本後記の記事を拾うと、812年に従五位下、846年には正五位上にのぼっている。(増田忠彦「資料にみえる碁の上手たち(江戸時代以前の碁打たち)」参照)
「坐隠談叢」に「夏井」に関する次の記述がある。
| 「夏井時に年十余歳、囲碁を小勝雄に習い、12年間にしてほとんど小勝雄を超ゆ」、「夏井、姓は紀氏、古佐美の曾孫にして、善峯の第三子なり。幼名を三郎と云い、性質温和、眉目秀麗、丈六尺三寸にして、文藻あり。承和の初め小野たかむらに就いて書を学ぶ。たかむら之を見て曰く、『三郎は実に書の聖なり』と。仁明天皇に仕え、嘉祥3年少内記に挙げられ、文徳天皇に歴任し、斉衛元年美濃少予を兼ね、夏井之を異母兄大枝に譲る。明年、大内記に転じ、従五位下に叙せられ右少弁に遷る。夏井、忠直にして規諫す。文徳帝之を寵賞す。尋で従五位上播磨守となり式部少輔を兼ね、幾ばくもなくして右中尉となり、讃岐守に任じ大いに治績あり。清和天皇貞観7年、肥後守となる。8年、伴善雄の伊豆に流さるるに連座して土佐に流され、尋で配所に於いて卒す。夏井、多芸多能にして書を百済の河成に学びて之を能くし、又薬物を究め、卜*に明にして、幼少より碁を好み、勝雄師として研鑽数年、弱冠にして技その師を超え、当代無双の名手と称せらるるに至れり」。 |
|
| 【補足、仏教説話集「日本霊異記」(にほんりょういき )の囲碁物語】 |
| 822(弘仁13)年頃、日本で最初の仏教説話集「日本霊異記」(にほんりょういき )が編纂される。説話集。三巻112編。景戒編。因果応報の仏教思想に基づいて大和時代の雄略天皇から平安時代の嵯峨天皇の頃までの説話を漢文で著している。日本での仏教普及をすすめた聖徳太子にまつわる話や、大仏建立の頃の行基の話、当時の庶民生活と仏教との関わりなどがリアルに描かれていて、まさに"物語による日本仏教史"ともいえる。各段末に付する訓釈は平安時代の国語資料として重要。正称は日本国現報善悪霊異記。名の通り、"因果応報"(善い行いや悪い行いに対する報い)の例となる話や、"霊験"(仏さまの力が実際にあらわれる)の話など、仏教の教えを判りやすく具体的に示すエピソードが多数おさめられている。ここを起点として後の今昔物語集など、たくさんの仏教説話文学が生まれた。同書に囲碁物語が記されており、僧と一般人が碁で戦い、一般人が僧を嘲ると帰路に頓死する話が登場。逆に僧が碁に負け続けて口が歪み、終生治らなかった話もある。 |
| 【続日本紀の記す仁明天皇御代の囲碁】 |
833(天長10)年、3.15日、続日本紀によれば、碁を好まれた仁明天皇(833-850年)が紫宸殿で群臣に酒を賜った後、囲碁が行われたと記している。
| 「天長十年(833年)3月壬寅、天皇、紫宸殿に御し、群臣に酒を賜う。囲碁の興あり。(後略)」。 |
翌834(承和元)年にも同様の囲碁記述がある。
| 「承和元年(834年)7月*申、これ中旬の初めなり。上(天皇)、紫宸殿に御し、侍臣に酒を賜う。すなわち至りて、親王大臣の座を御床下に促し、以って囲碁せしむ。夕暮れて罷(や)む。(後略)」。 |
837(承和3)年3月にも同様の囲碁記述がある。
| 「承和3年(837年)3月*戌、これ中旬の初めなり。天皇、紫宸殿に御し、侍臣に酒を賜う。御床下に至りて、侍臣に座を促し、以って碁を囲み、且つ琵琶を弾(ひ)かしめ、日斜めにして酒を止む。(後略)」。 |
837(承和3)年6月にも同様の囲碁記述がある。
| 「承和3年(837年)6月戌午、天皇、紫宸殿に御し、侍臣に酒を賜い、且つ碁を囲わしむ。天皇炎熱により御靴を脱がせられ、侍臣に勅して同じくまて之を脱がしむ。(後略)」。 |
|
| 【伴の雄堅魚(とものおかつお)と、その子の伴の須賀雄(とものおすかお)の囲碁対局】 |
839(承和6)年10月、天皇が同じく紫宸殿で群臣に酒を賜い、伴の小勝雄(伴雄堅魚、とものおかつお)と、その子の伴須賀雄(とものおすかお)に碁を打たせている。続日本後紀(869
年成立史書)が次のように記している。
| 「承和六年冬十月、己酉朔、天皇は紫宸殿に御し、群臣に酒を賜ふ。散位従五位下伴宿禰雄堅魚、備後権掾正六位上伴宿禰賀雄を御床下に召して、囲碁をせしむ。並びに当時の上手也。[雄堅魚は石を二路に下す。]賭物は新銭廿貫文、一局の賭くるところ四貫。約するところ惣じて五局、[
賀雄、輸四籌、贏一籌、]また遣唐准判官正六位上藤原朝臣貞敏に琵琶を弾ぜしむ。群臣つぶさに酔ひ、禄を賜ふに差あり」。 |
|
| 839(承和6)年、囲碁好きだった仁明天皇が紫宸殿で群臣を饗応した記録。時の碁の上手伴雄堅魚と帰国したばかりの遣唐使碁師の伴須賀雄(菅雄)とを召して囲碁をさせた。賭物には新銭が供され、雄堅魚が二子の碁で、局打ち、結果は須賀雄の敗勝。この日は、遣唐使の准判官・藤原貞敏に琵琶を弾かせ、群臣は酒に酔って禄を賜った云々とある。伴宿禰雄堅魚は、前の美濃介という官職から、前記年の延暦の遣唐使団の碁師伴宿禰少勝雄と同一人と知れる。対局相手の伴須賀雄は同族の縁者であろう。その延暦の遣唐使団から年の時をはさんで、新旧の遣唐使碁師が対局した記録である。囲碁の上手、伴雄堅魚と伴須賀雄の人はともに生没年が不明で、この年の年齢もはっきりしない。史書に見える消息でも、雄堅魚は先の散位従五位下伴宿禰雄堅魚が最後で後は名を見ない。須賀雄は以後も叙位の記事に名を散見するが、元慶年(
)の散位従四位下伴宿禰須賀雄(官職は年に因幡権守、三代実録)が最後で、卒伝を欠いている。ただ、雄堅魚は年も前の遣唐使の碁使だから、須賀雄とは親子ほど違う年配者であったろう。同姓の雄堅魚と須賀雄が親子だとしたら、代にわたって碁師遣唐使として派遣されたことになる。なお、西宮記の方には、遣唐使基師とある。基師の字は万葉集にもみえたが、この場合は明らかに碁師の義で使っているといえる。 |
|
西宮記(970年頃成立古実書、源高明編)が次のように記している。
| 「[恒例第三、十月、旬事、裏書] 承和六年十月一日、例に依り朝座に着す可し。八省院湿に依りて停止す。仍て右大臣、太政官廳に於て政を聴すと云々。了りて、主上南方に御す。皇太子参上す。公卿参入し、殿上に侍る。旬の酒恒の如し。時に、前美乃介伴雄堅魚・唐使基師伴菅雄二人、殿上に召し、銭三百貫を賭け碁を囲む。王卿大夫左右に相分く。魚方勝籌四、雄方勝籌一と云々」。 |
|
844年、前の年につづく伴宿禰雄堅魚と伴須賀雄の御前試合。こちらの方は史書( 続日本後紀)では冬十月庚辰朔、天皇紫宸殿に御し、侍従已上に宴、禄を賜るに差あり、云々とあるが、囲碁を催した記事は欠いている。人の手合割は雄堅魚の二石で、前の記事と変らない。こちらも賭金は貫文で一局に賭ける所也と、前回の局に対して一番勝負とするが、結果は記していない。
蕣庵随筆(1772年頃成立考証随筆、本居宣長編)は次のように記している。
| 「西宮記、承和六年十月旬に、美濃介伴雄堅魚と云人と、遣唐使碁師伴菅雄と云人とを、殿上に召て、銭三百貫を賭にして、碁をうたせさせ玉ひし事見えたり、遣唐使に碁上手を添て、遣はされしと見ゆ」。 |
(増田忠彦「資料にみえる碁の上手たち(江戸時代以前の碁打たち)」参照) |
| 【空海の御遺告】 |
| 835年、空海が死の直前に弟子たちに示した遺訓「御遺告」は、「僧は囲碁双六を停止すべし」と記している。このことは逆に囲碁の隆盛を知らせている。 |
| 【日本の王子】 |
杜陽雑編(唐世紀末成立説話集、東洋文庫玄々碁経集所収訳文による)「日本の王子」。旧唐書(五代後晋の劉年没編史書)「十八下宣宗本紀日本国王子、入朝貢方物、王子善棋、帝令待詔顧師言、與之対手」。冊府元亀(北宋世紀初頭勅命により編纂)に杜陽雑編と同内容が記されている。
「唐の宣帝の時の大中年間( 847-859)に、日本国の王子が来朝し、宝器や音楽を献上した。天子は、さまざまな技芸を行わせ、珍しい御馳走を用意して厚くもてなされたが、王子が囲碁を善くしたので、待詔の顧師言に相手するように命じられた。王子は如楸玉の盤、冷暖玉の石をとり出していうには、わが国の東三万里に集真島があり、島の上に凝霞台があり、台上に手談池があり、その池の中に玉の碁石が産する。手を加えなくても自然に黒白に分かれ、冬は温かく夏は冷たいので、冷暖玉と呼ぶ。また、如楸玉を産する。楸(ひさぎ)の木に似ていて、これを彫って碁盤にするが、清らかに輝き、鏡とすることができるほどであると。
さて師言が対局したが、三十三手目に至っても優劣が決しない。師言は、君命を辱めることを恐れ、手に汗して思いを凝らし、やっと着手した。これを鎮神頭といい、すなわち両シチョウを解決する形(一手で両シチョウを防ぐ手)なのである。王子は、目をみはり身をすくめ、ついに伏して敗れた。鴻臚にむかって、待詔は第何番目の打ち手であられるのかと聞いた。鴻臚(接待の官)はひざまずいて第三でございますと答えた。実は、第一の名人なのであって、王子が第一の方にまみえたいがというので、第三の者にお勝ちになって第二にまみえ、第二の者にお勝ちになって第一にまみえることができます。いきなり第一にまみえたいとおっしゃっても無理ですと答えた。王子は盤をおおって、小国の第一は、ついに大国の第三に及ばないのかとなげいた。現在でも好事者は、この顧師言の鎮神頭図を大事にしている」。
唐の宣宗の大中七年(八五三年)四月、日本の王子が来朝した。宣宗が顧師言に命じて王子と碁を打たせた。顧師言が鎮神頭の手段を読んでいたが、王子は知らず、ついに負けた。王子は旅館に帰り接待役の鴻慮に「師言は国中第何位の人か」と聞いた。鴻慮は、師言が国中第一の名手なのをいつわって第三位だと答えた。王子は「ああ小国の第一位は大国の第三位に及ばざるか」と大いに嘆息したという。
|
2011年8.26日、朱 新林(浙江大学哲学系 助理研究員)「黒白の碁石に古くからの情を思う」が次のように記している。
| 「唐代以降、中国と外国との文化交流の発展に伴い囲碁は日本に伝わった。遣唐使が囲碁を日本に持ち帰ると急速に流行し、数多くの名手が登場したばかりでなく、碁石や碁盤の制作にも技巧が凝らされた。例えば、唐代の宣宗大中二年(848年)に朝貢のため唐に渡った日本の王子がもたらした碁盤は「揫玉」を彫り、碁石は「集真島の手譚池中にある『玉子』を用いたと伝えられる」。 |
唐の宣宗の時(850年頃)日本国の王子が唐に渡りかの地の名人と対局した、という記録で、資料はいずれも中国のもの。三書ともに、日本の王子の入唐と献上の碁器、さらに待詔顧師言と対局したことを記している。興味深い囲碁の史話だが、史実として裏付けるような日本側の記録は見当たらない。 |
| 【日本文徳天皇実録の記す和気貞臣の囲碁記事】 |
和気貞臣(853年没)につき、日本文徳天皇実録(平安期成立史書)が次のように記している。
| 「仁寿三年四月十四日、甲戌。大内記従五位下和気朝臣貞臣卒す。貞臣、字は和仁。播磨守従四位上仲世の第三子なり。…貞臣は人となり聡敏、質朴にして華少し。性は甚だ雷を畏る。小芸に留意せず、ただ囲碁を好む。敵と対し交手するに、日暮れて夜の深むを覚えず」。 |
853年(仁寿3)年に没した和気貞臣の卆伝記録。和気清麻呂の孫で、疱瘡に罹り37歳の若死にであった。省略した文中には、若く老荘を学び秀才・対策の試験にも合格、時の人これを惜しむとあり、嘱望された人物だったようである。祖父の和気清麻呂は、弓削道鏡が宇佐八幡の神託を拠り所に帝位を狙った際(769年)、宇佐に派遣されて神託の虚偽を奏上して道鏡を排斥し、その後も平安の新都造営大夫の重職も果した官人として古代史に名を残す。大日本史の列伝にも、この阿部貞臣の父親・阿部仲世の項をたて、その中で子の貞臣の事蹟として、右日本文徳天皇実録の文を引いている。
江戸末期の稿本爛柯堂棋話に次のような記事がある。
| 「[碁の事、古く見えたる事] 日本史に、和気仲世、年一九にして文章生に挙げらる。性至孝、奉公忠勤、人となり聡敏質朴、意を雑芸に留めず、ただ囲碁を好む。のち大いに学び、研鑽輟まず。麿の子なり」。 |
この和気仲世( 年)は和気貞臣の父親で、1年前の852年に69歳で没している。この父親仲世の方も、日本文徳天皇実録に卆伝を記すが、囲碁にかかわることはみえない。 |
| 【日本三代実録の記す遣唐使碁師伴少勝雄の弟子であった紀夏井の囲碁記事】 |
日本三代実録が次のように記している。
| 「(応天門事件の関係者を処断する条) 貞観八年九月廿二日甲子、…是の日、大納言伴宿禰善男、男の右衛門佐伴宿禰中庸、同謀者紀豊城、伴秋実、伴清縄など五人、応天門を焼くに座し、斬るに当る。詔して死一等を降し、並て之を遠流に処す。善男は伊豆国に、中庸は隠岐国、豊城は安房国、秋実は壱岐島、清縄は佐渡国に配す。相坐して配流する者八人、従五位上行肥後守紀朝臣夏井は土佐国に配す。…夏井は眉目疎朗。身長六尺三寸、性甚だ温仁、稚くして才思あり。…夏井兼ねて雑芸を能くし、尤も囲碁を善くす。伴宿禰少勝雄は奕碁を善くするを以て、延暦の聘唐の日に使員に備へり。碁師を以てなり。嘗て父善岑は美濃守にして、少勝雄は介たり。夏井、時に年十余歳にして囲碁を少勝雄に習ひ、一二年の間に殆ど少勝雄に超たり」。 |
866年、日本三代実録の応天門事件の条、遣唐使碁師伴少勝雄の弟子であった紀夏井の記事。応天門の変は、866(貞観8)年の閏月日に起こった不審火に起因する事変で、その火災のさまは伴大納言絵巻の絵で知られる。引用文は変事の関係者の処断と略伝を記す条。事件は、火災から半年を経た月日に、密告を受けて伴大納言以下の関係者が処断された。
その罪人の略伝を記す条にみえる、紀夏井の少年時代の囲碁の逸話である。父親の紀善岑が美濃守の時、夏井は歳余の少年だった。囲碁の上手伴少勝雄が父の下官の美濃介で、夏井は彼について囲碁を習った。少勝雄は遣唐使の碁使にも選ばれた打ち手だったが、一両年のうちに夏井は師匠を超えた、という。夏井は事件に関与したわけではない。首謀者とされた伴大納言の舎人だった紀豊城が共謀者の人とされ、夏井はその異母兄ということで縁罪をとわれて土佐に流された。蛇足だが、古代の事変には政争謀略の匂いがつきまとう。仁明天皇を継いだ文徳帝は在位4年で急死して、9歳の幼帝清和天皇となる。この幼帝は皇太子のときに政略結婚をさせられて、外戚の祖父・藤原良房が実権を握って政事を行う。応天門事件があったのが閏3月、8月に良房は太政大臣から摂政に就き、その直後の月に密告によって関係者が処断されている。承和の変からつづいた良房の勢力拡大は、この応天門の変で完成し、良房は臣民としては初めて摂政に就いた。嵯峨・仁明のいわゆる親政時代が終って摂関政治の幕明けともなった事件であった。
爛柯堂棋話の「巻一[囲碁伝来、お尋ねの事]」が次のように記している。
| 「五十四代仁明天皇の承和五年、遣唐使あり。大使は藤原常嗣、副使は小野篁なり。伴勝雄という者、善碁を以て唐使の員に充てらる。これ唐の文宗の開成元(三)年に当る。紀夏井、勝雄に囲碁を学ぶ。年十余歳、一、二年の間に勝雄に超えたりという」。 |
同書「巻二[源氏物語、囲碁の事] 」が次のように記している。
| 「源氏物語絵合に、筆をとる道と碁打つことぞ、あやしうたましゐのほど見ゆる… といえり。按ずるに、紫式部深く感ずる事ありて誉めし言なり。あに筆と碁を善くする者の誉れに非ずや。ここに、これを兼ねたる人あり。紀夏井これなり」。 |
|
| 【菅原道眞(すがわらのみちざね)の囲碁の詩・四篇】 |
学問の神様と称されて広く知られている平安時代の貴族、学者、漢詩人にして政治家として右大臣まで昇りつめた菅原道眞(すがわらのみちざね)(845(承和12).6.25日-
903(延喜3).2.25日)が、囲碁愛好家として囲碁の詩・四篇を残している。
900(昌泰3)年、醍醐天皇に奏進された菅原道真の漢詩文集「菅家文草」全12巻(前半6巻に詩を、後半6巻に散文)に上進。(野田藤八、1700(元禄13)年)に記されており、これを確認しておく。かなり愛棋家だったことが分かる。
| 囲碁 |
|
|
| 手談幽静処 |
手談、幽の静まるところ |
手談が幽玄にして静かな中で始まっている |
| 用意興如何 |
意を用いての興如何(いかん)ぞ |
打つ手を考えるのはなんと楽しいことか |
| 下子声偏小 |
子を下すこと声偏(ひと)えに小さく |
碁石を打つ音はとても小さいが |
| 成都勢幾多 |
都を成すこと勢い幾(いく)ばくか多き |
次第に盛り上がり盤上が都の喧騒のようになる |
| 偸閑猶気味 |
閑を偸(ぬす)みてなお気味あり |
こういう碁を閑を偸(ぬす)んで打つのが楽しい |
| 送老不蹉(ダ) |
老を送りて蹉(ダ)ならず |
碁を打っていれば年をとっても退屈しない |
| 若得逢仙客 |
もし仙客に逢うを得ば |
もしかの碁の仙人たちに逢うことができたなら |
| 樵夫定爛カ |
樵夫(きこり)定めて斧の枝を爛(ただら)さん |
私も樵夫(きこり)となってきっと斧の柄を爛らせてしまうだろう |
|
| 【醍醐天皇と囲碁】 |
894(寛平6)年、唐朝の治安が悪化したことも理由の一つとして遣唐使を中止した。
延喜の世、醍醐天皇(885-930)が大変碁を愛好された。当時の碁聖的地位にあった橘良利が囲碁の理論書「碁式」を書き、醍醐天皇に献上している。(醍醐天皇が寛蓮に命じて献上させた云々の記述もある)但し、原本も伝本もない。
平安時代の頃から宮廷の祭祀に囲碁の道具が使われるようになっている。囲碁愛好の醍醐天皇が亡くなった後、承平年間(931-938)には宮廷の「月次祭」という祭祀に囲碁が登場している。 |
| 【古今和歌集の囲碁記述】 |
古今和歌集(こきんわかしゅう)は、平安時代前期の勅撰和歌集。全二十巻。勅撰和歌集として最初に編纂された。略称を古今集(こきんしゅう)という。古今和歌集は仮名で書かれた仮名序と真名序の二つの序文を持つが、仮名序によれば、醍醐天皇の勅命により万葉集に撰ばれなかった古い時代の歌から撰者たちの時代までの和歌を撰んで編纂し、905(延喜5)年4.18日に奏上された。ただし現存する古今和歌集には、延喜5年以降に詠まれた和歌も入れられており、奏覧ののちも内容に手が加えられたと見られ、実際の完成は912(延喜12)年ごろとの説もある。撰者は紀友則、紀貫之、凡河内躬恒、壬生忠岑の4名。序文では友則が筆頭にあげられているが、仮名序の署名が貫之であること、また巻第十六に「紀友則が身まかりにける時によめる」という詞書で貫之と躬恒の歌が載せられていることから、編纂の中心は貫之であり、友則は途上で没したと考えられている。その成立過程については、以下のように仮名序・真名序の双方に記載されている。
歌の中には長歌5首、旋頭歌4首が含まれるが、残りはすべて短歌である。二十巻からなる内容は以下の通りである(定家本による)。その古今和歌集には碁に関する次の句がある。
| 「筑紫(つくし)に侍りける時に、まかり通ひつつ碁うちける人のもとに、京に帰りまうできて、遣(つか)わしける」(紀友則)。 |
|
| 【後撰和歌集の囲碁記述】 |
和歌の勅撰第二集である後撰和歌集(巻第20、賀歌)にも次の和歌が入集している。ほかにも「斧の柄」が詠み込まれた和歌が入集している。
| 院の殿上にてみやの御方より碁盤出ださせ給ひける、こいしけ(碁石笥)のふたに をののえの くちんもしらず 君がよの つきんかぎりは 打心みよ |
|
| 【寛蓮法師物語その1】 |
| 874~?。平安時代に碁聖として讃えられた。「碁式」という日本初の棋書を著し、醍醐天皇に献上したと言われる。 |
寛蓮(かんれん)の醍醐天皇御前での対局が西宮記の「臨時四、宴遊、囲碁」に次のように記されている。
| 「延喜四年九月廿四日、寛蓮を召し、右少弁清貫と碁を囲ましむ、[唐綾四疋、法師勝つ、別に禄あり]」。 |
古今著聞集(1254年成立説話集)の「巻十二[博奕第十八]」にも次のように記されている。
| 「延喜四年九月廿四日、右少弁(藤原)清貫、寛蓮法師をめして、囲碁を打たせられにけり。唐綾四反、懸物には出だされける。寛蓮勝て給りけり。聖代にも、かやうの勝負いましめなかりけるにこそ」。 |
古今著聞集は次のような逸話も記している。
| 「ある日、寛蓮が一条から仁和寺に行こうとして西の大宮にさしかかると、一人の童女が現れて、我が家に立ち寄らせ給えと云う。寛蓮は何とない興味に誘われ、童女に導かれるままに車をやると、土衛門と道祖の大路との辺りに押し立門があった。前庭の樹木、砂などまいて、賎の小家だが清らかに住みなしている。秋のことで、夏の蚊帳がひんやりしてさ侘しいが、それが却って清潔な感じをもたらした。上がると碁盤があり、その上に碁笥、円座がひとつ置かれている。寛蓮がそこに立つと簾(すだれ)の向こうから愛嬌のある若い女の声がした。女の云うには、父は碁を教えてくれたが、十分とは行かないうちに死んだ。お噂を聞いて、一度教えてもらいたいと思いながら、その機を得なかった。幸い近くをお通りになったので、無理を申し上げてお出でを願い、こんな嬉しいことはない、ぜひ一局教えていただきたい。寛蓮も好きな道だから申し出を拒む理由はない。声だけの若い女がどのくらい打つのかと云う興味も湧いて、そこへ座った。女は顔を見せるのは恥かしいと云って、二尺ばかりの白い木を簾のほころびから差し出して、その先で盤に置く石を指し示した。寛蓮は碁笥の石を鳴らし、一人で自分の石とろ、指し示された相手の石を交互に置いて、盤面は進んだ。ところが、何としたことか、相手は滅法強い。寛蓮の石はみな死んで、碁にならなかった。寛蓮は背が寒くなった。これだけの碁を打つ者が、京都にいるとは思えない。顔を見せないのが既に怪しい。化生の者と思い当って、逃げるようにその家を出た。次の日、その家に人をやって調べさせると、病気の女法師が一人いるだけで、その女法師は碁などには無縁の者であった」。 |
故実書「西宮記」(せいきゅうき)に「904(延喜4)年9.24日条、醍醐天皇が右少弁/藤原清貫(きよつら)と法師・寛蓮を召し、賭物を供して碁を打たせて上覧した。寛蓮が勝ち、唐綾(中国渡来の綾織物)四疋を与えられ、別に給与があった」の記述がある。著者・源高明(みなもとのたかあきら、914-982)は醍醐天皇の皇子の一人で、碁聖・寛蓮の名が見える最も古い記録と思われる。一方の古今著聞集の成立は鎌倉初期で、西宮記によった逸話と知れる。寛蓮の相手の藤原清貫は、宇多法皇の信任厚かった参議保則の四男で母は在原業平の女。晩年には延喜式を編纂した智才の人物で、この時は38歳で五位の蔵人であった。この清貫には政事要略に、藤原仲平(藤原時平の弟)と宮中催事駒牽での囲碁対局の記事もある。
平安初期の囲碁の上手・寛蓮は、大和物語、源氏物語その他の文芸に語りつがれている。大和物語(951年頃成立物語集)の「巻二[旅寝の夢]」は次のように記している。
| 「 帝(宇多帝)、おりゐたまひて、またの年の秋、御ぐしおろしたまひて、ところどころ山ぶみしたまひけり。備前の掾にて、橘の良利といひける人、内におはしましける時、殿上にさぶらひける、御ぐしおろしたまひければ、やがて御ともに、かしらおろしてけり。人にも知られたまはで歩きたまひける御ともに、これなむおくれたてまつらでさぶらひける。かかる御歩きしたまふ、いとあしきことなるとて、内より、少将、中将、これかれ、さぶらへとて奉れたまひけれど、たがひつつ歩きたまふ。和泉の国にいたりたまうて、日根といふ所におはします夜あり。いと悲しかりけり。さて、日根といふことを歌によめとおほせごとありければ、この良利大徳、ふるさとのたびねの夢に見えつるは恨みやすらむまたととはねばとありけるに、みな人泣きて、えよまずなりけり。その名をなむ寛蓮大徳といひて、のちまでさぶらひける」。 |
源氏物語(1007年頃成立物語集)の「手習の巻」は次のように記している。
| 「尼上(僧都の妹の尼君)とう帰らせたまはなん。この御碁見せたてまつらむ。かの御碁ぞいと強かりし。僧都の君、はやうよりいみじう好ませたまひて、けしうはあらずと思したりしを、いと碁聖大徳(きせいだいとこ)になりて、さし出でてこそ打たざらめ、御碁には負けじかし、と聞こえたまひしに、つひに僧都なん、二つ負けたまひし。碁聖が碁にはまさらせたまふべきなめり。あないみじ」。 |
浮舟が囲碁を打つ場面。手習は宇治十帖の巻末に近く、源氏はすでに亡く薫の時代。薫と匂宮との愛のはざまに苦しんで、浮舟は宇治川に身を投げた。死にきれずに川岸に気絶した浮舟は、通りかかった横川の僧都に助けられ僧院で養われる。僧都や妹の尼君が留守のある日、尼僧にうながされて浮舟が碁を打つ。浮舟の意外の強さに手を焼いた尼僧は碁聖大徳ほどではないが、腕自慢の僧都を打ち負かした妹の尼君に、浮舟のこの碁を見せたいものだと述懐する。源氏物語には碁聖大徳とあり、寛蓮の名はない。数多くある後世の源語注解書のことごとくが、この碁聖大徳は寛蓮その人だと注解している。 |
| 【寛蓮法師物語その2】 |
913(延喜13)年、平安初期の仁明帝時代の伴の小勝雄(伴雄堅魚、とものおかつお)と、その子の伴須賀雄(とものおすかお)、清和帝時代の紀夏井(きのなつい)らの輩出後、延喜朝(宇多天皇、醍醐天皇の御代)に寛蓮が登場する。「坐隠談叢」が次のように記している。
| 「寛蓮、姓は橘、名は良利。肥前藤津郡大村の人。剃髪して寛蓮と号す。宇多院の殿上法師となり、囲碁に堪能なるを以って、碁勢大徳の称あり。醍醐、村上両朝に歴任して、斯道を鼓吹し、勅撰碁経を撰み、碁式を制定して以って範を後世に垂れる。常に大内に出仕し、醍醐帝に親しく碁技を授く。延喜13年5月5日、勅を奉じて、碁式を編纂して之を献ず。けだし本邦に於いて囲碁に関する著書の嚆矢とす」。 |
913(延喜13)年、碁聖と称され、宇多、醍醐の両天皇に囲碁の師匠として近侍した法師、鹿島市出身の碁師の僧侶・寛蓮が醍醐天皇の勅を奉じて「碁式」(「碁聖式」とも云う)を献じたという。実物は残っていない。口伝が鎌倉時代に僧・玄尊がまとめた「囲碁口伝」の載せられており、冒頭を次のように述べている。
| 「手ひとしき敵とは、常に四方を見て、慎みて誤りを見よ。ただ二、三目の勝負を数えて、多く勝つことを好まざれ」。 |
| (読解/「手ひとしき」手ひとしきとは実力互角。そういう相手と打つときは、常に盤全体に目を配り、誤りがないか慎重に対応するが良い。「二、三目の勝負」の意味は分かりにくいが恐らく、勝負は二、三目勝つのが良くて、たくさん勝とうとしてはいけない) |
| 「我が領域に入って来た石は、必ず取れる確信がなければ取りに行かず、小さく卑屈に生かして先手を取りなさい。相手の領域には深く入らず、浅くそろそろと入るのが良い」。 |
1472(文明4)年、当時の公卿・一条兼良が書き残した「花鳥余情」( 源語注解書)は次のように記している。
| 「備前の掾(ぞう)橘良利(たちばなのよしとし)は肥前国藤津郡大村の人なり。出家して寛蓮と名乗る。亭子院の殿上の法師たり。亭子院の法皇(醍醐帝の父、宇多天皇)が山ぶみし給う時、御ともしけるよし、大和物語にのせ侍(はべ)り。碁の上手なるにより、碁聖と云えり。延喜十三年五月三日、碁聖勅を奉じて、碁式を作りて之を献ず」。 |
肥前国藤津郡大村とは、鹿島市の大村方付近と考えられ、鹿島市行成付近には橘氏との関係を記す「橘園」という地名が残っている。「碁盤直して寛蓮を召す 君が代や女の鬼は碁にありて」と詠む雑俳(川柳)が残されている。寛蓮は史書にも、藤原清貫と御前対局をした記録がある。この上手の名を有名にしたのは大和物語、大鏡、今昔物語集、古今著聞集といった物語の逸話である。また源氏物語の「手習の巻」に語られる碁聖大徳は寛蓮がモデルとされ、これを考証する源氏釈など源氏古注書も多い。
大鏡(1025-1065年成立の歴史物語集)の「上巻十[五十九代、宇多天皇]」は次のように記している。
| 「寛平九年七月五日、おりさせたまふ。昌泰二年己未十月十四日、出家せさせたまふ。御名、金剛覚と申しき。承平元年七月十九日、うせさせたまひぬ、御年六十五。肥前掾橘良利、殿上にさぶらひける、入道して、修業の御供にも、これのみぞつかうまつりける。されば、熊野にても、日根(ひね)といふ所にて、たびねの夢に見えつるはともよむぞかし。人々の涙落すも、ことわりにあはれなることよな」。 |
大和物語は年ごろに成ったとされ、寛蓮の没後間もなくの記事で、宇多院の出家とその後の日常にも近侍していた様子が語られている。近世に編まれた大日本史も右の大和物語の条を引いて寛蓮の名をあげている。また、大和物語の近世の古注解書である大和物語虚静抄大和物語錦繍抄には、寛蓮が碁式を作って天皇に献じたとする考証を載せる。
寛蓮の素生と宇多天皇に近侍したことにつき、東宝記(東寺の結構事跡の記録)が次のように記している。
| 「一、宇多法皇於東寺御授与事延喜八年戊辰(九八年)五月三日、癸酉、[鬼宿、土曜、滅門、]禅定法王、[御年四十三、]於東寺灌頂院令授伝法位法三親王真寂、[法皇御子年廿三、四、]寛蓮、[年卅五、臈九、]会理、(四人の名、略)已上同日伝授、此日寛空入灌頂壇、奉打金剛輪菩薩云々、[已上寛信法務記、略抄之]」。 |
東宝記は東寺(護国寺)の記録。条は宇多法皇が伝法灌頂を授けられた時のもので、本朝伝法灌頂師資相承血脈にもある。寛蓮の名もみえ、908年時点で年卅五とある。院に随って出家したのは899年で、以後も亭止院(宇多法皇)の殿上法師として近侍したとする。
一葉抄( 1495年成立源語注解書)は次のように記している。
| 「河( 河海抄)基勢大徳也。備前掾橘良利は肥前の国藤津郡の大村人也。出家して寛蓮名づく。亭子法皇、山ふみし給ふ時御供しけるよし、大和物語にのせ侍り。碁の上手なるによりて碁聖と云り。延喜十三年五月三日、碁聖奉勅作碁式献之云々」。 |
紹巴抄(1565年成立源語注解書)は次のように記している。
| 「碁聖。肥前橘良利、肥前国藤津郡大村の人也、出家して名寛蓮為亭止院殿上法師。亭子法皇山ふみし給ふ時御ともしけるよし大和物語にのせ侍り。碁の上手なるによりて碁聖といへり。延喜十三年五月五日碁聖勅を奉じ碁式を作り之を献ずと云々。枹朴子曰、碁を囲む者世に之を碁聖と謂、故に厳子卿・馬綏明に碁聖之名有る也。或書曰、唐堯碁を造り其子丹朱に教。一説曰、然らず碁は戦国之時に於て出ると、云々」。 |
広益俗説弁の「附編巻三十三[碁聖大徳が説]」は次のように記している。
| 「俗説云、寛蓮法師は、俗名肥前掾橘良利といふ。肥前国藤津郡大村の人なり。亭子院[宇多天皇]御出家のとき、出家して寛蓮と名づく。殿上法師なり。囲碁をよくす。この故に碁聖と称され、碁式をつくる。是、日本の碁のはじめなり[
万首唐絶句に奕僧とあるは、寛蓮が類なり]。今按ずるに、碁に妙を得たる故に碁聖と称する説、非なり。蓬窓日録(明の書)云、林中朗以囲碁為座隠。或亦謂之手談。又謂之碁聖とあるを見るべし。続日本後記云、承和六年十月朔、天皇御紫宸殿、召散位従五位以下伴宿禰雄堅魚・備後権掾正六位須賀雄於御床下、令囲碁。並当時之上手也[雄堅魚下石二路]賭物新銭廿貫文。局所賭四貫、所約総五局[須賀雄輸四籌。贏一籌]。文徳実録云、大内記従五位下和気朝臣貞臣唯好囲碁。日暮夜深。三代実録云、従五位上肥後守紀朝臣夏井善囲碁。十余歳習囲碁於伴宿禰於勝雄。一二年間殊越于於勝雄とあるを知るべし」。 |
枯杭集( 1668年成立説話集)は次のように記している。
| 「さて、この碁、このくにへ、わたりしは、吉備大臣、遣唐使にわたりて、七宝をつたへて、帰朝したまひしより、あまねく、世にひろまれり、又、中比、備前丞橘良利と、きこえし人、肥前のくに、藤津の住人なり、寛蓮亭子院上法師といふ、碁名人なり、寛平法皇のときの人なり、これを、世間に、碁聖とは、いひならはせるなり」。 |
筆のすさび( 1806年成立考証随筆)(今昔物語集の引用、本文省略)
篠舎漫筆( 1749年成立、考証随筆)の「囲碁上手寛蓮」は次のように記している。
| 「今昔物語廿五に、延喜の御時に、寛蓮といふ碁上手の僧あり。宇多院の殿上法師にて有ければ、内にも常にめして御碁を遊ばしけり云々とあり。是は志貴山の第一の宝蔵物にて、飛鉢といふものあり。その銘に寛蓮とあり。いかなる人かとおもひしを、此人なり。かの銘の年号延喜七年とあり。同じ時代なり。大和物語、著聞集にも出たり」。 |
|
平安時代、醍醐天皇が囲碁が好きで、当時の一番の名手(めいしゅ)であった寛蓮上人(かんれんしょうにん)とよく囲碁をしたとある。先二の手合いであったと云う。ある時、金の枕を賭けた話が伝えられている。村松梢風の「本朝烏鷺(うろ)争飛伝古今碁譚抄」が概略次のように記している。
| 「ある時、寛蓮が醍醐天皇の御前へ出ると、『寛蓮、今日は懸け物をして打とう。2子でもし汝が勝たば金の枕を遣わすぞよ』と、帝が仰せられた。帝は平素寛蓮に対して先と2子の交ぜでお打ちなされたが、2子では決して負けたことがなかった。だから何を賭けても大丈夫だと思し召したのである。『その代わり汝が負けたらば以後は先じゃぞよ』。『畏まりました』。帝は直ぐに2子を置いてお打ちなされた。ところが、どうしたものか今日に限って楽々と寛蓮に勝たれてしまった。『お約束の金の枕を頂きとうございます』。寛蓮は意地の悪い目つきをして申しあげた。帝は今さら後悔遊ばしたが仕方がない。かくて侍臣に命じて御秘蔵の金の枕を取り出させ、残念そうなご様子でそれを寛蓮に賜った。寛蓮は大喜びで重たい金の枕を懐に入れて御所を退った。すると直ぐ後ろから『寛蓮待たれよ』と呼びながら、4、5人の若い殿上人が追いかけて来て、やにわに寛蓮を捕らえて懐から金の枕を奪い取ると、そのまま御所へ引き上げてしまった。その次寛蓮が御前へ出ると、『寛蓮、今日は懸け物をして打とう。2子で汝が勝たば金の枕を遣わす』と、帝はこの前と同じようなことを仰せられた。そしてお打ちなされたが、やはり寛蓮が勝った。寛蓮は約束通り金の枕を頂戴して退いたが、御所を出るや否や又殿上人に奪われてしまった。その後、帝は寛蓮の顔をご覧になるたび『懸け物をしよう』と仰せられる。寛蓮はそのつど碁に勝って金の枕を賜るのであったが、この宝物が御所を出てからものの一丁と彼の身に保っていた例がない。すると或る日のこと、寛蓮は例の通り拝領物をして御所をさがったが、殿上人に追いかけられると何と思ったかいきなり金の枕を路傍の井戸の中へ投げ込んですたすたと立ち去ってしまった。『寛蓮め、腹を立てて手数を掛けさせる気じゃな』。後で殿上人はこう云って笑ったが、井戸に人を入れて取り出させてみると、それは普通の木の枕に金紙を貼った物であった。寛蓮は金の枕を潰して仁和寺の傍に一寺を建立した。それが弥勒寺である」。 |
これにつき、別稿「囲碁落語、囲碁逸話その1」に記す。桑華蒙求(江戸中期成立説話集)の「五九、寛蓮金枕、道古博局」は今昔物語集を引用している。 |
918(延喜18)年、「碁手銭」初見(「西宮記」)。
923(延長)、新嘗祭に囲碁の催しを慣行とする。
935年、承平・天慶の乱始まる。
| 【空也上人伝説】 |
| 972年頃の逸話。空也上人(972年没)が、訪問先で留守番をしていた稚児に対し、「囲碁でも打って慰めてやろうと碁盤を持ってくるように命じるが、重くて稚児は運べない」。上人が数珠を碁盤の上に置かせると、碁盤が歩いて云々の伝説が遺されている。 |
982年、源高明が「西宮記」著す。
| 【三宝絵の囲碁論】 |
| 984年頃の逸話。19歳の尼・尊子内親王に献進した絵入り仏教説話集の三宝絵(984年成立、源為憲著)序文に次のように記されている。「春の日永、秋の長夜の徒然を慰めるもの」として囲碁をあげている。 |
| 【円賀伝説】 |
| 989年頃の逸話。高僧の円賀(989年没)が、関白藤原頼忠亭に招かれ、仏家の奇瑞を望まれ、碁盤の上で独*を躍らせて見せたと記載されている。「元亨釈書」(1322年)、本朝高僧伝(1702年)に載る。 |
1000(長保2)年、囲碁の名手の賀陽宣政あり。翌3年没す。この頃、枕草子が執筆され、うちに囲碁寸評あり。
| 【増賀上人伝説】 |
| 1003年頃の逸話。参議・橘恒平の子で多武峰に住し多武峰先徳とも云われる増賀上人(1003年没)が「名利を嫌い奇行譚を多く残す」。その一つが、「臨終の際、年来の望み通り、碁を打って往生した」との逸話を遺している。 |
| 【因幡堂の碁盤伝説】 |
| 1003年頃の逸話。因幡堂の通称で知られる平等寺の本尊の薬師如来立像が、碁盤の上に鎮座して遠く因幡の国から飛来した伝説を遺している。近世の京案内名所記の類に載り、俳諧や雑俳にも詠まれている。名所記の「京童」(1658年)、「洛陽名所集」(1658年)、「扶桑京華志」(1665年)、「出来斎京土産」(1677年)。「開帳花くらべ」(1773年)、「花洛羽津根」(1863年)。貞徳編の俳諧集「あぶらかす」(1643年)。 |
1005(寛弘2)年頃、小野宮太政大臣「内侍馬が家に、右大将実資がわらわに侍ける時、ごうちにまかりたければ、ものかかぬさうしをかけ物にして侍りけるを見待て。いつしかとあけてみたればはま千鳥跡あるごとにあとのなき哉。返しとじめても何にかはせんはまちどり、ふりぬる跡は波にきえつつ」。(太政大臣は藤原実頼)
1009(寛弘6)年、紫式部日記が執筆される。作中に囲碁の記事多し。
| 播磨守、碁の負けわぞしける日、あからさまにまかで、後にぞ碁盤のさまなど見給へしば、けそくなどゆへゆへしくて、すはまのほとりの水にかきまぜたり云々。(播磨守は藤原行成) |
1010(寛弘7)年、源氏物語が執筆される。作中に囲碁の記事多し。
1016年、藤原道長が摂政になる。
1017年-1045年、68代後一条帝の寛仁年代、「囲碁名手平祐挙あり。光孝天皇の流れ、忠望王の後裔、越前守保衛の子、従四位下駿河守に叙任す」(二中歴に囲碁名手として載録)。
| 【囲碁三昧の僧が焦熱地獄に落つ逸話】 |
|
1040年頃の逸話。「大日本国法華経経験記録」(1040年頃成立)、「今昔物語集」(1120年頃成立)が、「殺盗、淫妄、飲酒になずみ、連日双六、囲碁を欠かさぬ悪僧が、死んで蛇となり焦熱の苦しみを受ける」逸話を載せている。
|
| 【僧正・深覚の囲碁対局の治療で危篤患者が蘇生逸話】 |
|
1043年頃の逸話。「今鏡」(1170年頃成立)、「本朝高僧伝」(1702年成立)が、「深覚僧正が、関白・教通の危篤に参上し、囲碁対局で蘇生させた」逸話を載せている。
|
1049年、70代後冷泉帝の治承4年、祐子内親王家の賀陽宮に歌合せの会を催されることあり、(中略)満座高声興に乗じ感を催し本座に着き、後に碁手料紙を置く云々。
| 【僧・覚念の囲碁大往生逸話】 |
|
1050年頃の逸話。「拾遺往生伝」(1104年年頃成立)、「本朝高僧伝」(1702年成立)、「後拾遺往生伝」(1140年頃成立)が、「天台の僧・覚念が囲碁を愛し、出世は逃したが大往生した」逸話を載せている。
|
1058(康平元)年、狭衣物語に囲碁を打つの記事あり。(作者は後朱雀院皇女に仕えた女房宣旨)
| 【平安末期「後三年の役の囲碁事変」】 |
1062(康平5)年、東北地方で前九年の役と呼ばれる12年間の戦いが起り、清原武則が台頭する。その子の武貞、さらにその嫡子の真衡へと続く。
1084年頃、清原真衡があまりにも囲碁に夢中になり過ぎて、五条の君なる奈良法師と碁を囲み、挨拶に来た一族の吉彦秀武を無視したため怒って帰ったことが原因で「後三年の役」となったと伝えられている。
| この日、成衡の婚礼の際、陸奥の真衡の館に出羽から前九年の役の功労者で清原一族の長老である吉彦秀武が祝いに訪れた。秀武は朱塗りの盆に砂金を盛って頭上に捧げ、甥である真衡の前にやってきたが、真衡は碁に夢中になっており、秀武を無視し続けた。一族の長老としての面目を潰された秀武は大いに怒り、砂金を庭にぶちまけて出羽に帰ってしまった。真衡は秀武の行為を聞いて激怒し、直ちに秀武討伐の軍を起こした。一方の秀武が応戦し後三年の役が起る。まさかの囲碁トラブルで戦争になったことになる。
前九年の役の後、東北地方に覇を唱えていた清原氏が消滅し、奥州藤原氏が登場するきっかけとなった後三年の役で功を認められた源義家は囲碁好きで、屋敷に強盗が入った時も庭で囲碁に夢中だった。
|
|
| 【留学僧の囲碁逸話】 |
|
1073年頃の逸話。天台の僧・成尋の渡僧日記「参天台五台山記」(1073年頃成立)が、「天台の僧・延暦寺阿ジャリにして藤原頼通の護持僧などを務めた成尋が、商船で渡宋した囲碁日記」逸話を載せている。
|
1087年頃、73代堀川帝の寛治年代、源義家、陸奥前司の比、常に堀川右府の許にて囲碁を打ち、或る時、対局中、自ら声をかけて犯人を捕う。(「十訓抄」)
| 【達磨の囲碁逸話】 |
|
1100年頃の逸話。「今昔物語集」(1120年頃成立)、「宝物集」(1190年頃成立)、「宇治拾遺物語」(1200年頃成立)その他に、「天竺のダルマが囲碁を愛した」という逸話を載せている。
|
| 【僧・増誉が囲碁対局で重患を放置逸話】 |
|
1116年頃の逸話。「本朝高僧伝」(1702年成立)、「囲碁事蹟部類ショウ」(江戸末期成立)に、「藤原経輔の子の僧・増誉が、白河法皇の信を得て円城寺僧正から延暦寺座主を務めた。囲碁対局中に急患の幼児が来たが、対局が終わるまで放置し、対局後に『不発不発』と揺すり、子の*が治った」という逸話を載せている。
|
1124年頃、75代崇後帝の天治元年、「今昔、多武の峰に増賀上人と云う人ありけり。(中略)而る間、聖人既に入滅の日に成りて、弟子等に告げて曰く、我が死なむこと今日なり。但し碁*取りて来れと云ひければ、傍らの房にある碁*取りて来ぬ。(中略)碁杯に向かひて竜門の聖人を呼びて碁一*打たむと云々。(「今昔物語」)
1124年頃、75代崇後帝の天治元年、かの僧正(禅林寺深覚)大二条殿(藤原教道)の限りにおはしましけるにまいり給て、囲碁打たせ給へと申し給いければ、(中略)碁盤取り寄せ、かきおこされたまひて打たせ給いけれるほどに云々。(「今鏡」)
| 【天王寺冠者と長如来】 |
散木奇歌集(1125年頃成立の源俊頼の私歌集)に次の歌が詠まれている。
| 「(長如来といふごうちのごをうつをみて) 隆源阿闍梨 長如来ごをりやくともしけるかな (つく)天王寺なる凡夫にはまく」。 |
上の歌は、連歌付合のなかにある。詠み手の隆源阿闍梨は生没年は不詳だが藤原通宗の次男で隆源口伝の著がある歌学者。碁打の長如来は不詳。 |
| 【後白河天皇の囲碁愛好】 |
| 後白河天皇(1127(大治2).9.11日-1192(建久3).3.13日。在位は1155(久寿2).7.24日-1158(保元3).8.11日)が歴代天皇の中でも最強の棋力を持つとされている。平清盛との連携を重視したことこそ先見性に優れ、ビジョンを描いていた証と見る研究者がいる。 |
|
| 【鳥羽僧正の囲碁愛好】 |
| 1140年頃の逸話。「宇治拾遺物語」(1200年頃成立)に絵描きの大僧正・覚猷(鳥羽僧正)の逸話を載せている。僧正は、藁を浮かべた湯舟に飛び込む癖があった。甥子がいたずらをして湯舟の底に碁盤の足を上にして入れておいた。そこへ帰宅した僧正が飛び込み、碁盤の足に尾てい骨を打ちつけて気絶した云々。 |
| 【大坂に碁盤だけを作る家を7戸限定で認可する】 |
| 1141(天養元)年、鳥羽法皇の御代、大坂で碁盤だけを作る家ができ、7戸に限定され、これを仲間株と称して他には製作を許さなかったと云う。この制度は1155年まで続いた云々。 |
| 1142(天養2).2月、朝廷の列見式目で盃酌後に囲碁を催している。著聞集が「このこと絶えて久しく成りてけるに、めづらしけることなり」と記している。 |
| 【尾張兼忠、惟宗盛言対局】 |
1144(天養4)年、「台記」。
| 「8月4日*未、西京雑記、意に依りて尾張兼忠、惟宗、盛言に遣い侍らし、実長の家の北戸竹下に於いて、碁を囲わしむ。(二*)兼忠共予(頼長)勝平常兼忠負云々」。 |
|
| 【】 |
| 1145(久安元)年、「元年、2月11日、列見式日に行われけるに、宇治左府(頼長)内大臣にて参り給いて事々興し行われけり。朝所にて盃酌の後、囲碁あり。旧規に依る也。朝隆、成、能忠等二双つかうまつりける云々。」(「百錬抄」、「古今著聞集」)。 |
| 【鳥獣戯画囲碁絵】 |
| 平安期の画僧/鳥羽僧正の作と伝えられる「鳥獣戯画」大三巻に囲碁対局絵がある。構図も筆致もなかなかの出来栄えになっている。 |
| 【今鏡の関白藤原教通の囲碁治癒譚】 |
歴史物語「今鏡」(いまかがみ)は10巻。成立は、序文によれば高倉天皇の1170(嘉応2)年とされるが、それ以降とする説もある。作者は藤原為経(寂超)とするのがほぼ定説になっている。ほかに、中山忠親、源通親説もある。「今鏡」は「大鏡」の続きであるという意味で「続世継」(しょくよつぎ)とも「小鏡」(こかがみ)とも呼ばれる。いわゆる「四鏡」の成立順では二番目に位置する。内容的には「大鏡」の延長線上に位置し3番目に古い時代を扱う。なお、描く年代が4番目の「増鏡」との間には13年間の空白があり、藤原隆信(寂超在俗の子)の著である歴史物語「弥世継」(いやよつぎ、現存しない)がその時代を扱っていたためとされる。「今鏡」は「大鏡」の後を受けて後一条天皇の1025(万寿2)年から高倉天皇のまでの13代146年間の歴史を紀伝体で描いている。長谷寺参りの途中で大宅世継の孫で、かつては「あやめ」という名で紫式部に仕えた、150歳を超えた老婆から聞いた話を記したという形式を採る。はじめの3巻は帝紀、中の5巻は列伝、終わりの2巻は貴族社会の故実・逸話に割かれる。列伝のうち、巻四~六は藤原摂関家、巻七は村上源氏、巻八は親王である。各巻の巻名は、1.すべらぎの上、2.すべらぎの中、3.すべらぎの下、4.ふぢなみの上、5.ふぢなみの中、6.ふぢなみの下、7.村上の源氏、8.御子たち、9.昔がたり、10.打聞。王朝末期から中世への過渡期において政治的・社会的大きな変動があったにもかかわらず、政治への関心は薄く、儀式典礼や風流韻事など学問・芸能に重点を置く記述を貫いている。その一方で記述は歴史的事実に対して比較的忠実である。また、当時の物語に対する批判(「源氏物語」を書いた紫式部が妄語戒によって地獄に堕ちたとする風説)に老婆が反論する場面が盛り込まれるなど、仏教戒律を重んじて極楽往生を願うという当時の社会風潮が物語としての創作性を抑制したとする見方もある。
「もののけの日本史」(中公新書)によると、歴史物語「今鏡」に関白/藤原教通が危篤に陥った時の囲碁話が記されている。それによると、深覚僧正が招かれ、祈祷するかと思いきや、よほど囲碁好きなことを知ってと思われるが、教通に「囲碁を打ちなさい」と申し上げ、余りに熱心に進めるので「わけがあるのだろう」と思い、起こされながら打つうちに腹の膨れが治り、一局終る頃には治癒していた云々。 |
1156年、保元の乱。
1168年、79代六条帝仁安3年、「五月十一日、徒然により冠者と囲碁の戯れを成し云々」。(「愚昧記」)
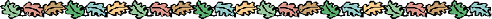



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)