
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3).7.24日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
ここで「日本囲碁史考5、徳川家康時代」として徳川家康時代の囲碁史を確認しておく。
2005.4.28日 囲碁吉拝 |
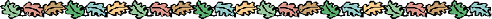
| 【朝鮮から撤兵】 |
| 1598年、豊臣家の家督は秀頼が継ぎ、五大老や五奉行がこれを補佐する体制が合意されている。また、五大老や五奉行によって朝鮮からの撤兵が決定された。当時、日本軍は、攻撃してきた明・朝鮮軍に第二次蔚山城の戦い、泗川の戦い、順天城の戦いなどで勝利していたが、撤退命令が伝えられると明軍と和議を結び、全軍朝鮮から撤退した。秀吉の死は秘密にされたままであったが、その死は徐々に世間の知るところとなった。朝鮮半島での戦闘は、朝鮮の国土と軍民に大きな被害をもたらした。また、明は莫大な戦費の負担と兵員の損耗によって疲弊し、後に滅亡する一因となった。日本でも、征服軍の中心であった西国大名達が消耗し、秀吉没後の豊臣政権内部の対立の激化を招くことになる。
|
| 【本因坊、利玄】 |
1599(慶長4)年、舜旧記。
| 「二月十一日、天晴る。栖松院・松楽庵、両人朝食に来る。次いで楽人備前来る。予色紙[三十六枚]持参す。次いで幽斉より[杉原十帖・三十疋、]年頭為礼来。次いで本因坊より[扇二本]来る」。 |
本因坊が吉田社に年礼する記録。
北野社家日記(北野八幡宮宮司記録)。
| 「三月廿日、天気快晴。今日当坊へ利玄来られ、碁これ有り。碁を利玄持参す。その外本能寺衆四五人来らる。当坊碁を三ツに手を直され候也」。 |
| 「閏三月十七日、天気快晴、晩少雨降る。今日利玄坊にて碁会これあり、本因坊も御出也。見物に参る」。 |
| 「七月廿九日、今夜大雨、今日も降る。内府様(徳川家康)へ御礼に[内衆、初尾五十疋]参る。百疋・かき一折持参す。…内府様に碁これあり、見物仕る。本任坊・利玄坊両人」。 |
北野社の碁会。この記録でも利玄と本能寺とのかかわりをみる。当坊碁を三ツに手を直され候とある。当坊は北野社の宮司だろうか。 |
| 【徳川家康の棋力】 |
| 徳川家康の棋力につき、「名人に五子」だったと言われている(当時は名人に四子の実力で初段の免状がもらえた)。これにつき、秀吉が五子で打っていたから家康も五子になったという説がある。「秀吉の五子」は本物で、秀吉の愛棋家ぶりがもう少し注目されて良いように思われる。 |
| 【徳川家康に囲碁を教えたのは誰か】 |
「烏鷺光一の『囲碁と歴史』」の「奥平信昌邸跡 浜松秋葉神社」転載。
浜松市中区三組町にある浜松秋葉神社は、永禄13年、徳川家康が岡崎から浜松城に拠点を移した際に、北遠(浜松市天竜区)にあった秋葉山の権現社を城のすぐ近くの丘陵にあった家臣奥平信昌の屋敷に勧請したのが始まりです。火の神を祀る秋葉神社は、防火にご利益があるとして人々に崇敬されてきました。
この地に屋敷があった奥平信昌は、三河出身の有力国人・奥平定能の長男で、元は奥平貞昌といいました。奥平氏は元々、今川氏の家臣でしたが、今川家が衰退すると一時徳川方に属しますが、その後武田家の傘下に加わっています。どうしても奥平氏を味方にしたい家康は、領地加増と貞昌に長女亀姫を嫁がせることを条件に家臣へ引き入れたそうです。奥平貞昌は長篠の戦いにおいて、長篠城に籠城して武田軍の猛攻をしのぎ、織田・徳川連合軍の勝利に大きく貢献します。戦後、貞昌の功績を賞賛した織田信長により「信」の字を贈られ「信昌」と改名。家康からも名刀大般若長光を拝領し、長篠城に替わる「新城城」の築城を許され大名となっています。
なお、武田家滅亡後、家康は多くの旧武田の家臣を召し抱えていますが、その際に家康への忠誠を誓わせた起請文を秋葉神社に奉納させています。徳川四天王にも数えられる井伊直政の部隊は、武具などが赤で統一され「井伊の赤備え」として知られていますが、これも「武田の赤備え」として知られた武田軍を井伊家が編入したためと言われています。秋葉神社は第二次世界大戦の空襲で焼失したため本物は残っていませんが、その写しが近年発見されたそうです。
奥平信昌は囲碁界とも関わり深い人物で、本因坊算砂の門人だったそうです。徳川家康に囲碁の手ほどきしたのも信昌だと言われ、師匠の算砂を家康に引き合わせたのも信昌であったと伝えられています。
静岡県浜松市中区三組町39 |
|
「烏鷺光一の『囲碁と歴史』」の「新城城 家康と算砂の出会い」転載。
新城市の新城小学校は、かつて奥平信昌の居城「新城城」のあった場所です。「新城城」は新城市の語源となった城です。天正3年(1575)の長篠の戦いにて長篠城を死守した奧平信昌は、戦後、家康の命により長篠城を廃して伊那街道の押さえの要地に「新城城」を築城します。築城にあたり長篠城の大手門を移築するなどしたそうです。奥平信昌は天正18年(1590)に家康の関東移封に伴い、上野国宮崎に三万石で移り、その後の新城城は池田輝政の所領などを経て江戸時代には天領となり、慶安元年(1648)に丹波亀山より菅沼定実が新城に7千石を領し陣所を置き明治を迎えます。
ところで、「新城城」を築城した奥平信昌は囲碁をたしなみ本因坊算砂の弟子であったと伝えられています。家康は信昌に娘の亀姫を嫁がせ義父となっていますが、家康が駿府に新しい城を築造した翌年の天正15年(1587)に信昌は城を訪れています。この時、算砂は信昌に同行し初めて家康と対面しています。家康はもともと囲碁は好きではなかったと言われていますが、この出会いにより囲碁に傾倒していき、後の江戸幕府による支援へと繋がっていったのです。家康と算砂を引き合わせた奥平信昌は囲碁界発展へ大きく寄与した陰の功労者とも言えるのです。 |
|
| 【徳川家康の碁好きぶり】 |
徳川家康の囲碁愛好ぶりは「言経(ときつぐ)卿記」(山科言経の日記)などに明るい。秀吉存命中の天正年間(1573-1591)末期、家康はしばしば上洛し、数カ月も滞在しては、ほとんど連日にわたって碁会を楽しんでいる。公卿、僧侶、豊臣の家臣など幅広い階層の者が、家康主催の宴席に続く碁会に招かれている。家康の意図は京の動静を探ることであったとしても、彼が碁を好んだことにかわりはない。この席には、すでに秀吉より囲碁の名人のお墨付きである「碁之法度可申付」の朱印を授かっていた初世本因坊・本因坊算砂(さんさ)も招かれるのが恒例となっていた。
徳川家康につき、日海が駿河に赴き碁を連日連夜打った記録があり、浅野長政、伊達正宗、古田織部が碁敵であったとされている。 |
| 「囲碁史散歩(2)」(2014年08月14日、 囲碁史会会員・光井一矢)を転載しておく。
|
「囲碁史散歩(3)」(2014年08月14日、 囲碁史会会員・光井一矢)を転載しておく。
初代本因坊算砂(三)
本因坊算砂と徳川家康について貴重な資料が発見され、平成十九年に囲碁史研究家によって解説されたので紹介したい。
| 廿七日 |
於 |
|
七条御門跡 他徳 五目 |
| 廿九日 |
於 |
|
因幡法印 御成 自徳番 十二目 自勝 |
| 八月二日 |
於 |
|
加賀大納言殿 御前 他徳 十一目 自勝 |
| 同日 |
|
|
自徳番 八目 自勝 |
| 同四日 |
於 |
|
新城駿河殿 御前 他徳 |
此一帋(紙)元祖本因坊算砂 法印棋帳之中天正文禄 年間之筆記也附属西村 広良丈尤可為家珍者也
寛延己巳年(一七四九) 十二月 井田道祐 書判
この文書は本因坊算砂棋帳の断簡に、井田道祐(本因坊道知門下)が奥書し、道祐の門人・西村広良に与えたもの。前半の七十六文字は算砂自筆の対局覚書ともいうべきもので、大変貴重なものである。紙が継がれた後半は井田道祐の筆。
まず、後半の部分だけ読み下しておこう。「この一紙は元祖本因坊算砂法印の棋帳のうち、天生文禄年間の筆記なり。西村広良丈(丈は尊称)に附属し、もっとも家珍(家宝)たるべきものなり。寛延二己巳年(一七四九)十二月 井田道祐」。算砂の棋帳文書を詳しく紹介したいところだが、紙数の関係で興味深い部分だけを紹介する。文書の中には加賀大納言の徳番で自十一目勝ちとある。加賀大納言は前田利家のことである。さらに駿河殿の徳番で対局したことが記されているが、結果は不明である。前田利家の加賀大納言に従えば家康は江戸内大臣殿もしくは江戸内府殿となるが、これは算砂と家康の関係から馴染めない。算砂にとって家康と利家の親疎の差なのかもしれない。手合制のことについて触れよう。徳番とは互先などのときに有利な側、つまり黒番であることを示す。となると、家康や利家は算砂と互先で、このとき黒番であったということになってしまう。
この文書が発見されたとき、家康と算砂は互先だったのかと思われたが、これには当然ながら疑問があり、異論もある。ここに二つの異論を紹介する。徳番を先番と見ると算砂と利家、家康とは互先のようであるが、これは置碁にも当てはまるのではないかということ。五子や四子の手合だったら、四子なら算砂が徳番、五子なら利家や家康が徳番というもの。もう一つの見方もある。「加賀大納言」
も「新城駿河殿」も利家、家康自身と対局したということではなく、その御前で算砂がほかの碁打ち、たとえば利玄などと対局したのではないかというもの。これなら徳番の意味もわかる。後者の意見が有力なのではないかと思われる。なお、他徳は相手が徳番、自勝は自分の勝ちという意味。覚書なので、そうした表現を使っている。 |
|
「囲碁史散歩(4)」(2014年10月20日、 囲碁史会会員・光井一矢)を転載しておく。
今回は徳川家康と碁敵について紹介する。家康とよく囲碁の記述があるのが、細川幽斎、伊達政宗、そして浅野長政である。特に家康と長政の対局に関するエピソードには面白い話がある。「武辺雑話」に二つ載っている。
あるとき、長政と対局していた権現様(家康)は形勢芳しからず、かなり機嫌を損じている様子。そこで、長政の末子である釆女長則が本因坊(算砂)に迎えを出して観戦させた。権現様は本因坊を見つけると、手招きしてこういった。「わしらの碁はどうじゃ。この石をハネたらどうじゃ。それよりほかに手はなかろう」と。本因坊は答えた。「おハネなさるよりありません」。そこで、権現様はハネを打って、その碁を勝ち機嫌がなおった。一方、長政は大いに怒り、本因坊を次の間へよびだし脇差に手をかけ「へんなところへその方がしゃしゃり出で、わしは碁を負けた。重ねて助言しようものなら斬って捨てるぞ」と詰め寄った、というもの。
もう一つは、別の日、屋敷の庭前に毛氈を敷き、両者はその上で碁を囲んだ。立会いの算砂は「日が当たり、まぶしいですから」と断って日除け傘をさした。その傘には、あらかじめ小さな穴が空けられており、家康が石を打つべきところへ穴からの日差しで示す。家康は算砂の意図をさとり、そのとおりに打って勝つことができた。長政は不興千万に思い悔しがったが、家康は算砂に「お前は頭が良い」といってほめたという。
長政が悔しがれば悔しがるほど、家康はカサにかかって追いつめた。長政が失着を重ねるたびに「待った」を許してやり、長政が投げようとすると、「こまかい、こまかい」といって投了をみとめない。最後まで打って、結局五十目以上の大差で勝つこともあった。長政が死んだとき、家康はしばらくの問、碁を打たなかったと言われている。
綱川幽斎も家康と囲碁の記述を多くのこしている。家康主催の碁会には幽斎はほとんど出席しているし、幽斎自身もかなりの回数碁会を催している。幽斎の没後も三日間、囲碁将棋を差し止めている。ライバルがいなくなるとこうして喪に服したのだろう。幽斎は遺言で愛用の盤石を家康に譲っている。
家康と囲碁のライバルではないが、囲碁を嫌っていたという人物では石田三成が有名である。あるとき両者は伏見から船に乗り、大阪の前田利家の館へ向かった。その船中で囲碁を打ったという。その席には、浅野長政をはじめ、福島正則、池田輝政、黒田孝高(如水)、加勝清正、藤堂高虎らがいた。後の関ヶ原合戦で東軍として戦う面々である。そこへ石田三成がひょっこり顔を出したので一同すっかり興醒めしたという。家康は囲碁で人の和を広げたが、三成は囲碁をしなかったので孤立してしまったという話まであるぐらいである。
織田信長、豊臣秀吉の囲碁の記録に関しては、伝説的な要素が強く、後生の創作であるとされるが、家康に関しては多くの記録から本当に囲碁が好きであったことがわかる。次回は織田信長の伝説について述べる。 |
|
| 【真田昌幸の碁好きぶり】 |
1600(慶長5)年、9.15日(10.21日)、天下分け目の関が原の戦い。この時、家康の跡目を予定されていた秀忠は、真田昌幸の立て篭もる信州上田城を攻めあぐね、遂に関が原の戦いへ馳せ参ずる機を逸した。戦いが既に終わってしまった後に駆けつけた秀忠は家康の面前に罷り出たものの「恐懼措くところを知らず、その状はあたかも犬の如くであった」。家康は苦虫を噛み潰した表情で秀忠に次のように訓戒している。
| 「微々たる辺隅の一小城に拘泥し、天下の大事を決する主戦場に間に合わぬなどとは、あたかも碁に於いて一局部の優劣を争って大局の計を忘れるに似ている。終局の勝利得て期すべからずじゃ。迂なるかな、愚なるかな」(「日本外史」)。 |
ちなみに、関が原の戦いの当時、秀忠に攻められた真田昌幸は、その落城の寸前まで碁を打っていたと伝えられている。昌幸は大変な碁好きで、永禄4年の川中島の戦いの時も、上田城を死守して一歩も動ぜず、専ら子の信幸を相手に碁に耽っていて、そのため謙信信玄の争覇戦に巻き込まれないで難を逃れた履歴を残している。この時の昌幸信幸父子の棋譜が残っており、現存の棋譜としては建長5年の日蓮日朗師弟が鎌倉で打った棋譜に次いで古いものとなっている。 |
1600年(慶長5).9月、名将の名高い真田昌幸(幸村の父)に関して次のような囲碁の逸話がある。 関ヶ原合戦のとき、関ヶ原に向かう徳川秀忠の軍が真田昌幸の居城上田城を攻めたとき、これを上田城に引きつけて翻弄し、関ヶ原の戦いに間に合わないようにさせた(5日遅れ)。昌幸は上田城のすぐ傍に敵軍が迫るまで家臣と碁を打っていたというもの。その碁を次男の幸村が見ていたとも記されている。
「徳川秀忠、兵を卒ゐ昌幸を大阪に攻む。時に家康より上方蜂起したるを以て、上田を捨てて、早々関ヶ原へ来るべきとのことなり。秀忠是は如何すべきと尋ぬ。本多刑部左衛門曰く、敵の為め京都を取られなば、西国は皆な敵に属し申すべく、大切の所急に参らざるも成り申しまじくと、然れども向いたる敵を一攻もせずして引くこと軍の法に之なきこと。この辺り焼打に致し、それを手持に引取り申すべくとて、その辺在家に火をかけ、本多刑部と名乗り掛け名乗り掛け分捕り焼打を為したりけり。
この時、上田の城には昌幸碁を打ち、幸村見物していたりし処へ、敵三、四里近所まで攻め寄せ、本多刑部と名乗り候て、焼打ち致し候と早打櫛の歯を引くが如し。昌幸、幸村に見物して来れと言て、碁を打居たり。幸村早々に乗出し、暫らくありて乗り返し、敵は引き候と申ければ、昌幸、引くとな、引く引く言て、終にその碁を止めずに打ち果せり」。 |
|
| 【徳川政権誕生前夜】 |
1600年(慶長5)年、北野社家日記(北野八幡宮宮司記録)。
| 「二月十三日、天気快晴。本因坊へ礼に参る。百疋持参す。大酒これ有り」。北野社家日記。「二月十四日、天気快晴。今日本因坊・弥蔵残らず碁打御出也。振舞申す。本因より碁はん(盤・)こけ(碁笥)二を給ふ」。 |
北野社と本因坊との音信。北野社から本因坊へ礼に赴き、翌日には本因坊以下の碁打が碁盤・碁笥を土産に北野社に返礼に来る。弥蔵は坊門の棋士と思われるが不詳。
| 「三月四日、曇。丸(円)山にて新作と申す碁打上手広めこれ有り。我等も参る。頓して帰る」。円山で囲碁上手の手広めがあったとする。北野社家日記。「三月廿八日、天気吉。内府様(徳川家康)へ礼に罷り出ず。一束・一本進上す。養命坊・実相寺同心申す。内府様御前にて碁を見物仕る。こ竹と利玄坊と碁二番これ有り、二番ながら利玄坊勝ち也」。 |
| 「七月四日、天気快晴。目代夜前之竹門よりの御返の事申し来り候由申す。ききやう(桔梗)・薄花共持来。則ち当坊前へよび出し酒を給ふ。法華堂かり屋の円(縁)に座す。目代と三智と碁うたせ見物す。目代白はかま・衣にて来る。衣はゆるし候間ぬぎ候へと申付く。忝なき由申し碁うつ。目代まけ申す。…、今夜三智と碁うつ。七ツにて十三番ながら当坊勝つ。帷子かけ也。二つの状取りて一笑し候」。 |
三智は碁打衆だろうか、不詳。
時慶記(参議西洞院時慶の日記)。
| 「十一月一日、天晴、…此亭には御福来入、田楽あり、内儀(記者室)には北政所(秀吉室)へ女御礼に被参、二郎兵衛来、弥介は朝の間に来て帰る、葛岡佐介殿後室より百々越前(綱家)守の病人被引合、御番は時直(記者息)勤、与吉雇、供に召具、吉蔵は午刻の間暇乞、与所へ出、奥平(信昌)にて本隠坊も馳走候」。 |
北野社家日記。
| 「十一月十四日、天気快晴。今日浅井勝兵へ所へ連哥に参る。晩には本因坊へ奥平作州(信昌)御出にて相伴に参る」。 |
奥平は、本因坊の碁の弟子だったという説もあり、この年は京都所司代の職にある。 |
| 【関が原の戦い逸話】 |
1600年(慶長5年)年9.15日、関ヶ原の戦い。この戦いは、松尾山に陣した小早川秀秋の裏切りによって大勢が決した。秀忠軍は期日に遅れること四日、家康はこれを咎め、秀忠の面会を許さなかった。家臣一同の死に物狂いの弁解とお詫びにより対面を許されたが、この時の家康の説教が次のように伝えられている。
| 「天下を治めるのは、例えて云えば一局の碁を打つようなものである。ひとたび、全局を支配する勝負どころの戦いで勝ってしまえば、あちらに三子、こちらに五子と敵の石があったところで、どうのこうのということはない。お前は、こうした話を聞いたことがないのか」。 |
|
| 【安井六蔵(後の安井算哲)が徳川家康に伺候】 |
| この年、安井六蔵(後の安井算哲)、11歳の時、榊原康政を介して徳川家康に伏見城で召し出され、30石12人扶持を与えられている。 |
| 【利玄】 |
1601年(慶長6)年、北野社家日記。
| 「四月廿七日、今朝本多佐渡殿(正信)へ参り候。一段御懇に候。宮仕悉く仰付られ候へと御取成これ在べき由仰られ候。各大名衆御聞候。利玄へ此由申聞、さらし一たん遣され候也」。 |
| 「五月十三日、天気快晴。今日宗振舞にて終日遊ぶ。各京衆重喜・かしわやなど参られ、碁これ有り」。 |
|
| 1603(慶長8)年 |
| 【江戸時代初期、名人碁所の誕生】 |
1603(慶長8)年2月、関ヶ原の合戦から4年目、徳川家康が征夷大将軍に任ぜられた。
2.12日、日蓮法華宗僧の法名/日海(1559-1623)がお祝いに伏見城に参上して、家康に祝賀を述べた後、五子で対局している。その後、家康の指示で京都寂光寺を法弟の日栄に譲り江戸に出仕し「本因坊算砂」と名乗った。「本因坊」名は、日海が、寂光寺の塔頭(たっちゅう)本因坊に住まいしていたことに由来している。 |
| 【家康が征夷大将軍就任の礼に天覧碁を催す】 |
| 4.19日、家康が征夷大将軍就任の礼に、碁好きの後陽成天皇のために当代最高の碁打である本因坊算砂、利玄、仙角(仙也の子)、道石(道碩)の四人を集め宮中で天覧碁を打つ。4局打たれ、天皇が最上座でそのほかの公家などが対局しているスペースを囲んでいたと云う。 |
| 【天覧碁記録】 |
「お湯殿上の日記」(禁裏女房日記)。
| 「四月十九日、はるゝ、ゆふふより御申にて、ごうちのほんにんぼう・りげん・せん六・たうせきまいる、くろ戸にて御らんぜらるゝ、十てうまき物くださる、ほんにんぼう、こばん・ごいししん上申、八てう殿・しやうこゐん殿・たけのうち殿なる、くげしうも、しこう、く御あり」。 |
慶長日件録(式部少輔舟橋秀賢の日記)。
| 「四月十九日、禁中に於て当代上手の碁これ有り。右府(家康)より叡覧に備へらるべきの由、内々に奏聞有りと云々。内々衆十人計り、召しにより伺候す。予も同じく伺候し畢んぬ。碁打四人、本因坊・利玄・仙・道石等也。先づ御黒戸の前に打板をかまへ、其上に畳一帖を敷き座とす。見物の公家衆は、其遶に円座を敷く。巳の刻計りに始む。先づ本因坊・利玄これを打つ、持碁也。次いで仙・道石これを打つ、道石三目勝つ。次いで本因坊・利玄これを打つ、利玄三目これを勝つ。次いで道石・仙これを打つ、仙負く。夜に入り終り、亥の刻に各退出す。碁打四人に一束巻物各これを下さる也」。 |
言経卿記(山科言経の日記)。
| 「四月十九日、乙巳、天晴る。禁中黒戸へ本音坊・利玄坊・仙・道石等召し了んぬ。棊を御覧也。直綴にて参り了んぬ。仙・道は衣也と云々。四番これ有りと云々。十帖に巻物を四人に下さる也云々。内々の衆少々参らる也と云々。伝聞也」。 |
上件の日次記は、いずれも月日の碁打衆の禁裏参内の記録。家康の斡旋で、後陽成天皇は碁打衆を召して囲碁を上覧した。本因坊対利玄、仙対道石(中村道碩)の対局がそれぞれ二局づつ、計局が打たれた。本因坊は碁盤と碁石を献上し、禁裏から巻物が下賜された。後陽成天皇はこの年歳、秀吉時代に即位、聚楽第に行幸するなど武家の朝廷干渉に忍従してきた。この碁打衆の上覧も家康の奏聞によるものとある。家康は、この年月に征夷大将軍と右大臣の宣下を受けて、その礼に宮中に参内している。碁打衆の参内を奏聞したのもその折だったのかも知れない。この日の行事も家康の顔を立てたものともとれるが、ただ天皇は、公家日記の中に多くの囲碁の記事を残す碁好きで、この一日はプロの対局を楽しんだと思われる。お湯殿上の日記に記すごとく、本因坊はほんにんぼうと訓じたと思われる。なお、将棋指しと禁裏との交渉は、この前年・慶長年暮に山科言経の仲介で、大橋宗桂が作り物を禁裏に進上している也。 |
1603(慶長8)年、浅野長政は実名安井氏にて、浅野は養姓なり(中略)。慶長8年より15年までのうち囲碁の御相手の為、度々召し出される。これは両御所(家康、秀忠)御密々にて、天下御政務相談ありという。(「浅野考譜」)
「7月壬戌、昨日も今日も将軍浅野弾正小*と御碁これあり」(「浅野考譜」)
| 【日海が算砂と改名、碁所と将棋所に任ぜられる】 |
10月、徳川家康が征夷大将軍となり江戸に幕府を開いた。江戸帰府に際し、日海(2世)に寂光寺を法弟日栄(3世)に譲らせ随行させる。日海ここにおいて本因坊を正式の氏とし、算砂と改名、碁所と将棋所に任ぜられる。「旧坐隠談叢」が次のように記している。
| 「日海は家康公の命により、寂光寺を法弟日栄に譲り、隠居して本因坊を氏とす。この時、家康公より棋所(ごどころ=碁打ち衆の総取締役)を命ぜられ、算砂と改名し、常に家康公に持し、江戸に下れり。算砂家康公の高恩に感じ、満腔の熱意を注ぎ経綸の奇才を揮(ふる)い、南光坊天海僧都と艫に御前にありて枢機に参じ、関が原の役、大坂の戦い、共に出陣して弾丸雨飛の間に出入りし、その危うきに臨むも、いまだかって君側を離れず、遂に家康公をして大業をなさしめたり」。 |
| 「家康公は天下静謐に帰し、大業既に成就したるも、なお殺伐残忍の気風は猛将勇士の間に充ち、ややともすれば骨肉の嘆に腕を撫する者あるを憂い、かりそめの遊戯に至るまでに心を用い、囲碁の如きは剛をして柔ならしめ、逆を変じて順ならしむるの徳ありとて、大いにこれを奨励し給いたり。それ、物は人によりて用を異にす。信長公はこれをもって陣中の欝を医し、家康公はこれをもって天下の経営に資せんとす。故にこの時より棋運は俄かに面目を一新し、上は諸侯より下庶民に至るまで大いに流行せり」。 |
「坐隠談叢」が次のように記している。
| 「徳川幕府に於いて家康の定めたる碁所は、天覧碁の組織、将軍の指南、外人対局の按排(あんばい)、全国棋士の統一及び一般に於ける囲碁の代表者と為って之を司配し、碁士の昇進を検定するが為に設けたるものにして、その将軍指南役たる関係を以って、御城碁の時には止め碁となし、特に命令あるに非ざれば、何人とも対局せざること、猶彼の書所のお止め筆と称するが如し。而して、之に補する者は九段の技量有する名人にして、又名人と碁所とは別物なり。(中略)されば各家元の子弟と雖も、皆な碁所の承諾あるに非ざれば昇進せしむる能わず。且つその昇進に対する免状は、皆な相当の手数料を碁所に納むる掟なれば、碁所以外の家元にありては、その子弟に対しても、頗る窮屈なる傾きありて、自然家元たるの権能を抑制せらるる理なるを以って、その資格上相続上に対して争いを為し、時々争碁を生じたるは之が為なり。而して、幕府が之を補する上に於いては、その名人たるを要するなり。而してこの名人たるは、第一、官命の場合。第二、共同推薦による場合。第三、争碁に勝ちし場合の三項に外ならず」。 |
|
|
この頃、家康が子の秀忠の夫人・達子(淀君の妹)に宛てた手紙の一節は次の通り。
「一身の楽しみの事、人々好き嫌い、得手不得手、有りの事にて候。とかくものの片寄らぬように致させ申す事に候。たとえば四季の花、色々様々咲きて、いずれも眺め有りの候。中にどくだみと申す草花、香りも悪しく、何の役にも立ち申さざる草のように存じ候えども、疥癬の薬に煎じ用いそうらえば妙薬に候。その如く何芸も人の覚えたる事は承りおき候えば、何か入用の事あるものにて候。第一自身に不得手のことは、人の致すも忌み嫌い候えば、また有りの候。それは大名の別して致さぬ事に候」。
「我ら中年の頃まで碁を一向に存ぜず、人の打つさえ無用の物、気詰まりにて役にも立たぬ事とばかり存じ、人の好み候、うつけ者のように存じ候ところ、近年覚え候えば、雨降り徒然(つれづれ)の慰めにもなり、先だってうつけ者と存じ候者を相手に致しおり候。これにて察しられ候よう、何事も詮なき事は古くより致さぬ事なれば、くれぐれも自分の気に入らぬ者を悪しきと存ぜぬように致す事、専一のことに候。ただ身の知恵の届かぬ事と朝夕に存じ候ことに候」。 |
| (自分は中年まで碁を知らなかった。人が碁を打っているのを見て、無用のもの、陰気で何の役にも立たないものに興じる者をウツケ者と思っていた。ところが、碁を覚えてからは、雨降りの日の徒然(つれづれ)の慰みにもなり、これまでウツケと思っていた者を相手に打つようになった。これより思案せよ。何事も詮のないことは昔からしない。碁も何かの役に立つから多くの人が好んで打ち継いで今日に至っている。してみれば、自分の得手としないものに興じている者を嫌って遠ざけるようでは浅はかの謗りを免れない。このことを深く知り、我が身の知恵の及ばぬばかりに至らぬことがありはしないかと朝夕に自問することが肝腎である) |
|
| 1605(慶長10)年 |
| 玄覚(井上一世因碩、古因碩)が山城で生まれている。本因坊算砂は、囲碁のみならず将棋も能くし、慶長10年には江戸城で宗桂と将棋の対局を行なっている。 |
| 1606(慶長11)年 |
12.4日、豊臣秀頼が大阪城で碁会を催す。「梵舜日記」が次のように記している。
| 「豊国二位宅の碁会において、本因坊、利玄坊、山内是安、六蔵(一世算哲)、春智、其のほかの本因坊弟子碁衆、十三人同道」。 |
|
| 1606(慶長11)年 |
碁打ち、将棋指し衆の統括者的な地位にあった算砂は両芸に秀で、囲碁は天下無敵。将棋も当時五本の指には入る腕前であった。今日宗桂、宗古との棋譜が残されている。やがて「名人碁所」に任ぜられ、初代本因坊となった。その際に将棋の司を宗桂に譲った。「同一人が囲碁と将棋の双方を束ねるのは、碁界にとっても将棋界にとっても不利益であると判断し、自ら将棋所を退き、宗桂に譲った」と解されている。囲碁界で開祖として尊崇をうける算砂は、将棋界にとっても大恩人と云うことになる。日海はこうして幕府公認のプロ棋士となった。これより以降、幕府が囲碁と将棋の家元に扶持を与え保護育成することになる。
この間、算砂は中村道硯(井上家元祖、二代目名人)、安井算哲(安井家一世)など多くの優秀な弟子たちを育てていった。
秀吉の息子である豊臣秀頼も、大阪城にて度々、碁会を開いている。梵舜日記が、この年に行われた碁会について、「豊国二位宅の碁会において、本因坊、利玄坊、山内是安、六蔵(一世安井算哲)、春智、そのほかの本因坊弟子碁衆、十三人同道」と記している。 |
1606(慶長11年)、「2月8日、大御所、江戸に於て伊達政宗へ御成りあり。囲碁の上手、本因坊、利玄、道石、図将棋の上手宗桂以下、祇候せしむ」。(「慶長日記」)
| 1607(慶長12)年、。 |
| 11月、算砂と利玄、大阪城本丸において対局。利玄、先相先で打つ。豊臣秀頼が観戦し給う。この手合いは、第1局、第2局と利玄先、次に本因坊が第3局を先番で打っている。これが先相先の手合割の先例となっている。 |
12.24日、日海当代記が次のように記している。
| 「囲碁の上手本因坊、法華宗宗清僧也。この頃囲碁手合いのこと、本因坊(利玄に半石強く、年49歳)、利玄(43歳)、道右(27、8歳。5、6年前より利玄と手合い同事並びの上手)、樹斉(50歳)、是清(22歳)、門人六蔵等也。並びの上手と云うは本因坊に先の碁なり」。 |
|
この年、算砂は将棋初代名人の大橋宗桂と将棋の対局をしたことでも有名だが、その宗桂に関する記述が「当代記慶長12年の項」にある。
| 「この時の上手、名は宗桂というものなり、是京都町人なり。この宗桂は、信長時代よりの指し手なり、今年五十三歳なり」。 |
|
| この年、大阪城で算砂と利玄の対局が行われている。 |
| 1607(慶長12)年12.15日、算砂が「本因坊碁経」を刊行している。詰碁や手筋などを収録している。これはわが国初の囲碁出版であるとされ現存している。 |
| この年、徳川家康が駿府に隠居する。 |
| 1608(慶長13)年 |
| 1608(慶長13)年、大坂城の豊臣秀頼の前で、初代本因坊・算砂が大橋宗桂(初代)と将棋対局している。これが将棋最古の棋譜となっている。 算砂は将棋でも第一人者であった。将棋初代名人大橋宗桂は算砂の弟子のような存在で、二人の将棋の実力は互角だった(ちなみに大橋宗桂の囲碁も算砂と互角だったという説もある)。千利休とも仲がよく、互いに碁とお茶を教えあったとの逸話がある。 |
3月、「囲碁上手本因坊、去る正月より江戸にあり、将軍象棋を見給うべしとて、京都より宗桂召し下され、十日に十番さしける」。(「当代記」)
この年、駿府の家康御前にて本因坊算砂と林利玄の対局が行われている。「12月24日、囲碁の上手、本因坊、法花宗の僧なり。この頃囲碁手相の事、本因坊、利玄に半石強し。利玄道石手相同事也」。(「当代記」)
その後、京都寂光寺にあった算砂は、毎年三月に他家の棋士を率いて江戸城に登城し、将軍に謁見して御前試合を行なうようになる。 |
| 【日本と琉球の外交史】 |
日本と琉球の外交史は次の通り。
1609(慶長14).3月、江戸幕府(日本)は、明国(中国)との国交樹立政策の一環として、薩摩藩(鹿児島)初代藩主/島津家久(しまづいえひさ)(1576(天正4)年~1638(寛永15)年)を琉球(りゅうきゅう、沖縄)に三千余の兵を出兵させ、4月1日、琉球が降伏。7月、徳川家康(1543(天文11)年~1616(元和2)年)が琉球を家久に与えた。
1611(慶長16)年、島津家久は琉球仕置を行い、琉球国王/尚寧(しょうねい)(1589年~1620年在位)に琉球が古くから薩摩の附庸国(属国)だったことを認めさせ、沖縄島ほかの諸島8万9000余石を与え、与論島以北の大島(奄美諸島)を直轄化した。
1634年(寛永11年)、琉球の日中両属(外見は独立国の琉球王国、内実は薩摩藩、徳川幕府の強い規制を受ける)が確定。同年、島津家久は琉球の王位を琉球国司に任じ、また、琉球国王/尚豊(しょうほう)(1621年~1640年在位)使節の2年一貢の江戸上がり(慶賀使、謝恩使、進貢)が始まった。
島津藩と琉球史は次の通りである。「琉球王国 日本の侵略と従属」を転載する。
| 「1590年頃、豊臣秀吉は琉球王国に 朝鮮を征服する戦役に協力するよう要請した。成功すれば秀吉は中国に向かう意図があった。琉球王国は明の朝貢国であったため要求は拒否された。秀吉の陥落に伴い登場した徳川将軍は島津家-薩摩藩
(現在の鹿児島県)の封建君主-に琉球を征服するための遠征軍を送ることを許可した。これによる侵略は1609年に起きた。占領は非常に速く起き、武器による抵抗は最低限のものであり、
尚寧 (しょうねい) 王は捕虜として薩摩藩に移送され、 次いで江戸 (現在の東京)に移送された。2年後に釈放された時に琉球王国はある程度の自治を
再び獲得した。しかしながら、薩摩藩は琉球王国の領地-特に奄美大島-を手に入れ、薩摩藩に組み込まれ、現在も沖縄県の一部ではなく鹿児島県の一部となっている。
琉球王国は日本と中国に二 重に従属することとなり、 琉球は徳川将軍と明の宮廷のいずれにも進貢することとなった。明は日本との貿易を禁止していたため、
薩摩藩は、徳川幕府の加護により、王国との貿易を使用して、王国が中国との貿易を継続するようにした。それ以前に日本がオランダ以外のヨーロッパの国と絶縁したため、
そのような貿易関係は徳川幕府と薩摩藩にとり極めて重要であった。薩摩藩はこのようにして手に入れた権力と影響力により、1860年代に幕府を転覆したのである。
琉球王は薩摩藩の隷属者であるが、彼の土地は藩の一部とはみなされなかった。これは1879年に島々が公式に併合され、王政が廃止されるまで続き、琉球は日本の一部とみなされることもなく、琉球人は日本人ともみなされなかった。技術的には薩摩藩の統制下にあったが、琉球にはある程度の自治が与えられ、中国と貿易をすることにより、薩摩藩にも幕府にも利益を提供したのである。琉球は中国の朝貢国であり、日本は中国と正式な外交関係を持っていなかったので、琉球が日本によって統制されていることを北京に知られないことが重要であった。従って、皮肉にも、
薩摩藩- そして幕府-はすぐにわかるようにあるいは強制的に琉球を占拠したり、琉球における政策や法律を強制することなどに関しては、ほとんど干渉しなかったのである。状況は関連する3者-琉球王国政府、薩摩藩、幕府-にとって、出来る限り別の外国であると見える方が都合がよかったのである。日本人は将軍の許可なしには琉球を訪れることが禁止され、琉球人は日本人の名前、衣類や習慣を採択することが禁止されていたのである。琉球人は江戸を訪れる際に日本語が理解できることを表明することが禁止されていた、薩摩の大名である島津家は江戸への道中、あるいは江戸内部の通行で、琉球の王、役人や琉球の人々を見せまわすことにより威光を勝ち得たのである。国王あるいは全王国を隷属させている唯一つの藩として、薩摩藩は異国的な琉球から非常に多くのものを得ることとなり、
まったく別の王国であることを強調したのである」。
|
|
| 「9月9日、今日駿府に於て、近習之衆、並年寄衆出仕、大御所面え、少しの間出経、奥にて碁あり」。(「当代記」) |
| 「11月4日、二位殿(豊臣秀頼)碁盤見に、哲願寺の盤屋まで御出、予も罷る也」。(「梵舜日記」) |
| 1611(慶長16)年、。 |
| 初代本因坊・算砂が僧侶としての最高位の「法印」に叙せられている。 |
| この年、杉村算悦(後に2世本因坊)が京都で生まれる。 |
| 【徳川家康と浅野長政の碁仇譚】 |
1611(慶長16)年4月、浅野長政が逝去。長政は家康の碁仇で、長政死後は家康も碁石を手にすることがなかったと云う。家康と長政の次の囲碁逸話が伝えられている。
| 「家康と浅野長政は無二の碁がたきで、顔さえ合わせれば碁を打った。或る日、家康が負けこんで、だいぶご機嫌が悪い。何番目かの碁も大石が死に掛かっており、気息奄々である。活きさえあれば勝ちなのだが、どう打てば良いのか分からない。そこへ算砂がひょっこり姿を見せ、盤側に座った。『おお本因坊か。見らるる通り難儀をしているさいちゅうじゃ』。家康は助け舟が現れたのを幸い、同意を求めるように話しかける。『ハネるものか下がるものか、二つの一つだとは思うのじゃが何とも思案に余る』。算砂、答えられるものではない。家康が重ねて云う。『どうじゃ、ハネであろう。ハネならば確かに活きておる。な?』。こうまで云われては、算砂も答えざるを得なかった。『御意。おハネになるがよろしゅうございましょう』。大石は活き、勝った家康はカラカラと笑った。おさまらないのは長政である。退出する算砂を追って出てくると、眉を吊り上げて云った。『こりゃ本因坊。余計なところにでしゃばりおって。お陰でわしの負けになったわ。もし今後もかようなことがあれば、本因坊とて容赦せぬぞ。さよう心得ろ』。この時、長政は脇差に手をかけていた」(田村竜騎兵著「物語り囲碁史」参照)。 |
|
| 「名将言行録」の「徳川家康は浅野長政を呼んで「賭碁をするぞ」」参照。
|
| 【徳川幕府の囲碁、将棋保護政策】 |
1612(慶長17)年、2.13日、徳川家康&幕府は、「碁打衆、将棋指衆御扶持方給候事」として、当時の名だたる算砂を始めとする碁打ち衆(囲碁師)、将棋衆(将棋師)の8名(囲碁の本因坊算砂、利賢(利玄)、道碩、春知、算碩、六蔵(後の安井賛哲)。将棋の宗桂、仙重)に俸禄を与え生活を保障した。
| 「慶長十七壬子年、権現様より下置かれ候御切米御書出しの写碁打衆将棊指衆御扶持方給し候事。一五拾石五人扶持本因坊、一五拾石五人扶持利賢、一五拾石五人扶持宗桂、一五拾石道碩、一二拾石春知、一二拾石仙重、一三拾石六蔵、一二拾石算碩、御切米合弐百九拾石、御扶持合拾五人扶持。右亥年分より毎年京枡を以て相渡し彼衆手形を取置き江戸御勘定相立らるべく候、以上 壬子二月十三日」。 |
俸禄の内訳は次の通り。
| 囲碁 |
本因坊算砂 |
50石五人扶持 |
|
|
| 鹿塩利賢 |
50石五人扶持 |
|
|
| 井上(中村)道碩 |
50石 |
|
|
| 春知 |
50石 |
|
|
| 林 |
50石 |
|
|
| 安井六蔵(後の安井賛哲) |
30石 |
|
|
| 算碩 |
20石 |
|
|
| 将棋 |
大橋宗桂 |
50石五人扶持 |
|
|
| 仙重 |
20石 |
|
|
猿能楽の金春安照の500石、絵師の狩野探幽、狩野常信の200石、連歌師の里村紹巴の100石などといった他の遊芸師たちとの俸禄と1対1比較すれば、碁打ちと将棋指しの評価はさほど高いものとはいえないが、囲碁・将棋の場合の俸禄人数を勘案すれば相当な石高になるはずであり、江戸幕府によって囲碁・将棋が技芸として認められ、後の家元制に繋がる基礎が築かれた意義が大きい。以降、上手(7段)以上の棋士によって五百数十局の御城碁が打たれることになった。
この時、扶持を受けた碁打ち衆のうち相続をして家を継いだのは本因坊家、安井家(六蔵のちの算哲)、井上家(道碩)、林家(利玄坊の弟子の門入斎)の四家で、囲碁をもって幕府に仕える囲碁の家元となった。家元制はその後幕府と共に凡そ230年間続くことになる。本因坊家は50石、本因坊算砂(日海上人、1559~1623)。井上家は50石、算砂の弟子で、のち名人碁所となった中村道碩(1582~1630)。林家は50石、林門入斎(1583~1667)。安井家は30石、安井算哲(古算哲とも、1590~1652)を祖とする。「坐隠談叢」は次のように記している。
| 「算砂時代に於ける碁士として著名なる者は、本因坊算砂、鹿塩利賢、中村道硯を第一流として、山内庄林、是*、算哲(六蔵)春智、仙角、門入、樹斎、仙重、徳蔵、覚順、宗数、算悦、算知等之に次ぐ。而して、道硯は井上の祖となり、算哲は安井家を、門入は林家を起したる者なり」。 |
安井家の初代・安井算哲は算砂の門人で共に家康に仕えている。算哲の長子が渋川春海(1639~1715)であり、碁方を離れて天文方に転じ、後に安井算哲2世を称すことになる。初代安井算哲は渋川春海が天文方に転じたのを受け、弟子の算知を養子として跡目にした。この安井算知(1617~1703)が安井2世となる。安井家の碁は、本因坊家の本因坊算砂、中村道碩が軽い手筋でサバク手法を好んだのに比して力碁であった。これによりモリモリ打つ手法を安井流と言った。安井家と本因坊家は両家は囲碁の世界の両極をリードし、互いにしのぎを削る厳しい闘いを展開することになった。大坂の陣では叔父の安井道頓が豊臣方にあったが、父・宗順や叔父・定吉を家康に引き会わせ、徳川方の案内者に推挙する。その後は京都に居を構え、毎年3月に算砂らとともに江戸に下った。 |
6.7日、算砂が法印に叔せられ、ロ宜案(薄墨の論旨)を受ける。同年、本因坊算砂が将棋所を大橋宗桂に譲る。「坐隠談叢」は次のように記している。
| 「算砂は碁将棋共に名人の域に達し、碁将棋所を兼司したりしも。将来一人にして之を兼ねるに足るべき技りょうを有する者を見るは不可能のことにして、之を自然に放任するときは、遂に紛擾争奪を見るに至るべしとて、公許を得て、将棋所を大橋宗桂に譲り、碁所は晩年之を中村道硯に譲りたり。当時の碁所印可状左の如し。『今度我ら永々患候而して快気得ず候就者其の方囲碁秀で諸弟子依無頼家督相譲候 於向後者我らの手合い同前許之候。以上は手相以下の法度可為。その方計者也。*印可状如件 本因坊 元和九亥卯月二十三日 中村道硯 是より以後、碁所将棋所は互いに相扶助し、争議の起りたる場合の如きは、必ず斡旋し合う事となれり」。 |
|
| 【「天下の碁所たる本因坊に対する幕府の待遇」】 |
| 四家元は互いに研鑽を競う間柄にして、その伎倆(ぎりょう)は時代により異なる。四家元のうち本印坊家が筆頭であったけれども、碁方の総元締めとなる職制としての碁所(ごどころ)の司でありえたわけではない。碁所に就位するには、その者が、神技の持ち主と目される名人(9段)の域に達した者として家元間の合議で認められることが条件だった。人間技での最高位とされる7段を上手、準神技級の準名人が8段、最高位が名人(9段)であった。推挙された名人に対し、幕府の吟味を経て碁所の地位が与えられ、名人碁所は幕府のお墨付き権威を得て家元四家の上に立って号令できることとなる。名人碁所には、1・全国棋家の代表としての最高栄誉権威。2、年に一度の御城碁(江戸城に出仕しての碁の対局)に参加する碁打ち衆の指名、対局相手の組み合わせの采配。3・碁打ちの全国的な統一基準を定め、棋力(段位)を認定し、免許状を発行する権限。4・その他、碁の行事に関する一切の権限が与えられた。中でも免許状発行は碁所又は宗家の重要な収入源となった。こうして、名声と収入を手中にする碁所の地位を勝ち取らんが為に四家なかでも本印坊、安井、井上の三家の間で激しい烏鷺の争いが展開されて行くことになった。江戸時代の囲碁界は、名人碁所をめぐる棋院四家の血みどろの抗争を繰り広げた歴史となったともいえる。 |
「天下の碁所たる本因坊に対する幕府の待遇」につき「坐隠談叢」が次のように記している。
| 「当時、天下の碁所たる本因坊に対する幕府の待遇は、五十石五人扶持にして、家康は特に算砂の身を終るまで別に三百石を支給したり。而して算砂は、既に権大僧都にして、法印に叙せられたる者なるを以って、総ての取り扱いは他と班を異にし、緋(ひ)の法衣を纏いて、袋入長柄の傘を用いるは勿論、登城の節は、下乗際まで乗輿を許され、その京都に遷る時は、三千貫の旗下格を許され、品川以西の街道を堂々と往来したるものなり」。 |
| 「算砂は常に、京都寂光寺の塔頭本因坊に居住し、次いで之を氏となしたる者にて、毎年三月中旬までに江戸に下り、着到の旨を、月番寺社奉行に届出で、四月朔日を以って他の三家(井上、安井、林)及び御城碁を勤むる者を率いて登城し、奏者番の口上を以って、本因坊碁将棋の者共参上の御目見え申し上げ候と披露に及ぶ。この時、本因坊は御祝儀として、扇子(函入り五本)を献上す。(中略)この式終わりて本因坊は一同を伴い、若年寄、月番寺社奉行等の役宅に就き、今日参上御目見え被仰せに付きありがたき幸せに奉り存じ候 と廻礼して、帰宅休養し、11月17日に至り、定例の御城碁を済まし、12月5日御暇を賜う。この時、本因坊には銀十枚、部屋住みには時服一重(他三家も同様)を賜い、又名人には黄金二枚を下賜せらる。而して、若年寄、月番寺社奉行を廻礼し、45日を経て京都に帰り、休養するものなり」。 |
|
斯波義麿「家元制度についての雑感」を転載しておく。
江戸時代の日本は、世界に先駆けてさまざまな今日的文明の基礎をなす制度、システムを商習慣や文化事業の中に築いてきました。大坂(今は大阪)の堂島の米相場会所の開設(1730)、これは、”帳合取引”と呼ばれ、現物をまったくともなわない純然たる先物取引の嚆矢として世界商業史に刻まれています。また、識字率の普及は、世界最高水準を誇っていました。木版印刷による”読み本”の出現は、ヨーロッパに先駆けた、大衆出版文化の到来を意味しました。こうした世界水準の最高レベルや”世界初の称号”を冠せられる江戸の文化事業の中に囲碁、将棋の家元制度の確立があります。はじまりを太閤秀吉時代の碁打ち衆(本因坊算砂)への二十石二十人扶持の支給にあるとするこの”専門棋士”の誕生は、徳川家康公が1612年に囲碁、将棋の強者八名に扶持を与え、それぞれ碁打ち衆、将棋衆として召抱えたことによって制度的に確立しました。(詳しくは、Wikipediaの「碁所」、「御城碁」等を参照ください。)囲碁の家元というのは、こうして生まれた「本因坊家」「井上家」「安井家」「林家」の四家を指します。四家の中の筆頭は「本因坊家」であり、幕末にいたるまでほぼ”碁所”すなわち碁打ち衆の”長官”の地位を独占したため、社会的にも”名人”の代名詞のような認識で受け止められてまいりました。厳密には”碁所”=碁打ち衆の長官と九段位=”名人”は同一ではないのですが、それは、よほどの例外なので普通は、碁所=名人=九段位といって間違いありません。今日ではその名跡は囲碁のプロ組織、日本棋院の所有となっています。有名な囲碁のタイトル戦「本因坊戦」はその名跡をめぐって、プロ碁打ちが、しのぎを競うという趣旨の一年任期の選手権戦です。現代でこそチェスの世界選手権戦や各国のプロ碁打ちのトーナメント戦は、当然のように行われておりますが、約四百年前に専門家集団による選手権戦、(碁所=名人位=長官位)争覇をめぐる家元四家による真剣勝負が幕府の庇護のもと、制度化されていた事は、世界文化史上の驚くべき特筆大事と申しても過言ではないでしょう。これは、囲碁を愛した徳川家康公の趣味をそのまま歴代将軍家が踏襲した結果であり、”真剣勝負”の結果を将軍家の御覧に上げる毎年の”御城碁”の日とは、家康公の命日である11月17日に他なりません。この日は、家元・碁打ちにとって、はれの将軍お目見えの特別の名誉の日であり、この儀式が完了するまで、中座したり、途中退席したりすることなどありえません。「碁打ちは親の死に目に会えない」の諺は、この故事に基づくものです。世界文化史上における意義を称え、囲碁を愛した家康公は、2004年に第一回囲碁殿堂入りに選出されました。
先ほど江戸時代に確立された家元制度のうち、碁打ち衆すなわち囲碁四家の成立事情に関して述べさせていただきましたが、世に家元と名のつく職能家系の多きこと、華道、茶道、礼式、能、狂言、武術等々無知な私が何を”雑感”として述べられましょうか。ただ、自分の趣味である囲碁に関してのみ、少しは、ご報告らしき何かを申せると考えているしだいです。にもかかわらず何ゆえ家元制度についてなどとえらそうな表題を採用したのか、それは、私が愛してやまない囲碁に関して”家元”という言葉が特別なキーワードであると考える理由があり、歴史に関する議論の中で囲碁を論じようとすれば家元制度の性格、意義、存在理由等を考察せずして正しい結論を導くことはできないと考えたからであります。私の囲碁論において家元制度はそれほど重要な位置を占めております。ゆえにこの後半においての”家元論”とは囲碁を論ずるためのツール、補助線的な意味合いで語られる事を先におことわり申し上げ、議論を進めたいと存じます。
そもそも何ゆえの”歴史コーナー”における囲碁なのか、歴史ファンにとって囲碁など関係ないではないか、と指摘されれば非常につらい面がある事を正直に申し上げて話を進めたいと思います。これに関する私の釈明は、私は、囲碁に関する或る救いを歴史に求めざるをえなかった、ゆえに、私の囲碁論は、そのまま、何らかの意味での広義の”歴史論”に相当するわけであり、”歴史論”ならばこのコーナーに投稿しても許されるであろうと考えたしだいです。しかし、もう、そうとう前置きがながくなりました。以下、本論でございます。
80年代に「日中スーパー碁」に何度目かの敗北を喫した後、日本囲碁界は、90年代後半からこの21世紀初頭の数年間にかけてアジアのとりわけ韓国の若き天才たちにこてんぱんに打ち負かされ、もはや、彼らは日本の囲碁を学ぶ必要性を認めなくなったかの印象があります。日本の囲碁ファンたちの反応も弱気で彼らのネット上の議論をみれば韓国最強、日本二流という意見が大半のようです。日本のプロ棋士たちも弱気な感想が多い。しかし、私の感想は、異なっています。私は、今でも日本を世界最強の囲碁国家であると考えており、その信念の拠り所が家元制度というしだいです。ところで、GoogleのWikipediaで「家元」を検索してみてください。他の分野の家元(華道や茶道、小笠原流のような礼式)が今も健在であるのに対し、囲碁、将棋は「家元が死滅した」と記されています。これが、世間一般の常識であり、多分、日本の囲碁のプロ棋士たちもそう考えているのでしょう。自分たちが”家元”そのものである、いな、そうあるべきである、という自覚がない。これが、”道場破り”すなわち、東アジアの中韓棋士たちに看板をうばわれて後塵を拝することになった原因の最たるものです。ここで私は、何故、徳川時代に確立された家元制度がすばらしいか、その理由を語りたいと思います。まず、わかりやすい数字から。囲碁に於けるもっとも高い評価を受けている数人の碁打ち、本因坊道策、丈和、秀策、道的、秀和、秀甫、秀栄(丈和以下すべて姓は本因坊)といった天才たちは、皆、江戸時代に生を受け(活躍が明治の棋士もあるが)家元の徒弟制度で修行したという事実です。ところで右の七名の棋士を上回る天才はプロ化した明治以降の近代碁界からは出現していない。贔屓目にみてもかろうじて互角の棋士が十数名といったところでしょうか。選手層の厚さは、大正、昭和、平成を合計すれば、江戸時代の家元四家の総延べ数の数十倍に値する院生、准棋士、見習いを抱えておりながら、数十分の一の江戸時代と同数もしくは、倍ぐらいの天才しか生み出せなかった。この効率の悪さは何か。否、江戸時代の家元四家の異常な効率のよさは何か、これは、統計から導かれた結果なのですから誰も反論できない。すべては、家元制度の一子相伝的な摩訶不思議な密教の奥儀伝承の如き霊的交感がなされた結果としか思えません。もっとも大切なものは、筆授できない(言葉、演繹的論理を駆使しても伝えられない)、このことは、司馬遼太郎氏が、「空海の風景」の中で空海と最澄の密教の奥儀伝承にあたる姿勢の違いを見事に描いておられるので是非ご一読いただきたい。家元制度にはこの超心理学的なテレパシー的な言葉によらない感化という神秘的側面があると私は、推測します。
私の好きな司馬氏の作品に「京の剣客」という短編があります。ここに表現されている吉岡憲法の姿こそ私が理想とする「家元」そのものです。家元は、在野のプロフェッショナルに負けてはならない。死に物狂いで修行した在野のプロ中のプロを手もなく捻るのが「家元」であるからです。努力は、天才に勝てない、その「天才性」を代々筆授や論理、左脳的人間知によらず、帰納法的な直観的な瞑想的な”霊感”のかたちで一子相伝させるのが(これは、遺伝学的な親子である必要はありません養子がむしろ普通です)家元、日本の家元文化であると私は、信じます。古来、日本の文化はそのようにして、師匠から弟子へと伝えられたのでした。かえりみて日本の近代碁界で最も家元徒弟制度に近かった育成方法をとっておられたのは、木谷実先生でした。木谷門下からは、競馬に例えれば、サンデーサイレンスからダービー馬が何頭も誕生したように多くのタイトルホールだーが生まれました。これをみても家元徒弟制度の如何に優れた教育方法かがわかります。日本のプロ碁打ちの方々は、自分たちが、日本棋院という看板を背負った現代の囲碁の「家元」であり、死に物狂いで武者修行したプロ中のプロである在野の「宮本武蔵」を木っ端微塵に返り討ちする義務があると自覚していただきたいものです。せっかく、家康公が敷いてくれたその伝統のシステムを是非、現代に蘇らせていただきたい。日本の文化の力を結果で証明していただきたい、と深く切に祈るものです。長々とご静聴いただき真に有難うございます。 |
|
09年02月17日「◆国技・1 ◆カムイ◆ 」。
二代将軍秀忠は、軍事では、優れた資質を見せなかったが、文化面での業績がある。江戸以前の文化芸能は、民間で自然発生し、発展したものが多い。散在する文化を統括し、監督官庁も定めて奨励したのは、秀忠の政治である。新しい制度が出来て、相撲と碁は発展期を迎える。どちらも古くから行われてきたが、専門職としてではなかった。相撲は古代から宮廷で、相撲の節会(せちえ)として、秋に行われていた。武士が政権をにぎり、皇室の力が衰え、源平の戦いがはじまると、承安4年(1174年)を最後として、節会は断絶した。相撲の中心は武士階級に移り、組討の武技として奨励された。戦時だけでなく、平時にも行われた。 曽我兄弟の仇討ちの原因となった、河津三郎と股野五郎の相撲は、源頼朝の前でおこなわれたものである。室町時代には、半職業的力士集団が、投げ銭目当ての辻相撲や、寺社建立の寄付を勧める勧進相撲を行っていたが、後世に名を残すほどの力士はいなかった。これらの相撲は、主に上方で行われていたのである。 すべての芸能が京阪で熟し、江戸に下ってきたように、江戸で勧進相撲が行われるようになった。木戸銭をとって見せる興行である。勧進は、正式に興行許可をとる名目だけとなった。いまも、地方興行の責任者を勧進元とよぶのは、その名残りである。芸能一般は寺社奉行の管轄だが、相撲興行が行われるときは、相撲奉行が特設された。力士が相撲のプロとして公認されたのである。初代横綱が生まれた。明石志賀之助、後世に名が残る力士である。横綱はこの時は、位でなく、最高力士で特に選ばれたものが締めることができる栄誉であった。その格式は、京五条家が許可した。150年後、第四代横綱からは、吉田司家が許可するようになり、今日に至っている。
碁所が設けられた。 碁打ちの総元締めである。官賜碁所の制度は、豊臣時代に定められたが、昇殿まで許される日海上人が、算砂と名乗り、碁を天職とするようになったのは、このときからである。碁の家元ができた。本因坊家につづいて、安井家、井上家、林家である。家元の中から碁所が選ばれる。最初の碁所は本因坊家である。第一世本因坊算砂は、法印の位をもつ僧侶だが、後に、織田、豊臣、徳川に仕え、指導碁も打った人である。初めての名人(初代名人とは言わない)になった。名人は、最高棋士で特に推薦されたものが称することができる位である。近世、第二十一世本因坊秀哉までに10名を数えるのみ。本因坊家7名、井上家2名、安井家1名である。名人は碁所当主であったように思う。井上家の元祖となった中村道碩は、算砂の門弟、算砂の後の碁所となる。本因坊家を継がず、新しい家元を起こすのは、算砂の意思による。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第二世以来、代代襲名することになる。碁所は道碩の後、該当するものがなく、一時欠所となる。横綱、名人、専門力士、専門棋士の誕生は、二代将軍の治世であった。 |
|
1612年、108代後水尾帝の慶長17年、「3月3日、在府の諸武士出仕。前殿に於て本因坊算砂、宗桂法師、将棋を囲む。(「駿府政事録」)
1612(慶長17)年、「有馬氏*及の名、父子兄弟に及ぼして世医を業とす。(中略)初代*及、臥雲と号し、又存庵という。後、水尾院特徴て御医とし、階法師を賜う。(中略)或る時、急に召さるるに、折節碁を囲みて参内遅々に及び、頻りに御使を下さるれども、なお局を結ざりしかば参らず、これに罪せられて京師を逐れ、大津に蟄す。しかもほどなく召還されふるとぞ」。(「近世奇人伝」)
| 【「当代記(慶長十八年三月の条)」】 |
「当代記の慶長十八年三月の条」に以下のような記述がある。算砂が本職の囲碁以外に将棋を得意としたように、利玄もまた中将棋を得意とし後陽成院と対局する機会がしばしばあったようである。
| 「五日、…碁打ちの本因坊、召しにより院参す。碁の儀色々院宣あり。中にも仙人の打ちし碁の作物、直に院作ありて、本因に見せらる。この時の院宣に、碁に別智ありと云ふ事は三家禄と云う書物にこれあり、酒に別腸ありと云ふは知らずと也。和云ふ、これは賓退の禄と云う書物にこれありと承る。この書物さがの妙知院にこれあり。又月合の比、利玄、召により院参す。これへも右の作物同前なり、則ち利玄これを仕る。奇特の由宣下あり。利玄、院、中象碁を遊ばさる。本因、利玄は出家の為によりて也。何も法花宗也。さて右の両人も駿府へ下る。院は中象碁天下一と思召す」。 |
|
| 【道頓堀譚】 |
| 1581(天正9)年、安井定次は信長から久宝寺一円領地たるの朱印をもらい、1584(天正12)年、秀吉から知領安堵の保証を得た。兄の定三の三男定吉を養子とした。定吉が壮年になると遁世し道頓と称した。道頓は大坂南堀(道頓堀安井稲荷のあるところ)に住んだ。1612(慶長17)年、道頓は、豊臣家に願い、自宅付近の東堀から木津川に至る上下28丁の地を買い、これを掘って船の便を拓いた。慶長の末年、豊臣秀頼が兵を集めると聞き、既に定次は死んでいたが、生前の厚誼に報いようと一族の仁兵衛と共に大坂城に入った。道頓は秀頼の近習役になった。秀頼と道頓は碁が強く毎日のように碁を打った。ところで、安井算哲1世は定次の兄の定正の四男宗順の子であった。算哲は家康、秀忠に愛顧され、一族の道頓、仁兵衛が大坂城に入った為に肩身が狭かった。算砂が案じて労をとり、そのとりなしで、算哲の父宗順、伯父の定吉が東軍の道案内者になった。大阪落城により道頓と仁兵衛は戦死した。定吉は、久宝寺、大蓮、渋川三ヶ村の代官となり、一族の私費で掘った南堀を浚渫(しゅんせつ)した。且つ道頓の志を追悼し南堀を道頓堀と命名した。 |
「大阪歴史博物館 安井家のルーツ」。
大阪歴史博物館の常設展示室に囲碁史にとっても興味深い展示物がありました。江戸時代の囲碁家元の一つ安井家のルーツが分かる文書が安井家の子孫より寄贈され展示されているのです。安井家初代の安井算哲の息子で初代天文方に就任した渋川春海(二代目安井算哲)が神道を学んだ京都の山崎闇斎を介して大阪の安井九兵衛家へ安井家の系図の調査を行ったやり取りの手紙が展示されています。安井九兵衛家とは初代算哲の叔父で安井道頓の跡を継ぎ大阪の道頓堀を造った安井道卜の家なのです。また、安井家の歴史を調査した渋川春海が作成した家系図も展示されています。
安井氏は清和天皇の流れを汲む河内守護の畠山氏一族で、河内国渋川郡を領有し渋川氏を名乗ります。つまり、二代目安井算哲が渋川春海と名前を変えたのは先祖の姓に戻したということなのです。その後、渋川氏は播磨国の安井郷に移封されたため、安井氏へと姓を変えます。数代後の安井定重の時に、先祖の居城であった河内国久宝寺城へ移り織田信長に誼を通じますが、信長と対立していた石山本願寺・一向一揆衆によって久宝寺城は陥落。定重も討ち死にします。この定重の弟・定次は信長、そして豊臣秀吉に仕えますが定次の息子が秀吉の命により道頓堀を開削した安井道頓だと言われています。また、安井定重にはもう一人の弟・定正がいて、その息子の一人が安井道卜といって道頓堀開削の道半ばで亡くなった道頓の跡を継ぎ堀を完成させた人物です。そして、安井道卜の甥こそが初代安井算哲なのです。
大阪歴史博物館:大阪市中央区大手前4丁目1-32
|
|
| 【「家康と算哲の囲碁掛け合い」】 |
次のような興味深い「家康と算哲の囲碁掛け合い」が残されている。
| 「或る時、算哲が家康と碁を打ちながら云った。『この石は活きているとおぼし召すか、死んでいるとおぼし召すか』。家康は暫く考え込み、『どうも死んでいるように思われる』と答えた。算哲『しからば存分に殺してご覧じませ。それがしは活きてお目にかけませう』。家康がその石を殺しにかかったところ、算哲の応答で造作なく活きた。『なるほど活きたか。死んでいる石とばかり思ったぞ』。算哲『いやいや、まだ決着のところは分明には御座りませぬ。御所様がまこと活きているとおぼし召すなら、それがしが攻めて殺して御目にかけませう』。今度は家康が活きにかかったが、算哲が造作もなく殺してしまった。家康『これは稀代じゃ。活きと死にと、いずれが正しいのじゃ』。算哲『活きると仰せあれば死に、死ぬると仰せあれば活きる。即ち死中の活の妙機秘奥、詳しくは口伝に譲り申し候』」。 |
|
| 1615(慶長20、元和元)年、7.13日、元和改元。 |
| 大阪夏の陣。豊臣家滅亡。 |
| 家康が先の五十石五人扶持のほか、特に算砂に終身三百石を与う。 |
| 【算砂が、加賀藩に招かれ以降2年間、囲碁指南役として過ごす】 |
| 本因坊算砂が、加賀藩3代藩主、前田利常に招かれ、法弟本照坊日至を伴って金沢に赴き、首席家宅・本多邸に滞在する。以降2年間、囲碁指南役として過ごす。1617年(元和3年)、藩の寄進で本行寺(ほんぎょうじ、日蓮宗、金沢、本多)を創建した後、帰洛する。本因坊算砂は、激動する戦国の世を生き抜き、後世の碁界に多くの遺産を残すことになる。 |
| 1616(元和2)年、。 |
1月、徳川家康が鷹狩に出た先で倒れた。
4.17日、駿府城において死亡した(享年75歳)。 |
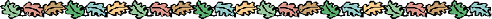



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)