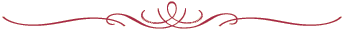
| 「れんだいこの著作権法論評」、悪法式読み取りとなぜ闘わねばならないのか |
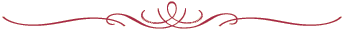
(最新見直し2007.3.5日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「著作権法の悪法式読み取りとなぜ闘わねばならないのか」、本サイトでこれを愚考してみることにする。その趣意は既に「著作権(表現の自由)保障協会」を立ち上げよ」でも述べたが再確認しておく。 端的な理由としては、「著作権法の悪法式読み取り」がサヨ族に多用され、「左」からの言論弾圧を招いているからである。我々は圧倒的に知識不足であり、まだまだ学ばねばならないことが多過ぎるこの局面で、知の摂取制限を為す如何なる企てにも反対せねばならない。これが我々の態度となるべきである。 著作権法の本質については、「『ヒトラー古記事問題』で見えてくる著作権の本質」で解析した。著作権問題を研究すれば、強権著作権はいわゆるユダヤ商法がもたらしているものであり、本来蓄財の道具にしてはならない知の領域まで押し拡げようとする知の対価理論であることが判明する。更に、その流れが、近現代史の裏権力である国際金融資本帝国ネオ・シオニストの「愚民化アジェンダ」(行動綱領)に通底していることが判明する。故に、我々は自律自存を賭けて強権著作権悪法と断じて闘わなければならない。 サヨとは何かに就いては、「左翼とは何か、ハト派とは何か、サヨとは何か考」で解析した。彼らは、正義の美名で強権著作権論を振り回すから始末が悪い。左派の理論を戴きながら「愚民化アジェンダ」に長期的に加担し得るのは、かなり変態嗜好の持主でなければ難しい。それはともかくも、著作権法の拡大解釈適用が新たな言論弾圧手段となっていることを認識し、これと闘う理論を構築せねばならない。かく問題意識が共有できれば、本サイトの使命が半ば達成されたことになる。 ごく最近、著作権法は、歴史的な闘争を端的に具現しており、それはかの昔のイエスとパリサイ派の論争の尾を引いているということに気づいた。著作権抑制派はイエスの御教えの流れを汲むものであり、著作権強権派はユダヤ教パリサイ派の拝金蓄財主義の流れを汲むものである。この両者はレールが違うから交わることは無い。してみれば、著作権法を廻る人民派と強権派の闘いは永遠の抗争になるだろう。そういうことに気づいたので追加しておく。 以上述べても通じない輩にもっと分かり易く追補しておく。我々は、非常に限られた情報で思想や史観や見解を編み出さねばならない状況の中にある。願うらくはもっと豊かに実証的な情報である。これを享受できるように智恵を働かせるべきで逆に向かうべきではない。著作権問題ではこれが公理となるべきである。この観点さえ保持すれば、問題は解ける。 2006.9.20日、2007.3.5日再編集 れんだいこ拝 |
| 【著作権の基本法理】 |
| ウェブ原野に著作権杭を打ち込んで囲い込みせんとする小賢しい輩が害悪を流し込みつつある。何食わぬ顔で史上のおいしいとこのタダ取りはするが、自作物には関所を設け関税を課そうとする。これを仮に「関所関税型著作権論」と命名する。それがオマンマ系の止むに止まれぬ分野にならまだしも、思想だとか政治だとかボランティアの世界でも「関所関税型著作権論」を導入しようとする。その癖云うことにそれが社会正義だと。馬鹿も休み休み言い給え。そういうウヨサヨ各界の正義仮面の不義を撃ってみたい。 ここにきてウェブ上の著作権を廻る紛争が目立ち始めた。今や、掲示板に対する著作権規制も為されてきそうな勢いである。サヨ勢力がご丁寧にもこの動きを後押ししているように見える。:これがサヨの偽らざる生態である。連中は、権利万能市民社会万歳という訳だろうか。その無原則ぶりを見れば恐らく究極、文字という文字の全てに著作権を付与し、会話するにも一々断り書きせねばならぬ不自由権利社会へ誘ってくれるのだろう。 こういう状況にあって、そも著作権法に関するスタンスをどう構図すべきだろうかと自問自答しながら次のように考えることにした。著作権法以前の社会的合意として、全て活字及び考案物に対しては関与者の権利がひとまずA・自然権的に認められる。この権利は、1・対象内容(客体)、2・その形態、3・主体によって区分認識される。 但し、それが法的権利として保護されるためには、法的権利化には馴染まない自然権もある故にいくつかの要件をクリヤーしなければならない。つまり、この時点でふるいにかけられる。次に、B・社会権としての著作権が認められる為の要件の考察が必要であろう。このように論を積み立てて行くべきではなかろうか。 【1・権利の客体(対象内容)】は、美術工芸品か詩歌音曲か小説か学術等の私的創作物か、政治・宗教・思想・評論等すぐれて公共的なものかに分岐しよう。これら客体の差は、その違いに応じて著作権法上の権利保護範囲が異なるべきではなかろうか。 【2・権利の形態】は、活字製本その他工作物として立ち表われるものか、最新のウェブサイトのように主として閲覧に供されるものか、ウェブ掲示板のように議論用のもので、引用・転載無しには一歩も先へ進まないもの、等々に分岐しよう。これら形態の差は、その違いに応じて著作権法上の権利保護範囲が異なるべきではなかろうか。 【3・権利の主体】は、個人か組織かレッセフェール式企業か官営企業か政党か宗教法人か行政当局かに分岐しよう。中にはマスコミ機関のように広範囲にまたがる特殊団体も存在する。これら主体の差は、その違いに応じて著作権法上の権利保護範囲が異なるべきではなかろうか。 こうした問いかけに対する真摯な検討も無く著作権が一人歩きさせられようとしている。その様はあたかも「小人閉居して不善を為す」が如くに「駄弁にまで著作権を認めよ」と迫りつつある。 こういう御仁は考えてみよ。仮に、医療分野で同様の権利を発生させたらどうなるか。手術にせよ処方箋にせよ幾十人百人の了解とパテント料を払わねば何も為しえず、患者は気の遠くなる手続きの過程であたら惜しくも手遅れになるケースが続出するであろう。さすがにと云うべきか医の分野ではそうした馬鹿げたことは起っていない。あるいは世の発明的特許において、これを権利で囲わず、市井の役に立てばそれで良いとした幾多の美談功績があり、我々はそのお陰を受けている。 それを思えば、近時の著作権亡者どもの戯言は、文の分野に巣くう人士の特に貧困なる精神系側からの見境いの無い申し出としか言いようが無かろう。もう一つ思うに、政治的分野での著作権亡者に日共系の者が多いという感じがする。偶然か必然かまでは分からないが、白い心で紅い話を得手とする人種に憑きものの現象のような気がする。 結論として、云わずもがなのことではあるが、強権著作権法は、近時の著作権の強権化には「ゴイム愚民化」を目指すネオ・シオニズムの狡知が働いており、彼らが裏で糸をひいており、ウヨサヨが太鼓を叩いて生み出しつつあるものである。こう認識すべきであろう。このことに無自覚なまま唱和する者が多過ぎる。 2002.10.26日、2006.12.29日再編集 れんだいこ拝 |
| 【著作権問題の要諦】 | |
2006.9.19日付毎日新聞「余禄」の「竹中平蔵総務相が小泉純一郎首相に…」の文中に、次のような文章がある。
れんだいこは、今や新聞各社が著作権を押し出し、無断での記事引用、転載厳禁としている折柄で、「余禄」執筆者が能天気にもかように述べているのが滑稽と思う。云っていることはまさに正論で、学者であろうが政治家であろうが市井の一人であろうが、良い文章や発言はそれ自体が世間に広まる事を名誉とする。この正論が通りにくい世の中になりつつあり、よりによってジャーナリズムがこれを後押ししている。本来広め役が押え役に廻るという倒錯現象が生まれている。そういう役割の只中に有る者が正論ぶっていることが滑稽であり、稚気であると思う。 そのことはともかく情報は伝えられることを求め、本当の思想は共認を求めて広がることないしは広められることを悦ぶ。これが思想の習性である。我々の身体機能も相互にネットワーク化しており、そのようになっているが、外界の社会も基本的には同じ構造になっていると看做すべきだろう。従って、コミュニケーションが抑圧されることを嫌う。欲深な独り占めと排他を最も嫌う。 しかるに最近、思想の伝播を妨げるために著作権法が悪用されつつある。旧著作権法と現代著作権法の違いはここにある。著作権法理解に当って、まずこの事態認識が踏まえねばならない。しかして、著作権法が情報閉塞の関所手段として使われていることに断乎として抗議せねばならない。サヨ族がその先兵となって情報閉塞化の旗振りをしている事を見極め、彼らの社会的正体を剥がさねばならない。まず、このスタンスが確立されねばならない。 最近の著作権問題の急所は、ネオ・シオニズムの愚民化政策を嗅ぎ取ることにある。これに気難し屋が追従し、訳の分からないヌエ正義論で事を混ぜ返していることを知ることにある。ネオ・シオニズムは隠れて良からぬ事を企むので、直に相手することはできない。とすれば、しゃしゃり出てくる気難しい屋と対決せざるを得ない。そういう訳で、我々は、事の理非曲直を弁え、ヌエ正義論を排斥する能力を持たなければならない。気難しい屋は、自分の弁舌の意味するものが自分の首を絞めていることさえ分からないまま言葉に陶酔する癖を持つ。普通の会話が通じないので、断乎退けるに如かずであろう。くれぐれも誤魔化されるな。 著作権問題の要諦は、A・著作権化する以前の「自律的共同著作マナールールの確立」、B・それを踏まえての社会的最小限著作権法の範囲の確立、C・著作権法と全方位全域著作権論の峻別、D・英知により強権著作権論の排除、を為すことにある。目下はこの識別混同が甚だしいように思われる。 論の積み上げ式として、1・レッセフェール式自然状態→2・マナールールの確立→3・著作権への移行→4・著作権化させない弁え→5・どうしても追加せねばならない著作権の策定という風に捉え、それぞれの段階で包摂されるべき諸権利を明確にさせ、最終の著作権法で法益とされる権利を絞り込み、その絞られた著作権法に対しては最高度な社会的権利として穏やかに保全する、という論理の流れを確認する必要があるのでは無かろうか。 なるほど社会がより高度複雑化していることに原因があるとは云え、それぞれに専門家がいる訳だからしてこれに対応できないというのは由々しき知の退歩では無かろうか。というか、いつの世も後追いかも知れないことを思えば、現代的課題として立ちはだかっており、いずれの日か解明を要するという只中なのかも知れない。 上述の流れに対して、近時の傾向は、「1・レッセフェール式自然状態」→「2・マナールールの確立」、「3・著作権への移行」、「4・著作権化させない弁え」をいきなり飛び越して、5・どうしても追加せねばならない著作権の策定を「5・全方位全域著作権論」への移行へとすり替えようとしている。為に、法律用語の概念、その規定が厳密さを失い、恣意的解釈が一人歩きし始めているように思われる。 れんだいこの見立てるところ、この連中の弁によれば、厳密に様式要求されている特許法は尻尾を巻いて退散せざるを得ない。何しろ著作権は何の審査も要せず、最も簡単横着にして云い得云い勝ちで権利取得でき、粗暴にして攻撃的な刃物的権利になっている次第である。 そういう著作権刃物を振り回す連中は、自称「民間ネット護民官」にして実は「民間ネット警察」の役割を担おうとしている。誰も頼んではいないのに警察的な目で市民活動の取り締まりに向い始めている。通常これらをウヨサヨというらしい。連中は性格的に好きなのだろうから今後もそういうおせっかいを焼き続けるだろう。 れんだいこがお願いすることは次のことである。頼むから説教だけはせんでくれ。お前たちは邪悪な意図を持って勝手に刃物を振り回しているだけで、それが正義などとはおこがまし過ぎる。そうか、世の中は、そういう悪が先生ぶるとしたものか。そうか、それなら次のように云い直さねばならない。正義面して説教する「白痴著作権論」に抗せよ! 2003.4.22日、2006.10.10日再編集 れんだいこ拝 |
| 【全方位全域著作権論を許すな】 |
| 著作権法が誕生した経緯にはそれなりの合理的理由がある。れんだいこはそれは認める。しかし、その当初極めて限定的な権利化で始まった。それにも正当な理由がある。そこを認めても良いとは思う。ところが近時、無限定全方位全域包括式の著作権が乱舞し始め、もはや誰もこれを止められない。 これにより人類の知恵が退化せしめられようとしているとなると我慢できない。これが偶然ならまだしも、意図的に仕掛けられている可能性さえある。通りで国際政治を見ても、マスコミに登場するコメンテーターの論理と論法を聞けば野蛮時代に突入した感がある。連中の愚論が容れられるとすれば、相対的に頭脳の背丈が低くなったのではなかろうか。 れんだいこが「近時の著作権理解」となぜ闘わねばならないと考えているのか。述べたようにこの如意棒が振り回されれば振り回されるほど文化文明が衰退することを憂うからである。例えて云えば、著作権は「文明のシロアリ理論」に他ならないからである。この「文明のシロアリ理論」は、人民大衆の知育を妨げ、つまり愚民化に資し、認識の共有を阻害するからである。 ちなみに、「認識の共有」は自由な議論の交差を通してしか生まれない。これを対話弁証法と云う。別の言葉で表現すれば、稽古弁証法とも云える。現代著作権法的理解は、対話とその稽古を妨げる。人間の認識は、不断の対話と稽古によってしか進歩しない。現代の著作権法的理解は、これを妨げる。よって、我々は、著作権理解を正しく制御する知恵を身に付けねばならない。その為には、合理的な著作権法を再確定せねばならぬであろう。 その際の基準は、その権利化によって人類の脳のシワを増やす方向になるのか、のっぺらツルツルにさせてしまうのかの見極めが当てられるべきであろう。何ゆえこの基準を持ち出すのか。それは、現代社会には国際的愚民化のワナが仕掛けられているからである。故意か偶然かまでは論評しない。汚染されていることははっきりしている。いずれ仕掛けた方も相互作用でのっぺらツルツルになってしまうのだが、そこまでは思い至っていないのだろう。 それはともかく、そういう理由によって、著作権法の現代的展開の危険な傾向について騒がねばならない。科学技術の発展の成果が全く生かされていないと思うから。深く考えもせず、方位除け占い師の如くに著作権師を登場させ、会話一つがギクシャクするような社会への突入に音頭とることは厳に戒めねばならない。近時のこういう傾向を未然に防がねばならない。著作権法問題は、勝れて政治性の強いものであることが弁えられねばならない。 れんだいこの趣旨が良く分からない者は次のように簡単に合点すればよい。現代著作権法的理解の全域全方位著作権論は新たな規制である。規制は少なければ少ないほど良い。我々が広げるべきは、自由・自主・自律的空間である。よって、規制強化に反対の態度を打ち出すべきである。近時の著作権論の本質はここにある。規制を撤廃せよ、こう得心すれば良い。 2004.9.5日、2006.10.21日再編集 れんだいこ拝 |
| 【「引用、転載」考の前置きとしての「著作権法の歴史的性格」について】 |
| 著作権法につき法理論的に考察してみたい。 まず、日本国憲法における該当条文を確認する。「第三章 国民の権利及び義務」の章の第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」のうちの「自由及び幸福追求権」、第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」の「思想及び良心の自由」。第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」の「言論、出版その他一切の表現の自由」が関連条項であるように思われる。 しかしながら、日本国憲法のこれらの規定は、市民(国民)対国家間の権利規定であり、市民(国民)相互間の「協調と利害の関係処理規定」とはなっていない。著作権問題は主として市民対市民間の権利規定であるから、つまり民間の利害に関する規定を憲法から直接的に導き出すのは難しいと、いうことが云えるように思われる。 但し、憲法が、個人の自由及び幸福追求として、思想及び良心の自由として、出版その他一切の表現の自由を保障している訳であるから、大枠としてこれに反する下位法を成文化することはできず、下位法はこの大枠に添って法文化されねばならす、そういう意味で当初の著作権法はこの大枠に添って条文化されている、と解するのが相当と思われる。 1970(昭和45).5.6日付けで「著作権法」が制定され、「著作権を廻る市民(国民)相互間の協調と利害の関係処理規定」が為された。これが、著作権問題を廻っての憲法の間隙を埋める直接の下位法であり、いわば著作権法は「著作権を廻る憲法」とも云える位置づけとなっている。れんだいこは仮に「ハト派時代の著作権法」と見立てている。 但し、時代は更にめまぐるしく廻る。この当時の著作権が対象としていたのは主として書籍、新聞記事、その他広報的印刷物等いわば「古典的著作物」であり、後にテープ、レコード等を含むようになるものの、今日的なインターネット媒体つまり「最新的な著作」を前提としていない恨みがある。そういう訳で、その後続々と新条文が付加されてきている。 留意すべきは、新条文が「ハト派時代の著作権法」に単なる接木したのならまだしも、理念思想的に齟齬している条文事例が多過ぎることである。こうなると、戦後憲法同様に「ハト派時代の著作権法」がどんどん骨抜きにされ、今や別種の「タカ派時代の著作権法」とでも云えるものに変質していることである。戦後憲法と日米安全保障法が共存競合している如く、著作権法もまた「ハト派時代の著作権法」と「タカ派時代の著作権法」が共存競合しつつある。 という訳で、著作権法につき思想的に考察してみたい。 最近のなし崩し的な著作権乱用の問題性が議論されていないように思われる。それは、各条項の技術的問題というよりそれ以前の著作権法の思想的問題のことを指しているのだが、これを議論せぬままに各条項の規定内容のみが解釈されているように思える。れんだいこは、「著作権法論評」、「著作権法での主要な論争点」、「著作権問題の一視角」でアプローチしようとしているがまだ十分には練成されていない。 どういうことかというと、著作権とは頭脳労働に対する私有財産制の導入であり、その是非が論議されねばならない、という文明的問題が介在しているにも拘らず、「頭脳労働に対する私有財産制導入の是非」を論議せぬまま、むやみやたらに条項が継ぎ足され始めている近時の傾向に対して追認と解釈ばかりで良いのか、「待てよ」と考える経路が必要であるのではないのか、ということが云いたい訳である。 この観点から見るとき、市井の著作権者の「あれもこれも規定せよ。規定の多ければ多いほど先進国であり、逆は野蛮を意味する」なる論調からの要請に対し、かっての法文担当官僚がそれを鵜呑みにせず一定のブレーキを掛けてきた見識が見えてくる。それはむしろ当時の官僚の頭脳の健全さを示している、とれんだいこは看做している。これがハト派時代の官僚の優秀さであった。 しかし、次第に防波堤が崩され、ごく最近では不恰好な体裁で次から次へと法文が増やされてきているようにも思える。この現象過程には官僚頭脳の変質が認められ、「彼らの思想が萎えている」ことを証しているのではないか、とれんだいこは考えている。これがタカ派時代の官僚の頭脳貧困によりもたらされている。 いずれの日か、ここら辺りを対象とした考察をしてみたい。 2006.10.10日再編集 れんだいこ拝 |
| 【「著作権法上保護されないもの」について】 | |
| 一般に、著作権は活字という活字に権利付与していると思われがちであるが、旧著作権法の法文作成者は次のことに付き抑制させている。実際の著作権は多分野での著作権を認めているので、ここでは簡略にするため「活字系」のものにターゲットを絞って論ずる事にする。これを踏まえて論ずれば次のように規定されている。 著作権法第2条その1で「保護される著作物の範囲」を示しているが、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」としている。この国語的解釈も多岐に分かれるように思われるが、れんだいこは、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであって」、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と解釈すべきではないかと思っている。 これによれば、著作権法上保護されるものは「活字でありさえすれば全て著作権保護の対象になる」というようなものではないということになる。更に云えば、「政治、宗教、思想、哲学」的な分野は著作権法に馴染まない」として法の適用を控えているのではないか、と考えられる。ここのところが弁えられず、著作物即著作権なる解釈で、著作権全方面全域適用を強行に主張する手合いが居る。彼らは、法律の条文を読解する知性が欠けているとしか云いようがない。 なお、同条その19で、「頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする」とある。この規定は、主として書物的著作物を対象とした規定であり、インターネットサイトに対する規定としては不向きなものとなっているように思われる。 同第10条で、「保護される著作物の対象」を示している。「活字系」のものにターゲットを絞って論ずるとしてこれをみれば、「一、小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」、「二、音楽の著作物」が指定されている。この国語的解釈も多岐に分かれるように思われるが、れんだいこは、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」という規定に注目する。 単に「論文」と明記されているところが曖昧であるが、凡そ「非政治的、非宗教的、非思想的、非哲学的なそれら」という言外の意味が込められているのでは無かろうかと解する。この識別は、著作権の及ぶ範囲を認識する上で重要と思われる。 注目すべきは、その2で、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」としていることである。この国語的解釈も多岐に分かれるように思われるが、れんだいこは、「新聞、雑誌などの事実の伝達にすぎない報道は、極力著作権保護から排除する」旨の表記ではないかと解する。つまり、著作権法は何から何まで保護規定しようとしているのではなく、「抑制的であることが弁えられている」ことを察するべきではなかろうか。 しかしながら、「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」は、れんだいこ的な解釈を徹頭徹尾排斥して次のように述べている。
しかし、日本新聞協会編集委的解釈はあまりにもギルド利権的では無かろうか。れんだいこは、本来の法の趣旨と反する解釈をしていると見る。「記者の個性作動論」をもってすれば、あらゆる記事に著作権を被せることができ、「単純な事実を伝える記事には著作権を適用しない」という法の趣旨を骨抜きにすることができる。これを公然とぶっている日本新聞協会編集委的解釈はオーバーランしているのではなかろうか。 ちなみに、日本新聞協会編集委がこのように著作権万能棒を振り回すのであれば、あらゆるプレス的特権が剥がされねば却って不公平だろう。例えば、首相の記者会見時などにおいては、公正な入札制度による機会均等的取材システムが確立されねば「特権取材による取材勝ち著作権」を許すことになろう。現にそうなっているのであるが。 著作権法は賢明にも抑制的であるから次のようにも記している。第13条で「権利の目的とならない著作物」を掲げ、「憲法その他の法令」、概要「行政機関の発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」、概要「裁判所の判決、決定、命令その他」、概要「行政機関が作成したこれらの翻訳物及び編集物」。 れんだいこは更にこう思う。著作権法は明確には規定していないが、フィクション系の創作物には著作権法を適用している。しかし、ノンフィクション系のもの例えば歴史書、思想、宗教の類の分野に於いては、条文化していないことでもって暗黙の非適用を示唆していないだろうか。実際に、歴史書、思想、宗教の類の分野に於いて著作権を適用すれば、学ぶこと、練磨することが非常に出来にくくなろう。そういう弁えから条文化することを抑制していると受け取るべきではなかろうか。 以上の様に著作権の及ぶ範囲が絞られている様を見ておく必要がある。 2005.11.25日再編集 れんだいこ拝 |
| 【「著作権法上の弁え」と近時の全域的万能著作権主張者について】 |
| まとめとして確認しておくべきことは、では、本来の著作権法が何故に「政治、宗教、思想、哲学的な分野は著作権法に馴染まない」と弁えしてきたのか、その理由を尋ねることであろう。それは偏(ひとえ)に、「それらが本質的に共同共認的なものであり、相互の議論練成、練磨を要請しており、その故の産物であり、これらは個人の思惟的産物として権利主張させるべきものではない、馴染まない」という認識に拠っているのではあるまいか。 現代著作権論による全域的万能著作権主張者にはこのことの弁えが無く、為に勘違い的自己都合的権利意識を芽生えさせ、それが為に非常に精緻な著作権法作りに勤しんでいるように思える、しかしその道は百害あって一利無しの不毛の道と考える。 これを考えるのに、諺(ことわざ)を例に挙げれば分かりやすい。諺は古今東西の優れた言い伝えであるが、これがあるために人間相互間の意思疎通に非常に便宜なものとなっている。今仮に、諺に著作権を導入したらどういう事態になるであろうか。一々誰それのどこそこへ記されている云々と断り書きしつつやり取りが為されねばならないとしたら不都合極まるであろう。我々は誰しも諺の無償無規制のやり取りという恩恵を受けた上で意思疎通を堪能している。 しかし、もう少し考えてみれば、諺段階に至らない定型句あるいは類似の思惟も又多少なりとも諺的便宜を提供しているのではあるまいか。それを相互に無償無規制でやり取りし得ているからこそ便宜を得ている訳である。つまり、我々には「人類史に於ける相互無償共有財産域」というものがあり、これは著作権法を適用させてはならない領域であるということを賢くも知るべきではなかろうか。 最近気づいたことに、その昔卒業式で歌われた「仰げば尊し」も作者不詳である。よって著作権侵害の心配なく唱歌されている。世の中にはこういう恩恵で満ち満ちているのではなかろうか。 ところが、近時の全域的万能著作権主張者はこのことを全く弁えず、規制が無いこの分野に対して規制が無い故に遅れているとでも錯覚し、あたかも正義気取りで規制の網を被せようとしている。日本新聞協会編集委然り、政党然り、学術団体然りで、近頃は図書館までがそのあおりを受けて率先して著作権的取り込みに励んでいる。 その姿は既に滑稽でもあろう。付ける薬が無い連中であることが判明しよう。何の知識人であるものかは。自称だけの、槍で知識の藪を突いて獲物を取ろうとする野蛮人そのものではなかろうか。本質的に愚昧な者が下手に知識を得ると、余計に馬鹿になる。というより危険な馬鹿になる見本ではなかろうか。 なぜ「政治、宗教、思想、哲学的な分野は著作権法に馴染まない」と弁えしてきたのか、その理由を考える便宜理論を思いついたので書き留めておく。仮に囲碁、将棋の例で考えてみよう。それらには古人より伝承されてきた技芸としての定石というものがある。この定石は今日に於いても発展系で次々新型定石が生み出されている。今仮に、この種の定石に著作権を被せたとしたらどうなるか。囲碁、将棋に興ずるのに厄介なことになりはすまいか。技芸としての囲碁、将棋の自殺行為ではなかろうか。 囲碁、将棋の棋院はさすがに賢明で、今のところ棋譜に著作権を被せる愚は採っていない。否最近は著作権を主張し始めたかも知れない。しかに、どんなに転ぼうと石の運び、駒の動きの定石に著作権を被せることはしないだろう。これをやれば忽ち囲碁、将棋がゲームとして成り立たなくなることを知っている筈だから。 ところで、政治、宗教、思想、哲学的な分野に著作権法を被せようとする全方位全域著作権論は、そういう愚を犯そうとしているのではなかろうか。この観点、この記述は俺の著作権であるが故に、今後は俺の断りなしには使用させないという主張は、定石に著作権を被せようとするものではなかろうか。 誰もそういうことは主張していないというなかれ。れんだいこの見るところ、引用・転載のルールとマナーの指摘を超えて、出典ないし出所明示の引用・転載であるにも関わらず盗用呼ばわりする輩には共通してこの種の野蛮な主張が認められる。甚だしきは、自分が編み出した定石ではなく、他人の定石の目先を少し変えて開示しているに過ぎないその種のものに対してさえも盗用呼ばわりする輩がいることである。 これを満座の中でやるものだからいずれ恥をかくのは当人だろうが、弁えが無いものだから未だ正論ぶっている。れんだいこは、恥をかかすのは嫌だから特段の遣り取りは控えているが、常識を欠損させた漬ける薬が無い手合いであろうぐらいには思っている。驚くことはこの種のエセインテリが跋扈しすぎていることである。 2005.11.25日再編集、2007.3.5日再編集 れんだいこ拝 |
| 【逮捕されない著作権法】 |
| 著作権法の現代的適用について「著作権Q&A」で解説している。膨大すぎて紹介しきれないので、リンク先で確認すれば良い。 |
【「白田教授の著作権の話」】
|
||
著作権法問題について、法政大学社会学部助教授・白田秀彰 (Shirata Hideaki)氏が、「もう一つの著作権の話」で貴重な言及しているのでこれを全文転載しておく。(れんだいこが興味を覚えた箇所につき任意にゴシックにした)
|
||
|
|
| 【「団藤教授の判例談義」考】 | |||
刑事法の神様と云われる東大名誉教授にしてロッキード事件の嘱託尋問調書の扱いを廻る最高裁宣明の時の最高裁判事でもあった団藤重光氏は、退官後の1984年春、学士会で「判例というものについて」と題する講話をした。学士会報の59年度第3号にその速記が掲載された。その一部を引用しておく。
|
|||
|
|
| 【れんだいこは現代強権著作権論の気難しさをからかう】 |
| 「稽古弁証法的発展を阻害する現代強権著作権論の本質」について愚考しておく。我々は、ある事物事象を考究する場合、次の作法に基づいて認識を高めて行く。まずは、基礎情報の収集(骨格)。次に、補足情報の収集(肉付け)。次に、関連情報の収集(彩り)。次に、異論、異端情報の収集(対比)。凡そ以上の精査を経て、何がしかの見立てを生む。これを理論化させて見識を生む。歴史の場合には史観を生む。この作業を高次的に何度も繰り返して、次第に精度の高い認識に至る。判断を生むためには、これほどの作業が必要となる。この道中は、猫の手を借りたいほど忙しいほどの各種情報の摂取と排泄の繰り返しである。人には寿命があり、論には期限があるから、これを高速度でやらねばならない。 ということが理解されるなら、現代強権著作権論者の「要通知要承諾、無断転載、引用御法度論」が如何に有害な理論であるかが分かろう。 我々は、対象に一生懸命取り組んでも正しい認識、史観に辿り着けるかどうか覚束ない。そこへ持ってきて現代強権著作権論者の「要通知要承諾、無断転載、引用御法度論」が振り回されたらどうなるか。良知を生むことは絶望ではないか。そうなると、政府や党中央の言う事はその通りとせざるを得なくなるではないか。政府や党中央が良知に基づき善政を敷く場合は許されても、その保証がどこにあるのか。 かく問えば、現代強権著作権論者が正義ぶって「要通知要承諾、無断転載、引用御法度論」を説けば説くほど、白々しくなるべきではなかろうか。こういう手合いは元々が賢くないのだと思う。そういう連中であるが故に、彼らは、新理論に対して有益理論であるか有害理論であるかどうか見極めることなく単に鵜呑みに学ぶ。その結果、却って訳が分からなくなっているのではなかろうか。馬鹿は学んで余計に馬鹿になるという事例である。最近は、人文系は特にこういう事例に満ち溢れている。 れんだいこが推測するのに、彼らをどう好意的に評しても、彼らは「武家の商法的著作権論」を振り回しているのではなかろうか。彼らが武家の出自であるかどうかとは別であるが、その昔の士農工商社会に於いて、武士は百姓町民に対して高圧的であった。その名残りで今も、「当方の商品を、誰に断って勝手に触っているのか、人づてしているのか」と小難しく理屈をこねる。この小難しさが愚昧な者の特徴である。他方、百姓町民は、「お武家さん、商品を宣伝しようとしたならお金がかかるのが我々の常識です。むしろ喜ぶべきですぞ」と云いたいのを堪えて、「仰せご尤もでございます」と受け答えしていたと思われる。 現代強権著作権論者の正義ぶりっこぶりは、この「武家の商法的著作権論」であるように思われる。事の理非曲直が根本的なところで分かっていない。こういう手合いにはつける薬が無い。問題は、本当の武士は、そういう小難しい理屈を云わなかったところにある。とするなら、「武家の商法的著作権論」を振り回すこの連中は本当の武士でもない。ならば、一体誰が何の為に小難しくしているのだろうか、ということになる。 2007.3.16日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)