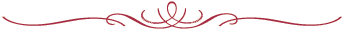
| 善玉菌良質論法/論理学 |
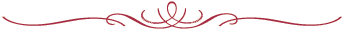
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.1.13日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 論理学の最終系は論法(話法)論理学に至る。「話法」は、弁論コミュニケーションの際に包丁のような切れ味を持つ。習熟するに越したことない。ここでは様々な「良質」論法(話法)を検討する。これを仮に「良質論法論理学」と命名する。これの逆が「悪質論法論理学」である。これについては次章の「【性悪論法】論理学」に記す。それとの対比で学ぶ必要がある。これを学ぶ要件を分かり易く例えれば、世の中では白いものを黒、黒いものを白と言いくるめる論法が流行っている。これに流されず、白いものを白いものとして黒いものを黒いものとして分別する必要がある。この眼力により白いものを黒、黒いものを白と言いくるめる論法に対して抗弁する力を持たねばならない、と云うことになる。 2007.5.30日再編集 れんだいこ拝 |
| 【5W1H話法、れんだいこ式「5W1HRP」話法】 |
| 論理学の「善玉菌良質論法」が最初に取り上げるへきものとして「5W1H法」がある。「5W1H」とは、一般に或る対象を解析する為の常法で、「何時(いつ)(when)、誰が(who)、どこで(where)、何を(what)」の4Wから始まる。これに、「なぜ(why)、どうした(how)」のWHを加える。これを物差し(定規)のように扱って照らしてゆけば、当らずとも遠からずとなる。要するに、「5W1H法」は事象認識の公理としてふまえられなければならないものである。 ところが、世に出てくる解説ものは「WHEN」(いつ)、「WHO」(誰が)、「WHAT」(何を)止まりであることが多い。肝腎の「WHY」(なぜ)、「HOW」(どうした)が抜けている。付け加えれば「REASON」(論拠)、「PROCEED」(経緯)の考察が必要である。これがなければ絵画彫刻で云えば「画竜点睛」を欠いていることになる。これを仮に「5W1HRP」と命名しておく。今後は「5W1HRP」を論証の黄金律としたい。 「WHY(なぜ)」、「HOW(どうした)」、「REASON(論拠)」、「PROCEED(経緯)」のくだりは難しいところであるから評しにくいのは分かる。しかし、ここを評さなければものになるまい。ものにならないまま上ヅラの情報のみで事勿れし、事足りている精神の持主はよほど幸せもんだろう。 |
| 津田左右吉学説考その1 |
| ここで、れんだいこの津田左右吉論を記しておく。過日、今後の古代史研究の方向性を探る為に津田左右吉の諸学説を確認しようと思いネット検索した。確かに「ウィキペディア津田左右吉」を始めとして出るには出てくる。だが津田学説の中身を知ろうとしても一向に分からない。こういう例は何も津田左右吉ばかりではない。極論すればあらゆる情報が表相であり肝腎の知りたいものが出てこない。あたかも「知らしむべからず寄らしむべし」を地で行っている感がある。これがネット情報の限界なのだろうか。政治や思想関係に限って言えば、敢えて入口止まりの情報に止められている気がする。グーグル検索とヤフー検索が次第に似てきており、こうなると情報統制の恐れなしとしない。こういう寒い状況に抗して、この閉塞を打破し、真相を解明し、これを積極的に知らせる為のサイトアップが要請されている。 一般に或る対象を解析する為の常法は「5W1H」である。「WHEN(いつ)」、「WHO(誰が)」、「WHAT(何を)」、「WHY(なぜ)」、「HOW(どうした)」を確認すれば、当らずとも遠からずとなる。ところが、ネット上に出てくるのは「WHEN(いつ)」、「WHO(誰が)」、「WHAT(何を)」止まりであることが多い。肝腎の「WHY(なぜ)」、「HOW(どうした)」が抜けている。更に付け加えれば「REASON(論拠)」、「PROCEED(経緯)」の考察が必要である。これがなければ絵画彫刻で云えば「画竜点睛」を欠いていることになる。これを仮に「5W1HRP」と命名しておく。今後は「5W1HRP」を論証の黄金律としたい。 「れんだいこの実践論理学」 (gengogakuin/jissenronrigaku/jissenronrigaku.htm) 「WHY(なぜ)」、「HOW(どうした)」、「REASON(論拠)」、「PROCEED(経緯)」のくだりは難しいところであるから評しにくいのは分かる。しかし、ここを評さなければものになるまい。ものにならないまま上ヅラの情報のみで事勿れし、事足りている精神の持主はよほど幸せもんだろう。 代わりにご執心なのが著作権である。著作権法によれば、著作者、出典元、出所元等を記し、盗用の恐れのないよう配慮に気をつければ引用転載可と読むべきところ、この規定を超えて事前通知、事前承諾なければ引用転載不可論、他にも文量規制論を公言する手合いが多い。中には引用は可であるが転載はダメ云々と、分かったような訳の分からない理屈をこねる者が後を絶たない。最近はさすがに少なくなったが、ネット上のリンクさえ事前通知、事前承諾の対象とするサイトが存在する。中には営業的利用は不可だが学問的利用は可論を唱える者もいる。しかし、営業的と学問的の仕切りをどこでするのかにつき精密に規定できるものはない、即ち問題を小難しくしているだけのことに過ぎない。 強権的な著作権論を振りまわして著作権森の中から獲物を見つけ出して狩猟に励むよりも、我々の学問水準が大きく立ち遅れていることを憂慮し、この遅れを打開する方向に頭を使うべきだろう。その頭脳がない腹いせ代償行為と思われるが、強権的な著作権論を仕立て上げ強硬的適用で正義ぶる手合いが多い。こういう連中に漬ける薬はないものかと思案しているが、れんだいこが身を持って手本を示すに如かずとして意欲的にサイトアップし続けている。これにより知識を得た者は己の狭い了見による囲い込みの非を恥じ、私も貰うがお返しもするの助け合いの精神に転じ、沃野の開墾に向かい始めるだろう。 分別すべきは我々の寿命である。朝に紅顔ありとも夕べには死す身の者が千年万年の鶴亀の如く生ある身と勘違いして欲心起こすこと勿れ。著作権野郎と、れんだいこおのこと、どちらの云いが生産的か暫し沈思黙考せよ。 |
| 【三段論法】 | ||||||||||||
|
〔論〕〔syllogism〕論法の典型であり、大前提から小前提へ進み、小前提から結論に至るという、二つの前提を順番に接続させて一つの結論を導き出す推理法を云う。
この例のようなものを定言的三段論法と云う。三段論法の大前提、小前提、結論の道筋は、結論を先出しにしても構わない。要するに論理論法のことを云う。その他に、前提に仮言的判断、選言的判断を含むものを、それぞれ仮言的三段論法、選言的三段論法という。 |
| 【起承転結話法(四段論法)】 | ||||||||||||
(代表例)(江戸時代の学者・頼山陽作と云われる) 京の五条の糸屋の娘。姉は十七、妹十五。諸国諸大名は弓矢で殺す。糸屋の娘は目で殺す。 |
| 【消去法話法】 |
| 論理的には、「選言的(結論肯定型)三段論法」と云われる。 |
| 【ドミノ理論(将棋倒し論法)】 |
| 【背理法】 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)