
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.5.2日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
中核派と云うのはなかなか味のある党派であるように思われるので、ここで履歴検証しておく。「ウィキペディア中核派」その他を参照する。
2007.10.20日 れんだいこ拝 |
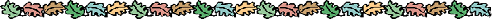
これより以前は、「党史1、結党から本多虐殺まで」で確認する。
| 【中核派が復讐全面戦争突入宣言】 |
| 1975.3.16日、中核派が記者会見。革マル派幹部である黒田寛一、松崎明、土門肇の「革命的処刑」を宣言するなど、革マル派への全面復讐を宣言。中核派の怒りは凄まじく、「革マル派一人残らずの完全殲滅、復讐の全面戦争への突入」を宣言した。「先制的内戦戦略」を確立。警視庁は19日に専従員配置を決定したが、報復は続いた。革マル派は「一方的テロ停止宣言」。しかし内ゲバを完全にやめたわけではなく、また中核派側の攻撃はおさまらず、死者は増えていくばかりとなる。この年だけで15人もの革マル派活動家が殺害された。中核派の「軍事部門」を指揮してきた清水丈夫氏がまとめた統計によると「1973年9.211以来の中核派の対革マル派『赤色テロ』は件数で436戦闘、『完全殲滅』(死亡)43人、そのうち、75年3.14(革マル派による本多殺害)以後の革マル派の死亡は31人」。革マル派と解放派の抗争の死者を併せて「内ゲバ戦争」は百名近くの死者を出した。しかし、現在に至るまで3氏の「革命的処刑」は実現していない(黒田は2006年に80歳で病気で死去。中核派は「恥多き死を強制した」と称している)。 |
| 北小路敏が、カクマルによる本多延嘉書記長虐殺をのりこえ、70~80年代を通して、権力・カクマルとの二重の内戦を革共同の前面に立って指導し抜く。革共同政治集会での基調報告は少なくとも70年代に30回、80年代に20回に及ぶ。 |
3.20日、革マル派の岡本良治及び中島章ら3名が潜伏していた荒川区東日暮里今村のマンションに、中核派が鉄製の三段式のはしごで侵入。3名をバールで殴打し殺害。
3.27日、革マル派の川崎市職・西田はるみが神奈川県川崎市役所裏で鉄パイプで襲撃され死亡。初の女性死者。
4.1日、革マル派千葉県委員長・船崎新が東京都墨田区内の喫茶店で殺害される。
9.4日、中核派活動家が横須賀緑荘アジトで爆弾を製造しているところ、誤って爆発させ、同アパート住人2名が死亡(中核派活動家も3名死亡)した。
1977年、北小路敏が、三里塚開港阻止の決戦を反対同盟・戸村一作委員長とともに闘う。動労千葉のジェット燃料輸送阻止闘争を全力で支援し、ともに闘う。
1978年、車両基地に停車していた京成電鉄のスカイライナーAE型に時限発火装置を仕掛けて全焼させるテロ事件を起こす(京成スカイライナー放火事件)。
1979.3月、動労千葉が動労本部から分離独立。北小路敏が、動労千葉の分離・独立に際し、動労本部カクマルの襲撃から動労千葉を防衛するために闘う。
1980年、対革マル戦争を担いロンドンに亡命していた上口孝夫が帰国し、正統本多派と称して「『勝利に向っての試練』編集委員会」(試練派)を立ち上げ、中核派から分裂する。(後に試練派は1983年、第四インターに近づくが失敗し、86年に「第四インターナショナル・ボルシェヴィキ派(準備委員会)」(ボル派)を結成し、機関誌『ボルシェヴィキ』を創刊した)
革マル派との内ゲバも、80年代に入ると国鉄分割民営化をめぐる対立で動労幹部などを殺害するなど激しく続いた。
中核派は、80年代に入ってテロ・ゲリラにその活路を見出していくようになった。同派はこれまでに、建設省(現・国土交通省)幹部宅や新東京国際空港公団(現・成田国際空港株式会社)職員宅などに対する放火・放火未遂ゲリラ事件、自由民主党本部や鉄道施設などを狙った火炎瓶や火炎放射器を用いた放火ゲリラ事件などを引き起こしている。
1981年、日帝の三里塚二期開港攻撃と国鉄分割・民営化攻撃の切迫にたいして、革共同は先制的内戦戦略フェーズⅡ(第2段階)への転換をもって対権力闘争の飛躍をかちとっていった。国鉄・三里塚決戦に全面的に突入。
1983.3.8日、主に「一坪再共有化運動」の是非をめぐって三里塚・芝山連合空港反対同盟が分裂。1980年代に入ると、三里塚闘争で、「一坪再共有化運動」の是非をめぐって反対同盟内部での対立が激化し反対・賛成両派が分裂した。共有化運動を推進したのは熱田派と呼ばれ、第四インター派らが支持。共有化運動を「土地の売り渡し」「金儲け運動」として反対したのは北原派で、中核派・革労協狭間派らが支持した。反対同盟内部の対立はそれぞれの支援党派の対立に発展してゆく。中核派は、第四インター派を「公団に土地を売り渡そうとする新しい型の反革命」と規定した。
6.7日、千葉県四街道市の成田空港関連の航空燃料用パイプライン敷設工事現場の飯場に放火して労働者2名を焼死させている。このような一般人の巻き添えのについて、中核派は未だ一つとして被害者遺族らに謝罪も賠償もしていない。
中核派は、第四インター派を「公団に土地を売り渡そうとする新しい型の反革命」と規定した。そして1984.1月、全国一斉に五箇所の第四インター派メンバー宅を襲撃、一人に頭蓋骨陥没させる重傷を負わせる。7月、ふたたび一斉に三箇所の第四インター派メンバー宅を襲撃した。一人に片足切断の重傷を負わせる。
前進紙上でこのテロの「戦果」を発表した際には、襲撃した第四インター派メンバーの本名と職場、そして地番までの住所を掲載した。さらに中核派は、第四インター派のメンバーや「熱田派」所属の空港反対派農家、あるいは「一坪共有者」の自宅や勤務先に押しかけたり、脅迫電話を掛けて「次はお前だ」などと組織的に恫喝を展開する。
このテロに対しては激しい批判が集中した。のちに中核派を離脱した小西誠によると中核派組織内においてすら批判的な声は少なくなかったが、指導部の「批判するものは組織を去れ」という統制によって中核派内部の批判が公然化することはなかったという。
1984.1月、全国一斉に五箇所の第四インター派メンバー宅を襲撃。一人に頭蓋骨陥没させる重傷を負わせる。
1984.7月、全国一斉にふたたび三箇所の第四インター派メンバー宅を襲撃。一人に片足切断の重傷を負わせる。
9.19日、中核派の地下軍事組織である「人民革命軍」が、火炎放射器で自由民主党の本部を襲撃。本部ビルの一部を焼失させる(自由民主党本部放火襲撃事件)。 実行犯として中核派活動家1人が逮捕されたが、後の裁判で無罪が確定している。1985年頃からは圧力釜爆弾や飛距離数キロメートルに及ぶ迫撃弾も使用するようになった。
1985.10.20日、 三里塚第一公園での集会後、三里塚交差点付近で、丸太、鉄パイプ、火炎瓶などを武器に、機動隊と大規模衝突を起こす。機動隊員数人に重軽傷を負わせたほか、活動家らが多数逮捕される(10.20成田現地闘争)。
1985.10-11月、三里塚二期決戦と国鉄分割・民営化阻止決戦を武装闘争として貫徹した。
1985年、北小路敏が、中曽根政権による三里塚二期攻撃の激化と国鉄分割・民営化攻撃に対し、全国の学生・労働者の力を結集して一大決戦を爆発させる。その後も一貫して、日帝の戦争・改憲攻撃との対決、とりわけ三里塚・沖縄闘争と国鉄闘争の前進と勝利のために心血を注ぐ。10月、三里塚2期着工阻止決戦。11月、国鉄分割・民営化反対で動労千葉がスト突入。
1985.11.29日、首都圏・大阪地区の国電運転線区で同時多発的に通信ケーブルを切断。さらに、浅草橋駅を占拠し、放火(国電同時多発ゲリラ事件)。以降、街頭実力闘争は行っていない。1985年頃からは圧力釜爆弾や飛距離数キロメートルに及ぶ迫撃弾も使用するようになった。以降、街頭実力闘争は行っていない。
1986.1.20日、京都大学で、中核派全学連の副委員長代行を務めていた福島慎一郎が、京大教養部構内で、一般学生に扮した数人の革マル派武闘派の鉄パイプによる襲撃で白昼殺害される。
4.15日、中核派活動家の福嶋昌男らが、在日米軍の横田飛行場を狙って、車の荷台から「迫撃弾」と称した発射物5発を射ち込む。
5.4日、 中核派活動家の福嶋昌男らが、東京サミットの式典会場となっていた迎賓館などを狙って、近くのマンションから迫撃弾5発を発射(迎賓館ロケット弾戦闘)。建設省(現・国土交通省)幹部宅や新東京国際空港公団(現・成田国際空港株式会社)職員宅などに対する放火・放火未遂ゲリラ事件も起こしている。現在、数名のメンバーが殺人・放火・爆発物製造などの被疑者として指名手配されている。中核派活動家4名が逮捕・起訴される。「5・7宣言」体制発動される。
10月、「10月の挑戦」と爆取弾圧粉砕の闘い。
1988.7.1日、京都大学で、中核派活動家6名が革マル派の襲撃を受け負傷する。
9.21日、千葉市内の路上で、当時千葉県収用委員会会長で弁護士の小川彰氏を襲撃。小川弁護士は全身を鉄パイプで殴られ、両足と左腕を骨折するという重傷を負った(小川弁護士は2003年7月にこのテロの後遺症を苦に自殺する)。このテロに中核派は犯行声明を出し、「収用委員会解体闘争」と称して「電話と手紙を集中せよ」として、他の収用委員全員の住所と電話番号を機関紙『前進』に掲載した。中核派は収用委員に組織的に脅迫じみた手紙、電話などを送り続け「家族ともども死刑台に乗っていると思え」という手紙が届いたこともあったという。その結果翌月、ついには収用委員全員が辞任し、千葉県収用委員会の機能が完全に停止する事態となる。
また、昭和天皇死去と現天皇の即位に関連して、1989年から約2年間にかけては「90年天皇決戦」と称して多くのテロ・ゲリラ事件を引き起こした。他にも同派は様々なテロ活動に手を染めた。
1989.7.3日、東京都議会選挙で中核派系とされる長谷川英憲が当選(「杉並革新連盟」として出馬、のちに「都政を革新する会(都革新)」と改称)。北小路敏が、長谷川英憲氏の都議選勝利に杉並区民の先頭に立って奮闘する。
1989年、昭和天皇死去と現天皇の即位に関連して約2年間にかけては「90年天皇決戦」と称して多くのテロ・ゲリラ事件を引き起こす。他にも同派は様々なテロ活動に手を染めた。
1989年、東京都議会選挙で、中核派系とされる長谷川英憲が当選(「杉並革新連盟」として出馬、のちに都政を革新する会と改称)。新左翼の候補者としては、都道府県議選で初の当選という。
1990年、天皇代替わりをめぐる日帝の攻撃にたいして天皇(天皇・三里塚)決戦をゲリラ戦と戦闘的大衆闘争としてうちぬいた。
1990.4月、日本飛行機(株)専務宅放火殺人事件について、中核派革命軍による犯行声明が出される。
1991.5月、 「五月テーゼ」(2003年以降は「新指導路線」と呼称)を決定。二重対峙・対カクマル戦に規定された特殊的闘い方から転換し、「将来の武装闘争に備えてテロ・ゲリラ戦術を堅持しつつも、当面は武装闘争を控え、大衆闘争を基軸に党建設を重視する」との方針を決めた(2003年以降、「新指導路線」と呼んでいる)
9月、外務省審議官実父宅放火殺人事件。
労働運動の分野では自治体、郵政、教育、JRを「四大産別」として、労組への影響力拡大を図ることになった。毎年11月頃に「全国労働者総決起集会」を東京で開催しており、その動員数は年々増加傾向にある。2005年の「11.6全国労働者総決起集会」では過去最高の2700名を動員した(平成17年の警備情勢を顧みてより)。
1991年、ソ連邦が崩壊し、ブルジョア評論家やマスコミは、「マルクス主義は終わった」と一斉に宣伝した。レーニンの石造が倒され、資本主義が勝利したかのような映像が世界を駆け巡った。
1991.5月、「五月テーゼ」を決定。70-80年代の闘いを総括し、革命的大衆行動の組織化と労働者細胞建設を基軸とした党活動へと転換させた。「将来の武装闘争に備えてテロ・ゲリラ戦術を堅持しつつも、当面は武装闘争を控え、大衆闘争を基軸に党建設を重視する」との方針を決め、テロ・ゲリラ等を控えて、組織拡大に重点を置き、市民運動や労働組合への浸透を図る戦術を採り始める。(2003年以降は「新指導路線」と呼んでいる)
1994.6月、マルクス主義基本文献学習シリーズの刊行開始。
1995年、第19回全国委員会総会(19全総)を買い指し、「先制的内戦戦略フェーズⅠ・フェーズⅡおよび5月テーゼ」のもとでの闘いを総括する。ソ連スターリン主義崩壊後の現代世界認識と情勢分析、沖縄奪還綱領の再構築と第三次安保・沖縄闘争論、憲法闘争論、7・7路線の革命的貫徹などについて討議・決定した。
1997.12月末、20全総。革共同の新指導体制が確立され、議長に清水丈夫、副議長・中野洋(安田)、書記長に天田三紀夫を選出。北小路敏が副議長に就任(清水丈夫議長―天田三紀夫書記長の最高指導体制)。但し、清水議長の指導、中野洋による労働運動重視(実際は動労千葉至上主義)の指導方針について党内で次第に対立が生じていくことになる。
1998.2.25日、革命軍が東京都世田谷区桜丘の運輸省元航空局長に時限式発火装置を仕掛け、放火。「「成田空港二〇〇〇年平行滑走路完成」攻撃を絶対に粉砕することを明らかにする戦闘宣言」と発表。
1999.3月、北小路敏が三里塚反対同盟・市東東市さんの逝去を悼み、現地集会で追悼演説を行う。
1999.11月、新東京国際空港公団(現・成田国際空港株式会社)次長の自宅に時限式発火装置を仕掛け、放火。
1999.11月、闘う労働運動の新しい潮流の形成へ3労組呼びかけの11月労働者集会始まる。
1999年、春の新安保ガイドライン決戦、夏の組織的犯罪対策法と「日の丸・君が代」法制化阻止闘争を闘いぬき、闘う労働運動の新しい潮流の形成をかかげて11月労働者集会の成功をかちとる。
2000.6.5日、公式ホームページを開設。
8.26日 運輸省(現・国土交通省)幹部の車両に時限式発火装置を仕掛け、放火。革命軍が「農民の営農破壊、生活破壊のためだけに暫定滑走路工事を強行してきた張本人」「強烈無比の爆破戦闘は、乗用車を大破し、家屋をも徹底的に破壊した」と軍報。
2000年頃、小西誠(いわゆる「反戦自衛官」)が、「清水による独裁体制」を批判して脱党。現在、「中核派vs反戦自衛官」、「検証 内ゲバ」などの著書で中核派を批判し続けている。
2001年前半頃、第6回大会。黒田寛一の主張する哲学(いわゆる「黒田哲学」)の徹底批判がおこなわれ、対カクマル戦の勝利を宣言し、新指導路線模索に向かう。また、中核派批判を行なっていた白井朗元政治局員への「粉砕」宣言がなされた。(白井朗は翌年の2002年12月、何者かによって襲撃される)。
2002.3月、北小路敏が革共同政治集会で、党を代表して長期獄中同志奪還への決意を述べる。
2002.4月、千葉県職員宅に時限式発火装置を仕掛け、放火。
12.18日、中核派元幹部で中核派を批判する本を書いていた白井朗が何者かに襲われる。
2002.12月、白井朗(元幹部(除名、『中核派民主派宣言』著者)、角田富夫(元幹部)が襲撃され重傷を負った。
2003.年、前進新年号が、「イラク反戦闘争・杉並区議選・国鉄決戦」の「三大決戦論」を打ち出す。(新指導路線)
2003.8月、千葉県警幹部と同姓同名の男性が住む民家に爆発物を仕掛け、放火(県警幹部と誤認した可能性が指摘されている)。
11月、日韓米の国際連帯闘争始まる。
12月、新生マルクス主義青年労働者同盟結成。
2004年、「前進」第2132号(2004新年号)で、「新指導路線にもとづく党の革命」路線が打ち出された。昨年夏の「政治集会」を区切りにして千葉労働の指導者・中野洋・氏が台頭し、概要「1・日帝のアジア侵略を内乱へという従来の総路線から資本攻勢との対決を軸とした階級的労働運動の飛躍・国際連帯を基本路線へ転じる。2・党の活動の中心・党建設の基本は労働運動・労働組合運動へのとりくみであり、労働者細胞の建設である、労働運動・労働組合運動に本気で取組み、それを党建設の基本に据える。動労千葉に学び、党の実体的変革を徹底的に進める。3・「非公然指導部、非合法・非公然体制の確立」から転じ、労働運動を基軸とした大衆運動に精力的に取り組む等々の方針を確認した。
2005.8.4日、歴史教科書問題で、新しい歴史教科書をつくる会が執筆した扶桑社発行の 教科書採択反対運動に積極的に介入し、東京都杉並区などで激しい反対運動を起こしている。デモの中で、参加者の中核派活動家の北島邦彦(現杉並区議会議員)が、ビデオ撮影をしていた男性に暴行を加えたとして逮捕される(後に釈放)。東京都杉並区、神奈川県、相模原市、大阪府、泉佐野市、高槻市の議会には中核派系の議員がおり、議会への進出度は日本労働党と並び、日本の新左翼の中では屈指。東京都知事選で青島幸男、国政選挙で社会民主党(個人では大田昌秀ら)、9条ネットのZAKIを支持、「都政を革新する会」の長谷川英憲を支援した。
11.6日、中核派及び関係労組らが主催する「全国労働者総決起集会」で過去最高の2700人(警察発表)を動員。
12月、警察庁の「治安の回顧と展望」は、中核派について、同派と関係のある市民団体と共闘して、「つくる会」の教科書の採択反対運動に関与していることを強く示唆した。公安調査庁の「内外情勢の回顧と展望」は、「教労(教育労働者)決戦の一環として、教職員組合や市民団体に対し、同派系大衆団体を前面に立てて共同行動を呼びかけた」と指摘。「つくる会」の教科書に対する反対運動に中核派が関与していることを強く示唆した。
2006.3.3日、迎賓館や在日米軍の横田飛行場などを狙って迫撃弾を発射し、爆発物取締罰則違反の罪に問われた中核派活動家に対し、東京地方裁判所が懲役12年の実刑判決を言い渡す。被告人側は即日控訴。
3.14日、中核派系全学連委員長ら29名が、法政大学で、大学敷地内で立て看板の撤去作業に抗議し、建造物侵入と威力業務妨害の容疑で現行犯逮捕される。逮捕時には約200名の公安警察が動員された。中核派はこの事件を「2006.3.14法政大学弾圧事件」と称し強く反発した。3.25日には29名全員が釈放され、そのうち法大生であった5名人には停学や退学処分が下された。その後、処分された者を中心に「3.14法大弾圧を許さない法大生の会」なる団体をつくり、学内外で抗議活動を現在も行っている。大学側は警備員を常駐させるなどして対処している。06,07年中に停学学生に対して無期限停学や退学など追加処分が下され、(大学無関係者含めて)逮捕者は40名を超えている。
2006.3.14日、「関西委員会指導部の腐敗、堕落」を訴えて関西を中心とする党員の一部が決起した(3・14決起)。関西地方委員会の議長であった与田を追放し、指導部に対して自己批判、路線の転換を求めた。党中央は、クーデターであると判断し、組織統制を強化した。これをきっかけに、党組織は、清水議長、中野(安田)副議長を中心とした「動労千葉派」運動を重視する「労働戦線派」(多数派)と、これまでの路線を踏襲し各方面での大衆運動に関わることを重視する関西地方委員会中心の「諸戦線派」(いわゆる「関西派」、「塩川派(塩川一派)」、少数派)の対立が表面化し、関西を中心とする「関西派」(「中央派」は「塩川一派」と呼称)との対立各地で「反中央派」の党員に対する処分が相次ぐ。これにより関西や九州などで「諸戦線派」に対する排除あるいは離脱などの内部対立が表面化した。これら両派の対立の背景には急激な路線転換の際に切り捨てられた「革命軍」の兵士たちの処遇をめぐる確執があるものとの推測もある。
2006.3月、北小路敏が階級的労働運動路線を断固支持し、革共同の変革と飛躍への新たな挑戦を開始する。
2006年、現役杉並区議2名も、議会闘争方針の対立から中核派の政治団体「都政を革新する会」から離脱し「無所属区民派」を結成した。
2006年、黒寛は80歳で病気で死去。中核派は「恥多き死を強制した」と称している。
秋頃 第22回拡大全国委員会総会(22全総)を開催。関西地方委員会の議長だった与田ら5名に対する除名処分が決議される。
2007年始め、北小路敏が闘病生活に入る。
1月、階級的労働運動路線打ち出す。
2007.4.27日、退学処分に対する中核派などのデモ中、中核派全学連活動家の学生ら2名が大学職員への暴行容疑で逮捕された。
7月、政治局によって「7月テーゼ」が発表される。
夏頃、第23回拡大全国委員会総会(23全総)開催。政治局から発表されていた「7月テーゼ」が全国委員会として正式決定される。党指導部から求められていた自己批判を拒否したとして、政治局員2名を除名。あわせて、「都政を革新する会」のメンバーだった現役杉並区議と前杉並区議の2名に対する除名処分も決議される。
秋頃、第24回拡大全国委員会総会(24全総)。「関西派」の中心人物とされる塩川らを除名。
12月、「関西党員総会」を開催。中央派と関西派の一連の対立で機能停止状態だった「関西地方委員会」(中央派)の再建が宣言される。
2008年、運動の進め方を労働戦線に集中して、部落解放闘争を労働戦線の付随とするような運動方針をめぐって、これまで共闘関係にあった部落解放同盟全国連合会(全国連)とも関係が悪化し、2008.2月、全国連から「広島差別事件」として糾弾を受ける立場になった。中核派はこの問題において、糾弾を受けた2月時点では沈黙していたが、4月になって全国連を「塩川一派」と規定して機関紙で公然と批判し始め、公式サイトから全国連サイトへのリンクを削除しているなど、その対立の溝は拡大し始めている。対する全国連側も中核派との「関係断絶」を宣言した。
5.28日、中核派系全学連委員長ら5名が傷害と公務執行妨害の容疑で逮捕される。
5.29日、法政大学でデモが起こり、中核派学生活動家33名が逮捕される。
2008.5月、「塩川派(塩川一派)」は、関西前進社を拠点として、中央派に対抗して革共同関西地方委員会は機関紙『革共同通信』、理論誌『展望』を発行し執行部批判などを行っていたが、革命的共産主義者同盟再建協議会を結成した。2009年、機関紙名を『未来』へ改題した。
6.29日、渋谷で洞爺湖サミット反対デモが起こり、中核派活動家ら8人が、公務執行妨害の容疑で逮捕される。後日、前進社へ家宅捜索。
7.3日、中核派活動家3名が法政大学の敷地内に無断で侵入したとして、建造物侵入容疑で逮捕される。容疑者は、仲間の退学処分に抗議するためキャンパス内に侵入したという。
2009.4.24日、法政大学で、東京地裁による「情宣活動禁止等仮処分命令」、大学側による処分発令などに対する中核派らによる抗議集会とデモが敢行され、中核派全学連活動家の学生ら6名が公務執行妨害などの容疑で逮捕された(集会中に5人、デモ後に警察署前で行われた抗議行動で1人)。
5.12日、千代田区一番町でデモ行進中、警備に当たっていた警察官に体当たりなどをした中核派全学連委員長織田陽介(28)が公務執行妨害で逮捕される。
7月、サンフランシスコ国際労働者会議。
9月、第25回拡大全国委員会総会(25全総)において、「綱領草案」が採択される。
2009.11月、中核派と共闘関係を維持している「西群支部」(大阪)、「杉並支部」(東京)、「品川支部」(同)の3支部に対し、「支部承認の取り消し」などといった「統制処分」を通告するなど、その対立の溝は拡大している。更に杉並では都革新と無所属区民派の間で裁判沙汰となっており、対立が広がっている。
2010.2.5日、法政大学で、大学側による処分の撤回などを訴えていた中核派学生活動家6人が、威力業務妨害などの容疑で現行犯逮捕される(2月26日に全員釈放)。
3.4日、副議長の中野洋が胆管ガンのため病死(享年70歳)。
3.16日、中核派系全学連副委員長、京大法学部生の原田幸一郎(26歳)が京阪電鉄上り特急電車の中で、女子大学生の太ももを触った疑いで逮捕される。
2010.11.13日、北小路敏が永眠する。
| 【北小路敏同志追悼】 |
週刊『前進』(2467号2面1)(2010/12/06 )
不屈の情熱引き継ぎ革共同は世界革命勝利へ前進する北小路敏同志の逝去を悼む
60年-70年安保闘争、非合法・非公然党建設と対カクマル戦争を指導した偉大な革命家
革命的共産主義者同盟政治局
(一)
北小路敏同志。あなたは多くの同志を残して、眠るがごとくに、闘いの人生の舞台から逝ってしまった。われわれは、北小路同志が常に全党の先頭で獅子吼(ししく)していた、あの姿、あの声をまざまざと思い出す。北小路同志を喪(うしな)ったその事実の大きさに、しばし我を忘れている。しかし革命運動もまた、最も豊かで人間的な営為であるがゆえに、生と死の冷厳な現実から逃れることはできない。
しかし革命運動の豊かさと根底性は、プロレタリア自己解放、人間の全人間的解放、共同性の奪還を求めて、陸続と決起する膨大な労働者階級と人民を生み出す。あなたの60年安保闘争以来の学生運動と革命運動へのひたむきな決起と情熱は、日本革命運動の躍動性と大衆性と根底性を階級闘争の歴史に刻み込んだ。これは誰もができることではない。あなたの堅忍不抜の精神が、新たな力を生みだし、革命運動を発展させた。革共同は、この素晴らしくも偉大な現実と地平を、闘いの糧としてさらに力強く前進する。
北小路同志。あなたが求めてやまなかった世界史的な階級対階級の激突情勢、革命情勢が急速に接近している。大恐慌は、米帝基軸の帝国主義戦後体制の解体を一挙に進めている。大恐慌は全世界に大失業を生み出し、労働者階級を食べさせることができなくなった資本主義は、ついに終わりを迎えた。また大恐慌は、領土・資源・市場の分割・再分割戦、侵略戦争・世界戦争へと転化し始めている。だがそれは全世界で、労働者の「生きさせろ!」の叫びと決起を生みだしている。
今こそ「大恐慌をプロレタリア世界革命へ」の闘いを発展させることが死活的になってきている。階級的労働運動の創造と発展は、労働組合の力、労働者階級の階級的団結をもって世界革命へと躍り出ることを可能にした。この世界史的現実こそ、北小路同志が何よりも希求した現実だ。階級対階級の激突に勝利し、労働者階級が社会の真の主人公となるために、あなたの労働者階級の決起への限りない確信を胸に、われわれもまた万里の波涛(はとう)をのりこえ、プロレタリア解放への道をしっかりと切り開いていく。このことこそ、あなたを尊敬し慈しむ革共同の最高の任務だと思う。
(二)
北小路同志は、全身全霊を傾けて革共同を守り、闘い、革共同の前進の基礎を築いた。それは何よりも現代のナチス、ファシスト・カクマル打倒に向けて最先頭で闘ったことである。日本階級闘争がかつて経験したことのなかったことが、現実の階級闘争の前面に登場してきた。それは階級闘争の発展に恐怖し、革命闘争を破壊するために、白色テロルをもって革共同に襲いかかってきたファシスト集団、カクマル反革命との戦争であった。
革共同の多くの労働者・学生の同志が、武装自衛の精神で、白色テロと闘う建軍闘争に決起した。全党が一丸となって、70年安保・沖縄闘争の爆発に対する反革命として登場したカクマル白色テロ集団と闘った。北小路同志を先頭に、71年12・4反革命、75年3・14反革命と闘った。反戦派労働者は自ら決起し、70年闘争を切り開いたその力を、現代のナチス=カクマル反革命完全打倒の戦いへと注ぎ込んだ。そして革共同とカクマル反革命の、血で血を洗う20年間の激しい激突を通して、ついに階級的力関係を変えたのだ。
われわれは、この二重対峙・対カクマル戦争とその勝利を誇りに思う。あの時、カクマル反革命との闘いにちょっとでもひるんでいたら、革共同は存在しなかった。大恐慌を世界革命の時代へと転化する情勢を迎えることができなかった。階級的労働運動に全精力を投入することもできなかった。このことへの心の底からの激しい喜びは、北小路同志が最も深く理解し、共有してくれていたことだと思う。
(三)
あなたは、革共同への国家権力の破防法(破壊活動防止法)攻撃を徹底的に粉砕するために、非合法・非公然体制建設の闘いを貫徹し、最も国家権力とファシスト・カクマルから恐れられ憎悪された、最高指導部であった。国家権力は、騒乱罪でデモの爆発を鎮圧し、大衆集会の演説に破防法扇動罪を適用して逮捕する。革共同の全同志を対象に不当な家宅捜索を行ったり、事務所の封鎖を画策する。許し難いデッチあげ弾圧を次々に強行する。
これらと闘い勝利してきたのは、革共同が先制的に非合法・非公然体制確立の闘いをやってきたからだ。この闘いは、帝国主義国家権力との死闘に勝利し、労働者党を建設する闘いそのものである。それはまた国際共産主義運動の総括でもあり、戦前・戦後の日本革命運動を総括し発展させる、本質的な闘いだった。わが革共同は、階級の大地に根を張り、労働者階級と一体となって、不撓(ふとう)不屈にこの偉大な闘いをやり抜いてきた。大恐慌時代への本格的突入、戦争と大失業の時代の到来は、こうした闘いをますます求めている。非合法・非公然体制確立の闘いにおける北小路同志の闘いは傑出していた。このことをあなたの霊前で、ともにしっかりと確認したいと思う。
(四)
74~75年世界恐慌は、戦後帝国主義の転換点であった。それは帝国主義の本質的危機、過剰資本・過剰生産力の問題を衝撃的に突き出した。帝国主義がこの危機を突破するために繰り出したもの、それが新自由主義だった。徹底的な団結破壊、闘う労働組合の解体によるむきだしの労働者支配という新自由主義攻撃を、米・英・日帝国主義が先頭となって強行してきた。
この日帝の新自由主義攻撃の突破口が国鉄分割・民営化だった。それは「血の入れ替え」と言いなし、JR総連カクマルを先兵として、そのファシスト支配を認めないものは一切排除する攻撃としてあった。国鉄分割・民営化の攻撃は、JR資本とJR総連カクマルの結託体制のもとに展開された。これに対し動労千葉は、1100名組合員の団結をかけて、分割・民営化攻撃に総反撃し、85年~86年の大ストライキを打ち抜いて闘った。しかもこの動労千葉の決起は、空港建設の攻撃と闘う三里塚芝山連合空港反対同盟との強い階級的一体感、労農同盟の絆(きずな)のもとに闘われた。
北小路同志は、この1980年代の新自由主義攻撃と闘う国鉄・三里塚決戦に断固決起し、日本階級闘争の前進を不屈に切り開く先頭に立った。これはまさに、80年代の闘いで革共同が胸を張って誇れる偉大な階級決戦であった。とりわけ労働者と学生の三里塚十字路決戦と浅草橋戦闘は、動労千葉の戦闘的組合の闘い、三里塚農民の農地死守の闘いに断固として連帯し、守り抜く、革命的な決起だった。
この80年代の勝利は、89年~91年の東欧・ソ連スターリン主義の崩壊、89年総評解散・連合結成という情勢に対し、闘う労働者階級がスターリン主義を徹底的に断罪し、マルクス主義を復権して、革共同が91年の5月テーゼ路線をもって労働運動に戦略的に体重をかけることを可能にした。北小路同志はその先頭で革命の大旗を振った。
(五)
北小路同志。あなたは疾風怒涛(どとう)の革命家人生を生き、かつ闘った。その精神は、60年安保闘争を継承し、発展させ、のりこえるものとしてあった。安保ブンドは、反帝・反スターリン主義の影響を受けて日本共産党から決別し、反スターリン主義の運動をつくりだすべく闘った。それはプロレタリア世界革命と暴力革命を立脚点にして、60年安保闘争という巨大な大衆闘争をつくりだした。しかし、革共同はこの60年安保闘争を切り開いた安保ブンドの大半を組織できなかった。それは、革共同の内部にあった小ブルサークル主義と同時に、安保ブンドの思想的基盤の脆弱(ぜいじゃく)性にも根拠があった。「社・共に代わる労働者党建設」「反帝・反スターリン主義世界革命」は、少なくともブンドの一定の指導部においては共通の認識であった。
その中で北小路同志は、これらの事がらを思想的に必死で総括しつつ愚直に実践し、ブンドから革共同に革命的に結集する闘いの先頭に立った。60年安保の精神を継承し、発展させ、のりこえる苦闘をやり抜いた。革共同はこの間、青年労働者が階級の指導部として労働者自己解放の闘いを開始すると同時に、学生運動の再生をかけて、強力な指導部建設の闘いを断固として前進させてきた。
日韓米を軸に打ち固めてきた国際連帯闘争は、動労千葉労働運動が切り開いた革命的地平である。この闘いは共産主義インターナショナル建設の闘いとして不可避的に発展していく。革共同は『綱領草案』を、闘病中の北小路同志に送り届けることができた。このことは無上の喜びでもある。
50年余の不屈の革命家人生は、その後に続く多くの同志を生み出した。階級的労働運動路線は、全世界のプロレタリアートの団結を基礎にして発展する。われわれは労働運動の前進で革命を主体的にたぐり寄せるのだ。北小路同志。われわれはあなたを失った深い悲しみの中から、しかし再び三たび不屈に立ち上がる。悲しみを階級的怒りに替えて突き進む。プロレタリア世界革命に勝利することが、あなたへの最大のはなむけだと思う。北小路同志。大きな風となって天空を舞いながら、ともにプロレタリア世界革命の勝利へ前進しよう! |
|
2010年12月20日「北小路敏同志の逝去に際し、万感の思いを込めて心から追悼の意を表す 革命的共産主義者同盟議長 清水丈夫」。
| 週刊『前進』06頁(2469号2面1)(2010/12/20)
北小路敏同志の逝去に際し、万感の思いを込めて心から追悼の意を表す
革命的共産主義者同盟議長 清水丈夫
(1)
私は、学生時代・青年時代から今日まで、全闘争生活・全組織生活を北小路同志とともにしてきました。北小路同志の御逝去に際して、本当に万感の思いを禁じえません。北小路同志の存在と指導性、そして偉大な力量に依拠することなしに、絶対に私自身ここまでやってくることができなかったことは明らかです。本当に北小路同志にいくら感謝しても感謝しすぎることはないと思っています。心から御冥福を祈ります。
(2)
北小路同志!あなたは全人生をかけ、帝国主義に対する激しい怒りを全身にたぎらせて、まさに仁王のごとく立って、プロレタリア革命の勝利のために、闘って闘って闘い抜かれました。そして、日本における反スターリン主義・革命的共産主義運動において、その草創期から今日にいたる戦略的前進の全過程の先頭に立って、指導的重責を担い抜かれました。そして今日、帝国主義とスターリン主義の世界体制が、大恐慌の重圧のもとで崩れかかりつつあり、資本主義の終わりがはっきりと見えてきた中で、階級的労働運動路線のもとに、闘う労働者とともに革共同・マル青労同・マル学同の全同志が一体となって、「大恐慌をプロレタリア世界革命へ」「国鉄決戦を貫徹してプロレタリア世界革命へ」の合言葉のもとに前進を開始している現実を、心からよろこび、プロレタリア革命の勝利への絶対的確信を日々強めて闘っておられたことと推察しています。
北小路同志!私は、同志が切り開き、築いた土台の上で、革共同の同志たちが、その遺志を継いで、必ず帝国主義の打倒、プロレタリア革命の勝利に向かって驀進(ばくしん)していくことを確信しています。私も、同志たちとともに徹底的に闘い抜くことを固く誓います。
(3)
北小路同志は、周知のように、他に類をみないスケールの大きさと精神的強靭(きょうじん)性をもった同志でした。これは、戦後革命以来の日本階級闘争の戦闘的伝統を踏まえつつ、反スターリン主義・革命的共産主義の労働者階級自己解放闘争の思想と実践の苦闘の中で、北小路同志がマルクス主義を本当に血とし肉とされたことに根拠があると思います。この労働者階級の革命性、階級性への全幅の信頼を不動の基盤とし、それに裏づけられて、北小路同志には、いくつかのすぐれた特質があったと思います。ひとつは、帝国主義・資本主義へのすさまじい怒りと憤りです。搾取、収奪、抑圧と支配、殺戮(さつりく)、反動、侵略、弾圧などをこととする帝国主義・資本主義を打倒せずにはやまずという精神がみなぎっていました。この意味で、彼は一度に何万という人びとに訴えかけ、心を揺さぶる力を秘めていました。いまひとつは、本当に徹底的に実践的であることに執念を燃やし、そして、いったん開始した実践は必ず貫徹することに徹底的にこだわる人だったということです。本当に心づよい、頼りがいのある同志だったと思います。私はいつも、このすごさに頭をたれ、敬服していました。
(4)
北小路同志を追悼するにあたって、何よりも決定的に確認すべきことは、わが反スターリン主義・革命的共産主義運動の闘いの歴史において、同志が残した足跡の大きさということです。数多くある中で、きわめて重要と思われる二点について提起します。ひとつは、何といっても60年安保闘争における6・15国会突入闘争の最高指導者として、断固たる闘いを貫徹し勝利したことです。もちろん60年安保闘争は、大きな歴史的背景と労働者階級人民・青年学生の総力をあげた闘いとして実現されたものですが、しかし、60年安保闘争が60年安保闘争として今日語られるようなものになったのは、やはり6・15闘争の革命的爆発を抜きにはありえなかったことだと思っています。そして、その60年安保闘争は、戦後の社共的指導下の政治闘争の継続として爆発したものではけっしてないということです。端的にいって、日本における50年代後半以来の反スターリン主義・革命的共産主義の闘いが一定の前進を切り開き、日本階級闘争の大地に根付き始めたことこそ、60年安保闘争をあのように爆発させるものとなったのだということです。だからこそ、60年を主導したブンドは崩壊したけれども、60年安保闘争で立ち上がった青年労働者・学生をはじめとして、労働者階級は、スターリン主義・日共を前衛とは認めず、社共を超える労働者党の建設こそ、本当に安保粉砕・日帝打倒を可能とするものであるとして、大きく革共同のもとへの結集を開始するにいたったのです。
かくて革共同を主軸として、日本の反スターリン主義・革命的共産主義の闘いは歴史的な歩みを開始しました。そして、革共同による革命的左翼の統一をバネに、革共同の闘いは前進し、労働者階級の党に真に成長するためには労働組合運動の戦闘的展開の先頭に立つべきだという、かの3全総決議への道が切り開かれたのです。このように見てくるならば、60年安保闘争がスターリン主義的勢力との激しい党派闘争の中で、反スターリン主義の影響下にある戦闘的学生のヘゲモニーで、6・15闘争として爆発し、勝利したことの意義は決定的に大きいのです。私がここで提起したいことは、反スターリン主義・革命的共産主義運動の影響を強く受けることをとおして、60年安保闘争はあのような歴史的大爆発をとげ、またそのことをとおして真に開示されたものは、日本の労働者階級の持つ反戦政治闘争(ひいては帝国主義打倒)へのとてつもない可能性、現実性だったということです。労働者階級が根底から全面的に決起したら、本当に天地をひっくり返す階級的力があふれ出てくるのだということが明らかになったのです。ちなみに、次のように言うこともできます。革共同は、3全総—3回大会をへて70年安保闘争に突入しますが、徹頭徹尾、革共同のヘゲモニーのもとで実現されたこの巨大な反戦政治闘争は、60年安保闘争の獲得した地平を前提に、いわばそれを一種の歴史的予行演習としてとらえ、真に労働者階級の党の立場に立って意識的に組織されたのです。こうして組織された70年闘争は、労働者党建設の圧倒的前進を切り開くものとなったのです。北小路同志の御逝去に際し、彼の遺志を受け継いでいく上で、これらの点について、しっかりと確認することは意義あることだと思います。
さらに、北小路同志の闘いの足跡という点では、70年闘争へのファシスト的反革命としてのカクマルとの激しい二重対峙・対カクマル戦を、革共同は徹底的に闘い、勝利しました。この過程における同志の指導力、意志の強さ、貫徹力というものが、いかに決定的であったかは明白だと思います。さらに、北小路同志は、本多延嘉同志の提起した革命的議会主義の闘いを、杉並の地で現実に開始するという創業的闘いを、全同志の先頭に立って闘い抜きましたが、このことは決定的意味をもっています。そして、言うまでもなく、この過程は、国鉄決戦と三里塚決戦が歴史的な大爆発をとげた過程であり、北小路同志はまさにその先頭で指導的重責を担い抜いたのです。これは、同志の不滅の貢献だったと思います。さらに、5月テーゼから今日にいたるまでの北小路同志は、革命家魂をたぎらせて、全党の先頭に立って闘い抜きました。まさに、同志は闘って闘って闘い抜いた偉大な革命家そのものでした。北小路同志。50年余のわれわれの闘いはついに若き全学連運動を生み出し、大恐慌をプロレタリア世界革命へ発展させる最大の階級決戦へ突入しようとしています。このことは、北小路同志と私が心から望んでいたことであります。
(5)
北小路同志! いまや大恐慌は、大失業のみならず、戦争を生みだしています。そして、戦後体制は、国際的にも日帝的にもガラガラと崩れています。先の11月労働者集会において、この情勢を革命に転化するために、「大恐慌を世界革命へ」「大恐慌・大失業・戦争を世界革命へ」という、まさにそのために、国鉄決戦を2011年階級決戦として圧倒的に闘い抜こうという確認が行われました。北小路同志が全人生をかけて切り開いてきた反スターリン主義・革命的共産主義運動のこの地平に立って、いま全同志たちは、闘う労働者の先頭に立って闘いに立ち上がろうとしています。自分自身、この同志たちとともに、どこまでも闘い抜くことを表明して、北小路同志への贈る言葉とさせていただきます。北小路同志よ。いつまでもわれわれとともにあって、日帝打倒=プロレタリア革命のその勝利の日まで見守ってくれ。
|
|
|
2015.9.9日、「革共同政治局の敗北 1975~2014」の「あとがき(2本)」。
岸 宏一「本多延嘉書記長の「遺言」によせて」
二〇〇六年七月に組織から離れて、まず考えたことは、それまでの革共同の歴史とは何だったのか、そして〇六年三・一四テロルがなぜ引き起こされたのか、であった。その総括に九年もかかってしまった。白順社の江村信晴さんに出版を打診してからも三年が経った。その理由は離党後も、ものの考え方、見方が革共同のままであり、その組織を客観的に対象化することの困難さであった。まずは自立した自己を再形成することが必要だった。
そのなかで最大の問題点は、私が関わった八一年以降の三里塚闘争の歴史的な総括がもっとも困難だったことである。八一年一月から〇六年五月までの二五年半、私は三里塚現地での革共同の責任者だった。本多延嘉書記長死後、つまり七五年三・一四以後の革共同を形づくった最大の闘争的要素は、対カクマル戦争と三里塚闘争である。とりわけ八一年の先制的内戦戦略第二段階への転換以降、革共同は三里塚闘争にいわば特化した組織となっていた。つまり、三里塚闘争の勝利のために、と称して、革共同をそれまでとは違うものとして形成してきた。三里塚闘争の路線、方針が党を大きな形で変容させてきたのである。その党とそこにおける自分を対象化するためには位相を変えたところから見直さなければならなかった。これは弁解ではあるが、検証と総括がこれほどまで長期にわたったことの最大の理由である。
〇六年に組織を離れ、本多さんの言葉が胸に浮かんでしばらく離れなかった。それは七二年のある日曜日、新橋にあった破防法裁判の弁護団事務局での話である。当時、本多さんは非公然形態がおもな活動形態であった。しかし時折、何の前ぶれもなく新橋の事務所に訪れてくることがあった。そのとき本多さんは共産党中央委員会発行の『日本共産党の五〇年』という党史(パンフレットのような本)を持ってきて次のような批判をした。
「五〇年間も革命運動をやっていて革命を成就させえない党は解党すべきである。革命党として五〇年史を出すことは恥である。そもそも革命はワンジェネレーションの事業である。結党から三〇年の間に革命を成就できなければ、その党はおしまいである。革命党は一世代の事業であり、世代交代は不可能である。また革命党の人格的継承も不可能である。日本共産党も宮顕(宮本顕治、当時幹部会委員長)から不破(不破哲三、当時中央委員会書記局長)への政権交代も簡単ではない。宮顕の世代とその指導体制はすべて退陣し、不破が新たに指導体制をつくる以外に党はつくれない。」
それは、本多さんの手工業的、中小企業的な組織論ともいうべき限界があるものでもあった。また、以下のようなことは本多さんの決まり文句であった。「革命党は独裁でなければならない。独裁がもっとも民主主義的なのである。だめなら交代すればいいのだ」と。前記の「人格的継承は不可能」ということと矛盾するが、聞いていると納得してしまうのが、本多さんの論法だった。それは私にとって本多さんの「遺言」となった。
七二年当時の本多さんは自らの人生の中でもっとも充実していた時期であった。彼の好きな言葉である「革命の現実性」を実感していたのであろう。理論的には代表的政治論文である「レーニン主義の継承か、レーニン主義の解体か」(『前進』六〇〇号記念論文として二号に分けて七二年九月に発表)、「革命闘争と革命党の事業の堅実で全面的な発展のために」(七三年八月に発表)を執筆していた。前年に一二・四辻敏明、正田三郎同志虐殺、一二・一五武藤一郎同志虐殺というカクマルの反革命テロルがあり、それにたいし党の軍事的武装を開始しており、本多さんの革命精神がもっとも高揚していたのだった。その本多さんの前記の言葉に、私は納得した。革命は困難な事業であり、現実的には可能性は薄いと実感しつつも、本多さんと一緒なら不可能を可能にしてくれそうな気持にしてくれるのだった。
しかし、その本多さんが七五年に虐殺され、彼が不可能であるといっていた党首の「人格的継承」が現実問題化したのである。直後はそんなことは考えずに、三・一四報復戦に全力を挙げていた。しばらくして、清水に本多さんの代わりはできない、と逡巡していた。しかし本文に書いたように、三里塚担当に着任するときは、本多さんに代わって「清水の党」を選択する、と決断したのである。
一三年一二月、『革共同五〇年史』上巻を手にした。また再び、前記の本多さんの言葉がよみがえった。「革命党にとって五〇年史などいうのは恥そのものだ」という言葉が。読後、このような歴史のねつ造、偽書は許せない、本書を早く仕上げなければ、と決意したのであった。まだまだ書ききれない部分があり、総括を深めなければならないことも多い、しかし、これ以上遅らせることはできないと決断した次第である。
離党当初は、政治運動、組織活動で知ったことは「墓場まで持っていく」という常套句に縛られていた。だが、革命運動のこのような敗北、その組織論的総括は歴史に書き残さなければならないと思い至った。後世、同じ誤りを次の世代が繰り返さないためにも必要だと考えて書いたものである。 |
|
水谷 保孝「七・七自己批判の実践を止めることはできない」
「七・七問題は毛沢東主義との党派闘争なんだよ」。本多延嘉書記長がこういったのは、七二年前半ごろだった。たしか全国会議を分散して開催し、その一つの少人数の会議に私も出席していた。清水丈夫、福島平和もそこにいた。会議場所の秘匿、結集と解散の方法など非合法・非公然活動の訓練を兼ねていた。それを聞いた私は少しむっとして、「華青闘は毛沢東主義者だし、金日成主義者の朝鮮人青年がいるのは事実だが、彼らは華僑総会や朝鮮総連の内政不干渉路線をうち破って、日帝権力と対決し日本の運動と共闘している。身体を張ってスターリン主義と対峙しているのだから、そんないい方は誤解を招く……」という趣旨のことを発言した。すると本多さんは「それはわかっている」といって、「正確にいえば、毛沢東主義、ホーチミン主義との党派闘争ということだ。水谷は〝アジアを反帝・反スターリン主義世界革命の根拠地に〟というスローガンが好きだろう。アジアで反スタの民族解放闘争をつくり出すんだよ」と応じた。その後、どんな討議になったかは憶えていないが、そういう意味なのか、と得心した。私にとってそれが、本多さんと直接ことばを交わした最後だった。
後日、党内文書で「民族解放・革命戦争の五つの指導原則」という提起がなされた。その内容は、本多論文「レーニン主義の継承か、レーニン主義の解体か」の第二章第二節に「民族=植民地問題、民族解放闘争への原則的態度の五つの視点」として簡潔に、しかし綿密に展開されている。それは①共産主義の実現、②プロレタリア独裁国家とプロレタリア党の指導、③戦略課題は民族解放と土地革命、④農民の圧倒的な動員、⑤民族解放・革命戦争が主要な現実形態、というものである。そうか、あのとき本多さんはこの五つの視点の理論を練り上げつつあったのだな、と合点がいった。ただ党内文書で「指導原則」となっていたのに公的な論文では「視点」と書き直されているはなぜなのか、と疑問に思った。当時政治局の入管闘争担当は福島さん(全国反戦世話人。九三年三月死去)だった。福島さんに質問すると、しばらく後で、「やはり視点とすべきなのだ」という返答だった。福島さんとおおむね次のような議論をした。
本多論文は七・七自己批判を深化させた。帝国主義の民族排外主義、社会差別とのたたかいは労働者階級人民にとって戦略的な恒常的課題だということを、本多論文は何度も強調している。つまり革共同がいままでつかんできた共産主義の原理の内容は不十分だった。アジアや全世界での民族解放闘争、解放闘争を始めとする差別撤廃のたたかいに連帯し、それを自らのたたかいとしていく。そのことでプロレアリア革命の内容を豊かにし、共産主義の原理を豊かにしていく。……
そのなかで福島さんは、本多さんからの伝言としてこういった。〝反スターリン主義が民族解放闘争をどうつくり出していくかは、革共同として未解明なこと、まだ実践がともなっていないことだ。だけど、いわなければならないことがある。だから「視点」なのだ。〟〝民族解放と共産主義的解放、解放と共産主義的解放はこれからの具体的実践をとおしてどんどん発展していく弁証法的関係にある。いまはその途上だ。だからこの弁証法的関係が発展していった先で、共産主義が民族抑圧や社会差別をどう解決しえるのかについて、本多論文では留保している。〟正確に再現できないのはもちろんだが、「未解明」「弁証法的関係」「途上」「留保」という本多さんのことばは明瞭に憶えている。
そのときから時代は大きく転回した。だが、米欧日の帝国主義支配下では、たえざる侵略戦争と大不況・大失業が全社会を蔽い、反イスラム、反韓・反北朝鮮、反中国を始めとする激しく凶暴で倒錯したヘイトクライム、排外主義、差別主義が奔流のようになっている。日本での安倍政権再登場はそれに拍車をかけている。労働者階級がかつてない主体的危機に直面している。日本の階級情勢の深刻な主体的危機に知らんふりをできるのは、観念論者にして機械的公式主義者の清水丈夫ぐらいである。革共同中央政治局派の松丘静司、大原武史らでさえ鈍感ではいられない(第七回大会特別報告1、同2)。労働運動の後退、戦闘的にたたかう労働者階級の姿の不在、正規・非正規の青年労働者が殺人的労働強化にさらされている現実、自分たちの孤立化にどうすればいいのか、じつは無力感を感じているありさまが伝わってくる。
いま本多さんが「七・七自己批判にもとづく実践は壮大な未完の事業なんだ」と語りかける声が聞こえてくるようだ。その世界史的テーマへの再挑戦が必要なときである。七・七自己批判の立場と実践は労働者階級人民のもつ階級意識を蘇らせ、自己解放の思想と底力を発揮せしめるだろう。
革共同は筆者らの愚かな破産と敗北を含めて、もう死んだのだ。弔旗もいらない。葬送の歌もいらない。ただインターナショナルな共産主義的解放を求める一人ひとりの人間がいればいい。本書がそのための踏み石になりえているかどうか、読者のみなさんの率直なご批判を切にお願いする。この三年余、筆者らの手さぐりの議論と遅々たる原稿執筆に粘り強くつきあってくれた江村信晴さんと、お名前は出さないが聞き取りや資料提供に応じ、貴重な指摘、批判をしてくれた方々に深く感謝を捧げる。
二〇一五年三月一一日 |
|
|
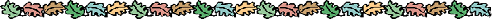



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)