|
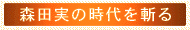
2003.4.1
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�P�n
21���I�����̐V���ȍ������̒��œ��{�������������߂ɂ͌Â��Œ�ϔO����̒E�炪�K�v��
�u���̓��Ƃ��ׂ��͏�̓��ɂ��炸�v�i�V�q�j
�@��L�̘V�q�̌��t�́A�u�����͗��]����B���̒��Ől�Ԃ�������^�̓��ɁA�i�v�s�ς̓��Ƃ������̂�����킯�ł͂Ȃ��B�ω��̎���̒��Ől�Ԃ͓Ǝ��̓����J���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��i�w�����̎v�z�x��U���u�V�q�E�v�Q�Ɓj�B�V�q�̋����́A�u���R�Ȕ��z�������ēƑn�I�ȓ������o���A��J���v�Ƃ����_�ɂ���Ƃ����̂����̉��߂ł���B
�@�܂����E��̑������B���E�͑�ω����n�߂��B�B��̒��卑�č������A�̘g����͂ݏo�ăC���N�푈���n�߂��B�����̍��A���S�̐��E�����̘g�g�݂͕��ꂽ�B���a�I���͂̎���͏I������B���E�I�����̎��オ�n�܂����B
�@���z�̑�]�������Ȃ���Γ��{�͐����Ă����Ȃ��B���̎��ɂ������{�l���w�Ԃׂ��́w�V�q�x�ł���B�V�q�N�w��m��Γ��͊J����B
�@�č���ӓ|�̍��̓��{�̐������ɂ��Ă��l�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���E���̋ߑ㕺���50���ȏ���ꍑ�ŏ��L����قǂ̌R�����卑�E�č������A�̌��c�Ȃ��ɃC���N�ւ̌R���s�����N���������Ƃ́A���j�̑�]���ɒ�������厖���ł���B�����Ȃ錋�ʂɂȂ낤�Ƃ��A���E�͐V���ȓ������ɓ������ƌ��Ȃ���Ȃ�܂��B���j�͈Â������Ɍ������đ傫�ȑ����ݏo�����̂ł���B
�@�B��̒��卑�ł���č����A���ۓI�ɌǗ����Ȃ���A���̋���ȗ͂�U��Ė\������Ƃ������ԂɂȂ�A���E�͒������I�ɍ������ɓ���B���̒��ŁA�e���͂��ꂼ��̐�������Nj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@������t�͕č��ɒǏ]���铹�ɓ��ݏo�������A����͌�������ł���B�]�ĘH���ɂ���ɐ[���肷��A���{�͐����I�ɂ��o�ϓI�ɂ��č��̎x�z���ɒu����邱�ƂɂȂ�B���{�͎匠���ł͂Ȃ��č��̐A���n�ɉ����Ă��܂��B�������A����Ȃ��Ƃœ��{�������Ă�����͂��͂Ȃ��B�Ǝ��̕����������A�P��3000���l�߂��l�������卑���{���č��̈ꕔ�ɂȂ�ȂǂƂ������Ƃ͂��蓾�Ȃ����Ƃł���B
�@�J��Ԃ����A���{�ɂƂ��č��K�v�Ȃ͔̂��z�̑�]���ł���B�]�ĘH�������{�ɂƂ��Ă̗B��̐��������Ƃ����Œ�ϔO���̂ĂāA��莩���I�ȈقȂ鐶������Nj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�V���Ȑi�H�̖͍��ɂ������đO��Ƃ��ׂ����Ƃ́A�o�ϑ卑�ӎ����̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@���ʂ���ꂪ�Ȃ��ׂ��́A���ĊW�𒆑]�����t�ȑO�A1960�N��A70�N��̒����I�ȊW�ɖ߂����Ƃ��B1982�N�ɓo�ꂵ�����]�����t�Ȍ�A���ĊW�ɐߓx������ꂽ�B�Ƃ�킯������t�͉ߓx�̏]�Ď�`�ł���B�������u�߂�����͗P�y���邪���Ƃ��v�B�s���߂��͐������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����E�؍��Ȃǂ̃A�W�A�����Ƃ̊W���P�͋}���ł���B�Ƃ��ɏ���̖����_�ЎQ�q�ł����ꂽ���ؗ����Ƃ̊W�C���ً͋}�̉ۑ肾�B����Ȃ��ɋɓ��̈��S�ۏ�͍���ł���B���̂܂܂ł͓��{�̓A�W�A�̌ǎ��ɂȂ�B
�@�V���ȃA�W�A�Ƃ̊W�̊m�������߂��Ă���B�A�W�A����]�����ɓ˓����Ă���B
�@���{�������g�A��]���Ɍ����ĐV���Ȕ��z���K�v�ł���B
�@���{�Đ��̕�����l����ɂ������ĕK�v�Ȃ��Ƃ́A���j��������Ƒ������A�߂��𐳂����Ƃ��B���{�̐����͂���20�N�ԑ傫�ȉ߂����J��Ԃ��Ă����B���{�����̉߂���1982�N�̒��]�����t����n�܂�B���]���͑ΕĊW�ɂ�����g�ߓx�h���̂āA�g�ߓx�̐ڋ߁h�Ƃ����߂���Ƃ����B���]���͉ߏ�Ȑ����I��S�������A���[�K���A�T�b�`���[�ƂƂ��ɐ��E�̑�w���҂����Ɩ������̂ł͂Ȃ����B�����w���҂̉ߏ�Ȗ�S�͍���łڂ��ő�̌����ɂȂ�B�ߓx�Ȃ����ĊW�̌��ʁA���{�̍��v�͑傫���������B1985�N�X��22���̃v���U���ӂ͓��{���{�ɂ����{�̍��v�̕����������B����ɂ��č��o�ς͕����A�t�ɓ��{�͒��v���邱�ƂɂȂ����B
�@�v���U���ӂ���17�N�����o�B���Čo�ϊW�͋t�]���A�č��͐��E�̉��҂ɂȂ����B���{�͕s���̂ǂ��ł������Â��A�j�ł̈����O�܂Œǂ��l�߂��Ă���B���̂܂܂����A���{�͕č��̐A���n�Ɖ����Ă��܂����낤�B��ғ��{�͋��ҕč��̓��ɂ���H�ׂ��Ă��܂��B����A���͂┼���H�ׂ��Ă��܂��Ă���B
�@80�N��ɂÂ���90�N������{�͉߂����Â����B90�N�ォ�獡���܂ł̊ԂɎO�́u���v���t�v���a�������B�������v�̍א���t�A�s�����v�E�������v�Ȃnjܑ���v���f�������{���t�A�\�����v�̏�����t�ł���B������̓��t�̒�����厸�s�ɏI������B
�@���̌����́A���ɁA���{�̕��y�E���������Ė�����A���O���T�N�\���Ɠ�������i�����Ƃ������ƁA���ɐV�����ᐬ���̎���ɓK�����悤�Ƃ����A����̗͂��ߐM���āA80�N��܂ł̌o�ϓI�����̖���ǂ��Â������ƁA��O�ɍ��ۏ�̕ω��Ƃ��ɕč��ƒ����̕ω�������������ƁA�ɂ������B
�@���{�Đ��̂��߂ɂ́A�܂��A��L�̎O�̉߂��ɋC�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�߂��𗦒��ɔF�߁A���̌����͂��A���v�E���P�̕����������o�����߂̓w�͂��n�߂�K�v������B
���̂��߂ɂ́A���ׂĂ̎w���I�����Ƃ����R�őn���I�Ȑ��_�������Ƃ���O��ƂȂ�B�����ɂ����Ė𗧂̂��V�q�N�w���Ǝv���B�i�Â��j
�y����A�V�q�N�w�̌�����{�����ւ̓K���ɂ��Ď������q�ׂ邱�Ƃɂ��܂��z
2003.4.2
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�Q�n
�A�����J�I���l���d�̕����͈ꎞ�I�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��B�A�����J�I��ΑP�Ȃǂ���킯�͂Ȃ��B
�u�L�����ʂ��v�i�V�q�j
�@�u�L�v�Ɓu���v�͑��ʂ���B�u�L�v�Ɓu���v�͑��݂Ɋ֘A�������A���肵�����A�]���������āA�ЂƂ̓�����Ȃ��Ă���i�w�����̎v�z
�Y�x�u�V�q�E��q�v�A���ԏ��X���A������E�呺�v�v��j
�@�u�V���݂Ȕ��̔������m��B���ꈫ�Ȃ�B�݂ȑP�̑P�����m��B����s�P�Ȃ�v�i�l�݂͂ȁu���v�͂˂ɔ��ł���ƍl����B���͓����Ɂu�X�v�ł���B���ꂵ���u�P�v�͂˂ɑP�ł���ƍl����B�P�͓����Ɂu���v�ł���j�̂������ƂɁu�̂ɗL���������c�c�v���Â��B
�@���ׂĂ��̐��̂��Ƃ͑��ΓI�ł���A���݂ɓ]�����������̂ł���B�����ɌŎ����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A�ƘV�q�͐����Ă���B
�@�č��͍��A����̖����`�Ǝ��R�o�ώ�`������������Ή��l�̂悤�ɐM�A����𐢊E���ɉ������悤�Ƃ��Ă���B�ĉp�����͎���̐����̐��͂��g���ăC���N�����ɋ������悤�Ǝ��݂Ă���B�C���N�̐����̐��̑P���f����̂̓C���N�������g�ł���B�u�b�V���đ哝�̂����߂�ׂ������ł͂Ȃ��B
�@�č����{�͂܂����{�ɑ��ĕč��I�O���[�o���Y�����������悤�Ƃ��Ă���B�č����M�鎩�R�f�Վ�`�A���R������`���������悤�Ƃ��Ă���B��������l�ɐ������Ȃ��B�ǂ̂悤�Ȍo�σV�X�e�����̗p���邩�͓��{�������g�����肷�ׂ������ł���B
�@�č��I�Ȑ�ΑP��M�A����𑼍��ɋ����I�ɉ������悤�Ƃ��邱�Ƃ́u���v�Ȃ̂ł���B
�@�����Ōy���ȃA�����J���Ԃ�̊w�ҁA�G���[�g�����ƈꕔ�����ƁA�ꕔ�W���[�i���X�g�����{�̃A�����J���Ƃ�������s�������ɐ����i�߂Ă���B���{�̌o�ώЉ�Ɛ����̍����̌����͂����ɂ���B
�@�č����{�́A���炪1945�N�U��26���A�T���t�����V�X�R�ō��ۘA�����͂ɏ��������Ƃ��ɐ��������Ƃ�Y��Ă��܂����̂��낤���i�ȉ��u���ۘA�����́v�O���j�B
�@�u����A�����l���́A����̈ꐶ�̂����ɓ�x�܂Ō���ɐ₷��߈���l�ނɗ^�����푈�̎S�Q���珫���̐�����~���A��{�I�l���Ɛl�Ԃ̑����y�щ��l�ƒj���y�ё召�e���̓����ƂɊւ���M�O�����炽�߂Ċm�F���A���`�Ə�̑��̍��ۖ@�̌��琶����`���̑��d�Ƃ��ێ����邱�Ƃ��ł���������m�����A��w�̑傫�Ȏ��R�̒��ŎЉ�I�i���Ɛ��������̌���Ƃ𑣐i���邱�ƁA���тɂ��̂��߂ɁA���e�����s���A���A�P�ǂȗאl�Ƃ��Č݂ɕ��a�ɐ������A���̕��a�y�ш��S���ێ����邽�߂ɂ���̗͂����킹�A�����̗��v�̏ꍇ�������O�͕��͂�p���Ȃ����Ƃ������̎���ƕ��@�̐ݒ�ɂ���Ċm�ۂ��A���ׂĂ̐l���̌o�ϓI�y�юЉ�I���B�𑣐i���邽�߂ɍ��ۋ@�\��p���邱�Ƃ����ӂ��āA�����̖ړI��B�����邽�߂ɁA����̓w�͂����W���邱�Ƃ����ӂ����B�@
�@����āA����̊e���̐��{�́A�T���E�t�����V�X�R�s�ɉ���A�S���ϔC��������Ă��ꂪ�ǍD�Ó��ł���ƔF�߂�ꂽ��\�҂�ʂ��āA���̍��ۘA�����͂ɓ��ӂ����̂ŁA�����ɍ��ۘA���Ƃ������ۋ@�\��݂���v
�@���̍��A���͂����������̂�1945�N10��24���ł���B
����̔s�퍑�ł�����{�́A1952�N�R��12���ɍ��A�ւ̉������t�c�Ō���A1956�N12��18���̍��A����ɂ����č��A���������F���ꂽ�B
�@�ĉp�������{�͂��̕��a�̐�����Y��A���A���݂͂ɂ����āA���A���c�̂Ȃ��܂܃C���N�U�����n�߂��B�Ƃ��ɏd��ȍ��A���͈ᔽ��Ƃ��Ă���B
�@�č��͂��܂�B��̒��卑�ł���B���̕č����͂����Ő��E�����������悤�Ƃ��Ă���B�����A����Ȃ��Ƃ������Â��͂��͂Ȃ��B
�@�w�Õ��^��x�i�����E�v�̎���̎����W�j�ɂ���Ƃ���u�����Ȃ�͕K�������A�m�`�Ȃ�͉�����v�i����̍����𗊂݁A�͂������Đ��𐧂���҂͕K���S�т�B����ɑ��m�`�������ė��҂͉��҂ƂȂ�j�̂ł���B
���{�����̕č��M��҂͕č��̂��߂ɓ��{�̍��v���]���ɂ��ĕ��R�Ƃ��Ă���B���{�̍����ƂƂ��ɐ�����̂ł���A���Ȃ��ׂ��ł���B
2003.4.3
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�R�n
�A�����J��ΑP��M�鐭���ƁE�w�ҁE�W���[�i���X�g�E�G���[�g�������A���{�̏����̍����ł���
�u���ׂ��Ȃ��A���܂炴��Ȃ��v�i�V�q�j
�@���ׂƂ͐l�ׂ�p���Ȃ������̂��ƁB�l�������R�ɐ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���ΓV���͂悭���܂�B���{�͐l���ɑ��āu��������v�u��������v�Ƃ��������w��������A�l���̐����Ɋ����Ȃ����������\�\�Ƃ����Ӗ��ł���B
�@���̌��t�̑O�Ɏ��̕��͂�����B
�@�u�������i�����Ɓj����A�������đ��킴�炵�ށB����݂̉��M����A�������ē����Ȃ����炵�ށB�~���ׂ������i���߁j������A���̐S�����ė��ꂴ�炵�ށB�����������Đ��l�̎��́A���̐S�����������A���̕����������A���̎u���キ���A���̍����キ���B��ɖ������Ė��m���~�Ȃ炵�߁A���̒m�҂����Ă����ĂȂ����炵�ށv�i�l�̌����͑��ΓI�Ȃ��́B�����d�����Ȃ���Ζ��̑����͂Ȃ��Ȃ�B��ɓ���ɂ������ݍ�����M�Ԃ��Ƃ����Ȃ���Γ��݂͂Ȃ��Ȃ�B�~�]���Ɏh������悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ���ΐl�̐S�͗���Ȃ��B�^�̐��l�̐����́A�l�̐S�����������~�]�͗}�����邪�A���N�ɐ����ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��B�l�����]�v�Ȓm�����]���ȗ~�]�������Ȃ���A�����������G���[�g�������]�v�Ȃ��Ƃ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��j
�@�ŋ߂̓��{�̐����́A���{�ŗL�̏K���╶���܂ŕς���悤�ȍs���߂������������ւ̊����s���X�������܂��Ă���B�s���߂������v������Ŏ��s���A���ʂƂ��đ厸�s���J��Ԃ��Ă���B
�@�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�P�n�ŁA���́A90�N��ȍ~�����Ɏ���܂ł̐l�C�̍��������O�̉��v���t�i�א���t�A���{���t�A������t�j�̎��s�Ɍ��y�����B
�@�ŏ��̉��v���t�E�א쐭���̎O����тƂ����Ă������̂́A(1)�����}�P�Ɛ������I��点�����ƁA(2)�K�b�g�E�E���O�A�C���E���h���ӂ�����ĕĂ̎��R���ɓ��ݐ������ƁA(3)�O�c�@�c���I���ɏ��I�������\�����������ƁA�ł���B
�@�������A10�N�Ԃ��o�āA����������������Ƃ͌�����B�ނ��낷�ׂĎ��s�ƕ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�������Ɏ����}��}�����͏I��������A�u���Ђ��v�u�������v�u�����ہv�Ƃ����A�������̌`���Ƃ��Ď����}�����͕��������B�����̘A�������͎����}�P�Ɛ��������͂邩�ɒዉ�Ȑ����ł���B�����}�P�Ɛ��������͂邩�ɔ��`�I�ł���A�����I�ł���B
�@�א���t�ɂ�鐭�����v�́A���ʓI�ɂ�舫�������̐��ݏo�����ƂɂȂ����B�����͍����̓��[���ʂł͂Ȃ��A���}�w���҂̐����~�ɂ��ƂÂ��삯�����ɂ���Č��܂�悤�ɂȂ�A���O�Ȃ����������s����悤�ɂȂ����B
�@���̕Ă̎��R���́A���ʓI�ɂ͓��{�̍��v�̐��i�ɖ𗧂����Ƃ͌�����B���{�_�Ƃ̐��ނ�H���~�߂邱�Ƃ͂ł��Ă��Ȃ��B���ꂾ���ł͂Ȃ��B���̌�̓W�J�͓��{�̕č삻�̂��̂̊�@�ɂȂ����Ă���B���{�̐H�Ƃ̐��Y�Ƌ����͕č��̎�Ɉڂ낤�Ƃ��Ă���B
�@��O�̐������v�ɂ��Ă��A����ɂ���Đ������\�ȓ�吭�}�������܂ꂽ�Ƃ͌�����B���I�������\���Əd�������ɂ�萭���Ƃ̌ւ�ƕi�ʂ͋ɒ[�ɒቺ�����B
�@�א���v�����͂��ׂĂ̖ʂŎ��s�����ƒf������Ȃ��B���s�̌����͉����B���_���猾�����B���{�̕��y�A�����A�K�������ĉ��ė��̂����A�����悤�Ƃ������Ƃɂ���B�������j�̂Ȃ��Œ蒅�����K���A�����A���y���A�������͂̎�ŕς��悤�Ƃ���̂͑�ԈႢ�ł���B�������̗͂��p�ł���B
�@���̉��v���t�́A�s�����v�A�������v�A���Z���v�A�Љ�����v�A�o�ύ\�����v�ܑ̌���v�i�̂��ɋ�����v�������ĘZ����v�j���f�������{���t�������B�����A��������Ƃ��Ƃ����s�ɏI������B���s�̓x�����͍א���t���͂邩�ɉz�����B���{�o�ς�ʖڂɂ����B
�@�s�����v�͏Ȓ��̐������炵�������������B�s�����v�̖{���̖ړI�\�\���ƌ������̍팸�A�����Ȓ��̌����̏k���A�����̍팸�͂قƂ�ǎ肪�������Ȃ������B�܂��ɖ�����̍s�����v�������B����ǂ��납�A���ʂ��猩��ƁA�����Ȓ��̗͂������Ȃ����B�����Ȓ��̌��͂͋������ꂽ�B�ړI�ƌ��ʂ��t�ɂȂ����B
�@�������v�͏���ň����グ�A��Ô�����グ�ȂǍ������S�傳���������ł���B�����͏d�ŘH���������B
�@�u���Z�r�b�O�o���v�ȂǂƑ呛���������Z���v�̖{�����A���{�̋��Z�@�ւ��Ԃ��A�č��t�@���h�ɓ������肷�邱�Ƃɉ߂��Ȃ��������Ƃ͂��łɖ����ł���B���{���{�ɂ�鍑���̕x�̕č��ւ̋����I���^�ł���B����͍����Â��Ă���B
�@�Љ�����v�Ƃ͒P�Ȃ鍑�����S���ł���A���{�I���v�͐摗�肳�ꂽ�B�����̂��߂̕����̗��O�͎̂ċ���ꂽ�B
�@�o�ύ\�����v�͋��҂�ی삵��҂������߂邾���̋K���ɘa�ɉ߂��Ȃ������B
�@������v�ɂ��ẮA���肳��Ȃ������ɋ��{���t�͑ސw�����B
�@���{�Z����v�͖��S�ȑ厸�s�ɏI������B���{���v�����ݏo�������͓̂��{�o�ς̐[���ȕs���������B���{���v�͓��{�o�ς��u�������̃��i�v�Ɋׂꂽ�B���{�o�ς͂��܂��s���̓D�����甲���o�邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B�����ɓ��{��č��̐A���n����������ֈ�����ݏo�����B����͏����Ɏp����Ă���B
�@��O�̉��v���t�����܂̏�����t�ł���B������ŏd�v�ۑ�Ƃ��Čf�����s�Ǎ������������Č������s�����B�����s�v�c�Ȃ��Ƃɏ�������̓}�X�R�~�̎x���������Ă���B�א쐭���Ƌ��{�����͐��������ɂ̓}�X�R�~�̔M��ȉ����������A�������ς�藎���ڂɂȂ��A�}�X�R�~�͎�̂Ђ��Ԃ����悤�ɐ��{�ᔻ���n�߂��B
�@�����������̏ꍇ�͈���Ă���B���Ɨ����㏸���Ă��A�|�Y�������Ă��A�}�X�R�~�͏������x���Â��Ă���B���̗����ɂ���̂́A������t�A�����G���[�g�A�}�X�R�~�̖����ł���B�����ő吭���^��̐����ł���B���̃o�b�N�Ƀu�b�V���Đ���������B���{�͌��͂̕��U�Ƃ������吭���̊�{�݊O������B
�@���{�A�����t�ɋ��ʂ���̂́A�����t���č����{�����i����č����O���[�o���Y�����x�����A����ɓ��{�o�ς����킹�邽�߂̉��v�����悤�Ƃ������Ƃł���B�א���t���߂������͕̂č��I�����̓��{�ւ̓����������B���{�E�����t�͓��{�̎Љ�o�σV�X�e����č����f���։������邱�Ƃ�ڕW�ɂ����B�����ĂR���t�Ƃ����s�����B�J��Ԃ����A���{�̎��Ԃ����A���{�̕��y�A�����A�K����Z���Ԃɋ����ɕς��悤�Ƃ������Ƃ����s�̌����ł���B
�@����������A90�N�ォ�獡���Ɏ�����v�̎��s�̌����́A�u�č���������Γ��{�͂悭�Ȃ�v�Ƃ����Œ�ϔO�ł���B���{�̐����ƁA���E�G���[�g�A�w�ҁA�}�X�R�~�����̌Œ�ϔO�̗��i�Ƃ肱�j�ɂȂ��Ă����B�č��ō���������������ƁA�G���[�g�����A�w�ҁA�W���[�i���X�g�ȂǓ��{�̎w���w�̑_���́A���{��č������邱�Ƃɂ������B
�@�ނ�͔ƍߓI�Ȃ��Ƃ��������B�]�v�Ȃ��Ƃ����Ȃ���悩�����B�ނ�͉������ׂ��ł͂Ȃ������̂ł���B��������A���{�͂���قǂЂǂ���Ԃɂ͂Ȃ�Ȃ������B
2003.4.4
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�S�n
�A�����J��Ύ�`�̊g��ƌŒ艻�����E�Ɠ��{��łڂ�
�u���́A�����̉s���������A�����̕��i���j��������ق����A�����̋P����a�炰�A�����̐o�i�悲�j��ɌȂ��������v�i�V�q�j�q�w�V�q�x��A�����V���Њ��r
�@���i���i���͂��̌��t�̈Ӗ������̂悤�ɕ\�����Ă���i�����ÓT�I10�w�V�q�x��Ap.65�j�\�\�u�Ȃ�̋C�������̂ċ���A���l�Ƒ������Ƃ��D�܂��A�˒m�̋P����[�����Ŗ}���̂Ȃ��ɖ}���Ƃ��Đ����鋭�ՂȎG���̐��_�A�d�S���n�ɗ��Ƃ��ĕ���邱�ƂȂ�������邱�Ƃ̂Ȃ��݊p�I�Ȑl���݂̍�����Ȃ�̂��̂Ƃ��邱�Ƃ��ł���̂ł���v
�@2003�N�R��20���A�ĉp�����̓C���N�U���ɓ��ݐ����B����͒����Ɂu�ĉp�x���v��\�������B����́A���{�̐����ƍߎj��ɋL�^�����ׂ���ƍ߂��Ǝv���B������t�͓��{���������Â��Ă������a��`�E���A���S��`�𓊂��̂Ă��B
�@�����̋L�҉�ɂ����ď���́A��������j�ɋL�^�����قǂ̋����ɂ��čߐ[�������������B�R��29���t�������V������13�ʁu���E�����ƃC���N�푈�v���炱�̔��������p����B
�u�č��́w���{�ւ̍U���͎����ւ̍U���Ƃ݂Ȃ��x�Ɩ������Ă��邽����̍����B���{���U�����悤�Ǝv�������Ȃ鍑�ɑ��Ă��i���ē������j�傫�ȗ}�~�͂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���{�����͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��v
�@���́A���̏������L�҉�̏ꂾ���łȂ�����ɂ����铚�قł��������B���̔����̓e���r�ł��J��Ԃ��������ꂽ�B���̔������A�����̊F����͂ǂ̂悤�ȋC�����ŕ������̂��낤���B���͓��{�̐����������܂ő������̂��A�����Ƃ̌ւ�͂ǂ��ɍs�����̂��\�\�ƁA���W����C�����ŕ������B
�@�������{�l�͕č����ƕč����{��M���A�F�D�W���ێ����邱�Ƃ���ł���B�������u�M���v�Ɓu�]���v�͈قȂ���̂��B�����̍��̖h�q�͑��`�I�ɂ��̍��̐��{�̐ӔC�ł���B�����������݂��邩��Ƃ����āA���{�̐ӔC�����͋�����邱�Ƃł͂Ȃ��B����Ȕ������͂��ׂ��ł͂Ȃ������B
�@�C���N�푈�u�����O�܂ŏ�����t�x�����͒ቺ�X���ɂ������B�����̎�ȊS�����{�o�ς̐[���ȕs���Ɍ����Ă���A�s���̌����������̌o�ώ����ɂ���Ƒ����̍����������Ă�������ł���B���̂������{�o�ς̂R����@���i�s���Ă����B�����ɑ��Đ����]���̗v�������܂�A���E�ɂ����鏬���͖Ԃ͋��܂��Ă����B
�@�Ƃ��낪�C���N�푈�u���Ɩk���N�j�~�T�C����@�����ɂ��A�����̊S�̓C���N�푈�Ɩk���N���ЂɈڂ����B�e���r�̓C���N�E�k���N�����ɏW�����A�����o�ϖ��͎�舵�����Ƃ��炵�Ȃ��Ȃ����B�����͌o�ϊ�@�ɖ��S�ɂȂ����B
�@���̊ԁA���{�E�����}�ƕč����{�́A���{�����Ɍ������Ėk���N�j�~�T�C�����Ђ����тÂ����B�}�X�R�~�����������B���{�����̑����́A���܂ɂ��k���N����j�e���������~�T�C�������{�Ɍ������Ĕ��ł���Ɗ�����悤�ɂȂ����B
�@�����͂��������̂Ȃ��ōs��ꂽ�B���{�����̂Ȃ��ɁA�������u���{���U������Εč��������Ă����B���{�̈��S�ۏ�͕č�������Ă����B���̑厖�ȕč��ɔ�����悤�Ȃ��Ƃ�����A���{�͕č��Ɏ���Ă��炦�Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����Ӗ��ɗ��������l�X�������B����������ł͂Ȃ��B
�@����Ɂ\�\�������厖�ȂƂ��낾���\�\�V���{�ɂ͎�����h�q����\�͂��Ȃ��B�č��ɗ��邵�������Ȃ��V�Ə���������Ă���悤�ɑ����̍���������ꂽ�B
�@���Ĉ��ۏ���T���ɂ͂�������\�\�u�e�������i���{�ƕč��̂��Ɓ|�M�Ғ��j�́A���{���̎{���̉��ɂ���̈�ɂ�����A�����ꂩ����ɑ��镐�͍U�����A�����̕��a�y�ш��S���낤��������̂ł��邱�Ƃ�F�߁A�����̌��@��̋K��y�ю葱�ɏ]���ċ��ʂ̊댯�ɑΏ�����悤�ɍs�����邱�Ƃ�錾����v
�@�������Ɂu���ʂ̊�@�ɑΏ�����v���ƂɂȂ��Ă��邪�A����������������t���ł���B���̏����Ƃ́u�����̌��@��̋K��y�ю葱�ɏ]���āc�c�v�ł���B�č������{�����Ɏ���Ă����킯�ł͂Ȃ��B���{���̑��Ɂu���ʂ̊�@�ɑΏ�����v�ׂ����ԂɂȂ����Ƃ��A�č���100�����{�h�q���s���Ƃ����ۏ�����킯�ł͂Ȃ��B���{�̖h�q�͑��`�I�ɂ͓��{���{�̐ӔC�Ȃ̂ł���B
�@�����A���������Ŏw�E�������̂́A���{���I�Ȏ����ł���B���Ĉ��ۏ�������荪���I�ȍ��̊�{�����邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����́A�����̍��͎������g�Ŏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�\���ȌR���͂������Ă��邩�ǂ����ɂ�����炸�A�����͎��͂Ŏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���_�̖��ł���B���{�͍����̐擪�ɗ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���{�������������͂Ŏ�邱�Ƃ���{�ł���B�č��Ƃ̊Ԃ̈��ۏ�ǂ�قǂ̏d�݂������Ă��悤�Ƃ��A���͖h�q��`�̊�{��ے肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B���̊�{�������������A�����Ɛ��{�͎����͎����Ŏ��Ƃ̋����ӔC���ƌւ���̂Ă邱�ƂɂȂ�B�����̖h�q�Ƃ������{�̐����̍ŏd�v�ۑ��č��ɗ���낤�Ƃ��鐭���p���͐����̑ޔp�ł���B���ē����ւ̈ˑ����J��Ԃ��������鏬��̎p�́u�Ղ̈Ђ���ρv�ɓ������B
�@����̐����͑��̋l�܂�悤�Ȃ����������������ł���B�������������̉��ł͍����͍K���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����͂����Ƒ傫�ȁu���v��i�ނׂ��ł���B��Ȃ͍̂�����l��l�̎��R�ł���A�����炩�ɐ����邱�Ƃł���B
�@���i���i���͎��̂悤�ȉ�����Ă���i�����ÓT�I10�w�V�q�x��Ap.65�j�B
�@�u�����̐��E�́A�l�Ԃ̎Љ�����T�^�I�ɑ�\����悤�ɍ��ʂƑΗ��̐��E�ł���A�����ɂ͐l�Ԃ̉s�p�I�Ȏ��Ȏ咣��l�ԓ��m�̕��G�Ȕ��ڂƓ����A�˒m�̋P���̂����ǂ��֎��₱�̐��I�Ȉ�̏X�������Ђ��߂��Ă���B�������l�Ԃ������R�̍����I�Ȑ^���ɖڂ��߂����Ƃ��A���̍��ʂ�Η��̑��i�������j�͂��͂⓹�̐�ΐ��̑O�ɂ��Ƃ��Ƃ����ΓI�Ȃ��̂ƂȂ�A��ʓI�ȉ��l�ς₻����Ŏ������s�Ȏ��Ȏ咣�A���Q�̔��ڂ�˒m���ȁi�Ă�j����Ƃ�P����Ȑ��҈ӎ��Ȃǂ͐l�Ԃ̂�������Ƃ��ċ����ꗎ����v
�@�ĉp�����̃C���N�ւ̕��͍U���Ƃ�����x�����鏬��̍s�ׂ́A�V�q�N�w�Ƃ������̑O�ł́A�����ŏX���Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ����Ƃ͖����ł���B
2003.4.5
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�T�n
�u�b�V���Đ����̐��E�x�z�̖�]�͕K�����s����
�u�V�n�͕s�m�A�������Ȃ�䍋�i�������j�ƈׂ��v�i�V�q�j
�@�V�n�ɐm�͂Ȃ��A�����߂��B������m�𑩂˂č�������̂悤�Ɉ����B�Ւd�ɋ������邪�A�Ղ肪���߂Ύ̂Ă��Čڂ݂��Ȃ��B�V�n�́A�l�Ԃ̂悤�Ȉӎu�⊴��A�ړI�ӎ��≿�l�ς������Ȃ��⍓�ȑ��݂ł���\�\�Ƃ����Ӗ��B
�@�ȉ��́A���i���i�w�V�q�x�i�����V���Њ��A�w�����ÓT�I10�x�j�́u����v����̑������Ő\����Ȃ����A�g���X�g�C�͂����������Ƃ����B
�@�u�l�ނ�Y�܂�������ЉЂ́A�l�Ԃ��K�v�Ȃ��Ƃ��ׂ��̂�ӂ�Ƃ��납�琶����̂ł͂Ȃ��B�������Ă��܂��܂ȕs�K�v�Ȃ��Ƃ��ׂ��Ƃ��납�琶����B�l�������V�q�̂�����V���ׁV���s���Ȃ�A�����ɂ��̌l�I�ȍЉЂ��̂����݂̂Ȃ炸�A�����ɂ�����`���̐����ɌŗL����ЉЂ������Ƃ��ł��낤�v
�@���i���i���͌����B
�@�u�l�ނ̕����̘c�݂Ɗ댯�����x�����A�l�Ԃ̕s�K�v�Ȃ��ƂȂ݂̓O��I�Ȑ�̂Ă������āA���ׂ̈��炩�ȎЉ�ɐl�ނ̎�����������̂��A�V�q�����̍ŏ��̓N�l�ł���v
�@�g���X�g�C�ƕ��i���̎w�E�͂Ƃ��ɐ������Ǝ��͍l����B���̎v�z�ƈ�v����B�����Ƃ́A���̂�̖�S�̂��߂ɁA�l�ނɂƂ��ĕs�K�v�Ȃ��Ƃ���肷����B�v�D�g�D�I�[�f���́u�����j�Ƃ����̂́A���܂�ɂ��ƍߓI���a�I�ł���A��҂̊w��Ƃ��Ă͂ӂ��킵���Ȃ��v�ƌ��������A����������ł���B�����j�́A��ʂ��猩��A�l�ނɂƂ��ĕs�K�v�Ȃ��Ƃ���s���������͎҂̍s��̏W�ςȂ̂ł���B
�@���㐢�E�ŋN���Ă��邱�Ƃ͉����B�u�b�V���đ哝�̂𒆐S�Ƃ���č����{�̎w���҂������A�C���N�푈�Ƃ����l�ނɂƂ��ĕs�K�v�ł��邾���łȂ��A�ƍߓI�Ȃ��Ƃ��n�߂��\�\�Ƃ������Ƃł���B�T�_���E�t�Z�C���͍D��I�ȓƍَ҂ł���B�����A�t�Z�C���������������邽�߂ɕč����푈���d�|����̂͋��s�ł���B��ƍِ����̍����͈Ⴄ���@�������čs���ׂ��ł���B
�@�C���N�푈�ł͌R���I�Ɉ��|�I�D���ȕč��������낤�B�����A���̏����͐V���ȁu�����̏Փˁv�������炷���낤�B�u�b�V���Đ����Ƀu���A�p����킪���̏�����ǐ����Ă���B
�@����͍�������ɂ����Ă��A�č����{�̎w���ɏ]���A�\�����v�Ƃ������{�l�ɂƂ��Ă͕s�K�v�Ȃ����łȂ��a�I�ŔƍߓI�Ȑ�����s���Ă���B����\�����v�͕n�x�̍����g�債�A���������҂Ɣs�ҁA���҂Ǝ�҂ɓ��A���a�ʼn����Ȓ��a�̂Ƃꂽ���{�Љ���A�Η��Ɖߏ�ȋ����ƍ����̎Љ�ɕς��悤�Ƃ���ƍߓI�Ȏ��݂ł���B
�@����ƒ|���������Z���́A���{�̋��Z�@�ւ̎�݂ɂ�����ŁA��s�����L�����A���{���{�̎�ŕs�Ǎ�������������ŁA�č����Z���{�Ɉ������鉿�i�Ŕ���n�����Ƃ��Ă���B
�@���{�̋�s�͊�{�I�ɂ͌��S�ł���B���{�����������������ڂŋ�s�̎����Đ��������p�����Ƃ��Ă���A��s�͗������邱�Ƃ��ł����ł��낤�B�܂��A�����̒������Ƃ��|�Y�E�p�Ƃɒǂ����܂ꂸ�ɐ������т邱�Ƃ��ł����ł��낤�B����A������ł��x���Ȃ��B�|�����Z�s������������܂��Đ��͉\���B
�@�u�b�V���Đ����́A����ȌR���͂ƌo�ϗ͂ɂ��̂����킹�āA�������ɕč��������V�X�e�����������A�����̌o�ς��x�z���A�Ζ�����ɓ���A�����Đ��E���x�z���悤�Ƃ��Ă���B�ČR�͈��������900�N�O�̏\���R�̂悤�ɂȂ邨���ꂪ����B�č��̗��v�Ɛ����Ƃ̖�S�̂��߂ɕč����̐������͂ő������ɋ������悤�Ƃ���ُ͈̂�ł���A�a�I�ł���A�ƍߓI�ł���B���̂悤�ȋ����I�Ȃ����������I�ɐ������邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�u�b�V���I�ȋ����ȌR���s���͐��E���̐l�X���甽������邾�낤�B�l�ނ̈ӎv�ɔ�����s�ׂ͉i�����Ȃ��B�ŖS�̓��͂��������͂Ȃ��Ǝv���B
�@���E�̐��������w�Ԃׂ��́u���ׁv�̘V�q�N�w�ł���B���{�������ł���B�������u���ׁv�ɓO���邱�Ƃɂ��A�l�ނ͎��R�ɐ����邱�Ƃ��ł���B����n���������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂Ƃ��A�l�ނ͐����̐l�דI��Q���玩�R�ɂȂ�̂ł���B
2003.4.6
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�U�n
�n���Ɣ_���̋��������A���{�̒����I�ȍĐ��̓��ł���
�u�J�_�i��������j�͎��Ȃ��B��������āi����т�j�ƈ��i���j���B���Ă̖�A�����V�n�̍��ƈ����v�i�V�q�j
�y�J�Ԃ̐_��͉i���s�łł���B����������s�v�c�Ȏ��Ƃ����B�J�́u��Ȃ���́v�B��Ȃ���̖̂�A���ꂪ�V�n�̍����ł���B�z
�@�����ɂ͎��R�̋��ՂȐ����͂��^������V�q�̎v�z�̐_����������Ă���B
�@2003�N�S���\�\�S�N�Ɉ��s���铝��n���I�̌��ł���B�S��13���ɂ͓s���{���Ɛ��ߎw��s�s�̎Ƌc���̑I�����s����B�㔼�̂S��27���ɂ͎s�����̎Ƌc������э���c���̕⌇�I�����s����B
�@�O���̑I���Œ��ڂ���Ă���̂��A�����A�k�C���A�_�ސ�A�O�d�A����̒m���I���B
�@���̂��������͒����̐��Ǔ����Ƃ̊֘A�Œ��ڂ���Ă���B�Ό��m���̍đI�͊m���ƌ����Ă��邪�A�ᔻ�[�̐��ɂ���Ă͐Ό����̍����ւ̓��ɉe�����o��B��������u�Ό��Җ]�_�v�͍��܂�B�t�����蓾��B�Ό����̓��[�����ӊO�ȂقǒႩ�����ꍇ�͂Ƃ��ɉe�����傫���B�u�Ό��v�̉\��������߂ĒႢ�Ƃ������ƂɂȂ�A�s���ɂ�����Ό����̋��S�͂͒ቺ����B�}�X�R�~�̐Ό���^�̃g�[�������ɂȂ邩������Ȃ��B���܂܂ł͐Ό��s���ւ̓s���̕s���́A�Ό����ɉߏ�ȍD�ӂ�����}�X�R�~�ɂ���Ė�������Ă����B�������Ό����̋��S�͂�������A���܂܂Ń}�X�R�~�ɂ���Čy������Ă����s���̕s�����\������Ă���B����ƂƂ��ɓ��{�B��̔ɉh�̋ɂł��铌���̂����������炩�ɂȂ�B���̕����֓����\��������B�����o�u���͏I���ɋ߂Â��B
�@�k�C���A�_�ސ�A�O�d�A����̂S�m���I�ɂ́A���E�m�����ށA�����Ƃ�����قǂ̑����̗����҂ɂ�錃��A�Ƃ�������������B���̌����́A�����̒n�������̊�Ղ̕���ɂ���āA�����}���m�����҂�����͂����������Ƃɂ���B
�@����\�����v�́u�D����s�v�u�����d���E�n���y���v����ɂ��A�n���̐��ނ͒������B�o�Ϗ͈����̈�r���B�n�������͕N�����A�����̗̂͂͐����Ă���A�O�C�҂���p�҂��w������͂͂Ȃ��B���̂����n���̗L���҂̐����s�M�͐[���ł���B
�@�n���Đ��͓����ē��������B
�@���̒m���I�\�\���A����A����A�����A�����A�啪�\�\�͖����I���̌X���������B���挧�̏ꍇ�͌��E�m���������[���I���邱�ƂɂȂ����B���̌��ł͗L�͑Η���₪�����Ȃ��B�����̌��ł͓��[���̒ቺ���S�z�����قǐ��������C�͂ł���B�L���҂̐����I���S���������Ă���B
�@������̑傫�ȑI����44���{���̋c���I�������A�ߋ��̑I���ɔ�ׂĖ����[���I�҂��}�����Ă���B����҂��������Ă��邩�炾�B�����Ƃ��߂����l�Ԃ����Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł���B�I�����s����ꍇ���A�^�̌����Ƃ����̂͂قƂ�ǂȂ��B
�@�S��27�����[�̎s�������x���̑I���ɂ����l�̌X����������B���̔w�i�ɂ���̂͒n���E�n��̐��ނł���B����́A���{�̍����܂ł̊����I�Ȓ����d������̌���ł���B������t�̍\�����v�͒n���j����}���ɐi�߂Ă���B
�@�n���E�n��ɂ́A���R������B�_�Ƃ�����B���R�Ɣ_�Ƃ͐l�ԎЉ�̊��͂̌���ł���B
�@���{�̍Đ��̂��߂ɂ́A���R���̕ۑS�A�n���E�n��̌o�ς̊������A�_�Ƃ̍ċ����K�v�ł���B
�@�����͕č��ւ̒�������`���Ƃ��Ă���B�����ł͓������ɉh����`�ł���B�u�����g�v�D��ł���B
�@���̂悤�ȕn������������߂����āA���R�̂��{���̊��͂������ɂ��鐭����Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����]���̎����߂Â��Ă���B���܂����A��Ȃ鎩�R�Ɣ_�Ƃ�h�点�邽�߂ɁA�������I��点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

2003.4.7
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�V�n
�@�u�V�͒����n�͋v���B�V�n�̂悭�������v�����䂦��́A���̎��琶������������ĂȂ�B�̂ɂ悭�������B�����������Đ��l�́A���̐g����ɂ��Đg��A���̐g���O�ɂ��Đg�����B���̎��Ȃ��������Ăɂ��炸��B�̂ɂ悭���̎��𐬂��v�i�V�q�j
�y�V�n�͉i�����B�Ȃ��i�����B�V�n�������悤�����悤�Ɠw�߂Ȃ����炾�B���l���A�l�ɐ�悤�Ƃ��Ȃ����߂ɁA�������Đl�̐�ɂȂ�B�킪�g��Y��錋�ʁA�������Ă킪�g��S������B���Ȃ�v�p���邩�炱�����Ȃ��m���ł���z
�@�ȏ�̘V�q�̌��t���A�Љ�ɂ�����l�Ԃ̏����p�Ƃ��ĉ��߂�����������邪�A���͏����p�z�����v�z�Ƃ��đ����Ă���B
�@���{�ɂ��Â�����g���Ă������t�Ƃ��āu�g���̂ĂĂ��������Ԑ�������v������B�o�T�́A����l�i903~972�j�̍�Ƃ�����u�R��̖��ɗ����ɍ��i�Ƃ�����j���g���̂ĂĂ��������ސ�������v�ł���B���́u�����ސ��v�Ƃ́A���̌���@���A�����̋@��̈Ӗ������A�����p�Ƃ��Ďg����ꍇ�͋��n�E�o�̍ۂ̐S�̎��������Ӗ����Ă���B
�@���݂̐���������ƁA�w���I�Ȑ����Ƃ̂Ȃ��ɂ́A���������̐����c���D�悳���A��ɐl�ɐ�悤�Ƃ���^�C�v���ڗ��B���̎�̏o�����^�łȂ���Ύw���I�Ȓn�ʂɂ����Ƃ�����ɂȂ��Ă���B�}�X�R�~�͏o�����^�����Ƃɂ̂ݒ��ڂ���B�����Ȑl���̐����Ƃ̓}�X�R�~�ɍD���ꂸ���������B�Q�[�e�́u�����ł��邱�Ƃ��킫�܂��Ă���l�́A�ō��̂��Ƃ���Ă邱�Ƃ��ł���v�ƌ��������A���{�̐��E�ł͌������Ɩ����ȃ^�C�v�̐����Ƃ��肪�ڗ����Ă���B�����Ȃ�̂̓}�X�R�~���ُ킾���炾�B
�@�u�b�V���哝�̂���u���̐����v�Ǝw�����ꂽ�C���N�Ɩk���N�̓�l�̓ƍَҁ\�\�T�_���E�t�Z�C���哝�̂Ƌ������k���N���h�ψ����\�\
�����łȂ��A�����`�̍��̎w���҂ɂ��o�����^�������B�u�b�V���đ哝�́A�u���A�p�A�������u���Ȃ�v����v�^�C�v�ł͂Ȃ��B���܂�u�I�����I�����v�^�C�v�̐����Ƃ��肪���ې����̕���Ŏ���̍����߂Ă���B
�@�l�ɐ�悤�Ƃ���w���҂��Փ˂��č��ƍ��Ƃ̑����������A�g�債�āA�₪�Đ푈�Ɏ���B�w���҂͐킢�ɏ����ĉp�Y�ɂȂ낤�Ƃ���B�푈�͂��������̏����̉p�Y�Ƒ����̎S�߂Ȕs�҂ݏo���B��l�̉p�Y���a�����闠���ŁA�������̐l����O���s�K�ɂȂ�B�����̎��҂��o��B�����҂��o��B�����̕x��������B����ł��o�����^�����Ƃ͐푈�ɓːi����B�����Ă�������푈���n�߂���A�����ēr���ł�߂悤�Ƃ��Ȃ��B�푈�͏��҂Ɣs�҂����肷��܂łÂ��B���̊ԑ����̐l����������B
�@���{�́A����E���̔s�k�Ȍ�A�u�T���ڎ�`�v�I���������Ƃ邱�ƂɂȂ����B�ŋ߂܂œ��{���{�͂��̐�������ʂ��Ă����B
�@�������A�C���N�푈���n�܂�ƁA�����͕č��x����\�������B�����͓��{�̍��Ƃ��Ă̐�������傫���]�����悤�Ƃ��Ă���B
�@�����A���{�͑����́u�T���ڎ�`�v���̂Ă�ׂ��ł͂Ȃ��B�u�l�ɐ�悤�Ƃ��Ȃ��������v���т����Ƃ��A���{�����E�̂Ȃ��ŕ��a�ɐ����铹�ł���B
2003.4.8
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�W�n
�n�x�̍��̊g����߂�������\�����v�͔������I����ł���
�u��P�͐��̂��Ƃ��v�i�V�q�j
�@�y�ō��̑P�͐��̂��Ƃ����̂ł���z
�@���̌��t�̌�Ɏ��̈Ӗ��̕����Â��\�\���͖����Ɉ̑�Ȍb�݂�^���邪�A�����Ƒ������Ƃ͂��Ȃ��B����ʂ��炱���A�ߎ����Ȃ��A��߂��Ă���邱�Ƃ��Ȃ��B
�@������t�����ȗ��Q�N�ԌJ��Ԃ��w�E���Ă������Ƃ����A����\�����v�Ƃ́A���ɕs�Ǎ������ł���B����́A���{�̋�s�������ߐs�����āA�₪�č��L�����A���̎�ŕs�Ǎ��������͂����Č��S��������A�č��̋��Z���{�Ɉ�������n�����Ƃ�_�����u�b�V��������d�̂��߂́u���v�v�ł���B����\�����v�͓��{�̍����̂��߂łȂ��A�č�����t�@���h�̗��v�̂��߂̉��v�ł���B�����ɗ��v�������炷�{��Ƃ͐����̂��̂��B
�@���̂悤�Ȕ������I�ȉ��v���A�������Ďx�������������}�X�R�~�̍߂͏d���B�}�X�R�~�̑�ƍ߂ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�Ƃ��ɍߐ[���̂́A����ƒ|�����Z���Ƌ��Z���̊������B�|�X�g����̓��t���ł�����A�������I����̎��s�ӔC�҂𐭎��ƍߎ҂Ƃ��ĒNjy���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
�@����\�����v�̑��́A�����Č����B����ƍ����Ȃ́A�ŗD�悷�ׂ��i�C���������Č��̕����d�������B����͑傫�ȉ߂��ł���B���̌��ʁA�i�C�͉������A�Ŏ��͌������B���Ɨ��͋}�㏸�B���ʂ͍����Č��ǂ��납�����̈�w�̈����������炷���ƂɂȂ����B����͑�ߎ���Ƃ����̂ł���B
�@����́A�i�C�����؍u���悤�Ƃ����ɁA�s�����i���ʂ̋����\�����v��i�߂��B����ł͌i�C�����g���邱�Ƃ͕s�\���B����͂��̖������u�ĕS�U�v�̘_���Ɓu�ɂ݂ɑς��Ċ撣�낤�v�̌y���Ȋ���_�ŏ��낤�Ƃ����B
�@����̍������]���ɂ��鐭����\�ɂ����̂́A�}�X�R�~�̏����x���������B�}�X�R�~�́u�ĕS�U�v�_�Ɓu�ɂ݂ɑς��悤�v�_��ϋɓI�ɉ��������B�}�X�R�~�͂��̓_�ɂ��Ă��傫�ȉ߂���Ƃ����B�������x���������Ƃɂ��ă}�X�R�~�̐ӔC�������ׂ��ł���B
�@����\�����v���X�^�[�g���Ă���Q�N�̊Ԃɕ��ϊ����͖��ɂȂ����B���Ɨ��͏㏸���A�ƍ߂͋}�������B�n�x�̍��͑啝�Ɋg�債���B�����̕x�҂����܂ꂽ���ʂŁA�����̕n�҂����ݏo���ꂽ�B�����̍K���Ȑl�X�ƂƂ��ɑ����̕s�K�Ȑl�X�����܂ꂽ�B
�@��P�͐��̂��Ƃ��\�\�����̍��{�����������t�ł���B�����炭�A�����|�����Z����̍\�����v�h�ɂ́A���̂悤�ȍ��M�Ȏv�z�͗����ł��Ȃ���������Ȃ��B
�@�����]�����}���ł���B����������]�������₷��Ȃ�A������t���̂��̂�|���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���}�Ɍi�C����u���āA���������A�������ƁA�_�Ƃ������o�ϐ�������s���ׂ��ł���B
�@��Ȃ̂́A���{���˂ɍ��������������{����Ƃ�Â��邱�Ƃł���B�����Ɂu�ɂ݂ɑς��āc�c�v�Ƌ��߂�悤�ȗ⍓�Ȍo�ϐ���͂Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
2003.4.9
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m�X�n
�����w���w�̉��₩�Ȑ����オ���{���~��
�u�������g��ނ��́A�V�̓��Ȃ�v�i�V�q�j
�@���̌��t�̑O�Ɏ��̈ӂ̕��͂�����\�\�u���������t�͂��܂ł������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�s���Ȑn���͐܂�₷���B�����~������Ȃ炸�_����B�x�M�ɂȂ��Ė��S����͍̂Ж���������Ƃ��v�i�w�����̎v�z�Y�^�V�q�E��m�x�A���ԏ��X���j
����Ȑ������͂���ɂ����w���҂ɂƂ��čł��ނ��������̂́u���ގ����v�̑I���ł���B�V�q�̋��������s����w���҂͂���߂ď������B�命���̎w���҂͌��͂���������Ƃ����A�撣��B���͂Ɏ�������̂ł���B�������A�����オ�Ȃ���ΐ����͍d��������B�Ⴏ��悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�����Ȑ����オ������������������B
�@�S���U���i���j���A�t�W�e���r�u�Q�O�O�P�v�ɒ��]���N�O���i84�j���o�����Ă���̂������B���܂ł����C�Ŋ���Ă���̂͂߂ł������Ƃł���B����͈ꌩ�悳�����Ɍ�����B�����A�u�߂�����͗P�y���邪���Ƃ��v�̊��͔ۂ߂Ȃ��B���]���������܂ł������Â��邱�Ƃɂ���āA���̐���i�Ƃ��ɏ��a�P�P�^����j�̊���̏ꂪ�}�����Ă���B���̐���̐����Ƃ͒n���ōT���ڂł��邽�߁A���]�����قǂɂ͖ڗ����Ȃ����A�D�ꂽ�l�ނ����Ȃ��Ȃ��B�����̐l�ނ��\���Ɋ���ł���ꂪ�Ȃ����Â��̂́A���{�ɂƂ��đ傫�ȑ����ł���B
�@���]�����Ƌ{���ꎁ�̓�l�̌��������A���܂ł��ˏo���ē��{�̎w���I������ێ����Ă���B����̓}�X�R�~�̕s�����ɂ�����������B���]���A�{�������܂ł����{�̎w����ɂ������Ƃ���̂͑傫�ȉ߂��ł���B
�@�����̓��{�����ʂ��Ă��鏔����̍��́A�����̌o�ϐ����̐������̂��̂ɂ���B���{�́A�s�풼��̖��̏��痧���オ��A��㕜����60�N��̍��x������B�����A70�N��̓�x�̐Ζ���@���������A80�N�㏉���Ɍo�ϑ卑�������������B�������A���̐����������炵���V�X�e�������̌�L�������������B����Ȃ̂ɓ��{�͉ߋ��̃V�X�e���̈ێ��ɂ���������B���ꂪ90�N�ォ�獡���Ɏ���厸�s�̂��Ƃł���B
�@80�N�㔼�܂ł̐����̂��ƁA80�N��㔼�̃o�u���o�ρA90�N�ォ��̒����s���\�\���̎��s�̌����́A�����̌��̈ӎ���V���Ȏ���ɂȂ��Ă��ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ����������̍d�����ɂ���B
�@���̐����Ǝ��s��50�N�Ԃ��A�����ƂƂ��ɐ����Ă����̂����a�P�P�^�O��̐���̐����Ƃł���B���̐���͐�゠�鎞���܂ł͍����̈�l�Ƃ��č����ƂƂ��ɋ�J�𖡂���Ă����B���̐���͐����{���悭�m���Ă���B���̎���ɂ͉����ǂ����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ�����m���Ă���B�����A���̐���̐����Ƃ������Ŋ�������@��͂Ȃ��B���܂ł����ނ��悤�Ƃ��Ȃ����̑O�̐���̐����Ƃ����邩��ł���B
�@���]����������c���ɏ����I�����̂͏��a22�N�A�{���G���[�g�������獑��c���ɂȂ����̂͏��a28�N�̂��Ƃ������B���]���A�{���͎w���w�̈���Ƃ��Đ��58�N���Ă����B����������Έ�ʂ̍����Ƃ��Ă̐����̌����Ȃ��B�ӎ��̖ʂō����ƗV�����Ă����B80�Α�̐����Ƃ́A���ܓ��{�ʼn����N���Ă���̂��A�{���̂��Ƃ͕������Ă��Ȃ��B
�@�Ƃ��낪���a�P�P�^����̐����Ƃ́A�푈���P�����Ƃ��Ă܂��w�k�Ƃ��đ̌����A�s�풼��͂ǂ��̂Ȃ��œ����Â��A���̌㐭���Ƃ̓����u�����l�����ł���B���̐��オ���x�o�ϐ��������S�����B
�@���a�P�P�^����͏O�@��60���A�Q�@��38���A���v98��������ɂ���B����c���i727���j�ɐ�߂�䗦��13�����B���̂Ȃ��ɂ͐��X�̈�ނ�����B�������A���̐���ɂ͍T���ځA�n���A�����ԌX���������A���]�����̂悤�ɔh��ȃp�t�H�[�}���X�����ӂłȂ��B���̂��߂Ƀ}�X�R�~�ɂ͂��܂�D����Ȃ��B
�@�}�X�R�~�Ƃ��Ƀe���r�͉��Z�͂̂���^�����g�^�����Ƃ��D�ށB�}�b�N�X�E�F�[�o�[�̐��������Ƃ̎����\�\��M�A���@�́A�ӔC���\�\����ɂ��Đ����Ƃ�]������悤�ȋC�̂������e���r�}���͂قƂ�ǂ��Ȃ��B�e���r�ǂ͎����������`�ł���B�����̓e���r�ɏo�����Ȃ������Ƃ̂��Ƃ͂قƂ�ǒm��Ȃ��B�m���x���ő�̉��l�ƂȂ������x��Љ�ɂ����āA�e���r�͒m���x�Ɖ��Z�͂��d�����ďo���҂����߂�B�m���x���Ⴂ�����Ƃ́A�����ɗD�ꂽ�����\�͂������Ă��Ă������I���[�_�[�ɂȂ�̂͂ނ��������B�e���r�}���̕s�����������ŗL�\�Ȏw���҂̓o���W���Ă���B
�@���ނ̓N�w�\�\���Ă̓��{�l�ɂ͂��ꂪ�������B��l�����͎��̐���ɏ\���ɓ������^���邽�߂ɁA���ނ̎������ԈႦ�Ȃ��悤�C��z�����B��������̐����w���҂́u�����ہv���킫�܂��Ă����B
�@�����吳����ɂȂ��āu���ނ̓N�w�v�������ʎw���҂��������B���]�������ɂȂ��Ă������30�N�ȏオ�o�B�����߂Ă���25�N�ȏゾ�B���̊ԁA���]�������w���͂��ێ����Â��Ă����㏞�Ƃ��āA�����̗D�G�Ȍ�p�҂������\���ȓ����ꏊ�邱�ƂȂ��������������茸�炵���B�{�̏ꍇ�����l���B�����͎��̑��I���ɂ����Ă����̓������s�g���āA����ŏO�c�@�c���̒n�ʂ��ێ����Â��悤�Ƃ��Ă���悤�Ɍ�����B�������V�q�̌����u�V�̓��v�ɏ]���āA������y�ɓ������邱�Ƃ�]�݂����B
�@�Â����x�����^�̐����o�σV�X�e�����I��点�A�V����21���I�^�V�X�e����z�����߂̑��p�̎d���́A���58�N�Ԃ̗��j��̌��������a�P�P�^�O�㐢��ɂ�点��̂��悢�B���̐��ケ���A�Â�����Ɉ�����n���A�I��点�A���̎���̘g�g�݂�n�����������S���ׂ��ł���B���̖������ʂ�������A�����Ɂu�V�̓��v�ɏ]���Ĉ��ނ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���Ⴂ����50��A40��A30��̐����Ƃɂ́A���̑厖�Ƃ�B������m�b���n�͂��Ȃ��B���̐���̐����Ƃ͗c�t�ł���B�m���͂��邪�m�b���Ȃ��B�{���̋�J��m��Ȃ��B�܂����n�ł���B�������炭�͒m�b�Ɣn�͂̂���70��A60��̐����Ƃɓ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���łɌ����A���{�̎̍ݔC���Ԃ͂Q�N�ŏ\�����B������č��̏]�����ł�����{�̎������������ێ����悤�Ƃ���̂́A���{�ɂƂ��Ċ댯�ł���B�č����{�̎x���邽�߂ɓ��{�̍��v���]���ɂ������]�����t�Ȍ�A���{�̍��x���ǂꂾ���č��Ɉړ]�������\�\���������A�����]�Đ����̊댯���͖��炩�ł��낤�B������t�̂Q�N�ԂɁA���{�̍��v���ǂ�قNj]���ɂȂ������B���z�̓��{�����̕x���č��̂��̂ɂȂ����B
�@����́u�V�̓��v�ɏ]���Ĉ��ނ���̂����{�����̂��߂ł���B����\�����v�͓��{�����ɂƂ��Ă͕S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��ł���B�@
2003.4.10
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m10�n
���a���肤���Ƃ��߈�������ŋ߂ُ̈�ȕ�����J��
�u�l���������������߂�ɂ��āA���ׂ�����Ă��邾�낤���B�c�c�����̗������߂�ɂ������āA�m�̌��E���킫�܂��Ă��邾�낤���B�w���x�͖����݁A������{���B���������ۂ����Ȃ�������̌��ۂ��Œ肳�����A���݂����Ȃ���������ւ炸�A���������Ȃ�����x�z���Ȃ��B���ꂪ�w���x�̒�m��ʓ��ł���v�i�V�q�j�m�w�����̎v�z�W�^�V�q�E��q�x�i������E��щv�v��j�A���ԏ��X���A�����p�n
�@�V�q�N�w�̍��{�ɂ���u���ׁv�Ƃ́A�u�����Ƃ��Η������A�����ɑ��Ă�����Ȃ��A�Ȃ���Ŏ������A�݂�����̌����ւ炸�A�Ђ�����Ƃ��ĐÂ��ɁA�������Ƃ��Ă������邪�܂܁v�i���i���i�w�V�q�x�A�����V���Њ��j�Ƃ����Ӗ��ł���B
�@�ŋ߁A���E�ƃ}�X�R�~�̂Ȃ��ɁA���a���肤���Ƃ����������߈��ł��邩�̂悤�Ɉ����ُ�ȋ�C�����܂�Ă���B���Ɋ댯�ł���B
�@�S���W���A�V���P�ʃg�b�v�ɂ́u�ČR�A�哝�̋{�a��苒�v�i�����A�����j�A�u�o�O�_�b�h���S�������v�i�ǔ��j�A�u�ĉp�A��s�����𐧈��v�i���o�j�A�u�ČR�A�{�a�苒�v�i�Y�o�j�A�u�o�O�_�b�h���������v�i�����j�̑匩�o����������B�O���̂S���V���̃e���r�́A�ČR���C���N�哝�̂̋{�a�𐧈������͗l���J��Ԃ����f�����B
�@�ŋ߁A�e���r�͒�����ӂ܂łǂ��납�A�I��24���ԁA�C���N�ɂ�����ČR�̌R���s��������Â��Ă���B���E�ɂƂ��đ�Ϗd��Ȏ����Ȃ̂ŕ���͓̂��R�����A���̒̕��g�����ł���B����l�ɐl�ԂƂ��Ă̐[�݂��������Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�����̈ӎ��̖ʂŐ푈���߈��ƌ����Ȃ��X�������܂��Ă���B�푈��������O�̌����ɂȂ��Ă��Ă���̂��B�푈���l�ԂɂƂ��Ăǂ�Ȃɋꂵ���A�h���A�߂������̂��A�Ƃ����ӎ��������Ȃ��܂܁A�l�X�͐푈��������Ă����B
�@�u�����̂������Ől�Ԃ̎c�s���͏X���ɂȂ����v�\�\�h�X�g�G�t�X�L�[��1864�N�ɏ������w�n�����̎�L�x�̂Ȃ��̈�߂��B�ĉp�R�̍ŐV�Z�p���킪�e�͂Ȃ��C���N�����̏�ɗ��т����A�߂Ȃ��C���N�̘V��j���̐������D���Ă���B�����Y�t�F���h�č��h�����̗₽�����������ԓx�������ڗ��B
�@�C���N�푈���n�܂������͕ĉp�R�̔�l���I�R���s�����߂�l���e���r�ɏo�Ă������A�ŋ߂͕ĉp�R�̔ᔻ�҂̓}�X�R�~����قƂ�ǔr������Ă��܂����B�l����`�̎咣�҂̓e���r����p���������B�u�b�V���đ哝�̂̏]���ȃT�[�o���g�Ɖ���������̎x�������㏸����悤�Ȉُ팻�ۂ��N���Ă���B
�@�u�l�Ԃ͏]���ȓ����ł���B�ǂ�Ȃ��Ƃɂ����Ă��܂����݂ł���v�\�\������h�X�g�G�t�X�L�[�̌��t�B�����ƃ}�X�R�~���A�푈���m�肷�镗�����L���A�����̏펯���펯�ɕς��悤�Ƃ��Ă���B�܂��Ƃɋ��낵�����Ƃł���B
�@���A���{�A�č��A�p���ɐ��X�̐����w���҂��o�ꂵ���B�č��̑哝�́A�p���̎̂��Ƃ̓j���[�X�Œm�邾�������A���{�̎̂Ȃ��ɂ͒��ډ�����l�����l������B���ڌ��������̐l������B�����̉ߋ��̐����w���҂Ɣ�ׂāA���݂̏���A�u�b�V���哝�́A�u���A�ɂ͍ۗ��������F������B�ꌾ�Ō����u�₽���v�ł���B���̂R�l�قǁu�������v�Ɍ����������w���҂͉ߋ��ɂ͂��Ȃ������悤�Ɏv���B�����g�b�v�́u�₽���v���}�X�R�~�ɓ`�����A�e�E�̎w���w�ɍL�����Ă���B�����̎w���w�̊Ԃɂ͋��낵���قǘc�⍓�Ȉӎ����g�債�Ă���B
�@�R�����߂̂��Ƃ������B�R�����܂ŃR�����e�C�^�[��w�߂Ă����^�e���r�ǂ̃j���[�X�ԑg�i���͂Ȃ��j�ŁA�C���N�ւ̌R���U�����}���č����{�̎p����ᔻ���邽�߁A�u���͂ɑi����O�ɁA�܂��S��̘a��������݂�v�Ƃ����č��̖@�w�҃P���g�i1763�`1847�j�̌��t���{�[�h�ɏ������Ƃ���A�X�^�b�t����u�X�c����A���̌��t���g�����ɁV�T�_���E�t�Z�C���x���Ō����̂ł͂Ȃ��V�ƌ����Ă��������v�ƌ����A��ϋ������B
�@���͑����ɋ��ۂ������A��i���玄�̔����ɒ��ӂ���悤�Ɍ����Ă����߂�������ꂽ�B�u���a�����Ԏ҂̓T�_���E�t�Z�C���̎x���ҁv�Ƃ����č��h���Ȃ̎w���҂Ɠ����c�ӎ������{�̃e���r�ǂ̏�w���ɓ`�d���Ă���B�P���g�̌��t�͍����Ȃ��̂ł���B���ׂĂ̐����w���҂��S���ׂ����O�ł���B
�@���͂���������O�̏펯���������Ƃ������A�����f���ɗ������Ȃ��c��C���e���r�Ǔ��ɂ��邱�Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B���{�̑�����Ȃ�炩�̓����������������̂�������Ȃ��\�\����Ȋ��������B
�@����́u�l���������������߂�ɂ��āA���ׂ�����Ă��邾�낤���v�\�\�ۂł���B�l�����������A���{�̍��v���ڂ݂邱�ƂȂ��A�����̉����̂��߂Ƀu�b�V�������ɒǏ]���Â��Ă���̂������ł���B���̂悤�Ȑ��������X�Ƃ��Ďx���Ă���G���[�g�����A�G���[�g�e���r�}���A�����Ď̎��ӂŃS�}������Â����p�w�ҁ\�\�ނ炱������łڂ������̎m�ł���B�w�V�q�x�́u���ׁv�N�w���w��Ŕ��Ȃ��Ă��炢�����Ǝv���B����͗]�v�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�V�q�́u�����v������B�u�����v�Ƃ́A�u���i���݁j�������l�i�Ђ���тƁj�̓��v�i���i���i��j�A�u�����Ƃ��[���ȁw���x�v�i��o�ːL�E���c�p�j��j�ł���B
�@
2003.4.11
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m11�n
�₽��ɖ@����������Ă��Ă͎Љ�̓_���ɂȂ�
�@�u���ׂČ`������̂��𗧂̂́A�`�������̂�������x����������ʂ����Ă��邩�炾�v�i�V�q�j�m���i���i��w�����ÓT�I10�^�V�q�x�A�����V���Њ��A�����p�n
�@�u�w���x�̂͂��炫�����邩�炱���A�w�L�x���𗧂v�i�w�����̎v�z�Y�^�V�q�x�A���ԏ��X���j�A�u�w�L�x���l�ɗ^����֗����́A�܂������w���x������I���������邩�炾�v�i�w�V�q�x�A�������X���j�Ƃ���������������B
�@�V�q�́u���v�̕�������I�Ȃ��̂ƌ���B
�@���i��w�V�q�x����ɋ����Ă���̂́A�Ԃ̋A����̂Ȃ��̋�ԁA�Z��̋�Ԃ̎O�́u��v�ł���B��������̔\�|�̋����E������́u����킴�v�ɑ���u���ʂЂ܁v���ʔ����ƌ������i���i��w�V�q�x�j�B
�@�V�q�͂����œN�w�I�Ӗ���_���Ă���̂����A�u���v�Ɓu�L�v�̊W�́A�l�Ԃ̍s�ׂɂ��Ă��������邱�Ƃł���B���i��w�V�q�x�ɂ͎��̖��̓������i�Ƃ������傤�j�̊G��_�����p����Ă���\�\�u�R�����悭�ɂ͋����𖾂�߂Ȃ���Ȃ�ʁv
�@�|�p�̖ʂ����łȂ��A�l�Ԃ̎Љ�I�����ɂ����l�̂��Ƃ�������Ǝv���B�����Ɛ����̊W�́A�P�Ɍ`������̂����̊W�ł͂Ȃ��B�`����W�ȏ�Ɍ`�Ȃ��W�̕�������ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B�����Ǝw���҂̊Ԃ̋�Ԃɂ����Ӗ�������B���̋�Ԃ߂�̂��w���҂̐����ȓ��ł���B�w���҂ɓ����Ȃ���A�����Ɛ����Ƃ̊W�͔p���B
�@�č��ŋ�������ŋ߂̎Ⴂ�����Ƃ́A�V�q�I�ȁu���v�̐��E�������ł��Ȃ������łȂ��A�S����Ȃ��B�Ⴂ�����Ƃ́A�����Ɛ��{�Ƃ̊Ԃ́u��v�𗝉��ł��Ȃ����߁A�₽��ɖ@�������肽����B���������N����ƁA�����Ɂu�@�������낤�v�ł���B���̌��ʁA�@���͎��X�ɂ����邪�A�������A����͎Љ�����ꎩ���̏ɒǂ����ނ����ł���B�Љ�悭�Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��B�s���R�݂̂��g�債�A�Љ�炨���炩����������B
�@�T�~���G���E�W�����\���i�p���̎��l�E��]�ƁA1709�`84�j�͌����\�\�u���s�����Љ�ɂ͑����̖@��������v�B���s�����Љ�ł͖@�����������B�������A����ɂ���ĎЉ�悭�Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��B�Љ�̊��͂͒ቺ���A�Z�݂ɂ����ƕs���R���g��Đ��Y�����B��Ȃ̂͋������������炩���ł���B
2003.4.12
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m12�n
�u�b�V���哝�̂�Đ��{�w���҂ɁA�푈�ւ́g�~�]�h��}���A���E���a���u�����錒�S�Ȑ��_�����邩?!
�@�u���l�́A�����ς���ʂ��[�������āA�O�E�̎h�������߂Ȃ��B�܂�A�~�]���̂ĂāA�w���x�ɂ̂��Ƃ�̂ł���v�i�V�q�j�m�w�����̎v�z�Y�^�V�q�E��q�x�A���ԏ��X���A�����p�n
�@���̌��t�̑O�Ɏ��̕�������\�\�u���ʂȂ���ǂ�́A�l�̎��o�������Ȃ��B�h���I�ȉ��y�́A�l�̒��o��������B��̂������͐l�̖��o�����킹��B�����D��Ŋl����ǂ����ƂɔM������A�l�̐S�͕��t�������B����ɓ���悤�Ɩ����ɂȂ�A�l�͍s��������܂�v�B
�@���݂̖����`�Љ�̎w���҂Ɂu���l�v�I�����������߂�̂́A������������i�̃��T�C�N���V���b�v�Œ������i��T���悤�Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ�O��ɂ��Ĉȉ��̂��Ƃ������B
�@���{�̒m���w�i�u���{�ɒm���l�͂��Ȃ��v�Ƃ������͖����ł��Ȃ����A�����ł͓��{�ɂ��m���w������Ƃ̌��O�d���邱�Ƃɂ���j�͕č����D�����B�č������h�ȍ����ƐM���Ă���B�������A�����ꕔ�Ƃ͂����A�u�b�V�������ɑ��Ă͋����x����������B�u�C���N�푈�ő叟������A�u�b�V���͎��ɂǂ̍����U�߂�̂��B�u�b�V���͐��E���e�ɏo�Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̋^�O������B
�@�B��̒��卑�E�č��̎w���҂����́A����ȌR���͂������Đ��E�x�z�ւ̓���i�ݎn�߂�̂ł͂Ȃ����Ƃ����S�z���A���ɂ͂���B�u�b�V���哝�̂̎p���A�ߋ��̐����҂ƃ_�u���Č�����B�A���N�T���_�[�剤�iBC356-323�j�A�\���R�̃E���o�k�X�Q���i1042�|1099�j�A�����S���鍑�̃W���M�X�J���i1162�|1227�j�A�i�|���I���i1769�|1821�j�c�c�B
�@�����S�z����̂́A�C���N�푈�ɂ����Ċ��S�ȏ��������ƁA�u�b�V���哝�́A�`�F�C�j�[���哝�́A�����Y�t�F���h���h�����炪����ȕ��͂������Đ��E���]�����悤�Ƃ��������҂̐S���ɂȂ邱�Ƃł���B����Ȍ��͎҂͘����a�ɜ��₷���B�����Ȃ�A���낵�����Ƃ��N����B���E�����������ޑ�O�����E���̂����ꂪ�����B
�@�đ哝�̂Ƃ��̑��߂������C�ɂ���Ȃ��ƍl����w���҂̂��鍑�ɑ��āA�e�͂̂Ȃ����͍U���������邨���ꂪ����̂��B�s�K�ɂ��A�đ哝�̂����ɂ܂��悤�Ȑ��{�w���҂������������́A�č��̔��e�𗁂т�����B�����鎩�R��D���邱�ƂɂȂ�B
�J��Ԃ����A�č��͂��܂�B��̒��卑�ł���B�R���I�ɂ��o�ϓI�ɂ����E����G�ɂ��Ă����͂������卑�ł���B���܂̕č��Ȃ�A�ǂ�ȂɂЂǂ����Ƃ����Ă��A����������ʂ��͂������Ă���B���E����G�ɉĂ��A�č������܂����ׂ�邱�Ƃ͂Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��č��̎w���҂͂����l���Ă���ɈႢ�Ȃ��B���͂�u�b�V�������̖\����j�~�ł���͕̂č��������Ȃ����A�������ƂɁA�č����̈ӎ������{�̏��ɂ���ăR���g���[������Ă���B�ނ���u���I���I�v�̋�C�������B�}�X���f�B�A�����{�̃R���g���[�����ɂ���B�����ł����R���郁�f�B�A������A�����ɒׂ����B
�@�}�b�N�X�E�E�F�[�o�[�́w�Љ�w�̍��{�T�O�x�̂Ȃ��Łu�w�x�z�x�Ƃ́A������e�̖��߂��������ꍇ�A����̐l�X�̕��]��������\���������v�Əq�ׂ����A�u�b�V���哝�̂����E���]�����悤�Ƃ����U�f�ɐg���䂾�˂��Ƃ�����ǂ��Ȃ邩�B�c�O�Ȃ���A����͕s�\�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
�@�I���e�K�E�C�E�K�Z�[�́w��O�̔��t�x�̂Ȃ��ł����q�ׂ��\�\�u�^���C�����̓i�|���I���Ɍ������Ď��̂悤�Ɍ������̂��B�w�É��A�e���������Ă���Ή������ł��܂����A������A�ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B����͏e���̏�Ɉ������邱�Ƃł��x�v�A�ƁB
�@����ȌR���͂������Ă���Ή��ł��ł���B�������G���F�E���ɂ��邩�������~���������Ƃ��A�R���͖͂��ɗ����Ȃ��Ȃ�B���X�ɓG�����߂ĕ��͂��s�g���Ă����x������B�킢�͂����͏I���B���͂��̂��Ƃ̎x�z�ɂ���B���肵���x�z���\�ɂ���̂́A���ɓI�ɂ͐��_�ł���B���_�̎x���������Ȃ���A�x�z�͈��肵�Ȃ��B���E���̐l�X�����܂ł��č��̌R���͂�w�i�ɂ������\�ɂ��т��Â��邱�Ƃ͂Ȃ��B��R�����ɗ����オ��҂��K���o�ꂷ��B
�@���܂̃u�b�V���哝�̂͂��ߕč��̃��[�_�[�����̐��_��Ԃ͂ǂ��������̂��낤���B
�@�V�q�̂����u�l����ǂ����ƂɔM������A�l�͐S�̕��t�������v�悤�ȏ�Ԃł���A��ςł���B�܂��A�C���N�̐Ζ��Ƃ����u����ɓ���悤�Ɩ����ɂȂ�A�l�͍s��������܂�v�悤�ȏ�Ԃł���A����܂���ςȂ��Ƃł���B�@
�@�G���X���X�͂����\�\�u�푈�͍��Ƃ̉u�a�ł��萳�`�̕��ł���B����ɂƂ肩���܂ꂽ�@�͒��ق���B�啔���̖��O�͂�����A���a�����Ă���̂��B�����ď�ɖ��O�̕s�K�̏�Ɏ����ׂ��ɉh���������鏭���҂݂̂��A�헐��]�ނ̂ł���B�ނ�̔�l�Ԑ����A�����������̑P�ǂȐl�X�̈ӎu�ɂ܂���ׂ��ł��낤���H�c�c�푈�͐V���Ȑ푈�������A���ĂсA�s���e�͕s���e�ނ̂ł���v�i�u���a�_�̒Q���v�j�B
�@�Đ��{�w���҂ɂƂ��āA���̃G���X���X�̌��t�́u�n�̎��ɔO���v�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ����A�č��ɗ������߂邱�Ƃ�]�݂����B
�@���Q�l�����F�w�����ܓN�w�̐X�x�ʊ��u��`�W�v�A�}�����[���B�@
2003.4.15
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m13�n
�����Ƃ̐������ɂ���
�u������ɐg���ȂĂ��Ĉׁi�����j�ނ�A��i���Ȃ�j���V�����ׂ��v�i�V�q�j
�y�^�̈Ӗ��ʼn䂪�g���ɂ��A�Ȃ�̐��������ɂ���l�Ԃł����Ă������l�̐������ɂ��A���l�̐������ɂ��Ƃ����݂���������B�c
�c�]���āA���̂悤�Ȑl�Ԃł����Ă������߂Ĉ��S���ēV���̐������܂�������i���i���i�w�V�q�x�����V���Њ������p�j�z
�@���������S���Đ������܂��������Ǝv���悤�Ȏw���҂͋H�ł���B���݂̓��{�̐��E�ɍ�������M������鐭���w���҂��قƂ�nj�������Ȃ��Ƃ����̂́A�{���Ɏc�O�Ȃ��Ƃ��B���̌����̈�́A�����Ƃ��[���Ӗ��Ŏ������g���ɂ��Ă��Ȃ�����ł���B
�@�ŋ߁A���m�̍���c�����玟�̂悤�Șb�����\�\�u����Q���ɍs��ꂽ�֓��n���̂��錧�̒m���I�ŁA�ŗL�͂ƌ����Ă���������c���̌�₪�������B�ő�̔s���́A�̂̐V���L���̃R�s�[�����̌����ɂ�܂��ꂽ���ƁB���̍s�ׂ͑I���ᔽ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�N����������͂킩��Ȃ��B��܂��ꂽ�R�s�[�͗�؏@�j�O�c�@�c���̐��������Ɋւ�����́B���̒��ɗ�؎����猣���i�����郀�l�I�}�l�[�j�������������c���̃��X�g������A���̌��̖����������B�ނ͗�؎����猣�����������Œm���ւ̓����������B���̌�����c���͐^�ʖڂȐl���������̂ɋC�̓ł������v
�@���̍���c���͗�؎��Ɠ����h���ɑ����Ă����B�������S�����̗�؎��͔h�����������Ă����B������f�邱�Ƃ͑�ςނ����������Ƃ��������Ƃ͓���ɒl����B�������A�f�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߂ɐ����������������B������ɂ��鋭���S�������Ă�����A�����m���ɂȂ邱�Ƃ��ł�����������Ȃ��B
�@�ȏ�̌����́A�����܂Ŏ��ɘb����������c���̎�ϓI�Ȍ����ł���B
�@�ŋ߁A������l�̋��m�̍���c�����畷�����b���Љ��\�\�u�哇���X�O�_�����͑P�l�B����Ȃ��Ɓi�_�������C�j�ɂȂ��ċC�̓ł��B���E�̎������Ԉ�������߂Ƀ{���{���ɂȂ��Ă��܂����B�������߂Ă���悩�����B�c�c�����炭�A�����Ɉ������߂�ꂽ���߂ɁA���߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂��낤�B����͔_���������E����Β�R���͂�����t�����v�����o��̂������ꂽ�̂��낤�B�哇���͏���Ɂw�m�[�x�ƌ����Ȃ��������߂ɁA�Ђǂ����ƂɂȂ����v
�@������A���̍���c���̎�ϓI�Ȍ����ł���B
�@�哇���͎������g���ɂ��鐸�_���s�����Ă����̂�������Ȃ��B���̂��߂ɁA�����傫�ȃ��[�_�[�ɂȂ�\�����������B
�@�������g���ɂ���S�������A���̐S�ō������߂邱�Ƃ��ł���悤�Ȑl���������A���̐������܂������鐭���ƂɂȂ蓾��̂ł���B
�@�����Ƃ̃X�L�����_�������Ƃ�₽�Ȃ��B���K�X�L�����_�������łȂ��A�Z�b�N�X�X�L�����_�����₦�Ȃ��B���̂悤�ȕs�����ɓ��荞�ނ̂́A�u�^�̈Ӗ��ŌȂ��ɂ��A�Ƒ���厖�ɂ���S�v�������Ă��邩��ł���B
�@����̐������O�������Љ�̏�Ɏ������悤�ƌ��ӂ��������Ƃ́A�ዉ�ȗ~�]��G�S�C�Y���ōs�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�L���S�Ŏ������ɂ��A�����S�ō����������鐭���Ƃ��A���܋��߂��Ă���̂��B
�@�����Ȑ��_�������Đ����Ȑl�������ł��鐭���Ƃ����A���������S���Đ������܂������邱�Ƃ̂ł��関���̐������[�_�[�ł���B
2003.4.21
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m14�n
�����̘������l�ނ̖������낤������
�u���̖@�����͌Í�����т��Ă���B���̖@����������߂邱�Ƃɂ���āA�����Ƃ��Ắw���x���F���ł���̂ł���v�i�V�q�j�m������E�呺�v�v��w�����̎v�z�Y�^�V�q�E��q�x�A���ԏ��X�A���n
�@�Â��|��͎��̂Ƃ���\�\�u�Ái���ɂ����j�̓������i�Ɓj��ĈȂč��̗L�i�䂤�j����i�����j�ށB�În�i�����j��m��A����I�i�ǂ����j�ƈ����n�B
�@���i���i���͂�������̂悤�ɖĂ���i�w�����ÓT�I10�^�V�q�x�A�����V���Ёj�\�\�u���Â���̐^�������肵�߂āA�������ۂ���ɂ��Ă���B���j�Ǝ��Ԃ̎n����m�邱�Ƃ̂ł�����́A����̖{���Ƃ�Ԃ̂��v�B
�@��o�ːL�E���c�G�v��i�C�p���w�V�q�x�A�������X�j�ł́A�u���ɂ�������́w���x�ɂ��ƂÂ��Ėڂ̑O�̋�̓I�Ȏ����i�L�j���x�z���A���ɂ�������̎n�܂��F�����邱�Ƃ��ł���A������w���x�̖@���Ƃ�ԁv�Ɩ�Ă���B
�@��҂ɂ��w�V�q�x�̗����ɍ������邪�A���͉����E�呺�悢�Ǝv���B�w�V�q�x�́A�u���v���A�����Ȃ����́A�������Ȃ����́A�`���Ȃ����́A���o�ł͂��Ƃ߂��ʂ��́A���Ȃ킿�F�A���A�`�A���o���z������ʐ������������̂Ƒ�����B
�@�Ђ邪�����Č���͉Ȋw���\�̎���ł���B�Ȋw�Z�p���\��`�̂��Ƃł́A���o�ł��Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����͖̂����l�ł���B��������́A����������́A�`�̂�����݂̂̂��A���l������A�Ƃ����B�l�Ԃ��m�o�ł��Ȃ����̂̑��݂�F�߂悤�Ƃ��Ȃ��X���������B��������l�Ԃ̒m�o�ɑ���ߐM����������B�Ȋw�Z�p�ւ̉ߐM�������ށB�Ȋw�Z�p���\��`����Ƃ́A�l�ނ̍������ُ�ɍ��܂�������Ȃ̂ł���B
�@�Ȋw�Z�p�͐l�ނɑ���̗��v�ƂƂ��ɑ���̑��Q�������炵�Ă����B�������A����Љ�͉Ȋw�Z�p�̃����b�g�ƃf�����b�g�������ɕ]�����Ă��Ȃ��B�Ȋw�Z�p�̐��ʂ��ߑ�ɕ]�����A���Q���ߏ��ɕ]�����Ă����B
�@�����́A�l�ގЉ�ɑ��ď����ȍK���Ƒ傫�ȕs�K�������炵�Ă����B�������͎҂������ɐ������Ƃ��́A�����͐l�Ԃ̕s�K�����炷�������ʂ����Ă����B�����������͎҂������ɂȂ����Ƃ��A�����͐l�Ԃɂ͂��肵��Ȃ��قǑ���̕s�K������o�����B�ő�̕s�K���푈�ł���B20���I�̓�x�̐��E���ł������B
�@21���I�����̐��E�́A�B��̒��卑�ł���č��̃u�b�V�������̘����ɂ���āA�d��Ȋ�@�ɒ��ʂ��Ă���B���{�̏����̓u�b�V�������ւ̒ǐ��H�����Ƃ��Ă���B�����͓��{�̓Ǝ�����������A���{�̐i�H���u�b�V�������Ɏ�����a���Ă��܂��Ă���B
�@���ė����̐����͑傫�ȉ߂���Ƃ��Ă���B���{���{�́A�č����{�������Ȃ��A�����ȕ��͍s�g���~�߂�����i�ނ悤�A����������ׂ��ł������B�����ȃu�b�V�������̐K�n�ɏ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
2003.4.22
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m15�n
�V�q�I�����Ƒ��Ɠ�l�̓��{�̐�����
�u�Ái���ɂ����j�̑P���m����҂́A�������ʁA�[�����Ď��i���j��ׂ��炸�v�i�V�q�j
�@�u�P���m����ҁv�́u�m�v�́A���ԏ��X�{�i�w�����̎v�z�Y�^�V�q�E��q�x�j�ł́u�N���⍲���鐭���ƁA�m���K���v�A�������X�{�i�w�V�q�x�j�ł́u�w���x���킩�����l�v�̈ӁB
�@�`���̌��t�́A���ԏ��X�{�ɂ��ƁA���̂悤�ɂȂ�\�\�u�̂̐^�ɂ����ꂽ�l���́A�����[���ŁA����m��Ȃ���ʂ����Ȃ��Ă����v�B�����ɘV�q�I���z�̐����Ƒ���������Ă���B����̓I�Ɍ����Ύ��̂悤�ɂȂ�i���ԏ��X�{���v�_��E�o����j�B
�@�u�܂������ɐT�d�ł���B���ɁA���ɓI�ł���B�������A�d���ł���B�����Ɏ������ʁB����C���Ȃ����ƁB���S�Ȃ��ƁB�����đ������̂Ȃ����ƁB����͎��ɒ�m��ʐ[�������l���ł���B�w���x��̓������l�́A���S�ɂȂ낤�Ɠw�߂��ɁA���̂��Ɗ��S�ɂȂ�v�B
�@�V�q�̐����Ƒ��Ǝ̐����Ƒ����Δ䂳��邱�Ƃ������B���̓_�ɂ��ĕ��i���i���i�����V���Ж{�j�͎��̂悤�ɉ�����Ă���B
�@�u�m�`�E��V�Ƃ����ϗ��I�ȋK�͂�����̉��l�Ƃ��Ă���Ɍł��g���Z�i���j�����Ƃ���͎̂�Ƃł��邪�A�m�`��哹�̔p�ꂽ���̂Ƃ��A�m��f���`�����鎩�R�̓�����������̂͘V���i�V�q�Ƒ��q�j�ł���A����ɂ͑��������A�g���E���Đm�𐬂��A�`�����Ă������E�����Ƃ���͎̂�Ƃł��邪�A������ɐg���ȂĂ��A�Ȃ�̐����������鉿�l�K�͂ɗD�悳����̂͘V���ł���v�B
�@���i���̉��߂͓`���I�Ȍ������\���Ă���B���̉��߂͏�L�̕��i���̌����Ǝ��Ă��邪�A�����Ɍ����Ώ����Ⴄ�B�V�q�͎I�u�l��`�v�������A�u���R��`�I�Ȑ������v���Ȃ킿�u���R�Ŏ��R���A�������Ȃ��������v���咣�����B���K���ƃX�s�[�h���d������s�s�^�Љ�̐����Ƒ������߂�̂ɑ��āA�V�q�͎��R�Ɠ�������_���Љ�̐����Ƒ������D�ꂽ���̂ƍl����B
�@�Ђ邪�����čŋ߂̓��{�B��l�̐����Ƃ��ĕ]������Ă���B
�@��l��1960�N�̓��Ĉ��ۏ��������̎������ݐM��B���Ƃ���2003�N�S��20���t���Y�o�V���i�Q�ʁj�́u�w�ݐ����x�ĕ]���̓����^�������ᔻ���w����ׂ������Ƃ̎p�x�v�Ƃ̌��o���̋L�����f�ڂ����B
�@���̋L���̂Ȃ��Ŋݎ��̑��ł�����{�W�O���i���E���t���[�������j�͂�������Ă���\�\�u���܂ň��ۏ��̔ے�I���ʂ��肪��������Ă����B��n�������ĉ���ł͎Ⴂ�������Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ�����A�ƁB�Ƃ��낪���A�k���N�ɑ���}�~�͕͂ČR�̑��ݔ����ɂ͂Ȃ��A�~�T�C����n�ɑ���͎̂O��̕ČR��n�ł���A�Ⴂ�ĕ��ȂƁB���ꂪ���ۏ��̖{���Ȃ�ł��B����œ��{�������Ƃ������Ƃɍ������ڂ��J������ł��B���āi�ݐ����ɂ́j�l�K�e�B�u�ȕ]���������������킯�ł����A����Ȃӂ��ɕ]�����Ă��������鎞��ɂȂ����̂��Ȃ��Ďv���Ă��܂��v�B
�@����̊ݐM��̐�����@�͋����ŋ����I�������B���̐��������A���̏���Y���Ɉ����p����Ă���悤�Ɏ��ɂ͌�����B���Ȃ݂ɁA���͊ݐM��|���c���v�|���{�W���Y�|�O�˔��|�X��N�̌n���ɑ����Ă���B
�@������l��1978�`1980�N�Ɏ߂��啽���F���B�n���ɏn�����d�˂�N�l�I�Ȑ������A�����Ȑ��i�ƂƂ��ɁA�����I�Ȏ���������Ă������Ƃ��ĕ]���̃|�C���g�ɂȂ��Ă���B�啽��1980�N�U���ɋ}���������߂ɓ��̖ڂ����Ȃ��������A�啽���t�́w�����̎���x�w�c���s�s�\�z�x�w�Y�Ɗ�Ղ̏[���x�w�����m�\�z�x�ȂǏ������{�̐������ɂ��Ă������̗D�ꂽ���c�����B�ŋ߁A�����̃��|�[�g���ĕ]�����铮��������B
�@���̈�w�c���s�s�\�z�x�́A�n���E�n��Љ���d�����A�ƒ���ɂ���v�z����b�ɂ������́B21���I���{�̐������Ƃ��āA�啽�����߂����Ȃ���ʂ������Ƃ��ł��Ȃ��������̍\�z�������Ƃ����������A���啽�h�̒n���c���̊ԂɍL����n�߂Ă���B
�@�|�X�g����̐��������́u�^�v�Ɓu�啽�^�v�̑I���ɂȂ�\��������B�ΕĈˑ���`�Ƌ��������̊ݗ��������Ƃ邩�A����Ƃ��A�č��ƂƂ��ɃA�W�A�����Ƃ̊W���d�������o�����X���鍑�ۊW�̂Ȃ��Œn��Ɖƒ���ɂ��鉸�₩�Ȓ��f�I�ȑ啽��������I�Ԃ̂��A������邱�ƂɂȂ邾�낤�B���͑啽�����x������B
2003.4.23
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m16�n
�����Ƃ̐������\�\���z�ƌ���
�u���ӎ����̂ċ����āw�Áx���̂��̂ɂȂ�邱�Ƃ���ł���B�c�c�����͂ЂƂ������X���W���Ă��邪�A���̉^���͏z���āA���Ƃ̌��ۈȑO�̏�ԂɕԂ�B���͖�h���邪�A�₪�Ă݂͂Ȃ��̍��ɕԂ�B���̍����ɕԂ�����Ԃ��w�Áx�Ƃ����B�c�c����́A�F�����т��w�@���x�ł���B�c�c���́w�@���x�͕��Ր���������A���ׂĂ��w��e�x����B���ׂĂ��e������̂́w���������x�ł���B���������́w���ҁx�̓����v�i�V�q�j�m���ԏ��X�w�����̎v�z�Y�^�V�q�E��q�x�����p�n
�@�u�����Ƃɓ������߂�̂́A���S���ɍs���ċ������Ƃ���悤�Ȃ��̂��v�ƌ������̂͌́E�`��͎��i�Q�c�@�c���E�@���j�������B���݂̎Љ�ł́A�����Ƃ̐l�ԂƂ��Ă̐M�p�͒Ⴂ�B�����̍����͐��E���u�������킵���l�Ԃ̐��E�v�Ǝv������ł���B
�@�����A���̌����ɂ͍s���߂�������B���E�ɂ͐^�ʖڂȐl���͏��Ȃ��Ȃ��B�����A�w���I�����̐������Ⴂ���Ƃ́A�c�O�Ȃ���F�߂���Ȃ��B
�@21���I�����̐��E�\�\����߂ĈÂ��B�l�ނ̐������̂��낤���Ȃ��Ă���A�Ǝ��͖{�C�ŐS�z���Ă���B��@�͐[�����B���E�͗e�ՂȂ炴�鎖�Ԃɒ��ʂ��Ă���B
�@�ő�̖��́A�B��̒��卑�ł���č����{���搧�U������U�肩�����A���ۂɍs�g���n�߂����Ƃɂ���B����E����A���E�̎w���҂́A�e�����{�̐搧�U�����֎~�����B���A���͂͊e�����{�̐搧�U������ے肷�邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���B����E����̐��E���a�́A���̐����̏�ɐ��藧���Ă����̂ł���B
�@�����A�B��̒��卑�̕č���������̂ċ���A���ۂɍs�g���n�߂��B����ɂ��A�����̕��a�Ȏ���͏I������B���E�͑�O�����̎���ɓ������ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B
�@���̌����̈�́A�č��̐����w���w�����ӎ��ߏ�Ɋׂ�A���e���Ɓu���������v�̐��_�����������Ƃɂ���B�u�b�V���哝�̂��͂��߂Ƃ���č����{�̎w���҂́A�č����{���ΑP�̗���ɒu���A�č����{�ɔ�������ᔻ���鍑�̐����w���҂��u���v�Ɩ��w�����A����C�܂܂ɕ��͍U�������悤�Ƃ��Ă���B
�@�č����{�̎w���҂͌������������A�����ɂȂ��Ă���B�������̂��̂ł���B�č����{�͐��E���ł�����قǂ̋���ȌR���͂�U��n�߂Ă���B�u9.11�����v�ւ̕ӎ������č����́A�R���͍s�g�ɑ���u�b�V���������x�����Ă���B��ϊ�Ȃ��B
�@�č��̌R���́A�A�t�K�j�X�^���A�C���N���U�����A�Z���Ԃŗ����𐧈������B���ɃV���A�A���r�A�A�C�����A�k���N��_���Ă���ƌ����Ă���B�č����U�����悤�Ƒ_���Ă��鍑�̎w���҂ɂ��傢�ɖ��͂��邪�A�B��̒��卑�̎w���҂����a�I�����̈ӎv�����āA������������ȌR���͂�w�i�ɑ���������A�����ɋ����Ȃ��Ƃ��͗e�͂̂Ȃ��R���U�����d�|����Ƃ��������́A���܂�ɂ��ُ�ł���B
�@���E�����\������u�b�V��������e�F�����Ƃ��A�l�ނ̗��j�͏I�����}���邩���m��Ȃ��Ƃ���v���B
2003.5.1
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m17�n
�u�����̂Ȃ������v������B�����́u�����ߏ�̐����v�B���������̂܂܂͂т��点������{�͖łт�B
�u����́A������������m��̂݁v�i�V�q�j
�@�ŏ�̌N��́A�l�������̑��݂�m���Ă��邾���B���̎��̑���N�̌N��́A�l�����e���݂���������J�߂��肷��B����ɂ��̉��̌N��͐l�����������B�l��������N��͍ŒႾ�B�N��ɐ��������Ȃ���A�l������M�p����Ȃ��B�悢�����Ƃ����̂́A�I�X�Ƃ��Đ��߂ȂǏo���Ȃ��B�������������Ƃ����̂́A�l�����A�����A���������͎��R�ɁA���邪�܂܂ɐ����Ă��邾�����Ǝv���悤�ȏ�Ԃ̂��Ƃ��B
�@�����̐����͂ǂ����B�ŋ߂̐����Ƃ͍����ɑ��āu��������A��������v�Ƃ₽��ɖ��߂�������B�����ɑ��āA�d�ł��ۂ��A�Љ����p�̕��S�������グ��B�������A�����T�[�r�X�͐�̂Ă�B�₽��ɍ����̎��R���S������悤�Ȗ@�������肽����B�l���ی�Ƃ��L�����@�������ɂ��č����̊�{�I�l���⌾�_�̎��R�낤�Ƃ���B
�@�Ƃ��ɂЂǂ��̂������̌o�ϐ��B���{�͋��Z�@�ւ������ߐs�����A�����ʂ��Ē������Ƃ����X�Ɠ|�Y�����Ă���B���̂��ߎ��Ǝ҂͋}���B���{��厸�ƁE���E�E�ƍߎЉ�ɂ��Ă��܂����B
�@���{�����ܑ��ɂ��ׂ����Ƃ͕s�������ł���B�����s���������������������Ă���B����ȂƂ��ɐ��{���Ȃ��ׂ��͌i�C��łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA������t�͔��̂��Ƃ������Ă���B�s�����ɕs���𑣐i����悤�Ȃ��Ƃ����Ă���B�u����Ȃ��\�����v�v�Ƃ̔����ł��܂����Ă��邪�A����Ă��邱�Ƃ͕s�����i�̂��̂��B
�@���Z���ɘa���ׂ��Ƃ��Ɏ��ۂɂ���Ă���̂͋t�̂��ƁB���Z�������߂��B�����Ȃ��č����Ă��鍑���o�ώЉ������z���グ�Ă���B
�@����������t���܂��B�����x�o���ł��邩���葝�₷�ׂ��Ƃ��ɁA�t�Ɉ������߂Ă���B����ł͍����o�ς͐�������肾�B
�@�s�v�c�Ȃ̂́A���{�o�ς�j�Ă��鏬����t�̎x�������ˑR�������Ƃ��B
�@���̌����̈�́A���{�Љ�ώ��������Ƃɂ���B�̂̓��{�Љ�͍������l��L���ȘA�ъ��̋����Љ�����B�ꂵ��ł���l������Ύ������g�̂��Ƃ̂悤�ɐS�z�������l�����������B�������͗אl�̂��Ƃ���قƂ�NjC�ɂ��Ȃ��Љ�ɂȂ��Ă��܂����B�u���������悯������v�Ƃ����l���������Ȃ��Ă���B�ꂵ��ł���l���ׂɂ��Ă����܂�C�ɂƂ߂Ȃ��悤�ȎЉ�ɕς���Ă��܂��Ă���B
�@����ɏ�����₽���B�،��݂Ƃ��������[�l�R�����|�Y�����Ƃ��A�u�\�����v���i��ł��錋�ʂ��v�ƌ�����Ƃ����b���`�����Ă��邪�A�{�����Ƃ���Ƃ�ł��Ȃ��b���B�o�c�҂��ǂ�Ȃɋ�Y���Ă��邩�A�E�������]�ƈ��Ƃ��̉Ƒ����ǂ�Ȃɋꂵ��ł��邩�\�\����ɔz������̂������Ƃ̋`���ł���B
�@����͗⍓�Ȑ����Ƃ��B���������₽�������Ƃ������̃g�b�v�ɒ��������Ă���ƁA���̗₽���������Љ�S�̂ɐZ������B���{�Љ�S�̂��₽���Љ�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�T���P���t�������V���́u���ǁi���j�v�i�S�ʋL���j�́A�u�����A�č������v�̌��o��������B���̂Ȃ��Ɏ��̂悤�ȋL�q������\�\�u���Ă͌����}�͎����}���{�h�́w�ʓ����x�Ƃ��ꂽ�B�c�c�����A���͈Ⴄ�B�n���I�O�ɋ��{�h�𒆐S�ɔ��������o�����T�����[�}����Ô�R�����S���ł��w�^�}�R�}�ŕs�ޓ]�̊o��ł�낤�ƌ��߂����Ƃ��x�i�~�ēS�O�������j�Ǝx����I�v�B
�@�����}�͏���ɋ}�ڋ߂��Ă���Ƃ����̂ł���B����ȏ@�����}���o�b�N�ɂ���@�����}������ɂނɐ����̒����ɗ��Ƃ��Ƃ��Ă���B�C���̈����b�����A���̋L���̌����͐������B
�@�Â��ē��L���͂��������Ă���\�\�u������̑��݂��č����B�c�c���݂̕Đ����́w����A�u�b�V���A�u���A�͐^�̐��E�̃��[�_�[���x�i�x�[�J�[������g�j�Ǝi��̗�����������c�c�Ă���v�B
�@���̌������������B�ŋ߁A�i�c���Ŗ����ɚ�����Ă��邱�Ƃ�����\�\�u�^���͎҂�������̏�ŕč��̃C���N�U����ᔻ�����Ƃ���A���̏�����ɕč����ɓ`���A�č���g�ً��璍�ӂ��Ă��ƂȂ����Ȃ����v�u���{�̐����ɑ���č����̊��͔s�풼��̐�̉��Ɏ��Ă����v�u��������C�ɂȂ����w�i�ɂ́A���̂悤�ȕč��́V�������V������v���X�B�����Ƃ���ΗR�X�������Ƃ��B
�@�����ł͌����}�A���ە���ł͕č��\�\���ꂪ������x���Ă���B������������F�߂Ă���B����قǕs�����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�������ڂ��o�܂��Ȃ���A���{�͊O����g�قƏ@�����}�̑���l�`�ɂ���Ă��܂��B
�@�w�T�������x�T��16�����L���́u����đI�m���̕s�v�c�v�ɂ��������Ƃ�������Ă���B���o���́u�C���N�푈�x���ŐԊۋ}�㏸�A�x�[�J�[�Ē�����g���x�^�{���v�B
�@���̂Ȃ��Ɏ��̂悤�ȋL�q������\�\�u�C���N�푈�̊J�풼��̂��Ƃ��B�Éꐽ�O�������⒆�]���N�O���A�X��N�O�玩���}���͎҂������E�ԍ�̕č���g�قɑ����^�B�������̂́A�n���[�h�E�x�[�J�[������g�v�u��̏���V���p�̑啨��g�ɂ��V�������V���̒ǂ����ɂȂ�Ȃ��͂����Ȃ��v�u���x����č��̉e�A����Ŏ��M��[�߂�̐S���́A�ɔᔻ�I�Ȑ����Ƃ������Ă���v�B
�@��̉��ɂ����������̓��{�̐����̔ߎS�����ɕ����ԁB�����͓��{���Ɨ����ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

2003.5.2
�u���{�Đ��̓��v�����\�\�w�V�q�x��m��Γ��͊J����m18�n
�����̊�{�́u�����̂��߁v�ɂ���
�u�哹�p��Đm�`����v�i�V�q�j
�@���̒��������ƁA�����Ƃ͖@��������A���߂�����A�����Ɍ������Ă���������悤�ɂȂ�B�������A����ł͖��͉������Ȃ��B��Ȃ��Ƃ͐��̒�������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��B
�@�`���̘V�q�̌��t��A�u�����Љ��傢�Ȃ铹���������ė���Ă���ƁA�m�`�̓��������������悤�ɂȂ�v�Ƃ������ƁB�Ӗ�A�u�m�`�̓������������̂͑哹���p�ꂽ���ʂł���v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̌��t�ɂÂ��ĂÂ��ĘV�q�͎��̂悤�ɏq�ׂ�i�Ӗ�j�\�\�u�l�ׂ��Ȃ킿�U�i�����j�����܂ꂽ�̂͒m�b���o�Ă������炾�B�F�⎜�̓����������悤�ɂȂ����͎̂��R�ȓ��e�̏������ꂽ���炾�B���b�̑��݂��������悤�ɂȂ����͍̂��̒��������ꂽ���炾�v�B
�@���̘_�q�́A�m�`��������E�q�𒆐S�Ƃ���ւ̒ɗ�Ȕᔻ�ł���B�V�q�́A�m�`�A�m�b�A�l���A���b�Ȃǂ͎Љ�a�C�ɐI�܂ꂽ���ʐ��܂ꂽ���̂ŁA�V�q�̂����u���ׂ̑哹�v���m�����Ă��Ȃ����Ƃ����{�̖�肾�A�Ƃ����̂ł���B
�@�l�ނ̕����͒m�b�̔��W�ɂ���Č`�����ꂽ���̂ł���B�m�b�́A����Ȃ��ɂ͐l�ނ��j�ł���悤�Ȋ�@�I�̂Ȃ��Ő��ݏo���ꂽ���̂ƌ��邱�Ƃ��ł��悤�B�������A�m�b�̔��B�́A�����Ɂu�U�v�ݏo���B
�@�����Љ�͈�ʂ��猩����U���܂���ʂ鐢�E�ł���B�ߑ㕶���Љ�͍r�X���������Љ�ł�����B�������₦�Ȃ��Љ�ł���B
�@�ߏ�ȋ����Љ�ɂ����Ă͋��U���܂���ʂ�B�����̕���ɂ����Ă͌��d�p�������퉻����B���̌��ʁA�����҂��x�����҂����҂ɂȂ�Љ�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B
�@�ߑ�Ȍ�̋����Љ�ɂ����ẮA���`���p��A���̕������A���`���₩�܂�������Ė@����������B
�@19���I���V�A�̍�ƃh�X�g�G�t�X�L�[�́w�n�����̎�L�x�i1864�N�j�ɂȂ��Ŏ��̂悤�ɏ������\�\�u�����̂������Ől�Ԃ̎c�s���͏X���ɂȂ����v
�@�l�ގЉ�ߑ㕶���Љ�ɓ����Ă��琔�S�N���߂����B�l�X�͉R�ƕ��������s����Љ�Ɋ���Ă��܂��Ă���B�����Љ�͎��R�Љ�Ɨ��ꂷ�����̂ł���B
�@���R�Ɛl�ԎЉ�̘������ɒ[�ɐi�s�������ʁA���R���l�ԎЉ���댯�ȏ�ԂɂȂ��Ă���B�l�ԎЉ����ȏ�u�����R�v�̕����ɑ���̂͂��͂���E�ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@�l�ԎЉ�̑����玩�R�ɋ߂Â������֕����]�����ׂ����������̂ł���B���̕����ւ̑�]���ɂ������āA�V�q�̋����͂悫�w�j�ƂȂ�B
�@������A����Ɉꌾ�B�i�C�Ȃ����č\�����v�Ȃ��v�u�i�C�Ȃ����ĎY�ƍĐ��Ȃ��v�u�i�C�Ȃ����Ď��Ɩ������Ȃ��v�u�i�C�Ȃ����ĎЉ���̈���Ȃ��v�\�\������t�͂��̓��ɐ�����]�����ׂ��ł���B
|


![]()
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)