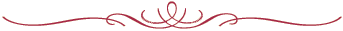
| 4289853 | 「首相の靖国参拝訴訟」考 |
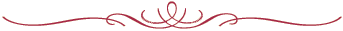
(最新見直し2006.6.24日)
| 【「小泉首相の靖国神社違憲訴訟、福岡地裁」の経緯】 |
|
小泉首相は、2001.4月の自民党総裁選で、「首相になったらいかなる批判があろうと8月15日に参拝する」と公約し、「終戦記念日に公式参拝する」、「中韓両国もいずれ理解してくれる」とも発言していた経緯がある。韓国、中国からの反発を受け「終戦記念日の公式参拝」は見送ってきたが、毎年の参拝は続けている。 憲法の政教分離原則に配慮して「二礼二拍手一礼」の神道形式の参拝を避けて祭壇に一礼するにとどめた。玉ぐし料は納めず、献花料を私費で納めている。玉ぐし料については、1975年に靖国神社を参拝した三木首相が「国庫からは支出しない」ことを私的参拝の条件としたことを小泉首相も踏襲し、政教分離の観点から「献花料」とした。「内閣総理大臣」の肩書を記帳することも、政府は78年10月、「肩書記帳は慣例化している」という統一見解を公表している。公用車の使用については「警備上の問題があるからだ」(政府筋)として問題はないという認識を示している。 |
| 【靖国参拝訴訟:首相の靖国参拝は違憲、「宗教活動に当たる」-福岡地裁が初判断、賠償請求は棄却】 |
|
2004.4.7日、「首相の靖国神社参拝違憲訴訟・福岡地裁提訴」の判決が福岡地裁(亀川清長裁判長)であった。亀川清長裁判長は冒頭で「いずれも請求を棄却する」と主文を言い渡したが、判決文で「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘し、原告らの「実質勝訴」を言い渡した。憲法は、国のあらゆる宗教的活動を禁じているが、その目的効果基準は「極めてあいまいな基準」となっており批判が絶えなかった。今回の判決は、同じ基準を使いながらも、それを厳格に適用したことに特質が認められる。 小泉首相の2001年8月の参拝については、各地で、政教分離の原則に反するとして損害賠償などを求める訴訟が起こされたが、他の地裁の判決は、参拝についての憲法判断に踏み込むことを避けていた。首相の参拝が、「社会通念」に照らして、特定の宗教を援助、助長するものと言えるのか、議論が分かれるところだが、今回の判決は「違憲性についての判断を回避すれば、今後も同様の行為が繰り返される可能性が高い」として、そこに積極的に踏み込んだ。 原告側は「実質勝訴」とみて控訴しない方向で検討している。原告が控訴しなければ、請求が棄却されているため、国側が判決理由を不服として控訴することは事実上難しく、違憲判断を示した判決が確定する見通し。 |
| 【原告団や支援者の評価「靖国神社:違憲判決に『画期的な判決』」】 |
|
実質勝訴を受けては、福岡県弁護士会で支持者約130人を前に判決文を約30分にわたり読み上げ説明。最後の「参拝は違憲である」との文言を強調すると、満場から拍手がわき起こった。 都留代表は「判決は我々の主張の大半を組み入れてくれた。これから、東京、千葉、沖縄で靖国参拝訴訟の判決が控えているが、今回の判決の影響は非常に大きい」と興奮気味。原告や支援者から大きな歓声と拍手がわいた。 また、原告団の郡島恒昭団長は「違憲の確認が私たちの目的だったので、完全勝利だ。過去の違憲訴訟判決では『違憲の疑い』だったのが、はっきりと憲法違反と認めてくれた。賠償は認められなかったが、違憲判決が出たら(原告側からは)控訴はしないということにしていたので、控訴もしない。本当にこれ以上のものはない」と声を震わせた。 原告団は今回の違憲判決を予想しておらず、事前に「勝訴」の垂れ幕を用意していなかった。木村真昭・原告団事務局員(53)は「これまでの靖国参拝訴訟の流れから、違憲とならないのではと思っていたので、準備をしなかった。まさかこんな結果が出るなんて」と興奮していた。 傍聴席で違憲判決を聞いた愛媛玉ぐし訴訟の安西賢二原告団長(56)は「裁判官の役務を十分に果たした立派な判決だ」と声を弾ませた。「国民は自治体の首長の違法行為なら住民訴訟を起こせるのに、首相については国家賠償訴訟の道しかないという法のひずみにも、今回の判決は言及した」と評価したうえで「これまでの裁判官が門前払いの形で形式的処理しかしてこなかったことと比べると大きな違いだ」と述べ、司法判断の流れが変わることに期待を寄せた。 また、被告訴訟団の安西賢二事務局長(56)は「国賠訴訟で勝てた意義は大きい。首相の参拝の違法性を問い続けてきた成果が出た。高裁に控訴中の四国の訴訟も、九州に続いて勝訴を勝ち取りたい」と喜びをかみしめながら話した。 |
| 【違憲判決に対する首相の反応】 |
|
①・第二次大戦のA級戦犯が合祀(ごうし)されている問題にも「抵抗はない」と公言、②・中国や韓国の批判にも「日本人が靖国神社に参拝してどうしていけないのか。(反発は)不思議で仕方がない」と反発、③・参拝をめぐる一連の提訴の際、「世の中、おかしい人たちがいるもんだね」と記者団に語り、④・首相就任以来、「年1回」の靖国参拝にこだわってきた小泉首相は、参拝を明確に違憲と断じた福岡地裁判決に対して次のように述べた。 |
| 【違憲判決に対する各界の反応】 |
|
福田官房長官は7日夕の記者会見で、小泉首相の靖国神社参拝に関する見解を明らかにした。見解の要旨は次の通り。①・福岡地裁判決は国の勝訴だ。②・首相の参拝が憲法に違反するという所見、国の考え方と異なる見解が示されたことは遺憾だ。③・首相の参拝は公人である内閣総理大臣が私的な参拝をしたということだ。首相が公人か私人かと言えば公人だが、私的な部分は当然ある。参拝は私的なものであると主観的にも客観的にも判断されるべきだ。④・「内閣総理大臣 小泉純一郎」の記帳は、どこの小泉純一郎かを表す「所番地」のようなものだ。歴代首相も官職を書くことにしている方が多い。⑤・公用車の使用は警備上の問題からだ。防弾ガラスや防弾ボディーなど特別な仕様がされている。緊急の連絡もできる。⑥・靖国神社とは別の国立・無宗教の施設の建設には国民的合意が必要だ。世論を見極めたうえで具体化を考えたい。今はその時期にあらずと判断している。 自民党の安倍晋三幹事長は、党本部での会合あいさつ、国会内での記者団の遣り取りの際、「地裁では時たまこういう判決が出るが、(参拝が)違憲とは思わない。政教分離(原則)には目的効果基準があって、参拝は憲法違反にならない範囲だ」、。「憲法違反という判断は間違っている。裁判長が判決の主文とは別に感想を述べた。そんなことをする必要があるのか」、「首相は全くこの判決を気にする必要はなく、今後も参拝を続けてほしい」と述べ、靖国神社参拝の必要性を強調した。 自民党内は、参拝継続支持の空気が根強い。 日本遺族会会長である古賀誠・元幹事長は「首相の公式参拝の定着が私どもの念願」、「遺族会は首相の靖国神社公式参拝を定着させるよう念願してきた。判決はまことに残念だ」と語った。7日発足した「日本の領土を守るために行動する議連」の設立総会では、自民党の森岡正宏衆院議員が「国家に命をささげた人に総理がお参りして何がおかしいのか。裁判官の方が間違っている」と声を強めた。一方、首相が今後も参拝を続ける方針を示したことについて「遺族会としては大変ありがたい」と評価した。 一方、公明党の神崎代表は記者会見で「首相の靖国参拝は憲法上疑義がある。参拝は自粛されるべきではないか」と指摘した。同党議員のパーティーでも「無宗教の国立追悼施設(構想)が頓挫しているが、建設を訴えていきたい」。公明党の太田昭宏幹事長代行は「我が党は以前から首相の靖国神社参拝は憲法20条の関係から違憲の疑いがあるという考え方を取ってきた。(判決は)同じ考えに基づいた判断ではないか」と語った。ただ、比較的抑制されたトーンであり、連立政権の基盤を揺るがすまでの反応ではない。 野党各党は「首相は判決に限らず、自分が気にいらないことは分からないと言う人」(民主党の菅代表)と、首相の姿勢を批判した。 |
| 【首相の靖国神社参拝訴訟史】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁判所関係者によると、原告が控訴せずに今回の福岡地裁判決が確定した場合でも、最高裁の判例ではなく、下級裁判所の判断の一つのため、同種の裁判で他の地裁の判断を拘束することはない。また、今回の判決を根拠に、参拝の差し止めなどの仮処分を申請しても、影響を与えることはないという。 法務省幹部は7日、「この部分は主文ではないため、法的拘束力はない」と指摘したうえで、「今後の首相の靖国神社参拝のあり方にも影響しない」との見方を示した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【岩見隆夫の近聞遠見「粗雑すぎる靖国・違憲判決」考】 | れんだいこ | 2004/04/13 |
| 2004.4.10日付け毎日新聞論説委員・岩見隆夫の「近聞遠見」記事で、「粗雑すぎる靖国・違憲判決」なる論評を書き付けている。この御仁の痴性がよくでているのでこれにコメントしておく。 冒頭、「イラクの邦人人質事件もそうだが、前日の小泉純一郎首相の靖国神社参拝違憲判決にも驚かされた。最近の司法は法の番人らしくない、という予感が当たった、とも言える」と書き出している。 「判決文を読んで異様な感じに襲われたのは、首相参拝が<宗教的活動>かどうかの核心部分で、裁判官が示した判断の粗雑さと政治的文言の数々である」と話をつないで、第1の争点・首相参拝の目的が宗教的意義を持っていたかについて、判決文を読んでも「何をもって信念、意図とみているのかまったく不明で、それがなぜ宗教的意義を持つかはもっとわからない」と云う。 第2の争点・参拝の効果が、宗教への援助、助長、促進、または圧迫、干渉になるかについて、判決が憲法が禁ずる宗教的活動と認定したことに対して、「これは恐るべき飛躍である」、「参拝をめぐる騒動の主たる原因は、中国の執ような反対圧力によるもので、いわば騒動の震源地に一般の興味が集中した結果とみるのが常識的だ。神道への信仰心が高まったわけではない。それがなぜ、援助、助長なのか」と批判する。 判決文は粗雑であると云いなし、その原因を、首相参拝を止めるべきだという<私的な気持ち>が先に立っていたからであると指摘する。裁判長の「違憲性の判断を回避すれば、今後も同様の行為(首相参拝)が繰り返される可能性が高いと言うべきで、参拝の違憲性を判断することを自らの責務と考えた」に対して、「『責務』などという上等な言葉にうっかり惑わされる」、概要「宮沢首相の穏便手法なら良いというのか。違憲性は乏しいことになるのか。歴代首相と多くの関係者、国民が、それぞれの立場で考えあぐねてきた、戦争を引きずる深刻な難題に、戦後生まれの一裁判官が気負って軽々しい憲法判断を下す。手をたたくのは、靖国問題を外交カードに使う中国と韓国だ。司法の本領は冷静さではなかったか」と云う。 ほぼ正確に要約しているつもりであるが、結局、岩見は何が云いたいのだろう。 小泉首相の歴代首相のそれと比較して突出した靖国神社参拝の政治性は大いに論議され司法判断されるべきものであるところ、他の地裁判決がこれを避けている中で福岡地裁裁判長が明確に違憲判断したことに対して、「時期尚早、司法の本領は冷静さ」なるコメント付けているに過ぎない。 これはジャーナリストとしての最も愚かなコメントでは無かろうか。人の論理に対して粗雑だとか尊大ぶって云い為すのは立花隆にも見られる兆候であるが、そういう風なぶしつけさを得意とする者の論法の方が粗雑ということはよくあることである。 岩見の場合は、ロッキード事件に対する対応に典型的に見られるが「片方で持ち上げ他方で落としこめる」二枚舌やぶにらみ路線を本領とする。従って、風向き次第でいか様にも物書きすることができるという処世法の名人でもある。 こたびの「粗雑すぎる靖国・違憲判決なる論評」は、今をときめく権力に擦り寄った典型的な提灯記事であり、愚昧なこと甚だしい。論評するなら、小泉はんが急遽「参拝は私的なものであるから何ら問題でない。参拝は個人の自由だろう」と居直り始めていることに対して、過去の言説との齟齬を指摘しウソをあばくことが第一点。 第二点は、「私的参拝なら韓国、中国の強硬な異議を逆撫でしてまで強行する政治的識見」を問うこと。結局、公的参拝の意義ないし違憲性論議を更に深めることが第三点だろう。いずれにせよ、靖国神社の歴史的経緯と戦後に一宗教法人化されたことの確認、その後の靖国神社の経緯、それでも残る諸問題等々を総評せずには認識は深まらない。 これらのことに何の論評もせず、福岡地裁裁判長の「勇み足」を叱責して得意然とするなどは、まさに現下のマスコミ人の能力を証しており、痴態と云わずして何と云うべきだろうか。 2004.4.13日 れんだいこ拝 |
||
| 【「小泉首相の靖国神社違憲訴訟、大阪高裁判決」】 |
| 2005.9.30日、大阪高裁(大谷正治裁判長)で、小泉首相の靖国神社参拝が憲法に定めた政教分離に違反し、精神的苦痛を受けたと主張し、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族ら188名が、首相と国、靖国神社に一人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が有った。 判決は、参拝は首相の職務行為と認定した上で、「憲法の禁止する宗教的活動に値する」との判断を示した。小泉首相の靖国参拝訴訟の違憲判決は、昨年4月の福岡地裁に続くもので、高裁段階での違憲判断は初めて。但し、賠償請求は認めず、原告側の控訴を棄却した。原告側が実質勝訴とみて上告しなければ、請求は棄却されるているため、国側が判決理由を不服として上告することは難しく、判決が確定することになる。 判決は、参拝の職務行為性について、1・公用車を使用し秘書官を同行している。2、「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳している。3・首相就任前の公約の実行としてなされた。4・首相は参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定していない。5・首相の発言や談話に表れた参拝の動機、目的は政治的と指摘し、「総理大臣の職務行為と認めるのが相当」と判断した。 更に、国内外の強い批判にも拘わらず参拝を継続しており、参拝実施の意図は強固だったと述べ、「国は靖国神社と意識的に特別の係わり合いを持った」と判断。「拝は極めて宗教的意義の深い行為で、一般人に対し、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与え、国が靖国神社を特別に支援し、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる。その係わり合いは社会的・文化的条件に照らして相当の限度を越えている」と判断し、憲法20条3項の禁止する宗教的活動と結論付けた。「津地鎮祭訴訟」の最高裁大法廷判決(1977年)が示した「目的・効果基準」に照らし、「憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたる」と、明確に違憲とした。 更に、小泉首相が8.15日に全国戦没者追悼式で式辞を述べていることに触れ、戦没者追悼について「靖国神社に参拝しなければ実施できないものではない」と言及。又参拝当時の首相が公私の別を明確にしていなかったことについて触れ、「私的行為であることをあえて明確にしない場合、公的参拝と認定されても止むを得ない」との見解を示した。 一方、慰謝料を求めた損害賠償について、「原告らの思想や信教の自由などに基づく権利を圧迫、干渉するような法的利益が侵害されたとはいえない」として首相らの賠償責任を否定し、訴えを退けた昨年5月の1審・大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。 首相は、2004.4月の参拝を違憲とした福岡地裁判決を受けて、「私人、小泉純一郎首相が参拝している」と述べ、私的参拝であることを強調していた。 30日の衆院予算委員会でも、大阪高裁が首相の靖国神社参拝を違憲と判断したことについて、「私の靖国参拝が憲法違反だとは思っていない。一国民として、首相として、参拝している。総理大臣の職務として参拝しているのではない。それがどうして憲法違反なのか、理解に苦しむ」と不快感を示した。同時に「憲法違反でないという判決も、出ている。裁判所でも判断が分かれている。今後また裁判で争われることになるだろう」と述べた。靖国参拝について、「戦没者に対する哀悼のまことをささげ、二度とあのような戦争を起こしてはならないという気持ちで参拝している」と説明。「これが憲法違反というのはどういうことか」と述べ、判決内容に強い不快感を示した。年内に参拝するかどうかについては「適切に判断する」と述べ従来の発言を繰り返すにとどまった。 9.30日夜、小泉首相は、記者団の質問に対し、「分かりませんね、何で違憲なのか」と判決への不満を強調した。記者団が「判決が今後の参拝の判断に影響を与えるか」と質問したのに対し、「ない。勝訴でしょう」と答えた。憲法の政教分離規定との整合性についても「それも厳格に対応しているつもりですけどね」とし、「伊勢神宮参拝は、これはどうなんですかね」と記者に反問した。判決理由が、首相が私的参拝だと明言していない点を問題視していることに対しては「別に言う必要ないと思ったから。(私的という言葉を)使う必要ないと思っているから。職務として参拝するのではないと、それで十分じゃないかと思ってるんです」と反発。「必要ない」との説明を国民は分かってくれると思うかとの質問には「分かってると思う」と明言した。また、自民党の支持団体である日本遺族会が「私的参拝」という言葉を使わないよう求めているからかとの質問には「全く関係ありません。全く関係ありません」と語気を強めて繰り返した。 細田官房長官は、「主たる判決では勝訴している。判決理由の中の傍論として、憲法に抵触すると言われたことは遺憾である。違憲判断の判決は傍論と云うか、主たる判決ではない。首相の判断のフリーハンドを奪うものではない」と述べた。 靖国参拝を巡る訴訟では、首相らに公式参拝を求めた岩手県議会決議と岩手県の玉ぐし料支出が憲法に違反するかどうかで争われた「岩手靖国訴訟」で、仙台高裁が1991年、首相の公式参拝を「明白な宗教的行為」として、初めて違憲判決を下した。85年の中曽根首相(当時)の参拝についても、92年の大阪高裁が「違憲の疑い」を指摘した。 |
| 【「小泉首相の靖国神社違憲訴訟、最高裁判決」】 |
| 2006.6.23日、首相の靖国神社参拝の違憲性を問う一連の訴訟での初の最高裁判決が下された。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は、憲法判断はせぬまま、原告の請求を退けた2審・大阪高裁判決を支持し、原告の上告を棄却する判決を言い渡した。これにより、原告側全面敗訴の二審・大阪高裁判決が確定し、原告側敗訴となった。第二小法廷が憲法判断に踏み込まない判断枠組みを示し、門前払いしたことで、後続訴訟でも憲法判断はされない公算が大きい。「憲法判断せず逃げる、もの言わぬ司法と最高裁」の実態が浮き彫りになった。 今回の訴訟の対象になったのは就任直後の2001.8.13の参拝で、首相は公用車で訪れ、供花料を私費で支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。小泉首相の靖国神社参拝は毎年続き、その違憲性を問う訴訟は全国6地裁で計8件提訴されている。これまでに2次訴訟も含め、地裁レベルで8、高裁レベルで4判決の12件の判決が言い渡され、原告側の損害賠償請求はいずれも棄却されている。2005.9月の大阪高裁判決は原告側が上告せず、他の3件が最高裁に係属している。 今回の訴訟はそのうちの一つで初の最高裁判決となった。 但し、2004.4月の福岡地裁判決と2005.9月の大阪2次訴訟の大阪高裁判決が違憲判断を示している。福岡地裁は、「憲法判断を示すことが裁判所の責務」との見解を打ち出していることで注目される。大阪高裁は、「国が靖国神社を特別に支援している印象を与え、特定宗教を助長している」との見解を打ち出していることで注目される。これを考慮してか、首相は同年10月の参拝では本殿に昇殿しないなど簡略化し、「私的な行為」を印象づけた経緯がある。 本件訴訟は、関西在住の日韓の戦没者遺族ら278人が、「首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けた」、「首相の参拝によって、公権力からの干渉を受けずに戦没者をどのように祭祀するか、しないかに関し遺族自らが決定する権利・利益を侵害された」として、首相と国、靖国神社を相手に1人あたり1万円の損害賠償などを求めて大阪地裁に提訴したもので、2004.2月の一審判決は公的参拝と認め、憲法判断には踏み込まず請求を棄却した。2005.7月の大阪高裁の二審判決は、公私の区別も憲法判断も示さず原告側控訴を棄却した。 最高裁判決は、「首相の靖国神社参拝そのものの憲法判断」に対する見解を打ち出さず、一般的に 「人が神社に参拝する行為は、他人の信仰生活に対して干渉を加えるものではない」、「他人が特定の神社に参拝して自己の心情や宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」、「参拝で原告の法律上の権利や利益が侵害されたとは認められない」との解釈を示すことで逃げた。かくて、凡そ司法の自己否定とも云うべき萎縮判決を最高裁が出すことになった。 首相は、訪問先の沖縄県で記者団に「最高裁の判決は妥当だ」と述べ、「哀悼の念をもって靖国神社に参拝するのは憲法違反だと思っていない」、「戦没者に哀悼の誠を尽くすのは憲法以前の問題」と繰り返し強調した。安倍官房長官も同日の記者会見で、「国の主張が認められ、判例が確定した」と語った。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)