
| JASRAC式音楽著作権論の違法性問題考 |

(最新見直し2009.1.17日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、JASRAC式音楽著作権論の違法性問題を検討する。このように問う者は稀であるが、れんだいこは、JASRAC式音楽著作権論は明らかに違法であると断じている。その法理を解析しておく。以下の10点に於いて違法性が認められる。とりあえずスケッチ風に記しておく。 2004.9.11日 れんだいこ拝 |
| 【違法性考その1、著作権侵害論について】 |
| JASRACは、その音楽著作権論を著作権法の大綱に止まらず、大幅に逸脱した独特の権利侵害論を構築している。一般に著作権法は、著作権者、管理権者、出版社、出版の同業他社間の法的折り合いをつけるガイドライン法と見なされるべきであるが、JASRAC式音楽著作権論はそのようには受け取らない。著作権法を、著作権者に対する権利侵犯取締法かの如くに勝手に解釈替えしている。 どういう違いがあるかと云うと、著作権法は流通に於ける川上規制であるのに対し、JASRAC式音楽著作権論になると川上から川下までの全域規制に化けている。この差は実は大きく、著作権法制定時に於いて川下適用は厳禁されていたことを踏まえるべきであろう。JASRAC式音楽著作権論はその禁足の地へ足を踏み入れ、全域全方位的強権著作権論を展開している。 この差を咎めるべきであろうが、司法及び警察がこれを後押しし、著作権法とは関係なくJASRAC式音楽著作権論を正規の著作権論であるかのようにすり替えて今日まで経緯している。この変調を早急に正す必要があろう。抽象的に述べたが、法理論的に云えばそういうことになる。 2009.1.17日 れんだいこ拝 |
| 【違法性考その2、演奏歌唱に対する課金制について】 |
| JASRAC式音楽著作権論はそういう按配で著作権侵害論を構築し、それを本来の著作権憲法である著作権法とは何らの関係もなく、川下適用している。これにより、店舗に於ける歌唱演奏に対する課金制を敷いている。これが違法である。 |
| 【違法性考その3、店舗経営者に対する課金制について】 |
| JASRAC式音楽著作権論は、店舗に於ける歌唱演奏に対する課金を、当の演奏歌唱者に対してではなく店舗経営者に請求している。著作権侵犯論で云えば演奏歌唱している者こそが対象者である筈であるが、そのチェックができないとの理由で、店舗経営者に皺寄せ請求している。 具体的実際のチェックができないのであればアイデア段階の法理論であり、チェック装置を発明するまでは徴収できないと弁えるべきところ、店舗経営者に責任を押し付けていることになる。しかしながら、店舗経営者は、演奏歌唱機会の提供者であり、本来の音楽著作権論で云えば音楽文化普及の功労者とみなされるべきである。その貢献人に対して課金するという理屈が違法である。 れんだいこは、携帯電話を通じて音楽聴取ができるようにしたアイポッド的発明を評価している。それに対する課金に同意しないが、JASRACが店舗内演奏歌唱に対して課金するなら、アイポッド的装置を開発して為すのが嗜みであろう。その種の装置を開発せぬまま店舗経営者に課金するのは違法である。 |
| 【違法性考その4、店舗面積割課金制について】 |
| JASRAC式音楽著作権論は、店舗経営者に対する課金を店舗面積割制にしている。どういう演奏歌唱が為されたかの把握がなされぬままの課金制は先走りで違法である。 |
| 【違法性考その5、別枠料金「1曲90円」制について】 |
| JASRAC式音楽著作権論は、店舗経営者が契約に応じない場合には、別枠料金規定として「1曲90円勘定制」を敷いている。これによると、1曲90円×みなし歌唱数×営業日数=1ヶ月の請求額となる。これにより、店舗面積割課金の数倍の課金額となる。いわゆる脅し制度であるが違法であろう。 |
| 【違法性考その6、遡及徴収制について】 |
| JASRAC式音楽著作権論は、契約に応じない店舗経営者に対して、前項の「1曲90円勘定1ヶ月料金制」×12ヶ月×営業年数=一括請求額で徴収に取りかかる。これにより、契約に応じない店舗経営者に数百万円から数千万円の請求額をふっかけ和解を迫る。違法であろう。 |
| 【違法性考その7、延滞利息徴収制について】 |
| JASRAC式音楽著作権論は、上記金額の一括支払いを求め、払えないとなると延滞金利5%を加算し始める。しかし、金銭消費貸借で借りた訳でもないのに延滞金利を取る手法が許されるのだろうか。違法であろう。 |
| 【違法性考その8、裁判及び逮捕攻勢について】 |
| JASRAC式音楽著作権論は、契約に応じない店舗経営者に対して裁判、警察に対する逮捕請求の挙に及ぶ。その様は権利暴力団の実態を示している。公益法人格の社団法人である資質に拘るというべきだろう。違法である。 |
| 【違法性考その9、演奏器具の撤去要請について】 |
| JASRAC式音楽著作権論は、契約に応じない店舗経営者に対して裁判に持ち込み、損害賠償請求と共に演奏器具一式、カラオケ装置一式の撤去を請求する。勝訴判決により、執行官に撤去させる。そこまで処置する手法が違法であろう。 |
| 【違法性考その10、契約書内容の暴力条項について】 |
| JASRAC式音楽著作権論は、以上の経緯を広報し、震え上がらせ契約に応じさせる。ところが、その契約書の中身たるや、1・異常に小さい字で読みにくい条文、2・一方的料金改定了承規定、3・立ち入り調査無条件応諾規定、4・歌唱実態調査報告書無条件応諾規定、5・契約書の他所での演奏歌唱に際しての事前通知・文書届出承諾制、6・解約時に於ける承諾制等々、明らかに民法一般の契約基準から逸脱している契約書を用意している。 これに署名捺印すれば、それを楯に今更何を云うかと脅す。署名捺印を拒否すれば、契約しようがしまいが支払わなければならないのだと脅す。 こういう無茶苦茶な論法と手法で脅しまくっているのがJASRACである。その昔のJASRACは、こういう在り方を批判して結社された経緯があるが、今のJASRACは、設立時に批判した在り方を受け入れ稼ぎまくっている。ここに問題がある。以上、簡単ながらスケッチしておく。 2009.1.17日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
「作曲家/ヴァイオリニスト 玉木宏樹ホームぺージ 」の「音楽著作権とJASRAC問題」
JASRAC/Japanese Society for Rights of Authors, composers and publishers
作詞家、作曲家、音楽出版社など音楽の著作権者から権利の委託を受け、また、世界の著作権管理団体と契約を結ぶことによって、音楽著作権を管理している日本で唯一の団体の名称。CDなどにあるJASRAのマークは、JASRACの管理作品の録音を
JASRACが許諾したことを示している。インターネットのホームページには、「音楽の著作権とは」「JASRACの紹介」「音楽をご利用になる方へ」「入会のご案内」「Monthly
Information」「内外国関連団体一覧」「資料集」「F.A.Q.」のメニューで構成されている。詳細情報はURL(http://www.jasrac.or.jp/)で知ることができる。また、社団法人日本レコード協会も1997年3月1日に、インターネット上にJapan
Musicのホームページを開設した。詳細情報はURL(http://www.japan-music.or.jp/)で知ることができる。
1997年3月25日に日本音楽著作権協会は、インターネットの音楽事業は、デジタル技術の向上でライブ中継やヒット曲の配信が低コストでできるようになり、パソコンメーカーや大手商社系に加え、独立系の業者も相次いで参入していることから、使用料が明確でないインターネット上での音楽配信の著作権について、配信業者がコンピュータ・サーバーに蓄積する音楽への対価(基本料金)と、ユーザーへの有料配信に応じた利用料との2本立ての料金規定を設定する方針を明らかにした。
米国では音楽著作権とインターネット上での音楽データの使用について、かねてから対立や摩擦があり、もっとも人気のあるバンドの一つであるロックグループのオアシス(Oasis)のファンたちの140のウェッブについて、RIAA(米国レコード産業協会/全米レコード業界組合/Recording Industry Association of America)から1997年8月10日にメールで、曲のデータ、ビデオマクリップから報道資料 まで撤去するようにという警告が出された。詳細情報はURL(http://www.riaa.com/)で知ることができる。
また、カントリーシンガーのJohnny Cashは1997年9月17日に、被害者の1人としてヒット曲「Ring of Fire」について、RIAA、SPAなどが集まり、議会に批准を要請する審議会の証言台に立った。審議会の内容もURL(http://www.house.gov/judiciary/schedule.htm)で知ることができる。
その原因は、米国での著作権はCashが保持しているが外国に対しては著作権を売却していたため、スロヴァニア共和国のWWWサイトから「Ring of Fire」が自由にダウンロードできるようになった。しかし、インターネット上で公開された場合は国境がないため、著作権のある米国国内でもダウンロードされているというものである。つまり、これまでのように著作権を国家単位で管理する体制では、インターネットに対応できなくなったことを立証したことになる。といって、それをどのように管理すればいいのかという手段がないのも現状である。詳細情報はURL(http://www.johnnycash.com/)で知ることができる。
日本音楽著作権協会は1997年9月26日に業務用通信カラオケ向けの音楽著作権料の規定について、音楽電子事業協会(AMEI)と合意した。この規定では、これまで複製権、優先送信権などの権利ごとに定めていた使用料の考え方を改め、通信カラオケのシステムを1つのくくりとして使用料を定めた。今後、家庭向け通信カラオケ、パソコン通信、インターネットなどを含めた利用形態に対応する規定も作られる。
JASRACとネットワーク音楽著作権連絡協議会は1998年5月に、インターネット上の音楽配信に関する著作権使用料について、暫定的な支払い規定を作成することに合意し、1998年6月に発表された。日本音楽著作権協会など6つの音楽関連団体は、著作権者の許可なく音楽を配信している違法なMP3サイトについて、1998年8月から注意を呼びかけるホームページを開設し、1998年8月6日から違反者には直接メールで警告していくキャンペーンを開始した。
ただし、MP3自体は音楽の環境をよくする技術であって違法な技術ではなく、音楽を無断で使用することが問題であり、米国ではすでに違法なMP3サイトに対してRIAAが損害賠償を請求する訴訟をいくつか起こしている。
日本音楽著作権協会、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会、音楽出版社協会、日本音楽事業者協会、音楽制作者連盟の音楽関連6団体は1998年10月1日から、著作権を無視した音楽利用について共同で撲滅キャンペーンを開始し、国内700社のプロバイダへの協力要請を実施し、問題のあるホームページを検索できるソフトの開発なども進めることになった。
1998年11月26日に電子ネットワーク協議会やマルチメディア・タイトル制作者連盟、ソフト制作関係の業界九団体で構成するネットワーク音楽著作権協議会と協議していたネットによる音楽ソフト配信の著作権使用料について、有料の音楽ソフト配信は売り上げの6〜8%、インターネット放送はパソコンなどに音楽データを保存できないことから売り上げの1〜3.5%にするといった大筋で合意し、最終調整することになった。これにより、インターネットによる音楽配信の可能性が大きくなったといえる。ただし、これらの協会に所属しない海外からのMP3を利用した配信など、不透明な部分もある。
また、1997年9月に設立したばかりのネットワーク音楽著作権連絡協議会の副代表世話人として、インプレスの社長であり、社団法人マルチメディア・タイトル制作者連盟(AMD/Association
of Multimedia Developers/1999年8月5日にデジタルメディア協会と組織替えされた)代表である塚本慶一郎(Keiichiro
Tsukamoto)が就任し、連絡先がインプレス内になっていることから、音楽に関係ない出版社であるインプレスの主導でネットワーク上の音楽著作権の内容が決定される可能性は高い。
日本音楽著作権協会はこれまで作家への著作権料の支払いなどの内部利用や、音楽利用者がその楽曲の権利者を探すといった用途に利用されてきた、曲のタイトルやタイトルの一部から作詞/作曲者、著作権を持つ出版社、楽曲に付くコード番号などが検索できる約145万曲が収録された音楽データベースのうち権利処理の済んだ約115万曲分を1999年4月から、無料公開することにしたことをインプレスのINTERNET
Watch 1月19日号が報道した。更新は3カ月に1回行われる予定である。その時点で、他が報道していないことから、インプレスが実質的な作業を担当することになりそうである。
日本音楽著作権協会は、1999年6月3日に、2001年までに楽曲のデータの中に不正コピーの防止機能と著作権情報を盛り込んだ電子透かしを埋め込み、ネット上で著作物の利用状況が把握できるようにして、有料音楽配信が可能になる著作権管理システムを構築するプラン「DAWN
2001」発表した。しかし、現在のようにJASRACだけが著作権を管理していたのでは、米国のように複数の管理団体によっては使用料のレートが異なり、アーティスト自身が自分の作品を管理してくれる団体を選ぶことがでず、現在の流通状態に対応していないことから、改革を望む声が高くなっている。文化庁では、音楽や小説などの著作者に代わって集中管理団体が独占的に使用料の徴収などを行う現在の制度を見直し、許可制を登録制にするという「提言」を発表した。そろそろ、インターネットなどで正規に安く、ユーザーが音楽情報を購入できる環境に着手される時期にきている。
日本レコード協会は1999年10月12日に、著作権とデジタル技術に関する声明を採択した。RIAAは、2000年1月21日に、デジタル音楽ポータルのMP3.comを著作権侵害の疑いで提訴した。
2000年4月3日、ネットワーク音楽著作権連絡協議会とJASRACは1999年来継続してきた2000年4月1日以降のネットワーク上の音楽利用に関する著作権使用料率について、1998年11月の暫定合意に、電話機の着信メロディ配信及び試聴等についての取扱いを加えて延長することに合意した。
日本音楽著作権協会は2000年6月15日に、野村総合研究所に委託し、国際著作権管理団体のCISAC/BIEMと音楽「電子透かし」技術の評価プロジェクト「STEP2000」を実施することを発表した。
日本レコード協会が音楽配信の著作権使用料をCDなみの6%を主張していたのに対し、文化庁は著作権審議会の答申に基づき、2000年12月15日にJASRACが申請していた1曲当たり7.7%を正式に認可することを発表し、2000年12月22日に1曲あたり月額150円または年額1200円の使用料へ引き下げ修正を行って正式に認可された。2001年7月1日から使用料を払う必要が出てきた。
ただし、日本レコード協会は、7.7%の料率が現行のCDパッケージでの料率(6%)に比べて高いことなどを不服としてNMRCを離脱し、音楽配信ビジネスを展開している日本レコード協会傘下のレコード会社とJASRACは個別に使用料について協議することになった。日本音楽著作権協会は2001年5月23日に、2000年度のカラオケや携帯電話の着信メロディなどの使用料徴収額が前年度比7.4%増の1063億3000万円であったことを発表した。
日本音楽著作権協会はネットワーク著作権連合協議会共同で2000年8月に文化庁へ提出していた申請書にしたがい、2001年6月1日より個人ホームページ上など、非商用目的の音楽配信を対象にした利用許諾申し込みを開始し、2001年7月1日より著作権管理を開始する。利用許諾をした利用者に対しては許諾書の発行、適法な音楽サイトであることを表示するライセンスマークなどを提供することになった。また、日本音楽著作権協会が管理している楽曲かどうかを検索できるデータベースサイトも公開した。詳細情報はURL(http://www2.jasrac.or.jp/)で知ることができる。
RIAAとMPAAは2001年10月3日に、Napsterと同様に、次世代のNapsterとして「Morpheus」、「KaZaA」、「Grokster」を著作権侵害に当たるとしてカリフォルニア州中部の連邦地裁に提訴したと発表した。詳細情報はURL(http://www.riaa.org/PR_story.cfm?id=456)で知ることができる。日本音楽著作権協会(JASRAC)は2001年10月19日、著作権管理に有効な音楽電子透かし技術を実現する能力のある企業として4社を認定した。また、野村総合研究所に評価実験も依頼していた。詳細情報はURL(http://www.jasrac.or.jp/release/01/10_2.html)で知ることができる。
日本音楽著作権協会と日本レコード協会は2002年1月29日に、日本で初めて登場した日本語版ファイル交換サービスを提供できるP2PプロジェクトJXTAに参画しているITP Web Solutionの技術を利用したクライアントソフト「ファイルローグ(日本語版)」を運営する日本MMOに対して、「法的措置」をとると表明し、ファイル交換停止を求める仮処分を東京地裁に申請した。「ファイルローグ」は音楽以外のパソコンソフトなどのファイルも交換対象であることから、パソコンソフト・メーカーなどでつくる業界団体コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)もJASRACの活動を全面的に支援する姿勢である。イギリスのCyber-Rights & Cyber-Libertiesは1997-2002のステートメントをPDFで公開した。詳細情報はURL(http://www.cyber-rights.org/5th_year_statement.htm)で知ることができる。
日本レコード協会の所属レコード会社など19社と日本音楽著作権協会は2002年2月28日に、電子ファイル交換サービス「ファイルローグ」を運営する日本MMOと、松田道人社長に対し、音楽ファイルの交換停止と、サービス開始から4カ月間に19社が約1億5,100万円(1カ月約2,805万円×4+諸費用)、JASRACは2億1,433万円(1カ月約3,969万円×4+諸費用)の損害があったと算出し、計3億6,533万円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こした。さらに、3月以降もサービスを継続した場合には、さらに月6774万円
(2,805万円+3,969万円)の加算を求めている。詳細情報はURL(http://www.riaj.or.jp/cgi-bin/press_release.cgi?id=28)または、URL(http://www.jasrac.or.jp/release/02/02.html)で知ることができる。
ただし、「金」と「組織力」などによる一方的な訴えにならないように、Marilyn Hall Patel判事は2002年2月21日に原告の大手レコード・レーベルに対して、反トラスト法の観点から、オンライン音楽事業関連で著作権の濫用がなかったか綿密な調査を行うよう命じた。日本の公正取引委員会も同様に、日本レコード協会の所属レコード会社など19社と日本音楽著作権協会を独禁法の観点から、著作権の濫用がなかったか綿密な調査を行う必要がある。
日本レコード協会は2002年3月5日に、東京から30キロ圏内の中学生から55歳までの男女800人を対象に、2001年10月に実施した2001年度の音楽パッケージソフトユーザー実態調査をまとめた「音楽パッケージソフトユーザー白書」を発表した。詳細情報はURL(http://www.riaj.or.jp/cgi-bin/press_release.cgi?id=30)または、URL(http://www.riaj.or.jp/news/pdf/press_020305.pdf)で知ることができる。日本レコード協会(RIAJ)は2002年3月20日に、コピー防止機能付き音楽CDを購入者に明示するための統一表示を発表した。
RealNetworks社は2002年4月9日に、有料ビデオ・サービスRealOne用として、Real Broadcast Networkでオンライン請求の管理や、ペイ・パー・ビュー、レンタル、一括契約などの配信方法に対応した、コンテンツ作成者が有料配信サービスを構築できるようにするためのソフト「RBN
Managed Subscription Service」を発表した。すでに「RBN Managed Subscription Service」はSoapCityが利用して、テレビ番組の音声エピソードをストリーミングするサービスを提供している。詳細情報はURL(http://www.realnetworks.com/solutions/media/subscription.html)で知ることができる。
また、RealOneに関してはURL(http://www.realnetworks.com/solutions/ecosystem/realone.html)で知ることができる。東京地方裁判所は2002年4月9日に日本エム・エム・オーに対し、MP3仕様により市販の音楽CDから作成したファイルを「ファイルローグ」ユーザーに提供することを禁じる、差止命令を下した。詳細情報は日本レコード協会会長富塚勇「日本MMO社に対する仮処分事件の勝訴にあたり」のURL(http://www.riaj.or.jp/cgi-bin/press_release.cgi?id=33)で知ることができる。
日本音楽著作権協会は2002年5月22日に、2001年度の著作権使用料徴収額を発表し、複合その他で表記された携帯電話着信メロディや楽曲のダウンロード配信を含む「インタラクティブ送信」の徴収額は対前年比で315%の成長を記録し、40億861万円となった。着メロが占めた金額は38億3100万円で、徴収額の95%を占めたことになる。全体では10%ダウンの1,052億8,000万円であった。詳細情報はURL(http://www.jasrac.or.jp/release/02/05.html)で知ることができる。
CNET News.comのレポートによれば、KaZaAのオーナーは2003年1月10日に米国で告訴された。詳細情報はURL(http://news.com.com/2100-1023-980274.html)で知ることができる。日本レコード協会と日本音楽著作権協会(JASRAC)は2003年1月22日に、音楽に電子透かしを埋め込んだ共同実証実験「CD音源の放送利用実態を把握する実験」「インターネット上の違法利用を発見する実験」に成功し、電子透かし技術の有効性を世界で初めて共同実証したと発表した。詳細情報はURL(http://www.jasrac.or.jp/release/03/01_2.html)または、URL(http://www.jasrac.or.jp/release/03/01_3.html)で知ることができる。
日本レコード協会は2003年1月23日に、CDの生産が数量ベースで3億2867万枚と、前年比11%減で、金額ベースで4318億円と前年比12%減となった2002年のレコード生産実績を発表した。詳細情報はURL(http://www.riaj.or.jp/product/200212.html)で知ることができる。KaZaAは2003年5月26日に、ダウンロード回数が230,309,616になったことを報告した。詳細情報はURL(http://www.kazaa.com/us/news/most_downloaded.htm)で知ることができる。
Nielsen//NetRatingsは2003年7月14日に、RIAAが2003年6月25日に、個人ユーザーを相手取って「数1000件の訴訟」を起こすと警告した後、1週間でトラフィックが15%以上減少したことを発表した。詳細情報はURL(http://www.nielsen-netratings.com/pr/pr_030714.pdf)で知ることができる。
AP(Associated Press)通信は2003年7月29日に、RIAAが、インターネット上で音楽を無料交換している米国内の利用者について900人以上を特定し、8月中にも著作権侵害で提訴する方針で、裁判所を通じてネット接続業者に利用者の情報を請求、提訴に不可欠な氏名や住所を1日に約70人ずつ得ていると報道した。米国議会のNorm Coleman上院議員はRIAAが発行依頼した、歴史に残るほど大量の前科者を一気に作りあげない異常に大量の召喚状には法的な懸念があるとして、2003年7月31日に調査を開始したことを発表し、RIAA に対して5項目に渡る質問状について、2003年8月14日までに書類を提出するよう求めた。詳細情報はURL(http://www.senate.gov/~coleman/newsroom/pressapp/record.cfm?id=207096)で知ることができる。
SBC Communications社は2003年7月31日に、RIAAの違法ファイル交換の疑いがある加入者の情報開示を求める召喚状に対し、拒否する訴えを起こした。一番のテーマは、RIAA側のインターネット上のファイル・シェアリングに対するセキュリティについての考え方で、インターネットには基本的にファイル・シェアリングを自由に利用できる環境があり、そのインターネットを利用した誰でも自由に利用できる環境を利用して音楽を自由に交換することを違法といえるか、もし違法だとした場合に、RIAA側で音楽データに限ってファイル・シェアリングが利用できない環境を構築してきたかという点が問題になることだろう。もし、RIAAが勝手にインターネットの機能を制限し、インターネットの機能を利用したから犯罪者で、罰金を請求するというのであれば、RIAA側が法律を管理していることになりかねない。Jupiter Researchはオンライン音楽販売について、2003年のUS$10億未満から2008年にはUS$33億に伸び、米国における音楽支出の26%がインターネットによるものになると予測し、2003年の音楽 CD オンライン売上は、ほぼ横ばいの7億5000万ドルに止まると予測し、The Pew Internet & American Life Projectは2003年7月31日に、2003年3月から5月にかけて米国の約2500人を対象に行なわれた調査から、米国の成人のうちインターネットを使って音楽ファイルをダウンロードする人は3500万人、ファイル交換を利用する人は約2600万人であったと報告した。詳細情報はURL(http://www.pewinternet.org/reports/toc.asp?Report=96)で知ることができる。
経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課は2003年8月9日に、ネットワークコンテンツの不正利用防止に関する技術のうち、ネットワーク上のコンテンツ流通を監視し、正当な取引の確認、不正な取引の摘発等を行うことを可能にする技術について現状を調査し、その技術を利用した場合の法的・制度的な評価を行い、技術面及び法制面での課題を明らかにすることを目的として、2003年6月10日〜6月30日まで財団法人デジタルコンテンツ協会に委託して、「平成15年度コンテンツ流通における不正利用防止手段についての調査研究」を一般公募した結果を公表した。詳細情報はURL(http://www.meti.go.jp/information/data/c30808bj.html)で知ることができる。
オーストラリアのsmh.com.auは2003年8月28日に、RIAAが音楽ダウンロードをしている人を見つけるために利用しているツールについて、解説した「RIAA discloses methods used to track music downloaders」を公開した。詳細情報はURL(http://www.smh.com.au/articles/2003/08/28/1062028262499.html)で知ることができる。MacWorldは2003年9月8日に、RIAAが2003年9月8日に、インターネット上で大量の音楽を無料交換していたとみられる個人1600人の中から261人を相手取り、著作権侵害訴訟を起こしたと報道した。詳細情報はURL(http://maccentral.macworld.com/news/2003/09/08/riaa/)または、URL(http://www.rollingstone.com/news/newsarticle.asp?nid=18648)または、URL(http://www.usatoday.com/life/2003-09-08-riaa-qanda_x.htm)で知ることができる。
RIAAが実際に著作権侵害で261人を訴訟したことから、ニューヨークタイムズ紙は2003年9月14日に、RIAAとミュージシャンと、ファイル・シェアリングで告訴された人を含めた一般市民などのバトルが始まったことを知らせるNiwl Straussのコラム「File-Sharing Battle Leaves Musicians Caught in Middle」を公開した。詳細情報はURL(http://www.nytimes.com/2003/09/14/technology/14MUSI.html?th)で知ることができる。
RIAAは2003年10月30日に、第2段として事前に警告を送った204人のうち、80人に著作権侵害訴訟を起こしたと発表した。RIAAは2003年12月3日、第3段として新たに個人41人を追加提訴した。また、これで訴えられたユーザーは計382人になったが、同時に220人と和解が成立したことも発表した。
The Registerはオランダの最高裁判所(Dutch Supreme Court)が2003年12月19日に、オランダの著作権保護団体「ブーマ・ステムラ(Buma/Stemra)」の訴えを退け、カザー(kazaa)社のファイル共有ソフト「KaZaA」を活用して交換されている音楽や映画ファイルの著作権侵害の責任を負わせることはできないという判決を下したと報道した。詳細情報はURL(http://www.theregister.co.uk/content/6/34613.html)で知ることができる。
また、米国のワシントンでも2003年11月19日に、ISPに違法コピーを行なった契約者の個人情報開示を請求することを認めた下級審の結果を覆し、米国連邦控訴裁判所(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia)はISPに対し、オンラインで音楽ファイルを交換した契約者の特定を強制できないという判決を下したと、TechNewsWorldが報道した。詳細情報はURL(http://www.technewsworld.com/perl/story/32443.html)で知ることができる。

JASRAのマーク
1999〜2005年までにOnline Musicで使うお金の総計予測
1999〜2005年までにOnline Musicで出荷される金額予測
1999〜2005年までにOnline Musicでダウンロードされる金額の予測
RIAAの対応に対するユーザーの意見分布
2001年の音楽データダウンロード予測
1998〜2004年のオンラインとダウンロード・ミュージックの売り上げ予測
DMAT(Digital Music Access Technology)のトレードマーク
2000年9月28にSDMIが公開したオープン・レター
JASRACが管理している楽曲か検索できるサイト
ブロードバンドとインターネット音楽配信
RIAAとMPAAが2001年10月2日に提出した告訴状
MPAAの告訴人リスト
RIAAの告訴人リスト
2001年10月19日のJASRACプレスリリース
JASRAC評価仕様の概要
JASRAC評価総括
SIIAとKPMGが公開した、インターネット経由の著作権侵害調査報告
Cyber-Rights & Cyber-Libertiesの1997-2002ステートメント
2001年音楽パッケージソフトユーザー白書
「日本MMO社に対する仮処分事件の勝訴にあたり」
IFPIの「Music Piracy Report 2002(音楽海賊版レポート2002)」
日本音楽著作権協会の2002年5月22日リリース
日本音楽著作権協会の著作権使用料徴収額
RIAAが2002年8月7日に発表したアナウンス
産業構造審議会知的財産政策部会第1回特許制度小委員会での配布資料
産業構造審議会知的財産政策部会第1回特許制度小委員会報告書
2002年のレコード生産実績
RIAAのa corporate policy guide to copyright use and security on the internet
KaZaAが2003年5月26日に報告した、ダウンロード回数230,309,616
米国のGAOが2003年6月27日に公開したビジネス管理システムとリスクに関する報告書
Nielsen//NetRatingsが2003年7月14日に公開した、P2P激減報道
Norm Coleman上院議員が2003年7月31日に発表したRIAA調査に関するリリース
The Pew Internet & American Life Projectが公開した米国での音楽ファイル・ダウンロード体験
The Pew Internet & American Life Projectの調査票
RIAA discloses methods used to track music downloaders
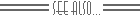
著作権
デジタル化権
STEP2000
BSA(Business Software Alliance)
ACGC
知的財産権
強制ライセンス
版権ビジネス
知的所有権担保融資
BMI
ASCAP
著作隣接権
WIPO
Internet Legal Task Force
Internet Law & Policy Forum
EPIC(Electronic Privacy Information Center)
SPA
21世紀の知的財産権を考える懇談会報告書
インターネット弁護士協議会
MusicReport
版権ビジネス
BEAT UK
ネットワーク音楽著作権連絡協議会
万国著作権条約
SoundJam
セキュア・アーカイバ
パソコン関連の著作権事件年表
コンピュータソフトウェア著作権協会
WIPO MEMBER STATES APPROVED PROGRAM AND BUDGET FOR 1998-1999
Quicken Business CashFinder
データベース保護法案
MP3
Corbis
デジタル情報の劣化消滅
リモート・コントロール・ソフト
BSAのクリントン大統領とゴア副大統領(当時)の発令記事
SPAのゴア副大統領(当時)の発令記事
ネットワーク上音楽利用に関する著作物使用料
MP3
カラオケ・オン・デマンド
著作物の法的集中管理
CDメディア新著作権法施行令
ネットワーク音楽著作権連絡協議会
SDMI
富山県立近代美術館裁判
CESAの宣言
プロテクト外し規制
MP4
a2b Music
Liqud Audio
メディア・アーティスト協会
MagicGate
OpenMG
Super MagicGate
OSG
EMMS
MS Audio
DRM
CAFE(the Consortium for Audio Free Expression)
SolidAudio
ID付きスマートメディア
デジタルメディア協会
MP3関連のURL
有線送信化権
複製権
版面権
MVP
DAWN 2001
RIAAからMP3.com社長への手紙
MP3.com社のサービスに対するRIAAのステートメント
MP3.comからRIAAへの返事
NARM
文化情報総合システム
American Memory
NMRCとJASRACが合意した暫定使用料
アンチ著作権パラダイス
電子書籍コンソーシアム
RIAAとNMPAによるNapster差し止め仮処分請求
DSS(Digital Speech Standard)
AAP
Napsterが証明した音楽の未来
Napsterに代わるサービス
ネットワーク環境を理解していない判決
NapsterやGnutellaは「悪魔」で「救世主」?
SpeechBalloon
MojoNation
サイファー・パンク
Soundom
NMRCとJASRACの使用料規程規定の必要性
NMRCとJASRACの使用料規程
NMRCとJASRACの使用料合意リリース
デジタル・ロッカー
Supreme/D.R.I.V.E.
SDMI Open Public Challenge
インターネットはクラブではない
RapidIOインターコネクト・アーキテクチャ
CuteMX
Groove
Napster: a review
Farsite
OceanStore
分散システム/インターネット運用技術研究会
ITベンチャー向け損害保険
Carracho
Gnuman
Media Tracker
Virtual Supercomputer
ラナム法
ネット文化
ワレザー
DSL(Design Science License)
cell computing
音楽CDコピー防止技術
CDS(Cactus Data Shield)
RealOne
RBN Managed Subscription Service
国際知的財産保護フォーラム
国際知的財産シンポジウム
Creative Commons
Postscribed ID
SID(Source Identification Code)
IFPI
SmarteCD
音声録音デジタル演奏権法
携帯電話着信メロディ
有料コンテンツ
バーチャル著作物マーケット
Peer-to-Peer Piracy Prevention Act
CTEA(Copyright Term Extension Act)
日本着信メロディ研究所
cIDf
DCD(Distributed Content Descripter)
RMP(Rights Management and Protection)
RMPI(RMP Interface)
B-CAS方式
RDD&REL
自由利用マーク
EYEマーク
デジタル暗黒時代
PeerGuardian
CATaC(Cultural Attitudes towards Technology and Communications)
マニフェスト
DRM(Digital Right Management)
知的財産高等裁判所
IP公民権運動
民主主義と特許
xCP(extensible Content Protection)
AOP(Association of Online Publishers)
潰れる雑誌、残る雑誌
Artists' Rights and Theft Prevention Act
オンライン・コンテンツ
●「マルチメディア・インターネット事典」Multimedia
& Internet Dictionary (c)Digital Creators Conference
●Indexへ