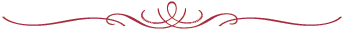
| 戦後衆議院選挙の投票率推移表 |
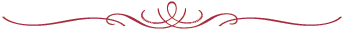
(最新見直し2005.9.11日)
| 【2003衆院選:投票率、59.86% 過去2番目の低さ 】 |
|
今回の衆院選で小選挙区の投票率は、59.86%(総務省発表)となった。過去最低の96年衆院選(59.65%)をかろうじて上回ったものの、過去2番目に低かった前回00年の62.49%より2.63ポイント下回り、戦後2番目の低さとなった。比例区の投票率は59.81%だった。前回の62.45%は下回ったが、最も低かった96年の59.62%は上回った。 都道府県別の推計投票率は、知事選、参院補選と選挙が続いていた埼玉県の53.98%(前回58.49%)が最低で、続いて大阪府(54.79%)茨城県(55.95%)の順に低い。一方、最高は唯一70%台となる見込みの島根県(70.66%)(前回77.18%)で、大分県(69.66%)山形県(69.60%)の順で高い。 衆院選の投票率は、戦後初の1946年の選挙が72.08%。「55年体制」成立後初の衆院選となった58年は、過去最高の76.99%を記録している。しかし、69年は47年衆院選以来の70%割れとなり、68.51%に降下。その後は93年まで8回の衆院選中、5回は70%台だったが、79年(68.01%)、83年(67.94%)、93年(67.26%)の3回は60%台後半に落ち込んだ。さらに小選挙区制が導入された96年は初めて60%を割り込んだ。 |
| 【衆院選に於ける投票率の推移 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
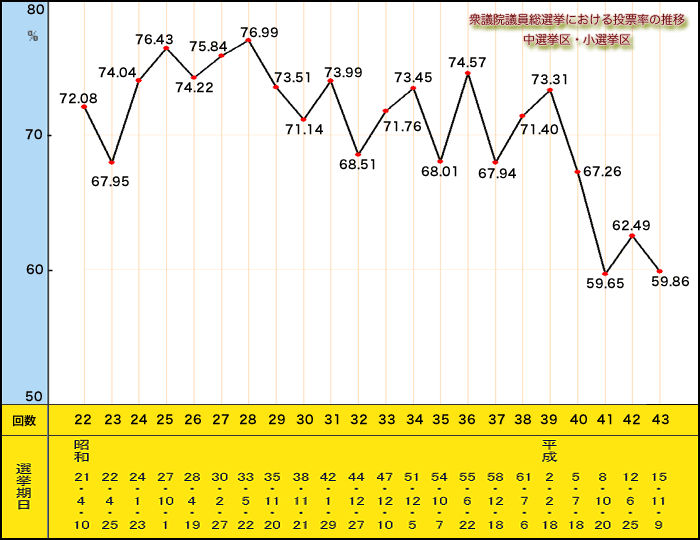
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
| 回数 | 投票日 | 政権 | 投票率 | 備考 |
| 第1回総選挙 | 1890年 7月 1日(火曜日) | 山縣有朋 | 93.91% |
小選挙区制。
選挙権は直接国税15円以上を納めている25歳以上の男性に制限。 |
| 第2回総選挙 | 1892年 2月15日(月曜日) | 松方正義1 | 91.59% |
大選挙区制。
|
| 第3回総選挙 | 1894年 3月 1日(木曜日) | 伊藤博文2 | 88.76% | |
| 第4回総選挙 | 1894年 9月 1日(土曜日) | 伊藤博文2 | 84.84% | |
| 第5回総選挙 | 1898年 3月15日(火曜日) | 伊藤博文3 | 87.50% | |
| 第6回総選挙 | 1898年 8月10日(水曜日) | 大隈重信1 | 79.91% | |
| 第7回総選挙 | 1902年 8月10日(日曜日) | 桂太郎1 | 88.39% |
選挙権は直接国税10円以上を納めている25歳以上の男性に制限。
|
| 第8回総選挙 | 1903年 3月 1日(日曜日) | 桂太郎1 | 86.17% | |
| 第9回総選挙 | 1904年 3月 1日(火曜日) | 桂太郎1 | 86.06% | |
| 第10回総選挙 | 1908年 5月15日(金曜日) | 西園寺公望1 | 85.29% | |
| 第11回総選挙 | 1912年 5月15日(水曜日) | 西園寺公望2 | 89.58% | |
| 第12回総選挙 | 1915年 3月25日(木曜日) | 大隈重信2 | 92.13% | |
| 第13回総選挙 | 1917年 4月20日(金曜日) | 寺内正毅 | 91.92% | |
| 第14回総選挙 | 1920年 5月10日(月曜日) | 原敬 | 86.73% |
小選挙区制。
|
| 第15回総選挙 | 1924年 5月10日(土曜日) | 清浦奎吾 | 91.18% | |
| 第16回総選挙 | 1928年 2月20日(金曜日) | 田中義一 | 80.36% |
中選挙区制。
普通選挙法(1925年)施行後初の衆議院選挙。 選挙権は25歳以上の男性に制限。 |
| 第17回総選挙 | 1930年 2月20日(木曜日) | 浜口雄幸 | 83.34% | |
| 第18回総選挙 | 1932年 2月20日(土曜日) | 犬養毅 | 81.68% | |
| 第19回総選挙 | 1936年 2月20日(木曜日) | 岡田啓介 | 78.65% | |
| 第20回総選挙 | 1937年 4月30日(金曜日) | 林銑十郎 | 73.31% | |
| 第21回総選挙 | 1942年 4月30日(木曜日) | 東條英機 | 83.16% |
翼賛選挙。
翼賛政治体制協議会は定数466全てに推薦議員を立て、381名を当選させる。非推薦議員は85名が当選。 |
| 第22回総選挙 | 1946年 4月10日(水曜日) | 幣原喜重郎 | 72.08% |
大選挙区制制限連規制。
1945年12月の選挙法改正により選挙権は20歳以上の男女となる。 |
| 第23回総選挙 | 1947年 4月25日(金曜日) | 吉田茂1 | 67.95% |
新憲法解散。
日本国憲法施行直前に体制を整えるために行われた選挙。 社会党(片山哲委員長)が比較第一党となる。 |
| 第24回総選挙 | 1949年 1月23日(日曜日) | 吉田茂2 | 74.04% |
なれあい解散。
昭和電工疑獄などで野党がありであったことや、政権与党が少数であったこと、憲法解釈の問題(69条による解散以外は認めないとする連合国総司令部・民政局の見解)などで衆議院の解散が出来なかったが、話し合いで内閣不信任決議案を可決し、解散するという手法が用いられた解散。 |
| 第25回総選挙 | 1952年10月 1日(水曜日) | 吉田茂3 | 76.43% |
抜き打ち解散。
公職追放されていた鳩山一郎グループの影響力が強くなることを警戒した吉田近辺は追放解除組の選挙態勢が固まる前に衆議院を解散した。 |
| 第26回総選挙 | 1953年 4月19日(日曜日) | 吉田茂4 | 74.22% |
バカヤロー解散。
衆院予算委員会で吉田茂首相が西村栄一(右派社会党)の質問中に『バカヤロー』と発言。右派社会党は首相懲罰動議を提出、自由党の一部が欠席して可決された。欠席した三木武吉・河野一郎らは自由党を離党。その後、吉田内閣不信任決議案が可決され、解散となった。 |
| 第27回総選挙 | 1955年 2月27日(日曜日) | 鳩山一郎1 | 75.84% |
天の声解散。
吉田内閣の総辞職を受けて、鳩山一郎が『早期解散』を約束して、左右社会党の支持を得て首班指名を受けた為、早期の解散となった。 |
| 第28回総選挙 | 1958年 5月22日(木曜日) | 岸信介1 | 76.99% |
話し合い解散。
自民党と社会党が『内閣不信任決議案上程、採決前に解散』という合意をした上での解散。 |
| 第29回総選挙 | 1960年11月20日(月曜日) | 池田勇人1 | 73.51% |
安保解散。
|
| 第30回総選挙 | 1963年11月21日(木曜日) | 池田勇人2 | 74.14% |
所得倍増解散。
|
| 第31回総選挙 | 1967年 1月29日(日曜日) | 佐藤榮作1 | 73.99% |
黒い霧解散。
|
| 第32回総選挙 | 1969年12月27日(土曜日) | 佐藤榮作2 | 68.51% |
沖縄解散。
|
| 第33回総選挙 | 1972年12月10日(日曜日) | 田中角栄1 | 71.76% |
日中解散。
|
| 第34回総選挙 | 1976年12月 5日(日曜日) | 三木 武夫 | 73.45% |
任期満了による選挙。
新憲法下初の任期満了による選挙。自民党結党以来、初の過半数割れ。 |
| 第35回総選挙 | 1979年10月 7日(日曜日) | 大平正芳1 | 68.01% |
一般消費税解散。
|
| 第36回総選挙 | 1980年 6月22日(日曜日) | 大平正芳2 | 74.57% |
ハプニング解散。
社会党提出の大平内閣不信任決議案が自民党の一部欠席により可決。史上初の衆参同日選挙に突入。選挙期間中に大平首相が急逝。 |
| 第37回総選挙 | 1983年12月18日(日曜日) | 中曽根康弘1 | 67.94% |
ロッキード解散。
|
| 第38回総選挙 | 1986年 7月 6日(日曜日) | 中曽根康弘2 | 71.40% |
死んだふり解散。
公職選挙法改正(定数是正)が成立し、周知期間(30日)が障害となり、解散しにくい状況の中、中曽根首相や藤波孝生官房長官は解散しないと公言していたが、衆参同日選挙が可能なギリギリのところで解散した。 |
| 第39回総選挙 | 1990年 2月18日(日曜日) | 海部俊樹1 | 73.31% |
消費税解散。
|
| 第40回総選挙 | 1993年 7月18日(日曜日) | 宮沢喜一 | 67.26% |
政治改革解散。
野党が提出した宮沢内閣不信任決議案に自民党の一部(羽田派)が同調して反対票を投じた。決議案は可決され、解散。 |
| 回数 | 投票日 | 政権 | 小選挙区 | 比例区 | 備考 |
| 第41回総選挙 | 1996年10月20日(日曜日) | 橋本龍太郎1 | 59.65& | 59.62% |
小選挙区解散。
中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に制度変更。 |
| 第42回総選挙 | 2000年 6月25日(日曜日) | 森喜朗1 | 62.49% | 62.45% |
神の国解散。
比例議席数を20削減後の選挙。 自民党が271議席から233議席に減、民主党が95議席から127議席に増。 |
| 第43回総選挙 | 2003年11月 9日(日曜日) | 小泉純一郎1 | 59.86% | 59.81% |
マニフェスト解散。
自民党は10議席減も公明党と合わせて絶対安定多数を確保。民主党は改選前から137議席から177議席に増。 |
| 第44回総選挙 | 2005年 9月11日(日曜日) | 小泉純一郎2 | 67.51% | 67.46% |
郵政民営化解散。
自民党は衆議院で郵政民営化関連法案に反対した37人を非公認、対抗馬を擁立し、改選前の212議席から296議席に躍進。自民・公明で327議席と衆議院の3分の2以上の議席を獲得。民主党は改選前から177議席から113議席に減。 |