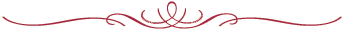
| 第49回2021総選挙結果総論 |
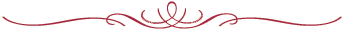
更新日/2017(平成29).10.23日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
![]()
| 【当日有権者数】 |
| 11.1日、総務省は、第49回衆議院議員選挙の各種数値を発表した。当日有権者数は1億5328万517人←1億609万1229人。 |
| 【期日前投票】 |
| 2017年時の2137万8400人(←1315万1796人←1203万8237人)比で3.72%減の約2058万人となった。 |
| 【在外投票】 |
| 在外投票の有権者数は9万6466人。在外投票の投票率は小選挙区で20.09%、比例代表で20.25%。 |
| 【投票率】 |
| ***295、比例代表***180の合わせて***475議席が争われる。2014総選挙よりも約***300人***少ない***1191人が立候補している。投票は一部の地域を除いて午後8時に締め切られる。即日開票され、深夜には大勢が判明する見通し。 11.1日、総務省によると、 小選挙区55.93%、比例代表55.92%と発表。前回2017年衆院選の小選挙区、比例代表共に53.68%を小選挙区で2.25ポイント上回ったが戦後3番目の低さになった。4回連続で50%台となつた。 |
| 小選挙区の都道府県別の投票率で最高は山形県の64.34←64.07%。次いで新潟県63.16←62.56%、島根県61.55%。最低は山口県の49.67%で、唯一50%を割り込んだ。次いで低い順に岡山県50.94%、福岡県52.12%となった。 男女別では男性が56.06←54.08%(前回比1.98ポイント増)、女性が55.80←53.31%(前回比2.49ポイント増)だった。 |
| 【2021衆院選小選挙区投票率推移】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【当確情報の正確さ考】 |
| 投票締め切り後、直ぐに当選確実が出、結果的に間違いがない正確な情報だったことになるが、それは何故か。これにつき、テレビ局の世論調査、出口調査、各種データ等の総力取材による分析の賜物としている。しかし眉唾である。第一の理由はテレビ局各社の発表にズレが認められないことの不自然さである。第二に、それらの理由は辻褄合わせの弁であり実際には集票機ムサシマシーンのインプットデータの台本があり、それを下敷きに発表しているから間違いがないと見なすべきではなかろうか。 |
| 【第49回衆院選の各党獲得議席数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日に投開票された第49回衆議院総選挙は、岸田自民善戦、枝野立憲惨敗、維新大躍進、れいわ大健闘の結果となった。自民261、維新41、国民11の三党議席数合計は313となり衆院3分の2の310を超えた。この三党で憲法改定に進むことも考え得る状況となった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
岸田氏は1日午後、国会内で公明党の山口那津男代表と会談し、自公連立政権の継続を確認した。10日に特別国会を召集し、首相指名選挙を経て第2次岸田政権を発足させる見通しだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第49回衆院選は31日投開票された。465(小選挙区選289、比例選176)で行われた。 自民党は、自民党は、追加公認した2人を含め、小選挙区で189議席、比例代表で72議席の合わせて261議席。単独でも国会を安定的に運営できる絶対安定多数(261)を上回り、選挙前勢力の276から議席を減らしたものの、単独で絶対安定多数の261を確保した。菅義偉首相が続投して総選挙に突入していれば惨敗していた可能性がある事を考えれば、岸田自民善戦と言ってよい。東京15区の柿沢未途氏と、奈良3区の田野瀬太道氏を追加公認。現職閣僚の若宮健嗣万博相は東京5区で敗れ、東京8区の石原伸晃元幹事長は落選した。岸田総理大臣は、「与党で過半数をとり、政権選択選挙で信任をいただいたことは大変ありがたかった。自民党の単独過半数も国民にお認めいただいた。これからしっかり政権運営、国会運営を行っていきたい」と述べた。甘利幹事長は神奈川13区で立民新人に敗れ議席を失い、比例代表で復活当選した。現職の自民党の幹事長が小選挙区で敗れるのは初めて。甘利氏は幹事長を辞任する意向を岸田総理大臣に伝えたのに対し、岸田総理大臣は1日午前、党本部で記者団に対し「よく話を聞いて、最後は私が決める」と話した。山口3区の公認争いの末、地元の比例代表中国ブロックから北関東ブロックへの転出を余儀なくされた河村建夫・元官房長官の長男・建一氏、栃木2区の公認調整で北関東ブロック比例単独候補となった西川公也・元農林水産相の長男、鎭央氏は落選。「選挙直前に公認争いの醜態をさらされ、そのマイナスイメージで戦える状態ではなかった。執行部の責任は重い」との怨嗟の声も噴出する。
公明党は公明党は、小選挙区で9議席、比例代表で23議席の合わせて33議席。公示前の29議席から4議席増。比例代表は***万票を割った。
共産党は、小選挙区で1議席、比例代表で9議席の合わせて10議席。 日本のこころは政党存続をかけ、比例選に2人を擁立したが惨敗した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野党共闘の正否を確認しておく。前回、一本化できず自民に敗れ、今回一本化により野党が勝った選挙区は7つ(茨城、千葉、神奈川、兵庫、奈良、徳島、宮崎)。30敗のうち6選挙区(宮城、秋田、山梨、長野、東京、愛知)は1万票差以内の惜敗。すべて野党共闘が成立していた。野党共闘が一定の効果を発揮したのは明らかである。野党乱立が与党を利し、トンデモ候補の当選を許すケースもある。東京16区ではがん患者や女性に対する暴言で知られ、落選危機が取り沙汰された自民・大西英男氏が当選したが、立憲と共産候補の票を足せば、大西氏の得票を上回っていた。野党5党(立憲、共産、国民、れいわ、社民)が乱立したのは全国で72選挙区。与党に勝てたのは6選挙区に過ぎない。立正大名誉教授の金子勝氏(憲法)が言う。「野党共闘を失敗と評価するのは間違っています。野党がまとまっていなければ、獲得できなかった議席もあるし、接戦にすら持ち込めなかった選挙区もあるでしょう。今回は競り負けた選挙区も少なくなく、力不足は否めない。選考方法など課題も多い。ブラッシュアップは必要ですが、野党が共闘に後ろ向きになれば、自公の思うツボです」。2013年の参院選1人区で野党は2勝29敗と惨敗。その後、野党共闘を進め、16年は11勝21敗、19年は10勝22敗と盛り返した。野党は「共闘」なくして、来年の夏の参院選挙は戦えない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本維新の会の躍進。新型コロナウイルス対策で名を広めた大阪府知事の吉村副代表を「選挙の顔」に据え、候補を立てた府内15選挙区は全勝。公示前11議席から4倍近い41議席まで増やし、第3党に躍り出たが、大阪以外の小選挙区を制したのは1つだけ。それも大阪のベッドタウン、宝塚市や伊丹市を含む兵庫6区である。自民を上回るトップの10議席を獲得した比例近畿ブロックの約318万票の内訳も、得票率42.5%と他党を圧倒した大阪の171万5862票が半数以上を占める。維新旋風は、なにわのパワー全開があればこそ。その支えによって京都1区、兵庫1区、奈良1区で次点にもなれず、3位に甘んじた小選挙区候補3人が比例復活。さらに「惜敗率」50%台で2人が当選した。全国を見渡せば、そんな“ゾンビ議員”がウヨウヨいる。近畿ブロック以外で比例復活した維新候補は15人。うち13人が惜敗率7割未満で、選挙区で次点になれなかった候補は9人に上る。中でも四国ブロックで当選した吉田知代(徳島1区)の惜敗率20.1%は歴史に残る“珍記録”。歴代でも3番目に低い惜敗率での当選者となった。立憲の「顔」がイマイチで反自民の受け皿になれず、比例票が維新に流れたせいで、選挙区で有権者に否定されたゾンビ議員が大量発生とはやりきれない。例えば沖縄3区で自民の島尻安伊子・元沖縄北方相と激戦を演じた立憲の屋良朝博の惜敗率は91.8%。それでも比例復活は果たせなかった。それが重複立候補制度の定めとはいえ、「民意を反映しているのか」と言いたくもなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.10.3日、枝野幸男が「希望の党」の小池百合子代表が「リベラル派の排除」を明言したことを受けて、立憲民主党を立ち上げた。 |
| 【第49回衆院選の各党得票数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【第47回衆院選の各党比例区獲得得票数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【大物議員落選劇、比例復活劇考】 | ||||
|
| 【自民党派閥勢力変動考】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自民党内の派閥勢力図は次のように変動した。最大の細田派は、選挙前の59から4人減らし55(衆参91)。麻生派は42→42(衆参57)。二階派は39→33(衆参41)。額賀派は34→29(衆参50。岸田派は30→28(衆参44)。石破派は18→18(衆参20)。石原派は13→11(衆参12)。無派閥は48。派閥未定は20。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田達夫・自民党総務会長と松野博一官房長官両氏とも、97人を擁する最大派閥・細田派(清和政策研究会)の所属だ。9月29日の自民党総裁選で細田派のメンバーの多くは、事実上のオーナーである安倍氏の意向で、かつて同派に籍を置いていた無派閥の高市早苗・元総務相(現・自民党政調会長)を支援し、決選投票では岸田氏の支持に回った。高市氏の善戦は、世論調査では人気の高かった河野太郎・前行政・規制改革相(現・自民党広報本部長)が一般党員票と国会議員票の比重が同じ第1回投票で一気に過半数を獲得する展開を妨げた面がある。このた
め、「安倍氏の本命は、初めから岸田氏だった」との受け止め方が専らだ。12月~78年12月)を支えた「福田系」だ。 派閥はもともと、総裁候補を擁し、その人物の政策や理念に共鳴する
。 安倍氏の祖父、岸信介元首相(在任1957年2月~60年7月)に源流を持つ細田派には、二つの系譜がある。岸元首相や、その女婿で有力な総裁候補だった安倍氏の父、安倍晋太郎元外相から連なる「安倍系」と、岸元首相に次いで清和会(清和政策研究会の旧称)出身の宰相となった福田赳夫元首相(同76年仲間が集まり、その政権を目指す集団だった。当然、誰が総裁候補かによって、集う仲間の顔ぶれも違えば、政治思想も微妙に異なる。 同じ名称と伝統を継承した集団だからといって、総裁候補の交代とともに自動的に忠誠心まで継承されるわけではない。とりわけ、宏池会や清和会のような伝統派閥には、そうした難しさがついて回る。 細田派では、自民党が野党だった時の2012年の総裁選で、それが表面化した。 清和政策研究会(当時は町村派)会長だった町村信孝・元外相が立候補したにもかかわらず、同じ派閥の安倍氏が出馬したことで、町村派は二つに割れた。安倍氏は派閥横断の運動を展開し、総裁の座に復帰するものの、町村派内では福田系と安倍系の間のミシン目がくっきりと浮かび上がった。松野氏はその総裁選で、町村氏の側に立った。福田康夫元首相を父に、福田赳夫元首相を祖父に持つ福田達夫氏も、安倍系ではない。官房長官人事では、安倍氏に近い細田派の萩生田光一経済産業相が有力候補に擬せられていたが、岸田氏周辺は「首相は初めから、松野氏の起用を決めていた」と証言する。松野官房長官、福田総務会長という配置は同派のミシン目の存在を、再び意識させる効果があった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自民党の二階俊博・元幹事長が率いる二階派の幹部は、会長/二階俊博・元幹事長、会長代行(参院)/中曽根弘文、副会長(衆院)/林幹夫・元経済産業相、事務総長/武田良太・前総務相、最高顧問/伊吹文明・元衆院議長(2021衆院選落選で引退)、会長代行/河村武夫・元官房長官(2021衆院選落選で引退)。 二階派が衆院選後の立て直しを急いでいる。衆院解散時には党内第4派閥で47人が所属していたが、最高顧問の伊吹文明・元衆院議長や会長代行の河村建夫・元官房長官が引退したほか、落選者が相次ぎ、37人に減ったためだ。自民党は5日付で、無所属の細野豪志衆院議員の入党を許可した。細野氏は民主党政権で環境相などを務めた。2017年に民主党の後継の民進党を離党。19年1月に二階派の特別会員となり、自民党入党を目指してきた。細野氏の入党に、二階派幹部は「ようやく認められた」と喜んだが、派閥を取り巻く状況は厳しい。二階氏は10月、5年余り務めた党幹事長を退き、岸田首相(党総裁)の下では無役になった。衆院選を経て目減りした10人は党内7派閥で最も多く、二階氏は今月4日の派閥会合で、「選挙は大変だと常々言ってきたが、決して言い過ぎではなかった」と振り返った。今後、二階派には衆院選で当選した新人や元議員らが入会し、40人台に回復する見込みだ。派内では、衆院当選4回の小林経済安全保障相(46)や小倉将信青年局長(40)ら次代を担う中堅・若手も頭角を現し始めているが、派閥の最高幹部だった伊吹氏ら重鎮が引退したことで、派閥の再構築が急務となる。 二階氏は9月の自民党総裁選に出馬した無派閥の野田少子化相との関係も良好だ。二階氏が幹事長時代、野田氏は幹事長代行を務めた。総裁選では二階派議員8人が推薦人になっており、先の衆院選で野田氏は二階氏の地元の和歌山3区に応援に駆けつけたほどだ。二階派内では「『ポスト岸田』に向けて派閥として、多くのカードを持った方がいい」との意見もある。老練な二階氏は「随一の政治的技術を持つ」(安倍元首相)と評されている。最大派閥・細田派のベテランは「このまま二階派が沈んでいるとは思えない」との見方を示す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.11.5日、「衆議院選挙 NHKの議席予測はなぜ外れたのか」。
|
| 2021.11.4日、無所属5人が衆院新会派「有志の会」届け出。衆院選で当選した吉良州司氏(大分1区)ら無所属5人が4日、衆院会派「有志の会」を結成し、衆院事務局に届けた。他は福島伸享(茨城1区)、北神圭朗(京都4区)、仁木博文(徳島1区)、緒方林太郎(福岡9区)の各氏。5人はいずれも民主党や民進党に所属経験がある。吉良氏は、立憲民主党などと統一会派を組む考えを記者団に問われ「白紙だ。情勢を確認しながら考える」と述べるにとどめた。 |
| 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK284」の「 レ」政党に屈しなかった吉本女性芸人“魂の叫び” 佐高信(まぐまぐニュース)」。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)