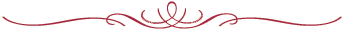田嶋慶彦 石松恒
朝日新聞 2017年10月23日21時07分
http://www.asahi.com/articles/ASKBR54WCKBRUTFK014.html?ref=nmail
今回の衆院選は、政権批判票の受け皿となる野党が分散したのが大きな特徴だ。複数の野党候補(野党系無所属を含む)が競合した「野党分裂型」226選挙区のうち、約8割の183選挙区で与党候補が勝利をおさめた。一方、朝日新聞が各野党候補の得票を単純合算して試算したところ、このうち3割超の63選挙区で勝敗が逆転する結果となり、野党の分散が与党側に有利に働いたことがうかがえる。
特集:2017衆院選 →
「野党分裂型」の226選挙区は全289選挙区の78%を占める。結果は与党183勝、野党43勝と与党側の大勝だった。これに対し、「与野党一騎打ち型」の57選挙区では、与党39勝、野党18勝。分裂型に比べて野党側が善戦した。
野党が分散した最大の原因は、民進党の分裂だ。民進の前原誠司代表が衆院選前に小池百合子・東京都知事率いる希望の党への合流を表明。民進で立候補を予定していた人は希望、立憲民主党、無所属に3分裂した。
ただ、民進は前原執行部の発足以前、共産党や社民党などとの野党共闘を進めていた。昨年7月の参院選では、32の1人区で野党統一候補を擁立し、11勝という成果を上げていた。
そこで、「立憲、希望、共産、社民、野党系無所属による野党共闘」が成功していればという仮定のもと、朝日新聞は独自に、各選挙区でのこれらの候補の得票を単純に合算する試算を行った。その結果、「野党分裂型」226選挙区のうち、63選挙区で勝敗が入れ替わり、与党120勝、野党106勝となった。
63選挙区のうち、圧倒的に多いのが、希望と共産が競合するパターンで、49選挙区にのぼる。また、立憲と希望が競合したのは19選挙区あった。
東京では、「野党分裂型」のうち、与党勝利の19選挙区を試算すると、14選挙区で野党勝利に逆転。萩生田光一・自民党幹事長代行、下村博文・元文部科学相、石原伸晃・前経済再生相はいずれも「立憲・希望・共産」候補の合計得票数を下回った。
また、野党統一候補が実現していれば、閣僚経験者も議席を脅かされる試算となった。野党候補の合計得票数は上川陽子法相、江崎鉄磨沖縄北方相の2閣僚の得票数を上回ったほか、金田勝年・前法相も「希望・共産」候補の合計得票数には届いていない。(田嶋慶彦)
■共闘崩壊で社共は「恨み節」
与野党で「1対1」の構図をつくる試みは失敗し、候補者の乱立で自民に「漁夫の利」を奪われた格好の野党からは、分断のきっかけをつくった民進党への「恨み節」が相次いだ。
「率直に民進党の行為には強い怒りを感じている。もし(民進、共産、自由、社民の)4野党の固まりとして総選挙を戦う形が取れたら、こんな自公の多数を許す結果にならなかった」
共産の志位和夫委員長は23日未明の記者会見で、解散直前に希望の党への合流方針を表明し、4党の野党共闘路線を壊した前原氏を強い言葉で批判した。比例得票の割合が33%だった自民が、小選挙区を含めた全議席(計465)の61%を得たことについて、同日発表した党常任幹部会声明で「虚構の多数に過ぎない」と指摘した。
社民党の吉田忠智党首も23日、「接戦区は一本化したかった。前原代表の判断は疑念を持たざるを得ない」と同調した。
ただ、小選挙区での共産党の擁立方針が、野党分裂を招いた面も否めない。共産は、立憲、社民と無所属の一部との間で競合する67小選挙区で候補者を降ろしたが、「自民の補完勢力」と位置づけた希望が候補者を立てた選挙区のほとんどには擁立した。その結果、小選挙区で議席を得た沖縄1区を除き、選挙区あたり数万程度ある共産票は事実上「死票」となり、立憲幹部は「共産党が降ろしていたら勝てる希望候補はたくさんいた」と悔やんだ。
ただ、批判を浴びる前原氏の受け止めは違う。23日未明の会見で、9月の代表就任直後に相次いだ離党騒動について、「最大の理由は共産党との共闘に対する反対だった。民進党のまま野党共闘で突っ込んでいたら空中分解するほどの離党者が出た」と主張。政権選択の衆院選では、安全保障など基本政策が異なる共産との共闘は不可能との立場を取る前原氏は、希望との合流について「何らかの局面展開に賭けた。結果責任は重く受け止める」と振り返った。(石松恒)