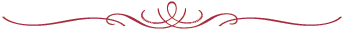
| 第47回2014総選挙情勢考 |
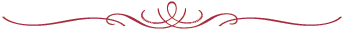
(最新見直し2014.12.12日)
参考サイト「阿修羅政治版」、「宮地健一の共産党問題」、「ザ・選挙立候補予定者」その他
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、2012衆院選の選挙情勢総論を解析しておくことにする。どうも、こたびの選挙はガラガラポンの選挙になりそうな気がする。何党が出てくるのか、何党が生き残るのか、これを見守りたいと思う。 2014.12.12日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【2014総選挙議席予想】 |
自民、圧倒的1強 野党、再編加速も 衆院選情勢14日投開票の衆院選は、共同通信社の世論調査で自民党が300議席超をうかがう勢いとなった。自民、公明両党で公示前の326議席を上回れば、年内解散に踏み切った安倍晋三首相(自民党総裁)の戦略が奏功した形となり、「安倍1強」の構図がさらに強まるのは確実。自民党単独での獲得議席の増減も焦点となる。一方、野党は第2党の維新の党が公示前議席を下回る見通しとなり、議席数次第では民主党を軸とした再編が加速する可能性もある。 「自民党が議席を減らしたとしても、公示前(295議席)の1割減までだ」。政府高官は公示前から強気の姿勢を示していた。 与党の公示前勢力は、自民党と公明党31議席を合わせた計326議席。首相が野党の選挙準備が整っていない年内の衆院解散に踏み切ったことで、自民党内では「小選挙区で多少の議席を失っても、比例代表は前回の57議席を上回る。公示前議席より増えることもあり得る」(選対関係者)との見方が広がっていた。 自民党が公示前議席の1割に当たる約30議席を失っても、公明党が議席を維持すれば300議席近くを確保できる。9議席減までにとどまれば、参院で否決された法案を衆院で再可決して成立させられる3分の2(317議席)は維持する。参院でも3分の2を獲得すれば、首相が目指す憲法改正を発議し、国民投票に付すことができる計算だ。 ■改憲発議が可能 単独317議席焦点 さらに公示前より与党の議席が増えることになれば、首相の政権基盤が強まるのは確実。来年の通常国会で予定する集団的自衛権行使に向けた安全保障法制の整備や、自民党内に慎重論が強い法人税減税や農協改革なども官邸主導で一気に進むことが予想される。首相サイドは、来年9月の党総裁選での再選にも弾みをつけ、長期政権の実現につなげたい構えだ。 自公両党幹部は公示前、衆院ですべての常任委員長を確保し、各委員会の委員の過半数を確保する「絶対安定多数」(266議席)を勝敗ラインに設定。与党内では「自公で絶対安定多数を割り込めば、首相の責任問題になる」(自民党中堅)との声が出ていた。 ただ自民党が300議席を超える可能性が出てきたことで、自民単独でも憲法改正の発議に必要な3分の2(317議席)を獲得するかも焦点に浮上した。公明党は憲法9条の改正には慎重だが、自民党は9条を改正して国防軍を新設する憲法改正草案をまとめており、首相は2日のNHK番組で「リーダーシップを発揮しながら、議論を進めていきたい」と述べるなど、改憲論議の加速に前向きだ。 ■反安倍の受け皿 なりきれぬ野党 一方、野党側は各党候補が乱立し自民党を利する結果となった前回衆院選の反省から、共産党以外の各党で候補者を一本化した選挙区を前回選挙の65選挙区から約3倍に増やした。「強権的」と批判する安倍政権の国会運営に歯止めをかけるためにも、自公の3分の2獲得を阻止できるかは大きな意味を持つが、「反安倍政権」の受け皿にはなりきれていない状況だ。 民主党が70議席前後の微増にとどまり、第2党の維新の党が公示前の42議席を大きく下回る結果になれば、「安倍1強に対抗できる野党勢力の結集が必要だ」(民主党中堅)との声が強まり、再編論議が加速することも予想される。(東京報道 則定隆史) |
衆院選、自民300議席超の勢い 全国序盤情勢、民主微増70前後か(12/04 07:50)
共同通信社は第47回衆院選について2、3の両日、全国の有権者約12万1700人を対象に電話世論調査を実施し、公示直後の序盤情勢を探った。自民党は小選挙区、比例代表で優位に立ち、公示前の295議席を上回る300議席超を獲得する勢いだ。民主党は微増し、70議席前後にとどまる公算が大きい。維新の党は公示前議席を減らし、共産党は上積みする見通しだ。投票先未定は小選挙区で53・5%に上り、14日の投開票に向けて情勢は変わる可能性がある。 公明党は堅調で、公示前の31議席からの増加も狙える。次世代の党は大幅に減少しそうだ。生活の党、社民党も厳しい戦い。新党改革は議席獲得を見込めていない。 自民党は定数295の小選挙区のうち、230以上の選挙区で優勢だ。11ブロックの比例代表(定数180)でも他党に大差をつけ、過去最多の80議席台も現実味を帯びている。自民党単独で衆院過半数(238議席)を大きく上回りそうだ。 2012年の前回衆院選で惨敗した民主党は、公示前の62議席から増加するとみられる。だが小選挙区、比例ともに伸び悩んでおり、計100議席台は困難な状況だ。 維新の党は比例で20議席以上をうかがう一方、地盤である近畿の小選挙区でやや苦戦。公示前の42議席維持は難しい。公明党は選挙区に立てた9人全員の当選と、比例で20議席超が視野に入る。 次世代の党は小選挙区で2議席程度をうかがう。比例での確保見通しは立たず、公示前の20議席を割り込む展開。公示前8議席の共産党は一部小選挙区で競り、比例では10議席超が有望だ。 生活の党は小選挙区で2議席程度の確保が期待できるが、比例は厳しい。公示前の5議席を下回る展開が想定される。公示前2議席の社民党は上積みが見通せていない。比例東京ブロックのみに候補者を擁立した新党改革は苦戦している。 投票先未定との回答は比例代表でも45・5%あった。衆院選に「大いに関心がある」「関心がある」と答えた人は計67・1%。前回の序盤調査での計79・5%を下回った。衆院議員定数は小選挙区「0増5減」に伴い、比例と合わせ475議席。 |
| 【各党の責任数値と選挙見通し】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「2009.7.17日現在の各党の責任数値と選挙見通し」は次の通り。
|
|
衆院選中盤の情勢について、朝日新聞社は6~9日に全295小選挙区の有権者約13万人を対象に電話調査を実施し、全国の取材網の情報も加え、比例区も含めた情勢を探った。現時点では①自民は単独で300議席を上回る勢いで、公明とあわせて定数の3分の2(317議席)を確保しそう②民主は100議席には届かないものの、70議席台に増やす公算が大きい③維新は30議席を割り込む可能性が高く、次世代も1ケタに激減する見通し④共産は倍増する勢い――となっている。 投票態度を明らかにしていない人は小選挙区、比例区ともに4割前後おり、情勢が変わる可能性もある。今度の衆院選に「必ず投票に行く」と答えた人は70%で、2012年衆院選の中盤調査での76%より低い。実際の投票率を推計すると、50%台半ばで、戦後最低だった12年衆院選の59・32%を下回る恐れがある。 自民が300議席に達すれば、中選挙区制時代の1986年の衆参ダブル選挙で衆院で300議席(定数512)を獲得して以来。現行の小選挙区比例代表並立制に移行してからは、09年の民主の308議席(定数480)が最多で、自民は今回、これを上回る可能性もある。 自民は小選挙区では、秋田、富山、山口、宮崎など14県で議席独占の可能性が高く、首都圏の埼玉、千葉、東京、神奈川でも71選挙区のうち55選挙区で先行するなど、全国的に優勢。ただし、岩手と沖縄は例外で、いずれもリードしている候補はいない。 公明も堅調で、候補を立てた全9選挙区で先行。比例区でも公示前を上回る勢いだ。 自公両党は公示前も定数の3分の2以上の議席を有していた。衆院で3分の2以上を占めれば、参院で否決された法案を再可決できる。両党は参院では3分の2に達していないが、衆参両院でそれ以上になれば、憲法改正の発議もできる。 今回の衆院選では、共産を除いた野党5党が194選挙区で候補者をすみ分けた。しかし、5党側がリードしているのは20選挙区程度で、「一本化」は功を奏していない。 民主が先行しているのは、愛知の3選挙区など22選挙区で、公示前の議席とほぼ変わらない。北海道や愛知の各5選挙区など全国の31選挙区で競り合っている。序盤はやや苦しかった海江田万里代表(東京1区)は接戦に持ち込んでいる。 維新は、前身の日本維新の会が12年衆院選時で12選挙区を制した大阪での戦いぶりが焦点。維新は14選挙区で戦っているが、優勢と言える候補はいない。日本維新の会は近畿ブロックで10議席を得たが、維新は今回、7議席前後の見通し。 共産は沖縄1区で接戦。もし議席を獲得できれば、1996年の衆院選で2議席を獲得して以来になる。比例区では序盤から勢いを増しており、倍増を狙う。 次世代は平沼赳夫党首(岡山3区)が競り合っており、最多でも5議席程度。生活は、序盤で接戦を強いられていた小沢一郎代表(岩手4区)が一歩抜け出した。社民は沖縄2区で優勢だが、他は苦しい。 |
| 14日投開票の衆院選は終盤戦に入った。報道各社の中盤情勢調査では自民党が単独で300議席を超す勢いを示したが、結果については予断を許さない。選挙後の政治情勢を決める、自民、公明両党の議席数について、それぞれの数字がもつ意味を整理した。朝日新聞社が6~9日に全295小選挙区の有権者約13万人を対象に行った情勢調査によると、自民は300議席を上回る勢いで、最大318議席まで伸ばす可能性を示している。自民党総裁の安倍晋三首相は11日、長崎市の街頭演説で「ここはまだ接戦なんです。いつも厳しい。どうか皆さんの力でこの選挙区から勝たして欲しい」とアピール。自民優勢とされる情勢結果で、自民の各陣営に「緩み」が出ることに警戒感を示した。衆院定数は戦後、460台から512の間で変動。今回は前回より5減の475で争われる。首相はこれまで、今回の勝敗ラインについて、一貫して「過半数」(238)の獲得をめざすと言い続けている。一方、与党幹部は、国会運営で主導権を握ることができる「絶対安定多数」(266)の確保を目安に挙げる。 |
|
読売新聞社は9~11日に、14日投開票の衆院選について世論調査を行い、終盤情勢を探った。 最終更新:12月12日(金)0時19分 |
|
「落選危機」が伝えられた大物候補16人の最終当落予想
大阪10区。民主党の辻元清美。過去3回は、辻元候補と維新の党の松浪健太候補が交互に当選し、敗れた側が比例復活した激戦区。今回は、自民党新人の大隈和英候補、共産党新人の浅沼和仁候補も含め混戦模様だ。 |
| 「当確」が出た自民党9人は中川郁子氏(北海道11区)、小池百合子氏(東京10区)、野田聖子氏(岐阜1区)、稲田朋美氏(福井1区)ら。「当確」ではないが、終盤に入って支持を広げているのは加藤紘一元自民党幹事長の三女、加藤鮎子氏(山形3区)だ。浅川氏は「公示日段階では、加藤氏と無所属の阿部寿一氏は互角だった。その後、自民党の谷垣禎一幹事長や小泉進次郎復興政務官ら大物弁士が選挙区入りし、加藤氏に勢いが出てきた。小渕優子前経産相の問題が、同じ『2世のお嬢さま』である加藤氏のハンディになるとの見方もあったが、『与党でなくては地元に予算を持ってこれない』とアピールし、ハンディを乗り越えつつある」と語る。
参院議員からくら替えした落下傘候補の佐藤ゆかり氏(大阪11区)も、「尻上がりに良くなっている」(浅川氏)と浸透を広げている。東京1区で、民主党の海江田万里代表と激突する自民党の山田美樹氏は「優勢」だ。山田氏は新人だった前回選挙でも海江田氏を破っている。
女同士の戦いとして注目されているのは新潟4区と、大阪7区だ。 新潟4区は、「元ミス日本関東代表」である自民党の金子恵美氏と、民主党の菊田真紀子氏の事実上の一騎打ち。「金子氏がリードしている。金子氏は『選挙の達人』である二階俊博総務会長率いる二階派の一員で、適宜アドバイスを受け、票を伸ばしている。菊田氏も選挙に強いが、新潟は地方格差が深刻で、与党に対する期待感が強まっている」(浅川氏) 。大阪7区は、「浪速のエリカ様」こと維新の党の上西小百合氏と、自民党の渡嘉敷奈緒美氏、共産党の村口久美子氏が争うが、渡嘉敷氏がややリードしている。 おわび行脚に奔走する元閣僚コンビも注目だ。元経産相の小渕氏(群馬5区)は「当確」だが、「うちわ問題」の元法相、松島みどり氏(東京14区)は「優勢」判定も油断できないという。 新党大地の鈴木宗男代表の長女で、最年少国会議員だった民主党の鈴木貴子氏(北海道7区)や、小泉政権時代に「ソーリ、ソーリ」の国会追及で有名になった辻元清美氏(大阪10区)らは、「接戦だ。選挙区が厳しくなっても比例復活の可能性は十分にある」(浅川氏)という。 |
| 14日投開票の衆院選で全国に設けられる投票所数が2012年の前回衆院選と比べて593か所減ることがわかった。投票所数は1960年から増加傾向だったが、市町村合併や人口減で2005年頃から急減。減少ペースは鈍化してきたものの、ピークだった01年の参院選に比べ4819か所減る。一部有権者にとっては投票所が遠くなり、投票率低下が懸念されるため、全国の市町村選管は無料バスの運行や、期日前投票所の増設など対策に取り組んでいる。読売新聞の調べでは今回の衆院選で全国の自治体が設置する投票所数は計4万8620か所(5日現在)。総務省によると、01年参院選では5万3439か所あったが、05~09年には市町村合併に伴い距離が近い投票所が再編されて約2000か所減った。09年以降も中山間地域を中心に有権者が減り統廃合が進んだ。 |
| 石原氏「もうくたびれたので引退しようと思う」 。次世代の党の石原慎太郎最高顧問は5日、長野市内での衆院選立候補者の応援演説で、「私も82歳。もうくたびれたので、さすがに引退しようと思う。今度の選挙を機会に辞める」と述べ、衆院選後の政界引退を明言した。石原氏は、衆院選の比例東京ブロックに同党の名簿登載順位で最下位となる単独9位で立候補しているが、当選は困難な情勢だ。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)