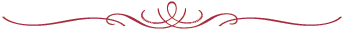
| 2009選挙結果の総評 |
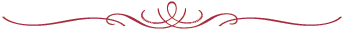
(最新見直し2009.9.2日)
| 【投票率】 |
|
2009.8.30日、第45回衆院選が始まった。総務省の発表によると、午前11時現在の投票率は21.37%で、前回の20.61%をと比べて0.76ポイント上回っている。午後2時現在の投票率は35.19%で、前回の34.94%と比べて0.25ポイント上回っている。午後4時現在の中間投票率は41.83%(男性42.83%、女性40.90%)で、前回05年衆院選の同時刻より0.74ポイント低い。 午後4時現在の投票率を都道府県別にみると、島根が最も高く52.72%。次いで岩手49.82%、鳥取49.78%、山形48.43%、新潟48.32%が上位を占めた。一方、最も低いのは沖縄の34.19%。3大都市圏をみると、東京は39.80%、愛知は40.46%、大阪は39.93%だった。北海道や東京都など13都道県で前回を上回っているものの、34府県で下回っている。特に東海、近畿、九州各ブロックでは全府県で低い。また、北陸信越、中国、四国各ブロックでも伸び悩んでいる。 一方、29日に締め切った期日前投票は1398万4866人(全有権者数の13.40%)で、過去3回の国政選挙で最も多かった約1080万人(07年参院選)を超え、過去最多となった。期日前投票はすべての都道府県で前回05年よりも伸びた。増加率が最も高かったのは秋田の1.79倍。次いで沖縄1.74倍、愛媛1.72倍、徳島1.70倍、山梨1.69倍と続いた。投票者数でみると、最も多かったのは東京の145万4116人。次いで神奈川94万2701人、大阪83万3696人、愛知82万3466人、埼玉70万4504人。 投票は一部の投票所を除き、午後8時で締め切られる。最終的な投票率は前回の67.51%(小選挙区)を上回りそうだ。 |
| Re::れんだいこのカンテラ時評599 | れんだいこ | 2009/09/02 |
| 【第45回2009.8.30衆院選考その1、永田城炎上】 2009.8.30日に実施された第45回衆院選の結果は、小選挙区300、比例区180の全480議席のうち、「民主308、自民119、公明21、共産9、社民7、みんな5、国民新党3、大地1、新党日本1、改革0、無所属6」となった。 総評として、「民主連合軍勢が津波の如く押し寄せ、自公政権の立てこもる永田城を炎上瓦解させた」との言葉が相応しい。まさに投票一揆により自公を壊滅させた感がある。ここに、日本政治史上初の、「『選挙による政権交代』と云う日本式平和革命による政権奪取史」が刻まれた。やる時にはやる、しかも極力穏和に下手な暴力より凄いことをやる日本人民大衆のこの資質は誇って良いように思われる。 かくまで完膚なきまでに自公勢力を壊滅させたことにより政権交代が確定した。これは、非自民の8党派による細川政権が発足した93年の衆院選以来の快挙である。野党が第1党となって政権交代を果たすのは、社会党を中心とした47年の片山内閣以来で62年ぶり。過半数を確保しての政権奪取は戦後初めてとなる。歴史眼的には、55年続いた自民政権が遂に崩壊し、幕引き期に続いた自公政権は10年で終止符が打たれ、政界は不可逆的な盤石の民主党時代に入ったとみなせる。現代世界を牛耳る国際金融資本によるクーデターないしはロッキード事件のような大がかりな陰謀事件が引き起こされない限り、この新体制は続くと観て良かろう。以下、分析によって見えてきたことを記しておく。 新聞各社の事前予想が当たった。2005総選挙の時もそうだったが、各新聞社の予想は非常に正確ということが裏付けられた。れんだいこの予想は、2005総選挙の時の大外れに比してこたびはほぼ的中した。社民、国民新党の議席増予想が外れたが、その分まで民主が食ったことによる。これがブーム威力なのかも知れない。 こたびの選挙の意義は、小選挙区制史上初めて、野党が小選挙区制の意味を理解して陣立てし、与党連合対野党連合の構図で激突したことにある。その結果、民主候補を立てた選挙区はほぼ圧勝し、社民、国民党で臨んだ選挙区ではそうはならなかった。つまり、社民、国民党は候補を立てなかった選挙区では民主を推薦し、実際に投票行動が結び付いたのに比して、民主が候補を取り下げ社民、国民党を推薦した選挙区では、民主票がさほど流れなかったことを意味する。この辺りが今後の教訓となるべきであろう。 共産党が、全選挙区立候補戦略から転じて選挙区を絞り込んだことで、候補を立てなかったところでの民主候補勝ちも際立った。もっと早くからそうしておれば、もっと早く分かったであろう。共産党の全選挙区立候補戦略が如何なる役割を果たしてきたのか、大衆的に明らかにしたことも意義深い。 れんだいこは、かって、2005総選挙の教訓として次のように指摘している。「最大野党民主党の単独政権構想は有り得ない。社共、造反派を相手せずでは結局こたびのようになる。造反派が二党発生したけれども、互いが連携しないようでは結局こたびのようになる。これは普通に算数で分かる話しであった。実際には相乗効果というものがあろうから、与党は一本化でより強化され、野党は乱立でより弱くなるという仕掛けになっている。誰かが高等数学で分析すれば、こういう闘い方では政権移動が有り得ない話だと云うことが証明されよう。通りで、政権与党が気前良く党首討論会に臨み、少数政党にも発言の機会を等しく与えるという鷹揚さを見せる筈である。そういう裏の意図が分かった。政権与党に取って、野党各党が互いに分裂的に票を分け合うことほど望ましいことはない訳だ。 小選挙区制が必ずしも悪いとは思わない。小選挙区制になっても、従来の中選挙区制時の頭で対応しようとしている野党各党の対応が悪いと思っている。いつもの定番ではあるが、日共批判をしておきたい。同党・不破−志位ライン指導による「国会共闘はすれども政権共闘、その為の選挙共闘はしない」という戦略戦術ほど政権与党を有利にさせる手法はない。「本物の野党」なるコマーシャルで選挙区に分け入り野党間をかき混ぜているが、悪質と断定すべきではなかろうか。自公のように「小選挙区共闘、比例区分かち合い」まで行かなくても、「小選挙区共闘、比例区競合」という戦術がありそうなところ、それに向わない同党指導部の意図はナヘンにありや。 この指摘が生かされたかの如く野党連合を誕生させたのが、こたびの勝利の戦略的要因であったと思われる。選挙は、お祭りであると同時に現代的な合戦でもある。戦となると軍師が要る。この理が分からず、日本左派運動同様、軍師なき合戦に明け暮れていた野党が漸く軍師的眼力を持ち、闘いに臨んだことが、こたびの当り前の結果を生んだと理解すべきであろう。そういう意味で、野党連合の形成、続く共産党の「我こそが真の野党論」から「建設的野党論」への転換は、遅すぎたとはいえ祝すべきであろう。 2005総選挙に比して、こたびの2009総選挙は何もかもが野党側の政権交代論を有利にさせた。これも勝利のキーワードであろう。自民党は、2005総選挙に於ける郵政造反派駆逐騒動のしこりが未だ深刻に続いており、そのダメージを修復できないばかりか、ますます傷口を深め広げつつある。この暗闘は今後更に強まることが予想される。れんだいこが見る限り、この問題は、小泉シオニスタン派が自民を飛び出して新党を結成しない限り解決しない。彼らが居残り続ける間じゅう悩みを深め党内亀裂を露にすることになるだろう。しかしながら、小泉シオニスタン派には自民を飛び出る勇気も能力もない。つまり、寄生する習性しかないので死ぬまで居座り続けることになるだろう。かくて自民は永遠のジレンマに陥り、恐らく解決能力を持たないままジリ貧化しやがて博物館入りして行くことになるだろう。ネオシオニズムを懐深く招き入れたところでは、いつでもどこでもそうなる。これが古来より歴史の教えるところである。 民主党は逆に、2005総選挙敗北を奇禍として立て直しに向かった。岡田代表辞任、続く前原代表の偽メール事件による辞任の後、最後の切り札として新進党→自由党経由の小沢が代表に就任し、政策を磨く他方で軍師的采配で「勝てる選挙」を目指して勝利の方程式構築に向かった。時は幸いし、2005郵政解散騒動を通じて郵政造反組の中から国民新党が生まれ、選挙後、共に天下取り戦略を練った。こういう観点は、口舌のみでしたり顔するいわゆる万年野党ボケの頭脳からは生まれない。かって自民党内で主流派として政権を運営していたことから来る責任政治能力を持つ頭脳からしか生まれない。これを持つ二者が連衡することで真の意味での政権取りが始動することになった。郵政民営化騒動は、こういう思わぬ副産物をもたらしたことになる。この二派のルーツを辿れば角栄チルドレンに至るところが奥ゆかしい。これを解き明かす政治評論家は、今のところれんだいこしか居ない。れんだいこ評は認められてはいないけれども稀少価値を持つとつくづく自分で思うふふふ。 民主党と国民新党は社民を引きよせ、福島執行部がこれに加わったことで三角トライアングルが形成された。こたびの選挙を見ても社民の足腰は相変わらず強くはない。福島党首に功績があるとすれば、細川政変で野に下らせた自民党を結果的に助け起こし政権党に帰り咲かせた村山、土井の旧社会党末期執行部に比べて、野党の共同戦線強化による政権奪取の道を採択したことであろう。野党連合内左バネに位置付けて党を再始動させた意義は大きい。 これに日本新党、大地党が加わったことで野党連合は厚みを増した。ここに四本柱が立った。何事も、四本柱が立つとどっしりする。この予行演習は参院選、都議選で試された。いずれも野党連合の勝利の方程式の確かさを確認させた。この流れを見て、共産党が都議選後急きょ、「我こそ真の野党論」から「建設的野党論」に転換し、野党連合の政権取り陣営に加担した。この時既に供託金没収の重みと党内批判により、従来式の全選挙区立候補を取りやめ選挙区絞り込み方式に転換する方針を打ち出していたが、党中央が敢えて「政権交代優先、空白選挙区に於ける自由投票」を指針させたことにより野党連合に票が流れ込む構図ができあがった。これが追い風となった。 この間、自公政権の失政は続き、人民大衆の間に次第しだいに怨嗟の声が強まって行った。バブル経済崩壊以降、何ら有効な対策を講ぜず不況を長期化させ、否むしろ国富の流失、民族系企業の外資売りを加速させて来た。国内問題では財源不足を持ち出す癖に、対外問題となると請われるままにいとも簡単に野放図にお供えし続け、軍事防衛絡みの支出には金に糸目をつけず、思いやり予算を計上し続けて来た。国内景気が良い時にはまだしも余裕とみなされたが、かくも悪化した現在では怒りを呼ぶばかりであるのに、相変わらず垂れ流し続けた。国内問題では費用対効果を云い公共事業を制限するのに、国外問題では問題にせず国際金融資本の要請するままにジャブジャブ金を使うシオニスタン売国政治ぶりが浮き彫りになった。景気対策と称するものは小手先、目先に終始し、せいぜい給付金発想で歓心を買うぐらいのことしかせず、長期戦略的な増収の道を開拓しない。国債発行抑制は掛け声ばかりで、実際には途方もなく刷りまくって来た。それでいて景気はいっこうに良くならない現実のイライラが高まって行った。 財源不足を名目に租税公課各種を引き上げ、こたびの総選挙では、麻生政権は堂々と消費税値上げを公言して選挙に臨む痴呆ぶりを見せていた。ハト派時代の自民党政権が確立していた医療、年金、雇用、教育システムが壊され、社会的貧富と所得格差が広がり、それを構造改革の成果と称して居直り続けて来た。年金等の国庫金をハゲタカファンドに運営を任し、スッテンテンにさせられて来た。税金で立て直した長銀を格安で売り渡して来た。いつしか社会に夢がなくなり、猟奇的犯罪が次から次へと引き起こされ、他方で自殺者、失業者、債務者が量産されて来た。生活保護世帯が増え続け、新たな社会問題になりつつある。個々の分野での目先の利益を追う結果が、回り回って総合損益上由々しき損失を生みだしつつある。 こういう馬鹿げた政治にうつつをぬかし、山積する諸問題を解決する能力を持たない自公政権の貧能ぶりに対するイライラ感とあきらめ感が募った。小泉政権以降、安倍、福田、麻生と1年も持たずに政権がたらい廻しされて来た。最後の麻生政権時代、カンポ施設の1円売り、残ったカンポ施設を破格安でハゲタカファンドが操るオリックスに一括譲渡する事態が明らかになり、異例なことに鳩山総務相がストップをかけた。小泉−竹中ラインの露骨な売国シオニスタン政治ぶりに人民大衆の怒りは頂点に達した。ところが、麻生政権は、麻生首相誕生の立役者であり閣僚仲間である鳩山総務相を支援するのではなく、逆に首を切るというお粗末な対応を示した。合わせて漢字を日本語的に読めない麻生首相の能力が問題になり、人民大衆の自公政権に対する失望とあきらめムードが蔓延した。この問題についてはこれから関係者に対する証人喚問で徹底調査し、小泉−竹中の政治責任を厳しく問わねばなるまい。民営化の背後に潜む悪巧みを明らかにして関係者を成敗せねばなるまい。 もとへ。この問題を切開せぬまま、検察があろうことか、民主党の小沢代表の政治資金収支報告書記載問題にメスを入れ始め、いきなり秘書逮捕という強権発動による国策捜査が始まった。臭い話でしかなかろうに、自公の大物議員が揃って大げさに取り上げ批判を強めて行った結果、小沢代表は辞任を余儀なくされた。こうして鳩山代表が登場したが、この時既に野党連合の政権取りシフトが完了していた。自公政権にとって皮肉なことに小沢降ろしが遅過ぎた。民主党はむしろ禊を済まし、鳩山代表、岡田幹事長体制の下でまなじりを決して衆院選を待ち受ける体制に入った。自民内の分裂模様に比して、民主はむしろ政権交代の一点に向けて阿吽の呼吸による各派共闘を成立させ、老壮青が一手一つになって今や遅しと待ちうける体制を構築した。総選挙のゴングが鳴るや、大物議員が手分けして全国津々浦々にテコ入れに向かった。他方、自民党は、選挙参謀の古賀が突如辞任するお粗末ぶりであった。 国際情勢の変化も、これに幸いした。米国ではブッシュ政権が命脈尽き、民主党のオバマがチェンジ、イエス・ウィ・キャンで新時代を切り拓いて行った。この風が日本政治に伝わる。これらの要因が合わさって、野党連合の政権交代が現実性を強め、こたびの総選挙で自公立てこもる永田城攻めに立ち向かった。人民大衆は、籠城する自公と攻めのぼる野党連合を比較して、野党側に正義を見出した。自公はネガティブキャンペーンを開始したがお粗末極まるもので、逆効果でしかなかった。そういう能力しか持たない哀れさが却って政権交代の流れを強めた。総選挙史上最長の40日ロングランを経て、ついにその日が来た。人民革命第一章の幕が開いた。 2009.9.2日 れんだいこ拝 |
||
| Re::れんだいこのカンテラ時評600 | れんだいこ | 2009/09/02 |
| 【第45回2009.8.30衆院選考その2、各党寸評】 2009衆院選の各党の議席の割り振りは次のようになった。これを各党別にみておく。 自民党は、212→300→119議席(小選挙区64、比例55)となり歴史的な大敗北を喫した。2005総選挙で300議席を獲得し大勝利したが、こたびはその逆に地滑り的に凋落しスッテンテンになった。目標としていた過半数の241議席を大きく割り込み、野党に転落することになった。自民党の野党化は、細川政権誕生時の1993年以来のことになる。2005総選挙では青森、群馬、栃木、石川、島根、愛媛など13県で小選挙区を独占したが、こたびは逆に岩手、秋田、福島、埼玉、新潟、山梨、長野、静岡、愛知、滋賀、長崎、大分、沖縄の13県の小選挙区で全敗し「空白県」となった。小選挙区で全議席を獲得したのは、福井、鳥取、島根、高知の4県のみにとどまった。麻生首相、党三役は即刻の辞任表明を余儀なくされた。 特記すべきことがある。こたびの選挙で、小泉系シオニスタンが脳震盪を見舞われるほど壊滅的打撃を受けた。僅かに手勢十数名が残ったが、もはや政治的影響力はない。それにしても小泉チルドレンが揃いも揃ってお粗末さ、不甲斐なさを示した。比例代表当選圏の座が保障されないという理由で降りた者、無所属に転じた者、ろくに選挙戦を戦わなかった者も続出した。そういう訳で、1対1の小選挙区ではレースにならず殆どが餌食にされた。総帥小泉の出向いたところ全員討ち死にという滑稽無残な結末となった。当人は既に引退し、無責任極まる余興生活に入っているというのに、小泉チルドレンは今なお慕うという漫画的構図を見せている。 ひょっとして、麻生政権の役割は、小泉派退治にあったのかも知れない。この観点から見れば頷けることが多々ある。そうとすれば麻生は重要な役割を果たしたことになる。吉田茂のDNAの為せる技かもしれない。付言しておけば、小泉教の信者たる武部、小池、中川がいずれも比例当選で復活しており、今後の動きが注目される。自民党は当分ゴタゴタし続け悩まされることになろう。小泉の息子の進一郎はオヤジの世話にならず、比例保険を掛けずの気骨を示し、ただ一人新人当選した。小泉チルドレンは時の甘言に乗り、手痛いしっぺ返しを受ける破目になった。やったら倍してやり返されるのが世の習いであることを肝に銘じるべきだろう。 公明党は、31→31→21議席(小選挙区0、比例21)。太田代表、北側幹事長、冬柴前幹事長ら小選挙区候補全員が討ち死にすると云う前代未聞の事態に陥った。同党の場合、お題目の力を信じてと思われるが、小選挙区候補は比例当選の保険をかけていない。これにより全員落選となった。遂に「全員当選常勝神話」が潰えた。公明党の今後は、自民と蜜月を深め過ぎた故に却って舵取りが難しい。総括する力があるだろうか。 民主党は逆に、177→115→308議席(小選挙区221、比例87)となり歴史的な大勝利を収めた。近畿では候補者が足りなくなり2議席が他党に回ったほどオセロ倒し的に自公候補をなぎ倒した。2005総選挙で議席を減らした分以上に大幅に取り戻す格好になった。岩手、福島、山梨、新潟、長野、滋賀、長崎の8県で議席を独占した。推薦区や無所属を含めると、秋田、埼玉、静岡、大分、沖縄でも非自民で全議席を占めたことになる。新たに「小鳩チルドレン」が生まれた。鳩山代表は続投し、間もなく首相として政権を担うことになろう。呉越同舟にならず三本の矢で結束できるかどうかが注目される。 社民党は、前回と同じ7議席(選挙区3、比例4)。将来の党首候補と評されている保坂展人は、東京8区で石原候補と対決したが競り負けし、比例区でも議席を獲得できず落選した。福島執行部は恐らく信任され、新政権入りの道が開かれようが、足腰を鍛える課題は「永遠の課題」となり続けるのだろうか。 国民新党は、4→3議席(小選挙区3、比例0)。小選挙区を譲り比例代表北陸信越ブロックに転じた綿貫民輔代表と亀井久興幹事長が落選した。亀井静香氏(広島6区)、松下 ただひろ(鹿児島3区)、下地幹郎(沖縄1区)が当選した。野党連合の下働きに尽力し、精も根も使い果たした格好となった。比例区で取れなかったのは、郵政問題1本槍が過ぎたのかも知れない。8.31日、東京で開かれた党の幹事会で、綿貫代表が国民新党最高顧問、亀井静香代表代行が代表に就任することを決めた。新政権入りと要職が担保されるべきであろう。 新党日本は、0→1議席(小選挙区1、比例0)。党代表の田中康夫(兵庫8区)が小選挙区当選し瞠目させた。公示前の駆け込みで立候補したにも拘わらず公明の冬柴前幹事長を破った。この功績により、新政権与党派の道が開かれたと思われる。 新党大地は、1→1議席(小選挙区0、比例1)。鈴木宗男(新党大地)が比例北海道ブロックで当選した。八代英太の当選までには至らなかった。新党日本同様に新政権与党派の道が開かれたと思われる。 みんなの党は、4→5議席(小選挙区2、比例3)。「政権交代プラス政界再編」を訴え、代表の渡辺、江田憲司の2名は小選挙区で、山内康一は比例単独で、浅尾慶一郎、柿沢未途は比例復活当選で、計5名が当選し善戦した。選挙直前に結成された党にも拘わらず非常に健闘したことになる。相変わらずの旧自公政権と新政権の両睨みによる遊泳が始まるものとみられる。 改革クラブは、1→0議席。唯一の現役候補であった西村真悟(大阪17区)が落選し、自公連合の別動隊の正体を露にしつつ露と消えた。 共産党は、前回と同じ9議席(選挙区0、比例9)を維持した。志位執行部は安堵し、建設的野党論の下に是々非々路線をまさぐることになる。 無所属は、6→6議席。このうち、平沼グループは、候補者17人のうち平沼元経産相、小泉龍司(埼玉11区)、城内実(静岡7区)の3名が当選した。3名当選は快挙であるが、公職選挙法が定める政党要件(国会議員5人以上)を満たさず、新党結成が厳しい状況となった。 宗教法人「幸福の科学」を母体とする幸福実現党は、小選挙区と比例代表計337名と云う候補者数では最大の候補を擁立したが、小選挙区、比例区とも議席0となった。特段の声明も出されず仕舞いになっている。 かように分析できるが、我々はどう受け止めるべきだろうか。れんだいこは、日本政治史の新たな時代が始まったと素直に受け取る。遂に、1980年代初頭の中曽根政権以来のシオニスタン政治からの転換を闘い取った。新政権が、内憂外患の中、有能に漕ぎ続けることを願う。真剣に学ぶべきは、1980年代初頭まで続いた政府自民党内のハト派政治の手法であろう。吉田茂、池田隼人、田中角栄の内外政治のキモである「内治優先の経済成長政策、国際協調の軍事防衛費軽減、自衛隊の海外派兵禁止」政治復権こそ日本の進路とすべきではなかろうか。その為にまずはシオニスタンを一掃し、如何に愛国的に見せかけようとも二度と売国勢力をのさばらせてはいけない。話はここからであろう。日本国憲法が息を吹き返し、光り輝くことになるのを願う。 2009.9.2日 れんだいこ拝 |
||
| Re::れんだいこのカンテラ時評601 | れんだいこ | 2009/09/03 |
| 【第45回2009.8.30衆院選考その3、世界がどう伝えたか】 8.31日、2009衆院選について、各国メディアがどう伝えたかを見ておくことにする。(2009.9.1日付け毎日新聞その他参照) 米国のウォールストリート・ジャーナル紙は、「日本現代史の分水嶺(ぶんすいれい)として後世に伝わるだろう。米国などにとって、自民党政権に比べ対応が難しくなるが、より意欲的な同盟国となるかもしれない」とジャーナルしている。冷静客観的に事態を分析していることが伝わる。 英国のフィナンシャル・タイムズ紙は、「極めて日本的な反乱。民主党に革新的な新政策が見られないのは、日本人が今もそれなりに現状に満足しているからだ。社会的な革命を求めたものではなく、これまでとは違った手法で現状を維持しようとする試みに見える」。インディペンデント紙は、「民主党の外交方針は、日本がようやく冷戦終結を確認したことを示す。アジア重視の姿勢から『地域勢力』化する可能性がある」。9.1日付けのアル・ハヤート紙(ハージム・サーギーヤ)はコラムで、「日本の政権交代について」採り上げ、「日本の革命?」との見出しで、「日本で、第二次大戦後と呼ばれた長い時期、自民党がその象徴であった時期は終了した。そのかっての盟友イタリアでキリスト教民主党が去ったのと同様に」とした上で、意訳概要「第一党となった民主党の鳩山代表は穏和系であり、革命的な動きは採らないだろう」と評した。 イスラエルのイスラエル民放は、「鳩山氏は日本のオバマ」と報じた。8.31日付のイスラエル有力紙ハーレツは、「鳩山政権は、例えば(パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム原理主義組織)ハマスの承認に踏み切るなど、より親アラブ的な姿勢を取るようになりそうだ」と分析した。執筆者は知日派の大学教授で、鳩山代表が選挙戦で自らをオバマ米大統領になぞらえて変革を訴えていたことを指摘し、「対イスラエル政策について、オバマ、鳩山両氏はイスラエルが望まない形の協調を進める可能性がある」と懸念を示した。 イタリアのメッサジェーロ紙は、「イタリアと日本は人口減、移民規制、年金問題など似た問題を抱え、右派から左派への政権交代が必要だった」と論じた。8.31日付のイタリア紙コリエレ・デラ・セラは、「東京に(政治的な)津波」との見出しで国際面の見開きで伝えた上で、鳩山代表を「日本のケネディ」に例えた。政権交代を翻訳することなくそのまま「セイケンコウタイ」と記し、歴史的な出来事として紹介した。 欧州のベルギー紙は、概要「民主党政権が、自民党の対米追従路線から、日米同盟を維持しつつ対米依存を軽減する方向へどこまで外交方針を軌道修正するのかに注目している」とコメントした。欧州のラジオは、「民主党は米国から多少距離を置き、アジアの近隣国との和解を進めようとしている」と伝えた。民主党内に意見の相違があることを指摘した。EU筋の「政権公約が政策にどう反映されるかを見極める必要がある」との声も伝えられている。 仏国際関係研究所(IFRI)アジアセンターのバレリー・ニケ所長は、「米軍基地の扱いなどを見直す余地はあるだろうが、米国は日本の安全保障戦略の中心であり続け、(日米関係の)激変ではない」と分析している。 オーストラリアのオーストラリアン紙は、「日本の近代史において、明治維新や戦後の経済復興に並ぶ大きな変革だ」と評した。 ロシアの政府紙「ロシースカヤ・ガゼータ」は、「震度7級の出来事。米国が終戦後の日本で2大政党制を根付かせようとしたが、当時の日本は受け入れられず、巨大な自民党と政権を担えない野党による『1・5党制』が続いたが、(経済)危機に耐えられなかった」と伝えた。 中国の京華時報は、鳩山氏のあだ名を「宇宙人」と紹介した上で、「『宇宙人』鳩山の夢かなう」と見出しに書いた。広州日報は、「吉田茂、鳩山一郎両元首相の孫同士の戦い。政権は代わっても、世襲政治は変わらない」と評した。 韓国の朝鮮日報は、「政権交代後の日本がどこに向かうかは非常に不透明」と伝えた。北朝鮮の朝鮮中央通信は、論評なしで「自民党が大惨敗を喫した」と選挙結果だけを伝えた。 インドのタイムズ・オブ・インディア紙は「鳩山氏は『新しい侍』」と伝えた。シンガポールのストレーツ・タイムズ紙は、「民主党のマニフェストからは、不振が続く日本経済をいかに上向かせるか、はっきりしない」とコメントした。 中東諸国でも関心をもって取り上げられている。中東の大手紙の大半が「自民党長期政権の終焉」を大きく取り上げた記事を流した。汎アラブ衛星放送の「ジャジーラ」は、投票日当日深夜、大勢が判明するとすぐ「野党、圧勝」の一報を流した。エジプトの最大日刊紙のアルアハラム紙は、「民主党の地滑り的勝利は、国民生活重視の政策を掲げ、官僚の政治支配に反対したことが背景にあった」と解説した。汎アラブ紙で「アラブのワシントン・ポスト」とも呼ばれるインテリ日刊紙の「ハヤート」は、9月1日付けのコラムで早速、民主党の成り立ちや鳩山代表の出自にまで触れて、「実は政策的には自民党とたいした違いはない」と分析している、とある。 もっともっと多くの情報を得たいが分らない。いずれにせよ、かなり注目されたこと自体は確かで、今後の成り行きに相当な関心が払われていることも間違いない。 れんだいこが興味深く思うことは、「2009衆院選政変」を「革命政変」と読むのか「穏和政変」と読むのかで両論が生まれていることである。れんだいこが、海外メディアにサジェスチョンするとすれば、「日本型平和革命」として評するべきであろうということになる。 1993年時の細川政変に比するならば、こたびは格段に重みが違う。この流れは不可逆的で、自民党の亀裂の深さから見て復権はもう有り得ないだろう、よって米英的な二大政党制による政権交代は有り得ないだろう、欧州的な多党化も有り得ないだろうということである。民主党が、かっての自民党の座に深く納まって盤石の政権与党化し、恐らくかっての自民党がそうしたように、左右両翼を抱えたまま「大同一致」で政局をこなして行くことになるだろう。そういう新たな日本型政治の始まりが予見できるということである。民主党の308議席の重みは、それほど画期的で、八百万の神々の為し給うた叡慮のように思われる。 国際金融資本勢力が、これを無理やり突き崩すとするならばクーデター的な非合法手段に打って出るよりない。しかし、日本政治に於いてそのような方法が受け入れられるだろうか。「和をもって尊し」とし、「談じ合い」に世界一長けている日本政治には邪道が過ぎるのではなかろうか。つまり、もはや民主連合政権を突き崩す方法はないということになる。こう認識すべきだろう。 かくて、日本の新時代がが始まったと受け止めるべきであろう。問題は、新日本政治が、どのように動き出すかである。それは恐らく、オバマ流のチェンジ、イエス・ウィ・キャンに感化されながら、日米同盟に依拠しつつも共に非軍事的な国際協調路線へと向かうことになるだろう。戦争に明け暮れる時代が食傷され、裏の仕掛けも見えてきたことでもあり決別へと向かうであろう。産業と通信技術の発展により世界はますます緊密化を深め国際化時代になる。これをこなす能力に於いて、日本的な在り方を追求する政治へと向かうであろう。 なぜなら、この道以外に現代世界の苦悩から脱出できないからである。なぜなら、それが国際社会の中で日本が生き延びる道であるからである。それは同時に国際金融資本への隷従から遠ざかる道である。その意味で革命的な政変であったことが、これから分かるであろう。中曽根政権以来営々と敷設してきた邪悪な政治が、この政治の日本における奥の院である中曽根、ナベツネの寿命が尽きるのに応じて一掃されるであろう。なぜなら、それが歴史の法理であるからである。れんだいこにはそのように世界が見える。 2009.9.3日 れんだいこ拝 |
||
「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK70」の「自民党売国政府たたき潰す 衆議院選挙結果 全国共通した大衆の思い(長周新聞)」を転載する。
|
| 【各党獲得議席数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【第45回各党獲得得票数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【政党交付金】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009衆院選の結果に伴い、国が各党に配分する政党交付金が次のように変動することになった。政党交付金は、国民一人当たり250円として税金から支出され、2009民分の総額は319億4100万円。各政党の国会議員数や国政選挙での得票率を元に毎年4月に計算され、年4回に分けて支給される。
選挙前から193議席増えた民主党は、2009年分の当初予定額より54億円余り多い173億200万円。逆に181議席減った自民党は52億円余り少ない104億6700億円となる。10議席減った公明党は3億2100万円少ない24億300万円。社民党は、議席は変わっていないが、得票率が減ったため3100万円少ない8億6900万円となる。その他は図の通り。共産党は受け取らない。 |
| 【自民党の大物議員落選考】 |
|
自民党は、首相経験者、党幹部、派閥領袖ら自公両党の「大物候補」が相次いで落選した。但し、麻生内閣の閣僚17名のうち、参院議員の3名を除く14名は比例の助けを借りることによって辛うじて全員当選した。小選挙区では、与謝野馨財務・金融担当相(東京1区)、野田聖子消費者行政担当相(岐阜1区)、佐藤勉総務相(栃木4区)、林幹雄国家公安委員長(千葉10区)、塩谷立文部科学相(静岡8区)、甘利明行革担当相(神奈川13区)が落選したが、全員比例代表で復活当選した。公明党の斉藤鉄夫環境相は、比例代表中国ブロックで当選した。党三役では、笹川尭総務会長(群馬2区)が落選した。現職党三役の落選は、96年衆院選の塩川正十郎総務会長(当時)以来13年ぶり。 町村信孝・前官房長官(北海道5区)は★、中川昭一・前財務・金融担当相(北海道11区)は落選。武部勤・元党幹事長は★。鈴木俊一・元環境相は×、赤城徳彦・元農相は×、額賀福志郎・元財務相は★、丹羽雄哉・元厚相は×、船田元・元経企庁長官は×、尾身幸次・元財務相は×、谷津義男・元農相は×、林幹雄・国家公安委員長は★、深谷隆司・元通産相は×、小池百合子・元防衛相(東京10区)は★、鴨下一郎・前環境相は★、島村宜伸・元文相は×、伊藤達也・元金融担当相は×、伊藤公介・元国土庁長官は×、長勢甚遠・元法相は★、堀内光雄・元通産相(山梨2区)は×、小坂憲次・元文科相は×、上川陽子・元少子化担当相は×、柳沢伯夫・前厚労相は×、斉藤斗志二・元防衛庁長官は×、海部俊樹・元首相は×、首相経験者が退任後の衆院選で落選したのは片山哲、石橋湛山の両元首相が落選した1963年の衆院選以来46年ぶりで、海部氏は政界引退の意向を表明した。杉浦正健・元法相は×、川崎二郎・元厚労相は★、伊吹文明・元財務相(京都1区)は★、中馬弘毅・元行革担当相は×、中山太郎・元外相は×、井上喜一・元防災担当相は×、渡海紀三朗・元文科相は×、高市早苗・元少子化担当相は★、中川秀直・元官房長官(広島4区)は★、山崎拓・前党副総裁(福岡2区)は×、太田誠一・ 前農相は×、久間章生・元防衛相は×、衛藤征士郎・元防衛庁長官は★、保岡興治・前法相は×。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【自民党派閥の変動】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自民党内の派閥勢力図は次のように変動した。最大の町村派は、選挙前の61から23に激減した。首相経験者の森、安倍氏は小選挙区で勝ち抜いたものの、会長の町村氏が比例当選したのをはじめ惨憺たる結果となった。津島派も45から14に激減した。古賀派は51から25に半減した。二階派は会長の二階氏一人当選し、12→1となった。山崎派の会長、山崎氏は落選した。新人の当選は、津島、伊吹両派一人ずつだった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【自民党派閥別勢力表】
|
| 2009衆院選の結果、自民、公明、民主、国民新など超党派の国会議員、元議員でつくる改憲派の議員集団「新憲法制定議員同盟」(会長・中曽根康弘元首相)所属の衆院議員が大量落選した。同議員同盟が2008年3月にまとめた会員名簿によると、現職の衆院議員で同盟に加わっていたのは139名。1955年に旗揚げした「自主憲法期成議員同盟」が前身で、2007年3月に名称を変更して再発足(中曽根康弘会長)。「9条の会」を名指しで敵視し、これに対抗する運動を全国で起こすという方針を掲げている。2007年6月にワシントン・ポスト紙に掲載した全面意見広告「従軍慰安婦に強制はなかった」を掲載。08年3月、民主党、国民新党の議員を新たに加えて超党派の新役員体制を発足させ、民主党の鳩山由紀夫代表が顧問に就任している。同議員同盟は今年5月、各党の幹部や財界関係者ら1200人を集めて大会を開き、「一日も早く国会における憲法審査会の活動が始められ、新しい憲法制定に向けて国会での議論が開始されることを願う」とする決議を採択している。 今回総選挙で再選したのは53名となった。党派別にみると、自民党は122名→39(−73)(引退や市長選などへの転出者は10)。公明党は1人で変化なし。民主党は1人が引退し、10→9、国民新党は1人が落選し、2→1。新党大地は1人で変化なし。無所属議員は1人が引退し、3→2となった。 「会長代理」の中山太郎元衆院憲法調査会長をはじめ、顧問の海部俊樹元首相、丹羽雄哉元自民党総務会長、中川昭一元財務・金融相、山崎拓元自民党副総裁、国民新党の綿貫民輔前代表、「副会長」の島村宜伸元農水相、深谷隆司元通産相、堀内光雄元自民党総務会長、幹事長の愛知和男元防衛庁長官、副会長兼常任幹事の船田元、常任幹事の亀井郁夫(国民新)など「大物」議員の落選が目立った。副会長の津島雄二、森山眞弓、玉沢徳一郎は引退した。 日本会議国会議員懇談会のメンバーは次の通り。小泉俊明(茨城3区)、長島昭久(東京21区)、松原仁(東京3区)、笠浩史(神奈川9区)、藤井裕久(南関東比例)、松宮勲(北信越比例)、田村謙治(静岡4区)、牧義夫(愛知4区)、小林憲司(東海比例区)、伴野豊(愛知8区)、中井洽(三重1区)、前原誠司(京都2区)、樽床伸二(大阪12区)、松野頼久(熊本1区)、川内博史(鹿児島1区)。 |
| 【新党大地が民主党会派入り】 |
|
9.1日、地域政党「新党大地」の鈴木宗男代表の衆院での民主党会派入りが決まった。民主党幹部が明らかにした。民主党と新党大地は、衆院選北海道ブロックでの選挙協力を通じて連携。鈴木氏は衆院解散前、国民新党の会派に所属していた。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)