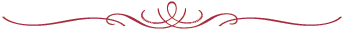
| 2005総選挙、自民内ゲバ考、民主政権取り王手考その2 |
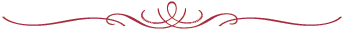
| 【第44回、9.11衆院選の公示及び各種の選挙指数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005.8.30日、戦後初の1946年から数えて23回目の第44回衆院選が公示され、9.11日の投開票を目指して12日間の選挙戦に突入した。 立候補総数は1132名で、前回の2003.11月の1159名を下回り、1996年に初めて小選挙区比例代表並立制による選挙が実施されてから4回目となる総選挙で最少となった。競争率も3.29倍と過去最低の少数激戦となった。小選挙区(定数300)には989名が立候補した。全国11ブロックの比例区(定数180)には779名(比例単独候補143名、小選挙区との重複立候補636名)が立候補した。 女性候補者数は147名で、前回より2名少なく、小選挙区制導入後の最少になった。自民党は女性候補も積極的に擁立し、1955年の結党以来、過去最高の26名を立てた。この結果、自民党候補者に占める女性の割合は前回より4・2ポイント増え、7・5%になった。民主党は8・0%で、前回から2・5ポイント減。 比例選には、自民、民主、公明、共産、社民の5党に、自民党離党者らが作る国民新党、新党日本の2党を加えた計7党が候補者を擁立した。政治団体の新党大地も、北海道ブロックに3人を届け出た。 小選挙区選の立候補者数を主要政党別に見ると、自民党290、民主党289、公明党9、共産党275、社民党38、国民新党10、新党日本6、諸派3、無所属69となった。 2大政党化の流れが進む中で、自民、民主両党の公認候補が対決する小選挙区は280選挙区にのぼり、前回の246から大幅に増えた。一方、郵政民営化関連法案を巡る対応などで自民党が分裂選挙となった結果、自民、民主両党と「保守系無所属または2つの新党」との三つどもえの戦いとなる選挙区は52にのぼった。 立候補者の顔ぶれをみると、新旧別では、前議員457人、元議員60人、新人615人となった。新人候補が占める割合は54・3%で、前回(58%)より減少し、現行制度導入後、最小となった。今回は突然の解散で、選挙の準備期間が短かったことが影響していると見られる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【9.11衆院選の特質】 |
| 首相専権論による小泉首相専断の「郵政民営化法案の是非を国民に問う選挙」となったが、最大の焦点は、小泉首相率いる自公与党が過半数の241議席を獲得できるのかに絞られている。これにより小泉政権を継続するか、民主党を中心とした政権に移行するのかという「政権帰趨」に関心が寄せられている。つまり、「小泉政権信任」が問われている。 今回の選挙を命名するなら、これを解散で見れば「違憲違法解散」、争点で見れば「郵政民営化是非選挙」、政権で見れば「小泉政権信選挙」、野党第一党の民主から見れば「政権交替選挙」、興味で見れば「くの一忍者落下傘部隊選挙」という風に色々な面貌を持っている。 いずれにせよ、小泉劇場の開幕ベルが鳴った。刺客騒動から始まった小泉マジックの連発が最後まで続いてショーが仕上げられるのか。各地での分裂劇が悲惨で、血で血を洗う内ゲバ選挙模様も呈している。自民党の候補者を派閥別に見ると、小泉首相の出身派閥の森派が55名と前回より6名増やしており、森派が党内最大派閥に躍り出る可能性が大きい。 しかし、「自民が比較第一党から転落し、公明との合計でも過半数に達しない」という衝撃的な結果が予想されており、むしろ小泉政権退陣の可能性が出ている。 異例尽くめを象徴するように、8.30日午前10時15分頃、首相官邸正門前で女性自傷事件が発生した。女性の車の中から小泉政権を批判したB4判のビラが20〜30枚見つかっている。 |
| 【各党の責任数値と選挙見通し】 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| 【A級造反派(反対派)選挙区事情1(2005.8.20日現在)】 | |||||||||
| ブロック | 議員名 | 所属 | 派閥 | 選挙区 | 公認 | 自民 | 民主 | 共産 | 社民 |
| 北海道 | 山下貴史 | 亀井派 | 北海道10区 | 飯島夕雁 | 小平忠正 | ○ | |||
| 東北 | 津島恭一 | 国民新党 | 橋本派 | 青森4区 | × | 木村太郎 | 渋谷修 | ○ | ○ |
| 野呂田芳成 | 橋本派 | 秋田2区 | 小野貴樹 | 佐々木重人 | ○ | ○ | |||
| 北関東 | 小泉龍司 | 橋本派 | 埼玉11区 | 新井悦二 | 八木昭次 | ○ | |||
| 東京 | 小林興起 | 新党日本 | 亀井派 | 東京10区 | × | 小池百合子 | 鮫島宗明 | ○ | |
| 八代英太 | 橋本派 | 東京12区 | × | 太田昭宏(公明党) | 藤田幸久 | ○ | |||
| 南関東 | 堀内光雄 | 堀内派 | 山梨2区 | ○ | 長崎幸太郎 | 坂口岳洋 | ○ | ||
| 保坂武 | 橋本派 | 山梨3区 | ○ | 小野次郎 | 後藤斎 | ||||
| 北信越 | 綿貫民輔(78) | 国民新党 | 橋本派 | 富山3区 | 萩山教厳 | 向井英二 | ○ | ○ | |
| × | 橋本派 | 長野2区 | 関谷理記 | 下条みつ | ○ | ○ | |||
| 松宮勲 | 亀井派 | 福井1区 | 稲田朋美 | 笹木竜三 | ○ | ||||
| 東海 | 野田聖子 | 無派閥 | 岐阜1区 | ○ | 佐藤ゆかり | 柴橋正直 | ○ | ||
| 藤井孝男 | 橋本派 | 岐阜4区 | 金子一義 | 熊谷正慶 | ○ | ||||
| 古屋圭司 | 亀井派 | 岐阜5区 | 和仁隆明 | 阿知波吉信 | ○ | ||||
| 城内実 | 森派 | 静岡7区 | 片山さつき | 阿部卓也 | |||||
| 青山丘 | 新党日本 | 亀井派 | 愛知7区 | 鈴木淳司 | 小林憲司 | ||||
| 近畿 | 小西理 | 橋本派 | 滋賀2区 | 藤井泰宏 | 田島一成 | ○ | |||
| 田中英夫 | 堀内派 | 京都4区 | ○ | 中川泰宏 | 北神圭朗 | ○ | |||
| 左藤章 | 堀内派 | 大阪2区 | 川条志嘉 | 荻原仁 | ○ | ||||
| 中野寛成 | 大阪8区 | 大塚高司 | ○ | ||||||
| 森岡正宏 | 橋本派 | 奈良1区 | 鍵田忠兵衛 | 馬淵澄夫 | ○ | ||||
| 滝実 | 新党日本 | 橋本派 | 奈良2区 | 高市早苗 | 中村哲治 | ○ | |||
| 中国 | 川上義博 | 亀井派 | 鳥取2区 | 赤沢亮正 | 山内おさむ | ○ | |||
| 亀井久興 | 国民新党 | 河野派 | 島根2区 | × | 竹下亘 | 小室寿明 | ○ | ||
| × | 無派閥 | 岡山2区 | 萩原誠司 | 津村啓介 | ○ | ||||
| 平沼赳夫 | 亀井派 | 岡山3区 | 阿部俊子 | 中村徹夫 | ○ | ||||
| 亀井静香 | 国民新党 | 亀井派 | 広島6区 | ○ | 堀江貴文 | 佐藤公治 | |||
| × | 亀井派 | ||||||||
| 四国 | 山口俊一 | 徳島2区 | 七条明 | 高井美穂 | ○ | ||||
| 九州 | 自見庄三郎 | 山崎派 | 福岡10区 | 西川京子 | 城井崇 | ○ | ○ | ||
| 武田良太 | 亀井派 | 福岡11区 | 山本幸三 | 稲富修二 | ○ | ||||
| 今村雅弘 | 橋本派 | 佐賀2区 | 土屋千昭 | 大串博志 | ○ | ||||
| 保利耕輔 | 橋本派 | 佐賀3区 |
広津素子 |
○ | ○ | ||||
| 衛藤晟一 | 亀井派 | 大分1区 | 佐藤錬 | 吉良州司 | ○ | ||||
| 江藤拓 | 亀井派 | 宮崎2区 | 上杉光弘 | 黒木健司 | |||||
| 古川禎久 | 橋本派 | 宮崎3区 | 持水哲志 | 外山斎 | |||||
| 松下忠洋 | 橋本派 | 鹿児島3区 | 宮路和明 | 野間健 | |||||
| 森山裕 | 橋本派 | 鹿児島5区 | 米正剛 | ○ | |||||
| 【逆刺客選挙区事情1(2005.8.20日現在)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 天木氏の小泉首相の選挙区神奈川11区出馬について | れんだいこ | 2005/08/28 |
| 元駐レバノン大使で小泉首相のイラク政策を批判して罷免された経歴を持つ時事評論家の天木直人氏が小泉首相の選挙区神奈川11区から出馬すると云う。なんでこういう戦略採るのか分からないが愉快犯首相には愉快犯で対抗するというユーモアなのだろう。しかし、れんだいことしては、民主党の斎藤勁(つよし)陣営に対する利敵行為ではなかろうかと思う。これは可能性の有ることだから、とても愉快な話なのに。 天木氏は、新党日本か国民党から出馬して、東京辺りの造反派が立候補しておらず、民主の勝ち目の無い選挙区で、自民党討ち取りに向った方が賢明と思うのだが。こういうことが分からないようではお粗末過ぎる、もう間に合わないのだろうか。 |
||
| 【その他注目面白見どころ選挙区総まとめ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【小泉首相お膝元選挙区の痴態】 |
|
小泉首相のお膝元選挙区である神奈川11区で、小泉選対本部長が未だ決まらないという醜態が演ぜられている。首相は前回衆院選で、一度も地元入りせずに自己最高の17万票を獲得した。だが今回は、系列県議がへそを曲げ、まだ選対本部長も決まっていない。
小泉選対の本部長が決まらないのは、親子二代にわたって小泉首相の選挙対策本部長を務めた自民党の竹内英明・神奈川県議が、首相の行動に感情を害したからだ。今年6月の横須賀市長選で、竹内氏は元自民市議を応援したが、首相はわざわざ地元入りして、旧自治省出身の前副市長をてこ入れした。結果は、前副市長が7000票を切るきん差で当選した。 竹内氏は「(市長選で)反小泉のつもりはなかったが、けんかを売られた。今回は、選対本部長は受けない。小泉に対する気持ちはもう冷めた」と語っている。 |
|
|
| 【新聞社の「情勢調査」大々報道の政治性について】 |
| 9.4日、各新聞社は一斉に「選挙中盤情勢報告」を報じた。朝日新聞社は「自民優勢、過半数の勢い 与党安定多数も 本社情勢調査」、読売新聞社は「自公、過半数超す勢い…読売調査」、毎日新聞社は「自民党、単独過半数の勢い 中盤情勢」等々。この調査の信憑性を確認するためサイトアップしておく。 |
| 各社共通して打ち出されている内容を整理してみると次のようになる。 自民は、優勢で単独過半数(241議席)の勢い。選挙区で290人を公認した自民は、前回03年総選挙の168議席を上回り、180議席近くをうかがう。都市部で民主をリードし、栃木、和歌山、鳥取、島根、愛媛など10県では自民が議席を独占する勢い。前回の11県と同じ水準だ。比例区は前回の69議席を上回り、70台半ばに達しそうだ。選挙区との合計では250議席を超え、公示前の212議席を大きく上回る見通し。単独過半数なら、海部内閣のもとでの90年総選挙以来になる。 公明は、公示前より議席を減らす見通しで、選挙区の9名全員の当選は難しい情勢で各地で接戦を続けている。比例区も前回の25議席維持は厳しい。ないしは堅調で、全ブロックで議席を確保しそうともある。要するに「微妙な情勢」となっている。 民主は伸び悩んでおり、170議席を大きく割り込む可能性がある。選挙区では前回の105議席を下回る公算が大きい。自民候補と競り合う選挙区で伸び悩んでいる。比例区は60議席台後半にとどまる見通し。前回は自民をしのぐ72議席を獲得したが、今回は自民を下回りそうで、全体でも公示前の177議席に達するのは難しい情勢。 共産、社民は厳しい戦いとなっており、ともに1ケタの議席にとどまる見込み。 国民新党、新党日本は、ともに厳しい戦いで公示前勢力に届かない見通し。新党大地は比例区の北海道ブロックで1議席を得る可能性がある。反対派前職27人の半数以上が議席を失う可能性があるとも指摘されている。 「などの情勢が分かった」とある。但し、「調査の時点で投票態度を明らかにしていない人が選挙区で4割、比例区で3割おり、終盤にかけて状況が大きく変わりうる」と逃げの手を打っている。 |
| 調査方法として朝日新聞社の例を取り上げる。「全国300の小選挙区を150ずつ二つに分け、8月31日〜9月1日と9月2〜3日のいずれも2日間、比例区分もあわせて、電話(朝日RDD法)による情勢調査を実施した。こうして、全国の有権者を対象に電話調査を実施した。具体的には対象者の選び方は無作為3段抽出法。回答者の目標数は小選挙区ごとに400人。コンピューターで無作為に発生させた番号サンプルのうち、有権者のいる家庭用番号にかかったのは全国で計18万7897件で、うち11万8616人から有効回答を得た。回答率は63%」とのことである。読売新聞社は、「8月31日から9月3日までの4日間、全国の有権者約15万5000人を対象に世論調査を行い、全国総支局などの取材を加味して終盤の選挙情勢を探った」とある。 この「調査」の問題性は次のことにある。「回答率は63%」と末尾で記しているように、その方法はともかくも回答率63%で判断が可能なのかどうかということにある。3人に1人強が解答していないことになる。非回答率37%の動向調査が為されない限り正確な判断はできない、とすべきではなかろうか。「非回答率37%の動向調査」が無理ならば、こうした「調査報告」は社内的には資料になってもも大々的に記事にすべきではない種類のデータということになりはすまいか。 せめて非回答率20%以下のそれならともかくも37%もあれば失敗というべきだろう。その無責任性を棚に上げて敢えて政府与党有利のアナウンス効果報道を新聞社各社が一斉に為すところに政治性の意図が見て取れる、というべきではなかろうか。ここには、公正中立を建前としている報道が機に応じて露骨に権力派の走狗となるという階級性が介在しているとみなすべきだろう。 もとより「勝ち馬ブーム」に対しては「判官びいき」も生み出すので権力派の狙い通りになるかどうかは分からない。しかし、何度も刷り込めば「マインドコントロール効果」が上がるのは事実であろう。 2005.9.5日 れんだいこ拝 |
| Re:れんだいこのカンテラ時評その93 | れんだいこ | 2005/09/06 |
| 【2005総選挙考】 2005総選挙は、自民圧勝の勢いと報ぜられている。9.4日、大手の各新聞社が一斉にこれを報じている。これが実報か虚報かはさておき(否応無く9.11には明らかになる)、自民の強さ要因を推測してみる。 その第一は、ブッシュー小泉連盟の好軍事性のアキレス腱である「自衛隊のサモアからの即時撤退」を打ち出さないバカさ加減に有る。代わりに、バカの一つ覚えのような政権交替論、郵政については郵便局が無くなる論、年金その他の増税必死論、憲法改正問題に逃げ込んでいることに有る。 れんだいこには、「自衛隊のサモアからの即時撤退」を打ち出さない理由が分からない。これを打ち出さないのには、大政翼賛会化しているか、「自衛隊のイラク派兵」については与野党一致しているからとしか考えられない。 社共は口先で批判するが、この時期に於いて自衛隊撤退を強く打ち出さないということは単なるアリバイ的職業的反対屋でしかなく、裏から小ネズミ・シナリオを支えているように見える。日本左派運動の活性化の為にはこうした社共のエセ運動を退け、真に闘争を組織し得る党派を登場させねばならない。 もう一つ野党非勢の要因が考えられる。小ネズミ首相の手法としてのレイプ政治はここでは問わないとして、彼の打ち出す民営化論法に対して、理論的にも標語的にも太刀打ちできていないことにくすぶりがあるのではなかろうか。要するにオツムで負けているのではなかろうか。小ネズミ・シナリオの裏には電通的な智恵袋が見え隠れしている。この連中が作り出すコマーシャルに野党がこぞって太刀打ちできていない気がする。 曰く、「官から民へ」、「郵政民営化こそ構造改革の関門」、「死んでも構わない。私はこれに命を賭けている」という単純明快分かりやすい論法に対して、各野党のそれはややこしくちまちましたものになっている。むしろ、小ネズミ・シナリオ上で駆け引きしているものだから旗色が悪くなるのも当然だろう。つまり、オツムで負けているように見える。他にも、選挙地盤に対する日頃の扶植活動の差が考えられよう。 この三つの要因が重なって、「自民圧勝の勢い」が生み出されているように思える。こうなると、野党は負けるように負けるように協力している気さえしてくる。民主の政権交替論は本来は値打ちものなのに、繰り出す政策アドバルーンが幻滅を与えている。わざとやっているようにさえ思える。 社共の現指導部は、日本左派運動をあれこれの選択肢の中から議会政治専一主義運動へ流し込んできた責任が有る。それならその責任に応えるのかというと、万年執行部体制を敷き勝っても負けても御身安泰の中で取り組むという無責任さを常態としている。そういういろんな事情が重なりパワーにならない。鳴り物入りの議会闘争がこのテイタラクであり、道理で世の中が右へ右へと靡いてしまう訳である。こういう運動を十年一日の如く垂れ流すのは犯罪的と云えよう。 れんだいこは、この劣性を覆す術を次のように考える。一つは、「自衛隊のサモアからの即時撤退」であり、これによりブッシュー小泉連盟の好軍事性をさらけだす。構造改革を云うのなら、これの是正こそ第一歩にして本筋であることを訴える。過重国債論もこの観点から訴える必要があろう。一体、小ネズミ悪政で国債がどんなに膨張した事か。その要因に軍事傾斜があるのではないのか。ブッシュに云われるままにいくら貢いでいるのか。 民営化論に対しては、「官から民へ」ではなく「官と民の棲み分け」を訴える。官業が良い場合もあれば民業が良い場合も有る。これは当たり前のことである。中曽根以来の「官から民へ」は実は国家機密解体的外資売り政策であり、国益に何ら合致しない。このことを訴える。 官から民へ、民から官への適正さこそ政治の見識と云うべきであろう。官の事業を民の事業の物差しで計るのは馬鹿げている。これらのことを明らかにして、「小泉改革路線」の虚を撃てば良い。それが出来ないのは、小ネズミ・シナリオに乗っているからにほかならない。 「選挙地盤に対する日頃の扶植活動」については如何ともし難い。選挙になって急に猫なで声されても誰も相手にしないのが当然だろう。自民は理屈を凝らさず、個人、企業、業界、団体、協会への日常的働き掛けに取り組んでいる。それが野党にはできない。せいぜい労組依存ぐらいで後は個人を対象にしている。 それは恐らく日共式個人主義的政治論に汚染されているからであろう。日共論法に追随すると実態に即しないものだから次第に無気力症に陥ってしまう。その無気力症を党中央専制によって引っ張っているのが日共式運動論組織論であるというのにその悪影響に引きずられている。 ろくなもんではないのにそれが通用している。それを痛痒と考える知力が無い。日共はこたびも相変わらず分裂選挙しかけ、唯我独尊的に悦に入っているが犯罪的な役回りをしている。それやこれやで野党の足腰は弱く分裂しており、為に政府与党の権力体制の独走を許している。角栄式ムネオ式議員活動には何らの咎が無くむしろ理に叶った運動をしているのに、これを率先してとっちめることにより、政界全体に一罰百戒式悪影響を与えている。 いわゆる利権論を振りかざしているが、地域から選出される議員が地域の面倒を見るのは当たり前のことである。問題は面倒を見る質であるが、面倒を見ること自体が悪いわけではない。日共利権政治論のウソを誰も衝かない。むしろ、日共の説教を許している。キレイ清潔運動がどの勢力を利しているのか、その先を問うものがいない。 政党も個人と同じで「カネが無いのは首が無い」のと同じである。それを思えば、党派は自律的な運動を推進するためにも、第一に財政を豊かにせねばならない。政党助成金を貰う貰わないには何の意味も無い。要するに如何なる政策を掲げ、如何なる運動力を示し、歴史に如何なる影響を与えたのかが評価の基準とされるべきである。土俵外で、キレイ清潔を競って何の意味があろう。むしろ、財政逼迫が、思わぬところからのヒモ付き政治献金を受けやすくさせる方がより危険であろう。 このことを考えると、政党が個人、労組、企業、団体、業界、協会へ資金無心に働き掛けることに何の罪があろう。問題は、献金のヒモ付き性であり、額の適正化であり、出入りの透明化であろう。この当たり前のことが出来ないように出来ないように「左」から仕掛けられ、野党の足腰を弱めていることに気付かねばならない。日共不破式政治論は意図的にこの道に誘っている気配がある。これをどう粉微塵に砕くか、これも問われている。 結論として云えることは、自公体制を覆すには、政策でも動員力でも資金力でも総じて政治能力において優らねばならないということである。それが出来ない間には本当の意味での政変は起らない。そうは云っても人民大衆は常に賢いから、こたびも素敵な結果を生み出すだろう。政財官学報の五者同盟が体制同盟でブロックしようとも、それをかいくぐるシュートを決めるであろう。しかし、ゴールを決めた瞬間から政治効率をより高める政治を創造せねばならない。それは楽しい道のりになるはずである。 2005.9.6日 れんだいこ拝 |
||
これより以降は、
| 選挙結果の総評 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)