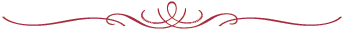
| 2003第43回総選挙結果の総評 |
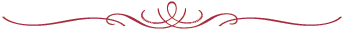
| 【2003第43回衆院選総括】 | れんだいこ | 2003/11/10 |
| 2003.11.9日、選挙運動のためのマニフェストの配布が解禁となった第43回衆院選が行われ、結果は新たな微妙な与野党バランスを生むこととなった。保守、社民、共産の各党が沈没し、唯一公明党が健闘した。小選挙区で自民、民主両党候補の対決となった246選挙区の勝敗は、自民党の144勝99敗(3選挙区は無所属候補が当選)という結果となった。いずれにせよ、流れが大きく自民対民主の二大政党制へ傾いた、と総括できる。 政権与党側は自民党が堅塁、公明党の奮闘、保守党の凋落という構図ながらも全体で現勢力を維持した。野党側は、民主党の躍進に象徴され、共産党、社会党は煽りを受け凋落という構図となった。戦後左派運動は遂にここで終焉した、と見なして良いと思われる。この後、どういう左派運動が生まれ出てくるのか注目される。 公明、保守新両党とあわせた与党3党では絶対安定多数(269議席)を超える275議席を確保し、就任後初の総選挙で改革の実績を訴えた小泉首相は、9日夜、「自民党が第1党で、与党3党で過半数なら(国民から)信を得たことになる。勝利だ」、「与党3党で安定多数を取れば、継続して頑張れということだ。公約に従って、改革を推進する」と述べ、首相続投に意欲を示した。公明党の神崎武法代表も10日未明、「小泉政権は信任を得た。小泉首相の下に結束し改革に取り組みたい」と語った。与党3党は10日、党首会談で連立政権の継続を確認する。 これを各政党別に分析してみる。 自民党は237議席と伸び悩み、目標としていた解散時勢力(246議席)を下回り、目標としていた単独過半数(241議席)確保に失敗し、93年衆院選以来4回連続の過半数割れとなった。但し、2000年衆院選(森喜朗首相)の233議席は上回った。群馬、栃木、富山、島根、香川、愛媛、高知などの11県で議席を独占したが、都市部で民主党候補に競り負ける結果が相次いだ。衆院の比例代表では初めて他党に敗れた。無所属当選組の入党で、「実質的には単独過半数を確保した」(党幹部)との見方もある。 公明党は、小選挙区が堅調で、解散時勢力(31議席)を上回った。選挙協力で自民党の公明党依存が深まったこともあり、今後の成り行きが注目される。 保守党は、選挙前の半数以下の4議席にとどまる惨敗となった。保守新党代表の熊谷弘氏が落選し、代表辞任の意向を表明した。党は参院議員とあわせ政党助成法の政党要件である5人以上の国会議員数は満たしたものの展望は厳しく、自民党との合流論が加速する可能性が強まり、投開票翌日に解党の方針を決め、衆参7人全員で自民党に合流した。 選挙前に自由党と合併し、マニフェスト(政権公約)を掲げて「政権選択選挙」を主導した民主党は解散時勢力(137議席)から議席を大幅に伸ばし177議席を獲得した。「2大政党制」への足がかりとなる結果となった。比例区では第1党となった。小選挙区でも都市部を中心に前回を上回る強さを見せ、北海道、埼玉、千葉、愛知、滋賀では過半数を制した。宮城、東京、京都、福岡でも自民党と互角に議席を分け、自民党と旧社会党による「55年体制」に移行して以来、野党第1党の最多議席である58年衆院選の旧社会党の166議席をも大きく上回る躍進を果たし、今後の政権交代に向け弾みをつけた。比例代表も自民党を上回った。 民主党の菅代表は10日未明の記者会見で、「(目標の)200議席に届かなかったが、国民から大きな議席をもらった。次の機会に政権交代につなげる」と語った。小沢一郎氏と二枚看板で戦った選挙戦を振り返り、「本当に良い戦いができたと感じている。国民の期待を裏切らない政権にたどり着きたい」、「小泉政権はそう遠くない時期に行き詰まる」と、手応えを語った。但し、菅氏が「天王山」と位置づけた東京では25選挙区中12議席にとどまり、前回から一つ減らしている。 共産党は、議席を半減させ70年代以降で最低の9議席となった。小選挙区は全敗で、前回、全ブロックから最低1議席を獲得していた比例代表でも今回、北海道、中国などで議席をとりこぼした。志位委員長は、「議席を大幅に減らしそうで、大変残念。今度の選挙では、これまでの政党関係が急激に変化した。我々は奮闘したが、時間が足りなかった」などと早々に敗戦の弁を述べた。 その後の記者会見では、「自民と民主の二つが主役で、他はあってもなくてもいいという今回の選挙の構図は、議会制民主主義にとって危険なあり方だ」、「(執行部の責任については)我が党で執行部の責任が問題になるのは、路線や方針で誤りを起こした場合。今回の選挙ではベストを尽くした。次の前進に力を尽くすことが責任だと考えている」と述べた。 社民党は、結党以来最低の6議席となり大きく落ち込んだ。小選挙区での当選が照屋寛徳氏(沖縄2区)1人、党首の土井氏からして小選挙区で敗れ辛うじて比例で復活という惨めな結果となった。土井党首は、「きつい、厳しい選挙でした」、「党自身が小さくなると、日本の政治がおかしくなる。やっぱり社民党ががんばっていないと、政治はよくならない」と、厳しい表情で語った。進退を問われると、「重く受け止めています」と繰り返した。東京・三宅坂の党本部は重苦しい空気に包まれ、土井党首は敗北の責任をとって党首辞任に追い込まれた。 無所属の加藤紘一氏、田中真紀子氏が当選を決めた。他方、各党の幹部や閣僚経験者ら大物の落選が相次いだ。落選者のうち、自民党の山崎拓副総裁は10日に小泉首相(総裁)に副総裁の辞表を提出する考えを表明し、政界引退も示唆した。村岡兼造元官房長官も政界引退の意向を明らかにした。 主な落選者は次の通り(敬称略)。 【自民党】村岡兼造(秋田3区)、太田誠一(福岡3区)、荒井広幸(福島3区)、山崎拓(福岡2区)、臼井日出男(千葉1区)、相沢英之(鳥取2区)。【民主党】二見伸明(茨城6区)。【公明党】若松謙維(埼玉6区)。【共産党】児玉健次(比例北海道)、木島日出夫(比例北陸信越)。【社民党】保坂展人(東京6区)、中川智子(兵庫6区)。【保守新党】佐藤敬夫(秋田1区)、熊谷弘(静岡7区)、松浪健四郎(大阪19区)。 れんだいこの最後のまとめ。何せ、国会中枢へ落雷しているからしてただで済む訳が無い。これからが面白い。小泉がどうはしゃぎのたうち回るのか。管−小沢組がどう切り込んでいくのか。志位と土井が三枚舌四枚舌を弄し続け、どうろれつが廻らなくなるのか。何らかの新しい動きが生まれるのか興味津々。おっと忘れてはいけない。ブッシュが我が日本をどう料理しようとしてくるのか。これが最大の関心事となるべきだろう。 2003.11.10日 れんだいこ拝 |
||
| 【供託金:衆院選で没収総額9億5700万円 前回比やや上昇】 |
|
2003.12.2日付毎日新聞(網谷利一郎)によると次の通り。 衆院選の候補者は法務局に1人300万円を供託し、得票が「有効投票総数の10分の1」を下回ると供託金が没収されて国庫に納まる。候補者乱立を防ぐのが目的。 今回は計1026人が立候補し、没収の候補者は計319人で、没収率は31.09%。前回は計1199人が立候補し没収は326人、没収率は27.19%だった。 没収がなかったのは55選挙区で、都道府県でゼロだったのは京都府(1〜6区)だけ。多かったのは東京都、神奈川県各29人▽埼玉県20人▽千葉、愛知県各15人の順。 全国最低得票は698票(東京1区)。21票差で300万円没収を危うく免れた候補(北海道1区)もいた。分岐点となる「没収点」の最高は福島1区(2万8316票)で、最低は高知1区(1万439票)だった。 党派別では▽共産党235人▽無所属・諸派51人▽社民党32人▽民主党1人。没収者についてみても、今回の共産・社民の退潮がうかがえる。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)