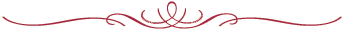
| 選挙用語の基礎知識 |
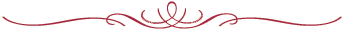
(最新見直し2014.12.12日)
| 【有権者年齢】 |
| 「年齢計算に関する法律」に基づく。投票日翌日までに満20歳の誕生日を迎える者が有権者となり選挙権を得る。同様に、投票日翌日までに満30歳になる人は、参院議員候補資格を得る。 |
| 【公示と告示の違い】 |
| どちらも有権者に投票日を周知させるものであるが、公示は衆参両院選。告示は知事選や市長選などの地方選。公示は憲法で定められた天皇の国事行為で、内閣の助言と承認に基づいて行われる。告示は、管轄の各種選挙管理委員会が行う。 |
| 【安定多数と絶対安定多数】 |
| 安定多数とは、衆院の21常任委員会すべての委員長を与党議員が務めても、与党が委員数で野党を下回らない状態で、252議席。提出法案の処理など、与党が安定した政権運営をはかるための指標となり、衆院選のたびに与党が目標に掲げる場合が多い。 絶対安定多数は、与党が全委員会の委員長を独占したうえで、委員数で過半数を確保する状態を指す。269議席がそのライン。 |
| 【小選挙区比例代表並立制】 |
| 衆議院議員選挙は、「小選挙区比例代表並立制」を採用している。これは、文字通り「小選挙区」と「比例代表」からできている。小選挙区では、都道府県を複数ブロックに分け、それぞれの選挙区でのトップ得票者が当選する。比例代表では、複数の都道府県を州ブロックに分け、政党名で投票される。政党は、得票数に応じて議席数が割り当てられ、名簿順に当選が決まっていく。 なお、小選挙区と比例代表の「重複立候補」が認められており、小選挙区で落選しても拾い上げられる仕組みになっている。但し、この拾い上げ方式は各党で異なり、名簿順位確定型と惜敗率型とに分かれている。惜敗率型は、民主党が採用しており、小選挙区での競り具合による惜敗率で判定される仕組みになっている。この制度は、1996年の衆議院議員選挙で導入された。 |
| 【期日前投票、不在者投票】 |
|
「期日前投票」と「不在者投票」制度のどこが違うのか。
■期日前投票 期日前投票が行えるのは、市区町村の選挙人名簿に登録されている人で、投票日当日に投票できぬ人が、選挙人名簿に登録された住所地で直接投票箱に投票する制度を云う。投票期間は選挙公示日の翌日から投票日の前日で、時間は原則午前8時半から午後8時まで。投票場所は役所や公共施設などに各市区町村が設ける期日前投票所となる。投票は、入場券が届いていればそれを持参し、実際に投票箱に投票する。ちなみに期日前投票を行った後に亡くなったり転居したりした場合でも投票は有効な票として取り扱われる。 ■不在者投票 不在者投票が行えるのは、選挙期間中に仕事や旅行などによって選挙人名簿に登録されていない市区町村に滞在している人で、仕事や旅行の滞在先などの選挙管理委員会で投票用紙を提出する。投票期間は期日前投票と同じ。投票手順は次のようになる。1)選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対し、直接か郵便で投票用紙などの必要書類を請求する。その際、滞在先の選挙管理委員会で投票をする旨を伝える。2)投票用紙と投票用封筒、不在者投票証明書が交付される。これらは絶対に開封せず不在者投票をする日に持参する。自宅などで投票用紙に記入して郵送された場合は無効になる。3)滞在地の選挙管理委員会に出向き、その場で投票用紙に記入する。それを内封筒に入れ、その内封筒を外封筒に入れて外封筒に署名し、選挙管理委員長に提出する。 不在者投票は名簿登録されている選挙管理委員会に投票用紙を送付する必要があるので日数には余裕を持って投票する必要がある。不在者投票は、そのほか、選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所中の人、さらに投票日当日に20歳になるが、投票日前には投票権利がない人も行うことができる。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)