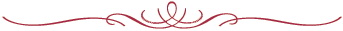
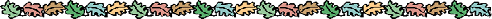
関連サイト・宮地健一のページの選挙戦コーナー
【2001.7.29日参議院選】
|
|
【ガイダンス】
比例代表には、今回から非拘束名簿式が導入された。定数5削減で、改選数は選挙区73議席、比例代表48議席の計121議席。
立候補者数は、496名(選挙区・292名、比例代表・204名)となり、前回参院選の474名(選挙区・316名、比例代表・158名)を上回った。女性は、選挙区が79名となり過去最高、比例と併せて計137名となった。
投票率は、選挙区選が56・44%、比例選が56・42%。前回98年参院選は選挙区58・84%、比例58・83%と比べて2ポイント程度下回った。参院選での60%割れは四回連続で7度目。過去最低だった九五年の前々回(選挙区44・52%)は上回るものの、史上三番目の低投票率になった。
投票時間の二時間延長や不在者投票の要件緩和といった改正公選法が前回選挙から施行された上、「小泉人気」などで有権者の関心が高まることが予想されたが、各党が「改革」を掲げるなど争点がいまひとつ明確でなく、選挙が夏休み時期と重なったことが投票率アップに結び付かなかった原因とみられる。前回と比べ激戦区が減ったことも影響したようだ。
不在者投票者数が前回の*倍になっていたにも関わらずの低投票率となった。当日の有権者数に占める不在者投票者数の割合は*.*6%で、前回の約*.**%を大幅に上回った。不在者投票者数は区市町村の窓口での投票分で、老人ホームなどからの送付分や郵便投票は含まれていない。
|
| 【総評】 |
第19回参院選の結果、自民、公明、保守の与党三党は計78議席に伸ばして参院の過半数と安定多数を確保した。自民は64議席を得て、国政選挙では1992年の参院選以来9年ぶりに改選過半数(61議席)を超えた。
民主は26で改選数を超えたが、目標の27を下回った。公明は13で改選議席を維持。自由は倍増の6と健闘。共産5、社民3で後退した。保守は比例で扇千景党首が一議席を守った。
比例代表の獲得議席は前回14だった自民が20、民主8、公明8、共産4、社民3、保守1、自由4で確定した。
選挙区は自民が44で、うち43人がトップ当選。民主18、公明5、共産1、社民0、自由2、無所属3。
自民は焦点の一人区で25勝2敗。4野党が選挙協力で合意した1人区13選挙区でも、三重で野党候補に敗れただけ。98年の前回参院選で全敗した大都市部の選挙区3、4人区も各1議席の計5議席を確保、15ある2人区でも14選挙区で議席を得た。
民主は埼玉、大阪などで競り勝ち、2―4人区で計18議席を獲得、1人区では議席を失った。公明は東京、大阪など5選挙区で全員当選を果たした。共産は東京で1議席だけ。社民は大分で自民に競り負けた。自由は岩手と新潟で2議席を得た。 |
| 政党名 |
候補者数(女性) |
|
選挙区 |
比例区 |
改選議席 |
|
非改選 |
現有議席数 |
| 自民党 |
75(10) |
|
48 |
27 |
61 |
|
47 |
108 |
| 公明党 |
22(7) |
|
5 |
17 |
13 |
|
10 |
23 |
| 保守党 |
5(1) |
|
0 |
5 |
3 |
|
4 |
7 |
| 与党総数 |
102(18) |
|
53 |
49 |
77 |
|
64 |
137 |
|
| 野党総数 |
|
|
|
|
|
|
64 |
113 |
|
| 民主党 |
63(17) |
|
35 |
28 |
22 |
|
33 |
56 |
| 自由党 |
31(6) |
|
14 |
17 |
3 |
|
2 |
5 |
| 準与党総数 |
94(23) |
|
|
|
25 |
|
35 |
61 |
|
| 共産党 |
72(24) |
|
47 |
25 |
8 |
|
15 |
23 |
| 社民党 |
24(10) |
|
14 |
10 |
7 |
|
5 |
12 |
| 新社会党 |
3(1) |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 社共総数 |
|
|
|
|
15 |
|
20 |
35 |
| その他 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
| 無所属の会 |
1(1) |
|
0 |
1 |
0 |
|
4 |
4 |
| 自由連合 |
92(33) |
|
45 |
47 |
1 |
|
0 |
1 |
| 二院クラブ |
10(1) |
|
0 |
10 |
0 |
|
1 |
1 |
| さきがけ |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 自由と希望 |
10(3) |
|
|
10 |
0 |
|
0 |
0 |
| 維新政党・新風 |
2(0) |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 女性党 |
2 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 諸 派 |
43(15) |
|
36 |
7 |
0 |
|
1 |
2 |
| 無所属 |
48(9) |
|
48 |
- |
6 |
|
4 |
9 |
| |
|
|
|
|
欠員2 |
|
|
欠員2 |
| 合計 |
496(137) |
|
292 |
204 |
126 |
|
126 |
250 |
| 定数 |
- |
|
73 |
48 |
121 |
|
|
- |
|
| |
新議席 |
(現・元・新) |
選挙区 |
比例区 |
議席増減 |
伸び率 |
公示前
議席数 |
新総議席数 |
女性議員(女性) |
| 自民党 |
64 |
(40.3.22) |
45 |
20 |
+3 |
|
108 |
112 |
10 |
| 公明党 |
13 |
(9.−.4) |
5 |
8 |
+0 |
|
23 |
23 |
4 |
| 保守党 |
1 |
(−.−.0) |
− |
1 |
|
|
7 |
5 |
1 |
| 無所属 |
1 |
(?.?.?) |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
|
|
|
| 与党総数 |
79 |
|
51 |
29 |
+2 |
|
137 |
139 |
|
| 野党総数 |
42 |
|
24 |
19 |
|
|
113 |
106 |
|
|
|
| 民主党 |
26 |
(12.−.14) |
18 |
8 |
+4 |
|
56 |
59 |
8 |
| 自由党 |
6 |
(1.−.5) |
2 |
4 |
+3 |
|
5 |
8 |
1 |
| 準与党総数 |
32 |
|
20 |
12 |
+7 |
|
|
|
|
|
|
| 共産党 |
5 |
(3.−.2) |
1 |
4 |
−3 |
|
23 |
20 |
9 |
| 社民党 |
3 |
(0.−.3) |
0 |
3 |
−4 |
|
12 |
8 |
4 |
| 新社会党 |
0 |
(?.?.?) |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
| 社共総数 |
8 |
|
1 |
7 |
−7 |
|
|
|
|
| その他 |
3 |
|
0 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 無所属の会 |
0 |
(−.−.0) |
− |
0 |
|
|
4 |
4 |
0 |
| 自由連合 |
0 |
(0.0.0) |
0 |
0 |
−1 |
|
1 |
0 |
|
| 二院クラブ |
0 |
(−.0.0) |
0 |
3 |
|
|
1 |
1 |
|
| さきがけ |
0 |
(−.−.−) |
0 |
0 |
|
|
1 |
1 |
|
| 自由と希望 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
| 維新政党・新風 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
| 女性党 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
| 諸 派 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
2 |
2 |
|
| 無所属 |
2 |
(1.0.1) |
2 |
0 |
|
|
9 |
6((0)1) |
1 |
| |
|
|
|
|
|
|
欠員2 |
|
|
| 合計 |
121 |
(67.3.51) |
73 |
48 |
|
|
250 |
247 |
38 |
| 定数 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
| |
 |
議席 |
得票 |
 得票率 得票率 |
政党名得票数 |
個人名得票数 |
| 自民党 |
|
20 |
21,114,706 |
38.57 |
14.925.437 |
6.189.269 |
| 民主党 |
|
8 |
8,990,523 |
16.42 |
6.082.694 |
2.907.829 |
| 公明党 |
|
8 |
8,187,827 |
14.96 |
1.865.797 |
6.322.030 |
| 共産党 |
|
4 |
4,329,210 |
7.91 |
4.065.047 |
264.163 |
| 自由党 |
|
4 |
4,227,148 |
7.72 |
3.642.884 |
584.264 |
| 社民党 |
|
3 |
3,628,635 |
6.63 |
2.298.104 |
1.330.531 |
| 保守党 |
|
1 |
1,275,002 |
2.33 |
609.382 |
665.620 |
| 自由連合 |
|
0 |
780,389 |
1.43 |
400.262 |
380.127 |
| 二院クラブ |
|
0 |
669,872 |
1.22 |
374.207 |
295.665 |
| 新党・自由と希望 |
|
0 |
474,886 |
0.87 |
108.979 |
365.907 |
| 女性党 |
|
0 |
469,692 |
0.86 |
381.752 |
87.940 |
| 新社会党 |
|
0 |
377,013 |
0.69 |
247.723 |
129.290 |
| 無所属の会 |
|
0 |
157,204 |
0.29 |
133.762 |
23.442 |
| 維新政党・新風 |
|
0 |
59,385 |
0.11 |
44.307 |
15.078 |
| 政党名 |
今回比例区得票数 |
今回得票率 |
前回比例区得票数 |
前回得票率 |
票数増減 |
率増減 |
絶対得票率 |
相対得票率 |
| 自民党 |
21.114.706 |
38.57 |
|
25.17 |
|
|
|
|
| 公明 |
8.187.827 |
14.96 |
|
13.80 |
|
|
|
|
| 保守 |
1.275.002 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
| 無所属 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 与党総数 |
30.577.503 |
55.86 |
|
|
|
|
|
|
| 野党総数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 民主党 |
8.990.523 |
16.42 |
|
21.75 |
|
|
|
|
| 自由 |
4.227.148 |
7.72 |
|
9.28 |
|
|
|
|
| 準与党総数 |
13.217.625
|
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| 共産 |
4.329.210 |
7.91 |
|
14.60 |
|
|
|
|
| 社民 |
3.628.635 |
6.64 |
|
7.79 |
|
|
|
|
| 新社会党 |
377,013 |
0.69 |
|
1.65 |
|
|
|
|
| 社共総数 |
7.961.959 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由連合 |
780.389 |
1.43 |
* |
0.92 |
|
|
|
|
| 二院クラブ |
669.872 |
1.22 |
* |
1.03 |
|
|
|
|
| さきがけ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由と希望 |
474,886 |
0.87 |
* |
|
|
|
|
|
| 維新政党・新風 |
59.385 |
0.11 |
|
0.10 |
|
|
|
|
| 女性党 |
469.692 |
0.86 |
|
1.23 |
|
|
|
|
| 諸派 |
|
|
* |
2.69 |
|
|
|
|
| 無所属の会 |
157.204 |
0.29 |
* |
|
|
|
|
|
| 無所属 |
|
|
* |
|
|
|
|
|
| 合計 |
54.745.422 |
100 |
* |
|
|
|
|
|
| (定数は***)(欠員*)参議院の改選議席は、今回から5削減されて
121となっています。 |
|
| (注)党派の順序は****。 |
| (5)主要政党の最近事例投票数・率との比較(やや不正確です) |
|
|
前回1998年参院選 |
|
改選議席年度1995年参院選 |
| 政党名 |
|
議席 |
議席増減 |
得票数 |
得票率 |
得票率増減 |
|
議席 |
議席増減 |
得票数 |
得票率 |
得票率増減 |
| 自民党 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公明党 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 民主党 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由党 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共産党 |
選挙区
比例 |
7
8 |
(−6)
(−4) |
875.9
819.5 |
15.66
14.60 |
−5.79
−.69 |
|
3
5 |
(−1)
(−2) |
431.5
387.4 |
10.38
9.53 |
−0.51
−1.62 |
| 社民党 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
過半数議席63議席の確保が自民、公明、保守の3党の最低目標。
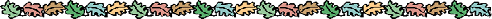
| 【(選挙前れんだいこコメント)】 |
|
小沢も宮崎兄ぃもがんばれ!頑張れ!それにしても、社共が中小企業を心配して、労働者の生活不安にコメントしないとは腐り切っている。
全国の左派人士は理屈を言わずに今回は宮崎兄ぃを大支援し、ここから次の選挙で複数候補の擁立を目指すべく奮闘しよう。この時どの党派の誰を立てるか喧喧諤諤すれば良い。共同戦線でこの闘いに当たるべし。小党分立で供託金に泣いて立候補さえできないなどの泣き言云う前に、早ぅ票読みせんかい。
|
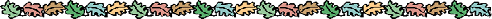
(開票後れんだいこコメント)
| 【(選挙後れんだいこコメント)】 |
| こたびの参院選総括記。 |
れんだいこ |
2001/07/30 |
れんだいこ板に結集される全ての皆様、只今よりれんだいこがこたびの参院選を総括して見ます。そんじょそこらの商業新聞、テレビでは聞けない話をご披露致します。ぶっつけですので、明日になったらああ書けば良かったと思う面も出てくると思いますが、まずはまずは幕開けでぇす。
まず投票率が伸びなかったことについてコメントします。従来より2時間延長、不在者投票も記録的に倍化していたにも関わらず、選挙区で56.44%(←58.84)、比例区で56.42%(←58.83)となり、史上三番目の低投票率になりました。これをどう見るか。小泉神風様々と揉み手する与党圧勝、台風一禍総括する野党惨敗というそれぞれのコメントにも関わらず、多くの有権者が本筋のところで見せ場を作らない出来レース学芸会運動に食傷気味であったことを物語っていると思われます。
自民党が64議席(←61)を得て、1992年の参院選以来の単独過半数を獲得しました。これは小泉首相が信任され、続投が確定したことを意味します。公明党も健闘し改選議席を維持しました。保守党の扇党首も首の皮一枚繋がりました。この与党三党で全有権者投票数の55.86%つまり約55%を獲得しました。
民主党は26議席(←22)を得て、かってのブームは消えたものの着実に前進を遂げていると見なすことが出来ます。自民党とは一味違う若手が続々と結集しつつあるようです。自由党は6議席(←3)を得て、小議席ながらも倍増しています。頑固に政策を訴える愚直な姿勢が好感を掴んだ模様です。この両党で、全有権者投票数の24.14%つまり約25%を獲得しました。
さて、ここでれんだいこ分析が光ります。民主党・自民党も主流の系譜から見れば本籍自民党と見なせます。自民党の単独長期政権は必ずや腐敗しそれはお国のために却って災禍であると観、社共には到底受け皿の力も意欲も無いという現実を見据え、止むに止まれず飛び出た連中が民社党、社会党の半数を巻き込んで結党されたのが新進党→民主党、その寄り合い世帯の烏合の衆化を嫌って分党したのが自由党と見なせます。という観点から、これを第二与党勢力と見なしますと、政権与党の支持率55%とこの両党の支持率25%を合わせますと、なんと!丁度80%というワンサイドな勢力地図化が見えてまいります。大政翼賛会社会が遂に完遂された、これがこたびの選挙結果であるという風に捉えることができると思われます。
さて、この現実を前にして、明日の赤旗と社民党の土井党首はどのような狡知弁を聞かせてくれるのでしょう、目下このあたりに政治通の関心が生まれつつあります。ちなみに、共産党は5議席(←8)、社民党は3議席(←7)で、この両党と新社会党(議席数0)を合わせて全有権者投票数の15.24%というシェアになっています。恐らく、社共現指導部は、この数字に対してもカエルの面にションベンで、そうそうは捲土重来は使えませんのでそれに替わる素敵な文句を聞かせてくれるでしょう。れんだいこの耳には、共産党が、東京で議席を取れて良かったと明るい総括をしてくれている様子が入っております。志位君良いおしゃぶり貰えてエカッタね。
さて、れんだいこが一押しした新党・自由と希望はあえなく玉砕しました。宮崎兄ぃの場合には、インターネット勢力の基盤はまだまだ弱く、選挙にまでは役立たない成熟度かなと身をもって知った体験になられたかと思われます。しかし、この体験は貴重な先駆けであったと思われます。次に何をすればよいのか、体を張った者だけに分かる何かを掴めたと思われます。
白川党首の場合、対公明党戦略の見直しが迫られていると思われます。公明党の存在そのものを否定するかのような党利党略的な政教分離論は共産党に任せて、あくまで運動の競り合いで抗する正攻法原則を確立することが望まれているのではないでしょうか。その過程で、個々の動きに不当性があればどこよりも鋭く暴き出し、その危険性を警鐘乱打するのが威風堂々としており、支持も増すのではないかとご意見申し上げておきます。
以上生意気に総括して見ましたが、れんだいこの未解明な関心事は自民党の強さの秘密を探ってみたいというところにあります。そういうことに取り組める余裕が無い身であるのが残念ですが、明らかにしておきたい最大のポイントは、権力=悪=自民党的な考え方は間違いで、今現在も混交しているもののひょっとして戦後の自民党は組織論的に見て非常に優れたシステムの元で運営されているのではないのか、この党の水準にしてはじめて大人の政党足りえているのではないのかという観点に興味を覚えております。
蛇足ながら、これは自民党を美化することを意味しておりません。そういう認識でもって歴史を見直さないといつまでもピンぼけの闘いにしかならず、スピッツがキャンキャン吠える程度のことで自己満足させられ、よくてせいぜい先生先生とおだてられながら最も無能な人士としての一生にさせられてしまうのではないかと懼れます。ここら辺りに現代政治絵巻を解くキーがあるようなそんな気がしております。
|
|
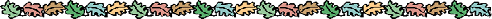
 自民党 自民党 |
名簿登載者 27人 |
獲得議席 20 |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
 |
| |
政党名票 |
- |
|
- |
14,909,237 |
 |
| 1 |
舛添 要一 |
新 |
|
当 |
1,588,862 |
研究所所長 |
| 2 |
高祖 憲治 |
新 |
|
当 |
479,585 |
元]郵政局長 |
| 3 |
大仁田 厚 |
新 |
|
当 |
461,021 |
プロレスラー |
| 4 |
小野 清子 |
元 |
|
当 |
296,263 |
財団法人会長 |
| 5 |
岩井 國臣 |
前 |
|
当 |
279,121 |
元]国交政務官 |
| 6 |
橋本 聖子 |
前 |
|
当 |
266,145 |
[元]北開政次官 |
| 7 |
尾辻 秀久 |
前 |
|
当 |
265,488 |
日遺副会長 |
| 8 |
武見 敬三 |
前 |
|
当 |
227,642 |
東海大教授 |
| 9 |
桜井 新 |
新 |
|
当 |
219,197 |
元]環境庁長官 |
| 10 |
段本 幸男 |
新 |
|
当 |
208,467 |
全土連顧問 |
| 11 |
魚住 汎英 |
前 |
|
当 |
198,121 |
全商連顧問 |
| 12 |
清水嘉与子 |
前 |
|
当 |
175,116 |
元]環境庁長官 |
| 13 |
福島啓史郎 |
新 |
|
当 |
166,670 |
元]農水省局長 |
| 14 |
近藤 剛 |
新 |
|
当 |
161,025 |
元]伊藤忠常務 |
| 15 |
森元 恒雄 |
新 |
|
当 |
157,251 |
元]自治審議官 |
| 16 |
藤井 基之 |
新 |
|
当 |
156,980 |
元]厚生省課長 |
| 17 |
山東 昭子 |
元 |
|
当 |
148,168 |
元]科技庁長官 |
| 18 |
小泉 顕雄 |
新 |
|
当 |
143,347 |
浄土宗住職 |
| 19 |
有村 治子 |
新 |
|
当 |
114,860 |
桜美林大講師 |
| 20 |
中原 爽 |
前 |
|
当 |
105,181 |
元]歯科医会長 |
 公明党 公明党 |
名簿登載者 17人 |
獲得議席 8 |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
 |
| |
政党名票 |
- |
|
- |
1,864,080 |
 |
| 1 |
山本 香苗 |
新 |
|
当 |
1,287,649 |
元]外務省職員 |
| 2 |
木庭健太郎 |
前 |
|
当 |
800,664 |
党参国対委長 |
| 3 |
遠山 清彦 |
新 |
|
当 |
794,546 |
党国際局次長 |
| 4 |
草川 昭三 |
新 |
|
当 |
699,170 |
党副代表 |
| 5 |
渡辺 孝男 |
前 |
|
当 |
697,298 |
脳神経外科医 |
| 6 |
魚住裕一郎 |
前 |
|
当 |
669,496 |
弁護士 |
| 7 |
福本 潤一 |
前 |
|
当 |
665,912 |
党参国対副長 |
| 8 |
加藤 修一 |
前 |
|
当 |
663,710 |
党国際局次長 |
 保守党 保守党 |
名簿登載者 5人 |
獲得議席 1 |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
|
| |
政党名票 |
- |
|
- |
608,697 |
|
| 1 |
扇 千景 |
前 |
|
当 |
610,349 |
国土交通相 |
 民主党 民主党 |
名簿登載者 28人 |
獲得議席 8 |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
 |
| |
政党名票 |
- |
|
- |
6,075,218 |
 |
| 1 |
大橋 巨泉 |
新 |
|
当 |
412,354 |
タレント |
| 2 |
藤原 正司 |
新 |
|
当 |
259,843 |
電力総連副長 |
| 3 |
池口 修次 |
新 |
|
当 |
230,522 |
本田労連会長 |
| 4 |
朝日 俊弘 |
前 |
|
当 |
217,178 |
医師 |
| 5 |
若林 秀樹 |
新 |
|
当 |
203,106 |
電機総研副長 |
| 6 |
伊藤 基隆 |
前 |
|
当 |
195,504 |
[元]党副幹事長 |
| 7 |
佐藤 道夫 |
前 |
|
当 |
184,743 |
[元]高検検事長 |
| 8 |
神本美恵子 |
新 |
|
当 |
173,972 |
日教組委員 |
 自由党 自由党 |
名簿登載者 17人 |
獲得議席 4 |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
|
| |
政党名票 |
- |
|
- |
3,639,501 |
|
| 1 |
西岡 武夫 |
新 |
|
当 |
121,816 |
元]文相 |
| 2 |
田村 秀昭 |
前 |
|
当 |
86,864 |
党常任幹事 |
| 3 |
広野ただし |
新 |
|
当 |
59,227 |
元]衆院議員 |
| 4 |
大江 康弘 |
新 |
|
当 |
44,000 |
元]県議 |
 共産党 共産党 |
名簿登載者 25人 |
獲得議席 4 |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
|
| |
政党名票 |
- |
|
- |
4,055,597 |
|
| 1 |
紙 智子 |
新 |
|
当 |
57,377 |
党中央委員 |
| 2 |
筆坂 秀世 |
前 |
|
当 |
40,571 |
党政策委員長 |
| 3 |
井上 哲士 |
新 |
|
当 |
32,485 |
元]赤旗記者 |
| 4 |
吉川 春子 |
前 |
|
当 |
26,386 |
党幹部会委員 |
 社民党 社民党 |
名簿登載者 10人 |
獲得議席 3 |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
 |
| |
政党名票 |
- |
|
- |
2,295,364 |
 |
| 1 |
田嶋 陽子 |
新 |
|
当 |
509,841 |
法政大教授 |
| 2 |
大田 昌秀 |
新 |
|
当 |
396,351 |
元]沖縄県知事 |
| 3 |
又市 征治 |
新 |
|
当 |
148,304 |
自治労県委長 |
 新党・自由と希望 新党・自由と希望 |
名簿登載者 10人  |
獲得議席 0  |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
 |
| |
政党名票 |
- |
|
- |
108,819 |
 |
| 1 |
白川 勝彦 |
新 |
|
|
310,010 |
|
| 2 |
宮崎 学 |
新 |
|
|
15,624 |
|
| 3 |
庄野 寿 |
新 |
|
|
15,387 |
|
| 4 |
村田 敏 |
新 |
|
|
6,493 |
|
| 5 |
臼杵 敬子 |
新 |
|
|
5,388 |
|
| 6 |
小森 禎司 |
新 |
|
|
5,325 |
|
| 7 |
田中 良太 |
新 |
|
|
3,071 |
|
| 8 |
福永 恵治 |
新 |
|
|
2,423 |
|
| 9 |
安東 尚美 |
新 |
|
|
1,462 |
|
| 10 |
児玉かがり |
新 |
|
|
883 |
|
 新社会党 新社会党 |
名簿登載者 3人 |
獲得議席 0 |
| |
|
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
 |
| |
政党名票 |
- |
|
- |
247,558 |
 |
| 1 |
小森 龍邦 |
新 |
|
|
49,546 |
|
| 2 |
矢田部 理 |
元 |
|
|
43,722 |
|
| 3 |
岡崎 宏美 |
新 |
|
|
36,188 |
|
 個人票
上位20 個人票
上位20 |
| |
|
党派 |
新旧 |
 |
当選当確 |
得票 |
 |
| 1 |
舛添 要一 |
自民 |
新 |
|
当 |
1,588,862 |
|
| 2 |
山本 香苗 |
公明 |
新 |
|
当 |
1,287,649 |
|
| 3 |
木庭健太郎 |
公明 |
前 |
|
当 |
800,664 |
|
| 4 |
遠山 清彦 |
公明 |
新 |
|
当 |
794,546 |
|
| 5 |
草川 昭三 |
公明 |
新 |
|
当 |
699,170 |
|
| 6 |
渡辺 孝男 |
公明 |
前 |
|
当 |
697,298 |
|
| 7 |
魚住裕一郎 |
公明 |
前 |
|
当 |
669,496 |
|
| 8 |
福本 潤一 |
公明 |
前 |
|
当 |
665,912 |
|
| 9 |
加藤 修一 |
公明 |
前 |
|
当 |
663,710 |
|
| 10 |
扇 千景 |
保守 |
前 |
|
当 |
610,349 |
|
| 11 |
田嶋 陽子 |
社民 |
新 |
|
当 |
509,841 |
|
| 12 |
高祖 憲治 |
自民 |
新 |
|
当 |
479,585 |
|
| 13 |
大仁田 厚 |
自民 |
新 |
|
当 |
461,021 |
|
| 14 |
大橋 巨泉 |
民主 |
新 |
|
当 |
412,354 |
|
| 15 |
大田 昌秀 |
社民 |
新 |
|
当 |
396,351 |
|
| 16 |
白川 勝彦 |
希望 |
新 |
|
|
310,010 |
|
| 17 |
小野 清子 |
自民 |
元 |
|
当 |
296,263 |
|
| 18 |
青島 幸男 |
二院 |
元 |
|
|
284,788 |
|
| 19 |
岩井 國臣 |
自民 |
前 |
|
当 |
279,121 |
|
| 20 |
橋本 聖子 |
自民 |
前 |
|
当 |
266,145 |
|
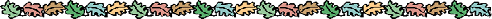
【自民党の主な支援団体】
|
候補者 |
擁立労組 |
組合員数 |
得票数 |
|
| 当選 |
高祖 憲治 |
大樹(特定郵便局長OB) |
23万人 |
47万票 |
|
| 当選 |
|
軍恩連盟 |
15万人 |
29万票 |
|
| 当選 |
岩井 国臣 |
建設業団体連合会・宅建 |
18万人 |
27万票 |
|
| 当選 |
尾辻 秀久 |
遺族政治連盟 |
11万人 |
26万票 |
|
| 当選 |
武見 敬三 |
医師政治連盟 |
9万人 |
22万票 |
|
| 当選 |
段本 幸男 |
土地改良政治連盟 |
9万人 |
20万票 |
|
| 当選 |
清水 嘉与子 |
看護連盟 |
12万人 |
17万票 |
|
| 当選 |
|
農協 |
1万人 |
16万票 |
|
| 当選 |
|
自治振興関係全逓 |
2万人 |
15万票 |
|
| 当選 |
藤井 基之 |
薬剤師 |
2万人 |
10万票 |
|
| 当選 |
中原 爽 |
歯科医師会 |
2万人 |
10万票 |
|
| 落選 |
中島 啓雄 |
ときわ会連合会(旧国鉄OB) |
7万人 |
9万票 |
|
| 落選 |
|
港湾関係 |
2万人 |
9万票 |
|
| 落選 |
|
防衛関係(自衛隊OB) |
0.1万人 |
7万票 |
|
|
|
|
|
|
|
| 自民党の支援団体の大樹(特定郵便局関連)、軍恩連盟などの候補が、組織人員を上回る票を得たことに比較すると、労組の集票力低下が目立ったことになる。 |
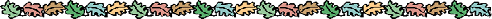
【連合参院選比例代表候補の当落】
会長・鷲尾悦也
|
候補者 |
擁立労組 |
組合員数 |
得票数 |
支援労組 |
| 当選 |
朝日 俊弘 |
自治労 |
100万人 |
21万票 |
|
| 当選 |
池口 修次 |
自動車総連 |
74万人 |
23万票 |
|
| 当選 |
若林 秀樹 |
電機連合 |
72万人 |
20万票 |
|
| 落選 |
柳沢 光美 |
ゼンセン同盟 |
58万人 |
15万票 |
|
| 落選 |
前川 忠夫 |
JAM(金属・機械製造関係労組) |
45万人 |
10万票 |
私鉄総連、化学リーグ21 |
| 当選 |
神本 美恵子 |
日教組 |
34万人 |
17万票 |
|
| 落選 |
高見 裕一 |
情報労連 |
26万人 |
15万票 |
|
| 当選 |
藤原 正司 |
電力総連 |
25万人 |
25万票 |
造船重機労連、全郵政 |
| 当選 |
伊藤 基隆 |
全逓 |
15万人 |
19万票 |
|
|
|
|
|
|
|
| 自民党の支援団体の大樹(特定郵便局関連)、軍恩連盟などの候補が、組織人員を上回る票を得たことに比較すると、労組の集票力低下が目立ったことになる。 |
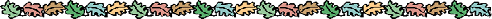
共産党の改選議席年度1995年および前回1998年との比較
1)、議席数の増減
2001年の議席結果は、1995年および1998年におけるいずれの議席数との比較でも、減退し、これは惨敗です。さらに、参議院議席は合計20に減り、衆議院に続いて、共産党としての議案提案権も失いました。次回2004年参院選では、改選15議席との比較になりますから、よほどの内外情勢変化か共産党の抜本的体質刷新がないかぎり、さらに惨敗が続くことになります。ただ、その間に、「綱領全面改定」予告の第23回大会があります。
これで、(1)2000年6月総選挙、(2)2001年6月東京都議選、(3)7月参院選と、この1年1カ月間に、日本共産党は3連続惨敗をしたことになります。常任幹部会は、その敗因として、(1)『60数種類、1億数千万枚の反共謀略ビラと公明党のビラまき部隊に負けた』、(2)『公明党が、共産党を落とすために、民主党に票を流したので負けた』(不破報告)、(3)『小泉旋風は大変なものがあり、私たちにかなりの圧力だった。それに敗れた』(7月29日夜、志位委員長、中日新聞)などとしています。これらは、すべて党外要因に惨敗原因を転嫁する、従来どおりの「宮本・不破・志位式選挙総括」スタイルです。
2)、得票数の推移
共産党は、毎回全選挙区で立候補しています。その点で、立候補しない選挙区のある他党のデータと比べて、共産党選挙結果の消長を正確に反映します。6回分データにおいて、1995年参院選までの4回は、95年比例区以外、一貫して比例区、選挙区とも減少しています。98年の結果は、過去最高の得票数です。95年比較で、比例区は2.1倍、選挙区は2.0倍という伸び率になりました。投票率14%アップ分を考慮しても、劇的な増加です。
2001年の結果は、前回98年と比べれば、選挙区340万票、比例区388万票の減少となっており、98年の共産党が、たんに“反自民無党派層の一時的受け皿”になったにすぎなかったかを示しています。しかし、95年度と比較すると、選挙区では105万票増えています。ただし、これは、2つのデータの単純比較には現われない実質的な得票数減退です。なぜなら、95年投票率44.50%、投票総数4305万票にたいして、2001年投票率56.44%、投票総数5713万票で、投票率11.94%アップにより、1408万票が全体として増えているからです。共産党の選挙区得票率が約10%なので、共産党は+140万票になっていなければなりません。それが、+105万票では、−35万票の実質的な減退と言えます。
3)、得票率の推移
6回分データの内、95年までの4回は、得票率で大きな変動はありません。得票数が一貫して減少しているのに、得票率に変動がないのは、投票率が一貫して減少しているからです。98年は、比例区14.60%、選挙区15.66%の得票率で、いずれも約1.5倍前後の伸び率になっています。この得票率自体、党史上最高です。
2001年では、95年、98年と比べて、得票率がいずれも減っています。とくに98年度との比較で見ると、この面からも、「共産党大躍進」は、政党再編・混乱過程における“一時的雨宿り現象”であったことを証明しています。
4)、組織票とその「歯止めのない党勢減退
政党選挙において、その政党の固定票、基礎票、組織票の推定値がよく問題になります。それとの比較で、浮動票の比率も話題になります。また、政党の組織の態様によって、組織政党か否かということも言われます。日本共産党と公明党は、組織政党とされています。それは、同時に、強固な、計算可能な組織票を持っているということも意味しています。ただ、組織票の内容となると、政党によって様々です。
共産党の場合は、2000年11月第22回大会時点で、(1)P(38.6万党員、4000人の党専従者、23000の支部)、(2)HN199万部(「しんぶん赤旗」日刊紙35万部と日曜版164万部)、(3)共産党議員4100人以上、(4)共産党後援会、(5)共産党系大衆団体(民青、民商、全労連、原水協、平和委員会、新婦人、民医連、学生自治会など)の5つが、組織票の内容となります。ただ、民青は、1972年の『新日和見主義「分派」事件』当時20万人から、現在2.3万人に激減しています。学生自治会も、共産党系といえるものは全国で数えるほどしかありません。
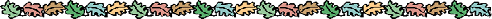
|
95年 |
98年 |
00年 |
01年 |
| 共産党 |
|
819万票 |
671万票 |
432万票 |
| 公明党 |
|
774万票 |
776万票 |
774万票 |
(寸評)
公明党はじわじわと票を伸ばし、今回は過去最高の800万票の大台を突破した。一方共産党は急降下している。
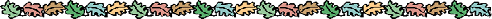



 (私論.私見)
(私論.私見)
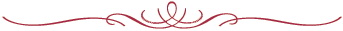
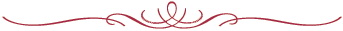
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)