| �y�u���j�h�̂Q�O�O�T�s�c�I�����v�Ƃ̑Θb�z |
�@���������u�Q�O�O�T�s�c�I�����v�́A�u��P�́@�V�w���H�����ŐV���Ɋv���I�c���`�ɒ���v�ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�v�����́A�鍑��`�̐��E�푈�A���E���Q�ւ̓˓��Ɗv���I��̋}���Ȑڋ߂̂��ƂŁA�V���Ȋv���I�c���`�̒�����J�n�����B���̗��j�I�o���_�Ƃ��Ă̍����s�c�I���A���J��p�������������đ����N�������������B
�@�v�����́A�I���������v�����^���A�v���������I�Ɉ�����V�w���H���̑S�ʓI���H�Ƃ��ē����������B�V�w���H���Ƃ́A���Y��`�^�����J���ҊK���̎��ȉ�������ł��邱�Ƃ܂��āA�}��J���ғ}�Ƃ��Č��݂���H���ł���B�v�����͂��̘H���̂��ƂɁA�K���I�J���^���̑O�i���т��A�J���ҊK���̎��̓I�l�����߂�������O�^���̔����������Ƃ�A���̔��W�̒��ŁA�I�������ɏ������Ă����Ƃ����܂������V���ȓ����ɒ��킵���̂ł���B |
 (���_�D����)�@�u���j�h�̊v���I�c���`�v�l (���_�D����)�@�u���j�h�̊v���I�c���`�v�l |
|
�@������́A���j�h���v���I�c���`�̈ʒu�Â��̉��Ŋe��I����Ɏ��g�ނ��ƂɎ^���ł���B���̓}�h���ł��Ă��Ȃ��i�K�ł̈푁������͕]������悤�B������́A�I�������͌���̌��F���ꂽ�u�n���̍Ղ�v���Ǝv���Ă���B�}�h�����̋@����������悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B������K�v�����܂�ɂ��ɂ�������ꂽ�\�N�ł������C������B����ł�������ł��x���Ȃ��B�C�Â���������n�߂�Ηǂ��̂��B�������A����̗��_�I�𖾂����Ă��˂Ȃ�܂��B�����Ƃ��A���_�l�������Ȃ������u��̗v�����Ă���K�v�Ȃ��Ƃ��܂����v�Ƃ���Ή��̕������ǂ��B�Ȃ��Ȃ�A��Ɋ����̕��������łقڐ������Ƃ���������B�������Ȃ���A���܂ł��v���_�ł����ɂ͂����Ȃ��B���������Ӗ��ŁA���h�̑��}�Ȋv���I�c���`�_�̔��\���҂��]�܂�Ă���B�Ƃ͂����A���h��������ׂ��͎̂���̋Z�ł��낤�B����́A����܂œ��}���l�����Ă��闝�_�y�ъ������̂̍�����h���Ԃ鎩�Ȕᔻ�I���ؔ����ɂׂ͈����Ȃ�����ł���B�������A�����ɓ��u�I����ɟ�����̂ł���Ίl��������ƍl����B�H���͂����W�O�U�O������̂ŁA�������҂݂̂������ȓ������o�����̂�����B�v����ɓ}�I�\�͂�����Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@���h�̎Q�l�ɋ�����ׂɁA������̊v���I�c���`�_��掦���Ă����B������̂���͖����ł���B�Ȃ��A�I���Ɏ��g�ނׂ����A���̂悤�Ȍ����ɂȂ�B
�@����́A�哌���푈�̔s�k�̌��ʁA��O�I���͂̈����������t��������A����ɗ��j�̙F��ɂ���Ďj�㖢�\�L�̃v���Љ��`�I�@�������������ꂽ����ł���B������́A��㒁�������̂悤�ɊŘB����͐��f�g�p���͂ɂ��哱���ꂽ���A����́A�����{�̐w�c��荞�݂�����ĕă\���삯�������A�Ē邪����̍�Ƃ��ă\�A�M�ȏ�̊J���I�����`�@���������Ƃ����u���j�̙F��v�ɕ����Ă���B���ɂ����R�����X���낤���A�ő�̗v���́u�Ē�ɂ����{�̎�荞�݁v�헪�Ɋ�Â����̂ł���A������A���ƃ��`�ŗႦ��Ȃ�A������ł������B���ʓI�ɁA�����{�͎j�㏉�߂Ẵv���Љ��`�I�@�؍��ƂɂȂ����B���̊ϓ_���~�����B
�@�t������A�����{�̖����`�I�@�����́A����杂Ɋ�Â��A�����J�������`�Ȃ���̂Ƃ��̌�̕č��ɓZ�������l�I�V�I�j�Y���Ȃ���̂Ƃ�����ȍR���������Ē�������̂����̑O�҂܂茚��杂Ɋ�Â��A�����J�������`���̃C�j�V�A�`�u�ɂ�蓱�����ꂽ�ƊŘׂ��ł͂Ȃ��낤���B�����A�Ē���̓l�I�V�I�j�Y���h�ɂ�萧������Ă��܂����B���̃l�I�V�I�j�Y���h���A�����{�̖����`�I�@���������ꂩ����ς��錛�@�����^�����w�}���Ă���̂́A���̊ϓ_�ɗ����Ƃɂ�����������ł��낤�B
�@�����������x�y�і@�̌n���l�������ȏ�A���{�l����O�́A���̂��܂����̙F���������������ׂ��ł������B�@�����͓������ꂽ�Ƃ͂����꒩��[�ɂ͒蒅���Ȃ��B�P���Ǝ�����ʂ��đ̓�����ׂ��ł��낤�B������O�́A�������錾�ꂱ���l�����Ȃ��������A���g�ɂ��݂Đ����{�̖����`�I�@�����̗L����m���Ă����B�̂ɁA���̎������Ɉ��Ċz�Ɋ����Č����ɓ������B�u�����{�̊�ՓI�����v�̔w�i�ɂ������G�C�g�X�͂���ł���A���̗v�f���Ă͌��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@��㍶�h�^���̌��_�́A�����{���v���Љ��`�I�@�؍��ƂƂ��Ĉʒu�Â����Ȃ����Ƃ���ɂ���B����w�i�ʂ��ʂ܂܁A�}���N�X��`�̋��{������ʂ�ɓK�p���A���Ƌy�ь��͔ᔻ����K����̂������ƐS���A�ׂɔᔻ�ɔM�����߂��Ă������炢������B�����A�}���N�X�[�G���Q���X�������{�͂����Ȃ�A�v���Љ��`�I�@�؍��ƂƂ��Ă���������]�����A����������ƂƂ��čX�Ȃ�Љ��`�����w�j�����߂��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�����������A��㍶�h�^���̐V�������͂��ꂼ�ꂪ�Η������Ƃ͂������ʂ��āA�u���Y��`�҂̐錾�v�����A���ۂɖ𗧂��Ȃ��悤���̉��i�����^���ɔP���Ȃ��čs�����B�̂ɁA�����ł��낤�Ƃ������قǃ}���N�X��`�̐^�����痣��A���̋��ߍ��킹��ׂ��k�ُp���K�n�����Ă������ƂɂȂ����B
�@������������ɂ����āA�u���Y��`�҂̐錾�v�̐����܂��A���������ɉ��p���čs�����̂́A���ƐV������������قǔᔻ���������A�ꎞ�͐��ێ�{���Ƃ���搉̂��������^�}�����}���n�g�h�ł���A����ƘA�t�������A���A�w�̖ʁX�ł������B���̎���̓��{�́A��㕜�����獂�x�o�ϐ����A�X�ɂ��̐�ւƋ삯�����悤�Ƃ��Ă����B����͐��E�j����Ӗڂ��ׂ��j���ł���悤�Ɏv����B
�@���̉h�_�́A�P�X�V�O�N��̓c���p�h�����̓o��Œ��_���}���A���̎��r�Ƌ��ɂ��ڂ�ł������ƂɂȂ�B�����ēo�ꂵ���̂��^�J�h�n�̎O�[���c�����ł��������A�n�g�h�̈А��Ȃ������A�啽�[��ؐ����ŃC�j�V�A�`�u��D�҂����B�������A�P�X�W�O�N��ɓ��蒆�]�������ƂȂ��Ĉȗ��A��{�I�Ƀn�g�h�͉e���͂��������B�ȍ~�A�ڂ܂��邵���قǂɐ�����オ�s��ꂽ���̂̎���Ƀ^�J�h�̃����T�C�h�ƂȂ�A�Q�O�O�O�N���ȍ~�̓^�J�h�n�̐X�[��������������x�z���ւ��Ă���B
�@���̊Ԃ̎Ћ��^��������Ȃ��̈ꌾ�Ős����B���̎Љ�I������[���������邱�ƂȂ��A�Љ�}�͎���Ɏ��{�̓z��̓��ւƓ�v����A���Y�}�͂��ꂪ���Y�}���Ƃ����قǐ^���̗}���^���Ō��ł�^�������Ă���B���̊ԁA�V���������܂ꂽ���A�ᔻ�Ɣ��������`�ł���A�����{�̃v���Љ��`�I�@�؍��ƌ������ׂ̈ɗL�v�Ȃ��Ƃ����Ă��Ȃ��B����Ό��ꍶ���Ƃ��Ċϋq������U���Ċ�Ԃ��炢�̉^�������ׂ����Ă��Ȃ������B
�@���A���{���h�^���ɗv�]����Ă���̂́A���̎�������Ō�̋ǖʂŁA������x�����{�̓����܂��A�����i�삵�X�ɓ�����[�߁A���̐�ւƓW�]���Ă������Ƃł͂Ȃ��낤���B�Ћ��^�������{�̐l����O�ɑS����������Ă���ܕ��A�{���̍����^�������R�o�ꂳ���邱�Ƃ����`�]�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B
�@������́A���������ϓ_����A���j�h���Ћ��^���ɕς��V���h�^���̎�̂Ƃ��ċ��肾���Ă��邱�ƂɎ^���ł���B�������Ȃ���A���h��������j�ς̔@���Ɉʒu�Â��������Ƃ͂قڂł��Ȃ��ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A���̗��_������Ԃ��Ă�������ł���B���̉ߋ��̉ו��͑傫���B
�@�������A���_�������H�̚k�o�̕������������Ƃ������B���̏��ꂽ�����𗊂�ɓ��������Ă������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B�t������A���}���P�Ƃʼn^�����x���҂��W�߂�ɂ͗]��ɂ����ڂ��߂���B�������Ƃ����t���N�V�������_�ł͂Ȃ����`�ʂ�̋���������_�ō��h�^�������W���A�n�����獑���܂ł̑S���I�I���ɏ��o�����Ƃ����҂��Ă���B���̂Ƃ���̓��[���ቺ�Ŏ�����鐭�����S���o������N���܂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q
|
�@���ɁA�s�c�I�ɉ����āu�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�v��D��ۑ�Ƃ������Ƃɕt�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���̓����ɂ����āA�u�����v���ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~���A���t�́u���̊ہE�N����v����̌p���E���W�Ƃ��āA05�N����̐��ۂ���������ΓI�ۑ�Ƃ��ĉ����グ��ꂽ�B
�@�u�����v���ȏ���Αj�~�́A�����̓���E�����c�A�t�@�V�X�g�Ό��̐푈�Ɩ��c���E�J�g��̍U���ƍł��s���Ό����锒�M�I�ȊK������I�ۑ�ƂȂ����B���ʂ̂S��Y�ʂ̌���I�U�h�̋A���i�������j�������ɂ��������B
�@���̓s�c�I������A�u�����v���ȏ��j�~�̑�O�����̔����ƈ�̓I�ɂ����Ƃ��Ă�������I�����́A�S�}�̈�ۂƂȂ��������N�����������B
�@�����ɂU�E�Q���ȏ��W��A�U�E12����W��̍��g����A�U�E22����ψ�����ł̐�����������͂���̑�ȑ�O�I���N���A�s�c�I����̂ǐ^�ŁA���|�I�Ɏ������ꂽ�B�}�̌��N�Ƒ�O�I���N���������āA�u�����v���ȏ��j�~�̋���Ȃ��˂肪�J�n���ꂽ�̂ł���B |
 (���_�D����)�@�u�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�^���v�l (���_�D����)�@�u�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�^���v�l |
�@������́A���j�h���u�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�^���v��D��ۑ�ɂ������Ƃ�]�����Ȃ��B�Ȃ�قǒn���I�Ƃ������ƂŁA�n�����L�̉ۑ�ɐݒ肵���̂����m��Ȃ��B�������A�n���I���Ɖ]���ǂ������ۑ�ɐG���ׂ��ł���A�����ƂȂ�u�X�g�b�v����A�Ό��@��������̌��ʂ�i����v�Ƃł��ݒ肵�A�f���Ƃ����|�t�^���ɂ������g�ނׂ��������̂ł͂Ȃ��낤���B�X�ɂ́A���[�s���͂��A���R�̔@�������������i������Ȃ�A����A�Ό��̎�Ґ؎̂Đ�����e�N���ׂ��������̂ł͂Ȃ��낤���B���R�A�D��I�R�������������e���A���q���̃C���N����̓P�ނ����i���˂Ȃ�Ȃ������B��́A���̊Ԃ��̎�̂��Ƃɂ�����ŋ����g���Ă���̂��A�X�Ɏg���悤�Ƃ��Ă���̂��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł���Ǝv����B
�@�u�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�^���v�́A�����炻���퓬�I�Ɍ���ʂ����Ƃ���ŁA�{����g�̂���ł����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�u��O�B�̋��ȏ������A������ł̍̑���ڎw���^���v�����ϋɓI�Ȃ��̂�����ł���B���炻��������ɂ����ȏ��̑�j�~��ڎw���̂́A�Ћ��^���̓�Ԑ����ł����Ȃ��낤�B
�@������͂��̂悤�ɍl���Ă���B�l����O�̐^�ɖ]��ł���n���Ƃ͈Ⴄ�Ƃ���ł�����͂�ł݂Ă��������Ȃ����낤�B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�X�Ɏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�����̓����̓y��Ɗ�b�ɂ́A��`�E��̊v�����������B�u�����v���ȏ��j�~���A�t�@�V�X�g�Ό��œ|�E�鍑��`�œ|�Ƃ��Ċт��A���̓�����������S�̂̎��ԂƋ�Ԃ����|�I�Ɋl������Ƃ����v���I�Ȑ�`�E��킪�A�͂̌��蓬�������ꂽ�̂��B
�@����͐펞���̑I�������̗l����O��I�ɕ�������ɂ������B����͒��ړI�ɂ́A���}�ԓ}�h�����̋�O�̌����Ƃ��Č��ꂽ�B�X���Ȃǂł́u�����v�h�A�E�����͂Ƃ̌��ˁA�Ό���h��Ό��^�}�̑S�������}�̖W�Q�A���{���Y�}�X�^�[������`�̂ނ������̓G�A�E���Ж����u�s���h�v�ɂ���O���N�̐����Ȃǂ̑唽�����������ꂽ�B�����̂������ɂ����āA�S�}�͂��Ă�͂��ӂ肵�ڂ�A�s���̓������т����B�����S��ŁA�斯�A�x���҂ƌł��A�т��āA�����̂Ȃ����������ʂ����̂ł���B
|
 (���_�D����)�@�u�I���핱���^���v�l (���_�D����)�@�u�I���핱���^���v�l |
�@���ł������N�����A�育�������L��A����������B���̎�̂��Ƃ����^���Ă��邾���ł��邩�炵�Ă�����͕������������ł���B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�����ŏ��߂đI�����ʂɐG��A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@���ʂ́A���I�������Ƃ邱�Ƃ��ł����A�V�X�V�V�[�i10�ʁj�̌������s�k�ƂȂ����B�����V�X�V�V�[�����A�u�����v���ȏ���Αj�~�ƁA���E������̂Ăւ̓{��̌��N�ł���B���̂��������̂Ȃ���[��[�𓊂��A���N�����斯�݂̂Ȃ���́A��Ώ����ւ̊ɂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���̒ɋ�Ȍ�����^�������猩�����A���̔s�k�����������߂ɁA�Ȃ�Ƃ��Ă��A�����s�c�I�Ōf�����u�����v���ȏ��̐����ł̍̑����Αj�~���A����ɉ��E�����̐�̂Ă�i�߂�t�@�V�X�g�Ό��m����ǂ��߁A���̗͂������āA05�N����㔼��̏����������đ����N���邱�Ƃ��A�v�����͌ł����ӂ������B |
 (���_�D����)�@�u�I�����ʕ��́v�l (���_�D����)�@�u�I�����ʕ��́v�l |
�@�{���Ȃ�A�`���ŏq�ׂ�ׂ��Ƃ���A���̉���ŕt�������I�ɐG��Ă���̂��C�ɂ���Ȃ��B�������A�u�������s�k�v�ƔF�߁A�u���̒ɋ�Ȍ�����^�������猩�����A���̔s�k�����������߂ɉ]�X�v�Ƃ���Ƃ��낪�����ŗǂ��B�����̂悤���k�ق�M�����A���̂悤�Ɏ~�߁A���̃X�e�b�v�����ׂ����낤�B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
|
�@�u��Q�́@�����ȏ��j�~��i���������̐������v�ŁA�`���A�u�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�����̈Ӌ`�v�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���ɁA�������s�k����������Ό�������قǁA�ɂ�������炸����ꂪ�����s�c�I�̊�{���j�ɁA�u�����v���ȏ��Ƃ̑S�ʓI����I�Ό��𐘂��ē��������f�́A���|�I�ɐ����������B
�@�u�����v���ȏ��̑��̍U���́A���邪���E�푈�֓˓����邽�߂ɁA�鍑��`�u���W���A�W�[�Ɛ����ψ���A����E����Ɠ��{�o�c�A�E���c�A�����Ă��̐敺�Ƃ��Ă̓s�m���Ό��炪�A�K���ӎu���I�ɖ��W�����ďP���������Ă�������ׂ��唽�v���ł���B
�@���̑��S����������U�����A�����I���Ȃ݂̓s�c�I�Ƃ�����������̏�ŁA�\�I���A�Ό����邱�Ƃ́A�J���ҊK���l���̐푈��Δ��̊K���ӎu�Ɛ����E��������邠�܂�ɂ����R�ȓ����ł������B |
 (���_�D����)�@�u�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�����̈Ӌ`�v�l (���_�D����)�@�u�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�����̈Ӌ`�v�l |
�@������͊��ɏq�ׂ��悤�ɁA�u�����ȏ��̐�����ł̍̑��Αj�~�����v�𐭍����ۑ�ɂ������Ƃɕt���ԈႢ�Ǝv���Ă���B�u���|�I�ɐ����������v�Ɖ]�����A���d�������Ă͂��Ȃ����낤���B���ɁA�v��u���̑��S����������U�����A�����I���Ȃ݂̓s�c�I�Ƃ�����������̏�ŁA�\�I���A�Ό����邱�Ƃ́A���܂�ɂ����R�ȓ����ł������v�Ɖ]�����A���̌��t�́A�u�����œ|�v���f�������̃Z���t�ł��낤�B����炷��ւ��Ă���悤�Ɏv����B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�����āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@
���������āA�u�����v���ȏ��ɑ����O�I�������A�S�N�O�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ�����I���N�ƂȂ����̂ł���B�{��͒n�̒ꂩ��킫�N�������B���w���A���Z���A�N�݂̂��݂��������N�A�ی�҂⏗���̐X�Ƃ������сA����J���҂��n�߂Ƃ����J���ҊK���̂�ނɂ�܂�ʓ{��̂��Ԃ��A����҂̑̂��ӂ�킹���i���Ȃǂ̊����I���N���A�O�ځi�ق��͂��j�Ƃ��Ċ����N�������B
�@�����A���̑�O�^���̍L�͂ŋ}���Ȋg����A����ɋ}���ɏW�[�ɓ]���関�]�L�i�݂����j�̒���ɂ����āA�������Ƃ����A��O�^���̊g����}���ɓ}�h�I���\���҂ւ̓��[�s���ɔ��W������Ƃ����ۑ�ɂ����āA�}�ƊK���̊W�ɂ�����{���I�Ȕ���ꂽ�B |
 (���_�D����)�@�u���Ȃ̕فv�l (���_�D����)�@�u���Ȃ̕فv�l |
�@�u��O�^���̊g����}���ɓ}�h�I���\���҂ւ̓��[�s���ɔ��W������Ƃ����ۑ�ɂ����āA�}�ƊK���̊W�ɂ�����{���I�Ȕ���ꂽ�v�Ɣ��Ȃ��Ă��邪�A�]����肭�˂������������D���Ȃ炵���B�v����ɁA�u�[�Ɍ��т��Ȃ������v���Ƃ��]�������̂��낤���A�l����O�͕�����Ղ�����̗ǂ��̂��D�ށB
�@����͂Ƃ������A�u�Ȃ��J�[�Ɍ��т��Ȃ��̂��A���ѕt����ɂ͉����ǂ�����Ηǂ��̂��v�͑I����̗v���ł���B�����b���͓��h������ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ낤�B����ŗǂ��̂��Ǝv���B�Ћ����Ƃ͂܂��Ⴄ�[�̎�����҂ݏo���Ăق����Ǝv���B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�����āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@����ɓ���x�z�K���́A�u�����v���ȏ��ւ̑唽�����A�s�c�I�ł̒��J�쏟���ւƔ��W���Ă������ƂɎ��ʂقNj��|�����B����䂦���J�쎁�ɑ��āA�S�}�h���P��������Ƃ����P��12�̋�O�̌��ˍ\���ƂȂ����B
�@�u�����v�h�́A���J��Ԃ��̂��߂Ɂu�ق��E���v�������������B�I�Ր�ɂ����ẮA�����x�z�}�h���A���̊�ՓI�ȑg�D�͂Ǝx�z�K���̒n��I�����͂���_�A���J�엎�Ƃ��ɑ����������B���̐��}�ԓ}�h�����ɂ����邷���܂����荇���������ɓ��������A�K���̔������s�������A�����ł��Ԃ���O�^���̑g�D�����ǂ����܂łɂ͎���Ȃ������B
�@���錠�́E�x�����́A���̐펞���̑I�������̑O�i�ɋ��|���A�f�b�`�����ߕ߂�s���{���Ȃǂ��ĂȂ���O�^�̑�e���������Ă����B�����́A���̍U�������S�ɕ��ӂ����B |
 (���_�D����)�@�u�������͍U���v�l (���_�D����)�@�u�������͍U���v�l |
�@�^�Ɋv���}�h�Ȃ�A���͔h�̒e���͂��ĉ�邱�Ƃ��낤�B��O�̓����ɑ��鋥�\�Ȓe���܂���Ύ����ł��낤�B���͗L�����Ƃɍ��ƌ��͂͐�O�قǂ̒e���ׂ͈����Ȃ��B���̂��Ƃt�I�ɓ��܂��A�����������E���A���́A������������̂��̋C�T���~�����B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�����āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���ɁA���̂悤�ɐ펞�^�I���ɂ����āA���Ă�͂��o������A�x�z�K����������}�Ɍށi���j���āA�S���������ׂďP���������Ă��Ȃ�������͂˕Ԃ��A�I���Ƃ������ŏ������邱�Ƃ́A�����ɂ͂Ƃ��Ă��s�\�Ȃ̂��B�f���Ĕۂł���B
�@�ЂƂ́A�I��������������ȑ�O�^���ł���A����͓}�h�I���Ƃ�����i�ƃ��x���A�b�v������O�^���ł���A�Ƃ������Ƃł���B���������āA������O�^���̔��W���I���̏����Ɍ��т��Ȃ��Ƃ���A����͑�O�^���̔������܂��s�\���ł���A�Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�@���܂ЂƂ́A�����̐V���ɊJ�n�����I�������́A�����܂ł��������Ƃ������Ƃ��B����͎n�߂�����̓����̕ǂł���A�����ł̕s�\�����A���n���A�Â��ł���B�����炱�������́A���̓_�ɂ��āA���i�ɒɋ�ɂ����肾���K�v������B�����������ɁA�K�������̓S�ŁA������ł��b���グ�邱�Ƃ̂ł���ۑ肾�A�Ƃ������Ƃł���B
�@���ɕ��m�h�Ƃ̓����ɂ��āA�����͍���̓����ŁA���́u�s���h�v�Ƃ������݂̔����I�������A���m�ɊK���I�ɂ��ނ��Ƃ��ł����B�����Ă��́u�ǁv�����A�K���I�J���^���̔��W�ɂƂ��Ă̑j�Q���ł���A���̓˔j�̒��ɁA�V�w���H���̗��j�I���W�̓�������̂��B |
 (���_�D����)�@�u�I���̕ǁv�l (���_�D����)�@�u�I���̕ǁv�l |
�@�u�I���̕ǁv�ɂ��Č���Ă��邪�A�u�����̐V���ɊJ�n�����I�������́A�����܂ł��������Ƃ������Ƃ��B����͎n�߂�����̓����̕ǂł���A�����ł̕s�\�����A���n���A�Â��ł���B�����炱�������́A���̓_�ɂ��āA���i�ɒɋ�ɂ����肾���K�v������v�ƔF�����Ă���Ȃ炻��ŗǂ��낤�B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�����āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@�����X�^�[������`�́A��X�I�ȉߌ��h�L�����y�[�����A�u�����v�h��x�@���͂ƌ��ԈႤ����ɍs�����B������܂���������͑傫�ȋt���ɂȂ����B���������́u�ߌ��h�L�����y�[���v�́A�u���̎���ɂ����āA�ߌ��h�ʼn��������v�Ƃ����ꌾ�ŁA���|�I�ɂ͂˕Ԃ����Ƃ��ł���̂ł���B����ނ���u�����v���ȏ��̍U�����@�ɂ���鍑��`�ɑ��Ắu����̉ߌ��h�v���������Ȃ��̂ł���B |
 (���_�D����)�@�u�����X�^�[������`�v�l (���_�D����)�@�u�����X�^�[������`�v�l |
�@�������u�����X�^�[������`�v�Ƃ��Ĕᔻ����̂͊v�����̊ϓ_�ł���B������́A����͔��ʋK��ł����Ȃ��Ǝv���Ă���B������̖ʂ́A�����͂P�X�T�T�N�̘Z�S���ȗ��}���������ǃX�p�C�h�ɑ����Ă���A���h�^���ɗL�Q�Ȏw������ɔM�����Ă���ƂƂ������Ƃł���B����āA�u�����Ǝ��ۂ��Ⴄ�����̍��h�y�I�^���v�ɑ�����ʂ̎��_�Ɣᔻ�̊ϓ_�������˂Ȃ�Ȃ��B���̊ϓ_�Ȃ��u�����X�^�[������`�v�ᔻ�͍��ƂȂ��Ă͂ނ���L�Q�ł���B���̊ϓ_���~�����B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�����āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@��O�ɁA���_�I�ɂ́A���̂悤�ɐV�w���H���̂��ƂŁA�܂������V���ȑI�������ɒ��킵�����Ƃ́A����ȊO�ɑI���̂Ȃ������ł������B
�@�s�c�I��J���ҊK���̎��̓I�l���ɂ���O�^���̔����������܂ł��O��I�Ɋт��ē������Ƃ́A�B�ꖳ��̓������ł������A�Ƃ������Ƃ��B����͓s�c�I�Ƃ�������ȑI�����A����̓}�̗͗ʂ܂��ď����������Ƃ���Ȃ�A�J���҂���O�^���̒S����ƂȂ��āA���ȉ���I�^�����I�ɔ��W������ȊO�ɂȂ��B�ꌾ�Ō����A�J���ҊK���̍L�͂Ȏ��ȉ���I���N�ɓO��I�ɗ��r�����I����������낤�A�Ƃ������Ƃ��B����́A�]���̖���I������̑�]���ł���A�����̓����ł͂Ȃ������B����́A����܂ł̖���Ώۂ���蔲���厖�ɂ����A�V���ɘJ���ґw��傫���l�����悤�Ƃ��铬���ł���B�����Ă��̓����́A���ɂ߂��܂������ʂ��l�������B
�@�펞���K�������ւ̓˓��̂��ƂŁA����̊K��������ōU����ł��j�铬���Ɨ͂́A�J���ҊK���̊l�����Ƃ�������O�����̔����ł���A�s�c�I��O�ꂵ����O�^���ŏ��������ȊO�ɂȂ��Ƃ������Ƃł������B
�@�������A�u�����v���ȏ������A�ł��������K��������ōU���ł���B05�N����̊j�S�I�ۑ�́A�鍑��`�̂��̍U���ɑ��āA�}�ƊK���������c�邱�Ƃł���B�����́A�s�c�I�̒n������A11���J���ґ����N�֗E���˂��i�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
 (���_�D����)�@�u�v���I�c���`�v�l (���_�D����)�@�u�v���I�c���`�v�l |
�@������ɂ���A���}�́u�v���I�c���`�v�_���\�z���A�S�}�I�ӎv��v���˂Ȃ�܂��B����܂ŏq�ׂĂ�������������Ɛ��荇�킹���ė~�����Ƃ���ł�����B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
|
�@�u��R�́@�푈�ƊK��������ł̑唽�v���������Ԃ����v�ŁA�`���A�u�s�c�I�̈Ӌ`�v�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u�����v���ȏ��ƑΌ������O�^���Ɠs�c�I����̈�̓I�����́A�����A����I�n�����J���Ă���B
�@�u�����v���ȏ��U���́A���̔��v�����ѓO�����Ȃ�A���K�������͂����ǂ���ɊD���i��������j�ɋA���A�J���g����K���I�ȑ��݂���ł���A����ɂ���āA�����ȍ~�̏�A���Ȃ킿�������ɐ푈�˓����\�ƂȂ��Ă�������}����B����������Ȕ��v���ł���Ȃ�A������O�ɂ��āA����Ӗ��ł͉�������C�ɉ\�Ƃ�������ȏ�̔��v���U���Ȃ̂��B����ɑ��āA�s�c�I�̏���O�^���̔����̃e�R�ɂ��������ɂ�����u�����v���ȏ���Αj�~�̓����́A���̋���Ȕ��v�����A����I�ɉ����Ԃ������ƂȂ����̂��B
�@�ЂƂ͑�O�^���̔����ɂƂ��ĕs���Ȏ���I�E���ȉ���I���N�Ƃ��̉^���̂��A�傫�����܂�Ă���B�S���I�ȋ��ȏ������̎i�ߓ��̓o�ꂾ�B
�@���܂ЂƂ́A�u�����v���ȏ��U���̌��������A�s�c�I�Ƃ�����D�̐��Ō}�������ē��������Ƃł���B���̍U�����A�s�c�I����Ƃ����X�P�[���̖I�N���ƏW�����������������Ō}�����������Ƃ́A���Ɍ���I�ȈӋ`������B
�@���̑�O�̎���I���N�̈��|�I���܂�ƁA�s�c�I�Ƃ��������I���M���Ɠ����̐������A�u�����v���ȏ��ւ̈�唽�������g�������ƌ�����̂��B |
 (���_�D����)�@�u�s�c�I�̈Ӌ`�v�l (���_�D����)�@�u�s�c�I�̈Ӌ`�v�l |
�@������ɂ���A���}�́u�I�������v�_���\�z���A�S�}�I�ӎv��v���˂Ȃ�܂��B����܂ŏq�ׂĂ�������������Ɛ��荇�킹���ė~�����Ƃ���ł�����B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�����Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���̂悤�Ȓn���܂��āA�����́A�܂��ɂ��ꂩ��ł���B
�@�u�����v���ȏ��̑唽�v���ł̓G�̑_���́A�����Ő��ʓ˔j���A����ׂ������Ŏ�s�E������Ȋ����邱�Ƃł������B�����A���̐����ŋ��͂ȑj�~�������Ă��邱�Ƃ��A���̃t�@�V�X�g�^���̑S�ʓI���������肬��őj��ł���B
�@���錠�͒������u�����v���ȏ��̑����s�̃V�t�g��~���A�G�̑������́u�K������v��ł��Ă���B����ɑ��āA�����_�ɑS���A�S�Y�ʁA�S����Ɂu�����v���ȏ��j�~�̑�^���������N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���̍ہA�u�����v��̔��؏G���́w�����̎v�z�x��A�t�@�V�X�g�Ό��̌����A�s����O��I�ɔᔻ�E�e�N���邱�Ƃł���B���ɔ��́A�u�����Q�q�v�Ɩ��c���͈�̂ł���ƌ����āA�T�b�`���[���w�ׂƌ����Ă���B�T�b�`���[�́A���c���������č��Ǝ�`�A���Ǝ���̐��_�v�����s���A���c���Ƃ���Ɂu������v�v�̒��ō������͂�o�ł����A�Ƃق߂��₵�Ă���B���̃T�b�`���[���s�������Ƃ͉����B�u�r�N�g���A����i�P�W�R�V�`�P�X�O�P�N�j�ɋA��v���X���[�K���ɂ��āA�S���Ȃǂ�����Y�Ƃ̖��c�����s���A�̓ƍٌ��͂����߁A�Y�z�X�g���C�L��O��I�ɒe�����A�������̂āA�j�������s���A�u�̓y����鎩�q�푈�v�Ə̂��ăA���[���`���ɐN���푈�i�t�H�[�N�����h�푈�j�����������B����ɘJ���҂́u�K���זE�v���ƈ��l�i�����j�𓊂����āA����̖��c����i�ߘJ���g������������̂��B |
 (���_�D����)�@�u�����ȏ��̑��̈Ӌ`�v�l (���_�D����)�@�u�����ȏ��̑��̈Ӌ`�v�l |
�@�����͔q�����Ă����B���c���ᔻ�_�����_������˂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
�@�����Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�����ďd��Ȃ̂́A�����A�T�b�`���[�������グ�锪��u�����v�h�A����Ƀt�@�V�X�g�Ό��Ɍ���Ȃ���̉����Ă���̂��A���钆���̏���E���c��ł���Ƃ������Ƃł���B
�@�����A����́A���X�i���悤�j�ɖ����Q�q�U�����d�|���Ă���B�����_�ЂƂ͗��j�I�ɂ�����̐N���푈�œV�c�̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ��u��сv�Ƃ�����푈�����̐_�Ђł���B�u�����v���ȏ�������ƈ�̂��B
�@�����Ă��ɏ���́A�x�z�K�������̕�����������X�����c���̏O�@�̌������s�����B����͎x�z�K���⎩���}���ɂ�������I�Ȉ�̂��̂���́E��|���悤�Ƃ������̂ł���A�푈�Ɩ��c���U���̖{�i�I�����ł���B
�@���{�o�c�A�́A�S�E19�ȂǂŁA�X�����c�����n�߂Ƃ��閯�c�����J�g�j��A�Љ�ۏᐧ�x��́A�ւ̌��͂̏W���Ȃǂ�����ł���B���ۂɁu�������j�X�v�i�U�E21�t�c����j�́A�u�����P�`�Q�N�̍\�����v�����ۂ����߂�v�ƌ������Ă���B
�@�܂��ɂ��̂P�`�Q�N�ŁA���c���i�J�g�j��j�Ɓu�����v���ȏ�����̉������K��������ōU���������āA�푈�˓��ւ̍��ƁE�Љ�����낤�Ƃ����̂��B |
 (���_�D����)�@�u�����_�v�l (���_�D����)�@�u�����_�v�l |
�@�������q���������B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
|
�@�u��S�́@�K�������̕���E�����ƊJ���ꂽ11���ւ̓��v�ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�s�c�I�̌��ʂ́A����ł́u�����v���ȏ��U�����[�Ƃ��閧�W�������������������A�����ł͊K�������̊�@�ƕ���E�����𐄂��i�߂Ă���B
�@���[���̒ቺ�́A�u���W���A�c��x�Ƃ��̕��s�ւ̐�]�E���]�Ɠ{�肪�[�܂��Ă��邱�Ƃ������Ă���B����͊K���I��@�����J���ҊK���̒��ɏ[�����A���Ȃ����̓{�肪���������ꂸ�ɉQ�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B�v�����^���A�v�����A�t�@�V�X�g���v�����̕���ƌ��˂��A���ꂩ��{�i�I�Ɏn�܂�A�������Ă����̂��B
�@�u�����v���ȏ����߂��錈��͂��ꂩ��ł���B����͊��S�ɁA11���J���ґ����N�������������Ɉ����p����A�傫�����W���悤�Ƃ��Ă���B�s�c�I���킪�A�u�����v���ȏ��j�~����Ƃ����傫���A�������������ē���ꂽ���Ƃɂ���āA�傫��11���ւ̌��H����J���ꂽ�̂��B
�@����͂܂����ɁA�u�����v���ȏ��j�~�E�Ό��œ|�̓��������A�푈�Ɩ��c���i�J�g�j��j�ƑΌ�����K���I�J���^���̍Đ��̓������̂��̂ł���A�Ƃ������Ƃł���B
�@�u�����v���ȏ��j�~����́A�u���̊ہE�N����v��������S�Ɍp���E���W�����A���J�𒆎��Ƃ���S��Y�ʌ���̔��W������ɉ����J���Ă���B�u�����v���ȏ��ɂ����ɑΌ����邩�ɁA�S��Y�ʂƑS�Y�ʂŏ���������������Ƃ������Ƃł���B
�@���ɁA�����s�c�I�ɂ���ď\���ɓ˔j�ł��Ȃ������傫�ȁu�ǁv�́A������11���ւ̖��]�̌��W��j�ށu�ǁv�ł�����A�Ƃ������Ƃł���B�t�Ɍ����A�u�����v���ȏ��j�~��O��I�ɓ������ƂŁA���̕ǂ̓˔j���\�ł���B���ɓ����̔�����ł��j��A���m�h�̘J���^���ւ̐�]�Ɠ��S���̂肱���铹�������ɂ���B����͓��ɓ����s�̘J���^���ɂƂ��Ď����I�ł���B
�@��O�ɁA�����́u�����v���ȏ��j�~�����́A���ۘA�т̓�����傫�����W�����Ă���B��N11���ȗ��̍��ۘA�т́A�u�����v���ȏ��ƑΌ����Ă��������̒��ŁA���ɓ��ؘJ���҂̘A�тŁA����ɑ傫����܂����B
�@��l�ɁA�V�w���H���̂��ƂɑS���̓}���c�����A��ۂƂȂ��āu�����v���ȏ���Αj�~�̑�O�^����n���������Ƃɂ���āA�V�w���H���̖����̔��W�̓��������ɂ������Ƃ��m�F�������B
�@��܂ɁA�V������̏d�含�ł���B�u�����v���ȏ��j�~�̂V�E24������W���A�V�E27���W�E�R�̐l�Ԃ̍���s���֑����N���悤�B�J�n���ꂽ�����~�ߑi�ׂ͗��j�I��ٔ������ł���B
�@�S��Y�ʌ��킪�A�V�E18�����g����擪�ɂ��悢��匈��ɓ˓����Ă���B����ɂV�����S���킪�d��ł���B���ɂV�E15�̓���J�쉹�S���W��́A�P�O�S�V�������̕s���̐w�`���m������d��ȓ����ł���B�܂����J��t�͉^�]���S�s���Ƒg�D�g��̓������߂����đ匈��ɓ˓����Ă���B
�@����ɂW�E�U�q���V�}�|�W�E�X�i�K�T�L��s���Ɛ��60�N�̂W�E15�W��́A11���ւ̌���I�����ۂ��Ȃ������ł���B
�@���d�ߍU�h�́A���悢�搳�O��ł���B�O���˓���������ɓ˓����Ă���B
�@�Ċ��ꎞ���J���p����ɏ����������B����ɋ@�֎��g�哬���𐄐i���悤�B
�@�V�E31�����v�����W��ɑ����W���听�������悤�B |
 (���_�D����)�@�u�������v�l (���_�D����)�@�u�������v�l |
�@�������q���������B
�@�Q�O�O�T�D�V�D�P�P���@������q |
|
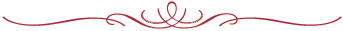
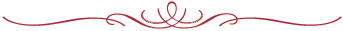
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)