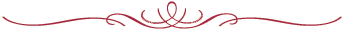
| 議員定数考 |
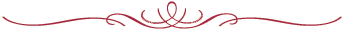
(最新見直し2010.11.22日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、議員定数について愚考しておく。 2010.11.8日 れんだいこ拝 |
| Re::れんだいこのカンテラ時評850 | れんだいこ | 2010/11/08 |
| 【石にしがみついてもなどと云い始めたらオワ考】
2010.11.8日、久しぶりに議員定数問題に言及して見る。と云うのも、国会質疑を聞きながら思った。自民党のシオニスタンと民主党のシオニスタン同盟が、互いに見解の相違はないと何度もエールを交換しながら遣り取りしている。こういう芝居ほど臭いものはない。嫌々ながら少し聞いてみた。何のことはない、小沢の徹底訴追、日中離間、日露離間、日米同盟進化、消費税等の増税、国債累積債務対応無能化路線で阿吽の呼吸で一致しながら、締りのない遣り取りを通じて衆院解散に持って行こうとしている。菅がボロボロになればなるほど選挙有利として、その為の地均し質疑と答弁を繰り返している出来レースに過ぎない。バカバカしい。 そこで、以下の考察に入る。こんな政治をさせる為に国会議員を抱え込むのは、もはや最大の無駄である。やはり議員定数を削減せねばならない。掛け合い漫談しかできない国会なら野放図に議員貴族を抱えるに及ばない。経費削減を云うのなら、まず自らが襟を正して議員定数を削減し、次に官僚貴族の冗費削減、国家予算の上手な使途を指令すべきではなかろうか。手前らの権益をそのままにして官僚、国家公務員の懐に手を突っ込むのは無理がある。そう思った。これまでは少数野党が断固反対するので、それもそうかなと思っていたが、よく考えると現下の少数野党で値打ちのある党はない。少数野党権益の為に都市部で異常な議員定数を設定するのは却って不正、邪道である。そういう意味で、何のシガラミのない立場からの定数設定を試みて見ようと思う。 参考になるのは、島根県、鳥取県の全県2区制であろう。これを基準に、1・面積、2・人口、3・産業力、4・文化伝統力、5・都市計画の5要素から判定して行くべきではなかろうか。それを思えば、「指標2の人口比」だけで「1票格差違憲論」を弄ぶのは空理空論である。その論で行けば、今後ますます都市集中を強めるからして都市部の議員が過密化し、地方部の議員が相対的に影を薄くしよう。何のことはない、政治が都市集中、地方斬り捨てを促進していることになる。そういう意味で、「1票格差違憲論」そのものが胡散臭くなりつつある。 さて、上記の指標5基準で設定すると、ざっと次のようになる(個々の精密な検討は後日に期す)。北海道選挙区数12区→10区、比例定数8→5。同様にして東北25区→19区、14→10。北関東32区→20区、14→10。南関東34区→20区、22→10。東京都25区→15区、17→8。北陸信越20区→15区、11→8。東海33区→21区、21→11。近畿48区→30区、29→15。中国20区→16区、11→8。四国13区→12区、6→4。九州35区→29区、21→15。選挙区合計309区→207区、比例定数182→104、総議員数491→311。 これによれば、衆議院で180議席減となる。若干水増しするとしても150議席ぐらいは減ずることができる。衆議院定数は300―350議席で良いのではなかろうか。参議員定数の場合、選挙区73、比例代表48の計121議席×2=242議席となっており、これはこのままでも良いのではなかろうか。これによる節税効果は、議員給与、諸手当、秘書給与、その他選挙等の国家負担費用を勘案すれば年間で約1千億円になるのではなかろうか。この1千億円を何か上手に使う方が賢いのではなかろうか。例えば、内地振興の経済対策費に充てる等、有効な特定財源化せしめた方が賢明なのではなかろうか。税金上げなくても済むのではなかろうか。間違っても軍事防衛費に充てたり、アメリカの景気振興策に使うべきではない。 政治家の数が多いのは本来は問題ない。ところが、日本の現在と未来の為に身命を賭し、脳に汗を掻いているのなら大目に見ても良かったが、かくも公然と国際金融資本の下働きとしてのシオニスタン活動に邁進し、国家と民族の溶解政治へ向けての請負ばかりするなら要らない。手厚く待遇するに及ばない。真に有能な政治家を求める為にも一から出直さねばならないのではなかろうか。政治家が下手な政治をするので却って日本が衰退していることを思えば。 シオニスタン同盟は今後、消費税増税に向けて太鼓を鳴らすだろう。憲法改正による自衛隊の武装公然派兵、しかも恒常的な世界各地への派兵、しかも武闘化の道を敷くだろう。最終的に日本はIMF的な機関の管理統治に委ねられるだろう。なぜなら、そう云う風に仕向けられているから。それを思えば我々は、議員定数大幅減から始まり、高給与公務員規制、同天下り高給与待遇禁止、軍事防衛費削減、原子力発電政策からの撤退、官僚の権益的税金無駄遣い廃止等々を掲げてムシロ旗て応戦せねばならない。 次の問題もある。現下の不況は余りに長過ぎる。これは景気循環論で云えば有り得ないことである。つまり、国策不況化政治による意図的故意の政策によるものと云わざるを得ない。そんなことは有り得ないと思うよりも、誰が何の為にそういう政策を押しつけているのかを詮索した方が良い。例えば、前原が行くところ必ず悶着が起こり日本の国益を害しているが、これは偶然だろうか。彼は、有料高速道路の無料化をせぬまま国交相を降りたが、意図的故意に実施させなかったのではないのか。その前原が外相就任と同時に尖閣諸島の領有化問題が発生したが、これも臭い。れんだいこの眼には、日中シオニスタン合作謀略により敢えて政策的に引き起こした紛争ではないのか。なぜならアジアの緊張を高める為である。こう問う方が真相が見えて来るのではなかろうか。 尖閣映像流出は、もっと早い段階で国民に知る権利が有り、このこと自体が悪いのではない。問題は、菅政権をイタぶる形で漏洩され翻弄されているところにある。しかして、その裏には、闇勢力の仕掛けがあると見る。「sengoku 38」を名乗っているのも思わせぶりではなかろうか。菅首相は石にしがみついても延命したいとしているが、そういう言葉を使い始めると大概オワである。何のことはない、菅政権は小沢政権を阻止する為に登場し、政権交代政権効果を台無しにして、元の木阿弥に戻す為の橋渡しをしただけの話ではないか。このシナリオの根は深いと思う。 2010.11.8日 れんだいこ拝 |
||
| 「国会議員定数の変遷」その他を参考にする。これによると次のような変遷を見せている。 衆議院の議員定数は、戦後初の1946(昭和21).4.10日の第22回衆院選時点で466(沖縄2を含めると468)であった。この総選挙は、第92回帝国議会で新憲法に考慮して改正した衆議院議員選挙法(同年3月31日公布)に基づいて行われた。選出方法は中選挙区制。1950年、衆議院議員選挙法を廃止して、新たに公職選挙法を制定した。このときは、選出方法・定数とも変わらず、中選挙区制・定数466人と定められた。1953年、奄美群島復帰により1増の467人。1967(昭和42).1.29日の第31回衆院選で、「大都市の人口増加に伴う定数是正」を理由として+19され486となった。1970(昭和45).11.15日、沖縄県(定数5)が加わり491となった。1976(昭和51).12.5日の第34回で、「選挙区別人口による定数是正」で+20され511となった。この定数が1986年まで続いた。1983年、一票の格差が3倍以上に達する場合には憲法14条に反するとも解される最高裁判所の判決が出された。1986(昭和61).7.6日の第38回衆院選で、「選挙区別人口による定数是正」で+1され512となった。初めての減員を含む8増7減(8選挙区で1人ずつ増員し、7選挙区で1人ずつ減員。差し引き1増)。これが最大定数となり、以降漸次下降是正されて行くことになる。1993(平成5).7.18日の第40回衆院選で、「選挙区別人口による定数是正」で−1され511となった。9増10減(9選挙区で1人ずつ増員し、10選挙区で1人ずつ減員。差し引き1減)。平成6年公選法改正により「小選挙区比例代表並立制」が導入され、定数500(小選挙区300、比例代表200)とされた。1993年、いわゆる政治改革の一つとして選挙制度改革が論じられた。その結果、従来の中選挙区制は廃止し、小選挙区比例代表並立制が導入された。同時に定数も改定され、511人から500人(小選挙区300人、比例代表200人)に減員された。1996(平成8).10.20日の第41回衆院選で、「選挙区別人口による定数是正」で−11され500となった。2000(平成12).6.25日の第42回衆院選で、比例区を20削減(小300、比180)され480となった。これが現在に至っている。 国民26.5万人あたり1議席の割合となり、メキシコ下院が21.9万人、韓国議会が16.2万人、ドイツ下院が13.7万人、トルコ議会が13.6万人、スペイン下院が13.1万人、フランス下院が11.3万人、カナダ下院が11.1万人、イギリス下院・イタリア下院が9.5万人、ポーランド下院が8.3万人に1議席であるのと比較すると人口に対して定数が非常に少ない部類に入る、とある。 参議院の議員定数は、戦後初の1947(昭和22).4.20日の第1回参院選時点で250(全国区100、地方区150)であった。地方区の2人区25、4人区15、6人区4、8人区2であった。半数は任期3年、第2回以降半数改選とされた。1950(昭和25)年、公職選挙法が制定された。1970(昭和45).11.15日、沖縄県定数2が加わる。1983(昭和58).6.26日の第13回参院選で、全国区改め比例代表とされ、252(比例区50、選挙区76)となった。地方区の2人区26、4人区15、6人区4、8人区2.。1985(昭和57)年、公選法改正により「拘束名簿式比例代表制」を導入し、定数252(比例代表100、選挙区152)とした。選挙区の2人区26、4人区15、6人区4、8人区2。比例代表制とは、各政党の得票数に比例した数の議員を選出する方法のうち、政党の届け出た候補者名簿の名簿順位にしたがって当選人を決定する方法を云う。2000(平成12)年、公選法改正により「非拘束名簿式比例代表制」を導入し、定数を10削減して、242(比例代表96、選挙区146)とした。但し、2004(平成16).7.25日までの間の定数は247(比例代表98、選挙区149)とする。1994(平成6)年、選挙区の定数是正が行われ「8増8減」。増員区は、宮城県2人→4人、埼玉県4人→6人、神奈川県4人→6人、岐阜県2人→4人。減員区は、北海道8人→4、兵庫県6→4、福岡県6→4.。定数252(比例代表選出議員100、選挙区選出議員152)。選挙区き、2人区24、4人区18、6人区4、8人区1。2000(平成12)年、定数削減及び非拘束名簿式比例代表制が導入された。定数削減―10、定数252から242とし、比例代表選出議員100→96、選挙区選出議員152→146。減員区は岡山県4→2、熊本県4→2、鹿児島県4→2.。選挙区は、2人区27、4人区15、6人区4、8人区1。拘束名簿式比例代表制を改め、非拘束名簿式比例代表制を導入。非拘束名簿式比例代表制とは、各政党の得票数に比例して、政党ごとの当選者を定めた後、政党の届け出た候補者名簿のどの候補者を当選させるかについて、候補者名簿に順位を定めず、候補者個人の得票数が多い順に当選人を決定する方法を云う。2001(平成13).7.29日の第19回参院選で、「比を2、選を3削減」し、247(比例区48、選挙区73)となった。2004(平成16).7.29日の第20回参院選で、「比を2、選を3削減」し、242(比例区48、選挙区73)となった。これが現在に至っている。2006(平成18)年、選挙区の定数是正。4増4減。増員区は、東京都8→10、千葉県4→6。減員区は、栃木県4→2、群馬県4→2.2人。定数:242人(比例代表選出議員96人、選挙区選出議員146人)。選挙区は、2人区29、4人区12、6人区5、10人区1。※定数別選挙区一覧(平成18年改正)
(注)各定数別選挙区の順序は平成17年国勢調査人口の多い順である。 |
| 2010.11.12日、民主党は、今夏の参院選マニフェスト(政権公約)で「衆院の比例定数を80、参院定数を40程度削減する」と明記した国会議員の定数削減をめぐり、菅首相が9月の党代表選公約で掲げた年内の党方針取りまとめを断念する方針を固めた。企業・団体献金の自粛撤回に続き、首相が約束した政治改革の看板倒れとなる。岡田克也幹事長は、「代案」となる国会議員の歳費1割削減を政治改革推進本部総会で提示したが、こちらも反発が相次いでまとまらなかった。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)