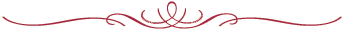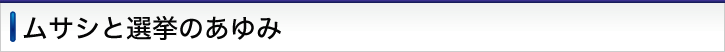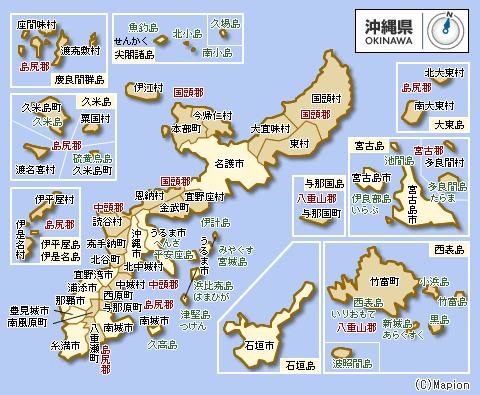<衆議院選>機械で投票用紙を振り分け 様変わりの開票作業【動画付き】
いよいよ14日に迫った衆議院選の投開票日。国政選挙の開票作業といえば、たくさんの人手をかけて行われ、時間がかかるイメージだが、近ごろは機械などのさまざまなテクノロジーが取り入れられ、ひと昔前と様変わりしているようだ。
【動画】折っても自然に開く投票用紙、実際に折って試してみた
■1分間に660票の高速処理
[写真]ムサシ社の投票用紙「読取分類機」
「この機械は1分間に660枚のスピードで投票用紙を分類できます」
こう語るのは、選挙機材メーカー「ムサシ」の篠沢康之広報室長だ。同社が2010年に発売した投票用紙「読取分類機」は、投票用紙に書かれた候補者の名前を瞬時に読み取り、候補者ごとのラックに振り分けていく。この読み取りの処理速度が毎分660票で、天地裏表など票の向きも揃えてくれる。
篠沢室長は「いろいろなクセがあったりするので、手書きの候補者名や政党名を識別するのが非常に難しい。ただ選挙なので正確性が第一。読み取り不能の枚数を減らしていくのが生命線です」と開発にまつわる苦労を語った。分類の精度はとても高く、読み取り不能になるのは4%ほど。それらは人の目によって改めて振り分けられる。
開票作業は大きく3つの作業に分かれる。まず一つ目が投票用紙を「開く」作業。二つ目が投票用紙を候補者ごとに「分ける」作業。三つ目は分類された票数を「数える」作業だ。
投票用紙を開く、というとピンと来ないかもしれないが、多くの人は投票する際に投票用紙を折って投票箱に入れる。そのため、開票はその折られた用紙を全部開くことから始まり、それがかなり骨の折れる作業なのだという。同社の「折っても自然に開く投票用紙」は全47都道府県で採用され、そういった手間が大幅に省かれることになった。また、これまで人の手によって候補者ごとに分けていた作業は「読取分類機」で、票数を数える作業は「計数機」で行う自治体が増えてきた。篠沢室長は、同社の市場シェアは実に8割という。