これほどの疑惑を振りまくを開票独占企業㈱ムサシを国会喚問なくしては、民主政治の名が廃る!!選挙は、民主政治の根幹だ。公職選挙に携わる資格が㈱ムサシにあるか否か??
あまりに当然の事だ。誰しも思いは同じだ。又、㈱ムサシも、正々堂々とその疑惑に応える事が出来るであろう。それでこそ、上場企業のディスクロージャーとして、企業責務であるばかりでなく、公職選挙に携わる企業として汚名挽回の絶好の機会でもある。
【転載開始】気弱な地上げ屋は・・今回の選挙も、選挙管理委員会の開票立会人を務めました。いや今回は・・過ぎる時間が・・長かったですね。(苦笑)
全国どの選挙区も・・だいたい投票締め切りの15分前・・つまり午後7時45分前後に開票所に集合するのですが気弱な地上げ屋の場合・・午後7時に呼び出されました・・。誰に呼び出されたのかって?選挙管理委員長と選挙事務長です。 (笑) 選挙管理委員長と言うのは地元の都議や区議を長年務め・・引退したジイサン。選挙長というのは・・区役所の局長クラスが務めます。2人とも・・「なんで? こんなガラ悪いヤツの対応・・オレ達がやらにゃならんの?」 損な顔してます。 (笑)
この3者会談。期日前投票所での不手際を草の者より知らされ・・選挙管理委員会にネジ入れたところ・・「ご説明に・・」と言うことで実現したのですが・・気弱な地上げ屋の・・ホントの狙いは別のところにございます。 (笑)
20分ほど・・グチャグチャ言い訳するのを黙って聞いたあと・・「そんな言い訳で良いわけないでしょ? でもまあ・・今回はこれ以上突っ込まないことにしますわ。 それはそうと・・こうして選管幹部とメンと向かってゆっくり話す機会もそうそうあるもんじゃありません。 この機会に・・是非お願いしたいことがあるんですがね・・。 前回に引き続き・・今回も、開票立会やるわけですけど・・舞台からただボーっと見てるだけじゃぁ・・面白くないのですね。 でね・・邪魔はしませんから・・開票作業を・・もっと近くで見たいんですよ。 ねっ!? いいでしょ? あれ? ナニ? 嫌な顔してません? まさかダメとは言わないですよね? 舞台より・・もうちょっと近くで見るってだけのことです。 でもやだなぁ・・。 もしダメだなんて言われたら・・さっきの件・・今回、35万票くらいですかね? 1枚1枚チェックしなきゃなりませんよね? 」 「・・・・」 「仕方ありません・・。 気弱な地上げ屋サンに選管職員が2人ついて・・各部署を視察してる・・ってことにしますからね、それでいいですね? あと・・ほかの立会人からクレームが出たら・・その時点で終了して戴きますよ、いいですね?」 「ハイ、結構です。」
上手くいきました。 (笑)
この仕掛けの目的は・・数十ヶ所の投票所から集められた投票用紙が、開票所でどのように開票され計数され・・発表されるのか。それらをつぶさに目の前でチェックしようという試みです。 (笑)
今回の選挙。小選挙区・・比例区・・都知事選そして、裁判官国民審査・・。各投票所には、この4つの投票箱が置かれています。夜の8時に投票が締め切られ・・8時15分過ぎから・・次々と投票箱が運び込まれます。キチンと施錠されてるか・・選挙立会人の前で確認させてから開票台の上に載せられます。「鍵かけられてても・・合鍵持ってたら、開けられるだろ?」 こうした疑いを向ける人もいるでしょう。尋ねてみました。台に載せられてる投票箱は・・200個以上あります。「凄い数の投票箱ですね!? 全部、南京錠かかってますけど・・同じ鍵で開くのですか?」 「いえ、全部違う鍵です。 投票箱と同じ数・・違う種類の鍵があります」 「でも・・凄い数ですよね。 無くしちゃったときのために・・マスターキー(筆者注:全ての鍵を1つの鍵で開けられる万能キーのこと) あるんでしょ?」 「いえ、ありません!」 「ホント? ホントはウソなんでしょ?」 「いえ、ウソじゃなくてホントです!」 どうやらホントのようです。 (笑)
開票作業が始まりました。1つの台 (投票箱) に16人がかりで票を開いてゆきます。これがまた凄いスピードです。でもアレ?おかしいですね・・。同じ投票をまとめているのではなく・・ただ単に、50枚づつまとめてるだけです。「投票用紙に書かれてる名前ごとに集めてるのではないのですか?」 「あそこに機械が見えるでしょ? OCR読み取り機です。 まとめた投票用紙は、あの機械使って・・選別します」 「ああこれね?」 「あっ! 気弱な地上げ屋サン!? この機械には・・近づかないでください!」 「アンタ、選挙事務長から聞いてないの? アタシはね・・隅から隅まで見ることを許可されてんの。 それともナニ? この作業全部止めて・・1枚1枚手作業でチェックする?」 「・・・、じゃあ・・近づくのはいいですから・・機械に、手は・・触れないでくださいよ。」 この日の気弱な地上げ屋は、とても機嫌が悪いので・・(笑)ヘタに刺激すると、やぶ蛇となります。 (苦笑)
この投票用紙読取装置。OCRは気弱な地上げ屋の会社にもありますが・・そんなチャチなもんじゃございません。
でも・・触るな・・なんて言われて言われたとおりに黙って見てる・・。気弱な地上げ屋が、そんなヤワな人間でないことはレギュラーの皆さんなら良くご存知ですね?試しに、目の前にある赤いボタン押してみましょう! (笑) 「あぁ! アンタ! 非常停止ボタンに触れないでください!」 ん? 最高に機嫌が悪い気弱な地上げ屋にコナかけてくるなんて・・いい度胸したヤツです。「この機械は、我々が管理してるものです。 手は触れないでください!」 「ふーん? アンタがた・・しか、この機械動かせないんだ? でもね、アタシは・・そんなアンタがたを監督するのがお役目なのよ。 だからね・・ここにこうしているの」 気弱な地上げ屋の監視役の選管職員がこのオトコの耳元で何か囁きます。「ねっ!? 分かったでしょ? じゃあ仕組み教えてチョーダイ? ん? さっきからヘンだな・・って感じてたんだけど・・アンタがた、開票作業員のプレートつけてないね? なんで?」 「アタシたちは開票作業員ではありません! この・・投票用紙読取分類機のオペレーターです。」 「分かってますよ。 で、なんで? ネームプレートつけてないの? と、こう聞いてるのよ・・」 「だからオペレーター・・」
「なら、オペレーターのプレートつけりゃいいじゃない?」 見かねて、選管職員が割って入ってきます。「気弱な地上げ屋さん・・。 この人たちは・・公務員・・区の職員じゃないのですよ。 機械が正しく動くかどうか・・チェックしに来てくれてる民間人です・・」 「なら、最初から言えばいいじゃない? で? アンタら、どこのどなたなの?」 「ムサシの・・職員です」 「昔の職員? そんな年寄りにゃ・・見えんけど」 「この機械を販売してる・・株式会社ムサシの社員です!」 民間企業の職員が・・民主主義の根幹を成す・・こんな神聖な場所でデカイツラしてるのはとても違和感を感じるものです。徹底的に・・調べなければなりません。 作業を見守りました。500枚単位ランダムにまとめられた投票用紙が機械に入れられると・・
ものの1分もかからぬうちに立候補者ごとに仕分けられます。機械でも読み取れない絵を書いて投票したような・・無効票や・・どうしても読み取れない疑問票。これらも、次々と・・
別々に仕分けられて行きます。「入れた票の数と・・出てきた票の数はどこでチェックするの?」 「入れた票、500枚は手作業で数えたでしょ? 出てきた票の数は、ここに表示されます・・。 今、430枚でしょ? あと5秒で・・ほら、今500枚ピッタリです。」 仕分けられたコンテナから何枚か抜き出しチェックしましたが・・まったく間違いはございません。 (苦笑)
「でも・500枚全部チェックしたわけじゃ・・無いからね」 「それをこれから・・手作業で2回づつ・・チェックします」 機械で振り分けられた票を更に2回、別の人間が手作業でチェックしてゆくわけです。イチャモンつけようがございません。「でも! 肝心の・・票の計数はどうすんのよ?」 「候補者ごとに仕分けられた票は・・手作業で数えられ・・更に、この2台の計数機・・で2回計数されます。 つまり・・人手も含めると・・合計3回数えるわけです」 「でもさ! ここの開票所だけ・・こんなにしっかりやってるってことは無いの? ほかの開票所は・・もっといい加減なんじゃないの?」 「少 なくとも・・東京都選管の管内は同一基準なんでまったく同じ作業をします。 ほかの道府県? 総務省の指導に準拠してますから・・チェック回数を増やすことはあっても・・減らすって選択肢はありませんね。 不正投票? そういうこと言ってる人には・・是非、開票所に足運んで・・ご自分の目で・・この作業を見てから・・もう一回言ってもらいたいですね」 完全に・・勝ち誇った表情で言い放ちました。 (苦笑)【転載終了】
みんなで国会招致を求めようではないか。植草先生の正論は、至極当然の話だ。公職選挙事務そのものも重大な争点になるだろう。その透明化無くして、日本の民主政治は有名無実となろう。自民党も公明正大に受けて立てば良い。それでこそ、自由民主党だ。自由に不正を擁護し、民主政治を破壊する政党と言われない内に、そのことを受けて立ってこそ、自民党の真の再生があると言うべきである。かつては自民党党員であった私からも願う。名実ともに日本の自由民主党に蘇る一大チャンスだ。
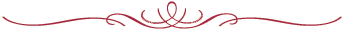
>1枚づつ小選挙区と比例代表の各投票所の投票状況が記された用紙が配布されます。
これは私の立ち会った開票所では配布されませんでした。 あったのは途中経過の際に市内全域での合計を口頭で発表されただけ。
その他については基本的に同じかな。 ウチの所は票の選別は機械でなく人が行っていましたが。 後、最初は小選挙区から開票しましたが、途中からは比例も同時に行い 最終的に開票作業が終了するのは両方ともほぼ同じでしたね。 まぁ、この辺はどうでもいいことなんですが。
不正に関しても意見もほぼ同じです。強いて考えるとしたら 投票所にあらかじめ別の投票箱があり、そこに改ざんされた用紙を入れる?とか。 これだと我々立会人は確認しようがありません。 ただ、そこまでするのか?とも思うし思いたい。 Posted at 23:06 on 2012-12-18 by blackbunny9