| 序章
2000年11月7日、4年に一回の米大統領選挙が行なわれた。現職の民主党クリントン大統領は二期目であり、本選挙は実質、現職の副大統領ゴア氏と第41代大統領ジョージ・ブッシュの長男でテキサス州知事である共和党のG.W.
ブッシュ候補との間での戦われる事となった。現職の副大統領であったゴア氏が景気から見ると多少有利なのではないかと見られていた。その一方で、クリントン政権が倫理面においては決してよいイメージがあったとは言えなかったため、いかにクリントン政権の成果を自分にも有利に使いながら、前政権との違いをどう強調していくかという、典型的な現職副大統領が候補となった時のジレンマがゴア氏にはあった。反対にブッシュ候補はアルコール依存症になった経験もあり、決して完全な人物像というわけでは無かったが、親しみやすいと評判も良かった。そして目立った争点が無かった今回の2000年大統領選挙はこのため、選挙前から接戦となる事が予想されていた。しかしこの大接戦がたった一つの州の結果によって選挙の結果自体を左右させてしまうような僅差の戦いとなった。
そして選挙のカギを握る事となった州はフロリダ州であったが、さらにフロリダ州内でも大接戦となった。その得票数の差が総票数の0.5%以下であり、そのためフロリダ州法に基づいて再集計が行なわれるととなった。フロリダ州の結果が加わる前の時点での全国の開票結果では、ブッシュ候補が29州で勝利し246人の選挙人を獲得、ゴア候補は19州と首都ワシントンDCで勝利し、260人の選挙人を得ていた。これにフロリダ州の再集計の結果が出ればフロリダ州の選挙人25人が加わり、過半数の選挙人を得た候補者は問題なく選挙人による投票で次期大統領に決定するはずであった。しかし、この再集計を行うにあたって続々と問題が浮上した。
再集計の方法を巡って両陣営が裁判という手段に訴えかける事となった。そしてその泥沼の戦いは本論文の第一章でも詳しく説明する連邦最高裁判所の判決によって集結することとなった。この判決のキーワードはEqual
Protection(法の下の平等)であったがこれは合衆国憲法修正条項14の内容によるもので、これにより州はその管轄内にいる者の平等な法の保護を無視することを禁じている。つまりフロリダ州の最高裁判所が許可した手集計による票の再集計は、それを平等に行う基準が無く、また公正な基準を設ける事は時間的に不可能なため中止すべきという判決が下され結果的にブッシュの勝利に結びついた。
大統領選挙が国家の長を決める選挙であっても連邦制を採っているアメリカでは、国家的な基準も州が守るかどうかは自由である。またどの集計機が使われるかはすべて州に任されていて郡ごとに違う投票方式を採用しても違憲ではない。また多くのアメリカ人にとって投票する権利は神聖なものとして考えられているが、実態は散々たるものである。
まず、その原因として挙げられるのが長年の渡るこの問題を直視する事が避けてこられたことである。このことにより選挙管理には予算が足りておらず、経験者が全く育たないのである。また票を数えている人の多くはマニュアルも読めないような人達ばかりなだけでなく投票者登録も同じくらい問題が多く潜んでいる。アラスカ州では有権者よりも38209人多くの投票者登録がされているし、インディアナ、アリゾナ、アイダホ、テキサス、オクラホマ、ユタ、ウィスコンシン州の登録者のうち20%以上が奇想天外な名前が登録されているという。
しかし、今回の選挙は接戦となったためにこういった今まで見過ごされてきた選挙管理がどのように行われていたかがとても重要な問題となった。そして2000年の大統領選挙の当日、どのようなことがフロリダ州の各投票所で起こっていたのか、投票者のみならず投票所の職員などからも聞き取り調査を行って分析した先行研究に「Draft
Report Voting Irregularities in Florida During the 2000 Presidential Election(Approved
by the Commissioners on June 8,2000)」をはじめ数多く存在する。
そこで今回の論文では当日の選挙管理の問題も加味しながらどのようにしてブッシュが2000年の選挙を勝ち得たのか明らかにしたい。はじめに再集計が決まってからこの連邦最高裁判所の判決が下るまで何が起こったのかを追っていきたい。次に選挙当日に目を向け、杜撰な選挙管理がどのように選挙の結果を左右したかを明らかにしていきたい。最後にこの選挙やフロリダ州の対応や両候補の対応はアメリカ全体にどのような影響をあたえたのか明らかにしたい。これには選挙制度への疑問を投げかける人々の議論や新たなる法律の制定への動きに与えた影響など全般的に明らかにしていきたいと考えている。
一 再集計
(一) 再集計に到るまでのメディアの誤報
はじめに今選挙の接戦の程度を理解するのにメディアの当日の反応を見てみたい。なぜならこのような接戦を経験したことがなかったメディアが混乱を拡大してしまった事は否定できないからである。事実関係を述べると、7日の19時50分頃まず、NBCとNBCの24時間ケーブル・ニュース放送であるMSNBCがフロリダ州でのゴアの勝利を伝えた。続いて、CBS,CNN,FOX,ABCも同様の内容を流した。しかし、22時ごろ新たな情報が入り、フロリダ州のある郡では開票結果で、ブッシュに行くべき票が間違ってゴアのものとして数えられていた事が判明したのである。ここでフロリダにおけるゴアの約17000票がそっくりブッシュに移される事とになった。このフロリダのミスは放送局の責任ではなく、実際の開票と集計の間違えである。しかし、19時50分の時点ではほとんど票は開票されていなかったという事実を考えると早すぎる段階でゴア勝利を断定して事は,放送局側の問題と言えるだろう。これが第一の誤報となった。
続いて深夜をまわって8日午前2時17分ごろ、フロリダ州では97%の開票が終わり、CBSではブッシュ2,759,232対ゴア2,707,798の数字が画面に映し出され、断定的に「ブッシュが大統領に当選しました。」と告げられた。正確にはその後「もし、CBSの判断が正しければ、ブッシュが当選する事になるでしょう。アメリカの歴史の中でももっとも接戦だった今回の選挙、ブッシュが勝利しつつあります。」と付け加えられた。しかしこの瞬間、ほとんどの人はブッシュが当選したと思ったであろう。実はこの間違えは多少の時間差はあったものの他局もしていて、新聞もこの時点で号外を刷ったところもあった。対立大統領候補であったゴアでさえ、ブッシュ当選決まりだと信じ、紳士的な候補者の証としてブッシュに当選を祝う電話をかけ、ゴア自信も公的に敗北を認めるために支持者の待つ広場へと向かった。しかし開票は進み、最終的には608票差のブッシュ2,887,426対ゴア2,886,620となってしまった。また、この段階ではまだ海外からの不在者票が届いておらず、またフロリダ州法の規定により票差が全体の0.5%以内であれば再集計を行わなくてはならず、まだ結論は出せない状況である事が判明した。まだ断定できない段階でのこの断定的な報道は第二の誤報となってしまった。同時にゴアが敗北宣言を取り消すという異例の事が起こった。
このような誤報が広くなされてしまった原因の一つとして選挙速報を出す時のコストを抑えるため、主要なメディアの共同で運営されているVNS(Voter News Service)という機関が使用されている点にあったと言える。ここの出す情報を元に各局は当選の宣言を行っていたが、このVNSの判断基準の大部分は出口調査をベースにし、過去の投票結果一覧と当該の出口調査とを比較し、見積もりを出すというものであった。単純に入力ミスがあった事も判明しているが、主要なメディアが揃ってVNSの情報を頼りにしていたため、その影響は大きかった。また年々選挙の結果をより早く出したがるメディアの傾向を受けて、早すぎる段階での発表に踏み切ってしまい結果としては誤報となってしまった。
またCBSを例に採ると、報道の中で使用された表現もまた混乱を招いた一因となったようである。’64年当時CBS社長であったフレッド・フレンドリーはニューヨーク・タイムズの取材でこう語っている。「11月3日の開票速報でわれわれは、われわれの分析結果と実際の票の行方とが完全に一致するまで、“当選”という言葉は使わない。“当選しそうな人”とか“当選が明白な人”“たぶん当選が予想される人”などの言葉を用いるだろう」。しかし、98年の「投票終了時および以後の放送用語」と題する社内メモでは、大分事情が変わっていた。それには「内部的にはCBSがレースの予測判定(CALL)をすると言っているが、一般の人には『ジョージ・ブッシュが勝った』と言ったほうがずっと分かりやすい。したがって、『CBSニュース予測では、ジョージ・W・ブッシュが知事に選ばれました』とか、あるいは単に『ジョージ・W・ブッシュがテキサス州知事に再選されました』と言ってよい。基本的にレースの予測判定がされるとき、われわれは誰かが勝ったと言っているのだ。われわれはそう言うのを恐れてはいけない。」と書かれている。おそらく今回の選挙でもこのように予測の段階のものまであたかも確定した事実のようなシンプルな口調で伝えられたのも、問題を大きくさせたものであったに違いない。
そしてこういったテレビ局の放送基準を見ても、今回のような接戦が起こることを誰も考えもしていなかったという事が言える。
(二) バロット
11月8日両候補の得票差が総評数の0.5%以下であったことから、フロリダ州法の規定に則って、自動的に機械による票の再集計が始まった。しかし、再集計が開始されるとまずフロリダ州パーム・ビーチ郡において、バタフライ・バロットと呼ばれる見開き型の投票用紙が問題となった。この投票用紙が紛らわしいかったためにゴア氏に行くはずの2000以上の票が、間違ってブキャナン氏に流れたという情報がカーネギーメロン大学助教授グレッグ・D・アダムスによって流された。そして9日怒った民主党支持者は投票やり直しを求めてデモを行った。
この問題となったバタフライ・バロットには候補者の名前の順番はブッシュ候補が一番上で二番目にはブキャナン候補、そしてゴア候補となっていたが見開きのため一見ゴア氏が二番目に表示されていると勘違いしてしまいやすい構造となっていた所に問題があった。事実ブキャナン氏は説明ができない程多くの票を獲得している。しかし、投票用紙は事前に民主党によっても確認され承認されていたもので、民主党としては投票用紙の構造について問題があったかどうか議論する余地がなかった。またむしろこの件で浮上した問題の真意は、バロットの構造がどうかという事よりは、投票者に投票の仕方やバロットについての充分な説明あるいは教育がなされていなかった事という問題を明らかにした側面の方が重要であったとも考えられる。
また民主党支持者はブッシュ候補が一番上に表示されていたのに、不満に感じた人も多かった。しかし、これはフロリダ州の知事が共和党であるため共和党が一番に表示されるという規則があるためそうなっていた。特にブッシュ候補の弟が知事であったから意図的に有利にするために一番に書かれていたという事ではなかった。また投票した時に間違えに気が付けば州法によって三回までなら投票用紙を交換してもらえる事となっているが、実際そのような事が可能であると知っていた人がどれだけいたのか疑問がある。また「Draft Report Voting Irregularities in Florida During the 2000 Presidential Election(Approved by the Commissioners on June 8,2000)」によると実際間違えてしまった人も投票所の職員は用紙を交換してくれなかったと話す人もいた。
このようにバロットに関する問題の大半は有権者と投票所の職員両者の教育不足が原因と考えられ、今後のバロットの構造の見直しも然ることながら、教育に予算を費やす必要性が顕著に表れたと言える。
(三) 手集計
そんな中でゴア陣営は集計に使用されている機械に着目し、パーム・ビーチ郡などの4郡に対し、機械ではなく「手作業」による再集計を求める記者会見を行った。地域によって集計機は異なっているが、特にマイノリティーの黒人の多く住む地域では予算が少なく精密の低い機械が使用されていた。そのため本来ならば有効となるはずの票が精密な機械に比べ何十倍もの差で票を無効と数えられてしまう欠点が性能の悪い機械にはあった。そしてゴア陣営はこの4郡は民主党の強い地区なので、機械で読み取れなかった疑問票を手作業により読み取ることで、ゴア票を加算することができるという読みが働いた。そして民主党は憲法が保障している法の下の平等に則り、「すべての投票は数えられなくてはいけない」という基本的メッセージを投げかけ、「全米での一般得票数ではゴアが勝っている」という事実を強調し、手作業による再集計の合理性を訴えた。
これに対し、ブッシュ陣営は「手作業を進める公正な基準がない」として、その差し止めを求めてパーム・ビーチ郡の連邦地方裁判所に訴えた。再集計にあたり、候補者の代理人として民主党がクリストファー前国務長官を、共和党もベーカー元国務長官をフロリダに送り込み、また大勢の弁護士を州内各地の開票の監視に送りこんだ。そして1ヶ月におよぶ法廷闘争が繰り広げられる事になり、最終的には12月12日の米連邦最高裁の判決が決め手となった。ここで、この法廷争いの概略を日付にそって明確にしたい。
| 11月8日 |
機械による再集計が法律の規定により即座に始まる。 |
| 11月9日 |
ゴアのキャンペーンチェアマン、ウィリアム・デイリーと元州務長官ウォーレン・クリストファーが記者会見を行い、四つの郡での手作業による再集計を求めた。パーム・ビーチとヴォルシア郡の選挙委員会はその要請に応じる事を承認した。 |
| 11月10日 |
機械による再集計が終了するが、結果は正式発表されない。ブロウワード郡は投票により郡内の3つの選挙区で試験的に手集計を13日に行う事となった。 |
| 11月11日 |
パーム・ビーチが郡内4つの選挙区で手集計を開始し、ブッシュは連邦地裁に「主観が入る」として手集計の停止を求め提訴。 |
| 11月12日 |
パーム・ビーチは試験的な手集計を終え、ゴア陣営に19票多く票を獲得したために、郡全体での手集計に取り掛かり出す。同時にヴォルシア郡も全部の票の手集計を開始する。 |
| 11月13日 |
ブロウワード郡は試験的な手集計の結果を受け、郡全体での手集計を拒否した。ハリス州務長官はこの日、再集計結果を14日に締め切ると宣言。同日連邦地裁はブッシュからの提訴について「連邦裁がかかわる問題ではない」として却下(翌日第11区連邦巡回区裁に控訴)。ゴア陣営は州巡回区裁に再集計の締め切りの延期を求め提訴。 |
| 11月14日 |
州巡回区裁はハリス州務長官の定めた締め切りに郡は合わせなければならないとしながらも、締め切り期限後の結果を恣意的に無視できないとした。パーム・ビーチ郡はフロリダ州州務長局からチャンバシングボードには郡全体の手集計を執行する法的権限がないという内容の法的見解を示されたため、手集計を停止させる。またマイアミ・デード郡でも試験的な手集計が終了しこの郡の選挙委員会は郡全体での手集計は行わないという決をとった。
また、この日ハリス国務長官はこの日67郡からの結果によりブッシュが300票差でリードしていると発表、同時に翌日の午後2時までに再集計結果の遅れる郡に対してその理由を書面で提出するように要求した。
|
| 11月15日 |
ハリスは締め切りを求める4つの郡からの要請を却下すると表明し、18日に届く不在者投票の票が加算されたら最終結果とするとした。しかしフロリダ州最高裁は手集計の中止の求めを却下し、これを受けてブロウワードは郡全体の手集計をはじめる。 |
| 11月16日 |
フロリダ州最高裁は手作業による再集計の続行を容認するが、その結果を認定される結果に含むべきかについては触れていない。ここでパーム・ビーチも郡全体の手集計をはじめる。 |
| 11月17日 |
レオン郡州巡回裁は「ハリス長官の決定は筋が通っている」と判断し、州最高裁ハリスに判断を下すまで票を確定しないよう命令。第11区連邦巡回区控訴裁はブッシュの再集計を止める要請を却下。
マイアミ・デードもここで再び、郡全体の手集計を行うことを決定した。
|
| 11月18日 |
不在者投票の票が集計され、ブッシュのリードが930票へと膨らむ。ゴア陣営はフロリダ州最高裁に手集計結果を最終認定結果に算入すべきとする書面提出。 |
| 11月19日 |
ブッシュ陣営が手集計結果の算入に反対する書面提出。 |
| 11月21日 |
州最高裁が手集計結果の算入を命令。11月26日を各郡から州への報告締切りに設定。 |
| 11月22日 |
ブッシュ陣営は州最高裁の判決は「三権分立に反する」として連邦最高裁判所に上訴。同日、マイアミ・デード郡は「締め切りに間に合わない」として手集計中止を宣言。 |
| 11月23日 |
ゴア陣営はマイアミ・デード郡の手集計中止は州法違反として上州最高裁に上訴。しかし、却下される。 |
| 11月24日 |
連邦最高裁は手集計の合憲性について審理すると発表。 |
| 11月26日 |
パーム・ビーチ郡は「集計が間に合わない」と締め切り延長を要求。しかしハリス州務長官はパーム・ビーチの要求を却下。ブッシュ氏が537票差でゴア氏に勝利と、最終結果を確定ブッシュ候補、「勝利宣言」したが、リーバーマン副大統領候補、フロリダ州の結果を法廷で争うと明言した。 |
| 11月27日 |
ゴアはレオン郡巡回区裁にパーム・ビーチ、マイアミ・デード、ナッソーの3郡の再集計結果を算入するよう異議申し立てた。 |
| 12月4日 |
レオン郡巡回区裁はこれを棄却し、ゴアは州最高裁に上訴した。同日11月22日のブッシュ陣営からの上訴を連邦最高裁は州最高裁に差し戻した。 |
| 12月8日 |
州最高裁は州全体での疑問票再集計を命じたのを受けて、ブッシュは連邦最高裁へ上訴した。また州議会では特別本会議で選挙人任命の手続きが開始された。 |
| 12月9日 |
連邦最高裁が疑問票再集計の中止を命じた。 |
| 12月12日 |
州議会下院では共和党支持者の選挙人25人を任命。
連邦最高裁は疑問票再集計を命じたフロリダ州最高裁判決を違憲の疑いで破棄・差し戻し、再集計は現実的に不可能になった。
|
| 12月13日 |
ブッシュ勝利宣言。 |
(この日付表はDeadlock, The Washington Post とCNN.co.jp 2000年米大統領選.htm を参考にしたものである。)
(四) 連邦最高裁判所の判決
ここで詳しく、この法廷争いを終わらせることとなった12日の最高裁判所の判決に注目したい。
この判決によると連邦最高裁は、判事9人中7人はフロリダ州最高裁が認めた手作業による再集計の違憲性を指摘した。再集計の基準が地域によって異なるため、有権者は法の下の平等が侵害される恐れがあったという。このため、再集計を行うには、州内統一の基準を設ける必要があるとして、再集計の是非を州最高裁が改めて審査するべきだと、訴えを差し戻した。しかし、現実的には選挙人確定期限12日と設定した合衆国法典にのっとり、フロリダ州下院が同日すでに、独自の選挙人を任命している。このため最高裁は5対4で、再集計を実際に命じる事もまた、憲法違反になると裁定した。
結果、連邦最高裁の決定は、ブッシュ氏の勝利を直ちに確定したものではなかったが、ゴア氏が求めていた疑問票の手集計再開を事実上不可能にした。そして民主党候補のゴア副大統領は13日午後9時すぎ、テレビ演説で敗北宣言をした。ゴア氏は、「連邦最高裁の判決に同意はしないが、受け入れる」と述べ、共和党候補のブッシュ、テキサス知事に「国の連帯のためにも、敗北を認める」と明言した。そしてブッシュ知事の第43代米大統領就任が確定するとともに、11月7日の投票から36日間も続いた混迷が収束した。
この判決で注目すべき点はこの判決は支持した判事も支持しなかった判事も党に関係無く判断を下していた点である。この判決を支持しなかった判事二人もまたそれぞれ民主党のクリントン前大統領に任命されたルース・ギンズバーグ氏と共和党のフォード元大統領に任命されたスティーブンズ氏であった。また、この判決の多数派だった陪席判事のクラランス・トーマスは今回の判決が下された直後にワシントンD.C.で学生たちを相手に話をした。そこで彼は「今回の裁判所の判断は政治的な要因や党派を考慮したものではなかったと信じている」と話した。また最高裁判所長官が後にこのクラランス判事の述べたことは、今回の件の真意をついているかという質問に対し、「まったくその通りである」と述べている。
しかしこの判決に違法行為の疑いがあると主張するジャックM・バルキン氏やスタンフォード・レビンソン氏のような見方もある。判決に賛同した判事は党を超えていたとは言え、現在の連邦最高裁判所の判事には保守傾向に偏りがあることが指摘できる。そして5人の最高裁判事によって停止された再集計は、その当時多くの人が完了すればゴア氏の勝利の可能性が高いと思われていたものであった。また法廷意見は粗末に書かれていて、理論付けが乏しく、すべての再集計が中止されるべきであるという最終的な結論は法の下の平等という前提から上手くつながるとは言えない。
違う論文でもバルキン氏はこの判決の裏側の意図について書いている。それによると賛同した5人は10年間以上もの間、公民権と連邦主義における憲法の見解の紛れもない革命に取り掛っていた。連邦最高裁判所の考えの基本には国家介入からの自治権の尊重や州の政治過程の国からの監視からの保護がある。そして今回の判決が重要であるのは、直接この考えを一歩前進させたことではない。むしろ、共和党政権を樹立させ事によって、共和党の大統領に保守派の判事を最高裁判所に任命してもらうことによって、こういった現存の最高裁の傾向を存続させることが可能とさせた点であった。
実際、バルキン氏らが主張するような意図が絡んで出された判決であったかどうかは断定できない。しかし政治的な意図がまったく働かなかったと判事達が主張しても疑問の残る余地は十分にある。また、この判決によって一方の候補者を有利にすることが可能であったのは事実だ。そのためやはり少なからず政治的な判断が絡んでいたと考えるのが妥当である。
しかし政治的な要素が絡んでいたのは、何も最高裁判所の判決だけはないと見られる。12月8日のフロリダ州最高裁の再集計に味方する判決は7人全員民主党の知事によって任命された判事が出した判決であった。また再集計の責任者となり、締め切りの決定権などを持っていたフロリダ州務長官もブッシュのフロリダ州のキャンペーン共同責任者であった。そのため、中立な立場で判断していたとは到底考えられない。
そしてその結果はThe New York Times の2001年11月12日の新聞で公開された。結果もっとも甘い基準、つまりえくぼ票も含める結果を採用すると、実質644票がゴア氏に加算され、107票差でブッシュ候補を上回る結果となっていた。さらに、もっとも厳しい基準の結果でも5,252票がフロリダ州の総票数に加算され、ゴア候補には652票の純増が加わり、115票差でブッシュ氏を上回っていた事が判明した。
しかし、これはフロリダ全州の結果であり、実際の選挙でゴア候補側が求めていたようにマイアミ・デード, ブロウワード, パーム・ビーチ, ヴォルシアの四郡での手集計のみの結果だと両候補者の票差は537票から225票に減少するだけで、いずれにしても選挙の結果を覆すまでには到らなかった事となる。またフロリダ最高裁が求めていたようにUnder
voteだけの再集計でもブッシュ氏が勝っていた事が分かり、Over voteも含めたすべての票で手集計が行われない限りゴアが勝利するという結末には到らなかったということである。つまり、連邦裁判所がフロリダ最高裁の手集計による票の数えなおしを中断させたからといって結果は変わっていなかった事になる。
しかし、同時にこれははじめからフロリダ州ですべての有効票を数える性能の良い機会が揃っていれば、違った結果に選挙は終わっていたということを意味する。またそもそもこれらの票は公正な選挙運営の下で投票されたものであったのだろうか。そこで次に当日の選挙がどのように行われたのか見てみたい。
二 選挙当日の問題
実際再集計の時の混乱に加えて、当日も様々な問題が発生していて、公正な選挙が行われていたのか疑問が残る。そのためにこの選挙では再集計の時の混乱が余計に増したと考えられる。そしてこれだけの接戦であったため通常では気にされない一つ一つのミスや設備的な不平等などが注目されることとなった。
(一) 設備的な面から生じた不平等
今回のフロリダ州の選挙では正当な投票権を持ち投票する意思のある者の多くが投票できずじまいあるいは、票が有効に数えられなく、結果的に選挙権が奪われた形となっていた。そしてその多くは黒人の票で、フロリダ州全体では黒人は白人の10倍も投じた票が有効に数えられていなかった事となる。この結果は教育レベルや識字率との関係は低く有効とされなかった黒人票の1%の釈明にしかならない。明らかとなった原因の一つに、各地区によって集計に使用された機器が異なっていて、貧しいマイノリティーの多く住む地域では性能の悪い集計機が使用され、白人が多く住む性能の良い集計機と比べ前者は8票に1票、有効票を無効票としてしまうのに対し、後者は1000票に2票あるかないかという大きな差があったためである事が挙げられる。しかし、同一地域内で教育も考慮に入れても人種と無効票数の間の関連性は弱まるもののまだ見うけられた。しかしこれは、民主党の後押しにより多数の黒人がはじめて投票を経験する者が多く、経験豊かな投票者よりもはじめての投票者の方が間違った投票の仕方をしてしまったとも原因として考えられる。
また投票所では身体的な障害をもった人や語学能力に問題がある人にも他の人と同様に投票する権利がある。そのためフロリダ州法によっても投票所はバリアフリーになっていなければならないが、40%近くの投票所では障害者が投票するには問題がある施設であった。実際身体的な障害を持った人の投票率は一般のそれよりも15から20%低い。英語を読み書きできない人にも職員が手助けしなければいけないが、多くの場合そのような処置は採られなかった。またフロリダ州法によって投票者は5分以内に投票しなくてはいけないため、このように語学に不自由がある人は充分に選挙権を発揮できたとは考え難い。
(二) 人のミスによって発生した不平等
さらに選挙の当日も、投票所へ行くと通知なしに投票所が移動したりして、予定の時刻よりも早く投票所が閉まっているところもあった。中には投票所にはたどり着いたものの、指定の投票所の名簿に自分の名前が無く、投票所の職員が登録を確認するため選挙管理局へ連絡しょうとしても電話が引っ切り無しに話中などで連絡がつかず、結局選挙権を奪われてしまった。そのため通常投票しようとする人が本当に登録されているかどうか疑いがある時に宣誓書を提出してから投票する(affidavit voting)という形式も採られない事が多かった。とりあえず投票をして投票者の正当性が確認されるまでその票が数えられない仮投票(provisional voting)もフロリダ州では認められていないため多くの正当な投票権を持った人は成すすべも無く投票を妨げられた事となった。そしてこのような形で選挙権を侵された者の正確な数は把握する事ができない。
この名簿に名前が無かった人の何割かはMotor Voter Lawと呼ばれる投票登録者を積極的に増やすために免許更新などの時に投票者登録を行った人で、選挙管理局とDHSMV(Department
of Highway Safety and Motor Vehicles)の連携が上手く作動しきれていない事を表している。またDHSMVで住所変更などを行ってもそれが選挙管理局に自動的に通知されるわけではないが、登録者はそれを知らない事が多いく混乱が起こりやすい。また不在者投票を希望した者で結局何も送られてこず、当日投票しに行こうとすると不在者投票したと名簿には記載されていたため、投票できずにいた人や不在者投票を申請していないのに不在者投票が送られてきた人もいた。何人かの人はブッシュ知事から郵便で投票するようにとの手紙を受け取っていたが、フロリダ州では郵便で投票することは許されていない。
他には黒人の多い地域の投票所の近くで許可されていなかった検問が行なわれていたりして、投票へ行くのを威嚇されていると感じる人もいた。しかし、このような威嚇ともとれる行為はフロリダ州の選挙規則に反し、投票所の近くに警察官などを配置する事も禁止されていてフロリダ州のハイウェイパトロール(FHP)の意図が問題となるが当のFHPはそのように選挙法違反はあったものの誰も投票することを威嚇によって止められたりはしなかったと話している。
(三) 責任の所在
では、選挙管理は誰の責任となるのか。公正な選挙が行なわれるための選挙法があり、知事がそれが運用される事を保障し、選挙管理委員が実行する。しかし、この法は活用の仕方によりほぼ存在しなくも絶大な権限を持つ事も可能なのである。また誰が最終的な責任を持つのかが元々曖昧であるのに、今回知事のジェブ・ブッシュは実の兄が大統領候補者であったことから積極的に選挙管理に関わらないようにしていたため、一層責任が何処にあるのかが分かりづらくなった。
フロリダ州の選挙制度について具体的に述べると、フロリダ州は67の郡と呼ばれる地区に分かれているが、日本とは違いその区域内に市も含みうる。また、基礎的地方自治体である市町村と比べ、州の出先機関的色彩を備えた地方行政単位であるが、選挙で選ばれる5_7名の委員から成る郡評議会は条例制定権限を持ち、限られているとはいえ政府としてのある程度の独立性を備えている。
選挙はこうした「郡」単位で行われる。郡内は多数の区に分けられており、選挙で選ばれる郡選挙管理官は、選挙実施の総責任者として、実際に選挙に当たる区毎の委員会を構成する役員を選任し、選挙の実施にあたらせる。郡の選挙に関する意思決定機関は、この郡選挙管理官、州裁判所の第一審裁判官一名、郡評議会議長で構成される郡選挙管理委員会である。選挙結果を確定させ、これに認証を与える権限もこの委員会にあり、選挙が州レベルのものである場合には、州の行政当局である選挙局に、結果を報告する権限と義務を負っている。ちなみにどのような投票方式を用いるかも郡が決める権限がある。
また今回の選挙で不平等が起きたのには財政的な問題も決して小さくない。州の選挙局は毎年予算を分け与えられているが、直接選挙管理委員会にはほとんど予算がつかない。そのためboards
of county commissionersや私的な財源に選挙のための職員の教育や機材の整備の予算をつけるように頼らなければならない。このような予算の少なさが選挙管理者に公正な選挙を遂行させる事を難しくさせた。
三 この選挙の波紋
- 選挙制度
今回の選挙、選挙制度そのものへの疑問の声も多く聞かれた。その中でも全米で一際大きな注目を浴びて、ニューヨーク州の上院議員に選出されたヒラリー・クリントン大統領夫人が、既存の12月11日CNNのLarry King Liveという番組で選挙委員団制を批判し、大統領直接選挙への憲法改正の必要性を宣言したことは、ゴア候補への実にタイムリーな援護射撃であった。一般得票数でブッシュ候補に勝っているゴア候補が負けるのは不自然だというメッセージを全米に発することで、手作業再集計への賛同を得ようとしたからである。ヒラリーの発言の巧妙な点は、あくまでも将来の選挙制度の変更を口にしながらも、実の狙いであるフロリダ州4郡での手作業再集計を納得させる理由をメッセージとして発信していたと言うこともあったが、選挙人制度に対する批判は多く聞かれた。
また選挙人制度は得票数で上まわっている候補が敗戦してしまう可能性があるだけでなく、選ばれた選挙人は必ずしも属している党の候補者に忠実に投票しなくてもいい場合がある点にも問題を抱えている。選挙人が忠実に投票する事は州法によって拘束する事ができるが、24州ではそのような制度は採られていない。そのため、2000年の選挙の得票数の結果を考慮して共和党側の選挙人が寝返り、民主党を勝利させてしまう事も可能なのであった。実際、元ニューヨーク州知事のマリオ・クオモ氏もCNNでフロリダ州の選挙人25人が共和党候補ブッシュに入ったからといって選挙の結果が確定したわけではないと示唆した。しかし、これに対しゴア候補のアドバイザー、ウォーレン・クリストファー氏はゴア氏はそのような圧力をかけるつもりは無いと話していて、実際そのような行為は行われなかった。しかし、このような事態が各州が自主的に選挙人の投票行動を拘束しない限り、現在の憲法で定められた選挙制度では不可能なのである。
既存の大統領の選挙制度自体は1804年の大統領と副大統領と別々に投票するという修正が加えられた以外、基本的な選挙制度は全く変化していない。しかし、選挙制度に対する不満がなかったわけではなく、1889年から1946年までの間には109件の憲法修正案が提出されていて、1947年から1960年の間にも99件もあった。また最近では2000年の選挙をのぞいて、1960年のケネディー対ニクソンの接戦によって大統領制度の議論が高まっており、過去にも得票率では上回りながらも敗北しているケースが3回ある。しかし大統領選挙制度は憲法によって定められているため、簡単には修正ができない。
また大統領選挙制度はアメリカの建国の歴史とも密接に関係している。合衆国憲法制定以前のアメリカの連合政府がもっていた政府機関は連合議会のみであり、権限がほとんど与えられていなかった。それは自ら直接支配できない政府は強い政府であってはならないという強い信念があったからであり、憲法制定そして中央政府が確立されてもその考えは引き継がれた。そのため中央政府の権限は制限されたものとなり、各州政府の存在が大きな意味をもった。そして大統領選挙制度を確立する上で国家議会による選出案、人民による選出案も考慮されたが、折衷案として選挙人による選出案が採用されることとなった。人民による直接選挙は国家議会の専制を抑圧し、行政首長の独立をはかり、行政首長を人民全体の利益の擁護者とすることを意図したものであった。しかしこれに対して、反対派は人民が大統領を直接選べるほど有能ではないと考えていた。当時はまだ交通、通信手段も未発達で、広大な連邦全体の行政権の長を選ぶにつき、一般の国民が果たして適切な判断を下せるかといった疑念があったのだ。そのため直接選挙のアイディアは良いが現実的ではないとの見方もあり、採用されなかった。
そしてこの選挙人制度は憲法に記され、法律のように改正するのは容易ではないため現在までこの選挙人制度が存続してきた。またこの選挙人制度はアメリカが合衆国である所以に存在するもので、州の重要性を有効的に保っているため、この制度が創られたときに人民の能力が軽視されていた事などを考えても安易に無くしてしまおうという議論も危険で今回の混乱はむしろ選挙制度から来る混乱よりも、選挙の運用のされ方にも問題があったと考える方が妥当であると感じる。
(二) その他の影響
憲法改正問題の議論をはじめる前にしかし、もっと容易に改善できる事は数多くある。フロリダ州では今回の混乱を受けて、2001年5月4日州の上下両院で投開票方式を州全体で統一する選挙システムの改革法案を圧倒的多数で可決した。
改革法案はパンチカード式投票方式などを廃止し、光化学式の投開票システムを導入することを盛り込んでいる。来年中間選挙での移行を目指し,設備導入費に2400万ドル,有権者・選管担当者の訓練費に600万ドルなどを予算に計上する。現大統領の弟であるブッシュ知事は改革法案を支持しており,近く署名して成立する見通しだ。
他の州も2000年大統領選挙の時は、フロリダ州を見て衝撃を受けたもののこのように具体的な動きが発生している州はほとんど無く、辛うじてジョージアやメリーランドが改革を行うことを承認しているが、充分な予算は付けられていない状態である。多くの州は国の予算から出してもらう事を期待しているようだが、いずれにしても2002年の3月までに資金が用意できないと2004年の大統領選挙までに、新しい機械を導入する事が難しいと見られているようだ。
さらに、全国レベルでは2000年の大統領選をきっかけにフォードとカーター両元大統領を代表とする超党派メンバーで連邦選挙制度改革委員会が設立され、2001年7月31日、ブッシュ大統領はこの委員会の選挙改革案を支持することを明らかにした。ブッシュ大統領はこの改革案の四つの根本的な考えは支持をしていて、ブッシュ大統領としては彼が主導権を握ってこの選挙改革を進めるよりは、議会がこの改革案を基に2001年秋にでも選挙改革の法案を通す事を期待しているようだ。
その四つの基本理念は以下である、
-
-
-
-
この改革案の具体的な案として注目すべきなのは、テレビ局などメディアは出口調査の結果の報道をアメリカ本土48州の投票が終了するまでアメリカ東部時間での午後11時まで自粛するように要請している点である。しかしこれに対してはメディア側からは公的機関の要請は自粛ではなく事実上の報道規制であるとして反発を見せている。
さらに、大統領選挙の一般投票を現行の11月の第一月曜日から、祝日である11月11日の退役軍人の日に変更する事や、投票の仕方を教育するための無料の放映時間の確保や選挙管理に掛ける予算をつける事や、大統領選挙での連邦政府の今まで以上の州への介入などが挙げられている。このように具体的な案の内容は論議を呼びそうなものも多く、大統領はこれらの内容を踏まえ、了承したうえで「連邦選挙に協力する州や郡の役割を妨げるような法律には反対する」との考えを示している。実際議会でこのような形の法案が通るのか、懐疑的な意見も聞かれているようで今後どのような展開となっていくのか注目される。
しかし2001年9月11日に起きた米同時多発テロからアメリカ国民はその一連の動きに関心が奪われ、選挙改革への関心が急激に落ち込んでいる事は確かである。2000年の12月に行れてたアンケートと同じものを2001年11月に行ったところ、「この国の投票、集計する器械は...その1.完全に交換しなければならない ‘00年:’01年→28%:19%、その2.大々的な改革が必要である→39%:24%、その3小規模な改革が必要である→27%:45%、その4改革は必要ない→4%:9%」という結果が出ていて、小規模な改革でいいのではないかと思っている人が2001年の11月の時点では45%もおり、その関心の低下具合が良く分かる。今後国際情勢の変化に応じてまた選挙管理改革問題が大きな関心ごととして浮上してくるのか、注目すべき点である。以下の円グラフ化された数値を見ると分かりやすい。(略)
その他に今回の選挙が違う面でもたらした影響としては、選挙予測とその方法論に対してもあった。2000年5月ワシントン・ポストのロバート・カイザー氏は数人の専門家に選挙予測を依頼した。この予測のパターンは96年の選挙のものとよく似ていて、二大政党間では民主党のゴア氏が53.5から59.6%のシェアを獲得するとの予想がでた。しかしまだこれは早い段階の予測に過ぎなかったが、8月のAmerican Political Science Association の年次集会で5月と同じ専門家と他数名によって言わば最終予測が出された。それによると、全員がゴアが勝利するとしてそのシェアの平均値は56.0%であった。またどの結果も確率的には90%を超えていた。つまり100回選挙があれば90回以上はゴアが勝利するという予測であった。ゴア氏が得票数で辛うじて上回っていた事を考えるとこの予測は当たっていたとも言えそうだが、シェアがわずか50.2%で危うい結果であった事自体が予測から外れていた。また今回の選挙予測で使用されたモデルの過去の成績を加味すると5.8%の誤差は非常に大きな値であった。どうやら今回の選挙は選挙予測においても混乱を起していたようで、今後の選挙予測に何らかの影響を与える事は間違いなさそうである。
結章
2000年の大統領選挙は正に引き分けといっても過言ではないほどの接戦であった。そしてこれを制したのはG.W.ブッシュテキサス州知事であった。しかしこれまで述べてきたように、この選挙は多くの問題点を含んでいた。なぜブッシュはこの選挙で勝利したのか。
正当性という観点からみるとブッシュはフロリダ州で公式に採用された票の集計結果をベースとし、また連邦最高裁判所の判決によりその票の再集計方法も正当性を持ったものになった。そしてアメリカ合衆国特有の選挙人制度によってブッシュは得票数で負けながらも大統領となり得た。この点に関しては誰もがブッシュが当選した事の正当性を否定することができない。しかし、正当性があるからといってこの結果が平等な条件の下の選挙とは決して言えない。
まず、第一章でも述べた裁判と再集計の責任者がその立場の権限を使って極めて政治的な判断を下す事が可能であった。そしてこの主要な決定を下せる立場に共和党支持者が位置していた事がブッシュの有利に働いた。このことは結果的に見れば、選挙の行方を左右するものではなかった。しかし、ゴアが手集計によって逆転勝利を収めることを可能性があった時点でそれを封じ込めてしまったためこれもブッシュの勝因の一つに数えたい。
次に選挙管理が杜撰なために民主党支持者の票が共和党の票よりも遥かに多く有効として数えられなかった事が挙げられる。そして長年の予算不足により、職員そして投票者に対する十分な教育が行われていなかった事が、結果的に民主党の後押しによりはじめて投票に向かった多くの人々の票を無効票としてしまった。杜撰な選挙管理からくる様々な障害も投票の機会をどれだけの人から奪ってしまったかは図り得ない。さらにメディアに対しても規制がなされていないため、早い段階で出されたゴアのフロリダ州獲得宣言はこれから投票しに行こうとしていた人々を止めてしまった可能性も否定できない。
このように小さな不平等が重なり合って、結果的にブッシュ候補への大きな力となってしまったのだ。
また2000年の大統領選挙の反省を活かすために、第三章で述べたような選挙改革の動きが出てきているという事は、何よりも今回の選挙はやはり公正を欠いていたと人々が感じているという証拠ではないだろうか。そして、12月12日の最高裁判所の判決が方の下の平等という理念そって出されたものだった事を考えると、選挙管理の甘さから到底平等とは呼べない基準で出した数字がその判決によって採用されることとなったのはなんとも皮肉に感じる。もしもっと前から選挙の重要性に気がついていれば、今回の問題は半減していたであろう。しかし、この接戦で今まで蓄積していた問題が一気に表面化し、法の下での平等な選挙の実施に向けての動きができたことはせめてもの救いである。
また杜撰な選挙管理はフロリダ州に限られた現象ではなく、アメリカ全土で早急な選挙管理を整える必要がある。その点でフロリダ州はどの州にも先駆けて具体的な選挙改革策を明確にした事は評価できるであろう。
|
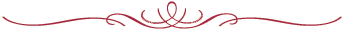
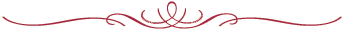
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)