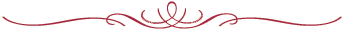比例代表制での当落の決定方法として「ヘア・ニーマイヤー式」、「ハーゲンバッハ・ビショフ式」、「サン・ラグ式」、「ジェファーソン式」、「クオータ式」、「ドント式」その他がある。日本が採用してるのは「ドント式」。これは、ベルギーの数学者のヴィクトル・ドント氏が考案したもので、それぞれの政党の得票数を「1、2、3‥‥」という整数で順番に割り算していき、その数の大きい順に議席数を振り分けていく方式である。
分かりやすく例を挙げて説明すると、A党が3000票、B党が1600票だったとする。そして、この得票数を、議席定数に応じて1、2、3で割る。1で割ると、A党は3000、B党は1600。2で割ると、A党は1500、B党は800、3で割ると、A党は1000、B党は533、4で割ると、A党は750、B党は400、5で割ると、A党は600、B党は320となる。これを議席定数に応じた数字の多い順に議席を振り分けていく。議席定数が3の場合、A党の3000と1500、B党の1600が上位3つとなり、A党は2議席、B党は1議席を獲得する。議席定数が4の場合には、A党が3議席でB党が1議席になる。但し、議席定数が5の場合には、A党3議席、B党2議席になる。
次に、B党の投票数を、A党の半分より少し少ない1400票だったとする。1で割ると、A党は3000、B党は1400。2で割ると、A党は1500、B党は700。3で割ると、A党は1000、B党は466。4で割ると、A党は750、B党は350。5で割ると、A党は600、B党は280となる。議席数が3の場合も4の場合も例と変わらないが5の場合は違ってくる。数字の多い上位5つを抜き出すと、A党が4議席でB党が1議席になる。即ちB党の得票数が1600票と1400票、わずか200票の違いで、A党は3議席から4議席へ増え、B党は2議席から1議席へと減る。これが「ドント式」である。
ここに、B党よりも小さいC党が参入してきたとする。C党の得票数は700票とする。1で割ると、A党は3000、B党は1600、C党は700。2で割ると、A党は1500、B党は800、C党は350。3で割ると、A党は1000、B党は533、C党は233。4で割ると、A党は750、B党は400、C党は175。5で割ると、A党は600、B党は320、C党は140となる。議席数が3の場合は、A党が2議席、B党が1議席で、C党は議席を獲得できない。議席数が4の場合は、A党が3議席、B党が1議席で、C党は議席を獲得できない。議席数が5の場合は、A党が4議席、B党が2議席、C党は議席を獲得できない。議席数が6の場合は、A党が4議席、B党が2議席で、C党はやっぱり議席を獲得できない。
それでは、与党であるA党に対して、野党のB党とC党が共闘して「D党」を結成したらどうなるか。1で割ると、A党は3000、D党は2300。2で割ると、A党は1500、D党は1150。3で割ると、A党は1000、D党は766。4で割ると、A党は750、D党は575。5で割ると、A党は600、D党は460。6の場合には、A党は500、D党は380。****。A党が3議席になり、D党も3議席になる。B党とC党の野党がバラバラに戦ってた時は、与党のA党が4議席、野党は2議席だが、B党とC党が協力して戦ったら、同じ得票数なのに与党のA党と並ぶ議席数を獲得することができることになる。
「きっこのブログ」の「2013.07.25 3年後の参院選に向けて」は次のように述べている。
|
もしも、社民党、生活の党、新党大地、緑の党、みどりの風の5党が手を組んでいたら、得票数の合計は「361万票」になるから、「361 180 120」となり、この「脱原発連合軍」が3議席を獲得して、この一覧の中で最も低い数字の2議席、自民党の102と民主党の101がそれぞれ落選してたことになる。自民党の最下位の102ってのは、そう、「ワタミグループ」の元会長の渡邊美樹氏だ。そして、「脱原発連合軍」の落選した候補者の中では、最多の17万6000票を集めた緑の党の三宅洋平氏と、もう1人が当選してたことになる。 ‥‥そんなワケで、一見、公平で公正なように見える「ドント式」だけど、この例からも分かるように、大きな政党には有利になり、小さな政党には不利になる面もある。特に、今のように与党の自民党の勢力が絶大で、それに対抗できる野党が見当たらないような状況では、なおさら「ドント式」は野党には不利になる。日本共産党が他の野党と手を組むことは現実的にはアリエナイザーだけど、イデオロギー的なことは抜きにして、とりあえず「脱原発」を掲げてる野党がすべて手を組んでいたとしたら、今回の得票数のままで、自民党の議席数を半分近くも減らすことができたのだ。国民の7割以上が「原発ゼロ」を望んでいるのに、何の反省もなく原発を推進する厚顔無恥な自民党などを圧勝させてしまったのは、野党が国民の声の受け皿になりえていなかったからだ。野党が1つにまとまらずに票を分散させてしまったからだ。だから、本気で「脱原発」を目指している野党は、3年後の参院選に向けて、この辺のこともシッカリと考えてほしいと思う今日この頃なのだ。 |