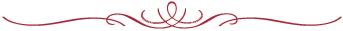
| 6期 | 第二次世界大戦緒戦期、中盤期までの歩み |
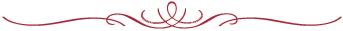
更新日/2020(平成31→5.1栄和元年/栄和2).1.18日
この前は、「第三帝国時代から第二次世界大戦突入までの歩み」
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 1939(昭和14)年、50歳の時 |
| 【第二次世界大戦開始】 |
| 同盟を結んでいたイギリス、フランスもドイツに宣戦布告。これによって第二次世界大戦を開始する。 ポーランド援助条約により英仏はあらゆる手段によって軍事援助を行う定めになっており、開戦初日にはドイツへの爆撃、15日目には大規模な攻勢を開始することになっていた。当時西部国境のドイツ軍はほとんどが2線級の34個師団、装甲師団は1個旅団戦車50両、空軍は50機ほどの手薄な配備になっていた。ヒトラーは英仏が西部国境で攻勢に出ることは無いと踏み、将軍連の反対を押しきりほとんどの戦力をポーランド作戦に投入したためである。 |
9.3−4日、大西洋で、英巡洋艦「アジャックス」が、ドイツ商船「オリンダ」「カール・フリッツェン」を撃沈。9.4日、英客船「アセニア」がドイツUボート(潜水艦)U30に撃沈され128人が死亡、中立国のアメリカ人28人が犠牲になった。アメリカを刺激することを恐れたヒトラーは攻撃はイギリスの陰謀と主張し客船の攻撃を禁止する(11月に解除)。9.17日、U29は英空母「カレイジャス」を撃沈。
| 【英仏、対独宣戦布告】 |
|
9.3日、英仏、対独宣戦布告。 イギリス、フランスはドイツに宣戦したものの、ドイツへの本格攻撃は行われずポーランドは短期間で降伏した。イギリスはフランスが動かないため共同作戦を理由に全面戦争をためらい、フランスは国境に築いたマジノ要塞線から出てこようとはしなかった。 |
9.7日、フランスはザール地方でごく小規模の消極的な攻撃をしたのみで、英仏の後ろ盾をあてにドイツに譲歩しなかったポーランドを見殺しにした。ヒトラーの賭けは的中し英仏は西部国境から攻勢をかけることはなかった。フランス軍は西部国境に102個師団、戦車2500両、空軍1200機を配備しており、イギリスも3個師団を派遣していた。英仏がこの好機をとらえて攻勢に出ればドイツ軍は危機に陥っただろう。
9月中旬、フランス軍総司令官モーリス・ガムラン元帥は、ポーランド軍総司令官に「東北フランス戦線では、軍の主力の半分以上が戦闘に入っている。ドイツ軍は猛烈な抵抗を試みているがわが軍は前進を続けている。ドイツ空軍の大部分をわが軍はひきつけている」と同盟を反故にした事を取り繕うためかウソをついた。この時既にポーランド軍は壊滅していた。
9.17日、 ソ連軍、ポーランド東部に侵攻開始。 独ソ間で「ポーランド分割」。
| 【ナチスの迫害と虐殺】 |
| その過程で、ポーランドのアウシュビッツに監獄が開かれる。ユダヤ人、シンティ・ロマ(いわゆるジプシー)、ロシア人・ポーランド人・セルビア人などのスラヴ人、精神障害者、身体障害者、同性愛者、ナチスに抵抗する人々に対する言語に絶する迫害と大虐殺(破壊と殺戮)を行った、とされている。 |
| 【ドイツ軍の緒戦の勝利とその後の戦局】 |
|
ドイツ軍は開戦当初の「電撃戦」が効を奏し、およそ1カ月でポーランドを占領するなど戦局はヒトラーの思うとおりに運び、一時、ナチの占領下もしくは親独政権下におかれた地域は、中立国(スイス、スウェーデン、トルコ)を除くヨーロッパ大陸部のほぼ全域に及んだ。 |
10.6日、ヒトラーは、英仏に対し戦う意志がないと声明、講和会議を提案するが、もはや英仏は乗ってこなかった。この間西ヨーロッパでは大きな戦闘が止み「奇妙な戦争」「まやかしの戦争」と呼ばれた静寂が訪れた。
10.14日、U47(ギュンター・プリーン艦長)は英スコットランド北方スカパフローの泊地に侵入し戦艦「ロイヤル・オーク」を撃沈し帰還。
| 【ヒトラー暗殺事件その二】 |
| 11.8日、ヒトラーは、1923年の「ミュンヘン一揆」を記念するミュンヘンのビアホール、ビュルガーブロイケラーの毎年恒例の集会に出席、例年より早く演説を終えて退席した。その十数分後の午後9時20分、ヒトラーが演説していた演壇の背後の柱に仕掛けられた時限爆弾が爆発。古参党員とウエイトレスの8人が死亡し、エバ・ブラウンの父親を含む63名が負傷した。 犯人は強制収容所から釈放されていた、ゲオルグ・エルザーという家具と時計の職人だった。エルザーはスイスへ出国しようとし、旅券の期限が切れていたため取り調べを受ける。その際ネジやビュルガーブロイケラーの写真を所持していたため拘束された。しかし、その時点で事件との関連を疑わせる物を持っていたのは不自然にも思える。ヒトラーは危ういところで難を逃れた。 犯行は共産主義者だったエルザーの単独犯行説、NSDAPの自作説、イギリス諜報機関の陰謀説などがあり今日でも真相は不明。エルザーの裁判は開かれず、ただちに処刑されず終戦直前の1945.4月に秘密裏に処刑されたことも謎を深めている。ヒトラーはこの後も44年の事件を始め、数々の暗殺計画を強運で乗り切ることになる。 |
11月、タラント港のイタリア艦隊は英空母「イラストリアス」を発進した雷撃機の攻撃を受け大損害を蒙る。ヒトラーは盟友の勝手な冒険とふがいなさにあきれたが、このままほっておくわけにもいかず、北アフリカとバルカン半島へ軍を送る。
| 【ソ連が参戦】 |
|
11.30日、独ソ不可侵条約によってヒトラーとの対決を先送りしたソ連は、互いの勢力圏を定めた秘密議定書に基づきフィンランドにカレリア地方割譲と軍事基地租借を要求。拒否されるとこの日宣戦布告なしに攻撃した。 |
12.13日、通商破壊作戦中に9隻の商船を沈めたドイツポケット戦艦「グラーフ・シュペー」(28センチ砲6門、11,700t)がラプラタ沖で英・ニュージーランド巡洋艦3隻と交戦、「エクセター」を大破させたが損傷し中立国ウルグアイのモンテビデオに停泊、英艦隊に包囲されたと誤認したラングスドルフ艦長は、17日艦を自沈させ自らは自決した(ラプラタ沖海戦)。
| 1940(昭和15)年、ヒットラー51歳の時 |
ドイツ軍部は再びフランスと戦うことを予想し、早くから戦略を研究していた。西部作戦の最大の敵は陸軍大国フランスであった。フランスは、第1次大戦でベルダンを守りぬいた勝利を経験にマジノ要塞(発案者の陸相アンドレ・マジノの名にちなむ)と呼ばれる320キロに渡る長大な要塞を、1930年代初めからばく大な費用と時間をかけてドイツとの国境沿いにスイスからモンメディまでに建設し、この要塞によってドイツのいかなる攻撃も阻止できるという自信を持っていた。
反面、要塞に頼った戦略は防御的になり予算を要塞に取られ軍隊の装備の近代化を遅らし、指導部は新しい戦略思想に冷淡になっていた。政情は不安定で政府は短期間に政権を交代、暴動やストが頻発し国民には厭戦の風潮が強かった。
これに対しドイツは第1次大戦で戦車によって大打撃を受けた戦訓から、要塞よりも装甲部隊による機動力と火力を生かした思想を具体化している。フランス攻撃のプランは1939.1月の案ではマジノ要塞の無いオランダ、ベルギー方面へ攻撃の重点を置き(B軍団)、マジノ線方面(C軍団)と、両方の中間(A軍団)に兵力を3分して侵攻するというものだった。A軍団の参謀長フォン・マンシュタイン中将はこの第1次大戦と同じ作戦(シュリーフェン計画)に不満で、新作戦をグデーリアン将軍と立案し総司令部に提出する。新作戦は攻撃の重点をA軍団に当たらせ、ソンム川に進む。戦車が通れないとされているベルギーのアルデンヌ森林地帯を通過し、セダン付近の比較的脆弱な防衛線を突破し、オランダ、ベルギー方面へ向かう連合軍の側面を攻撃するという冒険的な作戦だった。総司令部はいったんこの案を却下し、マンシュタインを歩兵軍に転属させた。
1.9日、作戦計画書を持った少佐が乗る連絡機がベルギーに不時着する事件が起き、作戦の変更を要求されることになった。マンシュタイン案はヒトラーの目にとまり、ヒトラーはこの案を自身で強く押し採用させる。
2月、ソ連軍が戦術を改め部隊を再編して兵力、冬季装備を増強して再び攻勢をかけると、さしものフィンランド軍も追いつめられ、2.14日には防衛線マンネルヘイム・ラインを放棄、3.13日には講和に応じる。フィンランドは第2の都市ヴィープリを含め、カレリア、ラドガカレリア、サツラなどの領土をソ連に割譲したが、英仏の軍事介入を恐れたソ連は傀儡政府を引っ込め、国家の独立をかろうじて守ることができた。
ソ連のぶざまな戦いぶりはドイツにソ連軍弱体の印象を与え、赤軍は「冬戦争」の冬季戦の教訓を後の独ソ戦に生かす。
イギリス、フランスが攻撃してこないことで第1次大戦時のような膠着した塹壕戦を避けたいヒトラーは、自分から攻勢に出ることを決意した。まずルクセンブルク、ベルギー、オランダを通るフランス攻撃の作戦立案を命令。その前にスウェーデンからの鉄鉱石輸入と、海への出口を確保するため海軍の要請でノルウェー、デンマークへの侵攻に向った。
4.9日、ドイツ軍、ノルウェー侵攻開始、無血占領。 ドイツ軍、デンマーク無血占領。ヒトラーはノルウェー侵攻作戦「ウェーゼル演習」の陸軍司令官にフォン・ファルケンホルスト将軍を任命し、その日の夕方までにノルウェー占領計画を作るよう命令した。将軍は急遽市販の旅行案内を買い、作戦を考えることになった。ヒトラーはこの作戦計画に満足し、作戦実行を命じた。
デンマークは装甲部隊の侵攻と降下猟兵(空挺部隊)の奇襲を受けほとんど抵抗せず、9日の昼には大勢が決まり国王クリスティアン10世と政府が降伏。ノルウェーは奇襲攻撃が悪天候で遅れ、オスロを逃れた国王ホーコン7世は降伏を拒否し、確保していた北部の小さなラジオ局から国民に抵抗を呼びかけた。英海軍はノルウェーの領海に機雷を敷設する作戦を計画していたがチェンバレンの反対でドイツ軍に先を越された。
| 【ソ連軍による「カチンの森事件」発生】 |
| ソ連軍は捕虜にしたポーランド軍将校数千人をスモレンスク付近のカチンの森で殺害して埋めた(この虐殺は後の独ソ開戦後、同地を占領したドイツ軍によって発見される。ソ連は長らくドイツの仕業と主張したが、ゴルバチョフ政権下で初めて、「1940.4月ごろ秘密警察NKVDによる虐殺」を認めた)。 |
5.10日、ドイツ軍、西部戦線に総攻撃開始。
中立国のオランダ、ベルギー攻撃は英仏の援軍がくる前にかたづけるためスピードが要求される。 オランダのハーグ郊外の3つの飛行場には降下猟兵部隊が着陸して政府と王室の確保を図ったが薄暗い中で目標を遮られ、激しい抵抗を受けて確保に失敗。ロッテルダムのマース川には水上機12機で着水し、スポーツスタジアムとヴァールハーフェン飛行場に降下した降下猟兵がヴィレム橋を確保した。
「ロスチャイルド家の代理人チャーチルの反撃」によると、次のように記されている。
|
| 【イギリスにチャーチル政権登場】 | |
| 5.10日、イギリスで、ドイツ軍の快進撃に衝撃を受け宥和政策を取ったチェンバレン首相が解任され、海相ウィンストン・チャーチルが首相になる。チャーチル内閣成立。イギリスの首相がチェンバレンからチャーチルに交代した時点から、天下分け目の真の世界大戦になった。(チャーチルに就いては、「ロスチャイルドの代理人チャーチル考」参照) 「ロスチャイルド家の代理人チャーチルの反撃」は、次のように記している。
|
| 【この頃のドイツとイギリス、フランスの軍事的バランス】 |
| 連合国軍とドイツ軍の兵力は数の上ではほぼ互角で、ドイツ軍136個師団、連合国軍135個師団であり、主力戦車の数と火力、装甲の厚さなどはむしろ連合国側が優っていた。しかし装甲師団の戦車はドイツが戦車を指揮官の無線通信下で、集中して投入する戦術を確立していたのに比べ、連合国側では戦車は歩兵に付随して運用するものであるとする旧時代的な戦術を採っており、フランスの機甲師団は編成されたばかりだった。 また、連合国側は統一した作戦司令部が機能せず、ベルギー(22個師団)、オランダ(10個師団)は中立政策を取っていたため開戦前の協調も取れなかった。また植民地から来た兵士や、急遽徴兵されたフランスの兵士は高齢者や労働者で訓練不足で士気も低かった。 ドイツ軍は統一された作戦司令部と優れた指揮官に恵まれ、革新的な装甲部隊により戦車の有効な運用を行い、良く訓練され実戦経験のある兵士は士気も盛んだった。 フランスの軍指揮系統は複雑極まりないもので、総軍参謀長と北東戦線最高司令官の肩書きを持つジョルジュ将軍と総司令官(連合軍総司令官を兼任)モーリス・ガムラン元帥は離れた場所に別々の司令部を持ち、ガムランがパリ近くの中世の城「シャトー・ド・ヴァンセンヌ」に置いた連合軍総司令部には無線さえ無く、命令が前線まで届くのに2日を必要とした。 |
5.10日、ベルギー軍は幅60メートルもあるアルベール運河の橋を落としてドイツ軍戦車を阻止すべく、橋には守備隊を配置し爆薬を仕掛けて、東から来る筈のドイツ軍を警戒していた。しかし、ドイツ軍降下猟兵部隊はグライダーで運河を超えて着陸し、西から橋を渡って来た。あっけにとられた守備隊は橋を爆破するひまもなく掃蕩された。一週間はドイツ軍を食い止めるはずだったアルベール運河は作戦初日にドイツ軍の手に落ちた。ベルギーの交通の要衝にあり約1200名の守備隊がいたエバン・エマール要塞は、降下猟兵75名がグライダーによる奇襲攻撃をかけ、要塞は成形炸薬によって無力化され1時間で占領される。この奇襲作戦はヒトラー自らの発案によってなされた。
ベルギー、オランダ方面が主戦場になると判断したフランス軍主力、ウィリアム・ゴート大将のイギリス大陸派遣軍は北上し、防衛計画に沿ってベルギーのディール河でドイツ軍を防ごうとするが、ドイツ軍装甲部隊7個師団はアルデンヌ森林地帯を踏破し、防衛線の弱体な陣地を突破した。
5.11日、フランス軍偵察機はドイツ軍部隊の縦列を発見したが、アルデンヌ森林地帯は戦車の通過は不可能だと思い込んでいた司令部は報告を無視した。空軍のJu87「スツーカ」などの急降下爆撃でフランス軍は地上戦の前に大損害を受けた。フランス軍機甲部隊は背面、側面から攻撃を受け要塞の砲台と、戦車の厚い装甲を生かした戦闘が出来なかった。
5.12日、オランダ、マーストリヒト近郊のドイツ軍が確保するアルベール運河の橋をイギリス空軍のフェアリー・バトル軽爆撃機6機が攻撃するが、対空砲火に遮られ全機が未帰還となる。同日、セダンではフランス空軍のカーチス・ホーク75戦闘機がJu87急降下爆撃機16機を撃墜。フランス空軍は多数の航空機を持っていたが雑多な機種を運用し、Bf109に対抗できるドボワチンD520は数が少なく、多くは時代遅れの機種だった。1940.5月には2千機を持っていたが作戦は不活発で使用されたのは500機に満たないとされる。ドイツ空軍のフランス戦線の戦力は2670機で約千機は戦闘機である。
5.13日、オランダ、ロンドンに亡命政権樹立。
ドイツ軍がミューズ川を渡り、橋頭堡が築かれる。グデーリアン、ホト指揮する19、15装甲師団は川を渡ったものの、フランス軍の反撃を受け進撃が停滞し、ラインハルトの41装甲師団は渡河が遅れていた。しかしフランス第9軍司令官コラーブは前線からの新鮮な情報を得られず、ドイツ軍司令官のように前線を見て自ら情報を収集することもしなかったので的確な情勢判断が出来なかった。仏第9軍の援護のため第1機甲師団は200台の戦車を擁してミューズ川を渡河したドイツ軍の前面に到着したが、ブリュノー将軍は司令部からの反撃命令を待っていた。しかし、第11軍司令官の命令を受け、第9軍に命令の修正の許可を得てふたたび第11軍司令官の命令を待っていたが第11軍司令官は移動して連絡が取れなかった。仏戦車は空しく待機したが予備燃料を持っていなかった。
5.14日、第9軍は戦線を維持していたが悲観的な情勢判断をしたコラーブは、第9軍に撤退を命じた。撤退は壊走となり、ドイツ軍は堰を切ったようにフランス領内を従来の軍事常識を超えた速度で突進した。同日、普仏戦争でナポレオン3世がプロイセン軍に降伏した古戦場でもあるセダンが占領される。
5.14日、ロッテルダムが爆撃を受け大火災が発生。ウィルヘルミナ女王はイギリスに逃れ、オランダはわずか5日で降伏。
5.14日、グデーリアンはクライストにセダンで停止して歩兵部隊の到着を待つよう命じられたが、奇襲の効果が損なわれるとしてこれを無視して威力偵察の名目で前進を続けた。
5.16日、パリで、フランス首相ポール・レイノーと会談したチャーチルは、「フランスは敗北を喫した、総崩れだ」と泣き言を言われ、戦闘機の派遣を求められた。チャーチルが「予備兵力はどこに?」と尋ねると「1つもない」と返事をした。
5.17日、ランではドゴール大佐が戦車をかき集めて新設した仏第4機甲師団が反撃するが、ドイツ第1装甲師団に阻止される。同日ベルギーのブリュッセルが占領される。
5.18日、ガムランに代わってレバノンから呼ばれたマキシム・ウェイガンがフランス軍総司令官に就いた。しかしウェイガンも73歳と老齢で会議だけに時間を消費した。
連合軍主力は、ドイツA軍集団がセダンを占領し、5.20日、大西洋に望むアベヴィーユへ到達したことによりドーバー海峡側に分断されてしまい補給を受けられなくなった。英ゴート大将はフランス側に戦線を突破すべくドイツ軍に反撃を計画、アラスに英仏混成部隊を集結させた。
5.21日、アラス近郊でエルヴィン・ロンメルの指揮する第7装甲師団は側面からフランス、イギリス軍戦車部隊の反撃を受けた。味方の戦車は前方におり、英仏軍の「マチルダ」(40ミリ砲装備)、「ソミュア」(47ミリ砲装備)戦車の装甲にはドイツ軍の37ミリ対戦車砲では歯が立たない、前方から引き返してきたドイツ戦車も機銃のみの2号戦車とチェコ製の37ミリ砲装備の38(t)戦車で、英仏軍の40ミリ対戦車砲で撃破され、ドイツ歩兵部隊は危機に陥った。
ロンメルは急遽、対空砲だった88ミリ砲の水平射撃を命じ(高射砲を対戦車に使用するのはロンメルの独創ではない)英仏戦車を撃破、危機を脱した。ロンメルの師団は急速な移動と優れた用兵から「幽霊師団」と呼ばれた。
フランス将兵はいきなり現れたドイツ軍に戦意を失い、抵抗する間もなく続々と降伏した。装甲師団の急進撃にはドイツ軍司令部とヒトラー自身も驚き停止命令を出すほどだった。連合軍の主力はドイツ軍の目論見どおり北部にひきつけられ、北フランスとベルギーに包囲されてしまった。5月24日にはブローニュが陥落しドイツ軍はドーバー海峡に望むダンケルクまで24キロの地点まで到達、グデーリアンはダンケルク攻撃を準備。英10個師団、仏18個師団35万人の連合軍は逃げ場を失った。
しかしヒトラーは装甲部隊にダンケルク進撃を禁止。理由は明らかでないが、空軍のゲーリングが爆撃のみでせん滅できると進言したためとも、戦車に不適な海岸の砂地で装甲部隊の消耗を懸念したルントシュテット将軍の進言のため、イギリス兵を逃がして和平の環境を作りたかったとの説がある。ともかく連合国兵は装甲師団の攻撃停止の間に空爆と砲撃を受け、駆逐艦9隻など多数の艦船と航空機302機を失いながらも民間のヨットや漁船まで撤退に動員。一部のフランス兵は勇敢に橋頭堡を死守し時間を稼ぎ33万8千人が海路イギリスへの脱出に成功する(ダイナモ作戦)。
5.27日、イギリス軍、ダンケルク撤退開始 (06/04 撤退完了)。
5.28日、ベルギーが降伏。国王レオポルド3世は国民と苦難を共にする決意で国に残った。
6.4日、ダンケルクは占領された。フランスの残存兵力は2線級の部隊で装備の完全な機甲師団は存在しなかった。
「ロスチャイルド家の代理人チャーチルの反撃」によると、次のように記されている。( 広瀬隆著「赤い楯」よりり)
|
| 【イタリアが英仏に宣戦布告】 |
| 6.10日、イタリアが英仏に宣戦布告。イタリアのムソリーニはドイツの勝利は確実と見て戦勝の分け前を得ようと、自軍の準備不足にもかかわらず瀕死のフランスとイギリスに宣戦した。「中立をとったらイタリアは大国の地位を今後100年間失うだろう」(ムソリーニ)。 ムソリーニは、ポーランド進攻の際にはヒトラーから事前に進攻を知らされていたが軍備が整っていないとして「非交戦国」に留まっていた。参戦2日後にも軍が進撃を始めないのにいらだったムソリーニは、参謀総長ピエトロ・バドリオに早く攻勢に出るように指令する。バドリオは「イタリア軍はシャツすらもっていないのですよ」と言った。ムソリーニは「そうだ、だが講和会議で栄光の席に座るためには数千人の死者が必要だということが君にはわからないのかね」と6.16日の全面攻撃を決めた。 |
6月、スターリンはバルカンで、ルーマニアから北ブコビナ、ベッサラビアの2州を奪う。ルーマニアは第1次大戦では連合国側で参戦し自国の戦線では大敗したが、戦勝国となり各国から領土を得ていた。ベッサラビアは旧ロシア帝国領だが、ブコビナは旧オーストリア・ハンガリー帝国の領土だった。またブルガリアがドブロジャ南部を割譲要求しこれも容れた。ルーマニアは国王カロル2世が議会を封殺、独裁を行っていた。国王は当初、英仏寄りの中立政策を推進した。しかし、支援関係にあったポーランド、チェコスロバキア、フランスがドイツに占領されると、独ソの2大勢力に挟まれ中立は不可能になった。
| 【ドイツ軍、パリ入城】 |
| 6.11日、フランス政府はパリを捨てトゥール、後にボルドーと逃れ、6.12日、パリを戦火から救うため無防備宣言をした。 6.14日、ドイツ軍、パリ入城。ドイツ軍は厳正な規律の下パリに入城した。ヒトラーは兵士に略奪行為を厳禁し、解放者として振る舞うよう求めた。 6.16日、首相レイノーが辞任し、第1次大戦の英雄で84歳のフィリップ・ペタン元帥が首相に就いたが、全く戦意がなくもはや次の日には休戦を乞うしかなかった。フランスの休戦申し入れの報告を受けたヒトラーは、反射的に片膝を上げて喜びを表したがアメリカに渡ったニュースフィルムでは、この僅かな動作のフィルムのコマが増やされ、あたかもはしゃぎまわるかのように加工されて上映された。 |
| 【 ド・ゴール将軍がロンドンに自由フランス委員会設立】 |
| 6.18日、 ド・ゴール将軍、自由フランス委員会設立 (ロンドン)。 |
| 【フランスが降伏】 | |
| 6.22日、フランス(ペタン政府)降伏。国土の3分の2をドイツが占領。パリの北コンピューニュの森で1918年の第1次大戦休戦条約署名を記念して、保存されていた食堂車が展示室から運ばれ用意された同じ場所で、フランスのシャルル・ユンチジェル将軍とカイテル将軍が休戦条約に署名した。ドイツは、前大戦の屈辱を晴らした。 6.24日、イタリアとフランスが休戦条約に署名。フランスにとっては過酷な条約となり、ドイツへの捕虜(人質、労働力として)の抑留、占領費の支払いを要求された。アルザス、ロレーヌ地域は再びドイツ領になり、パリを含むフランスの5分の3はドイツとイタリア占領下に置かれ、残りの地域はペタンが鉱泉町ビシーに置いた政府が統治することになった。 ビシー政権は自由地域と海外の植民地の主権を認められ、海空軍と10万の陸軍を保持したが、ユダヤ人狩りなどあらゆる政策はドイツの意向に従わざるを得なかった。 休戦までのフランスの被害は死者16万4千、負傷者20万人。ドイツは戦死2万7千、負傷11万1千、行方不明1万8千人。ヒトラーは39個師団の動員解除を指示した。 6.28日早朝、ヒトラーは、パリを視察、西方作戦の成功で自らの軍事的能力への自信をいよいよ深める。パリを訪れたヒトラーはオペラ座を視察、エッフェル塔を見物し廃兵院のナポレオンの墓に詣でる。ヒトラーはウィーンに置かれていたナポレオンの息子ライヒシュタット公(ローマ王)の棺を父の傍らに移すよう命じた。今日もナポレオン父子がパリで共に眠っているのはヒトラーの計らいである。 「ロスチャイルド家の代理人チャーチルの反撃」は、次のように記している。
|
| 【イギリスが徹底抗戦】 |
| イギリスは、ヨーロッパを征服したナポレオンの前に立ちはだかった歴史を持つが、ヒトラーにも屈服しなかった。ヒトラーは再び和平提案を行うがチャーチルは断固戦い抜く決意であった。チャーチルはフランスが降伏した日「フランスの戦いは終わった、今やイギリスの戦いが始まろうとしている」と演説。イギリスは大陸に派遣した虎の子の比較的精強な部隊を失っており、軍備の拡充も遅れ、地方防衛義勇軍(LDV)に配る小銃さえ不足していた。ドイツ軍が勢いにまかせて上陸してくると対抗するだけの力はなかった。しかし海峡には圧倒的に優勢な海軍があり、アメリカからの戦略物資が届いている。またドイツ軍には渡洋作戦の経験も装備もなく、イギリス攻撃の戦略も作られていなかった。 ヒトラーは8月まで和平を工作したが、急遽イギリス上陸作戦「ゼーレーヴェ(あしか)」作戦の立案を命ずる。上陸作戦のためには制空権の確保が必要であり、制空権を確保すれば狭いドーバー海峡ではイギリスの海軍力を無力化できる。英空軍よりはるかに優勢なゲーリングの空軍は自信満々であった。後に「バトル・オブ・ブリテン」(英国の戦い)と呼ばれるイギリスの存亡を賭けた航空戦(およそ40年7月から9月まで)が始まる。 ドイツ空軍2300機に対し、ヒュー・ダウディング大将のイギリス空軍(RAF)はフランスに投入した450機の「ハリケーン」戦闘機を失い、旧式機を合わせても800機に満たない戦闘機で迎え撃たなければならなかった。しかし英空軍には新鋭戦闘機「スピットファイア」(最高速度570km/h、Mk1型)が続々と供給されており、レーダー(電波方向探信儀・RDF)を備えた防空組織が編成されていた。 |
| 【ヒトラーが国防軍最高司令官に就任】 |
|
7.31日、ヒトラーは国防軍最高司令官に就任し、作戦面でも戦争の最高指導者となる。 |
8月、スターリンは次にエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト3国に最後通諜を突きつけ、ソビエト連邦に加盟させ、併合した。
8.12日、ドイツ空軍はイギリスの飛行場やレーダー基地、港湾、軍事工場を目標に爆撃を始めた、「スピットファイア」、「ハリケーン」を主体とした英軍はレーダーに誘導されドイツ機に大きな損害を与えた。ポーランド、フランス戦で大きな効果を上げた急降下爆撃機Ju87は英戦闘機に対しては低速で大損害を受け早々に引き上げられた。
ドイツ空軍の主力戦闘機Bf109は元々局地戦闘機として設計され航続距離が短く、He111などの爆撃機を十分護衛できず、援護を受けられない爆撃機は英戦闘機に大損害を受けた。しかし英空軍は味方の損害を上回る撃墜を記録したものの、元々の数が少なくパイロットの補充もすぐには出来ず、亡命してきた元ポーランドやチェコ空軍操縦士の部隊まで投入したものの、連続の出撃でパイロットの疲労が重なり乗員、機体の損害も増えてきた。航空基地や情報を集める地区監視基地も爆撃で破壊され英空軍の戦力は尽き果てようとしていた。しかし、ドイツ空軍は攻撃目標を変更しロンドンを爆撃しだした。
8.23日、ドイツ爆撃機が航法ミスからロンドンを爆撃。イギリスは報復として翌日ベルリンを爆撃した。
「もしベルリンが爆撃されたら私はユダヤ人とののしられてもかまわない」と豪語していた空軍大臣ゲーリング国家元帥の面目は丸つぶれとなり、最初首都爆撃を禁じていたヒトラーは、9.4日、スポーツ宮殿での演説で報復を宣言。ロンドン爆撃によってイギリス国民の戦意を挫くよう命令した。
| 【ドイツ空軍がロンドン爆撃開始】 |
| 9.7日、ドイツ空軍、ロンドン爆撃開始。ロンドン空襲では最初の2晩で842人の死者が出、大火災が発生した。しかし爆撃目標がロンドンに変更されたことで英空軍の飛行場や飛行機工場は一息つくことが出来、再編の機会が与えられた。 9.15日、ドイツ空軍はロンドンへの昼間爆撃を加えるため約200機の爆撃機と約800機の戦闘機で来襲した。一方、レーダー基地への攻撃は効果が薄かったとして中止されてしまった。レーダーで攻撃を知った英空軍は迎撃し、激しい空中戦が行われた、航続距離の短いBf109戦闘機はロンドン上空でわずか5分しか戦闘が出来ず、爆撃機はほとんどロンドンに到達できずに撃墜されるか、遁走した。この日はドイツ側75機、英側34機の損害を数えた。ドイツは英戦闘機隊を撃滅できず、爆撃による効果よりも自軍の消耗が激しいことに音を上げる、 9.17日、ヒトラーはイギリス上陸作戦を事実上中止した。7.10日から11月末までにドイツ空軍の損失1733機に対し英空軍は915機。 |
9.17日、ロドルフォ・グラツィアーニ元帥のイタリア軍21万は、北アフリカの植民地キレナイカからローマ帝国の版図の再現を目指し、英領エジプト西方に7個師団で進撃、国境から100キロほどのシディ・バラニまで進撃したものの、装備と補給に乏しく、同地で陣地を構築して停止していた。
9.22日、フィンランドはドイツと協定を結び、資源の供給とドイツ軍の通過を認めた。
| 【日独伊三国軍事同盟調印】 |
| 9.27日、ベルリンで日独伊三国軍事同盟調印。日独伊三国の枢軸体制を強化し、米英に対抗した。日本代表は松岡洋右外相。来栖三郎駐独大使、ドイツ・ヨアヒム・フォン・リッベントロップ独外相、イタリア・チアノ外相がこれに署名した。 ヒトラーは、抗戦を続けるイギリス、イギリスに戦略物資を援助するアメリカを牽制するため、中国政策をめぐってアメリカと対決姿勢を強めていた日本、同盟していたイタリアとの枢軸同盟で対抗しようとした。 |
10.12日、 ヒトラー、英本土上陸作戦(あしか作戦)中止を決定。
10.13日、ドイツ軍はノルウェー南部を占領したが、オスロ攻略では重巡洋艦「ブリッヒャー」が撃沈され、この日のイギリス艦隊のナルビク攻撃でドイツ駆逐艦10隻、貨物船、補給艦が多数撃沈されるなどドイツ海軍の損害も多く、ナルビクでは一時ドイツ軍が孤立した。
10.23日、ヒトラー・フランコ(スペイン統領)会談。ヒトラーは、スペインとフランスのビシー政権を対英参戦させようとする。フランス、スペイン国境のアンダイでスペインのフランコ総統と会見したヒトラーは参戦を求めるが、フランコは内戦の損害からまだスペインが立ち直っていないとして、過大な食料・兵器と領土の見返りを要求し曖昧に参戦を拒否。英領ジブラルタル攻略のドイツ軍通過もまた断る。ただ、フランコは内戦時の借りがあり、鉱物資源を供給することは取り付けた。
フランコは後に独ソ戦が始まるとスペイン人義勇兵を送る(スペイン人義勇兵部隊、第250歩兵師団「青師団」は41から43年まで東部戦線で戦う)が、中立を守り参戦を拒否したことによりフランコは大戦終了後も冷戦の中で政権を維持することになる。ヒトラーはこの会談の結果に多いに不満で「もう一度、会談をするくらいなら歯医者で歯を3、4本抜かれるほうがましだ」と語った。翌24日にはビシー政権の国家元首になっていたペタンと会見するがここでも参戦させることは出来なかった。
10.28日、ムソリーニはドイツへの通告なしに併合していたアルバニアからギリシャへ侵攻。ムソリーニはヒトラーの鼻をあかしてやるつもりで、同日フィレンツェで会見したヒトラーに「2週間後にはアテネに行っている」と得意げに侵攻を初めて知らせたが、2週間後には21個師団のイタリア軍は13個師団のギリシャ軍に撃退されアルバニアに押し返されるという醜態をさらした。
11.14日、イギリスへの空爆は断続的に続き、新電波誘導システムを使ったこの日のコベントリー爆撃では同市の多くが破壊され、380人が死亡している。一説にはイギリス軍はドイツ軍の暗号(エニグマ装置)をウルトラと呼ばれた解読器によって解読し、コベントリーへの攻撃を予知したが、チャーチルは暗号解読の事実を知られないために市民への警報を行わなかったとされる。
11.12日、ヒトラー・モロトフ(ソ連外相)会談 (ベルリン)。
12.9日、停滞していたイタリアのアーチボールド・ウェーベル大将の2個師団3千600の兵員が攻勢に打って出た。しかし、英軍にたちまち押し返される。
12.18日、 ヒトラー、ソ連侵攻作戦(バルバロッサ作戦)準備を指令。
これまで互いの勢力圏を拡大してきた独ソ両国はついに緩衝地帯を食い尽くし、直接勢力圏を接することになった。ヒトラーはこの日、ソ連侵攻作戦「バルバロッサ」(赤ひげ=神聖ローマ帝国皇帝フリードリッヒ1世の名にちなむ)の準備を41.5.15日までに整えるよう命令した。
12月、第二次世界大戦開始時までにSSの隊員数は25万人に上り、その中からSS戦闘師団(SS-VT)が組織された。この頃、SS-VTは武装親衛隊に改名された。一方、一般SSは国防軍や武装親衛隊の補充に人員を取られ、終戦時には4万人程度の弱小組織になってしまう。また実行部隊と呼ばれる部隊はウクライナなどのドイツ占領地域において、劣等民族とされた住民を徹底的に殺戮した後にドイツ人を入植させてナチズムに基く人種政策を実行した。
第二次世界大戦末期ドイツの敗色が濃厚になると、連合国による非人道的行為への追及を恐れたSS指導部はアルゼンチンを拠点としてオデッサ(Organisation Der
Ehemaligen
SS-Angehorigen―「元SS隊員の組織」の頭文字)と呼ばれる逃亡者支援ネットワークを組織した。
「オデッサ」は教皇庁や米軍諜報機関などとのコネクションを使って「ラットライン」と呼ばれる逃亡ルートを築き、絶滅収容所へのユダヤ人移送責任者だったアドルフ・アイヒマンや、アウシュビッツで人体実験を行った「死の天使」ヨーゼフ・メンゲレ、ゲリラ攻撃を受けた報復にローマ市民400人の殺害を命じた大尉エーリッヒ・プリーブケ、「リガの屠殺人」と称された強制収容所長エドゥアルト・ロシュマンなど多くの戦犯が、これによってニュルンベルク裁判の追及を逃れてラテンアメリカに渡った。
1940年にはオランダ・ベルギー、ノルウェイ・デンマーク・長年の宿敵フランスを武力により占領。
| 1941(昭和16)年、ヒットラー52歳の時 |
1月から2月、トブルク、ベンガジが陥落、イタリア軍13万人が捕虜になりトリポリを守るのがやっとという状況に陥った。
2月、ドイツ軍がイタリア軍援助のため介入してくるのは時間の問題と見た、ギリシャのメタクサス首相はイギリスに救援を要請。3月末までには英軍3個師団と空軍が上陸した。かねて枢軸側についていたブルガリア、ハンガリー、ルーマニアはドイツ軍の通過を認め、日独伊3国同盟に参加した。
2.12日、北アフリカに派遣されたロンメル中将は、先遣の第5装甲師団(兵力に余裕がないため通常の師団よりも軽装備だった)を率いて、2.14日、トリポリタニアのノフリィアでイギリス軍と交戦、4.6日、メキリの要塞を占領、キレナイカを奪回し、1カ月あまりで300キロも英軍を押し返した。4月にはトブルクを攻撃する。ロンメルに与えられたのは2個師団で(第15装甲師団は4月に上陸)イタリア軍をてこ入れして戦線を保持することしか期待されず、攻勢に出ることは禁じられており名目上はイタリア軍イタロ・ガリボルディ大将の指揮下に置かれていた。しかし英軍はギリシャへの派兵とイタリア軍への急追撃で補給線が伸び、疲労していると判断したロンメルは攻勢に出た。ウェーベルは兵力の少ないロンメルの攻勢を予想していなかった。皮肉なことにロンメルは第1次大戦で連合国側のイタリア軍にカポレット付近で大勝し、ドイツ帝国軍人最高の栄誉「プール・ラ・メリット」勲章を25歳で授与された経験がある。ロンメルに兵力を与えればエジプトとスエズ運河占領も可能性があったが、ヒトラーはソ連攻撃に重点を置いていた。ロンメルは少ない兵力ながら英知に富んだ巧みな戦術で「アフリカ軍団」と「砂漠のキツネ」の名声を敵味方から博した。
3.5日、 ヒトラー、「対日協力」を指令。
3.8日、アメリカが、武器貸与法案を60票対31票で上院を通過させた。
3.27日、ユーゴ、反独クーデター。
3.27日、 松岡・ヒトラー会談。
3.30日、ヒトラーは、「ロシアとの戦いは、騎士道を守って遂行するわけにはいかない。これはイデオロギーの戦い、民族の戦いであり、前例の無いきびしさを要するものだ。ロシアはジュネーブ条約を認めていない、我がSS隊員に対して容赦しないだろう。私は、赤軍政治委員を兵士とみなさず、捕らえたら捕虜にせずに直ちに銃殺するよう要求する」と軍司令官たちに訓示した。
4.6日、 ドイツ軍、ユーゴ・ギリシア侵攻開始。
4.6日、ユーゴスラビアは当初平和的にドイツ軍の進駐が行われるはずだったが、ドイツの圧力に屈したパヴレ公らの摂政政府に対しクーデターが起き、ペータル国王の親政が宣せられシモヴィッチ将軍の左右連合政権が出来た。ヒトラーは激怒し、ベオグラードを爆撃、装甲師団を大量に投入した。イタリア、ハンガリー軍も侵入し、4.12日、ドイツ軍はベオグラードに到達、元々セルビア人との民族問題を抱えていたユーゴのクロアチア人部隊は戦わずドイツと同盟し、4.17日、あっけなくユーゴは降伏する。
4.13日、 日ソ中立条約調印。
4.16日、アルバニアでイタリア軍と戦っていたギリシャ軍の背後にドイツ軍が殺到し、ギリシャが降伏。約5万の英軍は南へ向かって退却する、テルモピレーでは山地の地形を利用してドイツ軍戦車に打撃を与えるが、山岳師団に側面から攻撃されて英軍は退却、月末までには英軍の生き残りも降伏した。
4.23日、ギリシア軍、ドイツに降伏。
4月、北アフリカのロンメルは、この月2回に渡り要衝トブルクの英軍を攻撃したが、兵力不足で奪取できなかった。
| 【副総統ルドルフ・ヘスの講和画策事件】 | |||||
| 5.10日、ヘス事件。副総統ルドルフ・ヘスは対ソ連戦の前に祖先が同じアーリア民族である(彼は地政学者のハウスホーファー教授の影響でそう考えていた)イギリスとドイツの講和を画策しこの日、訓練飛行の名目で単身Bf110長距離戦闘機を操縦、アウブスブルク飛行場を離陸。そのままイギリスのスコットランドに飛び、燃料が尽きると落下傘降下した。ヘスは面識のあったダグラス・ハミルトン公爵に面会を求め和平提案を行った、しかし彼の話にはつじつまの合わない事が多く、報告を受けたチャーチルには無視され戦時捕虜として収容された。 ヒトラーはヘスの勝手な行動に怒り、ヘスが精神異常を来したと発表して体面をつくろい、ヘスと交際のあった占星術師やオカルティストを逮捕した。この飛行はドイツ空軍の飛行管制を突破している所からゲーリングの陰謀とする説もあり、多くの謎につつまれている。戦後、終身刑を言い渡されたヘスは1987年、西ドイツのシュパンダウ刑務所で自殺(替え玉説、殺害説も)する。ヒトラーは副総統ポストを廃止し、新たに創設した党官房長にほとんど無名だったマルチン・ボルマンを任命した。 |
|||||
2017.1.17日、
|
この後は、「第二次世界大戦中盤期、終盤期までの歩み」
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)