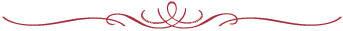
| 自民党派閥の歴史1 |
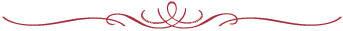
(最新見直し2009.9.16日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 自民党史の総合的な歩みは「自民党の党史検証」に譲る。そのうち政局絡みの派閥抗争史を中心に確認してみることにする。「自民党派閥の歴史」その他を参照する。おいおいれんだいこの観点で且つれんだいこ言葉で書き換えていくつもりである。 2002.7.15日 2009.9.23日再編集 れんだいこ拝 |
| 鳩山時代 |
| 自由民主党結成に参加した国会議員は衆議院299名、参議院118名であった。衆議院では圧倒的過半数を確保した。保守系で大同団結したものの、自由、民主両党の寄り合い世帯として結成されたことにより総裁は決まらず、総裁代行委員として自由、民主両党から2人ずつの鳩山一郎、緒方竹虎、大野伴睦、三木武吉の4名が選出され党の骨格を整備して行った。 首脳部の間では、総裁の座は「鳩山→緒方→岸」と譲られていく方針が既定のこととされていた。ところが、このシナリオは、翌年1月の緒方の急逝で崩れた。党首選挙は延期され、総裁代行委員の後任には石井光次郎が充てられた。結局、総裁選挙は4月に行なわれ、鳩山が圧倒的多数をもって自由民主党初代総裁に選出された。 鳩山政権の運営は、ことあるごとに異論が噴出し楽ではなかった。特に異論が激しかったのは、鳩山が政権の最大の課題としていた日ソ国交回復であった。異論は閣内からも飛び出した。その震源地は副総理級の外務大臣で元改進党総裁の重光葵であった。重光は、鳩山の次を狙うという思惑もあって、日ソ国交回復には慎重な立場をとった。鳩山は重光の頭ごしに国交回復交渉に臨んだ。 重光は対抗上、日米安保条約の改定を申し入れるが、米側に時期尚早として拒絶された。外務大臣の重光は立場を利用して日ソ交渉に横槍を入れ、交渉を中断に追い込んだ。重光は日ソ交渉に批判的な勢力を味方につけて、鳩山の後釜を狙おうとしていた。しかし、ソ連が北洋漁業の全面禁漁を発表し、日本の漁業が大打撃を受けることになった。鳩山を支えてきた一人で、鳩山が掲げた日ソ国交回復を全面的に支援する立場にあった農林大臣の河野一郎が打開のためモスクワに飛んだ。河野はフルシチョフ、ブルガーニンとの交渉の末、国交回復交渉の早期再開を条件のひとつにした上で漁業協定の締結に成功した。河野にとっては願ったりかなったりであった。 河野が脚光を浴びたのに比して、重光の影響力は大きく減退した。重光は、退勢を挽回するため日ソ交渉を再開し自ら全権として乗り込んだが、交渉は打開せず、遂に渉中断に追い込まれた。重光の総理総裁の目を潰れた。 河野の帰国直後、三木武吉が亡くなった。三木の死は鳩山にとってなによりの痛手となった。党内をまとめていた実力者三木が消えると、旧自由党系などの日ソ交渉に反対する勢力を押え込むことが難しくなった。日ソ交渉の座礁によって政権の存在意義が危ぶまれる事態に追い込まれた鳩山は、岸の抱き込みに向かった。その前に日ソ交渉を妥結させ、これを花道として引退したい意向を示し、そのために党内をまとめてほしいと密約した。岸の支持を取り付けた鳩山は自らモスクワを訪問し、日ソ共同宣言に調印、念願の国交回復を成し遂げた。帰国からまもなく、鳩山は退陣を正式に表明した。 |
| 派閥の誕生 - 岸・石橋の対決 |
| この時、岸が鳩山退陣後の最大の後継候補の立場にいたが、岸のもくろみとは違って鳩山は退陣に当たって後継者を指名しなかったし、調停の労をとることもしなかった。かくて後継総裁は公選で選出されることとなった。この公選過程で、自民党内に派閥がくっきりとした姿を現した。以降、党内派閥は自民党の常態となった。 当時の派閥は、「八個師団」、「八頭立ての馬車」と呼ばれる8派閥で形成されていた。旧自由党系4、旧民主党系4で、自由党系は吉田系と反吉田系に分かれていた。自由党吉田系は、池田勇人派と佐藤栄作派に分かれた。佐藤と池田は旧制高校時代の同級生で、佐藤は鉄道省、池田は大蔵省で出世を競い、ともに吉田の引きで政界入りした官僚出身にして吉田学校の優等生として実力をつけてきたライバルであった。この二人の反目がこの後も続き、戦後政治史を綾なすことになる。 自由党反吉田系として、緒方竹虎の死後派閥を引き継いだ石井光次郎派と、吉田時代から自由党内で党人派を代表していた大野伴睦派が位置していた。旧民主党は複数の政党の寄り合い世帯であるだけにもとから派閥色が強く、その中でも有力だったのはもと自由党から民主党に鞍替えした岸信介派であった。鳩山系は主流の河野一郎派と、傍流の石橋湛山派に分裂した。旧民主党系の中でも傍流の旧改進党系は三木武夫・松村謙三を中心に一派を立てた。以上、池田、佐藤、石井、大野、岸、河野、石橋、三木・松村派の8派閥が形成されていた。 この時の総裁選で、幹事長の岸、総務会長の石井、通産相の石橋が立候補した。岸派の参謀格は福田赳夫で、岸の実弟の佐藤派、河野派などが岸支持を表明した。石井は旧自由党系を代表して出馬し、石井派に加え池田派が支持した。石橋派の参謀長は石田博英で、石井派、三木・松村派が支持した。本命は岸、対抗馬は石橋で岸優勢とみられていた。 公選は国会議員と地方代議員の投票で行なわれ、過半数を獲得したものがいなかった場合には上位2名で決選投票が行なわれることになっていた。石橋派の石田は、岸の第1回投票での過半数阻止を目指し、決選投票での逆転を狙って石井派に決選投票での二・三位連合を申し入れ、石井派がこれを了承した。ポストの約束手形と実弾が飛び交い、自民党総裁選最初の公選は稀にみる派閥選挙となった。この時、石田は、5人に通産大臣のポストを、8人に農林大臣のポストを約束したと伝えられている。この「ポスト釣り」が以後の総裁選の前例となった。 1956(昭和31).12月、総裁選挙となり、第1回目の投票で岸が圧倒的多数で1位となったものの過半数に達せず、2位の石橋と決選投票を行なうことになった。決選投票で、3位の石井派が石橋に投票し、わずか7票差で岸を破り劇的な逆転勝利となった。土壇場で大野派が石橋支持に回り、「勝負師」石田の狙った通りになった。 1956(昭和31).12月、石橋内閣が発足する。最大の功労者である石田は官房長官に就任した。岸は副総理格の外務大臣として入閣し、石井は入閣しなかった。石橋は石井と連合して組閣し、岸が非主流化するはずであったが、岸は第1回投票で1位だったことを盾にして入閣を果たし、石井を閣外にはじき出した。これがのちに思わぬ結果を生むことになる。この時の政争によって派閥の形が大きく変わり、それまでの同志的関係から親分子分の固定的関係になり、党運営自体が派閥を考慮に入れずには行なえなくなってきた。 激しい選挙の末に総理総裁の座を勝ち取った石橋だが、就任わずか1ヶ月で病魔に倒れた。臨時首相代理に就任したのは副総理の岸であった。結局石橋は在任2ヶ月で辞任し、岸が後継した。岸は、総裁選で涙を呑んだものの棚から牡丹餅的に総理総裁の座を射止めることになった。 |
| 岸時代 |
| 岸政権は、閣僚のすべてを留任させ石橋内閣の継続させた。これ以後、総理の病気退任による交替では閣僚を引き継いで内閣を組織するというのが慣例となった。岸の政策は、「軽武装経済重視」を選択した吉田路線へのアンチテーゼ政策を次々と打ち出した。7月、岸は、東南アジア歴訪から帰国後、全面的に内閣を改造した。この改造で、外務大臣に藤山愛一郎を据えた。藤山は財界人で議席がなく、実質的に外交を岸自身がとりしきる体制であった。 1958(昭和33)年、岸は社会党と談合して衆議院を解散した。自民党結党以後、初の総選挙は自民党の圧勝に終わった。この安定多数を背景に、警察官職務執行法の改正を期した。安保改定時に予想される反対運動を未然に防止しようというのが狙いであったが、野党は「戦前の治安維持法の復活だ」として反対運動を展開し、輿論の批判もあって廃案を余儀なくされた。 岸政権は佐藤、河野、大野派を主流としており、池田、石井、三木派は反主流の立場にあった。反主流派は、警職法改正に失敗した岸に対して揺さぶりにでた。池田国務大臣、三木経済企画庁長官、石井派の重鎮・灘尾弘吉文部大臣が辞職して閣外に出た。反主流派の造反にあって、岸政権の党内基盤は一気に弱まった。岸は大野を取り込みを図り、佐藤同席の上で、大野が安保改定に協力することを条件に安保改定後、政権を大野に譲ることを取り決めた「政権禅譲の密約」を取り交わした。大野はこの密約に従い、党内を安保改定で取りまとめた。 続く総裁選で、岸は圧倒的優位で再選された。しかし、岸、佐藤は、大野と交わした「政権禅譲の密約」をすぐに反故にした。わずか半年後に内閣改造、党役員改選を行ない、それまで反主流だった池田、石井派を主流派に取り込んで、主流の河野、大野派を閣外に追い出した。官僚派を主流にして党人派を追い出した形になった。岸は、この改造内閣を率いて最終目標の安保改定に乗り出す。最大の目標は安保改定と、その成果を手にしてアイゼンハワー米大統領の来日を迎えることにあった。アイゼンハワーは、現職の大統領として初めて日本を訪問することになっており、昭和35年6月の来日が予定されていた。 1960(昭和35).1月、新安保が調印された。但し、この安保が発効を見るためには国会による批准が必要であった。野党は徹底して反対する作戦に出、国会外の勢力をも動員して岸批判を強めた。条約批准は、衆議院での可決後30日たっても参議院での議決がない場合、自然承認される。アイク訪日前に批准させるためには、5月20日までに衆議院を通過させればよい。岸はこの日、安保批准を強行採決させた。これにより、アイク訪日までには間違いなく批准が成立することになった。 ところが、岸の強行策に対して輿論が激昂した。史上稀に見る数のデモ隊が連日国会議事堂を取り囲み、岸退陣のうねりを創り出して行った。アイク訪日の下準備のために来日した秘書は羽田から東京へ向かう車がデモ隊のために立往生し、海兵隊のヘリで救出される椿事が発生する等、東京は無法地帯と化しつつあった。岸は自衛隊の出動を要請したが、赤城防衛庁長官はこれを拒否した。6.15日、議事堂への突入をはかった一部デモ隊と機動隊が衝突、デモ隊から犠牲者が出るに至って反岸感情は頂点に達した。それでもなおアイク訪日で起死回生をはかる岸に対して引導を渡したのは当時科学技術庁長官だった河野派の中曽根康弘が、閣議でアイク訪日の中止を進言、岸はやむなくこれを受け入れた。アイク訪日「延期」が発表され、6.19日午前零時をもって安保は自然承認され、23日に米大使と批准書を交換して新安保条約は正式に発効した。その日、岸は退陣を表明した。岸政権は3年余で幕を閉じた。 |
| 池田時代 |
| 岸が退陣すると、党内実力者の池田勇人通産大臣、大野伴睦副総裁、石井光次郎総務会長、松村謙三、藤山愛一郎外務大臣の5名が後継争いに名乗り出た。有力なのは池田、大野、石井であった。岸は、大野との密約を反故にして早々に池田支持を表明し、党内が池田で一本化されることを期待したが、調整の余地はすでになく公選に突入することになった。 この時、岸派は分裂した。藤山は出馬して次を伺う体制を敷き、川島正次郎は大野伴睦を支持した。福田赳夫は池田とは肌合いがあわず石井光次郎を推した。かくして前総裁派閥である岸派はこの公選で3つに分裂した。 大野は、自派と河野派、さらに岸派のうちの川島派を味方につけ、さらに決選投票の際には石井派、藤山派と「党人連合」を組んで官僚の池田派を陵駕する作戦を立てた。戦前の予測では、池田と大野で一・二位を分け合うことになるがいずれも過半数に達せず決選投票になると考えられていた。大会直前になって波乱が起きた。大会当日の未明、石井派の参議院議員が池田派に切り崩されて決選投票では池田に投票するという知らせが大野のところに飛び込んできた。大野、河野、川島で対策を協議した結果、「官僚」に政権を渡さないための策として、大野が立候補を辞退して石井に候補を一本化することを申し合わせた。石井と池田の決選投票になれば、大野、石井両派の票は池田を上回り石井が勝利する可能性が高い。他方、このまま進めば、石井派の一部が池田支持に回って大野が敗れる公算大である。大野は、「党人」政権のために立候補を辞退して石井を支持することになった。 大野の辞退という新情勢を盾に、河野らは無理矢理に党大会の一日延期を決めさせた。この間に大野支持勢力を石井支持でかためようとしていた。しかし、この一日延期は裏目に出た。池田陣営が猛烈な巻き返しに出た。この巻き返しに乗ったのが幹事長で大野支持だった川島であった。川島は、「わしは大野支持だったが、大野が辞退した今となっては石井を推す義理はない」として池田支持に鞍替えした。松村は石井支持にまわって辞退したが、藤山派は決選投票で池田を支持することになった。結局、池田は、佐藤派、岸派、川島派、藤山派の支持を得て決選投票の末、石井を破って総裁の座を勝ち取った。この総裁選でキャスティングボートを握った川島は、小派閥の長ながら以後要所要所で影響力を発揮することになる。 池田の勝利によって、「党人」派は完全に冷や飯を喰うことになった。主流派は池田、佐藤、岸の官僚3派と川島、藤山派で、戦前からの党人である大野、河野、三木派は反主流化した。この状況に業を煮やした河野は、大野を巻き込んでの新党設立をぶち上げる。しかしこの新党構想は大野の反対と支持勢力の慰留によって立ち消えとなり、自民党にとどまることになった。この新党騒ぎは自民党発足以来初めての分裂行動だったが、河野派の中からも自民党を離れることの不利から慎重論が大勢を占め、政権党を割ることへの不安が根強いことを伺わせた。 池田は政権が発足すると「所得倍増計画」を立ち上げて10年間で国民所得を倍増するという経済重視路線をひた走った。池田政権は主に佐藤、岸の支持を背景に成立したものだが、佐藤・岸兄弟はつねに「池田後」を伺っていた。池田はこうした動きに警戒感を抱いた。佐藤は、第二次池田内閣で通産大臣の要職を与えられていたが、改造後に与えられたポストは北海道開発庁長官兼科学技術庁長官の閑職に過ぎなかった。 池田は急速に「党人」派と接近し、公選で闘った反主流派の抱き込みに向かった。もともと大野と池田の仲は悪くなかった。大野は佐藤を毛嫌いしており、その関係からも池田政権の存続に動いた。池田も大野に副総裁のポストを与えて厚遇した。その大野の斡旋で、池田と河野の関係改善がはかられた。河野は農林大臣として入閣し、池田、大野、河野、川島派で新たな主流派が形成され、佐藤は非主流に追いやられた。 この間、岸は派閥を福田赳夫に譲っていた。岸派の実力者だった川島と藤山は福田に従うのといさぎよしとせず、独自の派閥を形成していた。結局、岸派は福田、川島、藤山の3派に分裂することになった。岸派嫡流の福田派も反主流となった。 1962(昭和37)年、総裁公選では対抗馬がなく池田が無投票で総裁に再選された。ちょうどこの頃から福田が「党風刷新懇話会」を創設して党の民主化運動を始めていた。福田は池田の大蔵省の後輩にあたるが、その財政政策は池田と隔たりがあり、なにかと言えば池田財政を批判するうるさい存在だった。池田は福田の動きを苦々しく思っていたが「党の民主化」という大義名分に正面から異議をとなえるわけにもいかず、かねてから改革論者として知られている三木武夫を会長とする党組織調査会を設立して党の近代化を研究させることにした。三木は「派閥解消」などを骨子とする答申をまとめて池田に提出する。しかし、この答申に対する池田の態度は冷淡なものであった。「三木答申」に従って、形の上では派閥は解消された。 佐藤は35年の総裁選で池田を全面的に支持したが、佐藤と池田は暗闘していた。台風の目が河野一郎であった。池田と河野、大野の党人・官僚連合政権から佐藤は反主流化しつつあった。佐藤は39年の総裁選に出馬するために閣僚を辞任、無官となって池田と全面対決する姿勢を示す。 1967(昭和39).7月、総裁選となり、三選を狙う池田と佐藤、藤山愛一郎が立候補した。この時、派閥があっさりと復活した。池田三選はほぼ間違いないところであったが、藤山と佐藤は決選投票になったときには佐藤で連合することを申し合わせ勝負に出た。党人派の実力者大野伴睦は総裁選直前に死去しており、池田支持確実とみられていた大野派は分裂して一部は佐藤陣営に走った。池田にとっては大きな痛手であった。 この総裁選はすさまじい買収合戦になった。二人の候補からカネをもらうことを「ニッカ」、三人の候補からもらうことを「サントリー」、全候補からもらっておきながら投票しないことを「オールドパー」といった。また、「一本釣り」に対して小派閥をまるごとカネで買うことを「トロール」と称するなど、隠語からも選挙戦の激しさが伺われよう。 池田陣営の指揮は実質的には河野がとった。佐藤は形の上では池田と争っていたが、実際には佐藤と河野の闘いであった。佐藤陣営の参謀は、佐藤派大番頭の保利茂と福田派会長の福田赳夫だった。投票の結果は、過半数を超えることわずか5票で池田が三選された。池田は三選を果たしたものの、党内の半数近くが佐藤・藤山陣営に投票したことから、佐藤の存在感が大いに高まった。 池田三選からわずか2ヶ月後の9月、池田は体調を崩して入院した。診断は癌であった。10月に予定されていた東京オリンピックを花道にして池田は退陣を決意する。後継候補は佐藤栄作と河野一郎となった。池田は幹事長の三木武夫と副総裁の川島正次郎に党内調整を依頼、三木と川島は各実力者の意見を聞いた上で佐藤を後継者に推薦した。河野は、池田政権に対する貢献度からして後継に指名されるべきと考え、「もし自分以外の者が後継になるようならあらかじめ教えてくれ」と三木や川島に伝えていた。ところが、池田は佐藤後継を決定した。党役員や実力者を集めて公表したが、その場には河野は呼ばれなかった。最後の最後で河野は池田から見限られた。池田は翌年死去するが、その直前には河野も失意のまま世を去っている。すでに大野もなく、戦前からの党人で残ったのは三木、石井だけになった。 |
| 佐藤時代 |
| 佐藤政権は、池田内閣の官房長官を自派の橋本登美三郎に更えただけで閣僚をほとんどひきついで発足した。翌年6月、佐藤政権の最初の改造が行われ、佐藤は河野を排除し、自派の田中角栄を幹事長、福田赳夫を大蔵大臣とした。さらに三木武夫を通産大臣、川島正次郎を副総裁、藤山愛一郎を経済企画庁長官、池田派を継承した前尾繁三郎を総務会長とし、挙党体制を布いた。佐藤政権を支える両輪は田中角栄と福田赳夫の二人であった。既に池田、河野、大野がなく、佐藤は「鳥なき里の蝙蝠」のごときワンマン体制で、閣僚や役員の首を巧みにすげ替えて自己の勢力を保持し、「人事の佐藤」の名をほしいままにした。 佐藤政権は発足早々、日韓基本条約の締結という外交成果を得た。佐藤は岸と同じく、米国中心の反共封じ込め政策を基本としており、日韓の関係改善も共産陣営に対して団結して対抗しなければいけないと認識していた。しかしそれから間もなく、いわゆる「黒い霧」事件が発覚した。この疑獄事件は結局ひとりの有罪者も出さず、「大山鳴動して鼠一匹」の結果となったが、自民党への国民の信頼を失墜させるには充分だった。 1966(昭和41).12.1日、佐藤と藤山の一騎討ちによる総裁選が行なわれた。結果、佐藤は過半数は獲得したものの、戦前の予想よりもはるかに少ない得票しかできず、佐藤に対する批判の根強さを伺わせた。総裁選直後、佐藤は内閣改造および党役員の改選を行ない、田中幹事長を更迭し、大蔵大臣の福田赳夫を後任に充てた。これは「黒い霧」事件への批判をかわすとともに、田中の勢力拡張を制肘して福田と拮抗させ、その上に長期安定政権を築こうという佐藤の目論みから出た人事であった。 しかし「黒い霧」事件に対する追求はまったく衰える気配を見せず解散総選挙に追い込まれた。福田幹事長の指揮下に行なわれた総選挙では、自民党は改選前議席を大幅にわりこむ敗北を喫する。しかし佐藤と福田は、「もっと大敗するかと思ったがこの程度でおさまったのだから勝利といってもよい」として居座った。党内でも、「黒い霧」批判がありながらも過半数を確保したのは上出来と、勝利感が漂っていた。しかしこの選挙では自民党の得票率ははじめて五割を割っており、やがて来る「長期低落傾向」のきざしが見られる。まもなく第二次佐藤内閣が発足したが、顔ぶれは総選挙前とほとんど変わらなかった。 ちょうどこの頃から「黒い霧」事件も山場を過ぎ、そのかわりに最大の政治課題として浮上してきたのが小笠原・沖縄返還問題であった。この両地域は大戦中から米軍の施政下に置かれており、昭和43年には小笠原の返還が実現した。しかしベトナム戦争が最高潮に達していた当時、極東の重要基地である沖縄の返還には難しい問題が山積していた。その一方で、20年以上米軍の軍政下に置かれていた沖縄住民の不満は根強く、復帰運動が繰り広げられていた。国内でも、沖縄の復帰運動に同調する傾向が強かった。当初、事務レベルでの協議では沖縄の特殊性を考慮した返還形態を考えていたが、「核抜き本土並み」の返還を要求する輿論のため、佐藤も「核抜き本土並み」を交渉の出発点とすると言わざるを得なくなった。 1968(昭和43).11月、三選を目指す佐藤に対し、前尾繁三郎と三木武夫が闘いを挑んだ総裁選が行われた。佐藤が三選を果たしたが、三木の票は思ったよりも多く、二位は確実と見られていた前尾を抜いて二位となった。前尾は三位に甘んじ、有力派閥の長でありながら弱小派閥三木に敗れたとあって面目を失った。佐藤は三選直後に内閣改造・党役員改選を行なって、田中幹事長、福田大蔵大臣のコンビを復活させた。田中と福田を拮抗させて、そのバランスの上でかじ取りを続けようという人事の佐藤と云われる采配であった。佐藤は、この頃から後継として自派の田中ではなく、他派ながら元官僚(大蔵省主計局長)で肌合いの近い福田を考えていた。しかし、福田を持ち上げ過ぎると佐藤政権の寿命を縮めかねないとのディレンマに陥っていた。 1969(昭和44).11月、佐藤とニクソン米大統領の会談で「核抜き本土並み」を基本として1972(昭和47)年中に沖縄を返還することで基本的に合意した。帰国した佐藤はこの成果を背景に解散総選挙をうつ。総選挙の指揮をとるのは幹事長の田中角栄であった。前回の総選挙では幹事長は福田であり、改選前議席を割り込んでおきながらも「勝利」と位置付けていた。この総選挙で、自民党は追加公認を含めて300議席を獲得するという大勝利を得た。この大勝利によって田中の勢威は大いに上がった。佐藤は、後継と考えている福田をさしおいて田中の影響力が強まることを恐れ始めた。 池田・佐藤両政権をつくるために大いに働いた川島正次郎は当時副総裁の地位にあった。田中は、この川島と組んで、党務を川島副総裁と田中幹事長で取り仕切り始めた。佐藤は、田中を入閣させ、幹事長を自派ながら福田支持の保利茂に更え、川島を三権の長たる衆議院議長にしようと図った。しかし、川島・田中の方が一枚上手だった。川島は、「わしはその任ではない」として拒否、田中は幹事長留任で党内を下工作し、前尾、三木、中曽根といった有力派閥の長から佐藤に提言させた。結局、佐藤は、川島副総裁、田中幹事長、福田大蔵大臣という体制にほとんど手をつけることなく、第三次内閣を組織するしかなかった。 田中・川島ラインは、昭和45年末に予定されていた総裁選で佐藤四選を画策した。田中は、党内実力者の地歩を堅めつつあったが、まだ佐藤−福田勢力に太刀打ちできる状況になかった。田中派旗揚げにはまだまだ時間が必要だった。佐藤が出馬せず、派として福田を推せば、福田が後継となることが確実だった。福田の後見人格の岸は佐藤に対し、福田後継を実現するために四選を断念して次の総裁選で禅譲するべきだ、今なら勝てるが田中派の伸張が著しく四選後では怪しくなると説いた。しかし、佐藤は、長期政権の間にワンマン化しており、兄である岸のいうことに耳を貸さなかった。結果としては岸の憂いた通りになる。 田中・川島は党内を四選でまとめていった。福田は、佐藤からの禅譲を信じてひたすら待ちに徹した。田中・川島は、有力候補である前尾の出馬辞退という策を講じ、党内一致して佐藤の四選を望む雰囲気を盛り上げようていった。前尾は、「総裁選後の改造人事で前尾派を優遇する」という約束をうけて出馬を取りやめ、佐藤はこの作戦に乗った。 佐藤は四選にむけて出馬した。佐藤と三木の一騎討ちとなった。佐藤、前尾、福田、川島、藤山、中曽根各派が佐藤を推し、佐藤が圧倒的多数の得票で四選を果たした。しかし、唯一の対立候補として立候補した三木の得票は戦前の見通しでは70票台であったが、蓋を開けてみると100票を超えていた。これは三木を支持したというよりは、佐藤への批判票であり、佐藤に対する不満の大きさを物語っていた。選挙後、佐藤は前尾に約束していた改造人事をとりやめた。その知らせを聞いた前尾派議員は前尾を激しく批判した。結局前尾は佐藤に利用されるだけで何ら得るものがなかった。派内の批判にあった前尾は、派の領袖の座を大平正芳に譲らざるを得なくなった 1971(昭和46).7月、四選から半年後、佐藤は先送りにしていた改造人事を行なった。この人事では福田支持の保利を幹事長とし、田中を通産大臣、福田を外務大臣とした。財政畑の福田を外務大臣にしたのは、将来の首相として箔をつけようという佐藤の考えであった。福田外相時代にドルショックと米中首脳会談という外交的新情勢が起こった。佐藤と福田は、伝統的に親台湾でアメリカの対中国封じ込め政策を完全に支持していた。しかしアメリカはその日本の頭ごしに中国との関係改善を遂げ、日本政府はこの動きをまったく察知できなかった。福田外交の面目失墜となった。 国外だけでなく、国内でも福田に不利な事態が起きていた。参議院議長を3期9年間勤め、自民党参議院に絶大な影響力を持っていた重宗雄三に対する批判が吹き出した。河野一郎の弟、河野謙三が「重宗王国」に反旗をひるがえし、野党の一部も巻き込んで重宗退陣を要求した。河野は重宗の対立候補として議長に立候補、重宗は議長を降りざるを得なくなった。重宗は福田派の有力者で、彼がいるかぎり福田は参議院の支持を期待できた。しかし今や重宗は失脚し、参議院の動向は予断を許さなくなった。 川島正次郎は昭和45年に急逝した。田中は、佐藤四選後、着々と勢力を固めていった。昭和47年に入り、政局の焦点はすでに佐藤がいつ退陣を表明するかに移った。5月の沖縄返還を花道に退陣するか、それとも秋の総裁任期いっぱい勤め上げるのかという問題になった。佐藤は任期いっぱい勤め上げようとしたが、禅譲を狙う福田と岸は沖縄返還で退陣、福田に禅譲というシナリオを描いた。田中にとっては佐藤退陣は遅いほど都合が良かった。しかし早期退陣をも充分に視野に入れて着々と準備を進めた。福田は、佐藤四選のときと同じく積極的に動けず、田中は精力的に勢力拡大に動くという構図となった。 佐藤は、国民の念願だった沖縄返還を実現すれば、その余勢で秋までの政権延命が可能だと考えていた。しかし実際に沖縄が返還されてしまうと、マスコミはもちろん自民党内でさえ「佐藤内閣の使命は終わった」との雰囲気が大勢を占めていた。佐藤長期政権が食傷され始め、小手先の延命策ではどうにもならない雰囲気が醸成された。マスコミが伝える支持率も史上最低にまで落ち込んだ。佐藤は岸からの督促もあって遂に退陣を決意した。退陣表明の記者会見で、佐藤は、それまで鬱屈していたマスコミへの不満を爆発させ、新聞記者の在席を拒否、テレビ局だけが中継するという異例のものとなった。 |
| 田中時代 |
| 佐藤長期安定政権が終焉した昭和40年代後半から50年代にかけては、いわゆる「三角大福中」の5大派閥が凌ぎを削り、そこにいくつかの中小派閥がからむ様相を呈した。 1972(昭和47)年にはいると佐藤は自派内を福田支持でまとめるために幹事長の保利茂に命じて工作を始めさせ、田中封じ込めに向かった。しかし、田中はこの時既に佐藤派内の半数以上を田中支持でまとめていた。「佐藤後」に不安を持つ議員たちは雪崩をうって田中支持へと流れていった。この支持を背負った田中は佐藤の思惑など無視して総裁選に向けて本格的な行動を開始した。沖縄返還も間近な一日、田中は支持者を新橋の料亭に集めて田中派を旗揚げした。衆院44、参院37でスタートした。 佐藤、福田、保利は、派内に福田支持を徹底させようとしたが、すでに時遅しの雰囲気となっていた。他派の支援を取り付けようとしたが、田中の手回しの方が早かった。池田派の流れをくむ大平派の領袖大平正芳は池田内閣時代に外務大臣をつとめ、当時大蔵大臣に抜擢された田中と親交を結んでおり盟友関係を構築していた。三木と中曽根が控えていたが小派閥でしかなかった。 佐藤は、中曽根康弘を呼んで総裁選への出馬を勧めた。中曽根は河野一郎派をひきついではいたものの、中曽根派は大派閥と中小派閥の中間といった程度の規模で、単独で勝負を挑むだけの力はもっていなかった。佐藤が中曽根に出馬を求めたのは、中曽根派の票が田中に流れるのを防ごうという魂胆であった。佐藤は、田中と福田を呼んで、「どちらが勝っても挙党体制でいくこと」、言い替えれば本選挙で過半数をとったものがなくても二位のものが辞退して一位のものを推すことを求めた。この時点では、福田は過半数はとれないまでも本選挙での1位は獲得できるとの算段があったからであった。田中は主旨には賛同したものの、明確な言質は与えることはなかった。 中曽根は迷った。派内からは「角福の草刈場とならないためにも出馬すべきだ」という意見もあった。中曽根に田中支持を勧めたのは河野一郎の息子洋平であた。中曽根は最終的に佐藤の要請を蹴って出馬せずに田中を推すことにした。中曽根の田中支持表明で中間派閥は一気に田中支持の方向に傾いた。大平は田中の盟友であり、三木も佐藤政治には強い批判を持っており、佐藤の直系である福田政権には反対だった。すなわち、「三角大福中」5派閥のうち「三角大中」が反福田で一致したことになる。 7月5日の総裁選の本選挙では、田中156票、福田150票、大平101票、三木69票となり、わずか6票差で田中が一位となった。決選投票では田中が大平、三木陣営の票の大部分を獲得して大差で新総裁に選出された。「角福戦争」は田中の勝利に終わった。 この選挙では、三位になるのは三木で、大平は100票に満たず四位に終わるだろうというのが下馬評だったが、実際には大平は100票を超えて三位となり、三木は70票もとれずに四位に終わった。三木の面目は潰れ、逆に大平は大いに面目を施した。この選挙で、「カネのけたが跳ね上がった」と云われているが、これは必ずしも金権的に受け止める必要がなく、日本経済がそれだけ豊かになっていたことを証していよう。 当然のことながら田中内閣では大平は重要な地位を占め、三木の立場は弱いものとなった。陰に陽に福田を後押ししていた佐藤は、田中の政権構想に口出しできる立場ではなかった。大平は外務大臣、中曽根は通産大臣の要職を得、三木は副総理とはいうものの実際には無任所の国務大臣にすぎなかった。福田は入閣せず、福田派は反主流化した。これ以後、「角福」は不倶戴天の仲となる。 田中政権の最初の大仕事は日中関係の正常化であった。佐藤政権当時、ニクソン米大統領が日本の頭ごしに米中関係改善を成し遂げたあと、佐藤は遅れ馳せながら関係改善を中国に呼び掛けていた。しかしそれまでの佐藤の親台湾政策がたたって、中国はこの佐藤の呼び掛けをまったく無視していた。田中は首相就任以前から日中関係正常化の必要性を説いていた。自民党内では三木がもっとも関係改善に熱心だった。田中が本来肌合いの違う三木と総裁選で連合できたのは、「佐藤亜流の福田政権では日中関係改善はすすまない」という共通の認識があったからでもあった。 田中は内閣の重要課題のひとつとして「日中改善」を掲げた。中国側もこれに応じて歓迎の談話を発表した。田中は政権発足から2ヶ月後の9月、自ら中国を訪問して日中共同宣言に調印、国交回復を成し遂げた。その一方で、台湾との国交を断絶した。一貫して台湾重視を唱えてきた岸、佐藤、福田らの面子が潰された。 田中が日中国交正常化と並ぶ政権の二本柱として掲げたのが、有名な「列島改造論」であった。しかし、これは裏目に出た。土地への投機を煽って「狂乱物価」をもたらす結果となり、物価は終戦の混乱期を除いて最大の上昇を示した。田中は、自らが幹事長として勝ち取った300議席の安定多数の上で政権を担当していくつもりだったが、「狂乱物価」の責任を追求する野党と与党反主流派の突き上げにあって、当初予定していなかった年内解散を余儀なくされた。「日中国交正常化」、「角栄ブーム」にのって大勝は間違いないと踏んでいた田中だったが、蓋をあけてみると改選前議席を大きく割り込んでかろうじて安定多数を確保したに過ぎない期待に反する大敗となった。この時、共産党が躍進し、国会の議員運営が様変わりすることになった。 総選挙後の組閣で田中は、これまで閣外においていた福田を入閣させることになった。しかし福田は入閣は承諾したものの、重要閣僚として田中と運命を共有することは拒んだ。結果、福田が得たポストは行政管理庁長官だった。これで「三角大福中」全員が何らかの形で入閣することになった。形の上では挙党体制はできあがったが、角福の角逐がおさまったわけではなかった。総選挙の敗北によって国会運営は難しくなった。 この頃、田中は小選挙区制の導入を考えた。福田もかねてよりの小選挙区論者である。田中は福田に協力を申し出たが、福田は「主旨には賛成だがタイミング的に難しいだろう」とあまり乗り気ではなかった。田中が構想した小選挙区の区割りは明らかに自民党に有利なもので、世に「カクマンダー」と呼ばれた。かってイギリスで恣意的な小選挙区区割りを行なった「ゲリマンダー」をもじったものである。結局この小選挙区構想は提案にもいたらずに立ち消えとなる。 昭和48年度予算は、狂乱物価にもかかわらず相変わらず強気に「列島改造」にシフトした。この時、第一次石油ショックが襲った。田中は、積極路線にのっとった補正予算を提出したが、その直後に田中が片腕とたのむ愛知揆一蔵相が急死した。田中はついに辞を低くして福田に蔵相就任を要請した。福田は積極財政路線を転換することを条件に蔵相就任を承諾した。福田は狂乱物価対策について一任を田中からとりつけ、かねて持論の緊縮財政路線に転換させた。これが功を奏したのか、あるいはちょうど物価上昇もピークに来ていたのか、いずれにせよ狂乱物価が鎮静し始めた。福田は面目を大いに施し、田中の株は下がった。 昭和49年夏、参議院選をケ買えた。田中は、前回の総選挙では不本意な結果に終わったものの選挙指揮については絶対的な自信をもっていた。戦前のマスコミの予想では、自民党敗北・与野党伯仲もしくは逆転というのが相場だった。危機感を持った自民党では全国区にいわゆるタレント議員を大量に擁立、票の底上げを狙った。この参議院選は稀に見る金権選挙となった。 この選挙で焦点となったのが徳島県であった。徳島は三木の地元で、参議院では三木派の久地米健次郎が議席を持っていた。ところが、元警察庁長官で田中の信頼厚い後藤田正晴が徳島地方区からの出馬を表明した。田中の推す後藤田と三木の推す久地米が公認争いを演じ、徳島県連も分裂した。扱いが党本部に一任され、公示が間近となって決断を迫られた田中と橋本登美三郎幹事長は後藤田の公認に踏み切った。三木は田中のこの仕打ちに激怒し、公認を無視して派を挙げて久地米の応援に投じた。 しかし徳島以外でも一部の選挙区で候補者の調整に失敗、複数の候補が立って争う情勢となった。結果として自民党は敗れた。当選確実と見られたタレント議員も意外な苦戦となり、候補者調整に失敗した選挙区では共倒れとなって野党に議席を許した。徳島地方区では、公認の後藤田は敗れ三木が意地と威信をかけて推した久地米が当選を果たした。自民党は改選前議席を下回り、非改選議席を合わせてもようやく過半数を確保したに過ぎなかった。 田中は、命運をかけて望んだ選挙に敗れ、窮地に追い込まれた。それに追い撃ちをかけるように、副総理の三木が辞職を申し出てきた。三木派は主流派の一角にありながら閣僚ポストでは冷遇をこうむっており、かねて不満が鬱積していたところに徳島の問題があって田中への批判が噴出し、ついに三木は「党内改革に専念したい」との名目で辞任した。表面上は「党内改革の必要性」という大義名分を振りかざしてはいたが、実際には「田中退陣」が目的であった。 三木の辞職をうけて、福田の去就が注目された。福田の後見人たる岸は、かねての「三木嫌い」もあって三木と手を組むことには懸念を示したが、田中退陣に繋がることならと賛成した。かつての佐藤派の大番頭であった保利行政管理庁長官は、福田と田中の調整に動いたが福田の意志と、何よりも福田派の強硬論を覆すには至らず、ついに福田も辞表を提出した。保利も調整失敗の責任をとって辞任した。かくて、参議院選に起死回生をかけた田中政権は、三木・福田・保利の辞職という思わぬ結果を呼んだ。「大角中」主流派と「三福」反主流派の対決という構図ができ上がった。福田の後任の蔵相には大平外相が横滑りした。参議院選直後から三木と福田は連絡を取り始めていた。 揺さぶられる田中政権に追い打ちをかけたのが、「文藝春秋」で発表された「田中金脈問題」であつた。田中の権力の源泉となった「カネ」の出所を詳細に分析したもので、既に一部では知られたことだったが、「文藝春秋」という権威ある雑誌で公にされたことで威力を増した。マスコミが一斉に批判を強めた。11.11日、田中は内閣改造を行ない、引き続き政権を担当する意思を示した。しかし、情況が打開できず、11月の現職アメリカ大統領としてはじめてのフォード大統領来日を花道に退陣表明した。田中は退陣発表の記者会見には出席せず、官房長官の竹下登に談話を朗読させた。田中はテレビでそれを見ながら、大粒の涙を流していたという。 |
| 三木時代 |
| 田中は2年余りで思い半ばのまま退陣を余儀なくされ、党内情勢はとても後継を指名できる状況ではなかった。田中退陣後、次期政権を狙っていたのは第一に福田、続いて大平だった。福田は佐藤後に総裁の座を田中と争って僅差で敗れている。その際の下馬評では本命と目されていただけに、雪辱を狙うのは当然の成り行きだった。一方で、大平には総裁選以来ずっと田中政権を支えてきたという自負があった。 田中政権末期、田中は、椎名悦三郎を副総裁に取り込んでいた。椎名は川島副総裁亡きあとの中間派を代表する人物で、参院選敗北後の三木・福田辞職騒動のあと、「党運営に関する調査会」を設立してその座長になっていた。田中は、椎名に後継裁定を任せた。椎名は、大平との会談の中で「健康の問題もあって自分から進んで引き受ける気はないが、推されれば考える」と述べた。大平は椎名にまだ色気が残っていることを見て取ると、会談の内容をマスコミに漏らした。このニュースは瞬く間に永田町を駆け巡り、あわてた椎名は「自分は調整役に徹する」と弁明した。こうして椎名政権の目は完全に潰された。 大平は、公選による総裁選出を主張した。最大派閥の田中派との連携により勝利できると判断していた。福田と三木は話し合いによる選出を望んでいた。佐藤栄作や岸信介などの長老には福田支持が多く、話し合いになれば影響力が大きいと見ていた。三木は、公選によって大平が勝利すれば田中派の支配が継続すると見て公選に反対した。かくして、大平の公選論と福田・三木の話し合い論が正面衝突することになった。 この間に立って調整役を勤めたのが椎名であった。椎名は福田、三木、大平、中曽根と会談を持ち、とりあえず挙党体制確立のために幹事長を総裁派閥から出さないことを申し合わせた上で、一晩の猶予を乞うた。翌日、椎名は、実力者を集めた上で、総裁に三木を指名した。三木は「晴天の霹靂だ」と驚いてみせたが、実際にはすでに前夜のうちに知り合いの新聞記者から情報を得ており、椎名の裁定文に注文をつけたりしていた。福田も前もって情報を得ていたが半信半疑だった。本当に晴天の霹靂だったのは大平であった。福田は話し合いによる選出を主張していた立場もあって表立って反対するわけにもいかず、諦めざるを得なかった。大平は裁定のあと田中邸を訪れたがあいにく田中は留守にしており、田中が帰宅するのを待っている間に大平も諦めの境地になっていた。帰宅した田中は「51対49で負けたな」と評し、大平を抑える側にまわった。 椎名裁定の裏には、当時の「角福対立政争」からの緊急避難的意味合いがあった。福田を推しても、田中の盟友である大平を推しても、党分裂の危険をはらんでいた。三木であれば福田も大平も党を割るようなことはできない。また、田中金脈批判のあとでは、「クリーン」のイメージがあった三木ならば国民に受け入れられるだろうとの判断があった。こうして誰もが予想していなかった三木政権が発足した。 三木は福田、大平、中曽根といった実力者を閣僚や幹事長に据え、派閥均衡に留意した人事を行なった。党内では、三木政権は田中金権政治のイメージを克服するための「暫定内閣」とみなされていたが、三木は「暫定総理」の座で満足するような殊勝な人物ではなかった。 三木は長年、政治改革を唱えつづけてきた。ひょんなことで図らずも総理総裁の座を得た機会に、三木は持論の実現に意欲的に取り組んでいった。まず、「政治資金規正法」の改正強化を図った。金権批判のあとを受けて成立した「クリーン」内閣としては、是非とも成立させたいところであったが、政治家の糧道を絶つ法案とあって自民党内は無論のこと野党からも反発をうけた。しかし、献金する方の財界側が成立を希望したことがうまく働き、かなり骨抜きにされながらも「政治資金規正法案」は成立した。だが、この結果、規正法案の範囲外である政治資金集めのためのパーティーが横行することになる。 続いて三木が取り組んだのは「独占禁止法」の強化である。ところがこれが大企業に不利に働くとあって、大手企業を支持基盤としている自民党内から一斉に反発が出た。この「独禁法改正案」には、「政治資金規正法」では賛成にまわった財界も反発し、廃案を強く迫った。「改正法案」は、とにかくも国会に提出されたが、三木の後見人格である椎名も反対にまわるほどで、審議は紛糾して修正を重ねたあげく、ついに審議未了で廃案に追い込まれた。 1976(昭和51)年、海の向こうから田中の致命傷となるロッキード事件が勃発した。米国の航空機製造会社であるロッキード社が、自衛隊や全日空などへの売り込み商戦で多額の賄賂を贈ったという。そしてその賄賂の一部は日本のの政府高官に渡っていたという。その糸を手繰れば田中元首相の現職時代の犯罪というシナリオに発展して行った。この事件が発覚すると、気息奄奄としていた三木は息を吹き返した。「事件の徹底究明」を約束し、米議会での証言記録なども取り寄せ、東京地検、警察庁、国税庁による合同捜査が始まった。 マスコミがこぞって事件の真相究明を求め、三木とマスコミの歩調が一致した。共産党の田中訴追運動が執拗に始まった。ところが、三木政権生みの親たる椎名は、「三木ははしゃぎ過ぎだ。惻隠の情というものがない」と批判し始めた。「三木を推薦したのは君じゃあないか」と云われ、「まったく、わしも今になって不明を恥じとるよ」と応じている。 この状況を見てとって、福田は「三木おろし」を策しはじめた。先の「田中後」でともに苦杯を舐めた大平を巻き込み、さらに三木政権樹立の立役者である椎名も取り込んで、三木を政権から引き摺り下ろそうとし始めた。福田は、「三木おろし」のために宿敵の田中にも接近した。田中は原則的に支持すると答えたが、積極的に「三木おろし」に手を染めようとはしなかった。この第一次「三木おろし」の動きがマスコミに漏れ、マスコミは「ロッキード隠し」だとして一斉にこれを非難し、福田や椎名も動きを取りやめるしかなかった。 捜査は順調に進み、昭和51年6月頃から逮捕者が出はじめていた。そして7月27日、前首相の田中が外国為替管理法違反で逮捕された。田中は拘置所内から離党届と派閥の脱退届を提出、形式上無所属となった。この逮捕劇が政界に衝撃を与えた。田中派の橋本龍太郎は人目をはばからず泣き崩れた。三木に対し、田中と田中派は根深い恨みを抱くことになった。 「田中逮捕」をきっかけに、「三木おろし」は再始動した。先の「三木おろし」では静観していた田中派が、今度の「三木おろし」では主導権を握ったのは当然の成り行きであった。党内最大派閥で「田中軍団」と呼ばれた戦上手の田中派が本腰を入れ始めた以上、抗争の激化は必然であった。8.19日、田中逮捕の翌月のこの日、田中、大平、福田派と中間派を糾合して「挙党体制確立協議会」いわゆる「挙党協」が結成され、両院議員総会の開催を要求した。三木政権を支えるのは、総裁派閥の三木派と、幹事長の中曽根派であった。三木と中曽根は「挙党協」の要求を拒否したが、「挙党協」側は独自に三分の二以上の議員を集めて「総会」を開催、全会一致で「党体制の刷新」、つまりは「三木の退陣」を決議した。大平と福田はこの「党議」を三木につきつけたが、三木はこれを拒否。「僕がやめたとして、あとの総裁には福田、大平両君のうちどちらがなるのかね」と痛いところをつかれた二人は、それ以上押し切ることができなかった。三木はマスコミを味方につけて「挙党協」を批判、ついで両院議員総会で臨時国会会期中の解散をしないことを約束し、さらに内閣改造を行なって当面の状況を乗り切った。 三木にうまくかわされた大平と福田は、本格的に手を組むことになった。「挙党協」としての総理候補を福田に一本化、大平は幹事長にまわってその次の政権を担当するという密約ができあがった。田中派もこの「大福提携」を支持した。10.21日、挙党協総会で福田を次期総裁に推薦することを決議、福田はこの決議を受けて閣僚を辞任し、三木との対決姿勢を鮮明にした。ところが、ここまでに挙党協は時間をかけ過ぎた。年末には任期満了にともなう衆議院選挙が予定されており、議員たちは雲の上の争いよりも自分の足元の方が気になり始めていた。かくして「三木おろし」は自然休戦となり、12.5日の総選挙に向けて走り出した。三木は「伝家の宝刀」である衆議院解散権を行使することはできなかったものの、とにかく自政権下での総選挙にこぎつけることができた。三木は、マスコミの支持を背景にして総選挙で勝利し、引き続き政権を担当する意欲を見せた。 総選挙は、党執行部と挙党協の分裂選挙となった。結果は、自民党の惨敗だった。過半数に満たない249議席しか確保できず、選挙後の入党者を加えて辛うじて過半数に達することができた。自民党内に三木を追求する声が巻き起こり、三木は総選挙敗北の責任をとって辞任を表明した。 |
| 福田時代 |
| 三木の後継としては、大平派と福田派が提携して福田を推したことによりあっさり「福田後継」が決まった。福田は、与野党伯仲の状況で、国会での総理大臣指名選挙で辛うじて過半数を勝ち得、総理大臣に就任した。昭和45年に「佐藤後継」として総理大臣の椅子を目前にしてから実に6年以上が経過していた。一時は年齢的にもう難しいと云われたこともあったが、ついに総理大臣の座を射止めた。 「三木おろし」の経緯からして、福田政権の主流派は「挙党協」を構成していた福田・大平・田中派となった。三木・中曽根派は反主流に追いやられた。大平は幹事長に就任、次の総裁を狙う。福田は大平に対し、「僕は一期2年でよい。その後は君だよ」と後継総裁の地位をちらつかせ、協力を迫った。 三木は、退陣にあたって置き土産として「総裁公選制度」を残して行った。党費1500円を二年分完納している党員すべて(200万人と言われた)で投票し、その上位二人で決選投票を行なう。決選投票は、党所属の国会議員の投票とするというもので、総裁を全国の党員党友による公選で選出するというところが目新しい党の近代化のひとつの目玉であった。全国の党員を相手に選挙戦を戦うことで、派閥色を払拭しようというのが三木のねらいであった。福田は、ロッキード後の国民の自民党不信を払拭するために、この公選制の導入を積極的に推進した。具体的には、昭和53年秋に予定されていた総裁任期切れにともなう総裁選に間に合わせようとした。この公選制度は目論見通り、昭和52年春に正式導入されて翌年の総裁選から実施された。 福田政権の官房長官である園田直は辣腕家として知られていた。もともとは河野一郎派に属し、河野の死後は派を引き継いだ中曽根と袂を分かつて園田派を率いていたが、のちに福田派に合流する。したがって、福田派内からみて園田は「外様」であり、その園田が官房長官という要職にあって福田にあれこれと吹き込むのをよく思わない者は少なくなかった。ところが園田はもと外務政務次官の外交通で、ことに日中国交正常化論者として知られている。日中国交正常化は、すでに昭和47年の田中内閣時代になされている。しかし、それを正式に文書化するための日中平和条約調印は、いわゆる「覇権条項」の取り扱いをめぐって暗礁に乗り上げていた。福田は親台湾派として知られていたが、園田はこの平和条約交渉の推進を福田に提言した。福田も、平和条約を調印にこぎつければ福田政権として大きな外交的成果となると考え、前向きな姿勢を示した。 しかし、岸信介をはじめとする福田派長老には親台湾派が多い。福田自身がもともと親台湾であったから、長老たちの反対論をむげに退けることもできず、結局福田の中国への呼びかけも抽象的なものにならざるを得なかった。中国は「具体性がない」として交渉推進に乗らず、この「平和条約」交渉は掛け声だけに終わった。 「日中平和条約」は園田が持ち出した外交的な課題である。福田は、内政的な課題として「行政改革」を持ち出し園田に相談した。行政改革自体はその必要性がいわれて久しく、ことにオイルショック後には重要な課題として認識されていたが、具体的な取り組みは何もされていなかったのが現状であった。園田はこれに一も二も無く賛成した。福田は、行政管理庁長官で田中派会長の西村英一に早急に腹案をまとめるように指示した。西村は、党内のコンセンサスができておらず時間もないと躊躇したが、とにかくにも首相の指示なのでわずか数日で原案をまとめ上げた。福田はこの原案をふところにして「行政改革」をぶち上げたが、これは拙速にすぎた。通産省の次官・局長たちが福田派の大臣を蚊帳の外に置いたまま一斉に反対を表明したのを皮切りに、官僚や党内から猛反対が湧き上がった。そこで園田は福田に「具体的な省庁の改廃には触れず、一般論としての行政改革の必要性だけを述べて、将来への芽を残しておく」という方法を建言、福田はこれに従い、行政改革も掛け声倒れに終わった。 組閣から1年近く経つ昭和52年秋、政界では内閣改造が取りざたされていた。福田は表向きこれを否定していたが、心中では改造を決心していた。その最大の眼目は、閣内での田中派の影響力の排除にあった。福田は秋の一日、与野党伯仲の状況下で挙党体制を組むためには反主流の三木・中曽根派を取り込む必要があるとして、大平幹事長をまねいて改造の決心をうちあけた。慎重な大平は表立って反対はしなかった。福田はこれで大平派と、大平が盟友関係をもつ田中派の同意を得られたと思った。ところが、大平も田中も、この改造に納得しているわけではなかった。田中−大平は、閣内での大平・田中派の勢力を弱め、その上で解散・総選挙にうって出て勝利し、その余勢で再選をはかろうという福田の目論見を察知していた。しかし、改造は首相権限であり、これを阻止することはではなかった。そこで田中と大平は、大平が幹事長の座にあって(大平の幹事長再任は確実だった)がっちりと党を固めているあいだに勢力を強めてつぎの総裁選での勝利をねらい、かつ解散を阻止しようという路線に出た。 福田は、改造によって党三役のうち政調会長に田中派から江崎真澄を起用したが、のこる総務会長に中曽根を起用、閣僚にも田中派には3ポスト(厚相、防衛庁長官、環境庁長官)を与えるにとどまった。福田はこの改造を自画自賛した。 この改造で福田は、園田官房長官を更迭した。派内からは園田のスタンドプレーを非難する声が福田に届いていた。改造にあたり、園田は官房長官留任を確信していたが、福田は「官房長官と蔵相以外できみの好きなポストをとりたまえ」と園田に通告した。言い方は婉曲だが、要するに官房長官としてはクビということである。園田は悔しさをかみ殺して、外相のポストをとった。かねてからの持論である日中正常化をめざしたのである。園田の外相就任により、平和条約の交渉は促進された。園田にかわって官房長官となったのは安倍晋太郎であった。 安倍は早くから「福田派のプリンス」と呼ばれた逸材で、岸信介の娘婿でもある。これまでは国会対策委員長をつとめていたが、これは舅岸信介の意向で、安倍は国対で苦労することが必要だとの意見からであった。将来の大成のために経験を積む時期だというのである。今回の官房長官就任も、その路線を引き継いだものであった。 昭和53年春、福田は安倍官房長官に「通常国会終了後の適当な時期に解散を考えている」と打ち明けた。解散には、安倍も賛成である。表向きには、解散・総選挙によって現在の与野党伯仲状況を打破しなければならない。また、解散・総選挙にうって出て勝利することができればその秋の総裁再選は確実になる。以後、福田と安倍は表向きには否定しておきながら陰では解散機運を盛り上げ、解散の時期をはかっていた。 この策謀はあっというまに田中に筒抜けとなり、田中から幹事長の大平に伝えられた。田中と大平は、福田に解散をさせてはいけないという点で完全に一致していた。福田に解散をさせてしまえば、秋の総裁選で福田の勝利は確定してしまう。田中と大平は、福田との激突を覚悟した。政局的には、この年の春には自民党総裁公選制度は成立しており、また予算も成立してしまえば解散を妨げる要素はなくなってしまう。そこで大平と田中は前回の総選挙から1年半しか経っていない点をついて、福田らの思惑とは逆に解散反対の機運をつくろうとした。現役の代議士にとって総選挙は一大事である。福田らは表立って解散のために動けない状況に追い込まれ、時期をさぐり続けた。 直接行動に出たのは、田中派の金丸信防衛庁長官であった。金丸は福田・安倍に会見を申し込み、3人の席で解散について問いただした。福田らはその場で「解散は考えていない」という言質をとられてしまった。それからまもなく、国会で公明党議員が金丸に「解散が噂されているが、金丸防衛庁長官の所信を伺いたい」と質問した。金丸はその答弁で福田・安倍が「解散はしない」ことを確認したと答え、解散を求められても「閣僚として署名を拒否する」と公言した。これは一説によると金丸が公明党に働きかけて打たせた芝居だったともいわれている。 解散に打って出られないまま、福田はサミットなどの日程をこなすうちに自信を深めていった。「今、総理総裁が変わるべき論理的理由がない」などと発言して大平を刺激した。大平は、2年前の密約、すなわち一期2年で総裁を譲るという約束のもとに福田を支えてきた。ところが、福田は密約を覆すような発言を繰り返し始めた。大平には福田と正面衝突して勝てる自信はまだ持っていなかった。福田の強気の発言も、その読みがあったればこそであった。しかし、田中の判断は違った。田中は、秋の公選は福田と大平の争いになると見て早くから党員の拡大に力を注いできた。ひとり3000円の党費を立て替えて、公選の投票権を持つ党員の獲得に勤めていた。 8月に行なわれた香川県知事選で、自民党の推す候補が落選した。香川は大平の選挙区で、地元の首長選挙で不覚をとったことで大平の株は下がった。同じ月、懸案の日中平和友好条約が調印にこぎつけた。福田はますます自信を強めた。この頃、総裁公選制度の成立にともなって派閥は一斉に解消されることになった。ほとんどの派閥は形の上だけ解散して「政策集団」に衣替えしてお茶を濁したが、福田は総裁が自ら範を示すべく、派を本当に解散してしまった。これにより、福田派は会合場所もなくし選挙運動のための本部にも事欠くようになった。 10月に入るころ、マスコミは一致して「福田優勢」を報じていた。気を良くした福田は、大平に「僕には、『世界のフクダ』としてまだやることがある。総裁選は辞退してもらえないだろうか」と申し入れたが、大平はこれを拒否した。 結局、総裁選に出馬したのは福田、大平と中曽根、そして三木派の河本敏夫だった。中曽根の出馬は派内情勢に圧されたもので勝算はなかったが、この出馬は福田にとっては不利に働いた。福田はかねてから「上州連合」を結んで一致して福田を推すように中曽根に申し入れていたからである(福田と中曽根はともに群馬が選挙区)。三木派では、三木が提唱してつくった新しい公選に候補を立てないわけにはいかないとの考えから、三木の後継者と衆目の一致する河本を立てることになった。福田は、予備選挙での勝利を確信していたが、国会議員による本選挙では田中派の大平支持が確実なだけに自信をもてなかった。そこで、さかんに「予備選挙で二位になった候補は本選挙を辞退すべきだ」、「予備選挙で百点以上差がついたときには、本選挙は行なうべきではない」と発言した。大平陣営も、予備選挙での一位は無理で、国会議員による本選挙で逆転するというシナリオを描いていた。 ところが、田中派はある意味大平派以上の熱意でもって予備選挙に力を入れ始めた。田中みずからが次々に電話をかけ、票のとりまとめを依頼した。党組織委員長の竹下登は極秘のはずの党員名簿を横流しして一本釣りをやらせたと噂された。田中は盟友の大平を総理総裁にせずにはいられないとの気概でこの総裁選に望んだ。 この公選は、提案者の三木の思惑を離れて、派閥を地方にまで拡散する役割を果たした。派閥が地方党員の党費をまるまる立て替えるという手法によって党員獲得にしのぎを削った結果、地方の隅々にまで派閥の論理が行き渡った。結局、公選は党中央の腐敗を地方にまで拡大させることになる。 予備選挙の結果は、マスコミの下馬評を覆すものだった。大平が、110点もの差をつけて福田に圧勝した。福田がかねて公言していた「百点」以上の差である。福田の立場としては、本選挙を辞退せざるを得ない。福田は「まあしょうがない。天の声だよ。でも、天の声もたまには変な声もあるね」と感想を述べ、本選挙の辞退を表明した。派内や閣内には本選挙に出馬しろという声もあったが、福田は案外あっさりと辞任した。 こうして総理総裁の座は大平に移ったが、その立役者はいうまでもなく田中派であった。田中派は単に大平を応援しただけではない。この公選の過程で田中派の勢力を飛躍的に拡張し、のちに「田中軍団」と称されるその素地をつくったのだ。 |
| 大平時代 | |
| 1978(昭和53).12.1日、福田内閣退陣のあと、自由民主党史上、画期的な全党員・党友参加による総裁予備選挙の洗礼をうけて、大平正芳氏が第9代総裁に選任され、党内外の多大な期待を担って大平新内閣が登場した。その政治史的意味は、吉田学校内ハト派に位置し、田中派と共に戦後保守本流路線を再構築することにあった。 大平政権は、ますます厳しさを加える内外情勢と、多難な政治運営の実情をふまえて、「信頼と合意の政治」、「国民と苦楽を共にする政治」を基本姿勢に掲げ、内政的には「日本型福祉社会の建設」、都市の活力と田園のゆとりの結合をめざす「田園都市国家構想の推進」を二本柱に据えた。外交では、日米安保体制の堅持に加えて、質の高い自衛力の保持と経済協力、人づくり協力、文化外交の積極的展開等、多角的な外交努力を複合させた「総合安全保障戦略の推進」、開かれたゆるやかな地域連帯としての「環太平洋連帯の樹立」を打ち出した。 大平政権は同時に、三木、福田政権下で歪められた財政の不健全化の立て直しに向かった。54年度予算の公債依存度は39・6%に達し、財政事情はもはやこれ以上の放置を許されぬまでに悪化していた。54年に日本経済が本格的な景気の上昇軌道に乗ったのを見さだめると、同年十月の総選挙では、大胆にも「新たな負担」の是非を国民に問い、また55年度予算では、徹底的な歳入・歳出の見直し等によって、公債発行額を1兆円減額し、財政の公債依存度を33・5%に引き下げるなど、懸命の努力を続けた。 この間、党組織を飛躍的拡充させ、福田前総裁時代の150万党員・党友の獲得に引き続き、「300万党員獲得運動」、「組織整備三カ年計画」、「党員研修3カ年計画」など、党下部組織の量的・質的拡充に党をあげて取り組んだ。その結果、55年1月には、登録党員数は310万6703名、党友たる自由国民会議の会員数は10万7073に達し、党の裾野を広げた。 同10.7日、大平政権は、政局安定をめざして解散・総選挙に打って出た。第35回衆議院議員総選挙の結果は、前回の1979年の衆院選の獲得議席249議席を僅かに下回る獲得議席248、保守系無所属の追加公認を加えても258議席という不本意な結果に終わった。 この日から11.20日の大平内閣の本格的発足までの約40日間、党内抗争に明け暮れることになる。これを「40日間抗争」と云う。三木は、1976年の選挙結果を受け辞任に追い込まれたこともあって、大平首相の責任を問う声を上げた。選挙後に行われた三木・中曽根康弘・福田赳夫会談で、中曽根が「実力者会談に大平の進退を預け、最終的に福田が判断する」という案を持ちかけた。大平は、党機関に進退を一任すべきと主張し、政権続投の姿勢を鮮明にした。 大平政権下で反主流派となっていた福田派・中曽根派・三木派・中川グループは辞任要求を強めた。主流派の大平派と田中派は中道政党との連立政権を模索し、反主流派は最終手段として自民離党、新党結成を画策するなど、党内は修復不可能なまでに分裂した。西村英一副総裁が調停に奔走し、大平の進退を預かる形で三木、中曽根、福田と相次いで会談した。福田と大平の会談がセットされたが決裂に終わった。その後、首相候補問題と大平首相の責任問題は党機関へ一任することで進められていったが、その党機関を代議士会(衆院議員のみからなり、反主流派優勢)とするか、両院議員総会(衆参両院の議員からなり、主流派優勢)とするかで揉めることになった。 主流派の大平派と田中派は両院議員総会での首相候補決定を決断した。一方、反主流派は福田を首相候補とするために「自民党をよくする会」を結成。反主流派は両院議員総会が行われるはずの党ホールを椅子でバリケードを作って封鎖し、物理的に両院議員総会を阻止しようとした。浜田幸一が反主流派と交渉に臨むも解決できず、交渉を打ち切って実力行使でバリケードを強制撤去し、何とか両院議員総会を開催にこぎつけた。両院議員総会では大平首相を首相候補とすることを決定したが、反主流派はそれを無視する形で独自に福田赳夫を首相候補とすることを決定した。 党分裂を回避したい一部勢力が「大平総理・福田総裁」という総理・総裁分離案、「次回総裁公選を翌年1月に繰り上げ・翌年1月まで大平体制維持」とする妥協案を出した。大平−田中派は、「第一党の総裁が総理となるのが議会制民主主義の常道」としてこれを蹴り、反主流派の福田・三木・中曽根・中川一郎は大平が1度辞任するということで了承したものの、山中貞則ら強硬派が「大平が次回総裁公選に出馬しないことを了承しなければ認められない」と主張し不調に終わった。自民党は首相候補が一本化できないために、国会を開会することができなかった。国会開会の期限が迫ってきたので10.30日に特別国会を開会するも、開会日は首相指名投票なしで散会という異常事態となった。 大平首相は、首班指名で大平に投票した新自由クラブと閣内連立を模索して閣僚入りさせようとしたが、反主流派が 反発して組閣が難航した。11.9日、大平首相が文相を臨時代理という形で兼任して第2次大平内閣を発足させ、新自由クラブとの連立枠としての閣僚人事の余地を残す形で急場を凌いだが、11.20日、最終的に閣内連立を断念し、文相は自民党の谷垣専一を起用して抗争が一応終結した。しかし、この対立感情がその後も依然としてくすぶり続け、翌年のハプニング解散につながる。
1980(昭和55).5.16日、社会党がパフォーマンスの意味合いが強い内閣不信任決議案を提出したところ、自民党の反主流派が採決を公然と欠席してことにより可決されるというパブにングとなった。当の野党も驚き、民社党の春日一幸委員長は、「切れない鋸を自分の腹に当てやがって」と野党の未熟ぶりを嘆いたと伝えられている。大平首相は衆議院解散に踏み切り(ハプニング解散)、総選挙を参議院選挙の日に合せて行うという初の衆参同日選挙という秘策で政局乗り切りを図った。 大平政権は、社会党の党利・党略的な大平内閣不信任案が提出された機会をとらえて、「衆・参両院同日選挙」の実施という非常手段に訴えて、国民の信を問う勇断を下した。ところが、この選挙戦中、病に倒れ、6.12日未明、急逝した。開票の結果、衆議院284議席、参議院69議席の圧勝となり、その後の保守系無所属の追加公認と参議院の非改選議員を加えた現有議席では衆議院286議席、参議院136議席と、衆・参両院にわたり安定過半数の体制を確立した。 |
| 【鈴木時代】 |
| 1980(昭和55).6月、衆参同日選挙のさなかの大平首相急逝が、鈴木善幸に宏池会を引き継がせ、更に首相へと押し上げていくことになる。選挙は急逝した大平首相への同情もあり自民党が大勝した。選挙後ただちに後継総裁問題に突入したが、衆参両院選挙の圧勝により大平政権系譜の跡目相続を順当とするとの意見が党内大勢を占め、話し合いによる円満な後継者の選出が妥当との党議が固まった。田中六助が奔走し、田中角栄、岸信介、福田武夫ら元首相の了解を取り付け、その結果、7.15日、衆参両院議員総会で、西村副総裁の指名をうけて宏池会会長・鈴木善幸氏が第70代総裁に選ばれ、鈴木内閣が誕生した。 当時の局面に於いて、「一番無難な人物」として鈴木善幸が、議員総会満場一致で自民党総裁に選ばれ、第70代内閣総理大臣になった。鈴木は後に、「カネを一銭も使わないで総裁になったのは、僕がはじめてじゃないか」と漏らしている(升味準之輔著「日本政治史4」)。 しかし、鈴木善幸の知名度は低く、海外から「ゼンコーWHO?」と云われた。前尾繁三郎氏は、「幕が開かないうちに芝居が終わった」と語った。 鈴木首相は、生粋の党人出身政治家らしく、新内閣の発足に当たり、「自民党40日抗争」で深刻な亀裂の入った党内の融和を目指し、「和の政治」、「全員野球」を政治運営の基本姿勢に掲げた。内政面では、大平政権の行政改革・財政再建路線を踏襲し、「財政の再建」(「増税なき財政再建」、「84年度までの赤字国債脱却」)、「行政改革の断行」を最重点政策とし、他にも「政治倫理の確立と行政綱紀の粛正」、「総合安全保障政策の展開」、「エネルギー政策の積極的推進」、「活力ある高齢化社会の建設」などを取り上げ、これらの実行を通じて、「21世紀への基盤固め」を行うことを新政権の使命として出発した。 70年代から80年代への時代の転換期に辺り、行財政改革は緊急かつ不可欠の課題となっていた。とりわけ70年代不況で乱発された国債による財政状況が悪化しつつあり、公債発行残高は累増の一途をたどり、財政の再建は、一刻の猶予も許されぬ急務となっていた。このため鈴木首相は、「いまや抜本的な行政改革の推進と財政再建の達成なしには、1980年代の行財政運営の基盤を確立することはできない」として「21世紀を切りひらく行財政改革の断行」を掲げた。「増税なき財政再建」、「赤字特例公債依存体質からの1984(昭和59)年度脱却」の二大目標を自らに課し、その達成を目ざして最大限の努力を傾注した。 マイナス・シーリングによる予算編成を行う。56年度一般会計予算では、赤字特例公債発行額を二兆円減額して、一般歳出の伸び率を4.3%増に引き下げたのに続き、57年度一般会計予算でも、前例のないゼロ・シーリング予算を編成して、公債発行額を1兆8300百億円減額し、一般歳出の伸び率をわずか1.8%増に抑制するという、実に四半世紀ぶりの超緊縮予算を組み、財政再建路線を大きく前進させた。 このような行財政改革に賭けた鈴木首相のあくなき努力は、不幸にして56年度の税収が景気の予想外の低迷を反映して当初見積りより6兆1千億円も落ちこんだため、当初予算を2兆1千億円減額した57年度補正予算で、3兆9千億円の公債の追加発行を余儀なくされるという不運に見舞われた結果、赤字特例公債依存体質からの59年度脱却は事実上不可能となりましたが、それにしても「歳出削減−財政再建」路線を定着させ、58年度予算編成における5%のマイナス・シーリングのレールを敷いた功績は、きわめて大きかった。 一方、行政改革に本格的に着手する。1981(昭和56).3月、土光敏夫経団連名誉会長(当時)を会長とする臨時行政調査会(第2次臨調)、政府・自由民主党行政改革推進本部を発足させ、文字どおり政府・与党一体となって、行財政改革の推進に乗り出した。以後、臨時行政調査会は、「増税なき財政再建」をかかげ、56.7月から58.3月まで五次にわたり答申、鈴木内閣では三次まで)を提出していくことになる。 このほか、鈴木首相はまた、「金のかからぬ政治」の実現に取り組み、57.8月、多年の懸案であった参議院全国区制度を改革して、比例代表制を導入した公職選挙法の改正を断行したことは、わが国選挙史上画期的な出来事となった。 外政面で、西側の一員としての国際的責任の分担と対外通商摩擦の解消を目指し、首相自ら陣頭に立っての華々しい首脳外交の展開した。56.1月のASEAN(東南アジア諸国連合)5カ国歴訪を皮切りに、同年5月の米国、カナダ訪問、同6月の西欧8カ国歴訪、そして一息入れる間もなく翌7月には、カナダのオタワで開かれた先進国首脳会議出席、10月にはメキシコのカンクンで行われた南北サミット列席。明けて57.6月には、フランスのベルサイユで開かれた先進国首脳会議、引き続きニューヨークでの第2回国連軍縮特別総会出席、中南米歴訪、9月には中国訪問と、まさに文字どおり東奔西走、めざましい首脳外交を繰りひろげた。 二度にわたるサミット出席、西欧八カ国訪問等を通じて、西側諸国は困難な国際情勢下にもかかわらず、「和の精神」をもって団結と協調を強め、国際情勢に対する共通の基本認識と基本戦略で対処する必要がある旨表明し、世界経済再活性化のための経済的諸協力、第三世界に対する政府開発援助の五カ年倍増目標の達成等により、国際的な政治・経済的役割を果たしていく旨を国際公約した。 1981(昭和56).5月、レーガン米大統領との日米首脳会談で、「日米両国は民主主義および自由という共有する価値の上に築かれている同盟関係にある」ことを確認するとともに、「防衛問題における適切な役割分担が望ましい」等の合意内容を盛った共同声明を発表、よりいっそう緊密な友好親善関係を確立した。ワシントンでの記者会見で「シーレーン防衛」を約束し、日米共同研究に道を開いた。 しかし、財政再建を至上命題としていた鈴木首相は、レーガン政権の防衛負担の要求に対して消極的に対応し、この時の「日米同盟(alliance)関係」の意味にづけで「日米同盟には軍事的な意味は含まない」との解釈を示した。しかし、外務省は同盟には当然軍事的なものが含まれると解するとの見解を示し、首相と外務省(高島益郎外務次官)が対立、伊東正義外相(当時)と外務事務次官の辞任に発展した。 1982.10.12日、党総裁選で再選が確実視される中、「「新しい指導者の下、人心の一新をはかり、挙党体制を確立し、もってわが党に新たな生命力を与えることが、党総裁としての私のなしうる最後の仕事であると確信するにいたりました。退陣することで党内の結束と融和、人心の一新を求めたい」と電撃的に表明。総裁選への不出馬を表明、退陣した。 |
| 【派閥系譜】 |
| 自民党派閥で後々にも命脈を保って行く派閥は大きくわけて5系譜で、次の通りである。 1、吉田茂を源流とし、池田勇人、前尾繁三郎、大平正芳、鈴木善幸、宮沢喜一へと続く派。 2、吉田茂を源流とし、佐藤栄作、田中角栄、竹下登、小渕、橋本へと続く派。 3、田中角栄を祖とし、竹下派経由で羽田孜、小沢一郎へと続く派。 4、岸信介を源流とし、福田赳夫、安部晋太郎、三塚、森派へと続く派 5、三木武夫を源流とし、河本敏夫へと続く派。 6、河野一郎を源流とし、中曽根康弘へと続く派。 7、中曽根康弘を経由して、渡辺美智雄、江藤・亀井派へと続く派。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)