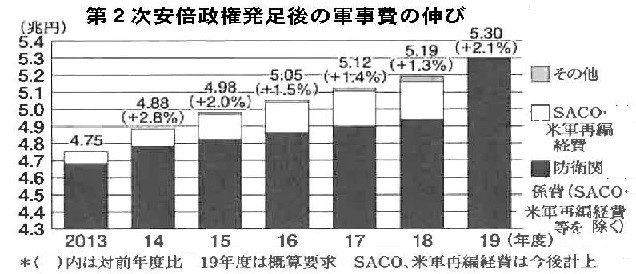1997年度の消費税引き上げで消費税収の対GDP比は1.6%から2.7%(+1.1%)に上昇しました。倍率にして1.69倍。3%→5%が1.67倍ですから大体税率引き上げ分と同じぐらい税収が増えています。グラフを見れば分かる通り、所得税や法人税に比べて極めて安定した税収が望めます。増税の議論で消費税が第一に出てくるのは、消費税収の対GDP比が国際的に見て低いこともさることながら(参考:日本の税収はOECDの下から3番目 - DeLTA
Function)、この安定性が財政サイドからすれば魅力的であるからでしょう。
ただ問題なのは短期的には景気に悪い影響を与えるわけですから他の税収が減ります。94~96年度は税収の対GDP比は10.2~10.4だったのが97年度には10.5%に増えています。景気が悪くならなければ10.2+1.1=11.3%に増えているはずなのですが、そうはなっていません。その後この対GDP比を上回ることは一度もなく、最も高かったのが2000年度の10.1%。その後だと2007年度の9.9%が最高です。結果として消費税増税で税収は減ってしまったのです。
1997年度の引き上げで不幸だったのはアジア通貨危機と三洋証券や山一證券、拓銀、長銀などの大型金融機関の破綻と重なってしまったことです。私としては98年の本格的デフレ突入は消費税引き上げよりこれらの影響のほうが大きかったと考えていますが、デフレ悪化に一役買ってしまったのは確かでしょう。消費税の5%引き上げが固まったのは94年11月で、94~96年頃は比較的景気も良好でした。こういう状況で97年のような金融危機が起こることを予め想定しておけというのは中々厳しい話で、橋本首相(当時)が増税延期に踏み切らなかったのも致し方ないと思います。タイミングが悪かったのは確かです。ただデフレ突入の全ての責任を橋本首相に負わせるのはどうかなと。
さて、この教訓から得られることは増税はタイミングが大事だということです。不況期にさらにブレーキかけるようなことをすれば増税しても税収は増えません。ただ、下のグラフにある通り、景気が回復してもいずれ増税しなければ財政の悪化は進行していきます(プライマリーバランスが安定的に黒字化したのは、赤字国債の発行が行われた1965年以降で見るとバブル景気のときだけです)。しかし今、増税の話が先行すれば景気をさらに悪化させて税収を減らすだけで本末転倒です。残念なことに民主党も自民党も増税の話ばかりになっています。全く愚かという他ありません。
税収は増えない中で歳出は順調に増えていっています。特に社会保障関係費です。このまま増えていけば消費税を10%(対GDP比で総税収が最大2.7%増)に引き上げても足りません。増税は必要ですが社会保障関係費の抑制もまた必要です。ちなみに2006年度に印をつけていますが、これはこの年度が近年最もプライマリーバランスの赤字が小さくなっていますが、これは税収増のおかげではなく(税収は減ってます)、大規模な歳出削減のためということを強調するためです。歳出削減が如何に重要かということです。
好況期では税収は成長率以上に増えて歳出は減るのですが、不況期では税収が大きく減る割りに歳出は減りません。むしろ増えることもあります。そのため中長期的には増税して税収を増やさないと財政の悪化が進んでいきます。ただ大事なのは増税は安定成長の軌道に乗った上での話です。リフレ政策の一環として消費税凍結+数年後引き上げのコミットメントを打ち出すなら分かりますが、財政再建のために増税なんて話は逆に財政を悪化させるでしょう。景気が悪化して税収が増えないのですから。

 DeLTA
Function
DeLTA
Function