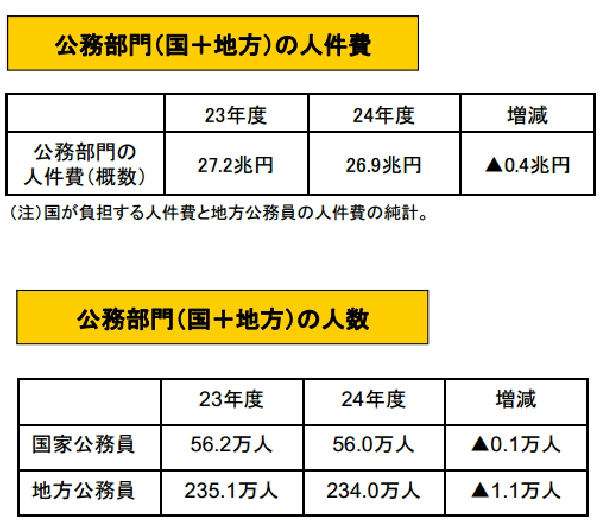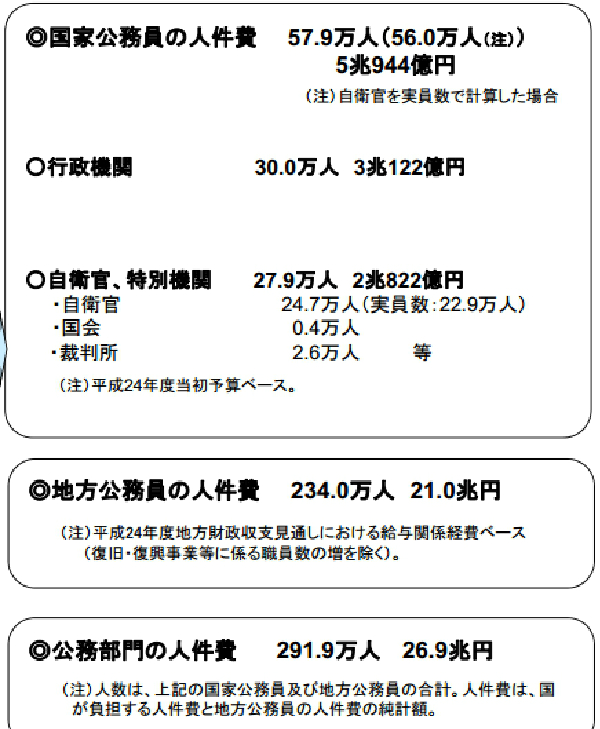所得格差が、日本でもこんなにあるとは知らなかった。相対的貧困率が2009年の厚労働省の調査であるが、国民の6人に1人が年間112万円未満で生活していることになるが、過去最悪の16,0%となった。
当然、生活保護費の水準にすら達しない金額だ。OECD(経済開発協力機構)の2000年代半ばの貧困率調査でも、日本は加盟30カ国中、4番目に悪かった。この格差を驚く人も多いのではないだろうか・・・。
OECDが敢えてこうしたデータを使用した理由は、日本においてはコスト削減を進める企業がパートやアルバイトなど賃金の安い非正社員を増やしたことが所得の二極分化を助長させたという報告書の主張と整合的であるための他、敢えて刺激的なデータを出して、OECDへの多額の拠出国日本のOECD報告書への関心を高めるためだと言う見方もあるが・・・。
民主党政権は3年前、貧困解消に向けた取り組みとして初めて06年の貧困率を公表。2回目となる今回はそれより、0・3ポイント悪化したのだ。
驚いているばかりではいられない。憲法は健康的で文化的な最低限度の生活を国民に保障している。いつまでに、どういう方法で、どれだけ貧困率を改善するのか。政府は、数値目標を設けるなど実効力のある対策が必要だ。
貧困率が悪化した原因は、所得の低い65歳以上の高齢者や非正規労働者の割合が増えたためだとされる。
最低賃金の引き上げは、企業にとっては負担が大きい。半面、労働者が消費に回す金が増え、景気浮揚効果もある。雇用し、労働に見合った賃金を支払うことが、地域や社会の向上につながる。それこそが企業の社会的責任だろう。
非正規労働者は、厚生年金や健康保険が適用されない場合がほとんど。政府の「社会保障と税の一体改革案」でも正規労働者並みの扱いを求めており、早期の実現が必要だ。
東日本大震災により、被災した企業から雇い止めされる派遣労働者も増えているという。手をこまねいていては、貧困率はさらに悪化するだろう。多くの政策を網の目のように張り巡らすことで、困窮にあえぐ人を救うことがなにより大事である。