| 元毎日新聞記者の西山太吉氏が、2月24日、心不全のため北九州市の介護施設で亡くなった。91歳だった。スキャンダル発覚後、猛バッシングを受けた西山氏であったが、平成に入って、西山氏がスクープした沖縄返還に伴う日米密約の存在を示す文書がアメリカで見つかって以降、再評価する動きがあった。いま言論界は追悼ムードだが、忘れてはならないのは、西山氏に“情を通じて”機密文書を渡したことが罪に問われ、職と夫まで失ってしまった外務省女性事務官の存在である。騒動の真っ只中、女性事務官が「週刊新潮」に寄せた手記を紐解きながら、昭和史に残る不倫スキャンダルを振り返りたい。 |
| 私の弱さが原因だった |
【「週刊新潮」昭和49(1974)年2月7日号「外務省機密文書漏洩事件 判決と離婚を期して 私の告白」ダイジェスト版の前編】
※掲載時、女性事務官を実名で報道していましたが、本稿ではプライバシーに配慮し匿名にしました。 |
〈事件のあらまし〉
いわゆる外務省機密文書漏洩事件とは、昭和四六年六月に調印された沖縄返還協定に絡んで、“黒い疑惑”があるとして、毎日新聞西山太吉記者が、愛知(揆一氏。当時、外務大臣)・マイヤー(当時、駐日大使)会談の内容と思われるものを毎日新聞紙上に発表したが、さしたる反響を得られなかった。
が、その後、国会で、社会党の横路孝弘代議士が質問、そのとき、このマル秘文書のコピーを横路代議士が外務省関係者に見せたことから、機密漏洩が明るみに出た。問題の文書を西山記者に渡した、といってA外務省事務官(41・当時)が警視庁に出頭。西山記者がA事務官と「情を通じて」、この文書を手に入れたことが判明。西山記者も逮捕された。毎日新聞は、「知る権利」を振りかざして応戦したが、西山記者の取材方法は、国民のみならずジャーナリズム界に多大なショックを与えた。
***
まるで人生が、すべて過ぎ去ってしまったかのような二年間であった。もし私が、こんなにも世間を騒がせた、いわゆる「外務省機密文書漏洩事件」などに巻き込まれなかったなら、おそらくいまなお外務省のごく平凡な女性事務官として、霞が関に毎日出勤し、書類や電話の応対に余念がなかったろう。大臣や次官、あるいは外務審議官などの秘書を、外務省では「付き」というふうに呼ぶが、私も相変わらずその「付き」の一人に数えられていたに違いない。事件当時、私の上司でいらした安川外務審議官が、現在、駐米大使をお務めだから、たぶん、私は後任の新しい外務審議官の「付き」になっていたかも知れない……。いや、もうよそう。そんなむなしい想像をいくら繰り広げたって仕方がない。愚かな女の感傷だといわれれば、一言もありはしない。いまさら、外務省が懐かしく、私の“誇るべき職場”だったといっても、誰が信じてくれよう。その懐かしく、誇るべき職場を私自身が深く傷つけてしまったことは世間周知の事実だし、そのために私は法の裁きまで受けたのである。たしかに今度の事件は、私の弱さが原因だった。しかし、決してそれがすべてではない。私の弱さ以上に、もっとあくどく、卑劣な力が「知る権利」の名において私をがんじがらめにした。弁解する気なんぞない。ただ、私にふりかかったいまわしい事実だけは、私の弱さとともに神さまに懺悔するような気持ちで、いまハッキリと告白しておきたい。 |
運命の私鉄ストライキ
〈西山氏は、毎日のように審議官室にやってきて、顔パスで入れるほど安川審議官に信頼されていた。Aさんは《のちに法廷で、私がいかにも西山記者に好意を抱いていたかのような証言や弁論があったけれども、私は「この方は安川審議官の大事な人なんだ」と考え、職務上親切にしたに過ぎない。それを不遜な西山記者は、私が愛情を示したなどと誤解していたのではあるまいか》と憤りを隠さない〉
西山記者に誘われた日を私は決して忘れない。昭和四十六年五月十八日。ちょうどその日は私鉄がストライキをやり、われわれが霞が関から乗る地下鉄もまた止まっていた。実をいうと、西山記者から“誘い”を受けたのは、その日が最初ではない。以前にも何回か、私と、同室の男の同僚に、
「いつもお世話になっているので、一度食事に招待しよう」といってくれた。しかしそれが一度も実行されなかった。同僚とよく、 「空手形かもしれないわね」と笑い合ったものだった。ところが、五月十八日にはその手形が確実に決済された。しかも、私の運命と引換えに彼の卑劣な“招待”は実現されたのである。いつものように審議官室から出て来た彼は、私にこういった。
「みんな、足がなくて困ってるんじゃない? 送ってあげよう」。私は即座に「結構です」と断ったが、同僚の男の事務官が、 「ぼくはいいから、Aさん送ってもらいなさい。せっかくああおっしゃってるんだから……」としきりに勧めてくれる。そこでようやく送っていただくことに意は決したが、とっさに、「毎日新聞社はどこにあったかな」と考えた。私は「付き」という職務上、記者の方にあまりご迷惑をかけてはいけないと思ったのだ。なるべく、毎日新聞社のある竹橋に近い東京駅か有楽町で車を降ろしていただいて、あとは国電で浦和の自宅まで帰ればいい……。
だが、西山記者の車はなかなか来なかった。「君が好きだ」と何度も繰り返した。ほんとは別の審議官「付き」の女性の事務官と新橋まで歩いて帰ろうと思っていたのだが、事情を告げて彼女を先に送り出してしまった。「こんなに遅くなるのなら、彼女と帰ればよかった」と少しばかり後悔していた時、西山記者から電話がかかった。
「もうじき車が来るから、もうちょっと待っててね」。西山記者には正面玄関で待つように指示されていたが、車が来たのは午後七時近くであった。車は毎日新聞と契約のあるらしいタクシー。西山記者は私よりもあとから正面玄関に現れた。
「ご迷惑をかけてすみません。有楽町か東京駅で落として下さい」と私はお願いした。車が外務省を左に折れてお濠の方向へ向うと、西山記者がポツンといった。
「これから新宿へ行こう。食事でもしようじゃないか」。私は一瞬あわてて答えた。 「今日は、申しわけないけど結構です」。彼は、常日ごろ、同僚の男の事務官と私の二人を招待するといっていた。その日は、私一人しかいないのだから、同僚にも悪い気がして、ひどく困ったのである。それでも強引な西山記者は、
「今日はいいチャンスだから、ご馳走しよう」と動じない。さっさと車の運転手に「新宿にやってくれ」と告げた。私の同僚をご馳走するについては、又別に機会を作るともいった。
新宿ではコマ劇場の裏の『車』という料理屋に入った。西山記者はウイスキーの水割り、私はお刺身にビールなどを頂いたが、はじめは、とりとめのない話をしていた。やがて、何杯かウイスキーの水割りを重ねた西山記者はいくらか酔い始める。そして突然、私にささやきだした。いま考えると、あれはまさしく“悪魔のささやき”であった。おまけに、少々お酒のまわった私の頭に、彼の甘く、かつ、けばけばしい言葉がまるで矢のように飛び込んできた。
「ぼくは君が最初から安好きだった。ぼくは毎日のように外務審議官室に行くのも、実は君の顔が見たかったからだ。ほんとに、ぼくは君の顔を見ると、たまらなくなる……」。あとは「君が好きだ」を何度も何度も繰り返した。
「ぼくはほんとうに君が好きだなあ。Aさんは個性的だよ」。 |
ちょっとどこかで休んでいこう
落ち着いて考えれば、これほど歯の浮くようなお世辞はない。ただ、その時の私は、この「個性的だよ」という言葉に酔った。それにお酒のほうの酔いも加わって、かなりいい気になってしまったことも確かだった。しかし、私は夫のいる身である。夫は私の行動にいたってきびしいし、こわい。いちいち口ではいわないまでも、私の帰宅時間や酔っていたかどうかなどをこまかくメモしている。私は早く帰ろうと考えた。けれども、西山記者は「もう一軒まわろう」といいだしたのだ。西山記者は私の肩を抱きかかえるようにして、『車』とはそう離れていない『スカーレット』という店に私を連れていった。今度は私もウイスキーの水割りを何杯か飲んだ。彼に誘われるまま踊りもした。この間、西山記者は私に対して“甘い言葉”のささやきっぱなしであった。私自身も酒と、西山記者の“愛の告白”に酔いつづけた。
『スカーレット』を出た時はもう十一時近く。「今度こそは帰らなければ」と私は懸命に考えた。 「今日はどうも……」といって、西山記者と別れようとすると、そんなアイサツなど耳にも入らなかったかのように、彼は、
「ちょっとどこかで休んでいこう」という。 「そんなこと結構です。私、帰ります」と断っても、ぜんぜん相手にしてくれない。いきなり私の肩に手をまわして、
「いいじゃないか。ちょっとでいいから休んでいこうよ。これだけ酒を飲んだから、もうたまらないんだ」。
生理だってかまわないよ
強引も強引。ほとんど力づくで『スカーレット』からさほど遠くない旅館に私を引っ張っていった。なぜ、あの時、私も強引に帰らなかったのか。いま、いくら悔やんでみても始まらないが、西山記者のささやきとお酒との両方に攻めたてられた私の気持はとても複雑だった。明らかに足が地面についていなかったのである。ともかく、旅館には私も入ってしまった。もう、頭はまるで混乱していた。夫の顔が目の前をチカチカする。何だか体から力がすっかり失われていくような感じがした。陶然としているわけでもなければ、気がめいっているわけでもない。自分であって自分ではないような、奇妙な状態のまま、私は旅館の部屋の中にいたが、突如、その日、私自身が生理であったことを思い出した。とたんに私の気持はさらに動揺し、生理に見舞われている私の体に対する心配やら恥ずかしさやら、頭の混乱は極度に達した。部屋の中で、もうとっくにその気になっている彼に無我夢中で私はいった。
「私、今日、生理なんです。どうかそれだけはお許し下さい」。自分でも不思議なくらいバカ丁寧な言葉を使った。ところが、西山記者はどっかりと落ち着いていた。
「生理だってかまわないよ」。すべては終わった。「愛の余韻」などとても味わっているヒマはない。私は急がなければならない。夫のことが気になって仕方なかったのだ。大急ぎで旅館を出ると、西山記者がタクシーを止めてくれた。彼はタクシーの運転手に、
「この人を送ってやってくれ」 と、五百円札を渡した。ちょっとイヤな感じがすると同時に、「浦和までの車代にはとても間に合わない」とも思った。尊大で一方的な西山記者は、およそ人のことを考えない。自宅に着いたのは、午前零時をすでにまわってからであった。まだ起きていた夫は、
「遅いじゃないか。明日もあるんだから早くやすみなさい」と、それだけいった。何かニュアンスから、夫はすでにわかっているのではあるまいかという気がして、胸の中に暗いわだかまりが生れた。「申し訳ありません」――。それまでにもお酒を飲んで遅く帰ったこともあるが、あの晩ほどではなかったのだ。その上、私は、西山記者の言葉に酔わされ、流され、とうとう最後の一線を越えてしまった……。
(「西山事件」外務省女性事務官「悔恨の手記」に綴られていた悲痛な叫び 「西山記者と毎日新聞は私の最後のトリデである家庭までも破壊した」に続く)
デイリー新潮編集部 |
| 「ベッキー騒動の比じゃなかった」。「西山事件」を記憶する人は口を揃えてこう言う。いまよりはるかに不倫への風当たりが強かった昭和40年代、「世紀のスクープ」のウラに”情を通じた”女性が存在したことを知って世間は怒り狂った。新宿の「連れ込み旅館」で西山氏と一夜を共にした後、Aさんは西山氏から強引に機密書類を見せるよう要求される。機密漏洩が発覚した後、西山氏と毎日新聞が取った”不誠実な対応”とは……。 |
| 【昭和49(1974)年2月7日号「外務省機密文書漏洩事件 判決と離婚を期して 私の告白」ダイジェスト版の後編】※掲載時、女性事務官を実名で報道していましたが、本稿ではプライバシーに配慮し匿名にしました。 |
二度目の逢瀬
翌日、役所で西山記者から私のデスクに電話がかかった。また次の土曜日に会いたいというのである。まわりに人はいるし、私はまごまごしてしまう。それをいいことに、西山記者は会いたいの一点張り。早く電話を切るためにも、つい私のほうから時間と場所を指示してしまった。土曜日の午後二時、『ホテル・ニューオータニ』のバー『カプリ』。以前、外務省の方に連れていっていただいたバーなのだ。
たしかに、西山記者と私とは特別な間柄になってしまった。しかし、どうしたわけか、ぜひとも彼に会いたいという感情はさほどわいてはこなかった。『カプリ』で待ち合わせたのも、必ずしも愛情の上の期待からではない。電話を早く切ってしまいたかったことと、「お食事程度ならもう一度くらい……」と軽く考えたのである。約束通り、土曜日の午後二時、私は西山記者と『カプリ』で落ち合った。「ともかく外に出よう」と彼にうながされ、ホテルの前でタクシーに乗り込んだ。
「横浜に行こう」と、彼は勢いよくいう。バカな私はその時、あまり行ったおぼえのない横浜を頭に浮べて、「今日は中華街でお食事でもするのかな」なんて、ほんのちょっぴり胸をときめかしたりした。ところが、車が動きだすと、「いまから横浜へ行くと遅くなるなあ」と独り言のようにいい、「渋谷にしよう」と、今度は断定的につぶやいて、運転手にそう命じた。「渋谷のどこですか?」と私がたずねると、「別にどうというところじゃないよ。ゆっくりできる場所があるから、そこで話をしよう」。 |
書類をこっそり見せてくれないか
それからはおたがいに黙って、窓の外を過ぎ去っていく都会の煩雑な風景をながめていたが、まさか車の到着地点に、『ホテル山王』があろうとは想像もしなかった。しかも『ホテル山王』は、この間の旅館と違って、別段、いかがわしい環境の中にあるわけでもない。ホテルの前に立つと、西山記者が、さも私を安心させるように、「ここはよく仕事で疲れた時、体を休めるために使ってるんだ」といった。男と女の間で、たった一度の経験ほどこわいものはない。決して西山記者にいとおしさや懐かしさをおぼえたはずもないのに、わずか一度の、しかも彼の強引さによる経験で、もう私は彼のいうままにホテルの一室に入っている。部屋に入ると、彼は待ちきれなかったように、「君と会えてうれしい」と、私の耳元でささやいた。そして、この前と同じように、大げさな愛の表現を使って私を酔わせた。意思の弱かった私は、ふたたび彼に身を託してしまった。不幸なクライマックスが急激にしぼみ、けだるさと罪悪感にさいなまれながら、私は身づくろいをして、帰り支度にかかった。その時である。西山記者が、いくらかきびしい目つきをして、私に「頼みたいことがある」と語りかけた。「実はぼくは、近く記者としての生命を絶たれるかもしれない。ぼくは記者としての生命を絶たれるんだ。もうダメになってしまうんだ。外務省の書類を見ないと記事が書けないんだ。安川(審議官)のところへ来る書類をこっそり見せてくれないか」。いい終わった時、西山記者は手を合わせて拝む格好をしていた。私はいっぺんに目が覚めたような気持になった。そして、「そんなことはできません」とほとんど叫ばんばかりにいい放った。私は仮にも安川審議官の「付き」である。その私が、どうして安川審議官のところへ来る外務省の書類を隠れて他人に見せることができようか。しかし、西山記者はなかなかあきらめない。それどころか、私の肩に手をかけ、顔を近づけて「頼む、な、頼むよ、な」と繰り返し、「ぼくを助けると思って頼む。安川にも、外務省にも絶対に迷惑をかけはしないから。ただ参考にするだけなんだ。見せてもらった書類はその場で返すから……」と、私の言い分など絶対に聞き入れない姿勢を見せた。いや、もし私が断り続けたら、あのホテルから一歩も外に出してもらえなかったかも知れない。「なあ、頼む、なあ、頼む」を執拗に耳元でささやかれ、とうとう私もコックリとうなずいてしまった。いまさら、私がだらしなかったといっても始まらないが、その時も自分の弱さがつくづくいやになった。 |
書類を渡した後は「事務的に抱かれるだけだった」
頭の中がクモの巣だらけみたいな重い気分の日曜日が過ぎ、月曜日、役所に出ると、やはり西山記者から電話があった。「書類を持って『ホテル・ニューオータニ』に来てくれ。社旗を下ろした車で『ホテル・ニューオータニ』の入り口まで行くから、その車のあとをタクシーでつけてくれ」。いつものように全く一方的で強引な西山記者の“命令”が受話器に響く。しかし、その声を聞いたとたん、私の考えや動作は、不思議と西山記者の“命令”に従う。バカなんか通り超してもはや夢遊病者でしかない。安川審議官のところに届けるべき書類をこっそり持ち出して、私は『ニューオータニ』に向った。
〈それからAさんのデスクには《来る日も来る日も》《安川審議官が役所を退出になる午後六時十五分から三十分の間に》、西山記者から電話がかかってきたという。Aさんは《西山記者が私を誘った意図もはっきりとわかってきた》とも記しているが、《命令的な『頼む』》を断りきれず、言われるがままに機密書類をホテル山王などに届けるようになる。Aさんは不倫関係を夫や安川審議官に暴露されるのではないかという恐怖があったとも訴えている〉
西山記者はたった一度だけ「書類を一晩貸してくれ」といって秋元事務所(注・秋元秀雄氏。元読売記者のジャーナリスト)から持ち帰ったことがある。あとで私が知ったのだが、それが事件を起こした、あの「沖縄問題に関する愛知・マイヤー会談」の秘密文書だったのだ。むろん、その書類は翌朝返してくれたが、一晩貸していた間に西山記者はコピーを取ったのだと思う。
書類を持ち出し始めてから、西山記者の私に対する態度は、かなり変わっていった。もう『ホテル山王』で会っても、決して甘い言葉なんかささやかない。私をごくごく事務的に抱いて、あとは私が持っていった書類に目を通し、おたがいほとんど言葉を交わさずに別れる。間違いなく私は彼にひっかかっている |
外務省をやめてもらう
〈昭和四十七年三月、「外務省機密文書漏洩事件」が新聞で報道され始める。翌日、Aさんの耳に「いま問題になっている重要書類は、安川審議官が見る前に持ち出されたものだ」という話が伝わってきた。その翌日の未明、自宅で待機していたAさんに西山氏から電話が入った〉
「私の質問に答えて下さい。いま問題になっている(外務省機密文書)事件に私は関係あるのですか、ないのですか」。いつも尊大な西山記者も、この時ばかりはややおどおどしていた。「オレのちょっとしたミスだった。オレはいまの君を心配している。ともかく君には即座に外務省をやめてもらう」、「外務省をやめてもらう」と聞いて、私は跳び上がった。「やめる? やめたら困るんです。そんなことはできません。私には主人がいるんです」と、ほとんど叫んでいた。病身の夫はやむなく私の細腕を頼りにしているのである。いまやめたら、いったい二人はどうなるのか。しかし、西山記者はやや冷静に、「ともかく外務省はやめてもらう。君のことは社をあげて考えている。政治部長も動いている。退職金もこっちで考える」。電話を切った私はすこぶる興奮しており、夫はそばでその私をじっと見つめていた。私は包み隠さず、ことの一切を夫に話した。夫は決して取り乱さなかった。むしろ私をなぐさめるように、「そうなってしまったことはもう仕方ない。まず退職届を出してすべてを安川審議官にお話しし、彼の指示に従いなさい」といってくれた。
〈翌朝、真実を告白したAさんに安川審議官は「残念だけど……、非常に残念だけど……、西山を君に近づけたぼくが悪かった。ぼくから記事が取れないものだから、彼は君をねらったのだ」と語った〉 退職届は安川審議官があずかって下さったが、翌日、正式な始末書も提出した。始末書は東京駅で男の同僚に渡したのだが、その帰り、うっかり間違えて山手線に乗り、日暮里で降りた。この時、フラフラと電車に飛び込みかかったが、夫のことが頭をはなれなくて、結局、自殺は思いとどまった。警視庁に出頭したのは、安川審議官のご指示による。私は警視庁に行く前に、もう一度西山記者の考えを確かめようと、電話で連絡をとった。西山記者は、私が警視庁に出頭すると聞いてびっくりしたようだった。そして、西山記者はこういった。「社をやめても君を助ける。しかし、警視庁に行くのなら、取り調べに対してはこういってくれ。君がオレに渡した書類は三通。渡した場所は外務省の中、いっしょに食べた食事は渋谷で一回、と……」。私はほんとにどうかしていた。また西山記者の口車に乗せられ、警視庁での取り調べに対し、最初は彼の指示どおりに話してしまった。しかし、そんなウソはたちまちばれてしまった。 |
西山記者と毎日新聞への怒り
〈逮捕二日目、取り調べ室で真実を語り始めたAさん。向かい合った刑事は「Aさん、こういうところに来て、人をかばったって仕方がないよ。あんたのほうが人を信じていても、相手はあんたのことなんか考えていないかも知れない。人間はみんな自分の身がかわいいからね。あんたも自分のことだけ考えればいんだよ。自分の身をだけを大事にすればいいんだよ」と諭した。その後、二人は逮捕・起訴され、裁判にかけられることになった〉 以来、西山記者と顔を合わせたのは、最初の公判廷でのことだった。彼は特別に裁判長の許可を得て、私への謝罪を行った。それも裁判長のほうを向いて……。しかし、あんなところで謝罪するなら、なぜ新聞で大騒ぎになった時、積極的に私のところへすっ飛んで来てわびてくれなかったのか。公判で謝るなんて、裁判で自分の立場を有利にするポーズとしか思えない。結局、西山記者と毎日新聞は、いつも自分たちに都合のいいほうを向いて謝っている。新聞紙上に「遺憾の意」を表明したのもそうだと思う。何よりもまっさきに、なぜ私に謝り、そして私を保護してくれなかったのだろう。事件の最中でも、事件のあとでも、一度もそういう誠意を示してくれなかった。夫にいわせれば、ジャーナリズムの上で、私は「情報源」と呼ばれるのだそうだ。「情報源」は最後までジャーナリストに保護されるものだとも聞いた。西山記者は、私を保護してくれるどころか、警視庁の取り調べにウソまでつくようにしむけた。私がワァッと泣いて「刑事さん、ウソをついてごめんなさい」といった時の気持が、西山記者と毎日新聞にわかっていただけるだろうか。身も心もすりへらされたこのあわれな「取材源」は、留置場を出て、それから神経科の病院に入院したが、もう生きる力を失ってしまった。
〈手記の最後は絶望に満ちた言葉でこう結ばれている〉
主人と私の結婚生活もついにピリオドを打つ時が来た。西山記者と毎日新聞は私の最後のトリデである家庭までも破壊してしまった。私は私の半生を孤独に生きるべく運命づけられた。しかし、これも私の人間としての弱さから出たことだと思って、あきらめざるを得ないのであろうか……。最後に、外務省のみなさんや世間のみなさんに深くおわびします。 |
|
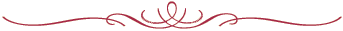
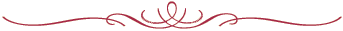
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)