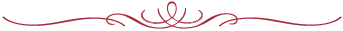東照宮御實記卷五 慶長八年二月に始り四月に終る御齡六十二
慶長八年癸卯二月十二日、征夷大將軍の宣下あり。禁中陣儀行はる。上卿は廣橋大納言兼勝卿、奉行職事は烏丸頭左中辨光廣、弁は小河坊城左中弁俊昌なり。陣儀終て勸修寺宰相光豊卿勅使として已一点に伏見城に参向あり。上卿奉行職事はじめ月卿雲客は轅、その他大外記官務はじめ諸官人は轎にのりてまいる。みな束帯なり。雲客以上は城中玄関にて轅を下り、それ以下は第三門にて轎を下る。この時土御門陽陰頭久脩御身固をつかふまつりて後、紅の御直埀めして午刻南殿に出給ふ。今日参仕の輩、諸大夫以上直垂、諸士は素襖を着す。勅使にまづ御対面ありて公卿宣下を賀し奉る。次に上卿職事辨みな中段にすゝむ。告使中原職善庭上にすゝみ、正面の階下に於て一揖し、声折して御昇進と唱ふる事二声、一揖して退く。次に廣橋勸修寺兩卿は上段第二の間の中程に左右にわかれて着座す。奉行職事參仕の辨等は第三の間に左右に别れ座につく。時に壬生官務孝亮廣庇に伺候す。副使出納左近將監中原職忠征夷大將軍の宣旨を亂箱に入て、小庇の方より持出て官務にさづく。官務これを捧てすゝむ。大澤少將基宥請取て御前に奉る。御拜戴有りて宣旨は御座の右に置き、基宥亂箱をもちて奥にいる。永井右近大夫直勝その箱に砂金二裹入て基宥に授く。基宥是を持出で官務にさづく。官務拜戴して退く。次に源氏長者の宣旨は押小路大外記師生持參し、基宥受取て御前に奉り、箱は基宥とりて奥に入り、直勝砂金一裹を入れ、基宥これを持出で大外記に授け、大外記拜戴して退く。そのさま上に同じ。次に官務氏長者の宣旨持出す。次に大外記右大臣の宣旨持出す。次に大外記官務牛車宣旨持出す。次に隨身兵仗の宣旨大外記持出す。次に淳和弉學両院别当の宣旨官務持いづる。その度ごとに亂箱に砂金一裹づゝ入て賜はる。次に職事辨等座を立つ。次に上卿勅使太刀折紙もて拜謁せられ基宥披露し、次に職事弁以下太刀折紙持出で、三の間長押の內にて拜し、大外記以下は太刀を三間の內に置て廣庇にて拜し、官務出納少外記史も同じ。次に陣の官人召使等太刀は献ぜず。廣緣にて拜して退く。次に右近大夫直勝、西尾丹後守忠永(寬政重脩譜には忠永この時未だ酒井の家に在て主水と稱すとあり)役送し、兼勝卿に金百両、御紋鞍置馬一疋、光豐卿に金五十両。鞍馬一疋遣はされて後奥に入御あり。次に參仕の官人召使等なべて金五百疋づゝ纏頭せらる。抑征夷の重任は日本武尊をもて濫觴とするといへども、文屋綿丸、坂上田村麻呂、藤原忠文等は禁中に召宣下有しなり。
幕府に勅使をつかはされて宣下せらるゝ事は鎌倉右大將家にもとひす。その時は鶴岡八幡宮に勅使をむかへ、三浦次郞義澄、比企左衛門尉能員、和田三郞宗實、郞從十人甲胄よろひて参りその宣旨をうけとり、幕下西廊にて拜受せられしこそ、この儀の權輿とはすべけれ。足利家代々この職をうけつがれしかど、等持院、寳篋院、鹿苑院三代の間は時いまだ兵革の最中なれば、典礼儀注を講ぜらるゝに及ばず。およそは勝定院のころよりぞ。式法もほゞそなはりけるなるべし。それも応仁よりこのかたは、幕府また亂逆のちまたとなりぬれば、礼義の沙汰もなし。こたびの儀はその絕たるをつぎ廢れしをおこされ、鎌倉室町の儀注を斟酌して、一代の典礼をおこさせ給ひしものなるべし(この日の作法は宣下記幷に勸修寺記。西洞院記にほゞ見ゆるといへども、麁略にして漏脫多し。ひとり出納職忠記詳なれば、今は職忠の記にしたがひてこれをしるし、宣下記、勸修寺記、西洞院記の中にもほゞそのとるべきをとりて補ひぬ。この時の作法は当家典礼の權輿といへども、いまだ全備せしにはあらず。これより世々たびだび沿革ありて、今にいたりて全く大備せしといふべし)。
次に勅使上卿をはじめ奉行職事辨を饗せられ、三宝院門跡義演准后出座して相伴せらる(三宝院は室町將軍家代々宣下のとき、出座して饗應の席に連る例なりしをもて、けふも召れしとしられたり。この門跡かならずこの式にあづかりしは、滿濟准后の鹿苑院將軍の猶子となられしよりこのかた、代々室町家の猶子ならざるはなし。その中には室町家の実子にて住職せしもあれば、この門跡かの家にては代々一門宗族のちなみにて、かかる礼禮にあづかりし事と見えたり。この外にも室町家出行の時は、三宝院の力者に長刀をもたしめられし事あり。この日出座ありし義演准后といふも、靈陽院の猶子なりしとぞ)。
この日、越前中將秀康朝臣を従三位宰相にのぼせらる(藩翰譜備考日を記さず。今家忠日記による)。又板倉四郞右衛門勝重は京所司代たるにより、豐臣家の例によりて騎士三十人、歩卒百人を付属せらる。又本鄕治部少輔信富はその家代々室町將軍家につかへ、将軍家の制度儀注にくはしければ、この後伏見に伺候して奏者の役をつとむべしと面命あり。伏見城下に於て宅地をたまふ。信富は世々足利將軍の家人なり。信富にいたり光源院義輝將軍につかへけるが、三好長慶が叛逆の時若狹の国本鄕の所領を沒落し、後に靈陽院義昭將軍につかへその後織田家にしたがひ、去年十月二日召れて采邑五百石を賜はりしなり(將軍宣下記。勸參寺記。西洞院記。中原記。續通鑑。家忠日記。家譜。寬政重修譜)。
○十三日、秋元茂兵衛泰朝從五位下に叙し但馬守と改む。この日生駒雅樂頭親正入道讃岐の国高松の城にありて卒す。壽七十八。この親正が先は參議房前に出で、数世の後左京進家廣が時より、大和国生駒の村に住ければ、終に生駒をもて家号とす。家廣が孫出羽守親重始甚助といふ。これ親正が父なり。親正父の時より美濃国土田村に住て織田家にしたがひ、後に豐臣家に属ししばしば軍功ありしかば、天正十四年、伊勢國神戶の城主とせられ三萬石を領し、又播磨国赤穗にうつされ六万石を領し、十五年八月十日、讃岐国に転封せられその国鶴羽浦に住し、また丸亀の城にうつり、このとし堀尾帶刀吉晴、中村式部少輔一氏と共に豐臣家三中老の一人に定めらる。これより先從五位下して雅樂頭と称す。小田原の軍にもしたがひ、朝鮮の役には先手に備へて軍功をはげみたり。文祿四年七月、十五日五千石の地をくはへらる。太閤薨ぜられて後大坂の奉行等。
我君をうしなひまいらせんと謀りし時も、親正、吉晴、一氏の三人心を一にしてその中を和らげ御つゝがもわたらせられず。五年、上杉景勝を征し給はんとて奥に下らせ給ふ時、親正は病にふしければ、その子讃岐守一正に軍兵そへて御供せしむ。かゝる所に上方の逆徒蜂起せしかば、又上方へ打てのぼらせ給ふ時、一正は御駕に先立て福島加藤等とおなじく海道を発向し、美濃国岐阜鄕戶等の軍に武功をはげまし、関ガ原の戦にも力をつくしける。父親正は国にありて石田三成が催促に従い、家卒を出して丹後国田邊の城攻めに與力せしかば、関ヶ原御凱旋の後一正は父が本領讃岐国にて十七萬千八百石余を給ひ、丸亀を改めて高松の城にうつりすむ。親正はなまじゐに田邊の城攻めに人數を出しければ、その罪を恐れ高野山に迯のぼり薙髮して謝し奉りける。されど一正旣に軍忠を著はし勸賞蒙る上は、御咎のさたに及ばれず。御免しを蒙りしかば、この後は高松の城に閑居して、一正にはごくまれけふ終りを取しとぞ(家譜。藩翰譜備考。寬政重修譜)。
○十四日、公卿殿上人伏見城に上り將軍宣下を賀し奉る(西洞院記)。
○十五日、島津少將忠恒が使の家司拜謁して帰国の暇たまはる(天元實記)。
○十九日、朝雨ふり未牌雨やみ。酉刻日蝕するがごとくにして色甚赤し。今夜又月蝕なり。衆人一晝夜に日月蝕す尤珍事とて喧噪す(當代記)。
○二十五日、南都東大寺三庫修理成功するにより、本多上野介正純幷に大久保十兵衛長安監臨す。修理の奉行は筒井伊賀守定次幷に中坊飛驒守秀祐これをつとむ。大內よりは勅使として勸修寺右大辨光豐卿、廣橋右中辨總光參向あり。この三庫は聖武天皇の遺物とて、蘭奢待をはじめ紅沈香。麝香。人參。綾羅綿繡。瑠璃。壺印子針。衣服。琴。瑟。笙竿、その外屏風、樂衣等五十の唐櫃●納め、千歲近く收藏して朽敗せず。天朝にも勅封ありて尤秘藏し給ふ所なり。足利將軍家代々一度、蘭奢待を一寸八分づゝ切て寳愛せらるゝ故事となりて、織田右府も切取て秘賞せられしかば、当家にも武家先蹤を追てこれを切たまふべきかと聞えあげしに、聖武天皇よりこのかた本朝の名品とて秘愛せらるゝを切取べきにあらず。たゞし久しく勅封を開かず。庫內朽損漏濕して古物の破壤せむ事思ふべきなりとて、去年六月、正純長安等を監せしめ、定次秀祐等奉行し、勅使參向して勅封をひらき、実物を他所にうつし庫內を修理せしめられ、九月に至る。唐櫃三十は新調して宝物を收貯せしめられしが、このほど告竣に及びしかば、勅使ふたゝび参向ありて宝物を庫內に收め勅封ありしなり(和州寺社記。筒井家記)。
○二十七日、三河国鳳來寺護摩堂火あり。又二王堂俄に崩壤す。天狗の所爲なりと流言す。又山中衆徒死亡する者多し(当代記)。是月、井伊万千代直勝正五位下に叙し右近大夫に改む。上杉中納言景勝卿江戶に参覲す。櫻田に於て宅地をたまふ。又諸国の大名より各丁夫をめして、江戶の市街を修治し運漕の水路を疏鑿せしめらる。越前宰相秀康卿を上首としてこれに属する者三人、松平下野守、忠吉朝臣を上首としてこれに屬するもの四人、加賀中納言利長卿を上首としてこれに属するもの四人、上杉中納言景勝卿を上首としてこれに屬する者三人、本多中務大輔忠勝を上首としてこれに屬する者四人、蒲生藤三郞秀行に屬するもの一人、伊達越前守政宗に屬する者一人、生駒讃岐守一正に屬する者十八人、細川越中守忠興に屬する者十人、黑田甲斐守長政に屬する者三人、加藤主計頭淸正に屬する者三人。(以上所屬の徒詳ならず)淺野紀伊守幸長に屬するものは、池田少將輝政、堀尾信濃守忠晴、峰須賀長門守至鎭、山內對馬守一豐、加藤左馬助嘉明、中村一學忠一、池田備中守長吉、山崎左馬允家盛、有馬玄蕃頭豐氏、中川修理大夫秀成、前田主膳正茂勝なり。(淺野家の書上による)
この役夫すべて千石に一人づゝ課せられければ、世に名けて千石夫とよべり。又この時より市街の名みな役夫の国名を課せて名付しとぞ。又このほど井伊右近大夫直勝が家司木俣土佐守勝拜謁して、舊主直政磯山に城築かんと請置しかど、磯山はしかるべしとも思はれず。澤山城より西南彥根村の金龜山は、湖水を帶てその要害磯山に勝るべしと聞え上しに御けしきにかなひ、さらばその金龜山に城築くべしと命ぜられし上、今の直勝は多病なれば、汝主にかはりてその城を守るべしと命ぜらる。時に守勝又申けるは、直勝多病なりといへども、その弟辨之助直孝とて今年十四歲なるが、父直政が器量によく似て雄畧すぐれて見え候。この者今少し成長して兄直勝が陣代つかふまつらんに、何のおそれか候はんと申ければ、その直孝召つれ來れと仰せあり。守勝かしこみ悅ぶ事斜ならず。速にともなひ見参せしめしに、その面ざし父に似たり。いかさまものゝ用に立べきものぞ。直に江戶へまかりて中納言殿によく仕へよとの仰せを蒙る。又牧野傳藏成里入道一樂ははじめ豐臣關白秀次につかへ、關白事ありて後石田三成に属し、關原の戰に石田が味方にて備しが、石田方大敗に及び家兵十余人ばかり引ぐし、大敵の中を切拔て池田輝政が備に來りしかば、輝政これを播州にともなひ歸り撫育なしをき、この程輝政御夜話に侍しける時この事聞え上しに、その傳藏は剛士なり。我に謁見するにも及ばず。今度井伊辨之助を江戶に奉仕せしめむため、酒井雅樂頭忠世にともなひ江戶へ參るべしと命じたれば、傳藏も同じく江戶へまからせ仕ふまつらしめよと仰せらる。輝政よろこびに堪ず。御けしきうるはしきを幸に、又先に御勘氣蒙りたる近藤平右衛門秀用恩免の事聞え上しに、これもゆへなく御ゆるしあり。一樂はこの後還俗して傳藏と改む。又松浦式部卿法印鎭信は孫壹岐隆信とて時に十一歲なるをともなひ、都にまかり初見の禮をとらしむ。鎭信が子肥前守久信は父に先立てうせければ、鎭信が所領はこの嫡孫にゆづるべしと面命ありて駿馬を給ふ。
又大納言殿射藝の師範たる佐橋甚兵衛吉久弓頭に命ぜらる。又先に遠江国久野の所領をうつされし松下石見守重綱、暇給はりて常陸新封の地に赴く。久野の城は舊主久野三郞左衛門安宗入道宗庵に給はり、下總の所領千石を合せ、旧領共に八千五百石になされ入城す。森右近大夫忠政この六日、信濃国より美作国に轉封せられたるをもて、信濃国川中島、松城、飯山、長沼、牧の島、稻荷山、五か所の城寨を保科肥後守正光に勤番せしむ。又第十の御子長福丸のかた今年二歲にならせ給ふ。訪諏部平助正勝はじめて其方の小姓とせられ采邑二百五十石たまふ。(家譜。北越軍記。創業記。木俣日記。石谷覺書。寬永系図。寬政重修譜。家忠日記)
○三月三日、伏見城にて上巳の御祝あり。烏丸大納言光宣卿。日野大納言輝資卿。廣橋大納言兼勝卿。飛鳥井頭侍從雅宣。勸修寺宰相光豐卿等參賀あり。この日、水野孫助信光死してその子孫助つぐ(勸修寺記。寬永系圖)。
○五日、尾崎中務某死してその子勘兵衛成吉つぐ。鎌倉鶴岡社人社僧伏見へ參謁しければ、歸路諸驛の御朱印を下さる(寬永系圖。八幡古文書)。
○六日、神龍院梵舜伏見城にのぼり拜謁す(舜舊記)。
○十日、中根喜藏正次小姓組に入番す(寬政重修譜)。
○十一日、永井右近大夫直勝を勸修寺宰相光豐卿のもとに御使して、御直廬の事を議せらる。よて叡聞に達する所、直廬は內廷に設るをもて規摸とする事なれば、長橋の局をもて御直廬に定らるべしとの內旨を、光豐卿のもとへ廣橋大納言兼勝卿もおなじく参りて兩卿よりつたふ。(勸修寺記、貞享書上)
○廿一日、伏見城より御入洛ありて、二條の新御所に入らせ給ふ(去年聚樂の御舘を二條に引遷さる。これを二條の新御所又は新屋敷と稱す。いまの二條城なり)。傳奏その外月卿雲客これを迎へまいらすとて、大佛堂西門邊まで出て拜謁す。廣橋大納言兼勝卿。勸修寺宰相光豐卿に御懇詞を加へらる。この日森右近大夫忠政就封す。忠政は封地美作國鶴山に城築事こふまゝにゆるされしかば。やがて新築して後に名を津山と改む(舜舊記。勸修寺記。作州記)。
○廿三日、小出遠江守秀家卒す。その弟五郞助三尹を世繼として采邑二千石を襲しむ。この秀家は故播磨守秀政が二男にて、母は豐臣大閤の外叔母なれば、豐臣家にはよきぬなからひなり。はやくかの家につかへ從五位下に叙し遠江守と稱し庇䕃料千石を授らる。慶長五年、上杉御征伐のとき父秀政は老病に臥ければ、秀家に從兵三百人を加へて御供に侍はしめ、下野国小山にいたる時上方の逆徒蜂起すと聞えしかば、先これを誅せらるべしとて大斾をかへされたるに、秀家も御供す。關原凱旋の後秀家最初より御味方にまいりし功を賞せられ、千石を加へられ二千石になさる。兄大和守吉政は石田三成が催促に応じ、丹後国田邊の寄手に加はりしかども、秀家が軍忠によりて父兄皆な御ゆるしを蒙り、秀家けふ三十七歲にて卒しぬ(秀家が世つぎ三尹が時、姪大和守吉英が所領を分て一万石になさる。秀家は二千石にて終りしなり。すべて万石以下の輩には傳をたてずといへども、秀家は大坂方の身にて最初より二心なく御味方にまいりたる者ゆへ、こゝにその來歷を詳にせざることを得ず)。この日、神龍院梵舜二條御所に出で御氣色を伺ふ(寬政重修譜。舜舊記)。
○廿四日、黑田甲斐守長政江戶より上洛し。二條の御所へまうのぼり拜謁す。
○廿五日、將軍宣下御拜賀として御参內あり。その行列。一番は雜色十二人。切子棒鐵棒を持て御成を唱ふ。この十二人のうち八人は素襖烏帽子。四人は肩衣袴なり。二番御物。(是は御進献の品なり。)下部是をもつ。公人朝夕十人左右にわかれ警を唱ふ。次に御物奉行。同朋谷全阿彌正次。騎馬侍十人。小結二人。大ころし一人。長刀持一人。龓二人。笠持一人。草履取一人。三番御出奉行板倉伊賀守勝重。騎馬侍二十人。烏帽子素襖。中間二人鞭鞢をもつ。龓二人。笠持一人。長刀持一人。草履取一人。敷革持一人。四番隨身。左山上彌四郞政次。島田淸左衛門直時。高木九助正綱。近藤平右衛門秀用。右は本多藤四郞正盛。渡邊半藏重綱。鵜殿善六郞重長。橫田彌五左衛門某。各金襴の袍。壺垂袴。帶劔。弓箭をもつ。龓二人づゝ。侍はみな馬前に列す。五番白張七人。六番諸大夫。風折直垂。太刀小刀を帶す。(これは帶刀のつとめにあたる)左佐々木民部少輔高和。近藤信濃守政成。松平若狹守近次。戶田采女正氏鐵。石川主殿頭忠總。西尾丹後守忠永。永井右近大夫直勝。三浦監物重成。右は竹中采女正重義。森筑後守可澄。三好備中守長直。三好越後守可正。內藤右京進正成。秋元但馬守泰朝。松平右衛門佐正綱。松平出雲守某。七番御車。(糸毛なり。)牛二疋。牛飼二人。舍人八人。白丁二人。榻持一人。御階持一人。次に本多縫殿助康俊。風折烏帽子。直垂。太刀小刀をさし。馬上に御劔をもつ。烏帽子着廿人。長刀持一人。笠持一人。龓二人。ひきしき持一人。つぎに布衣侍。左は成瀨小吉正成。安藤彥兵衛直次。榊原甚五兵衛某。阿部左馬助忠吉。豐島主膳信滿。林藤四郞吉忠。高木善三郞守次。朝比奈彌太郞泰重。石川半三郞某。都筑彌左衛門爲政。右は米津淸右衞門正勝。中山左助信吉。柴田左近某。橫田甚右衛門尹松。日下部五郞八宗好。長谷川久五郞某。花井庄右衛門吉高。伊奈熊藏忠政。加藤喜左衛門正次。鳥居九郞左衛門某。八番騎馬。諸大夫二行に列す。左は井伊右近大夫直勝。松平飛驒守忠政。松平玄蕃頭家淸。本多豐後守康重。本多中務大輔忠勝。右は里見讃岐守義高。松平甲斐守忠良。松平出羽守忠政。本多上野介正純。石川長門守康通。各風折烏帽子。直垂。太刀小刀を帶し。烏帽子着廿人。長刀持一人。笠持一人。龓二人。引敷持一人。九番米澤中納言景勝卿。毛利宰相秀元卿。越前宰相秀康卿。豐前宰相忠興。若狹宰相高次。播磨少將輝政。安藝少將正則。此輩各塗輿にのり。舁夫八人。布衣侍四人。烏帽子着三十人。笠持一人。白丁七人。長刀持一人從ふ。遠山勘右衛門利景。山口勘兵衛直友は路次行列の事を汰沙す。
禁廷唐門に公卿出迎られ、眤近衆は直に從ひて長橋にいらせらる。御降車の時勸修寺右大辨宰相光豐卿御簾をかゝげ、四條左少將隆昌御沓を奉り、大澤少將基宥御劔をとり、長橋の局もて御直盧代とせらるれば、こゝにて御衣冠にめしあらため給ひ御拜賀あり。主上も殊に龍顏うるはしく、本朝百有餘年の兵革を撥正し、四海太平の基を開く事、ひとへに將軍の武德によると詔あり。天盃たまはらせ給ひ、舞踏拜謝してまかむで給ふ。けふ進らせ給ふ品々は、主上へ銀千枚、幷に小袖 親王へ百枚、女院へ二百枚、幷に小袖。女御へ百枚、幷に新大典侍の局へ三十枚、權典侍に三十枚、長橋局に五十枚、すけの局大乳人へ三十枚づゝ、新內侍の局へ廿枚、伊よの局へ十枚、おこやおまみの局へ五枚づゝ、末の女房五人十五枚、女孺四人へ十二枚。非司二人へ二枚。御物師二人へ六枚。帥の局。お乳の人。やゝのおかたへ五枚づゝ。右衛門督の局へ三枚。おみつ御料人へ卅枚なり。この時池田三左衛門輝政。福島左衛門大夫正則は少將にのぼり。加藤主計頭淸正。黑田甲斐守長政。田中筑後守吉政。堀尾信濃守忠氏。蜂須賀阿波守至鎭。山內對馬守一豐。井伊右近大夫直勝ともに從四位下に叙し。淸正は肥後守。長政は筑前守。一豐は土佐守。忠氏は出雲守と改む。從五位下に叙する者十七人。板倉四郞右衛門勝重は伊賀守。松平次郞右衛門重勝は越前守。松平五左衛門近次は若狹守。三好久三郞可正は越後守。三好助三郞長直は備中守。佐々木藤九郞高和は民部少輔。松平長四郞正綱は右衛門佐。松平文三郞重成は志摩守。近藤七郞太郞政成は信濃守。加藤孫次郞明成は式部少輔。石川宗十郞忠總は主殿頭。西尾主水忠永は丹後守。松平源三郞勝政は豐前守。內藤四郞左衛門正成は右京進。松前甚五郞盛廣は若狹守。相良四郞次郞長每は左兵衛佐。遠山勘右衛門利景は民部少輔。山口勘兵衛直友は駿河守と稱す。森左兵衛可澄。赤井五郞作忠泰從五位下に叙し。可澄は筑後守と改め。千石加恩たまひて千五百石になさる。忠泰は豐後守にあらたむ。(將軍宣下記。行列記。家忠日記。紀年錄。續通鑑。寬永系圖。西洞院記。舜舊記。武德大成記。成功記。進上記。貞享書上。大三河志。武家補任。家譜。藩翰譜備考。寬政重修譜)。
○廿六日、こたび叙任せし四位五位の武家拜賀のため参內す(將軍宣下記)。
○廿七日、八條式部卿智仁親王、伏見中務卿邦房親王、九條關白兼孝公、一條前關白左大臣內基公、二條前左大臣昭實公、近衞左大臣信尹公、鷹司左大將信房卿はじめ、公卿殿上人二條の御所に參向ありて今度の宣下を賀せらる。攝家親王は上段、それ以下は下段にて御対面あり。この日江戶にて內藤修理亮淸成、靑山常陸介忠成公私領の農民へ令せしは、御料私領の農民等、その地の代官幷に領主を怨望してその地を迯去る時は、代官領主よりその事を注進するとも、みだりに還住せしむべからず。迯散の年貢未進あらば、奉行所に於て隣鄕の賦稅をもて各算勘し、その事終るまで何地にも居住せしむべし。領主の事をうたへんと思ふ者は、あらかじめその地を退去すべく思ひ定めて後うたへ出べし。さもなくてみだりに領主の事を目安を以てうたへ出る事停禁たるべし。免相の事近鄕の賦稅に准じてはからふべし。年貢高下の事、農民直に目安をさゝげば曲事たるべし。すべて目安を直に捧る事嚴禁なり。しかりといへども人質をとられ、やむ事を得ざる時はこの限りにあらず。代官幷に奉行所に再三目安をさゝぐると雖ども、承引ざるにをいては其時直にさゝぐべし。もしその事を代官奉行所にうたへずしてさゝぐる者は成敗せらるべし。代官に非義あるに於ては、その旨を告うたふるに及はず直に目安をさゝぐべし。みだりに農民を誅する事嚴禁なり。たとひ罪科ありともからめ取て奉行所に出し、上裁をへて定め行ふべしとなり(將軍宣下記。制法留)。
○廿八日、禁中方々の女房より、將軍宣下を賀して二條御所へまいらせものあり(西洞院記)。
○二十九日、諸門跡二條御所へ參賀せらる。江戶に於て大納言殿、佐野修理大夫信吉が家人蛻庵に時服三かづけらる。これは蛻庵能書の聞えあるをもて。硯箱印籠に描繪せしめらるゝ詩を書せ給ひしゆへとぞ(西洞院記。慶長年錄。慶長見聞書)。
◎是月、細川幽齋法印玄旨は足利家代々につかへければ、その身文武の才藝すぐれたるのみならず、武家の故実典礼にくはしく、当時有職のほまれ高かりしかば、永井右近大夫直勝もて、幽齋につきて武家法令典故を尋問はしめられ、今より後禮法議注を定制せらる。幽齋足利家の礼式を考て、今の世の時宜にしたがひ、家伝礼式三卷をえらびて献ず。又曾我又左衛門尙祐といへるが、これも足利家代々につかへ右筆の事をつかさどり、筆札の故実に精熟せしかば、これより先めして御內書以下の書法を定めらる(家譜。藩翰譜。明良洪範)。
◎是春、關西の諸大名は次第を追て江戶へ参り、大納言殿に拜謁す。伊達越前守政宗が子虎菊伏見より江戶に参り、大納言殿に拜謁し、守家の御刀、眞長の御脇差をたまふ。時に五歲なり。この頃江戶彌大都会となりて、諸国の人輻湊し繁昌大かたならず、四方の游民等身のすぎはひをもとめて雲霞の如くあつまる。京より国といふ女くだり、歌舞妓といふ戱塲を開く。貴賤めづらしく思ひ、見る者堵のごとし。諸大名家々これをめしよせその歌舞をもてはやす事風習となりけるに、大納言殿もその事聞し召たれど一度もめされず。衆人その嚴格に感ぜしとぞ(創業記。寬永系圖。當代記。慶長見聞書)。
○四月朔日、日蝕することあり(節蝕記)。
○二日、醫官片山與安宗哲法眼に叙せらる(寬永系圖)。
○三日、神龍院梵舜二條御所へまうのぼり拜謁す(舜舊記)。
○五日、二條御所にて猿樂催さる(舜舊記)。
○七日、猿樂催さるゝ事五日におなじ。この時進藤權右衛門とて山科の農民、森田庄兵衛とて京の商人なり。この両人そのわざ堪能なればとて觀世召具してまかり、權右衛門は脇をつとめ、庄兵衛には笛を吹せたるに、とりどり妙手なりければ、殊に御けしきにかなひてともに觀世座に列せしめらる。庄兵衛は時に十六歲にて、こと更笛音雲井をひゞかしければ、是より子笛とて常に召れしとぞ(舜舊記。傳記)。
○十日、智積院に御朱印をたまふ。その文にいふ。學業のため住山の所化廿年にみたずして法幢を立べからず。坊舍幷に寺領私にうりかふべからず。所化等能化の命令を用ひずひがふるまひせは、寺中を追放つべしとなり(武家嚴制錄)。
○十三日、石野新藏廣光死して、その子新藏廣次づく。廣光は長篠の戦に高名し、今は菅沼小大膳定利が家士を引具し、この年頃忍城を勤番せり(寬政重修譜)。
○十四日、神龍院梵舜二條城にのぼり拜謁し、三光双覽抄の事御尋問あり(舜舊記)。
○十六日、二條より伏見城へかへらせ給ふ(御年譜。西洞院記)。
○十七日伏見城にて將軍宣下御祝の猿樂催さる。けふ雨宮平兵衛昌茂死して、その子權左衛門政勝家をつぐ(當代記。慶長年錄。寬政重修譜)。
○十九日、諸國の大名伏見城へまうのぼり。太刀馬代幷に酒樽をさゝげ將軍宣下を賀し奉る(当代記。慶長年錄)。
○廿二日、豐臣大納言秀賴卿正二位內大臣に昇進せらる。よて廣橋大納言兼勝卿、勸修寺宰相光豐卿大坂へ參向あり。秀賴卿には此時十一歲なり。江戶よりは靑山常陸介忠成を大坂につかはされ任槐を賀せらる(西洞院記。家譜。當代記)。
○廿八日、御妹●田姬君逝し給ふ。こは大樹寺殿の御女にて、御母は平原勘之丞正次が女なり。長澤の松平上野介康忠に嫁し給ひ、源七郞康直、源助直隆、隼人直宗、この外にも女子二所まうけ給ひ、けふ五十七歲にてうせ給ふ。後の御名をば長廣院とをくりて、三河国法藏寺におさめられしとぞ(或は長光又長康に作る)。この日藤澤の淸淨光寺遊行伏見に参り拜謁す。夜中地震して後また天地震動すること甚し(家譜。西洞院記。當代記。慶長見聞書)。
◎是月、池田少將輝政、その二子藤松に備前国たまはりしを謝して江戶に参り物多く奉る。大納言殿御感淺からず。酒井雅樂頭忠世を御使せられ、滯留の料として粮米を下され、こと更營中に召て御みづから御茶を給ひ、辭見に及びて御刀及虛堂墨跡、幷に鳳凰麒麟と名付られたる駿馬二疋下され、帰国の時は大久保加賀守忠常、安藤対馬守重信をして箱根の関までをくらせたまふ。その優待恩榮人の耳目を驚かすばかりなり。輝政は帰路又伏見に參り拜謝して、藤松ことし五歲なり。成長するまでの間は兄新藏利隆に、備前の国務をとらせまほしき旨を請て御ゆるしを蒙る(寬永系圖。寬政重修譜)。
◎この春、江戶に参覲せし關左の諸大名辭見して伏見に参る。又長崎の地は天主教の淵藪なればとて、天正十六年、豊臣家の頃は、鍋島飛驒守某といへる者に所管せしめられ、文祿元年より寺澤志摩守廣高に所治せしめらる。しかりといへども邪風彌盛にしてやまず。こたび改て小笠原爲信入道一庵をその地の奉行に仰せ付けられ、法印に叙せらる。これ長崎奉行の權輿とぞ聞えし、よて與力十人付らる。又大村の處士奥山七右衛門、薩摩の處士八山十右衛門をもて町使役とせらる。これ長崎町使役の濫觴なりとぞ(年錄。長崎記)。
|