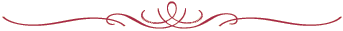
| 【余禄】れんだいこは南京事件の解明になぜ拘るのか |
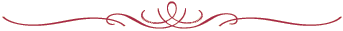
更新日/2020(平成31→5.1日より栄和改元/栄和2).2.25日
| 【【余禄】れんだいこは南京事件の解明になぜ拘るのか】 | ||||||||
| 南京事件に対するれんだいこの観点-冤罪の可能性を問う 2001.8.23日、笠原十九司著「南京事件」を読み終えた。読後感は良書であるということに尽きる。我がサイトに取り入れていかなければならない貴重資料を頂いたことを感謝する。南京事件ドキュメントを史実経過順に概説しているところが、妙にひねってなくて好感が持てる。恨むらくは、浮つくことなく公平な資料提供しているにも関わらず、それらを元にして笠原氏のコメントが加えられる下りになると、杜撰とも云える大虐殺論への傾きが見られることである。但し、本書が南京事件のガイドとして良書であることには相違ない。事件内容の重々しさは別にして、今私には一服の清涼感さえある。 本書を読み終えてもなお、南京大虐殺事件は云われるほどひどいものだろうか、本当に為された事件なのであろうか、という思いを禁じえない。その理由について以下記す。れんだいこは、当時の軍部の動きとして全体的に統制が取れていた頃の事件であることを重視する。南京事件は、いわば、日本帝国軍が史上最も精鋭であり得た絶頂期の頃の出来事である。このことは重要なポイントである。何が云いたいかと云うと、軍律の厳しさと無辜の民に対する暴行の少なさで定評を得ていた帝国陸軍の伝統は、この頃までは辛うじて維持されていたのではなかろうかという認識を大事にしたいということである。ここで見解が分かれているが、通史で見ればこの方が正確な見方なのではなかろうか。 いやそうではないのだ、既に出世機会主義亡者が武勲をあせる時代に変質しており云々の様々な理由が挙げられ、如何に野蛮な大虐殺が為されたかの説得が試みられているが、私のこの疑問を解きほぐすほどのものには接していない。よしんば将校レベルでそうであったとしても、末端兵士がそのように動くとは限らない。末端兵士は何をするか分かったものではないと見るのは偏見だろう。 相対的に見てであるが、「相身互いの穏和性」は日本人に染みついた習性であり、この伝統はそうそうは変化するものではなかろう。この点を軽視する被虐観点はあまりにも日本人ないしその歴史を知らなさ過ぎよう。我々の中にある仏教的ないし神道的ヒューマニズムには非常に高度なものがある、というのがれんだいこ観点である。そうやすやすとは虐殺なぞやれる民族ではない、この点の認識がいとも容易く放棄され過ぎている気がしてならない。 確かに大戦末期の頃には軍律弛緩による蛮行史実例に事欠かない。しかしそれはそれこそ敗戦前後のパニックを前提にしての茫然自失、疑心暗鬼から為された特殊例であったのではなかろうか。この場合でも、司令官、上官、部隊長辺りの資質能力に大きく左右されているというのが史実ではなかろうか。南京事件は、ノモンハン事件(1939.5.11日勃発)の2年前、太平洋戦争開戦(1941.12.8)の4年前の事件である。この当時にまで遡って日本軍がアナーキー且つ極悪非道な蛮行を本当に為したのかどうか、大いに精査を要するというのがれんだいこの観点になっている。 つまり、様々な事由によって否定されようとも、日本人の心に宿る習性として虐殺、暴行、略奪、凌辱は馴染まない国民性であることを重視しつつ、南京事件の経過を捉え返してみたいということである。本当に無原則、アナーキーな状態での大虐殺事件がなされたのであろうかという根源的な見直しをしてみたいということである。 繰り返すが、南京大虐殺事件の本質は、「無原則、アナーキーな状態での大虐殺事件がなされた」との見立ての真偽を問う論争である。戦争行為過程での虐殺数を累計している問題ではない。この区別が分からないままに虐殺論を述べ続け、そう主張するのが左派の証とでも勘違いしている手合いが多過ぎる。 むしろ、南京事件は、戦勝気分で沸き立つ日本国民の与り知らぬところで、発生当初より欧米諸国にセンセーショナルに打電され、反日感情を植え付けていくために徹底利用されていた節がある。中国人の抗日運動にも徹底活用され、その残虐性がプロパガンダされていった。それは、国際的レベルでの来るべき日本壊滅作戦がこの時用意周到に発動されており、そういう環の中で日本軍の蛮行がフレームアップさせられていった可能性を示唆している。 参謀本部第一部長・石原莞爾は「来るべき日本壊滅作戦」が待ち受けていることをキャッチしており、であるが故に「満州国経営」にじっくりと腰を据えるべきだとの論陣を張っていたのではなかったか。これは、石原を弁護しようというのではない。史実を明らかにしようとしているに過ぎない。その後の史実はこの石原の危惧を退け、一撃打倒論で戦線拡大していった。思惑が外れて泥沼の日中戦争に引きずり込まれ、やがて敗戦を迎え結果的に石原が予見した通りになったのではないのか。南京大虐殺事件は、こうした国際級機密レベルでの合意の中でフレームアップされた可能性があるのではないのか、という観点から事件を再精査してみたいという気持ちを押さえきれない。 史実検証の結果、云われる通リに大虐殺事件が為されたと云うことが実証されればそれはそれで良い。良いというのは変な言い方だが史実は史実として重んじられなければならないという意味である。れんだいこは何も「かっての戦争」の免責をしようというのではない。いずれにせよ、その最初に立ち戻って、アジアでの覇権を求めて植民地主義的に大陸に軍靴を乗り入れていった歴史的な責任を免れるものではなかろうから。その行為は良くても傲慢尊大であり、実際には文明史的に見て数千年来積み上げられてきた日中、日朝友好の歴史の岐路を右旋回で安直に渉っていった無能の証左であっただろうから。こうした観点から、南京事件をも俎上に乗せたいというのがれんだいこ史観である。 但し、れんだいこは、今まで知らされてきた資料にはどうも納得できないところがあり、気になっている。決め手のところで曖昧模糊とされている不自然さを覚えている。個別にはそれが真実だとしても、比較してみると互いが齟齬をきたしている資料が多すぎる。意図的な写真合成、無関係写真の紹介、「百人斬り事件」捏造等々訝られる資料等々が目に付きすぎる。これらは果たして何を語るのであろうか。結論は一つである。全て再精査され直さなければならないということである。 |
||||||||
もう一つ。れんだいこならではの、なぜ拘るのかという別の理由を以下記す。南京事件には、他でもない「宮顕の党中央内リンチ事件」の構図と似ている面があり過ぎるという臭いがすることによってである。つまり、こういうことになる。 南京事件と「宮顕の党中央内リンチ事件」の両者には、左派内にいわば公式化された次のような認識がある。
これが両者に共通する態度である。この場合、問題は次のことにある。小畑はスパイでも何でもなく有能な労働者党員であり、宮顕の素性の方こそ胡散臭いとしたらどうなるのだ。れんだいこの研究によれば、このことは既にはっきりしている。にも関わらず、世上の受け止め方は、小畑はスパイであり、当然の査問過程で特異体質で急死したと云う宮顕党中央のプロパガンダをまともに信じさせられている。この認識を逆転させねばならないというのがれんだいこ観点である。いわゆる冤罪に対する見直し運動と云えるかも知れない。 世に冤罪がそうはある訳ではなかろう。だが、何やら南京事件にも共通の臭いを嗅ぐから、よほど周到に南京事件の精査に向かわねばならないというスタンスにれんだいこは立っている。そういう訳で、南京事件の残虐性を大きく指弾すればするほど左派的構図であるという現在の公式に安易に乗れないことになる。それは確かに戦争過程での事件であるからして虐殺がなかったと云おうとしている訳ではないことはもちろんである。史上最大級の蛮行としてプロパガンダされている南京事件をそのままには受け止められない、れんだいこの納得いく精査を通して初めて見解を明らかにせねばならない妙な事件の臭いがするということが云いたいわけだ。 ひょっとしてれんだいこが感じている通りであるかも知れないとさえ思っている。「まぼろし論」は火のないところに煙は立たないということではなかろうか。これは、「まぼろし論」者の云う戦前秩序礼賛論に与することでは決してない。ここが、れんだいこと「まぼろし論者」とを隔絶するイデオロギーの差といえる。れんだいこは冤罪事件として見ようとしている。その為に、史実が史実として精密に検証されねばならないということだ。 世の中では支配権力からばかり冤罪が為されるのではない。左翼も既に体制内「裏」権力足りえており、左派の側からする冤罪事例にも事欠かないのではなかろうか。共産党中央の場合、反対派に対する冤罪事例は掃いて捨てるほどある。今や、こういう認識の観点抜きに左派が左派であり得ない複雑なご時世にあるのではなかろうかと思っている。ついでに付言しておけば、最近れんだいこが気になっていることは、左派の冤罪に対するアンテナが鈍っているのではないかという思いである。 仮にそうとならば反省せねばならないことがある。世に左派的な当然の観点として流布されているものの中にはいかがわしいものが混じっているということだ。その峻別なく、一見左派的な論調になんでもかんでも飛びついて、これを過激に主張すればするほど左派人士の証になるという単純な構図ではないのではなかろうか。偶然か意図的かそういう撹乱因子も混在していることを踏まえて、騙されずあやされず真紅の旗印を掲げていきたいというのがれんだいこ観点である。いかがなものであろうか。 2001.8.23日、2005.5.12日再編集 れんだいこ拝 |
| 【れんだいこの南京事件の見立てを批判し、左派ぶる者どもへ】 | |
れんだいこの上記の所論に対して、次のような批判が為されている。検索で見つけた「【中核派をお払い箱】うちはだいこ【日蓮正宗】 」に登場している。
他にも捜せばキリがないほどこの種の批判が出回っているようだ。以下、れんだいこが返歌しておく。「これを読んでもなお、れんだいこの所論に合点できない左翼がいるのなら、それはインチキ人間と言わねばならない」。 左翼というのは、定義はいろいろあるにせよ、少なくとも議論のとやかくある問題に対しては自身で精査し、持論を持たねばならない。人の尻馬に乗って片棒担ぐのはむしろ権力派の者に共通する作法である。行動であれ言動であれ仮に目的が正しくても、自身が得心した情動と理論を持たねばならない。「党中央の云う通り」、「今までそう認識されてきた」なる如意棒を振り回すのが左派精神であるかというと、それは逆だ。 「革命的名無しさん」なる芸名で書き込めば、革命的である言説をぶてる訳ではない。れんだいこは上記で立論している。その論がおかしいとならば、それを反論すれば良い。それを為さず「インチキ人間と言わねばならない」と記して得心する者はよほど粗雑な頭脳の持ち主と云わねばならない。こういう手合いに権力持たせてはならない、そう見立てるのが左派なのだ。 例えて云えば、陸上トラック競技で二、三周遅れの者が素通りしようとする先行者の袖を引っ張ったとしても、それは顰蹙を買うだけであろう。そういう顰蹙士になってあちこち引っかいて廻る者は、「革命的」と自称しようがしまいが左派戦線の者ではない。なぜなら、本来の左派は堂々と耳を傾け議論しあうべきものだから。なんとならば、明日の未来を担う者にはそういう資質が居るのだ。少なくとも全共闘できるものでなくてはならない。 ということは、この引っかき屋の素性が知れるということだ。なんかの思惑で必要もあってそういうお仕事に精出しているのだろう。それが分からないれんだいこではない。以上はなはだ簡単ながらコメントしておく。 2005.5.12日 れんだいこ拝 |
| 「上杉 信彦」「中村信一」。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)