| 「ラーべ日記」、「南京地区における戦争被害スマイス報告」について |
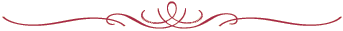
「ラーべ日記」につき、次のように評されている。
「ラーベ日記」の資料的価値は次のことにある。
|
「ラーベ日記」の伝える日本軍の蛮行、埋葬に関する記述資料についての記述は次の通りである。
|
許可が下りなかった埋葬「日本軍による支那地方民および武装解除された軍人の南京における虐殺並びに南京紅卍字会による死体埋葬の実況(検証1728)」 1937年(昭和12年)12月、支那国民政府が南京より移転せる際、国際委員会が中外の紳商並びに宣教師によって組織された。日本当局は中山北路以西に漢中路以北の地を避難民区域となす申し出に同意し、 紅卍字会は其地における救済事業を管理することを許された。 12月13日、日本軍の中島部隊が光華門より南京に入り、支那軍が下関の川岸に退却した際、 地方民衆及び武装解除された将兵は難民区域に入り、もしくはあちらこちらに隠れ場所を求め、その数は20余万であった。紅卍字会はアメリカの宣教師及び教授の援助により、毎日食事を給し、秩序を維持するため給食所を設置した。 (1殺戮 2強姦については省略) 3埋葬 殺戮後、死体は南京及び其の近郊に山積していた。 紅卍字会は彼らを埋葬するため埋葬隊を組織することを申し出た。日本側は約一ヶ月後までそれを許さなかった。そのため実際に仕事をはじめた時には死体は腐乱し変形していて識別が不可能であった。他の多くの死体が大塘及び河溝において河中より引き上げられた。しばしば、日本軍は10もしくはそれ以上の死体に長い針を通し、つなぎ合わせて、河中に投じた。 紅卍字会によって葬られた死体の総数は43.081であった。 死体埋葬作業、月日、死体の種別、死体発見場所、埋葬地の表を送付する。 世界紅卍字会南京分教会 印 会長(署名捺印) 呉仲炎 副会長(署名捺印) 許伝音 1946年(昭和21年)4月6日 日中戦史資料集8(東京裁判資料編)P385 解 説この文章は、時間系列が捻じ曲がっているので、分解して解読しよう。 『日本当局は中山北路以西に漢中路以北の地を避難民区域となす申し出に同意し』 ①安全区の設定に日本軍は同意した。これは12月1日のことだろう。「日本政府は安全区設置の申請を受けましたが、遺憾ながら同意できません。中国の軍隊が国民、あるいはさらにその財産について過ちを犯そうと、当局としてはいささかの責も追う意思はありません。唯、軍事上必要な措置に反しない限りにおいては、当該地区を尊重するよう努力する所存です」 「南京の真実(ラーべ日記) 文庫P88」 以上のような電報が安全区委員長ラーべに届いたのが12月1日である。 『紅卍字会は其地における救済事業を管理することを許された』 ②この部分は12月13日以降、南京陥落後の記述であると思われる。陥落前に救済事業を行う団体を日本軍が選定することはありえないし、またそのような選定をしたという記録もない。この救済団体選定が南京陥落前の行為だとすれば、安全区委員会と日本軍がやり取りした電文が残るはずだが、そのような記録は今のところ見つかっていない。 すると、南京陥落後「救済事業を管理」する団体として日本軍が選定したのは紅卍字会だった。と、いうことになる。救済事業の中には当然埋葬も含まれるが、当時、南京特務機関員だった丸山氏の証言によると埋葬活動は一括して紅卍字会に委託したということである。これは上記中国側史料と合致する。 『地方民衆及び武装解除された将兵は難民区域に入り、もしくはあちらこちらに隠れ場所を求め、その数は20余万であった。』 ③この文書によれば「南京陥落時12月13日の人口は、脱走兵を含めて20余万」だったらしい。もちろんこの文書は「検察側(中国側)証拠」 である。 『紅卍字会は彼らを埋葬するため埋葬隊を組織することを申し出た。日本側は約一ヶ月後までそれを許さなかった。』 ④この文章で問題なのは「約一ヶ月後までそれを許さなかった。」という部分である。「南京陥落から一ヶ月」と読むか、「紅卍字会が埋葬を申し出た日から一ヶ月」と見るかで内容が変わってくるが、埋葬許可が下りた時期については「一月中旬頃」と考えてよいだろう。 |
|
|
この「ラーベ日記」に対して、否定派は次のように云う。 アイリス・チャンは歴史を隠すだけでなく、新しく歴史を偽造し、嘘を付け加えています。アイリスチャンはジャーナリストで、歴史家ではありません。私も、彼女が書いた色々な時代の人物についての記述に間違いを見つけています。彼女は多くの日本の将軍を混同しています。私が彼女に賛成できない理由は、David Bergaminiの「日本帝国の陰謀」以外、南京に関する歴史書がないと言っていることです。しかもその本は余りにも感情的だと、長い間非難され、全世界の歴史家から受け入れられなかったものです。南京事件については日本、中国、アメリカ、イギリス、フランス等全世界で、多くの歴史文献があります。中には研究と言うより、感情的で抗議と言った方がよいものもあります。PRを目的としたものもあります。私は中国人ですが、このようなやり方は好みません。しかしあの本は100万人もの人を引きつけました。 南京事件に関するメモをヒトラーに渡したのは、ジョン・ラーベです。彼の日記は3年前、ドイツ・イギリス・中国・日本で出版されました。彼は南京安全地帯の国際委員会の委員長でした。当時ナチドイツと国民党中国は極めて親密な関係にあり、軍事顧問団を派遣し、高度の武器を売り込んでいました。ラーベは武器メーカー・ジーメンスの現地責任者でした。 ラーベはユダヤや少数民族に対するナチの政策を非難し、全体主義を批判した人物です。ナチドイツはユダヤ人の著作や、共産主義者の著作を大ドイツ民族の心を惑わせるとして、焼却しました。ラーベはこれらの図書を隠し持ちました。彼は生涯をかけた共産主義者だったのです。当時誰かが彼の命を狙っていると脅かされ、ドイツから逃げ出したのです。 ラーベは、中国人に極めて同情的であり、彼の日記は極めて偏向していました。 セントラルパークくらいの広さの安全地帯の中では、彼は1件の殺人も見ていません。それでも人の噂や、中国人からの情報により、日本軍の虐殺を告発しているのです。東中野教授のラーベ日記に関するエッセイを送りますので参考にして下さい。 |
|
「新 しい歴史教科書をつくる会」副会長の藤岡信勝教授は南京事件についてこう記している。「一般市民に対する非行は確かにありました。安全区国際委員会は47人の
市民の虐殺について抗議しています。この中には真偽の疑わしいものも含まれているはずですが、全部正しいとしても47人です。これは軍隊が外国の首都
を戦闘の上占領した場合に起こる一般的なケースに比べて特に多いとはいえな
い」。ラーベは、前回紹介したように、日本軍による市民の殺害は5万ないし6
万人とみていますが、これに対し藤岡氏は市民の虐殺をたった47人とみてお
り、相当な開きがあります。これは虐殺を矮小化する政治的発言でしょうか。 ラーベ氏の孫に当たり、ラーベの日記の所有者であるラインハルトさんは テレビのインタビューでこう述べていたのが印象的でした。 「ラーベはいつもいっていました。許し、そして忘れなさいと。でも人は加害者が罪を認めてはじめて許しあえるんです。南京虐殺がでっちあげだなんて公言する人がいたら、それは再び中国人を侮辱し、恨みを呼びおこすことにな ります」。 ラーベの上申書が「12日夜から13日にかけては、安全区はふたたび砲撃されました」と書いているように、砲弾や爆弾 は安全区にも落下している。 日本軍や大使館に兵士の暴行をやめさせてくれと何度も請願したが、「感謝状」と呼べるものは難民一同がラーベに渡したもの(217ページ)しか見当たらない。 たとえば「昨晩は千人も暴行されたという。金陵女子文理学院だけでも百人以上の少女が被害にあった。いまや耳にするのは強姦に次ぐ強姦。夫や兄弟が助けようとすればその場で射殺」(37年12月17日のラーベ日記)のく だりを引用しつつ、中村氏の「『千人も暴行されたという』は明らかに伝聞である。これが伝聞であるとすれば次の『・・・百人以上の少女が被害にあった』も伝聞に属すると見てよいであろう。百人以上の暴行場面を目撃した筈は ないし、またラーベも目撃体験として書いている訳ではない」とするが、いかにも苦しい。 この論法でいけば、今朝の新聞を賑わしている犯罪記事も、記者が「伝聞で書いているのだから信用できないことになる。警視庁からの「伝聞」であるから信頼できるというのなら、難民区委員長として事実上の南京市長を果たし ていたラーベも同格にみなせないか、という話になろう。 |
|
否定派。 9月30日に外国人特派員クラブの昼食会に、藤岡先生、東中野先生が招かれ「アイリス・チャン」の批判のプレゼンテーションを行いました。英文の詳しい資料も用意し(その大部分は、自由主義史観のホームページの英文、南京版にでていますのでご覧ください。)説明しましたが、勿論まともな反論はでませんでした。ところが、後になって、アイリス・チャンの本は日本で出版されていないのに批判するのは卑怯であるとか、全く見当はずれの批判を、そのときの司会者が特派員クラブの機関誌に書いているのを知り、あまりのひどさに呆れた次第です。The Rape of Nanking は日本の書店の洋書売場にはいくらでもでており、それを英文で批判することに対する批判がこれです。勿論反論をFax で直ちに出しておきましたが、答えられるはずもなく、なしのつぶてです。 それでは、外国人はこの論理になじまない、というか理解できないのかというと、とんでもない話しです。「南京虐殺の徹底検証」は既に全訳が出来上がっており、アメリカの出版社と出版の交渉中ですが、この全訳を読んだあるアメリカ人は、 "I'm a convert." と言うくらい、完全に理解者になってくれました。そしていろいろとわれわれに協力してくれています。要するに、南京問題に関しては、アメリカは「情報鎖国」状態にあり、「あった」という前提の本、資料しか手に入らない状況なのです。そこに風穴を開けようとして、努力をしているところですが、自由の筈のアメリカも、なかなか建前通りではないことを改めて痛感しています。 |
〈連載〉アイリス・チャン『ザ・レイプ・オブ・南京』の研究〈第1回〉日本語訳出版はなぜ挫折したか(月刊誌【正論】5月号掲載 藤岡 信勝)中国系アメリカ人の女性ジャーナリスト、アイリス・チャンの著書『ザ・レイプ・オブ・南京ー第二次世界大戦の忘れられたホロコースト』が米国でベイシック・ブックス社から発売されたのは、1997年12月のことであった。それから一年あまり、現在までにその売り上げ部数は五十万部に達したといわれている。しかし、この本の内容は、唖然とするほどお粗末なものである。同書は南京での日本軍による虐殺数を26万または35万とし、レイプ事件を2万件または8万件としている。それらの数字には何の根拠もない。これはまじめな歴史書にはほど遠く、戦後日本の内外で南京事件に関して捏造されたウソを集大成した反日プロパガンダのための偽書である。 この連載は、『ザ・レイプ・オブ・南京』の日本語訳出版を機に、亜細亜大学教授・東中野修道氏と私が担当して、同書の内容を全面的に批判するために企画されたものであった。ところが、2月25日に予定されていた翻訳書の出版は突然中止となった。出版社サイドは「延期」と表現しているので、今後出版の運びに至るかもしれないが、その時期は未定である。したがって、日本語訳が出るまでは、この連載ではベイシック・ブックス社刊の英語版から訳出して検討の素材とする。 連載の第一回として、今回はこの日本語訳出版がなぜ挫折したのか、その経過をたどり、その意味するものを分析したい。 翻訳書と解説書のペア出版を予告日本語版の版権は東京都文京区に所在する中堅出版社・柏書房(渡辺周一社長)が取得した。共同通信の3月4日付け配信記事によれば、同社が邦訳を決定したのは、昨年の5月だったとされる。昨年の秋には発刊の予告広告が何度か出た。しかし、実際は、その都度発刊は延期されてきた。翻訳作業自体はそれほど手間取るはずがないので、発刊の遅れがそれ以外の原因であることは明らかだった。それは、原著におびただしい誤りがあり、それをどう処理するかという問題であったであろうことも容易に想像がつく。私たちは、翻訳書がそれらの間違いをどう扱うか、実は興味津々と見守っていたのである。 2月8日付け夕刊の産経新聞は、社会面トップで『ザ・レイプ・オブ・南京』の翻訳書出版についての記事を掲載した。その見出しは、〈レイプ・オブ・南京/修正せず日本語版刊行へ/出版元「著者の希望」/事実誤認を黙殺/ニセ写真、そのまま掲載〉というものであった。 その記事のポイントは二つある。一つは、出版元の柏書房が本の内容に「事実誤認があることは知っているが、著者の要望で手を加えなかった」というものである。ただ、東京日日新聞を「ニチ・マイニチ新聞」としているなど、約十カ所の誤記を改めることにだけはチャンは同意した。一方、ニセ写真の方は米国の砲艦「パネー号」として掲載された写真についてだけは、その後米国で出版されたペーパーバック版でも正しいものと差し替えられており、日本語版ではその差し替えた方の写真が掲載されるという。 もう一つは、翻訳書『ザ・レイプ・オブ・南京』の不十分な点を補うものとして、内外の研究者の論文を集めた『南京事件とニッポン人』という本を翻訳書と同時に発売するというものである。この二冊は、2月25日に同時に発売されることになったという。以上が、産経新聞2月8日付け夕刊記事の内容である。 柏書房が出した「2月の新刊」というチラシによれば、二冊目の本には「『ザ・レイプ・オブ・南京』を正しく読むために」というサブタイトルが付けられている。これは翻訳書本体に対する一種の解説書という位置づけである。編者は「大虐殺派」の中心人物の一人である藤原彰氏で、収録される論文には、「『ザ・レイプ・オブ・南京』のもつ意味と問題点」(井上久士氏執筆)など日本人研究者の論文のほか、アイリス・チャンの議論の進め方に一部批判的なスタンスをとっている、チャールズ・バレス、リチャード・フィン、デビッド・ケネディなど、アメリカの学者やジャーナリストの文章も含まれることになっていた。 では、柏書房は、なぜ、このように二冊同時発売といった方針をとったのだろうか。その理由を理解するためには、『ザ・レイプ・オブ・南京』が発売されて以後一年あまりの動向を全体として見なければならない。 日本国内における活発な批判活動の展開アメリカ国内では、日本政府、なかんずく外務省の姿勢が災いして、「南京大虐殺」は確定した「史実」となりつつある。特に昨年12月の初め、斎藤邦彦大使がテレビでアイリス・チャンと討論したことが決定的な失敗だった。その放送のビデオは私も取り寄せて見たが、斎藤大使は、チャンの攻撃に対し、南京事件に関するチャンの言いたい放題の発言にはただの一言も反撃せず、日本は謝罪していること、日本の歴史教科書は南京事件について書いていること、の二点だけを反論のポイントにした。そのため、この放送を見ていたアメリカ人は、今まで疑いをもっていた人も含めて、「もうこれで大虐殺があったことは確定した」という受け取られ方をしているという。日本政府の立場を正式に代表する大使の発言なのだから、そう取られても仕方がない。チャンの本を使った反日運動は、それ以来一層盛り上がっているというのである。 しかし、目を日本国内に転ずれば、そこではこの一年間に、かつてないほど活発にチャンの反日偽書に対する批判活動が展開されてきたのである。その動向を最も特徴的な三点にわたって述べてみたい。 第一に、プロパガンダ写真による歴史の偽造を暴露する組織的な活動が行われたことである。南京事件についてはさまざまな議論があるが、甲論乙駁を読んでもなかなか初心者には真相が分かりにくい。そうしたなかで一番影響力をもってしまうのは、実はプロパガンダ用にしつらえられたニセ写真なのである。ことに学校現場では、写真のもつ効果は極めて大きい。いかに百万言を費やしても、「だって写真で見た」という子どもたちにことの真相を理解させるのは至難の業である。お人好しの日本人は国際政治の過酷な現実を知らないから、政治的な目的でウソの写真が国家の手によって組織的に偽造されているなどとは想像もできない。だから、反日・自虐史観を克服するためには、写真のウソを積極的に暴露していくことが効果的なのである。 こうした観点から、自由主義史観研究会では様々な世代のメンバーを糾合して、「プロパガンダ写真研究会」を組織し、『ザ・レイプ・オブ・南京』が出版された直後から同書に登場するニセ写真の検証作業を続けてきた。この間、産経新聞は社としての独自の取材をも交えて、同会の検証作業の成果を系統的に報道してきた。こうして、チャンの本にはおびただしいニセ写真が使われているらしいという知識は、いくらかでも南京事件に関心を持つほどの人の間では、もはや常識になっていたのである。 第二は、日本の雑誌ジャーナリズムがチャンの本の批判にかなり積極的に取り組んだことがあげられる。右にふれた『諸君!』4月号の秦論文を皮切りに、同誌5月号にはこの文藝春秋北米総局長・塩谷紘氏の現地レポート「外務省は『反日偽書』になぜ沈黙するのか」が載った。また、『正論』7月号には、鍛冶俊樹氏が「アイリス・チャン『レイプ・オブ・南京』の驚くべき背景」を書き、『文藝春秋』9月号には浜田和幸「『ザ・レイプ・オブ・南京』中国の陰謀を見た」が掲載された。この間、柏書房の「解説本」に収録されるデビッド・ケネディらアメリカ人の見方も日本の各種の雑誌で紹介された。 さらに、これらを取り巻く状況として、百万人の観客を動員した映画「プライド」の成功や、小林よしのり氏の漫画『戦争論』が五十万部をこえる大ヒットとなったことなどがあげられる。これらは南京事件そのものを中心テーマとした作品ではないが、戦争という大きな文脈のなかで南京事件における「大虐殺」がありえないことが説得的に描かれており、活字中心の媒体とは異なる映画や漫画といったメディアのもつ影響力の大きさを示したといえる。 第三に、南京事件そのものの学問的・実証的な研究が過去一年間で大きな飛躍を遂げたことをあげなければならない。この点でとりわけ特筆すべきは、昨年の8月に、東中野修道氏が8年間にわたる研究の成果をまとめた『「南京虐殺」の徹底検証』(展転社)が刊行されたことである。同書は、いわば「大虐殺なかった派」の立場を、広範な史料研究と明確な論理によって説得的に展開した本である。この本の出現によって、南京事件の研究は新しい段階に入ったといえる。同時に、同書によってアイリス・チャン『ザ・レイプ・オブ・南京』の批判のための学問的な橋頭堡が築かれた。 以上のべた、「写真」、「メディア」、「研究」の三つの分野の動向が相乗効果をもたらして、『ザ・レイプ・オブ・南京』の翻訳が出る前から、この本は間違いだらけの本らしいという常識が日本国内では多くの人々の間に共有される状況になった。 中学生も笑い出す間違いの山実際、『ザ・レイプ・オブ・南京』に含まれる間違いは、数においても質においても、言語を絶するものである。 例えば、チャンは「江戸時代二百五十年間、日本の軍事技術は弓と刀の段階を越えることができなかった」(ベイシック・ブックス版原著21ページ)と書いている。冗談ではない。1543年、種子島に鉄砲が伝わったことは、日本人なら中学生でも知っている。鉄砲が伝来するや、日本人はたちまちこれを自家薬籠中のものにした。日本は自前で優秀な鉄砲を生産し、その生産量は世界一であった。日本文明についての基礎的な理解を欠き、日本は極東の野蛮国にすぎなかったという程度にしか考えない中華思想にチャンはどっぷりと浸かっているらしい。 もう一つの例を引用しよう。「日本人に特異な性格をもたらしたもう一つの要因は、孤立ということであった。それは地理的な意味での孤立と自己規制的な意味での孤立の両方を含んでいる。15世紀の終わりから16世紀のはじめの時期までに、日本は徳川氏の支配をうけるようになっていたが、徳川氏はこの島国の国民を外国の影響から遮断したのである」(20~21ページ)。 この引用を読んで、読者はこの著者をどの程度の人物と思うだろうか。日本を見下した高慢ちきな中国人が、わかりもしない受け売りの知識を振り回していることだけは間違いない。しかし、私は、ここで、「鎖国はあったのか」などという高級な問題をこの著者にぶつけようというのではない。そんなことはこの著者には無意味なことである。私が問題にしたいのは徳川氏の支配、すなわち江戸時代のはじまりを、「15世紀の終わりから16世紀のはじめの時期」としていることである。江戸幕府のはじまりが1603年であることは、日本人なら小学生でも知っている。しかし、考えてみれば、記録の上でたかだか十件程度しか確認できない南京城内の日本軍兵士による強姦事件を、何の根拠もなく「二万件」に水増しして平然としている著者のことだから、それに比べれば日本の歴史を百年くらい誤魔化すのはかわいらしい間違いというべきなのかもしれない。 右の例は南京事件とは直接関係がないという人がいるかもしれないから、今度は南京事件について書いた部分から引用しよう。40ページには、次のような記述がある。「朝香宮の情報将校だったタイサ・イサモがのちに友人に告白したところによれば、[捕虜は皆殺せの]命令を案出したの彼自身であった」。 「タイサ・イサモ」なる人物は日本陸軍には存在しなかった。「タイサ」は「大佐」のことであろう。「イサモ」が「イサム」の間違いであるとすると、チャンはここで実在した人物「長勇大佐」に言及しようとしたのであろう。ただし、長はこの当時は中佐であったが、それはおくとしよう。問題は、チャンが日本軍の階級呼称の一つである大佐を日本人の名前の一部だと思い込んでいることだ。私はチャンの本を愛読している善良なアメリカ人に問いたい。「ジェネラル・マッカーサー」の「ジェネラル」をマッカーサーのファースト・ネームだと思い込んでいるような知識しか持たない日本人が、えらそうにアメリカ人の性格を批判する本を書いたとして、それをあなたがたアメリカ人はまともに相手にするかということである。 昨年の9月26日に開催された自由主義史観研究会主催の集会において東中野氏は、その時点までに気付いたチャンの本の中の間違いを列挙した資料を配布した。それは実に90項目におよぶリストであった。同氏の手もとのリストは今も増え続けている。このように、日本人なら中学生も笑い出すような間違いを含めて、おびただしい間違いをチャンは彼女の本の中で書き散らかしているのである。 柏書房が陥ったディレンマ『ザ・レイプ・オブ・南京』の日本語版の版権を獲得した柏書房は、翻訳・編集の作業を進めるうちに、深刻なディレンマに直面したはずである。なにしろ、こんなひどい間違いを放置したまま、そのまま訳出するわけにはいかない。すでに明らかになった写真の間違いもおびただしい。 出版社にとって一番よい選択肢は、何も断らずに、チャンの間違いを日本語版でそっと直してしまうことである。あまりにひどい写真も掲載しないことだ。しかし、それは、著者との出版契約上、できなかったに違いない。 そこで、第二の選択肢は、間違いはそのまま訳して、その間違いに注記をつけることである。これでは原著のひどさが浮き彫りになってしまうが、それでもウソをそのまま活字にするよりはマシである。しかし、これも著者は拒否した。チャンにすれば、日本人は何をゴチャゴチャ言っているのか、私の本は全体として「第二次世界大戦の忘れられたホロコースト」、「覆い隠されていた歴史の真実」を明らかにしたのだから、小さなミスなどたいした問題ではない、という思いであったろう。日本人は、自分の本をキズものにするつもりか。 それでも、チャンは、写真一葉の差し替えと、十カ所程度のミスの修正には応じざるを得なかった。しかし、これは、焼け石に水である。それ以外の写真と事実誤認は、版元もその間違いを承知の上で、出版しなければならないからである。では、実際にそうしてしまえばよかったのではないか。つまり、著者の言いなりになってそのまま出版するという第三の選択肢もあったのではないか。しかし、柏書房は、この第三の選択肢をとることはできなかった。そこには、次の二つの事情があったと思われる。 第一に、柏書房は左翼系の出版社の一つではあるが、歴史を中心としてしっかりした学術書をかなり出版している実績がある。キワモノを手がける出版社なら第三の選択肢もあっただろうが、柏書房がそんなことをすれば、会社の信用にキズがつくだけでなく、同社から本を出している他の著者の名誉にもかかわることである。そもそも、歴史書の出版社が、江戸時代は十五世紀の末から十六世紀のはじめに確立したなどと書いた本を出版したら、出版史上の一大スキャンダルである。 第二に、『ザ・レイプ・オブ・南京』の翻訳書の出版は、企業としての営利活動の一つであると同時に、「自虐派」の運動の一環に組み込まれた事業である。だから、企業にとっての利益だけではなく、出版がその運動の利益になるかどうかをも考慮せざるを得ない。もし、このまま出版すれば、反対派の総攻撃を浴び、運動にとって逆効果になるだろう。中学生や高校生の間違い探しのゲームのタネにされるだろう。そして、こんな愚かな間違いをしている著者が、南京事件についてだけは百パーセントの真実を書いているなどとは誰も思わなくなるだろう。つまり、このままで翻訳書を出版することは、日本国内での反対派にかえって勢いを与える逆効果になる危険があるのだ。実際、反対派のひとりである私自身がそう考えてきたのだから、「自虐派」もそう考えて当然である。 このように、抜き差しならないディレンマに追い込まれた出版社が苦し紛れに考え出したのが、第四の選択肢であった。つまり、翻訳書を誤りの修正なしに出版するキズを埋め合わせるために、その解説書を同時に出版するのである。そして、その中で「大虐殺派」の学者が、チャンの本の間違いを指摘しつつ、しかし、この本は南京事件を英語圏に知らせた画期的な意義があると評価する。大体、こんな組み立てで柏書房は困難を乗り切ろうとしたのである。まさに苦肉の策であった。こうして、二冊の本の発売日、2月25日を迎えようとしていた。前日の24日には、これらの本のお披露目のため、外国特派員協会での記者会見も予定されていた。 発売延期に追い込まれる事態が急転したのは、発売日まで二週間を切ったころである。小売り書店が取り次ぎ店に送った注文の短冊が返送されてきたのである。それには次の文書が添えられていた。「2月下旬発売予定の『ザ・レイプ・オブ・南京』は発売延期となりました。ご迷惑をおかけいたしますが、スリップを返送させていただきます。詳細未定につき、後日あらためてご案内申し上げます。 柏書房(株)営業部」。 2月19日、日本の各紙はいっせいに日本語訳の著書の出版延期を報道した。共同通信の同日付け配信記事は、出版延期の理由について、「写真の誤用や事実誤認」などが早くから指摘されてきたことをのべたあと、次のように書いた。「柏書房は、歴史事実の誤認などの点についてはチャンさんが認めた範囲で修正し、25日に出版する予定だった。さらに、原作への反論などを集めた解説書も同時に刊行することになっていた。しかし、今月10日、チャンさん側から『同時に刊行される解説書の出版を差し止めてほしい』という連絡があったため、二冊とも出版を延期することにした。同社は『とりあえずチャンさんの真意を確認中』と突然の差し止め要求に困惑している」。 では、なぜ、チャンは2月10日になって「解説書」の出版を差し止めると言ってきたのだろうか。直接の引き金は2月8日付け夕刊の産経新聞の記事(前出)であった。この記事を読んだ朝日新聞の記者がチャンにインタビューをした。ところが、チャンは、解説書のことを知らなかった。未確認情報だが、この時チャンは激怒したと言われる。考えてみれば、これは当然のことだ。自分が書いた本が外国で翻訳出版される。ところが、その訳書の出版社と全く同じ出版社から、全く同時にその著書を批判した本が出版されるというのである。こんな侮辱はない。柏書房側にすれば、藤原彰編の論文集は、チャンには関係のないことであり、チャンに知らせる必要はないと判断したのだろう。苦肉の策が裏目に出てしまったのである。 朝日系メディアの謀略的報道アイリス・チャン『ザ・レイプ・オブ・南京』の日本語版訳書の出版が挫折した経過は右にのべたとおりだが、これは言うまでもなく反日勢力にとっては大きな痛手であった。そこで彼らの一部は、驚くべきデマを流すことをあえて行った。そのデマに私が気付いたのは、ある偶然のキッカケによってだった。 2月25日、私は東京・有楽町にある日本外国特派員協会の昼食会に招かれて、日本の歴史教育について講演した。この席で「アサヒ・イブニング・ニュース」の記者で英国人のピーター・マクギル氏は次のようなとんでもない質問をした。「あなたが意図してのことだとは思わないが、あなたは今、この国の右翼暴力団のヒーローになっています。連中は出版社を脅迫し、暴力や殺人までやっている」。さらに昼食会の終了後、別の一人の外人記者が私に、「アイリス・チャンの翻訳書が右翼の脅迫で出版中止になったのは本当ですか」と真顔でたずねてきたのである。これは大変なことになっていると私は直感した。誰かが、外国人記者の間に全くのデマを流しているのである。それは、口コミなのだろうか、とも思った。しかし、ひょっとして、あの悪質な「アサヒ・イブニング・ニュース」の記者が記事として書いているのかもしれない、と思いついた。それで、同紙を取り寄せて調べてみた。 結果は、まさに私の予想どおりであった。2月19日付けの「アサヒ・イブニング・ニュース」に「南京本の出版延期」という見出しで記事が掲載されている。執筆した記者の署名はない。その書き出しの部分を訳出すれば次のようになる。 「消息筋が木曜日[2月18日]に語ったところによれば、東京の出版社が電話や手紙による脅迫を受けて、『ザ・レイプ・オブ・南京』の日本語版の出版を延期した。・・・・・・本の製作を中止したのち、柏書房が語ったところによれば、手紙のうちの一通は極右グループの構成員を名乗る男からのものであった。その脅迫状には『出版すれば何らかの行動を起こす』と書かれていた」 しかし、これがデマであることはちょっと常識をはたらかせればわかることである。 第一に、すでに広告が出され、取り次ぎとも契約済みの本の出版を中止するということは、出版社にとっては死活問題である。今回の場合、発行予定日から見て、印刷は当然済んでいたはずだから、出版社が被る経済的な損害は極めて大きい。出版社は取り次ぎその他に対する社会的信用をも失墜する。 第二に、右翼の脅迫程度でそんな非合理的な行動を出版社がとるはずがない。ある種の言論人にとって右翼の脅迫が日常茶飯事であるのは、別のある種の言論人にとって左翼の脅迫が日常茶飯事であるのと同じことである。そういう脅迫に簡単に屈服すること自体、大きな恥である。 第三に、もし本当に右翼の脅迫で出版が中止されたのなら、これはもう出版妨害の大事件である。ただごとではすまない。すべてのメディアが大騒ぎをするに違いない。また、それだけ報道する価値のある重大事であることに間違いはない。 このように、どの角度から見ても、「アサヒ・イブニング・ニュース」の記事がデッチあげの捏造記事であることは明らかなのだ。 3月3日午前、東中野修道氏と私は、東京・文京区にある柏書房を訪問し、日本語版出版延期の経過についてたずねた。応対に出た同社の佐保勲出版部長は、延期の理由について、「著者のほうから意見があり、著者と話を詰める必要を感じたので延期した」とし、右翼からの脅迫が出版延期の理由だったのかという質問には、「そのこととわれわれの[出版延期の]決定との間には関連はない」と明確に否定した。また、月刊誌『創』4月号では、同社の芳賀啓編集長が「右翼よりも一般の人から間違いのまま出版していいのかという電話が多かった。しかし、困ったのはその後、出版延期が右翼の脅しがあったからだと報道されたこと。実際は著者による出版妨害だったのです」と語っている。朝日新聞社は誤報の責任を明確にして、訂正と謝罪を行わなければならない。 「自虐史観」との闘いの新しい段階アイリス・チャン『ザ・レイプ・オブ・南京』の翻訳書の刊行が挫折したことは、日本における「自虐史観」との闘いが、新しい段階に到達したことを明瞭に示すものである。柏書房の出版延期の決定は、チャンの本が反日プロパガンダの目的で書かれた本であるというその本質から生じたものである。それは、決してまぬかれることのできない矛盾なのである。しかし、その矛盾を顕在化させたのは、この一年あまりの間に展開された同書に対する活発な批判活動であった。この出版延期はそれらの意識的な取り組みの成果でもあるのだ。 もちろん、私たちは自由な言論を断じて擁護する。むしろ、翻訳書『ザ・レイプ・オブ・南京』の一日も早い出版を待ち望んでいる。しかし、研究、運動、メディアの、どの領域においても、もはや、かつてのように一方的な宣伝がノーマークで浸透する時代ではなくなっている。日本人に「自虐史観」を植え付けるための最大の「教材」となってきた「南京大虐殺」のウソが通用しなくなる日も近い。 |
|
1937年の南京事件の時、アメリカから来たジャーナリスト(ニューヨークタイムズのダーディン記者)がいました。彼は南京陥落の2日後の1937年12月15日まで南京にいました。彼は南京から報道し、記事をニューヨークタイムズに送りました。その記事はニューヨークタイムズで出版されました。このニュースはナチドイツでも読まれました。アドルフヒトラーはびっくりし、計画中の日本との三国同盟締結を延期しようと考えました。 しかし彼の記事は必ずしも彼自身が目撃したことだけではありませんでした。後日幾つかの間違いも認めています。日本軍の占領直後から虐殺、強姦、略奪の噂が流れました。それらの噂は中国人からだけでなく、英字新聞に書かれました。しかし次第に根拠のないものであることが判明しました。そして報道から消えたのです。 1937年12月24日蒋介石がルーズベルトに手紙で南京虐殺事件について訴えています。彼の妻宋美齢も1938年1月5日に友人への手紙で数千人の市民が日本兵に虐殺されたと書いています。しかしその後彼らは一切虐殺について言及していません。その噂が事実ではなかったことが明らかになったためです。 戦闘に巻き込まれ、兵士の不法行為で、大変な重傷を負った人々がいたであろう事は、マギーのフィルムによって十分考えられます。しかしその数はそれほど多くありません。違法行為として軍事裁判で厳しく罰せられた兵士は10人以下です。この種の不法行為については「南京安全地帯の記録」でも述べられている筈です。南京のすべての市民、約20万人が、ニューヨークのセントラルパークと同じくらいの広さの安全地帯に集められました。しかし20万人の南京市民の目には言われているような残虐行為が目撃されておらず、したがって「安全地帯の記録」に載っていないのです。 中国駐留の日本軍に対する最初の攻撃は、1937年7月7日蘆溝橋で始まった。8年戦争の始まりです。当時の日本軍は日本、中国、満州に展開中のものを含め、総勢25万人でした。一方中国軍は蒋介石直轄の80万人を含め220万人です。これを見ても日本には侵略の意志などなかったことが分かります。日本が何故蘆溝橋の近くに駐屯していたか疑問を感じられるかと思いますが、1900年の義和団事件の後の国際条約によるものです。日本の他4カ国が自国民保護のため、軍の駐屯が認められたのです。これは中国人にとっては不愉快なことでした。しかし貴方も指摘されたとおり、中国は不安全であり、一つの国としての統一がとれていませんでした。事、生命の問題です。改善に関して関係各国で話合われました。日本は話し合いは決して拒否することなく、関係各国と共に解決に努力しましたが、不幸にも成功するに至りませんでした。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイス・S・C・スミス博士は、金陵大学の社会学教授(博士号は哲学だったようですが)であるからしてその調査方法に問題があるとは考えにくい。事件当時の1937年12月-1938年3月の記録であるからして貴重な資料であることには相違ないが、この「南京地区における戦争被害」レポートをどう評価すべきか定まっていない。 実際に、調査結果の把握の仕方が研究者によって次のように異なっている。
以上のように、スマイスの作成した調査結果を共通テキストにしてみた場合においても、各論者によって虐殺数の判断が異なっている。全体に各論者は、6600人としているようである。が、それは死傷者数の合計であるから、明らかな虐殺数は厳密には2500人前後とすべきであろう。 ところが、各論者は6600人では少なすぎると考えており、スマイス・レポートに記載されていた「市内および城郭附近の地域における埋葬者の入念な集計によれば、1万2000人の一般市民が暴行によって死亡した」も加味すべきだとしてこれを加える。秦氏は、スマイス調査(修正)による一般人の死者2万3000人の半数あるいは3分の1を虐殺者数としているが、この秦氏の把握の仕方の問題は、死者の半数あるいは3分の1を虐殺数と見なす理由については触れていない。笠原氏は、同調査による近郊区の虐殺数2万6870人をこれに加えた約4万人を民間人の推計虐殺総数としているが、「同調査による近郊区の虐殺数2万6870人」はどこに書かれているのか上記の文面には無い。 こうして、事件肯定側からは、案外と被害の実数が少なくされていることによって、「基本的に調査方法が大雑把ではないのか-この調査書で出された被害者数や被害に関する統計数字が『一番正確』ということではない」という疑義が出されている。その理由として、調査対象に抽出された家屋には「一家全滅したり住居を放棄したりした家庭」を対象にしておらぬ為、最も被害にあったと考えられる部分が抜け落ちているという欠点を挙げている。次に、「捕虜虐殺のことに触れていない」という欠点もある。洞富雄編『日中戦争史資料9 南京事件Ⅱ』河出書房新社,1973,P222によれば、概要「そして何よりも、この調査は日本軍の占領下によって行なわれており、『占領軍の報復を恐れて日本軍による死傷の報告が実際より少ないと考えられる』とスマイス報告書自身が書いている」という欠点を挙げている。逆にいえば、日本占領下にもかかわらず、このような調査を敢行したスマイスらの調査記録は評価されるべきであろうが、論者の視点によって前者にも後者にも受け取られている。 結局のところ、ルイス・S・C・スミス博士の「南京地区における戦争被害」レポートは、東京裁判にスマイスの宣誓を経て提出され受理されている。ところが、検察側も弁護側も証拠資料として活用していない。洞富雄編・前傾書,P111から112に弁護側と判事との議論が記載されているようであるが、これにつき「証人として出廷していないスマイスの調査書をとするには難があったのではないか」という解釈が行われている。こうして、スミス・報告書は「南京事件」最中の唯一といっても良い戦争被害実態レポートであるにも関わらず、政治主義的に処断されボツにされたという不遇のレポートとなっているという訳である。 |
|