| 「身はたとい武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし大和魂」 |
| 十月念五日 二十一回猛士 |
| 第一節 |
| 一 余、去年已来、心蹟百変挙て数え難し。就中趙の貫高(かんこう)を希い、楚の屈平(くっぺい、屈原くつげん)を仰ぐ。諸知友の知る所なり。故に子遠(しえん)が送別の句に、
「燕趙多士一貫高荊楚深憂只屈平のこと」と云うもこの事也。然るに五月十一日、関東の行を聞しよりは又一の誠字に工夫を付けたり。時に子遠死字を贈る。余、これを用いず。一白綿布を求めて「孟子至誠而不動者未之有也」の一句を書し、手巾ヘ縫い付け携て江戸に来り。これを評諚所に留め置きしも、吾が志を表する也。去年来の事恐れ多くも、天朝幕府の間、誠意相孚せざる所あり。天苟(いやしく)も吾が區々の悃誠を諒し給わば、幕吏必ず吾が説を是とせんと志を立たれども、蚊蝱負山の喩終に事をなすこと不能、今日に至る。亦吾が德の菲薄なるによれば今將に誰をか尤(とが)め且つ怨れんや。 |
(現代語訳)
自分は去年以来、心が百変した。なかんずく趙の貫高を尊敬し、楚の屈平的生き方を模範として来たのは諸君の知る通りである。子遠が送別の句に、「燕趙多士(えんちょうたし)一、貫高(いちかんこう)、荊楚深憂(けいそふかくうれう)。只屈平(ただくっぺい)のこと」というのもこのことである。しかるに、5月11日、関東東送りの由を聞いてから、新たな名句を得た。時に子遠が死字を贈ってくれたが、私は受け取らなかった。一白綿布を求めて「孟子至誠而不動者未之有也」の句を手拭に縫い付けて江戸へ持参した。これを評諚所に留め置いたのは、私の志を表す為であった。去年来(安政5年)、天朝と幕府の間に意思が通じないことがあった。天苟(いやしく)も吾が區々の悃誠を諒し給わば、幕吏必ず吾が説を是とせんと志を立てていたのだけども、蚊蝱負山の喩終に事をなすこと能わず(天の気持を幕府へ伝えようと試みたがだめであった)、今日に至る。自分の徳が薄いので至誠を通じることができなかったと受け取るべきであろう。誰を咎(とが)め怨(うら)むことがあろうか。誰も怨むことはない。 |
|
(解説)
松陰は、安政5年末に野山獄に入れられ、松陰の策があまりにも過激なので門弟の反対意見にあった経緯がある。子遠(しえん)とは、入江杉蔵のこと。当時、岩倉獄に繋がれていた。松陰からは数日しか指導を受けていないが松陰が最後まで信頼していた人物である。
|
| 第二節 |
| 一 七月九日、初めて評諚所より呼出しあり。三奉行出座尋鞠の件両條あり。一に曰く、梅田源次郎長門下向の節、面會したる由何の密議をなせしや。二に曰く、御所内に落文あり。その手跡汝に似たりと源次郎その外申立てる者あり、覚えありや。この二條のみ。それ梅田は素より奸骨あれば、余、與に志を語ることを欲せざる所なり。何の密議をなさんや。吾が性光明正大なることを好む。豈に落文なんどの隠昧の事をなさんや。余、是に於て六年間幽囚中の苦心する所を陳し、終に大原公の西下を請い、鯖江侯を要する等の事を自首す。鯖江侯の事に因りて終に下獄とはなれり。 |
(現代語訳)
7月9日、評定所の呼び出しがあり、三奉行(寺社奉行松平伯耆守宗秀、勘定奉行池田播磨守頼方、町奉行石谷因幡守穆清)の取調べがあった。一つは梅田雲浜(うめだうんぴん)が萩へ来たとき何か密談をしたのではないか。二つは御所内に落とし文があったが、筆跡が似ているのでお前が書いたのではないか。覚えがあるかと尋ねられた。訊問は、この二点だけであった。梅田は少し偏狭なところがあるので、私は胸襟を開いて語り明かすほどの者ではない。そういう意味で密議なぞしていない。私の性は公明正大なるを好む。どうして落文なぞの隠れごとをしようや。私は、ここで終わればよいものを、6年間幽囚の身で苦心して確信した所説を披歴し説いた。しまいに大原重徳(しげとみ)を萩に迎え、長州藩を中心に有志4、5藩で挙兵しようという策謀を自供した。越前鯖江藩主の老中間部詮勝の暗殺計画を話したので、遂に下獄の身となった。 |
|
(解説)
評定所(ひょうじょうしょ)の取調べの経過報告。三奉行とは、寺社奉行の松平伯耆守宗秀、勘定奉行の池田播磨守頼方、町奉行の石谷因幡守穆清のこと。松陰は、取り調べでは潔白を陳述した。これで容疑が晴れるところ自ら老中間部詮勝の暗殺計画を話したので下獄の身となった。つまり、吉田松陰自ら求めて死地に追い込んだことになる。下田踏海の時は幕吏が感激をし、対応が良かったので今回もその例にならったのかも知れない。至誠天に通じなかったことになる。
|
| 第三節 |
| 一 吾が性激烈怒罵に短し、務て時勢に従い人情に適するを主とす。是を以て吏に対して幕府違勅の已むを得ざるを陳し、然る後當今的当の處置に及ぶ。その説常に講究する所にして具に對策に載するが如し。是を以て幕吏と雖も甚怒罵すること不能。直に曰く、汝陳白する所悉く的当とも思われず、且つ卑賎の身にして国家の大事を議すること不届きなり。余、亦深く抗せず。是を以て罪を獲るは萬々辞せざる所なりと云いて已みぬ。幕府の三尺布衣国を憂ることを許さず。其是非吾、曽て弁争せざるなり。聞く、薩の日下部以三次は対吏の日、當今政治の缺失を歴詆して如是にては往先三五年の無事も保し難しと云いて鞠吏を激怒せしめ、乃ち曰く是を以て死罪を得ると雖ども悔らざるなりと。これ吾の及ばざる所なり。子遠の死を以て吾に責むるも亦この意なるべし。唐の段秀実郭曦に於ては彼が如くの誠梱朱。泚に於ては彼が如くの激烈然らば則ち英雄自ら時措の宜しきあり。要内省不疚にあり。抑亦人を知リ幾を見ることを尊ぶ。吾の得失當さに蓋棺の後を待て議すべきのみ。 |
(現代語訳)
吾が性は激しく短気である。故に務めて時勢に従って温和に生活してきた。そういう訳で、幕吏に対しては、幕府が勅許を得ないまま日米修好通商条約に調印したのはやむをえないことであると述べ、その後の措置こそ肝要なりと論じた。この説は、幕府に背くのではなく共に対策を講じようとするもので、穏和な意見であるからして、幕吏はこれ以上の追及ができないこととなった。これに対し幕吏は、「言っていることが全て的を得ているとは思えず、浪人の身でありながら国家の大事を論ずることは不届きである」と弁じた。私は抗(あらが)わず論争を避けた。是を以て罪を獲るは萬々辞せざる所なりと云いて終わった。幕府の三尺布衣国を憂ることを許さず。其是非吾、曽て弁争せざるなり。
聞くところによると、薩摩の日下部以三次は、取り調べの際に、幕府の失政をあげ、かようなことでは幕府は行く先三、五年しか持つまいと述べて幕吏を激怒させた。日下部氏は傲然と、死罪を受けても悔いはなしと云い放った。この気概には私も及ばない。私は、子遠の死に際して私を責めたように、私にできるのはこの程度である。思えば、唐の段秀実も郭曦に於ては彼らしい誠を梱朱した。こうして見ると、彼が如くの激烈こそ英雄と云われるべきであろう。時勢が要請した面もあろうが。私は、彼らに較べると内省的であり不疚を良しとしている。おおよそまず相手を知り、調子を合わせるのを良しとしている。私のような生き方の善し悪しは、死後に棺を蓋で覆って始めて評価が定まるとしたもので、それに委ねようと思う。 |
|
(解説) 幕府役人の調査の概要と松陰の弁明態度と心境を語る。
|
| 第四節 |
| 一 此回の口書甚草々なり。七月九日、一通リ申し立てたる後九月五日、十月五日両度の呼出も差したる鞠問もなくして十月十六日に至り、口書読み聞かせありて直に書き判せよとの事なり。余が苦心せし墨使応接、航海雄畧等の論一も書載せず。唯数ヶ所開港の事を程克く申し延べて國力充実の後御打拂可然なと吾が心にも非ざる迂腐の論を書き付けて口書とす。吾、言いて益なきを知る故に敢て云わず。不満の甚しき也。甲寅の歳航海一条の口書に比する時は雲泥の違いと云うべし。 |
(現代語訳)
このたびの調書は、(下田踏海のときの調書と比較して)はなはだ粗略である。七月九日、一通リ申し立て、九月五日、十月五日両度の呼出も差したる取り調べもないままに十月十六日に至り、供述書を読み聞かせあり、直に署名せよとの事であった。自分が一番苦心をして述べたアメリカ使節との外交交渉や海外渡航の雄大な計画に関する考えは一つも書かれず、ただ数か所のみ開港の事に触れ、国力充実の後、打払うべきなどと、我が心の真意ではない陳腐愚論を書き付けて供述書としていた。私は、言っても無駄であることを悟り、敢えて抗弁しなかった。これにより不満が甚だしく残った。安政元年の下田踏海での取調書と比べると雲泥の差だと云うほかない。 |
|
(解説)
9月5日、10月5日の両度の幕府役人取調べ。
|
| 第五節 |
| 一 七月九日、一通り大原公の事、鯖江要駕の事等申し立てたり。初意らく是等の事、幕にも已に諜知すべければ、明白に申し立てたる方却て宜しきなりと已にして逐一口を開きしに、幕にて一圓知らざるに似たり。因て意らく幕にて知らぬ所を強いて申し立て、多人数に株連蔓延せば善類を傷ふこと少なからず。毛を吹て瘡を求むるに斉しと。是に於て鯖江要撃の事も要諫とは云い替えたり。又京師往来諸友の姓名連判諸士の姓名等可成丈は隠して具白せず。これ吾後起人の為めにする區々の婆心なり。而して幕裁果して吾一人を罰して一人も他に連及なきは実に大慶と云うべし。同志の諸友深く考思せよ。 |
(現代語訳)
7月9日、三位大原重徳西下策、老中間部詮勝要撃策の事を一通り申し述べた。思うに、これらのことは幕府も既に事前情報で承知していると思われるので、誤解なきように明白に述べておいた方が却って良かろうと思い申し立てしたが、幕府は本当は全く知らなかったようで、ならば幕府の知らないことまで述べて多くの仲間内に累が及び善良な関係者を巻き添えにするのは賢明でないと思い直し、肝心なところの言及はしなかった。又、京都で連判した同志の姓名などはできるだけ隠して明らかにしなかった。これは、後の運動の為めを思ってした苦労の老婆心であった。これにより、幕府が、私一人を罰して他に累を及ぼさなかったのは大慶と云うべしであろう。同志諸君、この辺りの事深く熟考せよ。 |
|
(解説)
間部要撃策と松陰の態度(累犯者を出さず)。
|
| 第六節 |
| 一 要諫一條に付きの事不遂時は鯖侯と刺違いて死し、警衛の者要蔽する時は切拂うべきとの事、実に吾が云わざる所なり。然るに三奉行強いて書載して誣服せしめんと欲す。誣服は吾れ肯て受んや。是を以て十六日、書判の席に臨んで石谷池田の両奉行と大に爭辨す。吾、肯て一死を惜まんや。両奉行の權詐に伏せざるなり。是より先九月五日、十月五日、両度の吟味に吟味役まで具に申立たるに死を決して要諫す。必ずしも刺違切拂等の策あるに非ず。吟味役具に是を諾して而も且つ口書に書載するは權詐に非ずや。然れども事已に爰(ここ)に至れば刺違切拂の両事を受けざるは却て激烈を欠き、同志の諸友亦惜むなるべし。吾と云うとも亦惜しまざるに非ず。然れども反復是を思へば成仁の一死區々一言の得失に非ず。今日義卿奸權の為めに死す。天地神明照鑑上にあり。何惜むことあらん。 |
(現代語訳)
間部要撃策の件で、事が成らずの時は刺し違いで死ぬこと、警護の者が邪魔する時は切り払うべしとの事につき、実際には私が云っていないことである。然るに三奉行が強いてそのように書き記し、私を誣告しようとした。私は、そのようなことは云っていないのであるから認める訳にはいかない。これにより、16日、署名の席に臨んで、石谷、池田の両奉行と言い争いになった。私は、死を恐れたのではない。両奉行の策略に屈服しない為である。これより先の9月5、10月5日の両度の吟味に吟味役までもが共に申立たのだが、死を恐れず反論した。必ずしも刺し違えや切り払いの策を講じていたのではないと。吟味役もこのことを認めていたのに、供述書に書き記すのは良からぬ策略ではなかろうか。然れども、ここに至って刺違切拂の両事に拘り認めないのは却って我々の信念の激烈を欠くことになる。同志の諸友もそう思うのではなかろうか。私も惜しまない訳ではない。よくよく考えると、身を犠牲にしても仁をなし、正義を貫き通したい。言葉尻の得失はどうでも良くなった。そういう訳で、相手の言うがままに認め、これにより策略による私の死が確定するところとなつた。全ては天地神明の照鑑(しょうかん)上にある。何を惜しむことあらん。 |
|
(解説)
間部要撃策を廻る供述書の遣り取り。
|
| 第七節 |
| 一、吾、此回初め素より生を謀らず。又死を必せず。唯誠の通塞を以て天命の自然に委したるなり。七月九日に至りては略一死を期す故にその詩に云う継盛唯當甘市戮倉公寧復望生還。その後九月五日、十月五日、吟味の寛容なるに欺かれ又必生を期す。亦頗る慶幸の心あり。この心吾がこの身を惜しむ為めに発するに非ず。抑故あり。去臘大晦朝議已に幕府に貸す。春三月五日、吾が公の駕已に萩府を発す。吾が策是に於て尽き果てたれば死を求むること極て急なり。六月の末、江戸に来るに及んで夷人の情態を見聞し、七月九日、獄に来り、天下の形勢を考察し神国の事猶なすべきものあるを悟り、初めて生を幸とするの念勃々たり。吾、若し死せずんば勃々たるもの決して汨没せざるなり。然れども十六日の口書、三奉行の權詐吾を死地に措かんとするを知りてやり更に生を幸の心なし。これ亦平生学問の得力然るなり。 |
(現代語訳)
私は、これまでも今も単に生を得ようとしたことはない。死を求めたこともない。ただ、誠の道を訪ねて寿命は天命に委してきた。このたび7月9日、死を覚悟して取り調べに臨んだ。ところが、続く9月5日、10月5日の取調べが寛容なためにひょっと生きることができるのかと思った。これを慶んだ。これは命を惜しんでの気持ではない。安政5年12月30日、攘夷は一時猶予、いずれ公武合体により攘夷すべしとの勅状が幕府に下った。今春3月5日は、藩主はすでに萩をたち、策はなくなった。これにより処刑が切迫する身となった。6月末、江戸に来て、夷人の様子を見聞きした。7月9日、獄に繋がれた。天下の形勢を考えると、神国の為に私が為さねばならないことを悟り、初めて今生きていることを幸とする気持ちがふつふつと湧いた。私がもし命を長らえるとしたら、神国の為に更に尽さんとぞ思う。しかし、16日の調書で、三奉行がどあっても私を処刑にせんとしていることがはっきりし、生を願う気持をなくした。こういう気持になれたのも平素の学問の力であろう。 |
|
(解説) 三奉行の権詐と死生についての覚悟を語る。
|
| 第八節 |
| 一、今日死を決するの安心は、四時の順環に於て得る所あり。蓋(けだ)し、彼の禾稼を見るに、春種し夏苗し秋苅り冬蔵す。秋冬に至れば、人皆その歳功の成るを悦び、酒を造り、醴を為り村野歓声あり。未だ曾て西成に臨んで歳功の終るを哀しむものを聞かず。吾れ行年三十一。事成ることなくして死して禾稼の未だ秀でず実らざるに似たれば、惜しむべきに似たり。然りとも義卿の身を以て云えば、是亦秀実の時なり。何ぞ必ずしも哀しまん。何となれば、人事は定りなし。禾稼の必ず四時を経る如きに非ず。十歳にして死する者は十歳中自ら四時あり。二十は自ら二十の四時あり。三十は自ら三十の四時あり。五十
百は自ラ五十、百の四時あり。十歳を以て短とするは惠蛄(夏蝉)をして霊椿(霊木)たらしめんと欲するなり。百歳を以て長しとするは霊椿をして惠蛄たらしめんと欲するなり。斉しく命に達せずと。義卿三十、四時已に備亦秀。亦実その秕たると、その粟たると、吾が知る所に非ず。若し同志の士、その微衷を憐み継紹の人あらば、乃ち後来の種子未だ絶えず。自ら禾稼の有年に恥ざるなり。同志其是を考思せよ。 |
(現代語訳)
一、今日、私が死を覚悟して平穏な心境でいられるのは、春夏秋冬の四季の循環について悟るところあるからである。けだし、農事では春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。秋、冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒をつくり、甘酒をつくって、村々に歓声が満ち溢れる。未だかって、この収穫期を迎えて、その年の労働が終わったのを悲しむ者がいるのを聞いたことがない。
私は現在三十歳。未だ事を成就させることなく死のうとしている。農事に例えれば未だ実らず収穫せぬままに似ている。そういう意味では生を惜しむべきかもしれない。そうではあるのだが、私自身について云えば、私なりの潮時なのであり、花咲き実りを迎えたときなのだと思う。だから哀しもうとは思わない。なぜなら、人の寿命は銘々で定まりがないのだから。農事は四季を巡って営まれるが、人の寿命はそのようなものではない。
人にはそれぞれに相応しい春夏秋冬がある。十歳にして死ぬものには十歳の中に自ずからの四季がある。二十歳には二十歳の四季が、三十歳には三十歳の四季がある。五十には五十の、百には百の四季がある。十歳をもって短いというのは、夏蝉(せみ)のはかなき命を長寿の霊木の如く命を長らせようと願うのに等しい。百歳をもって長いというのも長寿の霊椿を蝉の如く短命にしようとするようなことで、いずれも天寿ではない。
私は三十歳、四季はすでに備わっているとすべきであろう。私なりの花を咲かせ実をつけているはずである。それが単なる籾殻(もみがら)なのか、成熟した栗の実なのかは私の知るところではない。もし同志の諸君の中に、私がささやかながら尽くした志に思いを馳せ、それを受け継いでやろうという人がいるなら、それは即ち種子が絶えずに穀物の年々の実りと同じで、私の命が生き続けていることになる。同志諸君よ、この辺りのことを熟考せよ。 |
|
(解説)
松陰の死生観(四時順環節)。
|
| 第九節 |
| 一 東口揚屋に居る水戸の郷士堀江克之助余未だ一面なしと雖ども真に知己なり。真に益友なり。余に謂て曰く、昔し矢部駿刕は桑名侯へ御預けの日より絶食して敵讐を詛して死し果して敵讐を退けたり。今足下も自ら一死を期するからは祈念を篭て内外の敵を拂われよ。一心を残置して給われよと。丁寧に告戒せり。吾れ誠にこの言に感服す。又鮎沢伊太夫は水藩の士にして堀江と同居す。余に告げて曰く、今足下の御沙汰も未だ測られず。小子は海外に赴けば天下の事總て天命に付せんのみ。但し、天下の益となるべき事は同志に托し後輩に残し度きことなりと。この言大に吾が志を得たり。吾の祈念を篭る所は同志の士甲斐々々しく吾が志を継紹して尊攘の大功を建てよかしなり。吾れ死すとも堀鮎二子の如きは海外に在とも獄中に在とも吾が同志たらん者願くは交を結べかし。又本所亀沢町に山口三輶と云う医者あり。義を好む人と見えて堀鮎二子の事など外間に在て大いに周旋せり。尤も及ぶべからざるは未だ一面もなき小林民部の事二子より申し遣りたれば小林の為めにも亦大に周旋せり。この人想うに不凡ならん。且つ三子への通路はこの三輶老に托すべし。 |
(現代語訳)
東口揚屋(ひがしぐちあがえいや)(松陰は西口にいた)にいる水戸の郷士堀江克之助(ほりえよしのすけ)とはこれまで面識はなかったが心友である。真の為になる友である。彼が私に曰く、その昔、矢部駿州は、桑名侯へ御預けの日より絶食して仇を呪って死を全うした。足下も死を覚悟するからには祈念を篭めて内外の敵を呪詛せよと。丁寧に告戒してくれた。私は、その言に感服した。又、鮎沢伊太夫(あゆざわいだゆう)は堀江と同房しており、私に告げて曰く、あなたの沙汰がどう出るかは分からないが、もし遠島されれば天下の事は全て天命に委ねるしかあるまい。但し、天下の益になることについては同志に後事を託し、言い置くべきことを伝えておかねばならない。この言は、大いに私の志を強めた。私が祈念を籠めるところのものに対して、同志は甲斐甲斐しく私の志を継承し、必ずや尊攘の大功を建てんことを願う。私が死んでも、堀江、鮎沢の両氏は遠島になろうが獄にいようが、私の同志たらんとする者は交わりを結んで欲しい。又、本所亀沢町の山口三輶(やまぐちさんゆう)は義に厚い人のようで、堀江、鮎沢の両氏の内外の世話取りをされている。特に言及しておきたいことは小林民部(こばやしみんぶ)のことで、堀江、鮎沢の両氏の意向を受けて小林の為に周旋している。この人について思うに、非凡な方ではなかろうか。三氏への連絡は、この三輶老にすれば良い。 |
|
(解説)
同志に対する遺言。諸友、門下の同志と獄中で新たに得た同志の連携結束を強め尊王攘夷の強化を依頼している節である。江克之助(ほりえよしのすけ)は、アメリカの総領事ハリスを切ろうとして逮捕された人物。矢部駿州は、堺町奉行、大阪町奉行、勘定奉行を歴任。天保12年、江戸町奉行の時、民政改革に努めたが故あって免職された。翌年、桑名に配所された人物。享年45歳。鮎沢伊太夫(あゆざわいだゆう)は水戸藩士で、水戸密勅問題で投獄。遠島。戊辰の役で戦死、享年45歳。山口三輶(やまぐちさんゆう)は、志士の面倒をよくみた町医者。小林民部(こばやしみんぶ)は、鷹司家の諸太夫、尊攘運動に奔走、水戸密勅事件で逮捕、伝馬町獄で死す、享年52歳。
|
| 第十節 |
| 一 堀江常に神道を崇め、天皇を尊び大道を天下に明白にし異端邪説を排せんと欲す。謂らく天朝より教書を開板して天下に頒示するに如かずと。余謂らく教書を開板するに一策なかるべからず。京師に於て大学校を興し上、天朝の御学風を天下に示し、又天下の竒才異能を京師に貢し、然る後天下古今の正論確議を輯集して書となし、天朝御教習の餘を天下に分つ時は天下の人心自ら一定すべしと。因て平生子遠と密議する所の尊攘堂の議と合せ堀江に謀り、これを子遠に任ずることに決す。子遠もし能く同志と謀り、内外志を協へこの事をして少しく端緒あらしめば吾れの志とする所も亦荒せずと云うべし。去年、勅諚綸旨等の事、一跌すと雖ども、尊皇攘夷苟も已むべきに非ざれば又善術を設け前緒を継紹せずんばあるべからず。京師学校の論亦竒ならずや。 |
| (現代語訳)
堀江氏は神道に熱心で、天皇を崇敬し、その御政道を明らかにし異端邪説を排除せんと奮闘している。その教えをまとめて本を出版しようとしている。私が思うに、本の出版は良いことだが更に策を講じ、京都に大学をつくり、天朝の御学風を天下に示し、全国の優秀な人材を集め、天下古今の正論、定説を編集して書物をつくり、その学問を普及せしめ、これを世に広めていけば人心は確固としたものとしてまとまるのではなかろうか。そういう訳で、私は平素より子遠と密議し、尊攘堂建設のことを堀江に謀り、この役を子遠に任じた。子遠れを入江杉蔵に託した。子遠が能く同志と謀り、内外の同志をしてこれに向かわしめれば私の志も幾分か叶うであろう。去年、勅諚綸旨等の事につき挫折したが、尊皇攘夷は已むべきものではないので、もっと善い方法を編み出し、この運動の緒を継承せねばならない。京師学校の論も言うまでもなく然りである。
|
|
(解説)
「尊攘堂」(京都に大学校設立)についての依頼(入江杉蔵にも依頼)。尊攘堂建設のことを入江杉蔵に託した様子については、安政6年10月20日付けの入江杉蔵あて書簡(実質的な遺言)に詳しい。その要点は次の通り。
「尊攘堂のことは断念した。(略)京都に大学を設ける。大学には尊皇の志厚い若者を全国から集めて宿舎をつくる。京都にある学習院を改組する意見もあるがそれも一つの方法である。(略)学問の節目を糺(ただ)すことが誠に肝要である。朱子学や陽明学を勉強したといっても何の役にもたたない。尊王攘夷の四字を眼目として、何人の書であろうと学であろうとそのよいところをとるようにすること。一つの学にこだわらないこと。本居学と水戸学とは異なるが尊攘では同じである。平田篤胤(あつたね)は本居とも違い癖があるが「出定笑語(しゅつじょうしょうご)」、「玉襷(たまたすき)」は良い本である。関東の学者道春以来、新井白石、・室鳩巣(むろきゅうそう)、荻生徂徠(おぎゅうそらい)、太宰春台(だざいしゅんだい)は幕府の家来であったが、いいところがあった。
伊藤仁斎は尊王攘夷では功績はないが、優れた学問がある。林子平は尊王の功績はないが攘夷の功績はある。高山彦九郎、蒲生君平(がもうくんぺい)、雨森伯陽(あめのもりはくよう)、魚屋の八兵衛などはみな大功の人であり、神牌(しんぱい)(神霊の名を記した位牌)を設けること。(略)今は安政の大獄の嵐が吹き荒んでいるから暫く見合わせ無理をしないように。しかし、近年の内、政権は倒れるだろう。松陰はこのように先を見ているのであれば、暫くじっとしていて、倒れた後活躍して欲しいといつも思っているが、それをしないところが松陰らしいところであろう。惜しいことである。(略)」。
尊攘堂は、明治20年品川弥二郎(しながわやじろう)が建てた。現在京都大学の構内に保存されている。松陰の木像を中央に安置し,文書などを集めている。学習院は東京へ移り現在に繋がっている。萩でも戦中に尊攘堂を建立との動きもあったが、そのままとなっている。尊攘の精神は後もずっと残っている。
|
| 第十一節 |
| 一 小林民部云京師の学習院は定日ありて百姓町人に至るまで出席して講釈を聴聞することを許さる。講日には、公卿方出座にて講師菅家清家及び地下の儒者相混ずるなり。然らばこの基に因て更に斟酌を加えば幾等も妙策あるべし。又懐德堂には靈元上皇宸筆勅額あり。この基に因り更に一堂を興すも亦妙なりと小林云えり。小林は鷹司家の諸大夫にてこの度遠島の罪科に處せらる。京師諸人中罪責極て重し。その人多材多藝唯文学に深からず處事の才ある人と見ゆ。西奥揚屋にて余と同居す。後東口に移る京師にて吉田の鈴鹿石刕同筑州別れて知己の由。亦山口三輶も小林の為めに大に周旋したれば鈴鹿か山口かの手を以て海外までも吾が同志の士通信をなすべし。京師の事に就ては後来必ずかを得る所あらん。 |
(現代語訳)
一 小林民部は云う。京都の学習院は日を決めて百姓町人に至るまで出席させて講釈を聴聞することが許されるようにしたら良い。講日には、公卿方が出向き、講師として菅家、清家及び地下の儒者が混ずるようにすれば良い。こういう風に工夫すれば更に妙案が生まれることだろう。又懐德堂には靈元上皇宸筆勅額あり。こういう風に工夫すれば会が盛んになり結構なものとなるだろう。小林は、鷹司家の諸大夫にして、この度遠島の罪科に処せらている。京都の同志の中でも極めて重い罪を科せられている。この人は、有能にして芸事深い方であるが特に文学に才能を見せているように思われる。西奥揚屋にて私と同居している。後、東口に移った。京都の吉田の鈴鹿石刕同筑州別れて知己の由である。又、山口三輶も小林の為めに大に周旋しており、鈴鹿か山口かの手を通じて遠島先まで我らが同志は通信をなすべしである。京都の事に就ては後になって必ずや再評価される日が来るであろう。 |
(解説)
「学習院」の利用、改善策(小林民部の案) |
| 第十二節 |
| 一 讃の高松の藩士長谷川宗右衛門、年来主君を諫め、宗藩水家と親睦の事に付て苦心せし人なり。東奥揚屋にあり、その子速水余ト西奥に同居す。この父子の罪科何如未だ知るべからず。同志の諸友切に記念せよ。予、初て長谷川翁を一見せしとき獄吏左右に林立す。法隻語を交ることを得ず。翁獨語するものの如して曰く寧為玉砕勿為瓦全と。吾甚だ其意に感ず。同志其之を察せよ。 |
(現代語訳)
讃岐の高松藩士の長谷川宗右衛門は、藩主と水戸藩との周旋につとめ苦心した人物である。尊攘に奔走し息子の速水と共に捕らえられ伝馬獄に繋がれている。同じ獄にいながら言葉を交わせなかったが、彼は独り言のようにして次のように言った。「命たるもの、玉(ぎょく)となりて砕(くだ)かれようとも、瓦(かわら)となって長生きするものではない」。同志諸君、この意を深く味わえ。 |
|
(解説)
西郷隆盛も同じようなことを言ってる。「幾何か辛酸を経て、志半ばにして上は玉砕するも瓦全を筈ず、我家の美法は子孫の為に美田を買わず」と。子孫の為に財産を残しておこうと言うようなことは考えない。薩摩の人は今もって西郷南州といえば誰一人悪く云わない。
|
| 第十三節 |
| 一 右数條、余、徒に書するに非ず。天下の事を成すは天下有志の士と志を通ずるに非ざれば得ず。而して右数人余此回新に得る所の人なるを以て是を同志に告示すなり。又勝野保三郎早已に出牢す。就て其詳を問知すべし。勝野の父豐作今潜伏すと雖ども有志の士と聞けり。他日事平を待て物色すべし。今日の事同志の諸士戦敗の餘傷残の同士を問訊する如くすべし。一敗乃挫折する豈勇士の事ならんや。切に囑す切に囑す。 |
(現代語訳)
一 これから述べる数條は、肝に銘じなさい。天下の事を成すには天下の有志の士と志を通じなければ達成し得ない。そういう訳で、右数人余はこたび新に得た人物であり、これを同志に知らせておく。なお、勝野保三郎は既に出牢している。何かのことについて詳細を問い質すが良かろう。心を通わせ運動をすすめて欲しい。勝野の父の豐作は今潜伏すといえども有志の士と聞いている。他日、頃合いをみて探し出すが良かろう。今日の事、同志の諸士は戦敗の餘傷、残りの同士を問訊する必要がある。一度失敗したからと云って挫折するようでは、どうして勇士足り得ようか。このことを切にお願いしたい、お願いしたい。 |
|
(解説)
|
| 第十四節 |
| 一 越前の橋本左内二十六歳にして誅せらる。実に十月七日なり。左内東奥に坐する五六日のみ、勝保同居せり。後勝保西奥に来り、予と同居す。予、勝保の談を聞て益々左内と半面なきを嘆す。左内幽囚邸居中資治通鑑を読み註を作り、漢紀を終る。又獄中教学工作等の事を論せし由、勝保予が為めに是を語る。獄の論大に吾が意を得たり。予、益々左内を起して一議を発せんことを思う嗟夫。 |
(現代語訳)
一 越前の橋本左内は26歳にして誅せらた。十月七日のことであった。左内東奥に五六日ばかり居た。その時、勝保が同居した。後に勝保は西奥に来て私と同居した。私は、勝保の談を聞いて益々左内と会えなかったことを嘆いている。左内は、幽囚の間、資治通鑑を読み註を作り、漢紀を綴った。又、獄中で教学や運動工作等の事を論じた。勝保予は、私の為にこれを語ってくれた。左内の獄中の論は、私を大いに納得させた。私は、益々左内を起して一議を発せんことを思うがあぁ。 |
|
(解説)
この節で、橋本左内を激賞している。
|
| 第十五節 |
| 一 清狂の護国論及び吟稿口羽の詩稿、天下同志の士に寄示したし故に、余、これを水人鮎沢伊太夫に贈ることを許す。同志それ吾に代りてこの言を践まば幸甚なり。 |
(現代語訳)
一 清狂の護国論及び吟稿口羽の詩稿、天下同志の士に寄示したし故に、余、これを水人鮎沢伊太夫に贈ることを許す。同志それ吾に代りてこの言を践まば幸甚なり。 |
|
(解説)
|
| 第十六節 |
| 一 同志諸友の内、小田村中谷久保久坂子遠兄弟等の事、鮎沢堀江長谷川小林勝野等ヘ告知し置きぬ。村塾の事、須佐阿月等の事も告げ置きけり。飯田尾寺高杉及び利輔の事も諸人に告げ置きしなり。これ皆吾が苟も是をなすに非ず。 |
|
(現代語訳)
一 同志諸友の内、小田村中谷久保久坂子遠兄弟等の事、鮎沢堀江長谷川小林勝野等ヘ告知し置きぬ。村塾の事、須佐阿月等の事も告げ置きけり。飯田尾寺高杉及び利輔の事も諸人に告げ置きしなり。これ皆吾が苟も是をなすに非ず。
|
(解説)
尊攘運動の同志を紹介(尊攘運動の全国的展開を期待)。この中で伊藤利輔が出てくるのには驚く。利輔は、松陰の死体を引き取りにも行ってる。 |
| (かきつけ終りて後ー五首の和歌) |
かきつけ終りて後心なることの種々かき置ぬ 思残せること なかりけり
呼びだしの聲まつ外に 今の世に待つべき事のなかりける哉(かな)
討れたる吾をあわれと見ん人ハ 君を崇めて夷拂へよ
愚なる吾をも友とめづ人ハわがとも友とめでよ人々
七たひも生かえりつゝ夷をそ攘はんこゝろ 吾忘れめや |
|
| (現代語訳) |
| 十月廿六日黄昏書 二十一回猛士 |
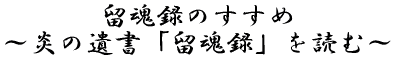 」で次のように紹介されている。これを転載しておく。
」で次のように紹介されている。これを転載しておく。
