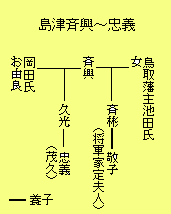ところが、清河八郎は、朝廷の警護番となり攘夷に向けて活動することを表明し尊王倒幕派へ移行した。この時、幕府の為に京都を護衛するのが筋として京都残留浪士組(近藤勇・芹沢鴨をはじめとする派の約23名)は会津藩・京都守護職・松平容保の支配下の御預かりになり、京の町の治安維持に当たることになった。
この流れが新撰組となる。3.13日、江戸帰還に反対した浪士13名が京都守護職に属して治安組織「新撰組」を結成。新撰組は隊内に厳格な局中法度を定め、組織を拡大していった。その内容は、一、士道に背くまじき事、一、局を脱するを許さず、一、勝手に金策致すべからず、一、勝手に訴訟取扱うべからず、一、私の闘争を許さず。
しかし、浪士組、新撰組、及びそれぞれの内部でイニシアチブ闘争が発生する。3.24日、殿内義雄が殺される。4.6日、阿比留栄三郎が暗殺される。4.13日、清河八郎が佐々木唯三郎らに暗殺される。
この間、新撰組による政治テロも頻発していった。つまり、志士派のテロルと新撰組のテロルが入り乱れ始めたことになる。