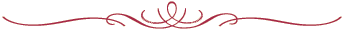
| ハウスキーパー問題 |
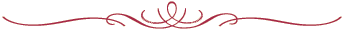
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).3.23日
| (れんだいこのショートメッセージ) | ||
| 構図的に見て何やら「転向問題」と似ているものとして「ハウスキーパー制問題」がある。これも「転向問題」同様に隔靴掻痒でややこしい判断世界へと誘われている。れんだいこは、この国の自称インテリの思想的営為にピントが合わない。以下、「ハウスキーパー問題」を考察する。「転向論の再構築」その他を参照する。 伊藤晃・氏は、1995年、ハウスキーパー制について次のように述べている。
ハウスキーパーの活動の内容は必ずしも明確ではない。そういう訳で、ハウスキーパー制度の実態は未だ曖昧さを残している。これをどう捉えるべきか。れんだいこがよろづ高く評価する宮内勇・氏は、1979年の座談会(石堂+原+福永+宮内)の中で次のように述べている。
れんだいこは、「ハウスキーパー制問題」に対する観点は、宮内勇・氏のこの観点を継承したい。以下、諸説を確認するが、平野見解は後付け批判に終始しており、宮顕見解は史実隠蔽論であり、その他のものもさほど役に立つものがない。この問題のポイントは次のことにある。「ハウスキーパー制問題」は、非合法時代に対応すべく編み出された都市型党活動であり、それに伴う否定事象は当時の情況との絡みで弁証法的に考察されるべきである。物事には長所もあれば短所もある。功罪の罪を指摘して功の面を理解しようとせず、単に否定見解へ導こうとするのは右翼的過ぎよう。既成のものは右翼的過ぎる。いくら学んでも、れんだいこ観点には至らない。よって学べば学ぶほどバカになること、れんだいこが請け負う。いずれ、「れんだいこのハウスキーパー制論」を生み出そうと思う。転向論然り、ハウスキーパー制論然り、その他諸々然りと思う。 |
![]()
| 【ハウスキーパー制問題はどう論ぜられてきたか考】 | |||||
| 戦前において、ハウスキーパーを扱った言説は存在した。小林多喜二の「党生活者」にも登場しているし、片岡鐵兵氏の1930年の「愛情の問題」は、ハウスキーパーの女性を描写している。蛇足ながら、文芸界に於ける宮顕の盟友・蔵原惟人はこの「愛情の問題」を「一般にこの種の作品には“男性的偏向”がある」と批判している。 1933年、「婦人公論3月号」は「主義と貞操」を特集し、その中で共産党のハウスキーパー制に言及し、「共産党の性利用」を批判している。平塚雷鳥は、報道されたスキャンダルをもって、女性党員を「新時代の新しい型の男性奴隷」と指摘し、「わたくしに言はせるなら共産主義思想そのものが元来男性本位の思想」と批判している。当時連載をもっていた山川菊栄は、平塚の共産主義批判には同調せず別の観点から批判している。それによれば、ハウスキーパーは党による性の利用であり、それは共産主義の理想を裏切り蹂躙するものである、として非難している。 「転向論の再構築」は次のように述べている。
戦後になって、ハウスキーパー制度自体の考察に向けたのは平野謙たちが最初であった。但し、概ね女性差別に基づく「人間侮蔑制度であった」として採りあげ言及した。平野氏は、ハウスキーパー問題について発言してきた数少ない人間の一人だが、1976年、ハウスキーパーについて以下のような説明をしている。
平野は、ハウスキーパー問題に関して、戦後直後よりかなり大きな関心を払っていた。1946年の「ひとつの反措定」において、概要「政治という『目的』のために人間、中でも女性が『手段』にされること、そうした例の一つとしてハウス・キイパー問題がある」と述べ、この問題を採りあげている。しかし、一時の議論が終わると、ハウスキーパーが問題として取り上げられることはほとんどなくなってしまった。 ハウスキーパー制度が再び取り上げられるのは1970年代半ばの立花隆の「日本共産党の研究」の連載によってである。同書によって、特にスパイリンチ事件を中心に当時の共産党の実態が政治的に焦点化され、ハウスキーパー制にも光が当てられた。そのような中で、平野が積極的に参加し、リンチ事件との関わりで、スパイ大泉のハウスキーパーであった熊沢光子の悲劇について取り上げた。 福永操・氏は、1979年、平野謙氏の「『リンチ共産党事件』の思い出」を読んだときに次のように述べている。
こうした結果、いくらかの研究は積み重ねられるようになったが、ハウスキーパーを主題とした研究はまだまだ少ない。 |
|||||
| 問題は次のことにある。果たして、平野の如くな「女性の政治利用としてのハウス・キーパー制論」で良いのだろうか。それが非人間的であったとしても、あまりにも過酷な党弾圧に遭って余儀なくされた都市型党活動の適応制度としての面も見なければ片手落ちではなかろうか。その結果としての、スキャンダルは当然予想されるものであり、その予想されているものを批判したからといって何の甲斐があろう。 むしろ、それでも何故生み出されたのか、その功の面は何なのか、負の面は何なのか、どうすればもっと適正足りえたのかを問うことが肝心ではなかろうか。こう問うことによって初めて現在の課題になるのではなかろうか。 2005.10.21日 れんだいこ拝 |
| 【ハウスキーパー制の歴史考】 | |||||||||
|
「ハウスキーパー」制度は、「党規約にも、党組織の図式にも存在しない」がその史実は次のようなものである。平野氏は次のように述べている。
ここに、ハウスキーパー制の由来が明かされている。それによれば、山代巴・氏の「黎明を歩んだ人」(1975年)を参照すれば、ハウスキーパー制は、三・一五事件でやられた党の再建過程で「自然発生的」に生み出されたことになる。つまり、党の地下活動化と共に必要から編み出されたのが、当局の眼を誤魔化すための「夫婦偽装ハウスキーパー制」であったということになる。
これを裏付ける平野発言(1976年)があり、次のように述べている。
栗原幸夫氏は、以下のように説明している。
しかし、これらの組織は三・一五事件で解散させられ、四・一六事件では、これらの組織から育った活動化の大部分が検挙されてしまう。栗原氏は、1977年に次のように述べている。
ハウスキーパーは、夫婦を偽装しながら男性党員の地下活動を支えた。その生活を支えると共に街頭化した地下活動の伝達レポ役をも引き受けていた。 |
| 【ハウスキーパー制に対する宮顕系日共の党史的位置付け考】 | ||||||
|
ところが、こうした史実を持つ「ハウスキーパー制」に対して、現日共党中央の創始者・宮顕が、戦後まもなくの発言の中で、「制度」としてのハウスキーパーの存在を否定して次のように述べている。
この問題に並々ならぬ関心を寄せていた平野氏は、さすがにこの「宮顕見解」を受け付けず、1976年、「キレイゴトの原則論」であるとして次のように批判している。
福永氏も、1979年、次のように批判している。
河合勇吉も、1979年のハウスキーパーをめぐる座談会(石堂+原+福永+宮内)で次のように批判している。
|
| 【ハウスキーパーなる用語の由来】 | |||
|
ハウスキーパーという用語はどのような歴史をたどっているのだろうか。山下智恵子(1985年)は以下のようにまとめている。
司法省刑事局の「思想月報」に収録されている「昭和三年以降昭和九年治安維持法違反に因り起訴せられたる婦人に関する調査」(司法省刑事局、1934年)を見ても、ハウスキーパーという語が登場するのは、「昭和9年」の項からのみであり、それ以前は、「内妻」という語しか出てこない。 |
| 【性の利用としてのハウスキーパー制度】 | |||||
|
初期の頃のハウスキーパーは、地下活動の要請に対する党(実態は仮に技術部であったとしても)の指令という形態はとっても、後に見るような明確に女性差別的な制度ではなかった。ハウスキーパーの本来の目的は、非合法活動のアジトを「普通の家庭」に偽装することであった。
つまり、運動の中で結婚し、女性がハウスキーパーの役割を果たすようになる場合や、あるいはハウスキーパーとして一緒になってそのまま結婚するような場合も少なからず存在したということになる。
あるいは、男達は、最初からハウスキーパーの役割をタテマエ通りには受け取っていなかった可能性もある。福永操・氏は、1979年の座談会(石堂+原+福永+宮内)で次のように述べている。
次のような事例も報告されている。秋沢氏は、1984年、次のように述べている。
いずれにせよ、妙齢の男女を共同生活させるのであるから、そこにはかなりな無理があったということになる。特に、女性の側の負担は大変であった様子が次のように語られている。平野謙の引用で紹介した山代吉宗のハウスキーパーをつとめた田中ウタについて、山代の方が「偽装夫婦」時代をこう振り返っている。その時田中ウタは豊原五郎と結婚していた。
|
|||||
| れんだいこは、ここでも、宮内氏の「どちらも一つの思想に燃えている二人がなんとなく結ばれていくのは非常に自然だった」見解を高く評価する。他の評者の如くに、偽装夫婦が真性夫婦になった事に対して批判するのは愚かであろう。いろんな例があって良いではないか。どのパターンが良いとかいうものではなく、いろんなパターンが認められるべきではないのか。道徳論で律するのはマルクス主義ではなかろう。 |
| 【ハウスキーパー制下での男尊女卑問題】 | |||||||
|
ハウスキーパー制に纏わる問題として性の問題以外にも次のようなことがあった。伊藤晃・氏は、1995年、以下のように注意を促している。
より主要な問題として、ハウスキーパーに割り当てられる仕事の意義の問題があったようである。男尊女卑的な関係で、軽業的なあしらいがされていたことが報告されている。作家の中本たか子は、「武装」共産党時代にハウスキーパーを体験した。彼女はそれを小説や手記として発表している。それを見ると彼女の活動がいかに献身的であったかわかる。1937年発表作で次のように述べている。
秋沢弘子(1984年)も同様に次のように訴えている。
福永(1982年)も同様で、こうした活動の意義の不明確さは街頭連絡(レポ)の場合にも見られたと云う。共産党が地下活動化を深めるにつれてレポ活動が重要な仕事して課せられてきたが、ハウスキーパーの女性もまた党員であるため、昼間は家事の他にレポに忙殺される場合が多かった。レポについて次のように述べている。
問題は次のことにある。しかし、単に忙しいだけならまだ良い。
田中ウタも袴田里見との地下活動でのレポ活動についてこう述べている。
つまり毎日どこかで誰かと会うのだが、その相手が誰なのか、伝えている内容は何を意味するのか、自分の行動が何の役にたっているのか、さっぱりわからないのだ。要するに、共産党が女性党員を「消耗品」としてのみ扱い、決して活動への主体的な参加を要求しなかったことが第一の問題なのである。
|
| 【ハウスキーパー制の帰結】 | ||
| ハウスキーパー制度は、現金拐帯や美人局などとともに、「女性を利用する共産党」として、マスメディアに格好のスキャンダルの材料をあたえる結果となった。 福永氏は、1982年、次のように述べている。
山下氏は、1985年、次のように述べている。
スパイであった大泉兼三のハウスキーパー・熊沢光子の事例は有名である。彼女は、結局獄中で自殺することになる。 |
| 【ハウスキーパー制の陥穽】 | ||
|
宮内勇(1976年)はこう回想している。ハウスキーパーに関してではないが、共産党の街頭化に対して次のように述べている。
宮内が言うとおり、共産党自身のこうした傾向は、現にスパイの潜入を許し、あるいはスパイだらけなのではないか、と疑心暗鬼を生む温床となった。
|
| 【ハウスキーパー制に横たわる組織論的問題点考】 | |
|
ハウスキーパー制もまた当時の党活動の水準に規定されていた。「転向の組織的土壌」の項で考察したが、組織論的に上下の命令系統が硬直化しており、「上に対して異議を述べることが出来ない構造」により、制度は空洞化させられ、何ら取り柄の無いものに変質させられていった。にも関わらず、それへの抗議も封殺された。 福永操(1982年)は、是枝恭二との「結婚」(恋愛感情などではなく、実質的にはハウスキーパーであったと福永自身は述べている)を、志賀義雄にすすめられたとき、こう思ったという。
ちなみにこのときの福永の「直観」は決して単なる思い過ごしではなく、後に是枝恭二本人から「中央(部)では、きみがぼくとの結婚を承諾しなければ、きみを除名することにきまっていたんだ」と告げられ絶句する。ただし、この場合は、福永自身の思想評価の問題も絡んでいるので、党員全般に対する共産党指導部の方針というわけでは全然なかった。ただ命令を受け入れる党員自身が、「上部」の命令の重さをどのように考えていたか、ということは福永の事例だけでもよくわかるだろう。 |
| 【「Ⅱハウスキーパー問題に表象される革命運動組織 」】 | |
秦功一「プロレタリア文学運動論考」の「Ⅱハウスキーパー問題に表象される革命運動組織 」を転載しておく。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)