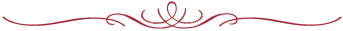
| 徳川幕藩体制前期 |
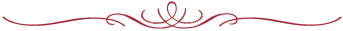
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.9.9日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「中山ミキ教祖伝」の筆を記すに当って、まずは、「みき」の誕生した頃の社会情勢及びその世間事情を踏まえておこうと思う。何人と云えども「時代の子」として、その時代の社会の仕組みあるいは風潮を母班として、その刻印を受けながら成長を遂げていく筈であるから。 天理教教団本部では、「みき」の誕生から中山家への嫁入り、天啓等々全ての進行を、「魂の因縁」の教理或いは「年限の理」の教えにより、予定完結的に理解することを建前としているが、こうした立場に立てば、「みき」の「時代の子」としての側面を見落とすことになることが避けられない。私は序文でも述べたように、それがどうであろうと、あるいは仮に「みき」自身の言説に違背しようとも、「みき」の言説をさえ可能な限り「時代の言葉」として捉え、「みき」をも又「時代の子」としての枠組の中での成長過程として辿ってみようと思う。 そういう意味で、「みき」を述べるにあたっては、まず「みき」の誕生した時代の特質並びに世相を俯観しておくことから始めねばならないであろう。「みき」の段階的な成育史は本稿各章に譲ることとして、ここでは寛政十年(1798年)に生まれた「みき」が過ごした時代つまり俗に「江戸時代」と呼ばれる徳川政権の特質、即ち歴史的な位相について概観していくことから論を起そうと思う。 ところで、その「江戸時代」を歴史眼的にどう評すべきか。これが、れんだいこの2015年初頭の現在の最新の学的探求である。従来の「後進未開的な封建制と見做したうえでの否定的な規定」からの大胆な転換としての「伝統的開明的な日本型政治秩序と見做したうえでの肯定的な規定」に向かいたい。前者は国際ユダ邪学の然らしめる論であり、後者こそ来るべき社会の歴史論とするべきである。これにより本稿を大きく記述替えしようと思う。本文中、批判的な記述のくだりは追って書き換えるつもりである。 2011.8.30日再編集 れんだいこ拝 |
| 【徳川政権の歴史的特質としての「朝廷権威、徳川権力体制」】 |
| 一般に人類の歴史的区分としては、古代、中世、近世、近代、現代というように段階づけられる。この仕分けに従えば、徳川時代は近世に位置することになる。この時代は、武家が、かっての権力者であった朝廷、寺社権力から権力を奪い、政権を掌中にして行く流れにあった。鎌倉、室町、戦国時代と続いてきた武家政権は織豊政権から徳川政権へと完結し、徳川時代が武家政権の頂点となり且つ最後の時代となった。 ちなみに、幕府とは、幕を張り巡らせた政府、という意味であり、天皇政府の将軍を、当時、外敵であった蝦夷を討ち平らげるための征夷大将軍に任じ、権限を与えて開かせたというのが起こりである。 京都の朝廷を朝堂というのに対して、幕府はいわば臨時軍事政権ともいうべき性質のものであり、天皇から節刀という刀をもらうことによって征夷大将軍という地位を得て、軍政を敷いたのが幕府の政治であった。 その徳川政権と朝廷は、世界史上珍しい「日本型棲み分け原理に基づく」二元支配体制政治を創造していた。この仕組みには二つの特徴が認められる。その一は、新支配権力が旧支配権力を打倒するものの一掃させるのではなく、即ち西欧的な「血で血を洗う」が如くな絶滅戦争に向かうのではなく、勝負の帰趨が見えるところまで戦い、その頃合いを見て両者が手打ちし、新支配権力を主、旧支配権力を従とする補完的な支配秩序を造る仕組みを云う。これを仮に「日本型棲み分け原理に基づく政治その一」とする。要するに和合的と云うことになる。 「日本型棲み分け原理に基づく政治」の特徴その二は、政治の淵源を神道に求め、神道の極意を司る天皇の裁可を得て権力を行使すると云う天皇制原理に基づく政治を旨としているところに認められる。しかも、この天皇制原理そのものが一筋縄ではなく主として二筋縄で形成されていたように思われる。これを確認しておけば次のように概括できる。この観点は、れんだいこ歴史学の薀蓄をひけらかすことになるが耳を傾けよ。天皇制原理は朝廷を拵える。この朝廷を仔細に見れば以下の如くになる。日本歴史の元々の支配権力者であったのは在地系の出雲朝廷である。その出雲王朝の国譲りの後、出雲朝廷系王権として出現したのが邪馬台国王朝である。その権力を奪ったのが来航系の神武天皇以来の大和王朝である。れんだいこ史観はこれを仮に前者を原日本、後者を新日本とする「原日本新日本/二重国家論」を獲得している。原日本政体は大王制であり、新日本政体が天皇制である。その後の天皇制史は、新日本系天皇制に原日本系大王制が融合し、それがうまく機能する御代、齟齬し抗争する御代を連ねながら「日本型棲み分け原理に基づく政治」の連綿史を刻印し続けていくことになる。 徳川政権は、日本史の「原日本新日本二重国家論」的特質を正確に理解し、その理解に基づいた仕組を創造していた。これが徳川政権の長期安定化の秘密だったと思われる。まず朝廷権威を認め、そういう朝廷の権威を尊重する政治を採用している。しかしながら政治の実権は武家の徳川政権が握り、本拠を江戸に構え号令を発する仕組にしている。但し、武家の権威を裏づける征夷大将軍の拝命や官位の授与は朝廷から賜るという二元支配制度を構築していた。即ち、政治の重要なところに於いて「朝廷権威、徳川権力体制」を敷いていた。徳川政権が、こういう風に日本的な統治の在り方としての特質である「日本型棲み分け原理に基づく政治」に基づいていたことはもっと注目されて良い。徳川政権樹立期に、こういう仕組みを良しとする知恵者の建言があり、それを受け入れらたことによりこういう統治が可能になったと思うしかない。 徳川政権がこの伝統的統治手法を踏襲したことにより、朝廷は将軍任命の押印者としての権威を温存していくこととなった。京都の朝廷は、裏政治とも云うべき「祭祀、天文、暦算」を支配し、学問、芸術などに影響力を維持した。朝廷の存在は、徳川政権の盛期においては、「日本型棲み分け原理に基づく政治」に基づく善政故に何ら問題とならなかったものの、幕末期に政権に蔭りが出てくるに随い、幕府に代わる権威者として押し出され、王政復古運動を盛んにして行くことになった。 明治来の歴史学は、こういう江戸時代までの日本史を未開野蛮な非文明的な歴史段階として規定し、「日本型棲み分け原理に基づく政治」を卑下させる観点を据えて叙述している。即ち、徳川政権が伝統的な日本型支配秩序に適合させた非常に高度賢明な支配体制を敷いていた面に注目していない。それは国際ユダ邪学の進歩主義史観に拝跪し過ぎているからであり粗暴な見立てでしかない。 こういう歴史学観点を獲得した以上、今後は「江戸時代」、はたまた日本歴史をどのように把握して行くべきか。ここを注視する歴史眼が問われている。この問題は、れんだいこの2015年初頭現在の最新の学的探求である。その意図するところ、従来の否定的姿勢から脱却し、むしろ大胆な転換として肯定的に向かいたい。前者は国際ユダ邪学の然らしめる進歩主義史観によりもたらされる論であり、後者はれんだいこ史観によりもたらされる論である。「日本型棲み分け原理」を日本的政治の生命、粋として称揚する政治学、歴史学を樹立することが待ち望まれていよう。これにより本稿を大きく記述替えしようと思う。本文中、江戸時代に対する批判的な記述のくだりは追って書き換えるつもりである。 2011.8.30日再編集 れんだいこ拝 |
| 【幕藩体制考】 |
| 徳川政権は家康(1542~1616年)を初代とし、1600(慶長5)年、家康を盟主とする東軍が美濃の関ガ原の役で、それまでの権力者であった西軍豊臣氏連合との戦いに勝利することにより覇権を確立し、1603(慶長8)年2.12日、朝廷より右大臣「征夷大将軍」の称名を拝戴するに及び、江戸に幕府を開設したことに淵源を発する。1614(慶長19)年の大坂冬の陣、1615(元和元)年の大坂夏の陣等数次の抗争を経て、豊臣家旧家臣勢力が一掃された結果、徳川の前に立ちはだかる勢力は皆無となった。以来、徳川政権は、1867(慶応3)年に慶宣公よって大政奉還される迄の将軍家15代、ほぼ266年にわたって続く、わが国の政権史上最長の、世界史上にも稀な長期政権となった。この長き体制を支えたのが、歴史学上は封建的諸関係に照応した社会統治制度として見做される幕藩体制と呼ばれる支配体制であった。 徳川政権の第二の特質は、既に直前の織田豊臣政権が、下剋上的な戦国時代の抗争期を終止させ、漸く全国統一的な支配権力を樹立していた果実を受けて、全国を支配下に組み込んだ、中央集権的な統一国家としての権能を備えた近代国家的的側面を有していた政権であったことに求められる。 徳川政権の第三の特質は、同政権が武家政権の完結体制に相応しく、全国を凡そ三百諸藩に纏めあげ、藩主に臣下としての絶対服従と忠誠を誓わせた上で、大名としての地位を授け、同時に所領としての封土を与え、この封土を各領国としてその経営統治に当らしめた封建体制に求められる。こうして、幕藩体制は、極めて日本的な統治形態として、幕府の中央集権制と各藩による分権的な封建制支配という二元支配体制として纏めあげられていた。この「中央と地方の芸術的調御仕組み」こそ日本的な封建制社会の辿りついた特質であり、よほど合理的で長期政権を可能にした秘策であったと云える。 徳川政権はその頂点に君臨した政体であり、その骨格は初代家康、二代秀忠、三代家光の治政の頃に定まった。特徴的なことは、徳川将軍自らを最大の大名として、以下の各大名藩主つまり封建領主を、政権の近しきより「御三家」(尾張、紀伊、水戸)、「親藩」、「譜代」、「外様」と区分序列化することにより、相互牽制と服従の強権的上下体制に組み込んだ統制ぶりにあった。 将軍家は、全国各地に天領と呼ばれる直轄地を持ち、これに直参の家臣旗本の知行地を加えると全国石高のほぼ四分の一(凡そ全国石高を3000万石とした場合400万石)を占める支配力であり、家臣団数からみても直参の戦闘力としてざっと旗本5千人、御家人1万7千人(1721・亨保6年統計)、合計2万2千人を擁していた。こうした権勢を背景に、各藩地方領主を、一国一城令、武家諸法度、妻子の江戸居住、三勤交代による江戸参府(参勤交代については別章参照)、臨時の御用、婚姻政策等々様々な形で支配し、更に、改易、減封、国替え(転封)といった強硬な鞭をも駆使して、諸大名の抵抗力を徹底的に排除した上で、「お上の御威光」を貫徹していた。 武家制度の頂点の権力構造は将軍制であり、その足下に位置する溜間詰(たまりのまづめ)制であった。ここが三権未分立時代の行政と立法と司法を一手に束ねる権力機構そのものであった。溜間詰は時代によって若干異なるが、安政年間の例で見れば家門で四松平家(高松、桑名、会津、伊予松山)、譜代の閨閥で井伊(彦根)、本多(岡崎)、酒井(姫路)、松平(忍)及び溜門詰の堀田(佐倉)、溜間詰格の酒井(小浜)の藩主により構成されていた。この中から将軍により老中首座が任命された。 |
| 御三家に加えて御三卿(ごさんきょう)がある。これを確認しておく。(「御三家と御三卿」その他参照)。 1730(享保15)年11.10日、江戸幕府八代将軍・徳川吉宗が御三卿のはしりとなる田安家を創設した。家康が御三家を作り、吉宗が御三卿を作ったことになる。仮に他家へ養子に行っても徳川の姓を名乗り続けられる特典があった。吉宗が田安家と一橋家、九代・徳川家重が清水家を創設した。計三つの家が作られたため御三家になぞらえて「御三卿」(ごさんきょう)と呼ばれる。田安、一橋というのは名字ではなく屋敷のあった場所から取った便宜的な呼び名である。田安家は現在でいえば日本武道館北あたり、一橋家は竹橋駅前、清水家は田安家の少し東側に屋敷を持っていた。慣例として将軍が御三卿の当主、養子に出す、迎えるを決めていた。通常の大名家は跡取りがいないと改易をくらうが、御三卿は当主がいなくなっても改易にならず名前を残した。これを「明屋敷」(あけやしき)という。元々が「宗家にも御三家にも良い人材がいないときに養子を出す」ための家なので、御三卿は養子を出しまくっている。「明屋敷」になったときは御三卿の別の家からさらに養子をもらっていた。一橋慶喜(十五代将軍・徳川慶喜)のように、格上の御三家から来た人もいる。逆に、十四代の徳川家茂のように、田安家から御三家の紀州へ養子に出、その子供が宗家に戻ってきたという例もある。将軍の実子がいなくなってしまった十代家治の頃からは後継者候補として御三家に並び御三卿の名前も多く出てくることになる。十一代将軍・徳川家斉は一橋家の出身。十二〜十三代までは血が続いたものの十四代と十五代も御三卿から来ている。後継者に困っていたのは宗家だけでなく御三家も同じだったので、御三卿の存在は実にありがたいものになっていった。 |
| 【陰陽道、風水をによる徳川政権安泰施策考】 |
|
江戸時代、家康から家光まで使えた天台宗の天海大僧正が東照宮、上野寛永寺を創建。この東照宮や上野寛永寺も輪王寺も中禅寺も陰陽道、風水を元に江戸を守る鬼門としての寺であり、全てが天台宗。ちなみに、徳川家の菩提寺の芝増上寺はなんと浄土宗。表鬼門にあたる上野寛永寺から輪王寺まで江戸を守る祈祷院の要素が強い、そのお寺には龍の絵が多い。東照宮の薬師堂の有名な鳴き龍を描いた堅山南風画伯が中禅寺の大雲龍も描いている。大猷院の天井には140体の龍が、陽明門には45体以上の龍の彫刻が、拝殿(大名などが参列参拝する)の天井にも110体以上の龍が、輪王寺の大護摩堂には狩野派の大昇龍が描かれている。 |
| 【兵農分離による士農工商秩序考】 |
| 徳川政権が敷いた幕藩体制は、それまでの武家政権が辿り着いた究極の組織体であり、完璧な迄に日本式な調和統制的な組織構造を造りあげていた。その一つの特徴は、直前の織豊政権が成し遂げた「兵農分離」を更に徹底させ、「士農工商」(しのうこうしょう)と呼ばれる職業別の階級的乃至は身分制の秩序を基軸としていたことにあった。「士農工商」は、更にその階級の内部を、家格乃至職階的な格式によって多重に階層化させられており、階梯的な身分的構造を造り上げていた。この構造が支配秩序となり、様々な軋轢を孕みながらもこの後二百五十年余の安定的な政権をもたらすこととなった。 ちなみに、「士農工商」とは、漢書に「士農工商、四民に業あり」とあるように、「民」の職業は4種類に大別され、社会の主要な構成要素としての官吏、農民、職人、商人を指す概念であった。これを「四民」とも云う。但し、士分としての官吏を除く農工商がこの順序で身分制化されていたかどうかは不詳である。「武士は支配層として上位になるが、他の身分については上下、支配・被支配の関係はない」と指摘されている。「農」が国の本であるとして「工商」より上位にあったと説明されることもあるが、身分上はそのような関係はなく対等であったと指摘されている。 こうした身分制度を基礎にしながら他方で、更に、これに横の基軸として、紋地紋柄とも云う家格、家柄を重視したお家の存続と継承を第一義とする「家父長制家族制度」を結合させ、「士農工商」のあらゆる階層を貫く原理とした。家父長制とは、お家の継承つまり家格、家柄、財産等の相続を第一義にする世継ぎの仕方であり、又家族・一族・郎党の束ね方の制度でもあり、概ね長子相続制度を基本として家督権が継承され、これに基づき紐帯的な主従関係が組織され、社会的な存続単位とされた。 こうして、家族員の義務は「お家」の為に奉仕する働き手であることが基準であり、婦女子は男尊女卑原理の下でこれに隷属する仕組みに於いて役割を果たすこととなった。「自由、自主、自律」的なるものは皆なこの原理を保全する範囲においてのみ認められものであった。こうして徳川政権は、それまでの代々の政権の如くの単なる政治支配にとどまらず、社会生活の隅々にまで規制を及ぼすという日本的秩序と規範の体系をつくりあげることに成功していた。 こうして徳川政権は縦横に相応しい精緻な権力構造を造りあげ、いわば縦横の系列的秩序化で補完するという仕組みで完璧であった。 |
| 【武家支配体制考】 |
| こうした「幕藩体制」を支えたのが、当時の人口のほぼ一割弱凡そ7%にあたる士族と呼ばれる武家階級であった。武家階級内部も又将軍と大名の関係がそうであるように、「家格」という形で表示された多層の身分秩序(例えば薩摩藩では、鹿児島城下に住む城下武士の家格を、一門、一所持、一所持格、寄合、寄合並、小番、新番、小姓与、与力の九階層に分けていた)、権威権限に絡められた役職を基本として、上下支配のもとに存立せしめられていた。 武家階級は一般に、侍(さむらい)身分としての「士」階級とその下の「徒歩(かち)」、さらにその下の「足軽以下の奉公人」とから構成されていた。その差別は厳格で、袴がはけるのは侍と徒歩だけ。足軽は土下座を習性とさせられており、「切り捨てご免」にされる場合もあった。武士身分の内部に差別構造が凄まじくあった、ということになる。今日的に云えば、エリートと非エリートつまりキャリアとノンキャリアの壁が厳然と存在していた、ということになる。 その職階職位の制度は、組織論的にみて合議制度と月番制から成り立ち、人材登用の仕組みを備える等今日的に見ても機能的な仕組を基礎にした統治機構となっており、徳川三百年の長期支配を可能にしえた実績に相応しい、成熟した制度を造りあげていた。とはいえ、今日的に見る場合においては、封建的身分体制内における合理性であり、その枠組から出るものではないことは時代制約のしからしめるところであったであろう。 又、士族はその支配階級としての地位を、他の農工商人に対して「苗字、帯刀、切捨御免」の特権を持つこと等により保全していたが、既述した様に武家は、兵農分離されており、究極的には石高制(各領主より割り当てられる石高により表示される扶持米を祿高に応じて与えられる)によって生活が支えられた階級であり、農工商民を強権的に抑圧する立場に立ちながら、これに拠りかからざるを得ないという背反の関係の中に存立せしめられていた。又給与であるその祿米は一定にされていたことからして、経済変動に為す術を持たないという意味においてインフレと共に窮乏化が進み、本質的に危弱な階級であった。 |
| 【朝廷統制考】 |
|
徳川幕府はこうした精緻な身分制支配秩序を各階級階層に作り上げながら、朝廷についても厳しく規制を為し、その権威を形骸化させることに成功した。朝廷については1615年(元和1年)に「禁中並公家諸法度」(きんちゅうならびにくげしょはっと)を定め、天皇の行動、公家の行跡、儀礼、官職、服装のことまで細かに規制を加えた。「天皇は学問を第一とする」などと説き、天皇の権限を年号や暦の制定など形式的なことだけにとどめた。この禁中並公家諸法度は、歴史上初めて武家の定めた法により天皇の行動を規定したものとなった。これにより天皇は、行幸、大名との交流を禁止され、「象徴天皇制」の地位に甘んじることになった。又、京都所司代をおいて朝廷の動行を監視した。 |
| 【農本体制考】 |
| 「幕藩体制」は、武家階級の支配する政治体制であったとはいえ、当時三千百万人口の圧倒的な層は農民であった。徳川幕府の支配機構は、米の収穫量を表わす石高を基礎にした「封土」で領地を定めていたことからもわかるように、「農は国のもとなり」といわれる様な農本社会を前提に成立していたことからして、社会政策の基本も又農業政策であり農民政策となった。こうして、農民には武家に継ぐ地位が与えられていたものの、実態としての農民の働きは収奪される対象であり、貢納の為に存立せしめられた階級でしかなかった。 ちなみに徳川幕府の税制は、その年その年の田畑の作柄に一定比率の税(年貢)を課すという、いわば所得に対する直税法式を基本としており、その率は、豊臣政権下の「毛見の上三分の二を領主、三分の一を農民に」(御掟追加)という「七公三民方式」を踏襲としながら、その後を受けた徳川家康の「百姓の年間の入用と作食をつもり、その余を年貢として取れ」(本佐録)、「郷村の百姓どもは死なぬ様に、生きぬ様にと合点致し、収納申し付ける様に」(昇平夜話)、「百姓と胡麻の油は絞れば絞るほど出るものなり」(神尾若狭守春央)の言の如くの、〃生かさぬよう殺さぬよう〃という支配原理に基づく年貢取立方式を基本に据えていた。 実際の江戸年間を通じての年貢率は、「六公四民」、「五公五民」で推移していたようであるが、農民は、領主ないしは地域差はあるものの武家階級社会を維持せんが為に一年中休みなく働かされ、あげくに作った米のほとんどを年貢として取り上げられ、粟やひえで辛うじて飢えをしのぐ生活を余儀なくされていた。 とはいえ、江戸年間を通じて農民の生活ぶりの実際が、一様に悲惨であったとはとは云えない。1650年頃より検地が行われておらず、年貢が以後ほとんど一定に押えられたことにより、農業生産力の向上した分に応じて余剰生産物が生まれていたことが推測される。又、時代が下ると共に、農民は換金性の高い工芸作物の栽培と加工に力を入れるようになり、地域的な差異があるものの、農民層富裕化の条件が整備されて行くこととなった。こうして農民は、収奪と増産を廻るせめぎ合いの中に存立せしめられ、やがて富農貧農の階層分化へと進展していくことが運命づけられる階級となった。 この農民階層も又武家社会と同様その地位を複雑に分化させられており、上は村方三役(庄屋、組頭、百姓代)と呼ばれ武家に準じた待遇を得た支配階層や上層農民から始まり、本百姓と呼ばれる自作農民、下は水呑百姓と呼ばれる小作農民、更に雇用人、隷属農民、枠外にえた、非人という層が設けられて、「上を見ればきりがなく、下を見てもきりがない」という身分秩序の枠内で生活することを余儀なくされていた。 こうした農民階層の要は本百姓であった。本百姓とは、所によっては高持百姓とも呼ばれ、検地により登録された土地に貢納責任者として検地帳に記載された年貢の支払い主体者であった。つまり適度の耕作地を持つ自営的な貢納責任を持つ農民層であり、この本百姓の創出と維持こそ農政の基本となった。江戸年間を通じての農村は、こうした圧倒的な層の本百姓の動向を通して振興と衰退が証されることになった。村人は、こうした身分制度のもとに、五人組という制度によって貢租納入の連帯責任、隣保共助、相互監視が為されており、又、村掟、村八分の制等によっても統制される等々社会生活の隅々まで支配の網の目が廻らされていた。 興味深いことは、農民は、こうして窮乏の暮らしに甘んじながら、他方では身分制度の枠組上最下層に位置づけられていたえた、非人との生活差別、差別意識を日常的に醸成しており、逆に、えた、非人は、いわゆる賎し業に従事し、百姓一揆の鎮圧役を勤めたり、刑場の役を担わされることによって、農民層とのぬかるみの敵対関係に入り込むことを余儀なくされていた。実に、巧妙な統治のなせるままであったと云える。 こうした武家、農民の下に「町人」と呼ばれる工商人が存在した。彼等は、概ね城下町に居住し、侍屋敷とは別に身分別職業別の区画が与えられていた。町人にも又地主、家持の層と地借り、店借りの層があり、その地位に応じて町政の参加資格にも区別が為される等厳しい身分制度の枠を嵌められていることに変わりはなかった。職工.商人は身分秩序の最後にされてはいたものの、農民に為された厳しい統制とは対照的に比較的自由な活動が認められており、商品経済の発展とともに次第に、上は大名を凌ぐ力を蓄える商人層から、下は下層農民並みまでというように階層分化を著しくさせ、やがては身分制秩序を覆す層として台頭を見せていくこととなった。 |
| 【宗教統制考】 |
| 神社、寺院も統制された。但し、住み分け的な必要な規制をした面もあり、神社、寺院の統制と云うよりは利用活用と捉えるべきかも知れない。神社、寺院は、神社が専ら人や物の誕生、成長に関わり、寺院が人や物の死亡、衰退に関わることで住み分けしていた気配が認められる。 |
|
幕府は、寺社に対しては、行政機関として寺社奉行を置くことにより、法令としては「諸宗寺院法度」を定めることにより規制した。「諸宗寺院法度」により仏教諸宗派は各宗ごとに本山、末寺の制度をたててピラミッド型の階層制度を敷くことになり、こうして全国の寺社が管理され権威が序列化させられた。これにより各教団は幕藩体制下に組み込まれた。 |
| 「諸社禰宣神主法度」で神社を統制した。法度は五条で構成され、装束に関すること、位階制度、「神道に励み、神社を掃除し修理しなさい」、「社領の売買と質入の禁止」などを規定している。幕府は神祓官領長の吉田家に神職の装束認可権を与えたが、特定の執奏家がある神社は他の家に頼むことが認められていた。装束の許可申請に多額の費用がかかり絶対必要なことではないこともあり執奏家自体を不要とする神社もあった。幕府は吉田家の一元的神職統制よりも神社神職を組織化し把握できればいいと考えていた。 |
| 徳川治政のイデオロギー統制政策の又一つとして、神社神道の浄、不浄の観念も利用された。更に、仏教の因果応報説、因縁論、業の観念も利用された。 |
| 1665(寛文5)年7月、「諸社禰宜神主法度」を発布。第三条により、無位の社人の装束許可権が吉田家に与えられた。 |
| 1674(延宝2)年8月、「伝奏なき社家も吉田執奏に及ぶべからず」との「覚」により、執奏(朝廷と神社の取次ぎ) は吉田家に限定されないことが幕府によって命じられた。(※白川家の参入が可能になった) |
| 【鎖国体制とキリシタン統制考】 |
|
こうして国内の統治に万全を期した徳川幕府は、海外との自由交易を禁止し、唯一長崎出島をその任に当たらせる等鎖国政策を採用することで 、その政体を完遂させた。それまで戦国の騒乱時代を通じて西欧の先進技術を取り入れることに争う如くの熱心さを示し、やがて日本の側から海外渡航を積極的に行う等海外列強とも対等の地位を占める勢いを見せていたが、こうした交易に伴い徳川政権の安定に好ましからぬ事情も発生し始めていた。 |
| 【儒教学問(儒学)・儒教道徳の援用考】 |
|
徳川治政は、支配秩序に様々な補完策を廻らすことに相当の配慮を凝らしていた。支配イデオロギ-として儒教学問(儒学)・儒教道徳を援用したこともその一つである。儒学とは、儒教を中心とする漢学の教えであり、四書(大学・中庸・論語・孟子)、五経(易経・詩経・書経・礼記・春秋)のことを云う。儒学には「官学」としての役割が与えられ、政体を維持する治政の基本理念として採用された。その大綱は、仁義礼智信の五常を道徳の基本とし、修身、斉家(せいけ)、治国、平天下を為政者の心得としていた。 |
| 【その他磐石の長期安定政権支配構造考】 |
| このようにして全ての政策が、徳川幕府の長期安定の為に、蟻の子一匹の入る隙間もなきが如くに精緻な政策が講じられることとなり、磐石の長期安定政権支配の基礎が固められることとなった。 なお、江戸幕府の通貨体制にも触れてみようと思う。江戸時代の通貨は、三貨体制といって金.銀.銭の三つの通貨より成り立っていた。このなかで、銭は全国通用の少額通貨であるが、金は江戸を中心とする関東.東国地域で、銀は京.大坂を中心とする畿内.西国で通用する高額通貨であった。この三貨は希望公定価格が定められたものの、刻々時々変化して一元化されることはなかった。三貨の交換は専ら両替商によって行われ、両替商は相場の変動による利益に預かることとなった。 当時の人々は、こうした身分秩序の幾層もの階梯と封建制度の枠内において暮らすよう順馳されており、何人もこうした時代の制約を受けずには存在しえなかった。「みき」を考察するにあたり、こうした時代背景の認識を得ておくことも又肝要のことと思われる。 |
| 【江戸初期の時代状況】 |
|
前述したように、江戸時代は、農村を土台とする「米遣経済」を基軸に領主の権力下に都市と商業資本の発達を統制して、武士階級が支配者の立場にたつという構造の元に、一方で徳川政権の絶対的権力による中央集権政治、他方での諸藩による封建的領国統治という二元支配を車の両輪とする幕藩体制でもって経緯して行くこととなった。 |
| 町人文芸家井原西鶴(1642~93年)は、「日本永代蔵」、「世間胸算用」、「好色一代男」等で、脚本家の近松門左衛門(1653~1724年)は「曾根崎心中」、「国姓爺合戦」、「心中天網島」等で世相を綴った。俳諧の松尾芭蕉(1644~94年)、人形浄瑠璃の竹本義太夫(1651~1714年)、歌舞伎の坂田藤十郎、市川団十郎、美術の尾形光琳(1658~1716年)、浮世絵の菱川師宣(1618~94年)、伊万里焼工芸の酒井田柿衛門(1596~1666年)等々一代巨匠が地位を踏み固めたのもこの時代であった。 |
| 【「江戸システム」考】 |
| 264年の長期安定政権となった「徳川の平和」の「江戸システム」が注目されつつある。最大の理由は、案外と合理的な統治システムであったことに気づかされる。合理的な統治システムの根拠の一つは、役人が極端に少なかったことに求められる。作家の石川英輔氏の「望星」2月号に拠れば、庶民人口55万人の江戸で、南・北町奉行所の役人は合計290名に過ぎなかった、と云う。月番交代だから、実質的には145名が実務していたことになる。それを補助するのが「大家さん」と呼ばれる住宅や店舗の管理人であった。「五人組」という組織がつくられ、給料は幕府からではなく所有者から貰っていた。「完璧な民間委譲システム」であった。「江戸時代は封建制社会で民衆は圧制に苦しんでいた」という江戸時代像は、再精査されねばならぬことになる。 |
| 幕府の奉行制もなかなか合理性が認められる。勘定奉行や外国奉行も二、三名居り、互いに仕事を分担し合いつつ監視している。町奉行所も月番交代制度であり、その仕組みには合理性が有る。当時の統制ぶりについてだが、幕政批判やシステム改変には制約があるようであるが、学問とか言論とか思想の自由については案外と許容されていた節が有る。法規制も緩やかで、解釈次第というところもあった。全体的に教育水準も高かった。 |
|
寛永20年10月2日(旧暦)は、南光坊天海の命日。家康による江戸の都市整備には風水が取り入れられたと伝わっているが、そこで重要な役割を果たしたのが天海で、徳川家康の側近として江戸幕府初期の朝廷政策・宗教政策に深く関与した。その本質は、出雲王朝御代の政体を取り入れており、案外と理に適ったものだったと考えられる。これが徳川幕藩体制の世界に稀なる長期政体となった秘訣ではなかったか。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)