|
「中山ミキ教祖伝」の筆を記すに当って、まずは、「みき」の誕生した頃の社会情勢及びその世間事情を踏まえておこうと思う。何人と云えども「時代の子」として、その時代の社会の仕組みあるいは風潮を母班として、その刻印を受けながら成長を遂げていく筈であるから。
天理教教団本部では、「みき」の誕生から中山家への嫁入り、天啓等々全ての進行を、「魂の因縁」の教理或いは「年限の理」の教えにより、予定完結的に理解することを建前としているが、こうした立場に立てば、「みき」の「時代の子」としての側面を見落とすことになることが避けられない。私は序文でも述べたように、それがどうであろうと、あるいは仮に「みき」自身の言説に違背しようとも、「みき」の言説をさえ可能な限り「時代の言葉」として捉え、「みき」をも又「時代の子」としての枠組の中での成長過程として辿ってみようと思う。
そういう意味で、「みき」を述べるにあたっては、まず「みき」の誕生した時代の特質並びに世相を俯観しておくことから始めねばならないであろう。「みき」の段階的な成育史は本稿各章に譲ることとして、ここでは寛政十年(1798年)に生まれた「みき」が過ごした時代つまり俗に「江戸時代」と呼ばれる徳川政権の特質、即ち歴史的な位相について概観していくことから論を起そうと思う。
一般に人類の歴史的区分としては、古代、中世、近世、近代、現代というように段階づけられる。この仕分けに従えば、徳川時代は近世に位置することになる。この時代は、武家が、かっての権力者であった朝廷.寺社権力から権力を奪い、政権を掌中にして行く流れにあった。鎌倉、室町、戦国時代と続いてきた武家政権は織豊政権から徳川政権へと完結し、徳川時代が武家政権の頂点となり且つ最後の時代となった。
徳川政権は、家康(1542~1616年)を初代とし、家康を盟主とする東軍が、1600(慶長5)年、美濃の関ガ原の役で、それ迄の権力者であった西軍豊臣氏連合との戦いに勝利することにより覇権を確立し、1603年に朝廷より右大臣「征夷大将軍」の称名を拝戴するに及び、江戸に幕府を開設したことに淵源を発する。豊臣家旧家臣勢力が大坂冬の陣(1614・慶長19年)、夏の陣(1615・元和元年)等数次の抗争を経て一掃された結果、徳川の前に立ちはだかる勢力は皆無となった。
以来、徳川政権は、1867(慶応3)年に慶宣公よって大政奉還される迄の将軍家15代、ほぼ266年にわたって続く、わが国の政権史上最長の、世界史上にも稀な長期政権となった。この長き体制を支えたのが、歴史学上は封建的諸関係に照応した社会統治制度として見做される幕藩体制と呼ばれる支配体制であった。「みき」はこの時代の末期にその生命を刻印した。
徳川政権と朝廷は、世界史上珍しい「日本型棲み分け原理」に基づく二元支配体制を創造していた。「日本型棲み分け原理」とは、政治の実権を徳川政権が握るが、江戸に住み将軍の任免や官位の授与は朝廷から賜るという仕組みになっていた仕組みを云う。京都の朝廷は、裏政治とも云うべき「祭祀、天文、暦算」を支配し、学問、芸術などに影響力を維持した。
徳川政権が敷いた幕藩体制は、それまでの武家政権が辿り着いた究極の組織体であり、完璧な迄に日本式統制的な組織構造を造りあげていた。その一つの特徴は、直前の織豊政権が成し遂げた「兵農分離」を更に徹底させ、「士農工商」と呼ばれる職業別の階級的乃至は身分制の秩序を基軸としていたことにあった。「士農工商」は、更にその階級の内部を、家格乃至職階的な格式によって多重に階層化させられており、階梯的な身分的構造を造り上げていた。この構造が支配秩序となり、様々な軋轢を孕みながらもこの後二百年余の安定的な政権をもたらすこととなった。
こうした身分制度を基礎にしながら他方で、更に、これに横の基軸として、紋地紋柄とも云う家格、家柄を重視したお家の存続と継承を第一義とする「家父長制家族制度」を結合させ、「士農工商」のあらゆる階層を貫く原理とした。家父長制とは、お家の継承つまり家格、家柄、財産等の相続を第一義にする世継ぎの仕方であり、又家族・一族・郎党の束ね方の制度でもあり、概ね長子相続制度を基本として家督権が継承され、これに基づき紺帯的な主従関係が組織され、社会的な存続単位とされた。
こうして、家族員の義務は「お家」の為に奉仕する働き手であることが基準であり、婦女子は男貴女卑原理の下でこれに隷属する仕組みに於いて役割を果たすこととなった。例外があろうともこの原理を保全する範囲においてのみ認められものであった。こうして徳川政権は、それまでの代々の政権の如くの単なる政治支配にとどまらず、社会生活の隅々にまで規制を及ぼすという日本的秩序と規範の体系をつくりあげることに成功していた。
こうして徳川政権は縦横に相応しい精緻な権力構造を造りあげ、いわば縦横の系列的秩序化で補完するという仕組みで完璧であった。この徳川政権の第一の特質は、同政権も又朝廷より征夷大将軍の拝命を受け樹立された政権であったことに求められる。この手法は古代から現代に至るまで踏襲されている日本的な統治の在り方としての特質である。当時朝廷には昔日の面影はなく、権力としては既に形骸化されてしまっていたが、徳川政権も又この伝統的統治手法を踏襲したことにより、朝廷は将軍任命の押印者として権威を温存していくこととなった。朝廷の存在は、徳川政権の盛期においては、その圧倒的な武力の前に何等問題とならなかったものの、政権に蔭りが出てくるに順い、他方の権威者として復古されて行くことになった。歴史的経過から見て、この時期の朝廷の在り方は幕藩体制の特質の一つとして看過しえないであろう。
徳川政権の第二の特質は、既に直前の織田豊臣政権が、下剋上的な戦国時代の抗争期を終止させ、漸く全国統一的な支配権力を樹立していた果実を受けて、全国を支配下に組み込んだ、中央集権的な統一国家としての権能を備えた近代国家的的側面を有していた政権であったことに求められる。
徳川政権の第三の特質は、同政権が武家政権の完結体制に相応しく、全国を凡そ三百諸藩に纏めあげ、藩主に臣下としての絶対服従と忠誠を誓わせた上で、大名としての地位を授け、同時に所領としての封土を与え、この封土を各領国としてその経営統治に当らしめた封建体制に求められる。こうして、幕藩体制は、極めて日本的な統治形態として、幕府の中央集権制と各藩による分権的な封建制支配という二元支配体制として纏めあげられていた。この仕組みこそ日本的な封建制社会の辿りついた特質であり、長期政権を可能にした秘策であったと云える。
徳川政権はその頂点に君臨した政体であり、その骨格は初代家康、二代秀忠、三代家光の治政の頃に定まった。特徴的なことは、徳川将軍自らを最大の大名として、以下の各大名藩主つまり封建領主を、政権の近しきより「御三家」(尾張、紀伊、水戸)、「親藩」、「譜代」、「外様」と区分序列化することにより、相互牽制と服従の強権的上下体制に組み込んだ統制ぶりにあった。
将軍家は、全国各地に天領と呼ばれる直轄地を持ち、これに直参の家臣旗本の知行地を加えると全国石高のほぼ四分の一(凡そ全国石高を3000万石とした場合、400万石)を占める支配力であり、家臣団数からみても直参の戦闘力としてざっと旗本5千人、御家人1万7千人(1721・亨保6年統計)、合計2万2千人を擁していた。こうした権勢を背景に、各藩地方領主を、一国一城令、武家諸法度、妻子の江戸居住、三勤交代による江戸参府(参勤交代については別章参照)、臨時の御用、婚姻政策等々様々な形で支配し、更に、改易、減封、国替え(転封)といった強硬な鞭をも駆使して、諸大名の抵抗力を徹底的に排除した上で、「お上の御威光」を貫徹していた。
こうした「幕藩体制」を支えたのが、当時の人口のほぼ一割弱凡そ7%にあたる士族と呼ばれる武家階級であった。武家階級内部も又将軍と大名の関係がそうであるように、「家格」という形で表示された多層の身分秩序(例えば薩摩藩では、鹿児島城下に住む城下武士の家格を、一門、一所持、一所持格、寄合、寄合並、小番、新番、小姓与、与力の九階層に分けていた)、権威権限に絡められた役職を基本として、上下支配のもとに存立せしめられていた。
武家階級は一般に、侍(さむらい)身分としての「士」階級とその下の「徒歩(かち)」、さらにその下の「足軽以下の奉公人」とから構成されていた。その差別は厳格で、袴がはけるのは侍と徒歩だけ。足軽は土下座を習性とさせられており、「切り捨てご免」にされる場合もあった。武士身分の内部に差別構造が凄まじくあった、ということになる。今日的に云えば、エリートと非エリートつまりキャリアとノンキャリアの壁が厳然と存在していた、ということになる。
その職階職位の制度は、組織論的にみて合議制度と月番制から成り立ち、人材登用の仕組みを備える等今日的に見ても機能的な仕組を基礎にした統治機構となっており、徳川三百年の長期支配を可能にしえた実績に相応しい、成熟した制度を造りあげていた。とはいえ、今日的に見る場合においては、封建的身分体制内における合理性であり、その枠組から出るものではないことは時代制約のしからしめるところであったであろう。
又、士族はその支配階級としての地位を、他の農工商人に対して「苗字、帯刀、切捨御免」の特権を持つこと等により保全していたが、既述した様に武家は、兵農分離されており、究極的には石高制(各領主より割り当てられる石高により表示される扶持米を祿高に応じて与えられる)によって生活が支えられた階級であり、農工商民を強権的に抑圧する立場に立ちながら、これに拠りかからざるを得ないという背反の関係の中に存立せしめられていた。又給与であるその祿米は一定にされていたことからして、経済変動に為す術を持たないという意味においてインフレと共に窮乏化が進み、本質的に危弱な階級であった。
「幕藩体制」は、武家階級の支配する政治体制であったとはいえ、当時三千百万人口の圧倒的な層は農民であった。徳川幕府の支配機構は、米の収穫量を表わす石高を基礎にした「封土」で領地を定めていたことからもわかるように、「農は国のもとなり」といわれる様な農本社会を前提に成立していたことからして、社会政策の基本も又農業政策であり農民政策となった。こうして、農民には武家に継ぐ地位が与えられていたものの、実態としての農民の働きは収奪される対象であり、貢納の為に存立せしめられた階級でしかなかった。
ちなみに徳川幕府の税制は、その年その年の田畑の作柄に一定比率の税(年貢)を課すという、いわば所得に対する直税法式を基本としており、その率は、豊臣政権下の「毛見の上三分の二を領主、三分の一を農民に」(御掟追加)という「七公三民方式」を踏襲としながら、その後を受けた徳川家康の「百姓の年間の入用と作食をつもり、その余を年貢として取れ」(本佐録)、「郷村の百姓どもは死なぬ様に、生きぬ様にと合点致し、収納申し付ける様に」(昇平夜話)、「百姓と胡麻の油は絞れば絞るほど出るものなり」(神尾若狭守春央)の言の如くの、〃生かさぬよう殺さぬよう〃という支配原理に基づく年貢取立方式を基本に据えていた。
実際の江戸年間を通じての年貢率は、「六公四民」、「五公五民」で推移していたようであるが、農民は、領主ないしは地域差はあるものの武家階級社会を維持せんが為に一年中休みなく働かされ、あげくに作った米のほとんどを年貢として取り上げられ、粟やひえで辛うじて飢えをしのぐ生活を余儀なくされていた。
とはいえ、江戸年間を通じて農民の生活ぶりの実際が、一様に悲惨であったとはとは云えない。1650年頃より検地が行われておらず、年貢が以後ほとんど一定に押えられたことにより、農業生産力の向上した分に応じて余剰生産物が生まれていたことが推測される。又、時代が下ると共に、農民は換金性の高い工芸作物の栽培と加工に力を入れるようになり、地域的な差異があるものの、農民層富裕化の条件が整備されて行くこととなった。こうして農民は、収奪と増産を廻るせめぎ合いの中に存立せしめられ、やがて富農貧農の階層分化へと進展していくことが運命づけられる階級となった。
この農民階層も又武家社会と同様その地位を複雑に分化させられており、上は村方三役(庄屋、組頭、百姓代)と呼ばれ武家に準じた待遇を得た支配階層や上層農民から始まり、本百姓と呼ばれる自作農民、下は水呑百姓と呼ばれる小作農民、更に雇用人、隷属農民、枠外にえた、非人という層が設けられて、「上を見ればきりがなく、下を見てもきりがない」という身分秩序の枠内で生活することを余儀なくされていた。
こうした農民階層の要は本百姓であった。本百姓とは、所によっては高持百姓とも呼ばれ、検地により登録された土地に貢納責任者として検地帳に記載された年貢の支払い主体者であった。つまり適度の耕作地を持つ自営的な貢納責任を持つ農民層であり、この本百姓の創出と維持こそ農政の基本となった。江戸年間を通じての農村は、こうした圧倒的な層の本百姓の動向を通して振興と衰退が証されることになった。村人は、こうした身分制度のもとに、五人組という制度によって貢租納入の連帯責任、隣保共助、相互監視が為されており、又、村掟、村八分の制等によっても統制される等々社会生活の隅々まで支配の網の目が廻らされていた。
興味深いことは、農民は、こうして窮乏の暮らしに甘んじながら、他方では身分制度の枠組上最下層に位置づけられていたえた、非人との生活差別、差別意識を日常的に醸成しており、逆に、えた、非人は、いわゆる賎し業に従事し、百姓一揆の鎮圧役を勤めたり、刑場の役を担わされることによって、農民層とのぬかるみの敵対関係に入り込むことを余儀なくされていた。実に、巧妙な統治のなせるままであったと云える。
こうした武家、農民の下に「町人」と呼ばれる工商人が存在した。彼等は、概ね城下町に居住し、侍屋敷とは別に身分別職業別の区画が与えられていた。町人にも又地主、家持の層と地借り、店借りの層があり、その地位に応じて町政の参加資格にも区別が為される等厳しい身分制度の枠を嵌められていることに変わりはなかった。職工.商人は身分秩序の最後にされてはいたものの、農民に為された厳しい統制とは対照的に比較的自由な活動が認められており、商品経済の発展とともに次第に、上は大名を凌ぐ力を蓄える商人層から、下は下層農民並みまでというように階層分化を著しくさせ、やがては身分制秩序を覆す層として台頭を見せていくこととなった。
徳川幕府はこうした精緻な身分制支配秩序を各階級階層に作り上げながら、朝廷についても厳しく規制を為し、その権威を形骸化させることに成功した。朝廷については1615年(元和1年)に「禁中並公家諸法度」を定め、天皇の行動、公家の行跡、儀礼、官職、服装のことまで細かに規制を加えた。これにより天皇は、行幸、大名との交流を禁止され、「象徴天皇制」の地位に甘んじることになった。又、京都所司代をおいて朝廷の動行を監視した。
寺社の統制も並行して進められ、行政機関として寺社奉行が置かれ、法令としては、「諸宗寺院法度」、「諸社禰宣神主法度」を定め、権威の序列化に成功した。これにより、各教団は幕藩体制下に組み込まれ、教団の運営から個々の僧侶の暮し向きまでの一切合財が規制された。こうして、仏教諸宗派は、各宗ごとに本山、末寺の制度をたててピラミッド型の階層制度を敷くことにより統制されることとなった。又、キリスト教を禁宗としてこれの弾圧に努め、各寺院に檀家制度を組織させ、宗旨人別帳に記載を義務づけたり、宗門改めをさせる等庶民支配に重要な役割を果たさせた。この檀家制度は、他面では各教団の公認存続権益の保障でもあった。だが、その代わりに要請されたことは教義の封建秩序への順応化であった。
この時代の僧侶は、宗教家としての役割のみならず、小役人的行政的官吏あるいは思想警察的な役割をもになわされることになった。こうして、寺院宮社も又政治支配の道具に利用された。「みき」との絡みで云えば、やがてこうした宗教統制は腐敗の温床となり、概要「(本門仏立講の開祖・長松日扇が見たものは)幕府の宗教政策に唯々諾々と付き従い、腐敗と堕落を繰り返す既成仏教教団の姿であった。彼は、それに失望する。そして、猛然と批判を加える。やがて、断固として還俗すると、出家者たちへの鋭い批判を開始した」(小滝透「神々の目覚め」)という事態を招くようになる。
こうして国内の統治に万全を期した徳川幕府は、海外との自由交易を禁止し、唯一長崎出島をその任に当たらせる等鎖国政策を採用することで
、その政体を完遂させた。それまで戦国の騒乱時代を通じて西欧の先進技術を取り入れることに争う如くの熱心さを示し、やがて日本の側から海外渡航を積極的に行う等海外列強とも対等の地位を占める勢いを見せていたが、こうした交易に伴い徳川政権の安定に好ましからぬ事情も発生し始めていた。
その第一の脅威は、キリシタン伝導が西欧の植民地獲得の野心に通ずるものであるという懸念にあった。事実キリスト教の普及ぶりには目をみはるものがあり、教徒がキリスト教のいうところの神の教えを絶対とし、その掟にはずれることは例え支配者の命令であっても従わないという強い信仰と団結を見せつけることにより、幕藩体制に重大な脅威としてたちはだかることとなった。こうして鎖国の第一の目的は、キリスト教の禁教となった。なお盛んとなる貿易に関係して諸大名や有力商人の台頭することが予想され、こうした動きも徳川政権の安定には好ましからぬこととなった。こうして徳川政権は、安定か繁栄かの二者択一に対し安定を採用し、この後唯一長崎の出島にてオランダとの貿易を細々と続けることとなった。貿易の管理これが鎖国の第二の狙いであった。
鎖国体制は、まず1616(元和元年)年の入港地を平戸と長崎に制限することから始まり、1623(元和9)年、イギリスが自発的に去り、1624(寛永元)年、イスパニアの来航が禁止され、1633(寛永10)年、鎖国令Ⅰが出され、奉書船以外の海外渡航が禁止された。1634(寛永11)年、鎖国令Ⅱにより長崎に出島が築造され、1635(寛永12)年、鎖国令Ⅲにより、日本船の海外渡航を全面的に禁止されることとなった。1636(寛永13)年、鎖国令Ⅳにより、ポルトガル人を出島に集め、1637(寛永14)年、島原の乱が起こり、1639(寛永16)年、鎖国令Ⅴにより、ポルトガル船の来航が禁止された。1641(寛永18)年、オランダ人が出島に集められ唯一の交易の場とされた。鎖国体制はこうした経過により完成されることとなった。
徳川治政は、支配秩序に様々な補完策を廻らすことに相当の配慮を凝らしていた。支配イデオロギ-として儒教学問(=儒学)・儒教道徳を援用したこともその一つである。儒学とは、儒教を中心とする漢学の教えであり、四書(大学・中庸・論語・孟子)・五経(易経・詩経・書経・礼記・春秋)のことを云う。儒学には「官学」としての役割が与えられ、政体を維持する道具として徹底的に利用された。
「官学」の教えは、もともと五山の僧藤原惺窩、その弟子林羅山等によって唱えられた儒教道徳であったが、徳川幕府は、これを日本型朱子学として利用し、例えば、「君君足らずとも、臣臣足るべし」、「君に忠、親に孝を」として、封建秩序の維持の教学に利用することとなった。
この儒教道徳は、統治学として又修身学とし武士の必須教養として受けとめられることになり、各諸藩は競って藩学校を設置したことから、普及と同時に学問としての奥行きも又深めていくこととなった。
歴史的に見て看過されておりながら重大なことは、この儒教精神が、武士階級の精神性を高め、時代の進展と共に極めてイデオロギッシュな人物を創造させて行くこととなった点であった。儒教の国家論・政体論がやがて時代の空気と触れ合うことにより、体制批判、体制改造の論に迄拡がりを示して行くこととなったことは歴史の皮肉と云えるであろう。
徳川治政のイデオロギー統制政策の又一つとして、神社神道の浄、不浄の観念も利用された。更に、仏教の因果応報説、因縁論、業の観念も利用された。このようにして全ての政策が、徳川幕府の長期安定の為に、蟻の子一匹の入る隙間もなきが如くに精緻な政策が講じられることとなり、磐石の長期安定政権支配の基礎が固められることとなった。
当時の人々は、こうした身分秩序の幾層もの階梯と封建制度の枠内において暮らすよう順馳されており、何人もこうした時代の制約を受けずには存在しえなかった。
なお、江戸幕府の通貨体制にも触れてみようと思う。江戸時代の通貨は、三貨体制といって金.銀.銭の三つの通貨より成り立っていた。このなかで、銭は全国通用の少額通貨であるが、金は江戸を中心とする関東.東国地域で、銀は京.大坂を中心とする畿内.西国で通用する高額通貨であった。この三貨は希望公定価格が定められたものの、刻々時々変化して一元化されることはなかった。三貨の交換は専ら両替商によって行われ、両替商は相場の変動による利益に預かることとなった。
「みき」を考察するにあたり、こうした時代背景の認識を得ておくことも又肝要のことと思われる。
|
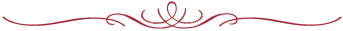
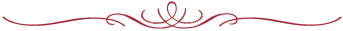
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)