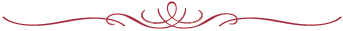
| 丸山敏雄の履歴 |
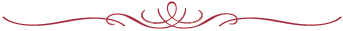
(最新見直し2013.07.28日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、丸山敏雄の履歴について検証する。「丸山敏雄 人と生涯 59年の足跡 −丸山敏雄小伝−」、「丸山敏雄」その他を参照する。 2013.07.28日 |
| 丸山敏雄は、1892(明治25)〜1951(昭和26)。大正・昭和期の社会教育家、倫理研究所初代理事長。全国約5万社が加盟する倫理法人会を擁する倫理研究所の創設者であり、人間普遍の真理として「万人幸福の栞」17カ条を著した人物でもある。 1892(明治25)年、福岡県上毛郡(現豊前市)の合河天和(てんわ)の里に、農家の四男として生まれた。 父・丸山半三郎は熱烈な浄土真宗信仰者であった。その父親から厳しいしつけを受けた。 「信を取れ(不動の信仰心を得よ)」が父親の口癖だった。学業は非常に優秀であった。した。 10歳の時、1歳年上の従兄と神社裏の池で遊んでいて溺れ死にそうになる経験をしている。近所に住む高橋孝六さんという青年に助けられて、命を助けられた「恩の意識」は、父親の「信を取れ!」という声とともに心中深く刻まれ、後の進路に影響してゆく。次のように述べている。
|
|||
|
16歳の時、岩屋尋常小学校の代用教員になる。翌年、小倉師範学校に入学。正規の教師の資格をとるために働きながら勉学を続けた。この頃の学友の「偉大なる友」という手記に次のような一文がある。
在学中、足立山麓の黄檗禅寺福聚寺で座禅を組んだりして、級友から「孔子丸山」というニックネームをつけられる。 1920(大正9)年、28歳の時、広島高等師範学校を卒業。郷里に近い福岡県久留米の県立築上中学校の教諭となる。(その年の7月、神崎キクと結婚とある)。続いて中学明善校に赴任する。この頃、東洋史担当の新任教師として生徒たちに次のように語っている。
1925(大正14)年、34歳の時、長崎女子師範学校の首席教諭として赴任する。全国で最年少であった。当時、左翼運動が勃興し、「歴史は科学で説明できなければならない、そうでないものは抹殺すべきだ」という論調が強まっていた。丸山はこの風潮に反発した。次のように述べている。
1929(昭和4)年、広島文理科大学に再入学。日本古代史、特に神祇(じんぎ)史の研究に没頭した。当時の有名な倫理学者であった西晋一郎(1873〜1943)博士の影響を受けて哲学、倫理の研究に精進した。 敏雄にとっては広島高等師範学校時代に、自宅にまで訪問して教えを乞うた恩師であった。後に敏雄は「自分の説いている倫理の学問的系統は西晋一郎博士に受けた」と語っている。 |
|||
|
この時、「ひとのみち教団」に入会し活動している。親友・岩田良昌から、西晋一郎の倫理と教団の教えが一致するという紹介に心を動かされ、教団の広島支部を訪ねたことから始まった。大倉による教団の教えを諄々(じゅんじゅん)と聞かされた。この教団は、天照大神(あまてらすおおみかみ)を太陽神として信仰し、教育勅語を教典とし、独特な技法で病気苦難の救済を行ない、もっぱら日常生活に即した実利的な処世訓を説いていた。丸山は、その場で入会手続きをとった。広島文理科大学を卒業した敏雄は、内定していた師範学校の校長職を辞して、「ひとのみち教団」の教師を志願した。
|
|||
| 1937(昭和12).4月、日中戦争が始まる直前、敏雄は突然検挙され、大阪府曾根崎警察署に勾留された。罪状は不敬罪だった。第2次世界大戦を予感させる不安な時代、大小の宗教団体は弾圧され、強制的に解散に追い込まれた。 「ひとのみち教団」もその一つだった。敏雄も幹部の一人として投獄された。体じゅう殴打され、横に打ち倒される。たたみかけるように罵声が飛んでくる。命を奪われかねない拷問を受けながら、敏雄は、教団の活動が不敬には当たらないことを真正直に答弁し、節を曲げなかった。勾留生活は14ケ月に及んだ。 この時の獄中生活で、宗教のあり方に対しても深く反省した。教祖の御木徳一(みきとくはる)を「真理の恩師」として尊崇敬慕し続けていたが、過剰な熱は冷め、さなぎが成虫へ羽化するように、宗教を脱した。戦中を通じてなお研究の体系化を進めようやく徳福一致の生きた生活法則を確信し、守れば必ず幸福になれる簡潔な生活道の悟りを得たと伝えられている。次のように述べている。
1938(昭和13)年、46歳の時、敏雄は仮出所を許され大阪堺市の自宅に戻る。生活の糧を得るため青年期から続けていた書道を教授し「秋津書道院」を創設した。のち東京で古代史や宗教、日本の精神文化の研究に熱中する。いつ果てるとも知れない公判に備えながら、猛然と勉学に明け暮れた。それまで以上に深く古典や真理を追求した。そうした8年余りの労苦が、やがて倫理運動へと結実していく。 |
|||
|
1945(昭和20)年8月15日、終戦。焦土と化した国土に立つ国民の驚愕と悲嘆のさめやらぬ9月3日、敏雄は、戦後日本の再建を期した論文「夫婦道」の執筆にとりかかる。日記にはこう記した。「この平和と世界文化建設の大任に入る」。ここに倫理運動が事実上のスタートを切った。日常生活の純粋倫理、徳福一致の生活道(純粋倫理)を提唱し倫理運動を始める。これが後の社団法人倫理研究所となる。 敏雄は、宗教修行により見出した「真理」を、西晋一郎の倫理学を仲立ちとして、自らの深い人格と深い教養のフィルターを通して継承した。その理論は、さらに洗練、深化、また拡充されて、万人幸福の生活道である「純粋倫理」として開花結実した。
9月、 丸山が「明朗・愛和・喜働」を実践の柱 とする生活法則である「純粋倫理」を提唱し、早朝からの「おはよう倫理塾」 をベースとした活動を始めた。現在個人会員数は約20万人を擁し研究・教育・文化・環境活動等幅広い活動を行っている。「おはよう倫理塾」(朝の集い)は毎朝5時から5時50分まで全国430ヵ所で開かれている。毎週1回、朝6時から1時間、全国680ヵ所で経営者「モーニングセミナー」が行なわれている。 丸山敏雄の純粋倫理は、どこに独自性があるのか。ひとつには、道徳と幸福が一致する「徳福一致(とくふくいっち)」の生活法則だという点がある。 旧来の道徳・倫理は、正直者が必ず繁栄するとは限らないように、徳目と幸不幸が必ずしも一致しないところに欠陥があった。それに対して純粋倫理は、徳福が一致することを「実践」を通して確認(実験実証)しているところに大きな特色がある。加えて、行為する人の心のありよう(どんな気持ちで行なうか)と、行為の結果(うまくいくか否か)が強く結びついている点に純粋倫理の特色がある。ふつうは、「勤勉」という徳目を教えるとき、その内面(精神)にまで言及することはない。ところが、その人の気持ちや心構えと、実際の仕事の結果との間には、実は深い関わりがある。喜んで取り組んだ仕事は、きっとうまくいく。反対に、嫌々ながら、心配ばかりして行なうと、うまくいかない。行為の隠れた内面、すなわち心のありようを純粋倫理は重視する。言い換えれば、純粋倫理は「心の生活法則」にほかならない。 翌年、しきなみ短歌会、新世文化研究所(のちの倫理研究所)を創立し、所長に就任した。雑誌「文化と家庭」(のちの『新世』)の創刊、「万人幸福の栞」を発刊したのもこの頃である。純粋倫理は「純情」を核にして、「明朗」「愛和」「喜働」の実践を提唱している。 1947(昭和22)年10月、社団法人の認可を得て「新世会(しんせいかい)」(のちに「倫理研究所」と改称)を発足させた。草創期の困難を踏み越えながら、敏雄は、さまざまな活動を展開していった。 膨大な執筆、講演、指導の数々。純粋倫理のエッセンスともいうべき17カ条を抽出し、『万人幸福の栞』をまとめた。それは、人生の難問を明快に解決する集大成であった。純粋倫理の体系化をはかるべく、さらに心血を注いで数々の論文を書き綴った。日に日に増えていく共鳴者に、実践を呼びかけ、個々の指導も怠らなかった。 |
|||
|
神渡良平 (著) 「丸山敏雄の世界 一粒の麦」()が、丸山氏の生涯を小説形式で世に問うている。目次は次の通り。 |
|||
|
丸山キク |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)