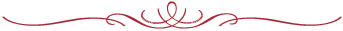
| 仏教基礎知識 |
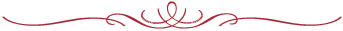
(最新見直し2008.1.22日)
約2500年前、釈迦が、迷信から逃れ真理を会得するべく解脱(涅槃の境地に至ること)し、真如(ありのまま)を説いた。今生の現実を直視し、前生後生譚で推論する事を排し、諸行無常の立場で、真理を探究する道を開いた。これを仏教と云う。
| 【四聖諦】 |
|
四つの真理「苦集滅道」の教え。真如(ありのまま)には、不変真如(永遠不変の真理=胎蔵界マンダラで表現される)と随縁真如(現実相=金剛界マンダラで表現される)に分かれる。 |
| 【八正道】 | |||||||||||||||||
|
八正道(はっしょうどう)(aaryaaSTaaGgo-maargo、आर्याष्टाङ्गो मार्गो)とは、「八聖道」とも「八支正道」とも倶舎論では「八聖道支」とも表現される。「聖者精進の道」である。 釈尊は、「娑婆苦」を生き抜く仏教者の精進法として八つの有るべき道を解き明かした。これが、正見→正思→正語→正行→正命→正精進→正念→正定という方法である。これらすべての方法に「正」の字がついているが、「正」とは、「真理に合った」、「調和のとれた」、「総合的」な考えや見方、行動を指している。これを仏教では「中道」と云う。「中道」とは、真ん中という意味ではなく、偏らない正しさと云う意味である。法華経では「妙」を現す。
|
| 【十界論】 |
| 佛教の十界論 (1)佛 界 (2)菩薩界 (3)縁覚界 (4)声聞界 (5)天 界 (6)人 界 (7)修羅界 (8)畜生界 (9)餓鬼界 (10)地獄界 |
| 【六道論】 |
|
仏教で人の輪廻する世界は、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天の六道とする。人間界の上位に位置する天界は、具舎論によれば、下から六欲天・色界・無色界に別れる。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)